�R����
�u�ӂ��Αn���v�Њ� �m�ꂳ��i��6��j
�@���̑�S������4�N���o�߂����B�����͖��������A�����ɂȂ�������w�߉����ɂȂ�̂��N������Ȃ��ł̒��ɂ���B�܂����w�������̗߂��łĂ��A�ȑO�Ɠ����悤�Ȑ������߂��Ă���ۏ͑S�������B����ǂ��납�V���ȋ��̎n�܂�ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�ӂ闢�̐l�X�͋ꂵ�݁A�Y�݁A��]�̕��ɂ���B���̂悤�Ȏ��Ɉ��ՂƂ��ĖT�ς��Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B�ӂ闢�̎S����~�ς������A�菕���̕��@�͉����Ȃ����A���Ԃ����������B�o��OB�Ƃ��Ďv���͓����A������h��Ƃ��ĉ����o���Ȃ����B�����Ɋe��̎�������AOB���Z�o�̉b�q�ƍs�������҂������B
��6�� �Њ� �m��
��\�l�́@�������̌�̍���
�@�A�����J���{�̑Ή�

�@��ꌴ�����̔����̗�������A�O�@�����̃A���_�[�Z����n���疳�l��@�@�O���[�o���z�[�N���A������A�������������ɔ��A���m�Ȏ��̏�c�����Ă����炵���B
�@���̒�@�@�̐����͌R���@�������A�������J����ƍ��x1��8��m���s���Ȃ���d�q���w�E�ԊO���J�����A�_�����鍇���J�����[�_�[�𓋍ڂ��A�җ�ȑ��x�Ŕ�s�A�؋�30���ԂŎ������c�A���A���^�C���̉f����n��ɑ���A���̉�͔\�͂͒n��30cm�l�������ʂ���ʐ^�B�e���\�A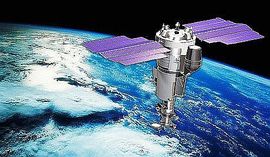 ���������ƍׂ����������ʂ���\�͂�����炵��������ȏ�͌R���@���B�ő�q��������2��5��km�B
���������ƍׂ����������ʂ���\�͂�����炵��������ȏ�͌R���@���B�ő�q��������2��5��km�B
�@��ꌴ���̌����������������_�ŁA�A�����J���͍����\�ȌR���q���ʐ^���A�܂����l��@�@�����đN���ȉf���ɂ��u4���@�̎g�p�ς݊j�R���v�[������ɂȂ��Ă���A�����������Ȃ��Ƒ�ς��v�Ƃ̏�c�����Ă����悤���B
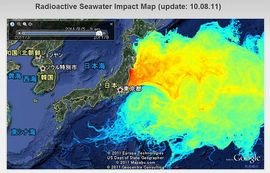
�@�������A���d�͏�c�����Ă��炸�A�]���Đ��{���Ή����o�����A�A�����J�����������錋�ʂɂȂ��Ă��܂����B
�@�����A�����J���{�͎��̑�ɑS�ʓI�Ɏx�����邱�Ƃ�\���o�Ă������A��c���ł��Ă��Ȃ��O���ȁA���@�͓��{�����̖�肾���獑���ʼn����ł���Ǝ��M�������Ă������A���d���O���̉�����������݂������B
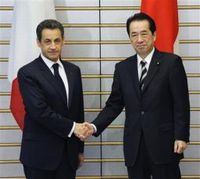
�@�܂��t�����X���{������\���o������A�T���R�W�哝�́A���q�͑��̃A���o�Ђ̍ō��ӔC�ҁiCEO�j�A���k�E���x���W�������������A�C�]�c�o�Y���Ɂu���B���b�̏]�ƈ��Ƃ��Ďg���Ăق����v�ƒ�Ă��Ă���B
�@�����̃��^�c�L������܂��B
�@���E��̌��������A�����J�A���ʂ̃t�����X�Ƃ��ẮA���{�ł̌������̂����Ƃ����������A�������Ή^���̊g���H�~�߂����Ƃ̎v�f���������̂ł��傤�B

�@���[�X�����đ�g���������Ƃɂ���āA���q�͈��S�E�ۈ��@�A���d�A�Č��q�͋K���ψ���iNRC�j������āA21���ɂȂ��āu������ꌴ�����̂̑Ή��Ɋւ�����ċ��c�v���A����Ɣ����A�哝�̂̌�������ΓI�ȏ�Ӊ��B�̎Љ�ƃ{�b�g���A�b�v�A���C�悭��������K���A�摗��̏K���A�����̈Ⴂ�A�ً}��v����A�����i�s�^�̓�ɑΏ�����ɂ́A�Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ����{���̂��Ǝ���A�X�Ԃ����炯�o�������������B
�@���͔c�����Ă���
�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ����q�͈��S��ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B
�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B
�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B
�@���������Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B
�@���������̋M�d�ȏ��͌��\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏�ꕔ�����ꂽ�炵���A��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B�������ɂ��t�@�b�N�X�ő����Ă��Ă����j
�@���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ٖ����Ă������A���̂悤�ȕٖ����ʗp����̂��B��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉͂��ꂾ�B
�@��������߂ɉ����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��āA�����Ȋw��b��SPEEDI�̏������̌��\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�Ɠ��فA���ɂ́u��ʂɂ͌��\�ł��Ȃ����e�������v�Ɩ��ӔC�ȓ��ق��J��Ԃ����B
�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v����ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�͌��\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B
�@���̈�ː쒬�����،������A�����J���{�́u�����}�b�v�v�ɂ��Ă��\���q�ׂ����B
�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B
�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B
�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B
�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B
�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B
�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B
�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B
�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
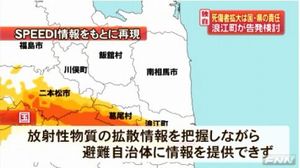
�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��Ƃ��N�����B�Q�]���ԉF�ؒn��ɔ��Ă����l�B�̑O�ɔ������̉��l������A�����͊댯�����瑁��������Ǝw���A���̗l�ɋ����Ă����炵���A���������O�������Ȃ̂炸�����Ă��܂������A����̗����ł������̐E���ł��Ȃ��炵���A�Ɖ\���Ă����B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@�Ƃ��������@�ɂ�SPEEDI���ǂ̕����Ȋw��b�A�A�����J���{������ꂽ�u�����}�b�v�v��SPEEDI���v�Z�������ː������g�U�\�z�}�̗���������Ă����͂��̌o�Y��b�ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�X�ɂ͌��q�͈ψ����܂ł��l�߂Ă���ɂ��S��炸�A���@�ɂ͑S�����オ���Ă��Ȃ��A���̂��Ƃɋ^��������Ȃ������̂��B�Ȓ��̒��Ƃ͒P�ɂ�����ɉ߂��Ȃ������̂��낤���B
�@�A�����J���{�̐\���o

�@�A�����J�E�N�����g�������̎x���\���o����{���{���f�����B�Ƃ����L���̍ŏ��͓ǔ��V���ł����B���̌�̒����V���̋L��������p����B
�@1981�`82�N�ɂ����āA�A�����J�ɂ���I�[�N���b�W�������������A�����J���q�͋K���ψ���̈˗����đ傪����Ȏ����A���̃V�~�����[�V������1981�`82�N�ɌJ��Ԃ��s���A���̕��ψ���iNRC�j�ɒ�o�����B
�@���̌������́A�����̑S�Ă̓d��������ꂽ�ꍇ�̃V�~�����[�V���������{���ē���������������̂ł��B
�@���̃V�~�����[�V�����Ɏg��ꂽ���f���́uGE�А��}�[�NI�F�v�ŁA����͕�����ꌴ����1�`5���@��GE�А���A���������̂őS�������^�C�v���q�F�ł����B
�@���̕��ɂ��ƁA�S�d�����r�����Ĕ��p�o�b�e���[���l���Ԏg�p�\�ȏꍇ�A�u���ԂŊj�R���I�o�v�u���ԂŐ��f�����v�u�Z���Ԍ�ɔR���n���v�u�����Ԍ�Ɉ��͗e�퉺���������v�Ƃ����̂��A��Ȍo�߂ł����A�܂��ɕ�����ꌴ���̎��̂̌o�߂̓V�~�����[�V�����ʂ�ƂȂ����B
�@���̕�����NRC�͒����Ɉ��S�K���Ɏ����ꊈ�p�����̂ł��B
�@�ł́A���d�Ƃ��Ă͂��̂悤�ȕ������邱�Ƃ�m��Ȃ������̂��A����������1���@�̌��݂�1971�N�AGE�Ђ��v�A�@�ނ��琘���t���H���܂őS�Đ��������u�t���E�^�[���E�L�[�v�_��ł�����A���̌�̐ӔC������܂��B
�@���̕�����o���ꂽ�̂�1982�N�Ȃ̂ŁAGE������͂���ANRC������A�����������悤�ŁA���̎��������邩�炱���A���ŋ߂�10��4���A�����J�c��ɂ����镟����ꌴ���Ɋւ��������ł̏،���ɗ������O���S���[�E���c�RNRC�ψ��������{���{�̑Ӗ�����O��I�ɂ������낵���،��������Ȃ����̂��A���������Ƃ������A���u���Ă��܂������{���ɉ䖝�ł��Ȃ������̂ł��傤���B
�@�ł͉��́A���{���͊��p���Ȃ������̂��A���������S�d�����r������悤�ȏ͋N���邱�ƂȂ��A�N���蓾�Ȃ�����z�肷��K�v�͂Ȃ��A�������͕K�v�Ȃ��A�̊댯�ɂ܂�Ȃ��O�i�_�@���ʗp���Ă��܂����B
�@�������A�����Ɍ������̂͋N���āANRC�ɂ��邱�Ƃ��N���Ă��܂����B����ł����d�͑��v���ƐM���āA�A�����J��t�����X����̉�����f�����̂́A���d���̓o�b�e���[�̉ғ�����8���ԁA���̊ԂɊO���d���͉ł���B�ƐM���Ă����悤�ŁA����܂����S�_�b�̐_���݂ɏI�n�����B
�@��������A�В��A���В�(���q�͒S��)���o�����ŁA���d�̎i�ߓ��͕s�݁A�c���ꂽ�����̓}�j�A���͂Ȃ��A�ӔC�͕��������Ȃ��ƃI���I���������A���@�͂���܂����d����̕��Ă��A����������A���f�ł���l�ޕs���A���{�l�S�̂̊�@�Ǘ��ɑ��銴�o����������ɐi�W�����B
�@���̒���A�N�����g�������̘A���́u�����ɐ��i�z�E�_���j���A�����J�����A����v�ƁA����̓A�����J�̌R���q���ŕ�����ꌴ���̎��̖̂͗l���Ԃ��ɊĎ����Ă������h�Ȃ��璷���ɘA���������A����������{���{�\���o���̂ł��傤�B
�@�R���Ď��q���̉�͔\�͂͒n��Pm�ȉ��̕��̂܂Ŕ���\�͂������Ă��܂�����A���̂̓��e�͐��m�ɔc�����A��p���u��ŁA�S�d���r������͂������ŁA�����炱�����̒��������ŗD��A����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B�Ɣ��f���đ����ɐ\���o���̂����A���{���{�ł͎��̌�͏ڍוȂ��A�������̂͑z��O�Ŋ��@�̊�@�Ǘ������@�\���Ȃ��B�S�d���r���ȂǑz��O������}�j�A���Ȃ��A�]���ăA�����J�̐\���o�ł��鐅����A���鎖�̈Ӗ��������o���Ȃ��܂ܒf���Ă��܂����悤���B
�@���̌�̉ߒ�������Ή���ʂ萅�𒍓�����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ������B
�@����ɓ��{���Ƃ��Ă̓A�����J�A�t�����X�̉����������A�����̎w������D���Ă��܂��B���q�F�{�݂��O���ɔ��荞�����Ƃ��Ă��鎞���ɊO���̋Z�p����Ȃ���Ε����ł��Ȃ��B�Z�p�̖��n�������\���邱�ƂɂȂ�B��������{�������őΏ�����B�Ƃ���̂����{�A���d�̗��������������悤�ŁA������f���Ă��܂����B
�@���Ԍo�߂Ƌ��Ɍ��q�F�Z���A���f�����ƂȂ��āA�A�����J�A�t�����X�ɏ��������߂���Ȃ��������A��ɃN�����g�����������A�t�����X�E�T���R�W�哝�́A�A���o�Б��كA���k�E���x���W�������̑����������A�킴�킴���������ɗ����킯�ł͂Ȃ��B���{�����ɔC���Ă����琢�E����ς��Ƃ̔F������ŁA��������ȏヂ�^�c���Ď������x���Ό������̉^�����������Ă��܂��ƁA������i���ł���t�����X�A�A�����J�ł͐����ێ���������Ȃ�A�����h�C�c�ƃX�C�X�͌����S�p���c�������B���̔g�������ɋy�Ԃ̂��Ȃ�Ƃ��h�������A����ɂ͈ꍏ�������������̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���{�����ł͖����Ɣ��f���Ă���ė����킯�ŁA���{�ɑ���D�ӂ����ł���ė����킯�ł͂Ȃ��B
�@�N�����g���������́u���{�͋Z�p�I�����͍������A��p�܂͕s�����Ă���͂��v�������R�@���g���ċ}�������Ɛ����\�������A��ō����ȍ��������{���{���f���Ă����̂ő���Ȃ������A�Ɣ��\�����B �@�V���ɂ́u���𑗂�ƁA�A�����J���{�̐\���o�v�ƋL���ɂ��������A��p�܂̈Ӗ��͑����A�z�E�_�i�z�E�_���A�ʏ�e�{�����f�ƌĂ�ł���j�z�E�_���͊j����������}������A��������̐���_�ɐ��肤����̂Œ����n�Ɏg�p���Ă���̂�����A�z������ɐ��ƌ������̂̓z�E�_���̂��Ƃ��Ǝv���B�܂��z�E�_���𒍓����Ă��p�F�ɂ��Ȃ���ΐ���Ȃ��قǘF�������t���邱�Ƃ͌����Ă��蓾�Ȃ����ƁA�p�F��S�z���Ēf�����B�Ƃ����͉̂������ő}�����ꂽ������ł����Ȃ��B

�@�A�����J��g�ق̓���
�@���̑O�i�K�ɂ����āA���̃��[�X��g���}�슯�[�����Ɂu�A�����J�̐��Ƃ����@�ɏ풓�����ė~�����v�Ɨv���������Ƃ��������炵���B�Ƃ��낪�}�쎁�͂Ƃ�ł��Ȃ����Ǝ匠���Ȃ�������ɂ�����̂��Ɖ��߂����₵���Ƃ̂��ƁB
�@�Ɨ����Ƃ̖ʖڂƂ��Ă͓��R�����m��Ȃ����A����A�����J�����王��A���E���䂷�����厖�̂��N���Ă���A�Ⴕ����������{�͉�œI�ȑ�Ō����邩������Ȃ����ˍۂɂ���Ȃ���A�N���ǂ��Ώ����悤�Ƃ��Ă���̂������ς蔻��Ȃ��B �@�͂����������O�̊댯��Ԋׂ��Ă���A���d�͓P�ނ��������Ƃ�����������A�Ɍ���ԂɊד����Ă�������A�A�����J���{�́u���ƕ���v�̍ŏI�V�i���I��ǂ�ł����̂����m��Ȃ��B
�@�͂����������O�̊댯��Ԋׂ��Ă���A���d�͓P�ނ��������Ƃ�����������A�Ɍ���ԂɊד����Ă�������A�A�����J���{�́u���ƕ���v�̍ŏI�V�i���I��ǂ�ł����̂����m��Ȃ��B
�@�����炱���������Ƃ��ĂȂ�Ƃ��j�~�������B�����������Ƃ̎v���������A����ɂ͊��@�����ɐ��Ƃ��풓���������������̂��낤���A�A�h�o�C�X�����������̂��낤�B���̂��Ƃ̓��[�X��g�̎v�f����ł͂Ȃ��{�����{����̗v���������낤���A���邢�͑哝�̗̂v�������������m��Ȃ��B���ē����̍�����h�邪������ŁA�����Ƃ͉�����Ɩ����ْ������u�Ԃ������炵���B
�@���̂��炢���@�̎w���͂͊낤���������̂��낤���B

�@���ʓI�ɂ́A���q�͔��d�͐�Ɏ��̂͋N���Ȃ��A�Ƃ������S�_�b���f���A�M���Ă������{�A�d�͊e�ЁA���S�Ȃ̂����玖�̑�E�����͕K�v�Ȃ��Ƃ���A���̏������@�ނ��Ȃ��������̂ɁA���@�����ɃA�����J���{�̐��Ƃ��풓�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�S�ʓI�ɃA�����J�A�t�����X�̉������v��ق�����͂Ȃ��A����ɂ��������肢�ƂȂ炴��Ȃ������B
�@�����̈��S�Ǘ��ړI�ɒS�����Ă����ǒ��́A�o�Y�Ȃ̊O�ǂł��鎑���G�l���M�[���̓��ʋ@�ւƂ��Č��q�͈��S�E�ۈ��@���S�����Ă����B
�@�Ƃ��낪�����ɂ́u���S�_�b�v�Ȃ�d���b�����݂��A���̘b�����������M�����Ă������߂ɁA���S����u���邱�Ƃ͈��S�_�b��`�����邱�Ƃł���A�M���邱�Ƃ����ō��̑�Ƃ��Ă������߂ɁA�������̂ő厸�Ԃ����炯�����Ă��܂����B
�@2012�N9��19���ɔp�~�A���Ȃ̊O�ǂł��錴�q�͋K���ψ���ֈڍs�����B
�@�o�Y�ȥ���q�͈��S�E�ۈ��@

�@�o�ώY�ƏȂ̈�@�ւł���A�@�ߏ�́u�����v�G�l���M�[���̓��ʋ@�ցv�Ƃ���2001�N�i����13�N�j1��6���A�V�݁A�������̂́u���q�͈��S�E�ۈ��@�v�B�����ւ̖{�@�̉��A�n���@�ւƂ��đS���ɎY�ƕۈ��ē��A���q�͕ۈ����������������u����Ă���B
���@�C���i���q�͈��S�E�ۈ��@�j

(1) ���q�͂ɌW��鐻�B�A���H�A�����A�ď����y�єp���̎��ƕ��тɔ��d�p���q�͎{�݂Ɋւ���K�����̑������̎��Ƌy�ю{�݂Ɋւ�����S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
(2) �G�l���M�[�Ƃ��Ă̗��p�Ɋւ��錴�q�͂̈��S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
(3) �Ζ�ނ̎���܂�A�����K�X�̕ۑS�A�z�R�ɂ�����ۈ����̑��̏����ɌW��ۈ��̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
(4) ���������ɌW��鍑�ۋ��͂Ɋւ��邱�ƁB
(5) �O�e���Ɍf������̂̂ق��A�@���i�@���Ɋ�Â����߂��܂ށB�j�Ɋ�Â��o�ώY�ƏȂɑ�������ꂽ����
�@���̂悤�ɁA�{�@�́u���q�͈��S�v�Ɓu�Y�ƕۈ��v�Ƃ���ȏ��������ŁA�����Č��q�͊W�݂̂���Ƃ��Ă���g�D�ł͂Ȃ��B���q�́A�d�́A�s�s�K�X�A�����K�X�A�t���K�X�A�Ζ�A�z�R�W�̎{�݂�Y�Ɗ����̈��S�K���A�ۈ������ǂ��A�����̎{�݂ɑ��Ă͕K�v�ɉ����āA���������A�����A���P���ߓ����s�����Ƃ��ł���B
�@�ۈ��@�̉����g�D�́A�e�n���Ɏ�����������A������ꌴ���ɂ�7�l�̕ۈ��@�E�����풓���Ă���A��F��JR���w�߂��́u�I�t�T�C�g�Z���^�[�v�ŊĎ����悤�Ƃ������A�S�Ẵ��j�^�[����d�A�ʐM����s�ʂŎg�p�ł����A���S���ɖ�肠��A�H���⋋���m�ۂł��Ȃ����̗��R�����������������̌��n���{���֑S�������グ�Ă��܂������Ƃ��A����ŒNj����ꂽ�B
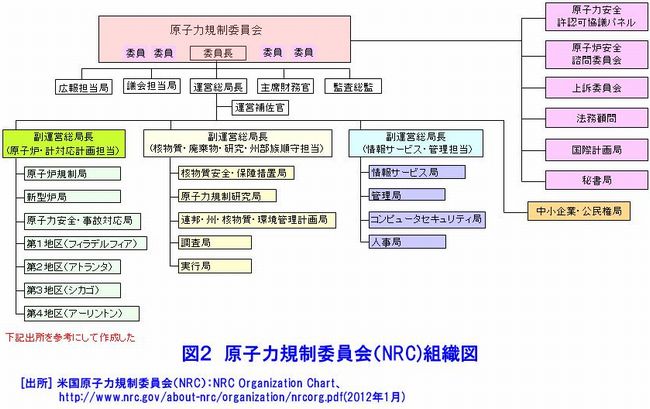 |

�@�A�����J�̊ē������x
�@�A�����J�̊ē����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B
�@�A�����J�E���q�͋K���ψ���iNRC�j�́A�A�����J�����̌��q�͂Ɋ֘A����S�Ă̎{�݂̈��S�Ɋւ���ēƖ���S������B���̈ψ���̈ψ����͑哝�̂ɂ���đI�C����A�����q�͂̈��S�Ɋւ���Ɩ���S�ĈϔC����Ă���B
�@���̑̐��͑S�Ă̌��q�͔��d��104�J���Ƃ��̑��̌��q�͊֘A�{�݂Ɍ��q�͋K���ψ���̌�����������2�l���풓���A���S������Ă��邩�ǂ������������`�F�b�N����B
�@�������́u���ł��A�ǂ��łł��������o����v����������A�����ł��I�Ɍ������s���B����6�����A�����̍�Ɠ��e��������c�ɂ͕K���o�Ȃ��ĖT�����A��Ɠ��e���������A�܂��O���̉^�]�������ƕ������ׂĖڂ�ʂ��B
�@����ɁA�^�[�r�������⌴�q�F�����ɂ͑��ɂ������B�g�p�ςݔR���v�[���⒆�����䎺�̂悤�ȗ�������֎~�����ɂ��t���[�p�X�œ����o���邵�A�W���ɒ��ڎ��₷�邱�Ƃ��o����B
�@�킪���̌��q�͈��S�E�ۈ��@�̌������́A�d�͉�Ђ��쐬���錟�����ނ̐R�����邱�Ƃ���ŁA����̌����͑a���ɂȂ�B
�@NRC�̏ꍇ�́A���V���g���x�O�ɂ���{���ƑS��4�����ɂ���n���ǂ̐��E���������Ɩ��S���A�s�������Β����������ɘA������B
�@�d�v�Ȗ�肪���t����L�҉�Ŗ��炩�ɂ����B2011�N��1�N�ԂőS�Ă�200���]�̕s������ɂȂ����B�킪���̂悤�ɉB���H�삪����̂悤�Ȍ��q�̓����̑̎��͂Ȃ��B
 |
| �i���c�R�������j |
�@NRC�̌������͌��q�͍H�w�̏C�m�ȏ�̊w�ʂ�L����l�������A�������Ƃ��Ă̌P����7�T�ԁA�K�{�͌��q�F����Ղ̃V���~���[�^�[�̑���A�����A��펞�ɂǂ̂悤�ȑ��삪�K�v���O��I�ɏK������B�S�ے����C������ƁA����Ɍ����1�N�ԌP�����d�ˁA�X�Ɏ����ɍ��i���Č������ɂȂ�B
�@�]���Đ��E�Ƃ��āu��������NRC�̖ڂł���A���ƂȂ��āv�Ɩ���簐i���邱�ƂɂȂ�B
�@�킪�����č��̂悤�Ȍ����`�ɓO���Ȃ��ƁA����̌������̂ɂ��E�������̑卬�����J��Ԃ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��A�����͌������ނ�R�����邾���ł̏��ގ�`��E���A�啝�Ȋ������x�̉��v�������K�v�B
�@������ꌴ�����̂̍ۂ́A�����[�����h�B�ɂ���NRC�I�y���[�V�����Z���^�[�ɂ��ꂼ��̐��Ƃ��W�����A�������W���Ė�2�����ɂ킽�芈�������Ƃ̂��ƁA���̊ԁA���f�����̕K�v���ȂǓK�ȃA�h�o�C�X�𑗂葱�������A�u�����n�}�v���l�A�i�ߓ��s�݂̂킪���ł͊��p�ł��Ȃ������炵���B
�@����NRC�ψ����ł������O���S���[�E���c�R����2011�N10��4���A�A�����J�c��E������ŏؐl�Ƃ��ēo�d���A������ꌴ�����̂ɂ��ď،������B
�@����ɂ��ƒn�k�A�Ôg�͗\�z����Ă������Ƃł���A���̑��S�������Ă��Ȃ������̂͑Ӗ��ł��薳�ӔC�ȑ̐��ɂ����̂ŋN����ׂ����ċN�����l�Ђł���ƕ����B
�@���̌�̏����Ɋւ��Ẵ��^�c�L�͎i�ߓ��̕s�݁A�����@�̕s���A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D�̕s�����X�A�җ�ȓ��{�ᔻ���،������B
�@�����͎w�E�̒ʂ肾���甽�_���o���Ȃ����A���̒��㑦���ɉ����\���łāA���ނ̒ȂǃA�����J���̍D�ӂ���\���o���A���̂̋K�͂������o���Ȃ��܂܂ɂ��Ƃ��Ƃ��f���Ă��܂������{���{�Ɠ��d�̘����ȑΉ��ɑ����������Ă����悤���B����ɂ͐��Ƃ�{������h�����Ĕ�s�@�ɂ���Ē����E���肵�č쐬���������}�b�v�����{���{�������������Ƃɑ��Ėҗ�Ɋ��݂����B
�@�����������̂̑�ɐ�O�������A���̍ۃA�����J�����̌��q�͋K���Ɋւ��A�@�K���̋�����d������A�A�����J���{�̓��{�ɑ���Ή���������������A�V�K���q�F�̐V�݂�30�N�Ԃ�ɔF�Ɋւ���ψ���ł̑Η��A�j�p���������ꌚ�v��𒆎~������Ƃ̓��̓ƒf��s���������̂��A��4��l�̐E�����E�w������̂�5�l�̈ψ������A���̃g�b�v�߂�̂��哝�̂ɂ��C���ł���ψ����ł��邪�A���̃��c�R�ψ��������̈ψ��ƑΗ����A�r�ˉ^��������A���C���������̂��A�˔@���\���o���E�������Ă��܂����B�A�����J���{�����ɂ����낢�날��̂��낤���B

�@����A���c�R�����C�̐^�������炩�ɂȂ����B01�N9��11���A�A�����J�ōq��@�ɂ�铯�������e���i9.11�����j���������B
�@���̎��͌�����_�����Ƃ͂Ȃ��������A�_����\��������A02�N�Ɂu���q�͎{�݂ɑ���U���̉\���v�ɔ��������ʂ̑�����邱�Ƃ��e�����ɋ`���t���閽�߂��o�����B���ꂪ�uB5b�v�őS�Ă̍ЊQ�ɑ���h�쥕ۈ��[�u�Ƃ����B
�@���R���̏��͉䂪���̌��q�͈��S�E�ۈ��@�ƌ��q�͈��S��Ջ@�\�Ƃɐ����ɓ`�B����A���̖h�쥕ۈ��[�u���������ꂽ���A�̐S�̌��q�͈ψ���ɂ́A���́uB5b�v��S������Ă��Ȃ������B
�@B5b�̏��Ɋւ��Ăͤ���̌�A�����J�����炪���̑���u���Ȃ������̂��Ƌl���āA���߂�B5b�̑��݂�m���ċ������Ƃ����B
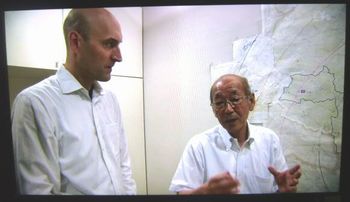 |
| �i�n�꒬���ƃ��c�R����k�j |
�@�c�O�Ȃ���䂪���ɂ́u���S�_�b�v���������Ă���A���オ���S�Ə�����Έ��S���ƖҐM���Ă��܂�������������A����i�J�~�j�͐_�ɒʂ�����̂�����炵���B�]���đS�Ă��u�z��O�v�Ƃ��Č��������o�܂�����B
�@�������̎��A�h��[�u�������Ă���Α�ꌴ���̎��̂͂�����x�h�����͂����ƃA�����J���{�̌����ł������B
�@�Ƃ��낪NRC�ψ����ł��������c�R���́A��ꌴ���̎��̂��Ԃ��Ɍ������ē������_�́uB5b�v�����邩��ƌ����Đ�ΓI�Ȉ��S�͕ۏ���Ȃ��Ƃ��āA�uB5b�v�̌������𐭕{�ɔ������B
�@���̂悤�Ȑ܁A�A�����J���{��34�N�U��Ɍ����̐V�݂�F�߂��BNRC�̈ψ��l�̂���4�l���^���A���̓��c�R�ψ�������1�l�ŁA��]�������c�R���͎��\���o����NRC���������B
�@����3�������12�N8��27���A���c�R���͈�l�ŘQ�]����K��A�h�앞�p�Ŋ��I�̒�������A���̗l�q�����ĉ��A���̌�A��{���s�ɂ���Q�]��������ɔn�꒬����K�ˁA��k�B�����͏�Ȃ��܂�30km���ꂽ�Ó��n��ɒ�����U�����������A�������ł����˔\�������Ƃ��낾�����̂���Œm��A������픘�����Ă��܂������ƂɐӔC��ɐɊ����A��Y�������Ƃ��q�ׁA���c�R���͖ڂ����܂��ĕ����������Ƃ����B
�@�䂪���ɂ����c�R���̂悤�Ɉ��S�_�b�Ȃǂɘf�킳�ꂸ�A�^���ɂȂ��Ď��g��ł����l�ނ���l�ł������Ȃ�A�܂�������W�J�ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��B
�@��@�Ǘ��Z���^�[�̑���
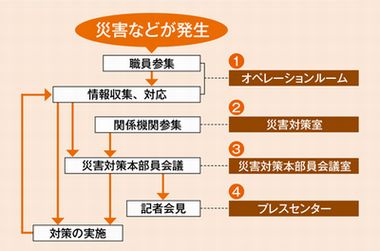
�@��_�W�H��k�Ў��A����t�ɋ������ė���̂��x��A�~�������̔��߂��啝�ɒx��Ă��܂������ƂȂ��A�V�������@�̒n��1�K�ɃI�y���[�V�������[����݂��A���������@��@�Ǘ��Z���^�[�Ƃ����B�i�A���A�g�D���ł͂Ȃ��j
�@��������ɉ^�p���Ă���͓̂��t������W��Z���^�[��24���ԑ̐��i5��20�l�j�ŏd�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɔ����x�@���A�x�����A���h���A�C��ۈ����ȂNJ�@�Ǘ��ɊW����Ȓ��ƃz�b�g���C���Ō���Ă���B

�@�Ǘ����Ă���̂́u���t��@�Ǘ��āv�i���ł͂Ȃ��w�āx�j���̓��t��@�Ǘ��Ă͑啨�x�@����OB���A�C���Ă���B
�i�x�����Čo���ҁj
�@�L���̏ꍇ�͑����������A�e���q���i���C��j���������Q�d�Ƃ��ē���B
�@�ݔ��͑f���炵���@�킪�ݒu����Ă���̂��낤���ǂ�������܂��i�ߕ��Ƃ��Ă̓����͂��Ă��Ȃ��B�A���A�Ƃ��̑��߂͏�K�̎������Ŏw���������Ă����炵���B

�@�܂������m�̏�Łu����܂�v�����ߍ��Ƃ͎v���Ȃ����A�����̋M�d�Ȏ���������_�ň���Ԃ���Ă��܂����͎̂����炵���B�������̊�@�Ǘ��Z���^�[�����S�ɋ@�\���Ă�����ASPEEDI�̑��݂����m���Ă���͂��������オ���Ă��Ȃ����Ƃɕs�R�������Ȃ������̂��A�z�b�g���C���Ōq�����Ă��Ȃ���e�Ȓ��ɖ₢���킹�����Ȃ������̂��B
�@���t��@�Ǘ��Z���^�[�͑��݂��Ă������A���S�_�b��M���ăV�~�����[�V������ӂ��Ă����̂��낤���B
�@���Ă̎Q�d�{���͐i���̍��͉X�������s�������A�P�ލ��͑z��O�ŃV�~�����[�V�����̔��z���Ȃ������炵���B�s�s���ȏ��͍����N���X�̎Q�d������ׂ��Ă��܂��A�̐S�̎Q�d�������͂��߂Ƃ���Q�d�����ɂ͓͂��Ă��Ȃ������Ƃ����B
�@��@�Ǘ��Z���^�[�̑��݈Ӌ`��₤
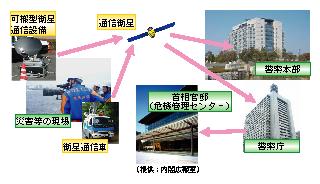
�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B
�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����n�}�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B
�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B
�@�Ƃ��낪�����E�Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�Ȋ��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B
�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤���B
 |
�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B
�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@��@�Ǘ��Z���^�[�͉��̂����̋M�d�ȏ���c���ł��Ȃ������̂��A���邢�͔c�����悤�Ƃ��Ȃ������̂��B�����V�~�����[�V�������J��Ԃ��Ă��ĂΕK�R�����Ƃ��čs�����Ă����͂������A�c�O�Ȃ���Ӗ��͉ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B
�@�܂����@���f�[�^���Ȃ��܂܂ɁA3km���A5km���A10km���A20km���A30km���Ɠ��S�~���`���Ĕ��n������߂����A��@�Ǘ��Z���^�[�͂����̌���ɂ͎Q�����Ȃ��g�O�̑��݂������̂��B
�@�����ɉ����Ĕ������߂�ׂ������A�����Ɋ���Ĕ������߂�ׂ����ƈӌ���\���������������Ƃ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�������͗��̉��l�ɂ����Ȃ������̂��낤���B���邢�́A���@�͊�@�Ǘ��Z���^�[�₻�̑��̐��@�ւ�S���������Ă����̂��B
�@���̂悤�ȏd�厖���ɂ��S��炸���ݕs�M�Ɋׂ��Ă����̂��낤���B
�@�ČR����̎����َ͖E����A���u���ꂻ�̑��݂��������炩�ɂ��Ȃ��������A1�N3�������6��18���A�����V������1�ʂŃX�b�p�����ꂽ�B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȓ́u���˔\�����n�}�v�𒓓��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɑ��t���A��������O���Ȃ͒S���Ȓ��ł��镶���Ȋw�Ȃƌo�ώY�ƏȂɓ]�������B���A���̋M�d�Ȏ������Z�����ɐ�������邱�ƂȂ��A�����܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�1�N3������ɒ����V���ɂ���ăX�N�[�v���ꂽ�B�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B
�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂���A����ȏ�͎���܂���ƚ������B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B
�@�������A���̂��̋M�d�ȃf�[�^�����Z���^�[���ɂ���Z�������S���ł���u�Z�����S�ǁv�ɓn��Ȃ������̂��A�Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��Ắu����Ȃ��v���J��Ԃ������A�������A�u�����n�}�v�͓��Z���^�[���̃z���C�g�{�[�h��A2���Ɋg�傳��Čf������Ă����Ƃ̂��ƁA�]���ē������ō�Ƃ���u�Z�����S�ǁv�̌W�����ڂɂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@�������A�����Ɏ�̂��Ȃ���ΑS���S�������Ȃ��A�^����ꂽ�Ɩ��͌����Ɏ��g�ނ��A�e���g���[�͈͈̔ȊO�͖��S�A�܂��ĊO���̃f�[�^���͖��������R�A�������A�����Ȋw�Ȃ��u���͋��L���ׂ������������m��Ȃ����A����ł̃��j�^�����O�����W���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒S���v�ł��邱�Ƃ������A�]���ĊC�O����́u�����n�}�v�̎�舵���ɂ��Ă͓����҂ł���F���͂Ȃ��B
�@�u�����n�}�v�̎�舵���͕ۈ��@���S��������̂Ƃ̔F����\�����A�����Ȋw�Ȃɂ͂Ȃ�痎���x�͂Ȃ����Ƃ����������B
�@����Ȃ�Ε����Ȋw�Ȃ��S�����Ă���SPEEDI�ɂ��f�[�^������Ȃ�����\���Ȃ������͉̂��̂��A���m�łȂ�����������\���Ȃ������ƕٖ����Ă��邪�A�댯�������Ă���n���F�����Ă����͂��A�ł�����߂Č���ӔC�̂��镟�������̒S���҂ɘA�����ׂ����ƍl����B
�@�Ȃ���Ȃ��܂܉����n��ɔ��Ă����l�X�͔픘���Ă��܂����B
�@�Ƃ��낪���̒n��ɔ��Ă����l�X�̂Ƃ���ɁA�˔@�������i�h��ߕ��j������A�����Ȃ̂炸�u�����͊댯�����璼���ɔ��ĉ������v�Ƃ��������ĕ��̂悤�ɋ����čs�������1�s�������炵���B
�@����s�����̌W���ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁA�u�����n�}�v���������Ă����l�X�̒��ڍs���Ȃ̂��A���݂ł����̐��͕̂s���B
�@�ł͉��̂���قǍ������Ă��܂����̂��A���q�͋K���g�D�Ƃ��Čo�ώY�ƏȁA���q�͈��S�E�ۈ��@�A�Ɨ��s���@�l�E���q�͈��S��Ջ@�\�B���t�{�A���q�͈��S�ψ���B�����Ȋw�ȁA���ː����j�^�����O����A�S�Ă��c����s���B
�@��������Ȓ����قȂ�g�D���������̂Ƃ���1���̍ЊQ�ɑΏ������ꍇ�A���O�ɖȖ��ȑł����킹�ƁA�g�D�S�̂����f�I�ɓ�������{���y�юi�ߊ������Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɍs�����邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��ɍ�����������炯�o���Ă��܂����B�o�Y�Ȃƕ����Ȋw�Ȃ����������ō�Ƃ��Ă��Ȃ���u�����n�}�v�����L�A���p���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�܂��A���i�ߊ��ł���ׂ��������͏�W�܂�Ȃ��܂܁A����ɉ��������A���d�{�X�ɓ{�荞��Ɠ�����������A���i�ߊ��Ƃ��Ă̎��o�����܂�Ȃ��̂����i�ߕ��𗯎�ɂ��Č����d���K��A������č���������ȂNJ�@�Ǘ��̐����S�������Ă��Ȃ����Ƃ����g�̍s���ŘI�悵�Ă��܂����B
�@��ꌴ�����̂ŒS������ۈ��@�͎��̒���ɏ����W�߂��ꂸ�A�����Ă����p�ł����g�D�Ƃ��Ă�����Ƌ@�\�ł��Ȃ������B
�@�܂��A���̈ȑO�ɂ��n�k�E�Ôg�E�n�Փ��A�ߍ����̂̌x���F�����Ă��Ȃ�����A�d�͉�Ђւ̎��m�O���ӂ��Ă���A�X�ɂ͌����̎蔲���Ɏ��݂�����Ɠd�͉�ЂɎC�����Ă������Ƃ����X�Ɩ��炩�ɂȂ茴�q�̓����̗l����悵���BSPEEDI���NJ����镶���Ȋw�Ȃ��f�[�^���������Ȃ�������\�����A���\�̋`���͂Ȃ��A�����x�͂Ȃ��A�S�ēK�ɍs�������A�Ƌ��ق��J��Ԃ����B
�@�������ɍ��Ƃ��Ă͂��̐��x�̌��ׂ�F�߁A�o�ώY�ƏȂ̌��q�͈��S�E�ۈ��ǁB���t�{�̌��q�͈��S�ψ����p�~�B�������̏Ȓ��ɂ��������q�͈��S�Ɋւ��镔�ǂ�p�~���A1���ɓ������邱�ƂɂȂ����B
�@�L����5�l�ɂ��u���q�͋K���ψ���v�ƌ����Ɨ������g�D��9�����������h�ɂ��Ĉψ��C���҂�I�l���B
�@�Ɨ����̍����ψ���Ƃ��āA�Z�p�I�E���I�Ȏ����̔��f�͈ψ���ɈςˁA���͈̔͊O�̔��f�͎�����A�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�ۈ��@���s���Ă����Ɩ����́A�V���Ɋ��Ȃ̑g�D�̈ꕔ�Ƃ��āu�K�����v��ݒu���A��1��l�̐��̊����ɂȂ�炵���B
�@��ь����͖�c���������̊������Ĉ��S�f���A�ĉғ���F�߂����A����ɑ������̌����̍ĉғ��́A�V�����o����u���q�͋K���ψ���v�����S�����m���߂Ĕ��f���邱�ƂɂȂ�B�����A�ǂ̂悤�Ȋ�ɂȂ�̂��͂��ꂩ��̖�肾�B
�@���̌��߂Ă��܂����̂�
�@������܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�12�N6��18���A�����V��������ɂ���ăX�N�[�v����A�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B
�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂����B
�@�X�ɒ�����i�߂�ƁA�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�Ɛ��ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B
�@�Ƃ��낪�����E�Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�Ȋ��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B
�@�̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�B���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B
�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B
�@��ꌴ�����̂̂��ƒ����ɃA�����J������q��@�ɂ������ŕ��ː��ʂ̏ڍׂȁu�����n�}�v������Ă����ɂ��S��炸�Z�����w���Ɋ��p�����A���̋M�d�ȃf�[�^����u���Ă������ŁA���̑��݂���F�߂悤�Ƃ��Ȃ��������{������Ƃ��̑��݂�F�߁A�o�ώY�ƏȌ��q�́E�ۈ��@�̕����p��������12�N6��26���A��F�A�x���A�Q�]�̉������K��Ӎ߂����B���̌�A����12�s������K��Ӎ߂���\��ɂȂ��Ă����B
�@���ɓ�{���s�ɂ���Q�]��������ł͏�x�ꂽ���̂ɍ����ː��ʂ̒n��ɑ����̔��҂����܂��Ă������ߔ픘���Ă��܂��������m��Ȃ����ł́A�n�꒬���Ɣ�����Ȃ��璷���Ԃ̉�k���s��ꂽ�Ƃ����B
�@�������A���̖��Ŏ��̌�1�N3�������o���Ȃ���ΐ����ȎӍ߂������Ȃ����̍��̍s���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��BSPEEDI���ł͕����Ȋw�Ȃ����S�ɒ��ق����܂܂����A�����B�v���������n���ɎӍ߂ǂ��납�A���̐������Ȃ��͈̂ӊO���A�Ɣᔻ���Ă���B����s���̒������������̑ԓx���B
�@�X�Ɍ��q�͕ۈ��@�̐X�R�P�́E���q�͍ЊQ��Ă�6��28���A�L�҉���s���A�ۈ��@�ً̋}���Ή��Z���^�[�ɂ͉����n�}�f�[�^�̎����͎c���Ă��Ȃ������B�Ɩ��炩�ɂ��A�j�������̂��A���������̂��A���݂��Ȃ��̂͊m�����Ƌ��������B
�@���݂��Ȃ��Ƌ�������Ζƍߕ��ɂȂ�炵���B
�@�ۈ��@�̐E���ɒ�����蒲�����������ʁA�ۈ��@�̍��ێ������A���Z���^�[�̕��˔ǂɓ͂����B
�@���̎����̓z���C�g�{�[�h�ɒ����Ă������̂��̐E�����ڌ����Ă������A���p�����`�Ղ͑S���Ȃ��A�X�ɏ���@�ւɕ��悤�ȂǂƂ͑S���l���Ȃ������B
�@���̎��������ː��ǂɂ͎c���Ă��炸�A���ː��LjȊO�̕����ł͎����Ƃ��Ă͎���Ă��Ȃ��Ƃ����B�]���Ĕ��U���ׂ̈̎����Ƃ��đS�����p����Ȃ��܂ܕ��u����A�����Ă��܂����̂��A�����ꂽ�̂��B

�@���̑g�D��Љ�̑g�D�́A����Ռ��I�ȏo�������N����ƁA���i�͑S�������Ă��Ȃ��f�ʂ����X�ƕ����яオ���Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂��ɍ���̌������̂͂��̗�ŁA�䂪���̑g�D�͂���قnj��ׂ��炯�������̂��ƒɐɎv�����炳�ꂽ�B
�@�i�ߓ��ɂȂ�ׂ����t���s����Ȃ̂��������W�A���͂���\�͂Ɍ����Ă������A�������g�����Ȃ���r�Ɍ����Ă����B
�@���̊������䂪�Ȓ�����������͈͂ŁA�Ȓ��Ԃ̘A�g�ɂ͂قlj����A�c����s���̕��Q������ɏo�Ă��܂����B
�@�X�ɂ����Ώ����i�K�ʼn䍑�̐����E�����̖��ԉ�Ђł��铌���d�͂ɐU���Ă��܂������Ƃɂ���B
�@���̌��ʂ��ǂ����͎���Ȃ����A�d�͉�ЂƂ̖������r�����������o�Y�Ȍ��q�́E�ۈ��@�͉�̂���A���̑g�D�Ɉߑւ������B�A�����g�͓����炵���B
�@���ꂪ���̜����Ȃ̂��A�X�P�[�v�S�[�g�Ȃ̂��͔��f�ɖ����Ƃ��낾���A�S�ӔC�͓��t�ɂ���Ƃ͂��Ȃ������B

�@�����悤�Ȏ��́E�����Ƃ��āA�؍���300�l�]�̋]���҂��o����4���̃t�F���[���v���̂ŁA���̍����L�́u�����ӔC�v��哝�̂ɋ��߂��B
�@���̌��������炩�ɂȂ�ɂ�A�D�������̐��A���E�ƋƊE�̖����̐��A���{�̐ӔC�͑傫�����Ƃ͊m�������A���̐ӔC�͌��哝�̂ɏW�����郍�W�b�N�������B

�@���̌��ʂƂ��āu���̂�������ƑΏ��ł����A�ŏI�ӔC�͎��ɂ���v�Ƒ哝�̂͐������o�����B
�@�e���r�̉f�������Ŕ��f����̂͊댯�����~���Ԑ��ɖ�肠��Ɗ����Ă���A����ɋ삯�t�����C�m�x�@���̑D���E���̋~���Ԑ��Ɋւ��Ă��B���̌��ʂƂ��ĊC�m�x�@�����̂��̂���̂���Ă��܂����B
�@�܂��D���ȉ��̐E�������ׂ���q�~����������Đ^����ɓ����o�������ƂɊւ��ẮA�V�[�}���Ƃ��Đl�ԂƂ��Ă܂��Ƃɑ������ׂ��s�ׂł����āA�������狊�e�𗁂т邱�Ƃ͓��R�̌��ʂ����A�Y����������ނȂ��B
��Q�F�������ɃA�����J�����ŕ�����ꌴ���̂悤�Ȍ������̂��N�����ꍇ�A�Ή�����g�D�͂���̂ł��傤���H
�@A�F�A�����J���O�����q�͋K���ψ���iNuclear Regulatory Commission�ANRC�j�̓A�����J���O�����{�̓Ɨ��@�ւ̈�ł���A���O�����ɂ����錴�q�͈��S�Ɋւ���ēƖ��i���q�͋K���j��S������B
�@NRC�̋K���Ɩ���3�̎�v�ȕ�����J�o�[����B
�@���@���q�F�F���d�p�A�����p�A�J���̂��߂̎���i�A�����p�A�P���p�̏��p���q�F
�@���@�e�����F��w�A�H�ƁA�w�p�̂��߂̊e�{�݁A�y�єR�������{�݂ɂ�����e�����̗��p
�@���@�j�p�����F�j�����y�ъj�p�����̗A���A�����A�p���y�ъe�{�݂̔p��
�@NRC�g�D�͖{���i�����[�����h�B���b�N�r���s�j�A�S��4�̒n��ɕ����A���ꂼ��n���ǂ�u���A104��̔��d�p���q�F��36��̔d�p���q�F�̉^�]���ē��Ă���B
�@���̋Ɩ����e
�@���@�e���d�p���q�F�ɂ͊ē����풓���A�����̉^�]�����j�^�[����B
�@���@�l�X�ȃX�y�V�����X�g����\������鑽���̓��ʊč��`�[�����A�e�T�C�g����č����s���B
�@���@�������ʕ�҂���̒ʕ�͖{���K���ǂ̐\�����Ē�������ɂ�蒲�����s���BNRC�S�E��4,211�l�i2010�N10�����݁j
�@NRC�̈ψ��̓A�����J���O���哝�̂ɂ���Ďw������A�A�����J���O����@�̓��ӂɊ�Â��ĔC��5�N�A�ψ�5������Ȃ�B
�@5���̂����A1���͑哝�̂���ψ����y�шψ���̌��I���X�|�[�N�X�}���Ƃ��ĔC�������B
�@���݂̈ψ����̓O���S���[�E���c�R�iGregory B Jaczko�j���A2005�N1��21���u�b�V���哝�̂ɂ���đI�C���ꂽ���A2009�N5��13���I�o�}�哝�̂ɂ���čĂёI�C���ꂽ�B�i�哝�̐ꌠ�����j
�@�䍑�̕ۈ��@��A�z���邪�A���̌����͐��ŁA���������Ō������̂��N�����ꍇ�A���̑Ή��̌����͒������܂߂đS�Ĉψ����Ɉς˂���B
�@���c�R�ψ����͑f���q�����w�҂ŁA���q�͂Ɋւ��Ă͐��Ƃł���A���̈ψ�����⍲����̂��G�l���M�[�����ł���`���[�����A���̐l�̓m�[�x�������w�܁A��܂̐l���B
�@�I�o�}�哝�̂͑S�Ă̌�����^���A�哝�͎̂��̑�ɉ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�d�v�Ȍ��f��K�v�ȂƂ��Ɋւ��ẮA���������F��^���邱�Ƃ͂����Ă��A�哝�̂����߂����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�����A����̕�����ꌴ���̂悤�ȋK�͂̎��̂��A�A�����J�����ŋN�����ꍇ�́A���̒����A�����̊�����NRC�ψ������i�ߓ��ƂȂ�S�w��������܂��B
�@����NRC���c�R�ψ�����2011�N10��4���A�c��̌�����ŕ�����ꌴ�����̂Ɋւ���،��Ƃ��āA�n�k�A�Ôg���\�z����Ă����ɂ��ւ�炸�A����u���Ȃ������̂�����A���̂͋N����ׂ����ċN�����l�Ђ��B���̌�̎��̏����̃��^�c�L�͍����@�̕s���A�S�ӔC�������Ďw���ē���i�ߓ��̕s�݁A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D���̂��̂̕s�����������A�ƒɗ�ȓ��{�ᔻ�̏،��������B�iCNN�j
�@�m���Ɉꍑ�̍ɑ����A���̌���A�d�͉�ЁA�n�������̓��X�Q���������삯����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ���Ύi�ߓ����A��������g�D�͑��݂��Ȃ������A�Ɣᔻ����Ă��d�����Ȃ��B
�@NRC�̌�������m�点���ɂ��W��炸�A����������A���{���{�A�d�͉�ЁA���A���̂��N���Ă���̃N�����g����������̉����\���o�܂ł��f���Ă������{���{�̑ԓx�ɓ{�肪�����o�����悤�ł��B
��Q�F������ꌴ���̎��̂̌o�߂��V�h�����h���ȏ�ԂŔ��\���Ă���ۈ��@�̐E�������܂������A�ǂ̂悤�Ȗ����Ȃ̂ł����H
�@A�F�}�슯�[�����̔��\�Ƃ͕ʂɋL�҉���Ă�����l������܂����B�����͕ۈ��@�ł���������������Ȃ̂��A�ǂ��ɏ������Ă���̂��A����Ȃ��������������Ǝv���܂��B
�@���[�����͓��t�̃X�|�[�N�X�}���ł�����A���t�̃��b�Z�[�W��`����̖�ڂŁA�v�̂悭�`���Ă���܂����B
�@����A�ۈ��@�́A���q�͈��S�E�ۈ��@���������̂ŁA�o�ώY�ƏȂɑ������@�ւŁA���q�́A���̑��̃G�l���M�[�Ɋւ����S�y�юY�ƕۈ��̊m�ۂ�}�邽�߂̋@�ցA�����G�l���M�[���̓��ʂ̋@�ւł���B
�@2001�N1��6���A�����Ȓ��ĕ҂̍ՂɐV�݂���A�����̕ۈ��������傽��C���Ƃ���s���@�ւł���B�{�@���o�Y�ȑ������ɕʊقɂ���A�n���@�ւƂ��āA�S�����v�̒n�ɎY�ƕۈ��ē��A���q�͕ۈ�������������������B
�@����@803���i�{�@443���A�ē���360���j
�@���̋Ɩ��Ƃ���
�@���@���q�͂ɌW��鐻�B�A���H�A�����A�ď����y�єp�Ƃ̎��ƕ��тɔ��d�p���q�͎{�݂Ɋւ���K�����̑������̎��Ƌy�ю{�݂Ɋւ�����S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
�@���@�G�l���M�[�Ƃ��Ă̗��p�Ɋւ��錴�q�͂̈��S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
�@���@�Ζ�ނ̎����܂�A�����K�X�̕ۈ��A�z�R�ɂ�����ۈ����̑��̏����ɌW���ۈ��̊m�ۂɂ��邱�ƁB
�@���@���������ɌW��鍑�ۋ��͂Ɋւ��邱�ƁB
�@���@�O�e���Ɍf������̂̂ق��A�@���Ɋ�Â��o�Y�Ȃɑ�����鎖���B
�ȏオ�{�@�̋Ɩ��ł���A�o�Y�Ȃ�1�@�ւł���B
�@�]���āA�ۈ��A��������̂ŁANRC�̂悤�ȓƗ��@�ւł͂Ȃ��A���̂ɍۂ��Ă͒��ڂ̒������ɑΏ�����@�ւł͂Ȃ��B
�@�����̑唼�͕ۈ��@�̑��݂�m��Ȃ������B���̑��݂�m�����̂͌������̂̌o�ߔ��\���A�ۈ��@�̐E�����V�h�����h���̔��\�ŁA�I���Ǝv���A�����ĕۈ��@�Ƃ͂ȂɁA�ƂȂ�A���q�͂̊ē������ƒm��A���̂�h���Ȃ��������肩�A�����ɒm�点��ׂ������B�����̂����삵���̂��A�N�̂��߁A�Ȃ�̂��߁A���݉��l���̂��̂�����Ă���B
�@����̕�����ꌴ�����̂��A���q�͗��p�𐄐i����o�Y�Ȃ��猴�q�͈��S�E�ۈ��@���o���邩�ǂ����A���i�ƌ����͕ʑg�D�ɂ��ׂ��s�������͂��߁A���t�{�ւ̈ڊǁA���͍ЊQ�����ږh�~�ɖ��߂邱�Ƃ��ł��鑍���ȏ��h���Ƃ̍ĕ҂���������邾�낤�B
�@���̕ۈ��@�̐E���͌����ɏ풓���Ă���A���̌�͌���Ɏc���Ė{�@�A���@���ɏ����`��������̂��낤����ǁA�������ƕ��������֔��A�X�ɌS�R�s�֔��A������Ȃ̂��A�㕔����̎w���Ȃ̂�����܂���B�������A���d�̐E���u�t�N�V�}�E�t�B�t�e�B�v�͌���Ŋ撣���Ă���Ă���̂ɁA�����Ў藎���̋C�����܂��B
��Q�F���{���{�͏����B���Ă���̂ł͂Ȃ����A�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƊO�����f�A����啪�������ꂽ�悤�ł����A�z���g�ɉB���Ă����̂ł����H
�@A�F�܂��ɒʐM�q������ŁA���E���ɑ���ꂽ���܂����Ôg�̉f���ɁA�e���r�̑O�ɓB�t���ɂȂ�A���E���ɏՌ����������B����ɑ����Č����̎��́A�Ď��q���Ő��f�����Ŕj�������̉f���ɁA�����C�����A���q�F�̔����Ɖ��߂��Ă��܂�������A���k�n���E�֓��n������ł��邾�낤���f�����悤�ł��B
�@������ݓ��O���l�͉��ɂƍ��O�ւƔ��Ă������B�ݓ��e����g�فA�̎��ق͑S�͂������ē��k�E�֓��ݏZ�̎������ɓd�b�ʼn��x�������Ăт������B
�@����͍ŏ��A�����J���{���A�ݓ��A�����J�l�ŕ�����������80km�����ɏZ�ރA�����J�l��ΏۂɌ��O�����g�ق�ʂ��ĘA�����͂��߂����Ƃ���A���̍ݓ���g�ق��玩�����ɑ���Ăɔ��x�����������̂ł��B
�@�O�����{��25�N�O�̃`�F���m�u�C���������̂̔ߎS�����O���ɂ���A�����̃\�A���{�͎��̂����\�����A���ː��������������ɏ���ĔE�т���Ă������|�A�ŏ��ɋC�t�����̂́A�y���������ꂽ�X�G�[�f���̌����ŁA�Ď��p�̃K�C�K�@�[�J�E���^�[�̌x����A���[�^�[�̎w�j�͒��ˏオ�����B
�@�W���͓����q�F�̎��̂��Ƌ����Ē����������A���̒���Ȃ��A���̂������[���b�p�e�n�ɂ��錴���A�������A��w���ł��K�C�K�@�[�̌x�A���[�^�[�̋}�㏸�A�呛���̂����Ɋe�n�̕��ː������̔Z�W�A���̕��̕�������T��A�����_�̓\�A�������Ɠ��肵�����A�\�A���{�͒��فA�ܘ_�}�X�R�~�⒲���c�̓����͔F�߂Ȃ��A�����A��ނ͏o���Ȃ��A
�@�]���āA�����Ŋϑ����Đ������邱�Ƃ����o���Ȃ������̂ŗ]�v�ɋ��|���������B
�@���̌��ǂ����邩�猴�q�F�����ɊS�����܂�A���x�̕�����ꌴ���́A�����{��k�ЂŒn�k�A��Ôg�Ő��E�������ڂ��Ă������ő����ċN�������߂ɐ��f�����̉f���𐢊E�������߂Ď����̂ŁA�����C�����ɂ�錴�q�F�{�̂̔����Ɗ��Ⴂ���A�`���C�u�C���̔����͂P�@�ł������A���������͂R�@�ғ����Ă���A�P�������A�R�������A�����A�Q�������������オ��Ƒ����A���E�����`�F���m�u�C�����y���ɑ傫�ȏd�厖�́A�ɒ[�Ɍ������̐��̏I������킹��܂ł������B
�@�]���āA���{���M�͐̕��܂����ߎS�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�A�v���Ă������A�ۈ��@�̔��\�͉��̂����{�l�������Ă��Ӗ��s���ȃV�h�����h���ȉ����A�O���l�L�҂ɂ͗����ł��Ȃ��L�҉�A�}�슯�[�����̐��{���\������͂悢���A�o�߂����̔��\�ʼn��s�����Ȃ��A��������b�ʖ�͂����Ă��A�����ʖ�͂Ȃ��Ў藎���̋L�҉�ł����B
�@������A�ۈ��@���O���l�����̋L�҉������Ă���ACNN�ł��̒��p�������B
�@�ۈ��@�̐����R�c�����S�����Ă���A�������������₪����܂������A����܂�����̈��������ɐ���Ȃ��悤�ȉ����ɏI�n�A�L�҉�ɗՂL�ҒB�͉����Ă����悤���B
�@����Ɍ���Ɏ�ނɍs���Ȃ����ǂ������v�������������̂ł��傤�B�L�҉�̌�ŁA�P�L�҂��H���A�{�Ђ�������ƌ@�艺�����L���𑗂�Ɩ�̍Ñ������A���\�����Ȃ��A�������o�߂����̕\�ʂ����ŁA����L�������Ȃ��̂ŁA���{���{�͉����d������B���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ�����͓̂��R�A�������̗l�ȋL���𑗂����悤���B
�@�������A���Ă̑�{�c���\�̂悤�Ȉӎ��I�ɋ��ӂ̔��\���������A�Ƃ������̓[���ł͖����ł��傤���A���Ȃ������Ǝv���B
�@�ŏ��̐��{���\�ł̓��x��4�����Ƃ��Ă��܂�������A�X���[�}�C�������̂��͒Ⴂ���炢���Ƃ����S���Ă��܂������A���̔��\�̓��x��5�ɂȂ�A����Ƀ��x��7�ƈ����グ���Ɣ��\���ꂽ�Ƃ��̓`�F���m�u�C���Ɠ������x�ƒm���ċV�����B
�@�e���r�Ō��q�͂̐��Ƃ�������Ă������A���ŗ�₵�Ă����Α��v�A�䍑�̋Z�p�͂������Ă���Ύ�������̂͋߂��ƁA���Ă������A���x��7�Ɉ����グ���Ă���͉���҂��ԑg��������Ă��܂����B
�@�O���ł̕ł́A���d�A���{���{�̐ӔC�Njy�̘_���������A���Ƀt�����X�E���f�A�͌������荞��ł����B���d�̃g���u���B���A�u�Ӗ��ƕs������10�N�v�A���̌�̌��ʂ��̊Â��A���{�ɂ͌��q�͂̐��Ƃ͂��Ȃ��A�Ƃ܂Œf���Ă���B�h�C�c�ł́u���̋��|�����v�u�����ɕ��ː��̉_�v�Ɣ����������悤�ȋL���������A���V�A�A�����A�؍������E�̃��f�A���������ĕ��͓̂��{���{�A���d�̌��ʂ��̊Â��A���ɉ��Ή��A�����݂̓����w�E�A�܂���萳�m�ȏ������Ȃ�A�����J���{�Ɏ�ނ��������m�����A�Ƃ̔���������������B
�@���{���{�̏�����B���̐^���͂ǂ̒��x�Ȃ̂��͕�����Ȃ����A�����̓��h�A���]��Q��|��ĉߏ��]���������炢�͂������悤�����A�܂��A���d���̂������o���ɂ���ł����悤�ŁA���̑O�ł�������ₖ��A�B���H��A�����̓������ݏ��������x����莋���ꂽ�O��������A���R���̌���������Ă��邾�낤�Ɛ�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�O�����f�A����͔ᔻ�I�ȕ����������������A����Ȃ��̂Ő��_�ő�U���ȋL�������ꂽ�̂��������B
�@��M�����Ȃ�����A���邢�͏��̌��ʁA�������ē��{�ɑ��鈫��������A�M�p�������Ă��܂������ƂɂȂ�B
�@�S�Ă̂��ƂɌ����邱�Ƃ͓��{�l�͏�M����肾�B�B��������͍̂��������B
��\�́@SPEEDI���
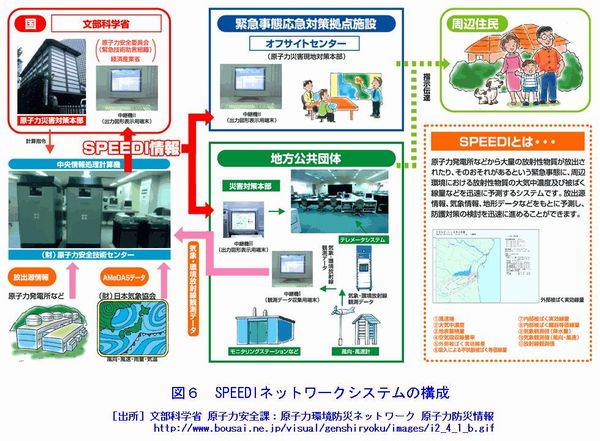 |
�@SPEEDI�Ƃ�
�@SPEEDI�@�ً}���v�����˔\�e���\���l�b�g���[�N
�iSystem for Prediction of Environmental Emergency Dose Information�j
�@�����Ȋw�ȏ��ǂ̍��c�@�l�E���q�͈��S�Z�p�Z���^�[���^�p����A���˔\�̉e����\�����邽�߂̃V�X�e���B
�@���q�͔��d���Ȃǂ̎��̂ɂ���ʂ̕��ː����������o���ꂽ�ꍇ�A�Ⴕ���͑��̋��ꂪ����Ƃ����ً}���Ԕ����ɑ��āA���o���̏����ӂ̋C�ۏ�����n�`�f�[�^�Ɋ�Â��A���ӊ��ɂ�������ː������̑�C���Z�x��픘���ʂ̂ȂNJ��ւ̉e����\������V�X�e���B
�@SPEEDIINNET�@���h��N�l�b�g
�@SPEEDI�ɂ�2�̖���������B
1�A���q�ً͂̋}���ɂ����āA����W���{�����h���̌�����i�߂�ۂɁA���ː������ɂ����ւ̉e���\��������邱�ƁB
�\�����ɂ́A��C�̕����A�����A��C���̕��ː������̔Z�x�A�ړ������A���x���A�O���픘�ɂ��������ʁA�z���ɂ��b��B�������ʂ�����B
2�A�S���̌��q�͎{�ݎ��ӂ̊����ː��Ď��ƈُ펙�̒ʕ�B
SPEEDI�ł́A�S���̊W���{��������E�Ď����Ă��錴�q�͎{�ݎ��ӂ̊����ː��f�[�^���A�펞�I�����C���ŁA10�����Ɏ��W���āA�����̊����ː��f�[�^�������l���������ꍇ�A�����I�Ɍ��q�͖h�ЊW�ҁi���q�͋K���ψ���A���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�j�̌g�ѓd�b�ɒʕ��B
���{�����ɂ̓t�@�b�N�X�ŏ��͏ڍׂȐ}�ʂ�������B
 |
�@SPEEDI�̊J���E�^�p�̌o��
�@���a54�N3���ɔ��������A�����J�E�X���[�}�C���A�C�����h���q�͔��d�����̂��_�@�ɁA���a55�N�ɓ��{���q�͌������ɂ����āA���̔������Ə����ӊ��̕��ː������̕��z�Ɣ픘���ʂȂǂ̗\���̂���SPEEDI�V�X�e���̐v���J�n�A���a59�N�Ɋ�{�V�X�e���������A���V�X�e���̊J���ɂ����Ă͌v�Z���f���������邽�߂ɁA��O�g�U�����A���Ր��ϑ��A�����������̊e��������J��Ԃ��A�\�����x�̊m�F���Ȃ��ꂽ�B
�@���a59�N����l�b�g���[�N���̂��߂̒������s���A���̗��N���畟�����A���ꌧ�Ȃǂ�ΏۂƂ���SPEEDI�l�b�g���[�N�V�X�e���̈ێ��E�^�p���J�n�����B
�@����2�N�ɒ�������v�Z�@���i�����j���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�ɐݒu����A���݂̉^�p�`�ԂɂȂ����B
�@���̌�l�b�g���[�N�͂��g������ĕ���14�N�ɂ�19���{���ƂȂ�A�X�ɑS��22�����ɐ������ꂽ�I�t�T�C�g�Z���^�[�Ƃ��ڑ����ꂽ�B
�@���̊ԁA�n�[�h�E�F�A�[�̐i���ɂƂ��Ȃ���������v�Z�@�A���p�@�P�y�ђ��p��Q�̍X�V���s��ꂫ���B
�@����17�N1���ɂ́A�C�ۗ\���̕��@���͂��߂Ƃ��āA�\�����x�̌����}�邽�߂ɉ��ǂ��ꂽ�v�Z���f���ւ̍X�V���s��ꂽ�B
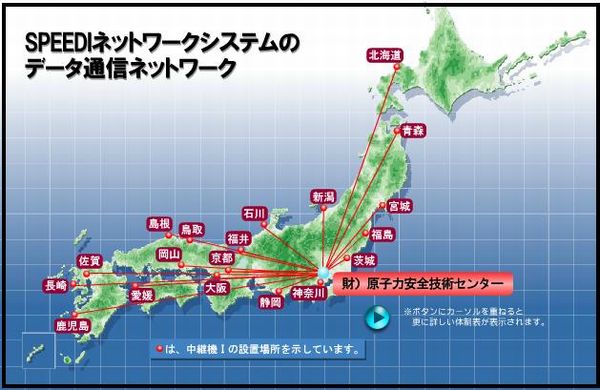 |
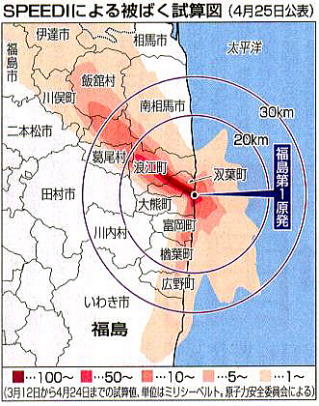 |
�@AMeDAS
�@�A���_�X�iAMeDS�j�iAutomated Meteorological Data Acquisition System�j
�@�C�ے����Ǘ����鍑����1,300�ӏ��̖��l�C�ۊϑ����u����d�b����Ńf�[�^�����Ԗ��ɋC�ے��̃R���s���[�^�ɑ��荞�܂��B
�@�ϑ�����C�ۗv�f�́A�~���ʁA�C���A���Ǝ��ԁA�����A������4�v�f�ł���B
�@�ϑ��œ���ꂽ�f�[�^��ISDN����Ȃǂ�ʂ��ċC�ے����̒n��C�ۊϑ��Z���^�[��10�����ɏW�M����A�f�[�^�̕i���`�F�b�N���o����S���ɔz�M�����B
�@�A���_�X�̃f�[�^�́A�C�ے�HP�Ō��J�����悤�Ȓn�}�A�\�`���̊ϑ��l�Ƃ��ė��p�����ق��ɁA���l�\��̓��̓f�[�^�Ƃ��ėp������B
 |
 |
�@�l�ʂ�n���ɂ��A���_�X���u�͐������ݒu����Ă���A����3��11���ɓd�b����Ɉꕔ��Q���������̂��A���͌��݂�10�����ƂɊϑ��f�[�^�𑗂葱���Ă����B
�@SPEEDI�͕����Ȋw�ȏ��ǂ̊O�s�c�̂ł��錴�q�͈��S�Z�p�Z���^�[���^�c���Ă���A��������v�Z�@�𒆐S�Ƃ��ĊW�{�ȁA�W���{���A���{�C�ۋ���A�I�t�T�C�g�Z���^�[���ƃl�b�g���[�N�Ō���Ă���A�W���{������̋C�ۊϑ��_�f�[�^�ƃ����^�����O�|�X�g����̕��ː��f�[�^�A�y�ѓ��{�C�ۋ�����GPV�i�i�q�_�����j�f�[�^���펞���W���ً}���ɔ����Ă���B
�@��ꌴ�����̎��ɂ́A11����ɂ͕��o��������ɁA�����A�����A���ː������̑�C���Z�x�A�픘���ʓ��̗\���v�Z���s���A�����̌��ʂ́A�l�b�g���[�N��ʂ��ĕ����Ȋw�ȁA�o�ώY�ƏȁA���q�͈��S�ψ���A�W���{���ɑ���ꂽ�B
�@���@�ɂ�12�������ɓ͂���ꂽ�B���������ɂ��t�@�b�N�X�ŏ��͑����Ă����B
�@����������A�Ɗ��@���������������������A���͂������B���������x�����x���t�@�b�N�X�ő����Ă������Ƃ͎������B
�@����̒����ɂ��ƁASPEEDI���͕��������ɓ͂��Ă������Ƃ������B
�@���������ЊQ���{���i���������\����24�N5��19���j
�ۈ��@����Fax�ɂ��3��13��10��37����M�A3��12������3��13���܂ł̎��Z���ʂ���M�B
NUSTEC����d�q���[���ɂ��3��15�����A3��15��8���̎��Z���ʂ���M�B
�@�����̌����i����24�N5��23�����\�j
NUSTEC����d�q���[���ɂ�蕟��������3��12��23��54���ɑ��M�����B
NUSTEC����d�q���[���ɂ��3��11��23��49���A���q�̓Z���^�[�֑��M�B
�@�������̑���Ɋւ������̌���
���ЊQ���{���ɂ�����SPEEDI���̎�M�J�n��3��12��23��54���ł���A3��16��9��45���܂ł�86�ʂ�SPEEDI������M���Ă������Ƃ������B
����͍��̌����ƈ�v�����B
���̊ԁA��M����86�ʂ�SPEEDI���̂����AUSB�������[�A������Ƃ��ĕۊǂ���Ă����̂�21�ʂ̂݁A�c���65�ʂɊւ��Ă͓d�q���[���f�[�^�̎c���L�^�͏������Ă��邱�Ƃ����������B
�@��SPEEDI������M���Ă��Ȃ���S�����p�o���Ȃ���������
�@�E���ЊQ���{���ɂ�����SPEEDI���̎�舵���K��̕s��
�@�E���ЊQ���{���ɂ�����g�D�Ή��̕s��
�@�E�d�q���[����M�e�ʂ̐���
�@�����̑Ή��̖��_
�@�E���ЊQ���{�������ǂɂ�����SPEEDI���̏�L�ӎ��s��
�@�E���ЊQ���{�������ǂɂ����錧�ƍ��̌����̑���ɌW���ڍג����̜��

�@���̌��ʂƂ��āASPEEDI���͌��ЊQ���{���ŗ��܂��Ă��܂��A�̐S�̔픘�̋���̂���n��ɂ͓`��炸�A�������m���ɂ��͂Ȃ����悤�ŁA�������̑g�D�Ƃ��Ă��s�������������Ƃ�\�I���Ă��܂����B
�@���̓_�Ɋւ��ẮA���{�����ł���ςȕs�������邱�Ƃ����������B
�@3��12�������A���@�ɂ�SPEEDI���͓͂��Ă����B����A�}�슯�[�������F�߂��B�܂�SPEEDI�̉^�p�͕����Ȋw�Ȃł���A���t�̈���ł��镶���Ȋw��b�͊��@�ɋ����̂����當���Ȋw�Ȃ���A���͂����Ă����͂������A�������ɂ͓`����ċ��Ȃ������݂������B
 |
 |
�@SPEEDI���͂������̂�����͍ō��i�ߕ��ł��銯�@�ɏオ���Ă���͂������A���������Ă��܂����̂��A���������̂��͂킩��Ȃ����A���t�Ƃ��Ă͒N���C�t���Ă��Ȃ������Ƃ����ُ펖�Ԃ��N���Ă��܂����B
�@���͔c�����Ă���
�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ����q�͈��S��ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B
�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B
�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B
�@���������Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B
�@���������̋M�d�ȏ��͌��\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏�ꕔ�����ꂽ�炵���A��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B�������ɂ��t�@�b�N�X�ő����Ă��Ă����j
�@�������ЊQ���{���ɂ͊m���Ƀt�@�b�N�X����M���Ă����B�ł͉��̌��n�ɏ�����Ȃ������̂��B
�@���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ƕٖ����Ă������A���̂悤�ȕٖ����ʗp����̂��B��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉��B
�@���������͒m�����͂��ߌ�������SPEEDI���̑��݂��环��Ȃ������ƕٖ������B�ӔC���ǂ̒��x�����Ă��邩�͐��������B
�@��������߂ɉ����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��āA�����Ȋw��b��SPEEDI�̏������\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�ƕى����J��Ԃ����B
�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v�Ƃ���ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�����\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B
�@���̈�ː쒬�����،������A�����J���{�́u�����}�b�v�v�ɂ��Ă��\���q�ׂ����B
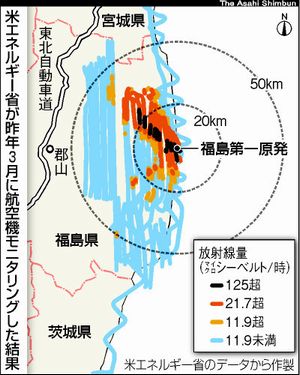
��SPEEDI���ȊO�ɂ��������i�����n�}�j���������B
�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B
�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B
�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B
�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B
�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B
 |
�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��Ƃ��N�����B�Q�]���ԉF�ؒn��ɔ��Ă����l�B�̑O�ɔ������̉��l������A�����͊댯�����瑁��������Ǝw���A���̗l�ɋ����Ă����炵���A���������O�������Ȃ̂炸�����Ă��܂������A����̗����ł������̐E���ł��Ȃ��炵���A�Ɖ\���Ă����B
�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@�Ƃ��������@�ɂ�SPEEDI���ǂ̕����Ȋw��b�A�A�����J���{������ꂽ�u�����}�b�v�v��SPEEDI���v�Z�������ː������g�U�\�z�}�̗���������Ă����͂��̌o�Y��b�ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�X�ɂ͌��q�͈ψ����܂ł��l�߂Ă���ɂ��S��炸�A���@�ɂ͑S�����オ���Ă��Ȃ��A���̂��Ƃɋ^��������Ȃ������̂��B�Ȓ��̒��Ƃ͒P�ɂ�����ɉ߂��Ȃ������̂��낤���B
�@��@�Ǘ��Z���^�[�̑��݈Ӌ`��₤
�@��@�Ǘ��Z���^�[�͉��̂����̋M�d�ȏ���c���ł��Ȃ������̂��A���邢�͔c�����悤�Ƃ��Ȃ������̂��B�����V�~�����[�V�������J��Ԃ��Ă���ΕK�R�����Ƃ��čs�����Ă����͂������A�c�O�Ȃ���Ӗ��͉ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B
�@�܂����@���f�[�^���Ȃ��܂܂ɁA3km���A5km���A10km���A20km���A30km���Ɠ��S�~���`���Ĕ��n������߂����A��@�Ǘ��Z���^�[�͂����̌���ɂ͎Q�����Ȃ��g�O�̑��݂������̂��B
�@�����ɉ����Ĕ������߂�ׂ������A�����Ɋ�Â��Ĕ������߂�ׂ����ƈӌ���\���������������Ƃ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�������͗��̉��l�ɂ����Ȃ������̂��낤���B
�@���@�͊�@�Ǘ��Z���^�[�₻�̑��̐��@�ւ�S���������Ă����̂��B
�@���̂悤�ȏd�厖���ɂ��S��炸���ݕs�M�Ɋׂ��Ă����̂��낤���B
�@�ČR����̎����َ͖E����A���u���ꂻ�̑��݂��������炩�ɂ��Ȃ��������A1�N3�������6��18���A�����V������1�ʂŃX�b�p�����ꂽ�B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȓ́u���˔\�����n�}�v���A�����đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɑ��t���A��������O���Ȃ͒S���Ȓ��ł��镶���Ȋw�Ȃƌo�ώY�ƏȂɓ]�������B���A���̋M�d�Ȏ������Z�����ɐ�������邱�ƂȂ��A�����܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�1�N3������ɒ����V���ɂ���ăX�N�[�v���ꂽ�B�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B
�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂����B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B
�@�������A���̂��̋M�d�ȃf�[�^�����Z���^�[���ɂ���Z�������S���ł���u�Z�����S�ǁv�ɓn��Ȃ������̂��A�Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��Ắu����Ȃ��v���J��Ԃ������A�������A�u�����n�}�v�͓��Z���^�[���̃z���C�g�{�[�h��A2���Ɋg�傳��Čf������Ă����Ƃ̂��ƁA�]���ē������ō�Ƃ���u�Z�����S�ǁv�̌W�����ڂɂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@�������A�����Ɏ�̂��Ȃ���ΑS���S�������Ȃ��A�^����ꂽ�Ɩ��͌����Ɏ��g�ނ��A�e���g���[�͈͈̔ȊO�͖��S�A�܂��ĊO���̃f�[�^���͖��������R�A�������A�����Ȋw�Ȃ��u���͋��L���ׂ������������m��Ȃ����A����ł̃��j�^�����O�����W���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒S���v�ł��邱�Ƃ������A�]���ĊC�O����́u�����n�}�v�̎�舵���ɂ��Ă͒S�����łȂ���Ή�ւ����A�C�O����̏���S������S�����͑��݂��Ȃ��A�]���Ė������ē��R�Ƃ̔F���ł����Ȃ��B
�@�u�����n�}�v�̎�舵���͕ۈ��@���S��������̂Ƃ̔F����\�����A�����Ȋw�Ȃɂ͂Ȃ�痎���x�͂Ȃ����Ƃ����������B
�@����Ȃ�Ε����Ȋw�Ȃ��S�����Ă���SPEEDI�ɂ��f�[�^������Ȃ�����\���Ȃ������͉̂��̂��A���m�łȂ�����������\���Ȃ������B�ƕٖ����Ă��邪�A�댯�������Ă���n���F�����Ă����͂��A�ł�����߂Č���ӔC�̂��镟�������̒S���҂ɘA�����ׂ����ƍl����B
�@�Ȃ���Ȃ��܂܉����n��ɔ��Ă����l�X�͔픘���Ă��܂����B�Ƃ��낪���̒n��ɔ��Ă����l�X�̂Ƃ���ɁA�˔@�������i�h��ߕ��j������A�����Ȃ̂炸�u�����͊댯�����璼���ɔ��ĉ������v�Ƃ��������ĕ��̂悤�ɋ����čs�������1�s�������炵���B
�@����s�����̌W���ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁA�u�����n�}�v���������Ă����l�X�̒��ڍs���Ȃ̂��A���݂ł����̐��͕̂s���B
�@�ł͉��̂���قǍ������Ă��܂����̂��A���q�͋K���g�D�Ƃ��Čo�ώY�ƏȁA���q�͈��S�E�ۈ��@�A�Ɨ��s���@�l�E���q�͈��S��Ջ@�\�B���t�{�A���q�͈��S�ψ���B�����Ȋw�ȁA���ː����j�^�����O����A�S�Ă��c����s���B
�@��������Ȓ����قȂ�g�D���������̂Ƃ���1�̍ЊQ�ɑΏ������ꍇ�A���O�ɖȖ��ȑł����킹�ƁA�g�D�S�̂����f�I�ɓ�������{���y�юi�ߊ������Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɍs�����邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��ɍ�����������炯�o���Ă��܂����B
�@�o�Y�Ȃƕ����Ȋw�Ȃ����������ō�Ƃ��Ă��Ȃ���u�����n�}�v�����L�A���p���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�������A�c����s���̕��Q���o���Ƃ̔F�������A�c����s���̒��_�͓��t���B�ɂ�������炸�A�����̋M�d�ȏ���i�ߊ��ł���ׂ��������͏�W�܂�Ȃ��܂܁A����ɉ��������A���d�{�X�ɓ{�荞��Ɠ�����������A���i�ߊ��Ƃ��Ă̎��o�����܂�Ȃ��̂����i�ߕ��𗯎�ɂ��Č����d���K��A������č���������ȂNJ�@�Ǘ��̐����S�������Ă��Ȃ����Ƃ����g�̍s���ŘI�悵�Ă��܂����B
�@��ꌴ�����̂ŒS������ۈ��@�͎��̒���ɏ����W�߂��ꂸ�A�����Ă����p�ł����g�D�Ƃ��Ă�����Ƌ@�\�ł��Ȃ������B
�@�܂����̈ȑO�ɂ��n�k�E�Ôg�E�n�Փ��A�ߍ����̂̌x���F�����Ă��Ȃ�����A�d�͉�Ђւ̎��m�O���ӂ��Ă���A�X�ɂ͌����̎蔲���Ɏ��݂�����Ɠd�͉�ЂɎC�����Ă������Ƃ����X�Ɩ��炩�ɂȂ茴�q�̓����̗l����悵���B
�@SPEEDI���NJ����镶���Ȋw�Ȃ��f�[�^���������Ȃ�������\�����A���\�̋`���͂Ȃ��A�����x�͂Ȃ��A�S�ēK�ɍs�������A�Ƌ��ق��J��Ԃ����B
�@�������ɍ��Ƃ��Ă͂��̐��x�̌��ׂ�F�߁A�o�ώY�ƏȂ̌��q�͈��S�E�ۈ��ǁB���t�{�̌��q�͈��S�ψ����p�~�B�������̏Ȓ��ɂ��������q�͈��S�Ɋւ��镔�ǂ�p�~���A1�ɓ������邱�ƂɂȂ����B
�@�L����5�l�ɂ��u���q�͋K���ψ���v�ƌ����Ɨ������g�D���A9�����������h�ɂ��Ĉψ��C���҂�I�l���B
�@�Ɨ����̍����ψ���Ƃ��āA�Z�p�I�E���I�Ȏ����̔��f�͈ψ���ɈςˁA���͈̔͊O�̔��f�͎�����A�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�ۈ��@���s���Ă����Ɩ����́A�V���Ɋ��Ȃ̑g�D�̈ꕔ�Ƃ��āu�K�����v��ݒu���A��1��l�̐��̊����ɂȂ�炵���B
�@��ь����͖�c���������̊������Ĉ��S�f���A�ĉғ���F�߂����A����ɑ������̌����̍ĉғ��́A�V�����o����u���q�͋K���ψ���v�����S�����m���߂Ĕ��f���邱�ƂɂȂ�B�����A�ǂ̂悤�Ȋ�ɂȂ�̂��͂��ꂩ��̖�肾�B
���A�����J�̑Ή�
�@�����{��k�Ђ̔�Q�~���ŃA�����J�R�́u�F�B���v�Ƃ��đ�K�͂ȉ��������������B
�@�A�����J�����̊����Ƃ��āA������ꌴ�����̔����㒼���Ƀ����[�����h�B�ɂ���NRC�I�y���[�V�����Z���^�[�ɂ��ꂼ��̐��Ƃ��W�����A�������W���Ė�2�����ɂ킽�芈�������Ƃ̂��ƁA���̊ԁA���f�����̕K�v���ȂǓK�ȃA�h�o�C�X�𑗂葱�������A�u�����n�}�v���l�A�i�ߓ��s�݂̂킪���ł͊��p�ł��Ȃ������炵���B
�@����NRC�ψ����ł������O���S���[�E���c�R����2011�N10��4���A�A�����J�c��E������ŏؐl�Ƃ��ēo�d���A������ꌴ�����̂ɂ��ď،������B
�@����ɂ��ƒn�k�A�Ôg�͗\�z����Ă������Ƃł���A���̑��S�������Ă��Ȃ������̂͑Ӗ��ł��薳�ӔC�ȑ̐��ɂ����̂ŋN����ׂ����ċN�����l�Ђł���ƕ����B
�@���̌�̏����Ɋւ��Ẵ��^�c�L�͎i�ߓ��̕s�݁A�����@�̕s���A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D�̕s�����X�A�җ�ȓ��{�ᔻ���،������B
�@�����͎w�E�̒ʂ肾���甽�_���o���Ȃ����A���̒��㑦���ɉ�����\���o�āA���ނ̒ȂǃA�����J���̍D�ӂ���s�ׂ����̂̋K�͂������o���Ȃ��܂܂ɂ��Ƃ��Ƃ��f���Ă��܂������{���{�Ɠ��d�̘����ȑΉ��ɑ����������Ă����悤���B
�@����ɂ͐��Ƃ�{������h�����Ĕ�s�@�ɂ���Ē����E���肵�č쐬���������}�b�v�����{���{�������������Ƃɑ��Ėҗ�Ɋ��݂����B

�@�����������̂̑�ɐ�O�������A���̍ۃA�����J�����̌��q�͋K���Ɋւ��A�@�K���̋�����d������A�A�����J���{�̓��{�ɑ���Ή���������������A�V�K���q�F�̐V�݂�30�N�Ԃ�ɔF�Ɋւ���ψ���ł̑Η��A�j�p���������ꌚ�v��𒆎~�����蓙�̓ƒf��s���������̂��A��4��l�̐E�����E�w������̂�5�l�̈ψ������A���̃g�b�v�߂�̂��哝�̂ɂ��C���ł���ψ����ł��邪�A���̃��c�R���͑ސE��A�Q�]����K��n�k�A�Ôg�A�����̎O�_���Ԃ��Ɍ����A��{���s�ɂ���Q�]��������ɔn�꒬����K�ˉ�k�����B
���S��������������n�ł̑Ή��́H
�@12��15��36���@1���@���q�F�������f�����A�����Ō���ޔ��A����l�̋~���A���������{�A�i���d3�l�A���͊��2�l�j�z�E�_�������|���v�͔����ɂ���U���ɂ��~�݂����P�[�u���������A�����d���Ԃ͎�����~�B�������Ă����C�������̂��߂̃z�[�X���������Ďg�p�s�\�A��ƒ��f�B
�@���̍��A��F���ł͔��w�߂ɂ��S�������s�����Ă̂Ȃ����ƂȂ������A��Îᏼ�s�ɉ������ݒu�����B
�@�o�t���͍�ʌ���{�s�ɉ�������ڂ��A�Q�]���͓��������̒Ó��n��Ɉړ��A��������͖�30km����Ă��邩��ƈ��S���Ă����B
�@12���[���A���̏W����1��̃��S���Ԃ����ꒆ�ɂ͌�����ʖh�앞�ƃK�X�}�X�N�𒅗p������l�����āu�����͕��ː��������g�U���Ă���B�댯�����璼�����Ă���v�Ɛ^���ȕ\��ői�����B���������̎���10km�����������A2�A3���������Ƃ̒ʒB�������̂ŁA30km�ȏ㗣��Ă���Ó��n�悪�댯���Ƃ͘I���̋^�����Ȃ���������V���Ē����ɕ����B����h�앞�̓�l�͘Q�]�������ɂ͉����`���������s���ʂ֑��苎���Ă��܂����B
�@�X��12��18���A�����甼�~20km�����w�߂��o���B�אڂ��銋�����ł͑S���������߂āA�h�Ж����ő����ɔ����Ăт����Ă���Ƃ̏�`�����A���Ă���Q�]�����̊Ԃœ��h���������B
��14���ߑO11��1���A��ꌴ��3���@�̔����Ŕ��Z���̕s���͉Q�������Ă����B������2���@4���@�����K�͂̔�����������˔\�͕��o�A�g�U�����B

�@3��14���ߌ�A�f���I�ɍЊQ���{����c���J����A�Ĕ��ׂ����ǂ������c���������B�������O������̕��˔\���͑S���Ȃ��A���ׂ̊������͑S�����Ă���A�Ó��n����댯�ł��邱�Ƃ͖{�\�I�Ɍ���Ă���A�����̍Ĕ������c�����B14�A15���͉J�ƐႪ�~��A��C���ɕY���Ă������ː������͒n��ɍ~��A���̂܂��������ɔ��Ă������ƂɂȂ�B
�@�����A�Ó��n��ɂ͉��̏����`����ꂸ�A������̏�͒f�ГI�ȃe���r���ł���A������j���[�X�\�[�X�͐��{���\����������A��@�I�ȗl���͑S���`�����Ȃ������B
�@����ɓ��d�̉������̐l�����ʌv�����Q���Ă��āA���̕ӂ͍��Z�x�����n�悾���璼���ɍĔ��������ǂ��Ɩ��ꗙ���ɍ����ė����������B
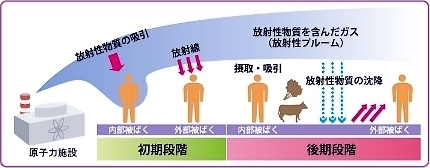 |
�@�f�ГI�ɓ����Ă�����ɂ��ƁA�����Ɋ댯��Ԃ̋��Ȃ̂��Ǝ��o�������A���̂���14���ߌォ��ЊQ���{���̉�c�������A�Ĕ��ׂ����ǂ��������c���u�ꍏ�������Ĕ��ׂ��v�̈ӌ�����ь������B
�@�������A���ː��ʂɊւ��鐳���ȏ��͑S���Ȃ��A����ł��Z���͍Ĕ��̕K�v����i���A�ЊQ���{�������A�n�꒬���ɔ������B
�@����̓e���r�ɂ��f�ГI�ȏ����A�אڂ��銋�����̑S�����̏���m��Ύ����B�����R�댯�ɔ�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B
�@14���[���ɂ̓��E�f��1�����͂����A�z�z���������p����̂͊e���̔��f�ɔC����Ƃ����B���̍��ɂȂ�Ɣ��Ă���Z�����s�������Ĕ������߂������B
��3��15���ߑO6���A4���@�����A2���@����

�@�n�꒬���͕K���Ŏ��̎�����T���A����v���E�Q�肵�A����Ɠ�{���s�̗����āA15������5��30���A�撷�A�Z����\���W�߁A��{���s�֍Ĕ��邱�Ƃ��������B
�@15����������Z���ɓ�{���s�֍Ĉړ����邱�Ƃ������A�e���ړ������A�ߑO10���A�ړ��J�n�A��Ăɓ�{���s�����ړ��J�n�A���̃o�X�͘V��҂��悹��{���s�ցA���̑��A��Òn���⌧���O�̐e�ʁA�m�l�𗊂��Ă��ꂼ��̒n�֎U���Ă������B15���[���ɂ͓�{���s�������a�x���ɘQ�]����������J�݂����B
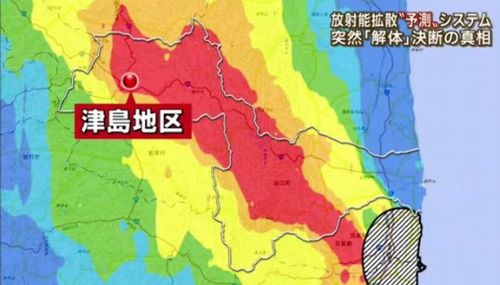 |
�@14���̔������̕��͒Ó��n����ʂɌ������Đ����Ă����B���̂��ߔ��w�����a20km���͉��̈Ӗ����Ȃ��A�Ó��n��A�ב��̊������A�X�ɉ��n�ɂ���ъڑ��A�얓���̈ꕔ���Z�x�̍��������n��ɂȂ��Ă��܂����B
�@14���̋L�^�͂Ȃ��B����͖���ɂ͕��ˑ�����������Ă������A�����҂��Ƃ̎v�����݂��玝�Q���Ă��Ȃ������B3��15���ߌ�A�Ó��n��͔Z�����˔\���ɏP���A��ƉJ���~���Ă����߂ɁA���˔\�͒n�\�ɗ����A�������˔\�͂��̒n�\�ɋ��������B
�@15����A�����Ȋw�Ȃ���h�����ꂽ�����^�����O�J�[���Ó��n��e�n�ő��肵�����A�v��͂Ȃ�Ɩ���270�`330�}�C�N���V�[�x���g���w�����B
�@16���̒Ó��n��̑���l����58.5�}�C�N���V�[�x���g�̕��ː��ʂ����肳��A4��22���Ɍv��I���n��ɐݒ肳�ꂽ�B
�@�ĒE�o����3��15���A�ߑO10���ɋ��c�̏�A��{���s�ֈړ����邱�ƂƂ��A�������V��̒��A��{���s�₻�̑��̉��҂����ďo���������A���̎����ɏ��ɂ͕��ː������P���Ă���A�J���Ƌ��ɒn�\�ɗ����Ă��Ă����B�ň��̒��ł̍ĒE�o�ƂȂ������A�����͋~���ɂȂ�͕̂��ː����̗��P�ƍĒE�o���������ł��������ƂŁA����1���ł��扄���Ă���Δ픘�̕|�ꂪ�������B
�@15��17��50���A�ŏI�E�o�o���B���̍��A�㍏�̒����ł͒Ó��n��A�ԉF�ؒn��̉����x�͍ō��l�������Ă���B
�@�ǒn�I�ɍ��Z�x�̉����n�悪���t�������B7��26�����_�ł̒����ŐԉF�ؒn��ő喈��26.3�}�C�N���V�[�x���g�A��Ó��n��ő喈��40.1�}�C�N���V�[�x���g�A���̖ڈ��ƂȂ�N�ԐώZ����20�~���V�[�x���g��Z���Ԃŏ�����ʂ��v�����ꂽ�B
�@�Ó��n��ɔ��Ă����Q�]������14���A15���A16���̊ԁA���̖ڈ��ƂȂ�N�ԐώZ�ʂ�啝�ɏ��鉘���n��ɑ؍݂��Ă������ƂɂȂ��Ă��܂����B
�@�X�ɂ͒Ó��n��̏Z���͉ƋƂł���ƒ{���̂ĂĂ܂Ŕ���̂����߂炢�A�唼�̏Z���͋��c���Ă��܂����B���̂��ߖ��ꗙ�����c��������邱�ƂɂȂ����B
�@���ː��v���[���i���ː��_�j�Ƃ������ۂ�����B�C�̏�i�K���X�邢�͗��q��j�̕��ː���������C�Ƌ��ɉ��̂悤�ɗ�����Ԃ���ː��v���[���Ƃ����B
�@���ː��v���[���ɂ͕��ː���K�X�A���ː����E�f�A�E�����A�v���g�j�E���Ȃǂ��܂܂�A�O���픘�A�����픘�̌����ɂȂ�B
�@���̕��ː��v���[�������ɏ����F1����Q�]�����ʂɗ���A���ː�ɉ������R�Ɉ͂܂ꂽ��n���悤�ɗ��ꂽ�Ɛ��������B
�@���ː��v���[�������ʉߒ��A�J��Ⴊ�~��Ƃ��̗��q�Ɍ��т��Ēn�\�ʂɍ~���Ă��邱�ƂɂȂ�B15��������J�ƐႪ�~���Ă����̂Œn�\�ʂ���������Ă��܂����B
�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@'12�N7��10���A�Q�@�\�Z����Ŗ�c���F�i�����j�́A���d������ꌴ�����̂Ŕ�Q�����������Q�]���ɁA�č�����������ː����茋�ʂȂǂ�`���Ȃ��������ƂɊւ��āu�W�@�ւ̘A�g�A��L���s�\���ł���A�Z���̖�����邽�߂ɓK�ɏ������J����p�����ł��������Ƃ͑傫�ȋ��P�ł���A�Q�]���̊F�l�ɂ����f�����|�����܂������Ƃ����l�т������v�ƒӂ����B
�@���̓��i7/10���j�Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă����Q�]���c��g�c�����c���́u�����͖��p�̔픘�������l�Ђ��̂��̂��B���O���Ɠ����ɕ���������Ă���v�Ə،��B
�@�����ɏ��v����Ă����o�t����ː썎�钬�����A�����l�܂点�Ȃ���u�����Γ����������ς��Ă����B���B���͔[���ł��Ȃ��v�Ə،������B
�@�픘�̎����͏ؖ��ł��Ȃ����A�����픘�����Ƃ��Čx�����Ƌً}�������A�v������A���������Z����4�ˈȏ��Ώۂɓ��N6������J�n�A3�ˈȉ��͍s�������ɂ����ی�҂�ΏۂɌ������s���A�Q�]����2,618�l�����B
�@���̌�A�b��B������10������n�܂�A3��11�����_��18�ˈȉ��������S�������ΏۂƂ��Č������s���邱�ƂɂȂ����B
�@��������ʘ_�����A������߂��n�}��ɃR���p�X�ʼn~��`���Ĕ��n������߂������n�I�Ȃ������S���Ӗ����Ȃ��Ȃ����s�ƂȂ����B
�@���͐��X�������B�A�����J������q��@�ɂ�钼�ڂ̑�C�ϑ��A�q���ʐ^���́A���l��@�@�ɂ��ϑ������f�[�^�͂��ē��{���{�ɏ�������B
�@���{���͎����Ă����Ȃ��疳���A���u���܂�������A�����J���͌��{�����B
�@���̐ӔC�҂ł�����NRC�����O���S���[�E���c�R���͌���A���l�̘Q�]�������@���A��{���s�ɂ���Q�]���������K��A�n�꒬���Ɖ�k���A�S����������œ����f����������A���c�R���͗܂��ׂȂ��畷���������Ƃ����B
 |
 |
��\�Z�́@���̑��̏������
��15��14���@���{�E�ً}�ЊQ���{���ݒu
�@�����E���K���ɂ��铌�d�{�Ђł́A�����В��͊��ցA������͒����֏o�����ŕs�݁A�u�d����������Ό��q�F�͗�₹�Ȃ��v�����Ă��Ă����������͂ǂ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B
�@���@�ւ̕�11��15���u1�`5���@���S�𗬓d���r���v�u1�`2�@�����s�\�v�����ē��d���u���q�F�̗�p���ł��Ȃ��Ƃ��A8���Ԃ܂ł͖�肪�Ȃ��v�ƕA����͔��p�o�b�e���[�̎g�p�\���ԁA���̊Ԃɗ�p�@�\�������ł���Ɣ��f�����炵���B
�@�������A8���Ԃ��߂�����6���ɂȂ��Ă����@�ɂ͘A�������A���@���瓌�d�֘A������Ɨv�̂Ȃ��ԓ������Ȃ����Ƃɓ{���������́A���痤�㎩�q���̃w����p�ӂ���7�������ɂ́A������ꌴ���֓������Ă���B
�@���ЊQ���{���̂���Ɛk�d�v���̉�c���œ{�蔚�����A��ꌴ���̋g�c���Y�����Ɋ��@�֒��ژA������悤�ɂƁA���d�{�ЂƂ͋�����u�����B
�������͒m���𒆐S�Ƃ��čЊQ���{����ݒu
�u���Ⓦ�d����̘A����҂��Ă����Ȃ��v�ƁA11��20��50���ɂ͌������甼�a2km�i�o�t���E��F���j�̏Z���ɔ����Ăт������B
��11��15���@���d�́u�����̑S�𗬓d���r���̂��߁A���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@��10���Ɋ�Â��A1�A2�A3���@�ɂ��ē��莖�۔����̒ʕ�v
��11��16��30���@1�A2���@��ECCS�i���p�F�S��p���u�j�����s�\���
��11��16���@2���@�ɂ��đ�15��ʕ�
������L���鍑�O�̐��Ƃ͍ő�̊S�������ĉq���ʐ^����͂��Ă���A���̎��_�Ő�]�I��ԂɊׂ��Ă���ƕ��͂��āA�F�S���n�������郁���g�_�E���i�F�S�n�Z�j�Ɏ��邱�Ƃ����O�������悤�ŁA�e���̃��f�B�A���T�m���ĐV���ɂ����̌��O��_���Ă����B
��11��20��50���@�������m�����������a2km�����̏Z�������w��
��11��21��23���@���A�������m����ʂ��āA�x�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɏZ���ւ̔��w����ʒB�B
���̓��e�u1���@���甼�a3km���ȓ��̏Z���͔��A���a10km�����̏Z���͉����Ҕ��B���n�̑��{��������V���Ȏw�����o���ꂽ�ꍇ�́A���̎w���ɏ]�����Ƃ��������Z�Ҏ��m���ꂽ���v�i�d�b���s�ʁA�w���͕s�O��A����̍s���͒����Ǝ��̔��f�ɂ��j
��12��0��6���@�i�[�e������̈��͂������1.5�{�ɏ㏸���m�F�A�x���g�J�����w���A�����B�������A�x���g���{�́A�A�o�ώY�Ƒ�b�A���q�͈��S�E�ۈ��@�ɐ\������A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�t�ߏZ���̔����オ�����B
��F���̈ꕔ�Z�������Ă��Ȃ������A��������m�F���Ă���Ƃ���B�x���g�يJ���͕��ː������̕��o�����O����邩�炾�B
��12��00��30���@�ΏۏZ���̔��[�u�����ƕ����B
��12���@�d���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���S�ɗ������đ��݂��Ȃ��A���邢�͐��v���Ă��܂������Ƃ��C�O�ł͊Ď��q���̉f���ŏ������Ă���A���̓_�ɐG��悤�Ƃ��Ȃ����{���\�͉������B�����Ă���Ƃ��đS���M�p���Ȃ��Ȃ��Ă����B
��12��08�����@1���@�R���̑啔�������͗e��̒�ɗn���������B
��12��10��17���@�x���g�J����ƊJ�n�B��C���k�@�̋�C�s�\���ō�Ɠ�q
��12��05��44���@���������畟�����m���ɕx�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɑ��Ĕ��w��
���̓��e�u���a10km�����̏Z���͌��O�֔��v�Y���Z����5��1,000�l�B
���̎w���ɂ�葁�����h�Ж������S���������Ăт����A�x�����ł͐�����ւ̔����w���A���w���̓��e�́u�����d�͋Z�p�҂ɂ�镟����ꌴ���̌��q�F��~�ɔ�����蔭���̕����̂ŁA���̗\�h�[�u�v�Ɠ`����ꂽ�B
��n�k�ɑ�����Ôg�A�]��ɂ��r��Ȕ�Q�ɕ�R�Ƃ��Ă����������h�Ж�����ʂ��ēˑR�����^���悤�ȓ��e�̕������������B
�e���͒����̎w�߂ɂ����J�n�A�A���ڂ������͒N���m�炸�A�ʼn_�ɑ�ꌴ����藣��邱�Ƃ����ŁA�R�̕��������Ĕ����J�n�����B
���̊�@�̏d�含�ɂ́A���Ƃ��Ă��������Ă��炸�A�܂��Ē����͒N������2�A3���Ŗ߂��Ƃ̔F���ŋM�d�i����K���i�����Ƃɂ������܂o�����Ă��܂����B�S��������Ăɔ���ȂǑO�㖢���̎��ۂɓ��R�Ȃ����x�̌P���������A�V�~�����[�V���������������̂ɁA�������͂��߂Ƃ���S�E������ۂƂȂ��ĕ��������C���𐋍s�ł������Ƃ͌����Ƃ����ق��Ȃ��B
��12��5��46���@���Όn�z�ǂ���W��������t���̏��h�ԂŒ����A9���ԂŖ�80�g���𒍓��A14��56���ɊC�������ɐؑւ���B
��12���@�n��g�e���r17���̃j���[�X�ōŏ��̉f���������B
��12��15��36���@1���@���q�F�������f�����A�����Ō���ޔ��A����l�̋~���A���������{�A�i���d3�l�A���͊��2�l�j�z�E�_�������|���v�͔����ɂ���U���ɂ��~�݂����P�[�u���������A�����d�@���Ԃ͎�����~�B�������Ă����C�������̂��߂̃z�[�X���������Ďg�p�s�\�A��ƒ��f�B
��12��16���@���ː���500��Sv/h�i�}�C�N���V�[�x���g�j�������ƂŁA���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@15��ʕ�
��12��18���@���猧�m����ʂ��āA�x���A��F�A�o�t�A�Q�]�̊e�����ɔ��w���A���̓��e�u���a20km�͔��v�B
�]���ĐV�ɂ��킫�s�̈ꕔ�i�v�m�l�j�A�L�쒬�A��t���A������A�������A�쑊�n�s���ΏۂƂȂ�A����10km���Ŕ��Ă����������X�ɔ��n������ɉ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
������ɔ��Ă����x�������͎O�t����ڎw���Ĕ��A�X�ɌS�R�s�ցA������̑��������s���邱�ƂɂȂ����B�Y���Z�����v�͖�17��7,500�l
��12��20���@1���@�ɏ��Όn���C����ʂ��ĊC���̒������J�n
��13��05���@3���@��ECCS�����s�\��Ԃ�15��ʕ�
��13��08���@3���@�@�R���I�o�n�܂�B
���ː���500��Sv/h���z��������15��ʕ�
��13��08��41���@3���@�x���g�J�n�A�ȍ~��������{
��13��09��08���@3���@���q�F����
��13��10�����@3���@�F�S�����n�܂�A���f����
��13��09���@3���@�Ƀx���g�J�����u���̋�C����o
��13��13���@3���@�ɑ��ĊC�������J�n�i�h�ΐ����̒W���͌͊��j
��14��11��01���@3���@�Ŕ����A������������ԁA������
�����ɂ����h�ԋy�уz�[�X�j���A�g�p�s�\�ɂȂ�B
��14���@�����̏��h�Ԃ��t�߂܂œ����������A���H�Ɗ��I�Ō���t�߂ɋ߂Â��Ȃ��B
��14��13��18���@���q�F���ʂ̒ቺ�X�����m�F�A�i�[�e��x���g�̌�ɊC������������
��14��16�����@���͗}�����ɏ��C���u���������S�فv�ɂ�錴�q�F�̌�����D��B
��14��18�����@���q�F�̌������J�n
��14��18��22���@2���@�̌��q�F���ʂ��}�C�i�X3,700mm�ɒB���ĔR���_���S�I�o
��14��20��22���@�F�S���n�Z����\��
��14��22��22���@���q�F�i�[�e�푹���̉\��
��14����@���̍��A������������d�{�Ђ��犯�@�ցu������ꌴ������Ј���P�ނ��������v�Ƃ̈ӌ�������Ɠ`���A�����́u���d�͓d�͉�ЂƂ��Ă̖������������̂��A�В����Ăׁv�Ɛ������炰���B
��15��05��30���@�����瓌�d�E���K���{�Ђɏ�荞�݁A��c���ɋ����ԓ��d������O�Ɂu�P�ނȂǂ��肦�Ȃ��A�o������߂ĉ������B�P�ނ����߂��瓌�d��100���ׂ�܂��v���{�Ɠ��d���������̑��{���𓌓d�{�Ђɐݒu���邱�Ƃ����߂��B���̍�2���@�ł͔������������A���͗}�����ɑ����̋^�����o�n�߂��B
���̍��ɂȂ�ƁA���̔���������œ����Ă����n��������Ђ̍�ƈ������҂ɉ����A���d�����u���S�ė������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�ڌ����Ă������߁A���̏�u���Ԃɔ��҂̊ԂōL����s�����������Ă������B
��15��06���@4���@�����������ĕǂɌ����B3���@���甭��
2���@���͗}���v�[���t�߂Ŕ��������ē����ቺ�B
��15��07���@4���@�������ό`�E�j���B
��15��08��30���@2���������甒��
��15��09��30���@4���@�ʼnЊm�F�A���h���ɒʕ�
��15��10���@4���@�̉Ђɂ��āA�o�Y�Ȃ��ČR�ɉ����v��
��15���@�����~�n���̐���`����O�ɐݒu���ꂽ���˔\���葕�u�A�}�㏸
��15��11���@�����u20�`30km�����̏Z���͉������v���w��
��͔��a30km�̏��͔�s�֎~
�������Ƃ́A����s���悪�Ȃ��A���̎�i���Ȃ��A��҂��������c����錋�ʂƂȂ�B
��15���@�h�q�ȁA�k��h�q��b�Ɨ��������A���d�����̉�k���s���A�w���ɂ��������̐��b������ꂽ�B
�R���v�[������̏������������琅���C�����������Ȃ����A���������}�ɐ������Ȃ��Ɨn�����N�������Ƃ͕K��A���s�����߂�B
��16��16���@���X���Ԃ牺�����w��2�@���������ɒB�������A�\�z�ȏ�̋������ː��ɑj�܂�A���̓��͒f�O���P��
��17��08���@������蒼���A3���@���̑Ԃ�4�����ƌ���2�@�̃w����9��48���J�n�A�v��30�g���𓊉������B
��17��19���@�x�������@�����A�f�������p�̍��������Ԃ��n������̐�w�������āA3���@�ɖ�10���Ԃ�44�g��������B���㎩�q���̏��h��5��Q���B
��18���@�������h�����h�~�������i�n�C�p�[���X�L���[�j���A3���@�ւ̕����v13����30���ɂ킽��2,400�g���ȏ�̊C�����������B
���̌�A�q�q���q���n�z���̑�^���h�ԁA���l���h�ǁA�����h�Ǔ��̉������������B
���͔c�����Ă���
�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ��A���q�͈��S��ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B
�@21��12���FSPEEDI�ɂ���1��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j
�@23��49���A���������q�̓Z���^�[�ASPEEDI�ɂ��\���}���t�@�N�X��M
�@12��01��12���FSPEEDI�ɂ��2��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j
�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B
�@�����E�����́A�C�ے��ɃA���_�X�iAMeDAS�j�Ƃ������l�ϑ��{�݂ł���u�n��C�ۊϑ��V�X�e���v������A�S���ɖ�1,300�J���ɐݒu����Ă���A�ϑ��f�[�^��10���̖���ISDN�������ʂ��ċC�ے����̒n��C�ۊϑ��Z���^�[�ŏW�M����A�C�ۗ\��̊ϑ��f�[�^�Ƃ��Ċ��p�����B
�@����AMeDAS��SPEEDI�͘A�����Ă���A�������̕����E�����͊ϑ����Ă���̂�����A�k�������ɗ��ꂽ���Ƃ��ϑ����Ă���͂��B�]���Ď��̌�̎��Z�\������Έ�ڗđR�ł���͂��̎��Z�\���ǂ����̃Z�N�V�����Ŗ��v���Ă��܂����B
�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B
�@�����̈��S�Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B
�@�����Ԃɖ�������u�オ��Ȃ��v�u���Ȃ��v�u����Ȃ��v���̂܂܂ɁA�ŏd�v�ł���͂��̏���@�ɂ͓͂��Ă��Ȃ��������A�͂��Ă������ł��Ȃ������̂��B�����Ȋw�Ȃƕۈ��@��SPEEDI�ɂ��ŐV�����������Ă����B�]���Ă��̏Ȓ��̃g�b�v�ł����b�ɕ���̂����R�Ǝv�����A���̒S����b�����銯�@�ɂ͓͂��Ă��Ȃ������̂͂ǂ��䂤���ƂȂ̂������ɋꂵ�ށB
�@�����炱�����@�ł͒n�}��ɃR���p�X�Ŕ��~��`���A3km�A5km�A10km�A20km���Ə����݂ɔ��n����L���s���������n�I�ȕ��@�����̂�Ȃ������B
�@���̋M�d�ȏ��͋��L����邱�Ƃ����\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏�ꕔ�����ꂽ�炵���A��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B���������ɂ��t�@�b�N�X�Ŏ�f���Ă������Ƃ��㍏�����j
�@���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ٖ����Ă������A�����ǂ��납���@�ɂ��Ȃ��̂͗����ł��Ȃ��B
�@���̂悤�ȕٖ����ʗp����s�v�c���B��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉͂��ꂾ�B
�@��������߂ɘQ�]���̒Ó��n��̉����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B
�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��ĕ����Ȋw��b��SPEEDI�̏������̌��\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�Ɠ��فA���ɂ́u��ʂɂ͌��\�ł��Ȃ����e�������v�Ɩ��ӔC�ȓ��ق��J��Ԃ����B
�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v����ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�͌��\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B
���O�̓���

�@��ꌴ���@���̔����̗�������A�O�@�����̃A���_�[�Z����n���疳�l��@�@�O���[�o���z�[�N���A������A�������������ɔ��A���m�Ȏ��̏�c�����Ă����炵���B
�@���̒�@�@�̐����͌R���@�������A�������J����ƍ��x1��8�烁�[�g�����s���Ȃ���d�q���w�E�ԊO���J�����A�_�����鍇���J�����[�_�[�𓋍ڂ��A�җ�ȑ��x�Ŕ�s�A�؋�30���ԂŎ������c�A���A���^�C���̉f����n��ɑ���A���̉�͔\�͂͒n��30cm�l�������ʂ���ʐ^�B�e���\�A���������ƍׂ����������ʂ���\�͂�����炵��������ȏ�͌R���@���B�ő�q��������2��5��km�B
�@��ꌴ���̌����������������_�ŁA�A�����J���͍����\�ȌR���q���ʐ^���A�܂����l��@�@�����đN���ȉf���ɂ��u4���@�̎g�p�ς݊j�R���v�[������ɂȂ��Ă���A�����������Ȃ��Ƒ�ς��v�Ƃ̏�c�����Ă����B
�@�������A���d�͏�c�����Ă��炸�A�]���Đ��{���Ή����o�����A�A�����J�����������錋�ʂɂȂ��Ă��܂����B

�@�䂪���Ƃ��Ă̋�B�ɂ����͑S���Ȃ��A3��24���ɂȂ��ĐV���������s�ɂ���uAir Photo Service�Ёv�Ƃ������ԉ�Џ��L�̎ʐ^�B�e�p�̃����R�����c�@���}篎�A����Ə��̎ʐ^���B�e�ł����B
�@�܂��ɓ��Ă̗͂̍��A���ʁE���̍��A�̐��̍��ɜ��R�Ƃ����B
�@�����A�����J���{�͎��̑�ɑS�ʓI�Ɏx�����邱�Ƃ�\���o�Ă������A�����̏���c���ł��Ă��Ȃ��O���ȁA���@�͓��{�����̖�肾���獑���ʼn����ł���Ǝ��M�������Ă������A���d���O���̉�����������݂������B
�@�܂��t�����X���{������\���o������A�T���R�W�哝�́A���q�͑��̃A���o�Ђ̍ō��ӔC�ҁiCEO�j�A���k�E���x���W�������������A�C�]�c�o�Y���Ɂu���B���b�̏]�ƈ��Ƃ��Ďg���Ăق����v�ƒ�Ă��Ă���B�����̃��^�c�L������܂��B
�@���E��̌��������A�����J�A���ʂ̃t�����X�Ƃ��ẮA���{�ł̌������̂����Ƃ����������A�������Ή^���̊g���H�~�߂����Ƃ̎v�f���������B
�@���[�X�����đ�g���������Ƃɂ���āA���q�͈��S�E�ۈ��@�A���d�A�Č��q�͋K���ψ���iNRC�j������āA21���ɂȂ��āu������ꌴ�����̂̑Ή��Ɋւ�����ċ��c�v���A����Ɣ����A�哝�̂̌�������ΓI�ȏ�Ӊ��B�̎Љ�ƁA�{�b�g���A�b�v�A���C�悭��������K���A�摗��̏K���A�����̈Ⴂ�A�ً}��v����A�����i�s�^�̓�ɑΏ�����ɂ́A�Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ����{���̂��Ǝ���A�X�Ԃ����炯�o�������������B
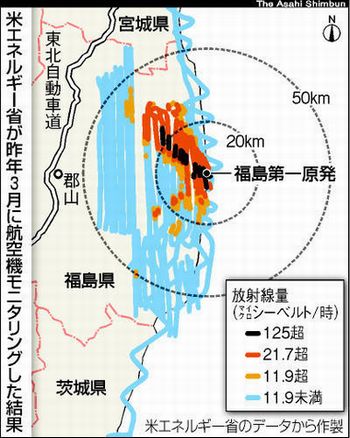
�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B
�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B
�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B
�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B
�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B
�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B
�@���̌��ʁA�Q�]������������܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�������ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��Ƃ��N�����B�Q�]���ԉF�ؒn��ɔ��Ă����l�B�̑O�ɔ������̉��l������A�����͊댯�����瑁��������Ǝw���A���̗l�ɋ����Ă����炵���A���������O�����̂炸���̂悤�ɋ����Ă��܂������A����̗����ł������̐E���ł��Ȃ��炵���A�Ɖ\���Ă����B
�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@�Ƃ��������@�ɂ�SPEEDI���ǂ̕����Ȋw��b�A�A�����J���{������ꂽ�u�����}�b�v�v��SPEEDI���v�Z�������ː������g�U�\�z�}�̗���������Ă����͂��̌o�Y��b�ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�X�ɂ͌��q�͈ψ����܂ł��l�߂Ă���ɂ��S��炸�A���@�ɂ͑S�����オ���Ă��Ȃ��A���̂��Ƃɋ^��������Ȃ������̂��B�Ȓ��̒������Ȃł͂ǂ̂悤�ȋƖ����Ă���̂������m��Ȃ��������ƂɂȂ�B
�@����ɐV���Ȃ������@�̒n�K�ɂ́A���@��@�Ǘ��Z���^�[������A�펞24���ԑԐ��i5��20�l�j�A�d�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɑΉ�������̂����A�Ɩ��̈�Ɍ��q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@��16��1��������A���R������ꌴ�����̂ł����̑��{����ݒu�����͂������A�ǂ̂悤�ȑ�������̂��͔���Ȃ����ASPEEDI������肵�悤�Ƃ����`�Ղ͂Ȃ��B����Γ��R�������@�̏�K�ɕ��Ă���͂����B
�@�A�����J���{�̐\���o���A�����J�E�N�����g�������̎x���\���o����{���{���f�����B�Ƃ����L���̍ŏ��͓ǔ��V�����������A���̌�̒����V���̋L��������p����B
�@1981�`82�N�ɂ����āA�A�����J�ɂ���I�[�N���b�W�������������A�����J���q�͋K���ψ���̈˗����đ傪����Ȏ����A���̃V�~�����[�V������1981�`82�N�ɌJ��Ԃ��s���A���̕��ψ���iNRC�j�ɒ�o�����B
�@���̌������́A�����̑S�Ă̓d��������ꂽ�ꍇ�̃V�~�����[�V���������{���ē���������������̂ł��B
�@���̃V�~�����[�V�����Ɏg��ꂽ���f���́uGE�А��}�[�NI�F�v�ŁA����͕�����ꌴ����1�`5���@��GE�А���A���������̂őS�������^�C�v���q�F�ł����B
�@���̕��ɂ��ƁA�S�d�����r�����Ĕ��p�o�b�e���[��4���Ԏg�p�\�ȏꍇ�A�u5���ԂŊj�R���I�o�v�u5���ԂŐ��f�����v�u6���Ԍ�ɔR���n���v�u7���Ԍ�Ɉ��͗e�퉺���������v�Ƃ����̂��A��Ȍo�߂����A�܂��ɕ�����ꌴ���̎��̂̌o�߂̓V�~�����[�V�����ʂ�ƂȂ����B
�@���̕�����NRC�͒����Ɉ��S�K���Ɏ����ꊈ�p�����B
�@�ł́A���d�Ƃ��Ă͂��̂悤�ȕ������邱�Ƃ�m��Ȃ������̂��A����������1���@�̌��݂�1971�N�AGE�Ђ��v�A�@�ނ��琘���t���H���܂őS�Đ��������u�t���E�^�[���E�L�[�v�_����A���̌�̐ӔC������B
�@���̕�����o���ꂽ�̂�1982�N�Ȃ̂ŁAGE������͂���ANRC������A�����������悤�ŁA���̎��������邩�炱���A���ŋ߂�10��4���A�����J�c��ɂ����镟����ꌴ���Ɋւ��������ł̏،���ɗ������O���S���[�E���c�RNRC�ψ��������{���{�̑Ӗ�����O��I�ɂ������낵���،��������Ȃ����̂��A���������Ƃ������A���u���Ă��܂������{���ɉ䖝�ł��Ȃ������̂��낤�B
�@�ł͉��́A���{���͊��p���Ȃ������̂��A���������S�d�����r������悤�ȏ͋N���邱�Ƃ͂Ȃ��A�N���蓾�Ȃ�����z�肷��K�v�͂Ȃ��A�������͕K�v�Ȃ��A�̊댯�ɂ܂�Ȃ��O�i�_�@���ʗp���Ă��܂����B
�@�������A�����Ɍ������̂͋N���āANRC�ɂ��邱�Ƃ��N���Ă��܂����B����ł����d�͑��v���ƐM���āA�A�����J��t�����X����̉�����f�����̂́A���d���̓o�b�e���[�̉ғ�����8���ԁA���̊ԂɊO���d���͉ł���B�ƐM���Ă����悤�ŁA����܂����S�_�b�̐_���݂ɏI�n�����B
�@��������A�В��A���В�(���q�͒S��)���o�����ŁA���d�̎i�ߓ��͕s�݁A�c���ꂽ�����̓}�j���A���͂Ȃ��A�ӔC�͕��������Ȃ��ƃI���I���������A���@�͂���܂����d����̕��Ă��A����������A���f�ł���l�ޕs���A���{�l�S�̂̊�@�Ǘ��ɑ��銴�o����������ɐi�W�����B
�@���̒���A�N�����g�������̘A���́u�����ɐ��i�z�E�_���j���A�����J�����A����v�ƁA����̓A�����J�̌R���q���ŕ�����ꌴ���̎��̖̂͗l���Ԃ��ɊĎ����Ă������h�Ȃ��璷���ɘA���������A����������{���{�\���o���悤���B
�@�R���Ď��q���̉�͔\�͂͒n��30cm�ȉ��̕��̂܂Ŕ���\�͂������Ă��邩��A���̂̓��e�͐��m�ɔc�����A��p���u��ŁA�S�d���r������͂������ŁA�����炱�����̒������ŗD��A����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��Ɣ��f���đ����ɐ\���o���̂����A���{���{�ł͎��̌�͏ڍוȂ��A�������̂͑z��O�Ŋ��@�̊�@�Ǘ������@�\���Ȃ��B
�@�S�d���r���ȂǑz��O������}�j���A���Ȃ��A�]���ăA�����J�̐\���o�ł��鐅����A���鎖�̈Ӗ��������o���Ȃ��܂ܒf���Ă��܂����悤���B
�@���̌�̉ߒ�������Ή���ʂ萅�𒍓�����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ������B
�@����ɓ��{���Ƃ��Ă̓A�����J�A�t�����X�̉����������A�����̎w������D���Ă��܂��B���q�F�{�݂��O���ɔ��荞�����Ƃ��Ă��鎞���ɊO���̋Z�p����Ȃ���Ε����ł��Ȃ��B�Z�p�̖��n�������\���邱�ƂɂȂ�B��������{�������őΏ�����B�Ƃ���̂����{�A���d�̗��������������悤�ŁA������f���Ă��܂����B
�@���Ԍo�߂Ƌ��Ɍ��q�F�Z���A���f�����ƂȂ��āA�A�����J�A�t�����X�ɏ��������߂���Ȃ��������A��ɃN�����g�����������A�t�����X�E�T���R�W�哝�́A�A���o�Б��كA���k�E���x���W�������̑����������A�킴�킴���������ɗ����킯�ł͂Ȃ��B���{�����ɔC���Ă����琢�E����ς��Ƃ̔F������ŁA��������ȏヂ�^�c���Ď������x���Ό������̉^�����������Ă��܂��ƁA������i���ł���t�����X�A�A�����J�ł͐����ێ���������ɂȂ�Ɣ��f���Ă̍s�����B
�@�����h�C�c�ƃX�C�X�͌����S�p���c�������B���̔g�������ɋy�Ԃ̂��Ȃ�Ƃ��h�������A����ɂ͈ꍏ�������������̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���{�����ł͖����Ɣ��f���Ă���ė����킯�ŁA���{�ɑ���D�ӂ����ł���ė����킯�ł͂Ȃ��B
�@�N�����g���������́u���{�̋Z�p�I�����͍������A��p�܂͕s�����Ă���͂��v�������R�@���g���ċ}�������Ɛ����\�������A��ō����ȍ������A���{���{���f���Ă����̂ő���Ȃ������A�Ɣ��\�����B
�@�V���ɂ́u���𑗂�ƁA�A�����J���{�̐\���o�v�ƋL���ɂ��������A��p�܂̈Ӗ��́A�z�E�_�i�z�E�_���A�ʏ�e�{�����f�ƌĂ�ł���j�z�E�_���͊j����������}������A��������̐���_�ɐ��肤����̂Œ����n�Ɏg�p���Ă���̂�����A���Ƃ������̂̓z�E�_���̂��ƂɂȂ�B�܂��z�E�_���𒍓����Ă��p�F�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǘF�������t���邱�Ƃ͌����Ă��蓾�Ȃ����ƁA�p�F��S�z���Ēf�����B�Ƃ����͉̂������ő}�����ꂽ������ł����Ȃ��B
�A�����J��g�ق̓���
�@���̑O�i�K�ɂ����āA���̃��[�X��g���}�슯�[�����Ɂu�A�����J�̐��Ƃ����@�ɏ풓�����ė~�����v�Ɨv���������Ƃ��������炵���B�Ƃ��낪�}�쎁�͂Ƃ�ł��Ȃ����Ǝ匠���Ȃ�������ɂ�����̂��Ɖ��߂����₵���Ƃ̂��ƁB
�@�Ɨ����Ƃ̖ʖڂƂ��Ă͓��R�����m��Ȃ����A����A�����J�����王��A���E���䂷�����厖�̂��N���Ă���A�Ⴕ����������{�͉�œI�ȑ�Ō����邩������Ȃ����ˍۂɂ���Ȃ���A�N���ǂ��Ώ����悤�Ƃ��Ă���̂��A�����ς蔻��Ȃ��B�@�͂����������O�̊댯��Ԋׂ��Ă���B���d�͓P�ނ��������Ƃ�����������A�Ɍ���ԂɊד����Ă�������A�A�����J���{�́u���ƕ���v�̍ŏI�V�i���I��ǂ�ł����̂����m��Ȃ��B
�@�����炱���������Ƃ��ĂȂ�Ƃ��j�~�������B�����������Ƃ̎v���������A����ɂ͊��@�����ɐ��Ƃ��풓���������������̂��낤���A�A�h�o�C�X�����������̂��낤�B���̂��Ƃ̓��[�X��g�̎v�f����ł͂Ȃ��{�����{����̗v���������悤���B
�@���ē����̍�����h�邪������ŁA�����Ƃ͉�����Ɩ����ْ������u�Ԃ������炵���B���̂��炢���@�̎w���͂͊낤���������̂��낤���B
�@���ʓI�ɂ́A���q�͔��d�͐�Ɏ��̂͋N���Ȃ��A�Ƃ������S�_�b���f���A�M���Ă������{�A�d�͊e�ЁA���S�Ȃ̂����玖�̑�E�����͕K�v�Ȃ��Ƃ���A���̏������@�ނ��Ȃ��������̂ɁA���@�����ɃA�����J���{�̐��Ƃ��풓�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�S�ʓI�ɃA�����J�A�t�����X�̉������v��ق�����͂Ȃ��A����ɂ��������肢�ƂȂ炴��Ȃ������B
�@�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�iMIT�j���q�͈��S���Ƃł���W���E�E�H���V�����m���A�A�����J���������͂����ʐ^�����āA�X���[�}�C�������ꡂ��ɍ����A�`�����m�u�C���ɋ߂��Ɣ��f�A�����ɕ�����ꌴ����蔼�a50�}�C���i��80km�j�����ɋ��Z����A�����J�l�̑����������������B�����u�������O���̍ݓ���g�فE�̎��ق�100km�������Z�̎������Ɍ��O�ւ̔��������A�Ⴕ���͖{���A��Ɠd�b�Ŗ��߂ɋ߂��������J��Ԃ��A�A�����b�V���ƂȂ����B
�@�܂��A�ꍑ�̉Ƒ�������A���Ă����ƌJ��Ԃ��d�b���������炵���A���k�n���A�֓��n������ł͂Ȃ������{�ɏZ�ފO���l���A�������炵���B
�@����͐��E�e���ŘA����������Ă��������{��k�Њ֘A�f�����A�ҏW�҂��悭���e��c���ł��Ȃ������炵���A�������̂ƌ��q���e�̋�ʂ������A���̃q���V�}�ɂȂ��Ă��܂����ƕ���A�s���̃R���r�i�[�g�Ђ̉f�����ꌴ���̑唚���ƕ��̂�����S�z����̂����R�Łu�����Ɋ҂��Ă����v�ƌ����̂��������Ȃ��S��낤�B
��@�Ǘ��Z���^�[�̑���
�@��_�W�H��k�Ў��A����t�ɋ������ė���̂��x��A�~�������̔��߂��啝�ɒx��Ă��܂������ƂȂ��A�V�������@�̒n��1�K�ɃI�y���[�V�������[����݂��A���������@��@�Ǘ��Z���^�[�Ƃ����i�A���A�g�D���ł͂Ȃ��j
�@��������ɉ^�p���Ă���͓̂��t������W��Z���^�[�ŁA24���ԑ̐��i5��20�l�j�ŏd�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɔ����x�@���A�x�����A���h���A�C��ۈ����ȂNJ�@�Ǘ��ɊW����Ȓ��ƃz�b�g���C���Ō���Ă���B
�@�Ǘ����Ă���̂́u���t��@�Ǘ��āv�i���ł͂Ȃ��w�āx�j���̓��t��@�Ǘ��Ă͑啨�x�@����OB���A�C���Ă���B�i�x�����Čo���ҁj
�@�L���̏ꍇ�͑����������A�e���q���i���C��j���������Q�d�Ƃ��ē���B
�@�ݔ��͑f���炵���@�킪�ݒu����Ă���̂��낤���ǂ�������܂��i�ߕ��Ƃ��Ă̓����͂��Ă��Ȃ��B
�@�A���A�Ƃ��̑��߂͏�K�̎������Ŏw���������Ă����炵���A��@�Ǘ��Z���^�[�����p�����̂��ǂ����͔���Ȃ��B
�@�܂������m�̏�Łu�ك��܂�v�����ߍ��Ƃ͎v���Ȃ����A�����̋M�d�Ȏ���������_�ň���Ԃ���Ă��܂����͎̂����炵���B�������̊�@�Ǘ��Z���^�[�����S�ɋ@�\���Ă�����ASPEEDI�̑��݂����m���Ă���͂��������オ���Ă��Ȃ����Ƃɕs�R�������Ȃ������̂��A�z�b�g���C���Ōq�����Ă��Ȃ���e�Ȓ��ɖ₢���킹�����Ȃ������̂��B
�@���t��@�Ǘ��Z���^�[�͑��݂��Ă������A���S�_�b��M���ăV�~�����[�V������ӂ��Ă����̂��낤���B
�@���Ă̎Q�d�{���͐i���̍��͉X�������s�������A�P�ލ��͑z��O�ŃV�~�����[�V�����̔��z���Ȃ������炵���B�s�s���ȏ��͍����N���X�̎Q�d������ׂ��Ă��܂��A�̐S�̎Q�d�������͂��߂Ƃ���Q�d�����ɂ͓͂��Ă��Ȃ������Ƃ������A���60���N���o�Ă����̈����͎c���Ă���炵���B
�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B
�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����n�}�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B
�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B
�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�Ȋ��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B
�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤���B
�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B
�@���̌��ʁA�Q�]������������܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B
�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�������ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@��@�Ǘ��Z���^�[�͉��̂����̋M�d�ȏ���c���ł��Ȃ������̂��A���邢�͔c�����悤�Ƃ��Ȃ������̂��B�����V�~�����[�V�������J��Ԃ��Ă���ΕK�{�����Ƃ��čs�����Ă����͂������A�c�O�Ȃ���Ӗ��͉ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B�܂����@���f�[�^���Ȃ��܂܂ɁA3km���A5km���A10km���A20km���A30km���Ɠ��S�~���`���Ĕ��n������߂����A�������@�̒��ɂ���Ȃ����@�Ǘ��Z���^�[�͂����̌���ɂ͎Q�����Ȃ��g�O�̑��݂������̂��B
�@�����ɉ����Ĕ������߂�ׂ������A�����Ɋ�Â��Ĕ������߂�ׂ����ƈӌ���\���������������Ƃ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�������͗��̉��l�ɂ����Ȃ������̂��낤���B
�@���@�͊�@�Ǘ��Z���^�[�₻�̑��̐��@�ւ�S���������Ă����̂��B
�@���̂悤�ȏd�厖���ɂ��S��炸���ݕs�M�Ɋׂ��Ă����̂��낤���B
�@�ČR����̎����َ͖E����A���u���ꂻ�̑��݂��������炩�ɂ��Ȃ��������A1�N3������̗��N6��18���A�����V������1�ʂŃX�b�p�����ꂽ�B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȓ́u���˔\�����n�}�v���A�����đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɑ��t���A��������O���Ȃ͒S���Ȓ��ł��镶���Ȋw�Ȃƌo�ώY�ƏȂɓ]���������A���̋M�d�Ȏ������Z�����ɐ�������邱�ƂȂ��A�����܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�1�N3������ɒ����V���ɂ���ăX�N�[�v���ꂽ�B�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B
�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂����B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B
�@�������A���̂��̋M�d�ȃf�[�^�����Z���^�[���ɂ���Z�������S���ł���u�Z�����S�ǁv�ɓn��Ȃ������̂��A�Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��Ắu����Ȃ��v���J��Ԃ������A�������A�u�����n�}�v�͓��Z���^�[���̃z���C�g�{�[�h��A2���Ɋg�傳��Čf������Ă����Ƃ̂��ƁA�]���ē������ō�Ƃ���u�Z�����S�ǁv�̌W�����ڂɂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@�������A�����Ɏ�̂��Ȃ���ΑS���S�������Ȃ��A�^����ꂽ�Ɩ��͌����Ɏ��g�ނ��A�e���g���[�͈͈̔ȊO�͖��S�A�܂��ĊO���̃f�[�^���͖��������R�A�������A�����Ȋw�Ȃ��u���͋��L���ׂ������������m��Ȃ����A����ł̃��j�^�����O�����W���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒S���v�ł��邱�Ƃ������A�]���ĊC�O����́u�����n�}�v�̎�舵���ɂ��Ă͒S���҂ł���F���͂Ȃ��B
�@�u�����n�}�v�̎�舵���͕ۈ��@���S��������̂Ƃ̔F����\�����A�����Ȋw�Ȃɂ͂Ȃ�痎���x�͂Ȃ����Ƃ����������B
�@����Ȃ�Ε����Ȋw�Ȃ��S�����Ă���SPEEDI�ɂ��f�[�^������Ȃ�����\���Ȃ������͉̂��̂��A���m�łȂ�����������\���Ȃ������B�ƕٖ����Ă��邪�A�댯�������Ă���n���F�����Ă����͂��A�ł�����߂Č���ӔC�̂��镟�������̒S���҂ɘA�����ׂ����ƍl����B
�@�Ȃ���Ȃ��܂܉����n��ɔ��Ă����l�X�͔픘���Ă��܂����B�Ƃ��낪���̒n��ɔ��Ă����l�X�̂Ƃ���ɁA�˔@�������i�h��ߕ��j������A�����Ȃ̂炸�u�����͊댯�����璼���ɔ��ĉ������v�Ƃ��������ĕ��̂悤�ɋ����čs������̈�s�������炵���B����s�����̌W���ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB�u�����n�}�v���������Ă����l�X�̒��ڍs���Ȃ̂��A���݂ł����̐��͕̂s���B
�@�ł͉��̂���قǍ������Ă��܂����̂��B���q�͋K���g�D�Ƃ��Čo�ώY�ƏȁA���q�͈��S�E�ۈ��@�A�Ɨ��s���@�l�E���q�͈��S��Ջ@�\�B���t�{�A���q�͈��S�ψ���B�����Ȋw�ȁA���ː����j�^�����O����A�S�Ă��c����s���B
�@��������Ȓ����قȂ�g�D���������̂Ƃ���1�̍ЊQ�ɑΏ������ꍇ�A���O�ɖȖ��ȑł����킹�ƁA�g�D�S�̂����f�I�ɓ�������{���y�юi�ߊ������Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɍs�����邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��ɍ�����������炯�o���Ă��܂����B�o�Y�Ȃƕ����Ȋw�Ȃ����������ō�Ƃ��Ă��Ȃ���u�����n�}�v�����L�A���p���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�܂��A���i�ߊ��ł���ׂ��������͏�W�܂�Ȃ��܂܁A����ɉ��������A���d�{�X�ɓ{�荞��Ɠ�����������A���i�ߊ��Ƃ��Ă̎��o�����܂�Ȃ��̂����i�ߕ��𗯎�ɂ��Č����d���K��A������č���������ȂNJ�@�Ǘ��̐����S�������Ă��Ȃ����Ƃ����g�̍s���ŘI�悵�Ă��܂����B
�@�ݔC���Ɏ���Ƃɓ{�荞��́A�펞���̓������Ɏ����ŗ����ڂ̏o�����ł������B
�@��ꌴ�����̂ŒS������ۈ��@�͎��̒���ɏ����W�߂��ꂸ�A�����Ă����p�ł����g�D�Ƃ��Ă�����Ƌ@�\�ł��Ȃ������B
�@�܂��A���̈ȑO�ɂ��n�k�E�Ôg���ߍ����̂̌x���F�����Ă��Ȃ�����A�d�͉�Ђւ̎��m�O���ӂ��Ă���A�X�ɂ͌����̎蔲���Ɏ��݂�����Ɠd�͉�ЂɎC�����Ă������Ƃ����X�Ɩ��炩�ɂȂ茴�q�̓����̗l����悵���B
�@SPEEDI���NJ����镶���Ȋw�Ȃ��f�[�^���������Ȃ�������\�����A���\�̋`���͂Ȃ��A�����x�͂Ȃ��A�S�ēK�ɍs�������A�Ƌ��ق��J��Ԃ����B
�@�������ɍ��Ƃ��Ă͂��̐��x�̌��ׂ�F�߁A�o�ώY�ƏȂ̌��q�͈��S�E�ۈ��ǁB���t�{�̌��q�͈��S�ψ����p�~�B�������̏Ȓ��ɂ��������q�͈��S�Ɋւ��镔�ǂ�p�~���A1�ɓ������邱�ƂɂȂ����B
�@�L����5�l�ɂ��u���q�͋K���ψ���v�ƌ����Ɨ������g�D���A9�����������h�ɂ��Ĉψ��C���҂�I�l���B
�@�Ɨ����̍����ψ���Ƃ��āA�Z�p�I�E���I�Ȏ����̔��f�͈ψ���ɈςˁA���͈̔͊O�̔��f�͎�����A�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�ۈ��@���s���Ă����Ɩ����́A�V���Ɋ��Ȃ̑g�D�̈ꕔ�Ƃ��āu�K�����v��ݒu���A��1��l�̐��̊����ɂȂ�炵���B
�@��ь����͖�c���������̊������Ĉ��S�f���A�ĉғ���F�߂����A����ɑ������̌����̍ĉғ��́A�V�����o����u���q�͋K���ψ���v�����S�����m���߂Ĕ��f���邱�ƂɂȂ�B�����A�ǂ̂悤�Ȋ�ɂȂ�̂��͂��ꂩ��̖�肾�B
�Ӎ�
�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B
�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B
 |
�@��ꌴ�����̂̂��ƒ����ɃA�����J������q��@�ɂ������ŕ��ː��ʂ̏ڍׂȁu�����n�}�v������Ă����ɂ��S��炸�Z�����w���Ɋ��p�����A���̋M�d�ȃf�[�^����u���Ă������ŁA���̑��݂���F�߂悤�Ƃ��Ȃ��������{������Ƃ��̑��݂�F�߁A�o�ώY�ƏȌ��q�́E�ۈ��@�̕����p��������12�N6��26���A��F�A�x���A�Q�]�̉������K��Ӎ߂����B���̌�A����12�s������K��Ӎ߂����B
�@�@���ɓ�{���s�ɂ���Q�]��������ł͏�x�ꂽ���̂ɍ����ː��ʂ̒n��ɑ����̔��҂����܂��Ă������ߔ픘���Ă��܂��������m��Ȃ����ł́A�n�꒬���Ɣ�����Ȃ��璷���Ԃ̉�k���s��ꂽ�Ƃ����B
�@�������A���̖��Ŏ��̌�1�N3�������o���Ȃ���ΐ����ȎӍ߂������Ȃ����̍��̍s���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��BSPEEDI���ł͕����Ȋw�Ȃ����S�ɒ��ق����܂܂����A�����B�v���������n���ɎӍ߂ǂ��납�A���̐������Ȃ��͈̂ӊO���ƁA�����Ȋw�Ȃ𖼎w���Ŕᔻ���Ă���B����s���̒������������̑ԓx���B
�@�X�Ɍ��q�͕ۈ��@�̐X�R�P�́E���q�͍ЊQ��Ă�6��28���A�L�҉���s���A�ۈ��@�ً̋}���Ή��Z���^�[�ɂ͉����n�}�f�[�^�̎����͎c���Ă��Ȃ������B�Ɩ��炩�ɂ��A�j�������̂��A���������̂��A���݂��Ȃ��̂͊m�����Ƌ��������B
�@���݂��Ȃ��Ƌ�������Ζƍߕ��ɂȂ�炵���B
���q�͈��S�E�ۈ��@��NRC
�@�o�ώY�ƏȂ̈�@�ւł���A�@�ߏ�̈ʒu�t���͎����G�l���M�[���̓��ʋ@�ւƂ���A2001�N1��6���A�����Ȓ��ĕ҂̍ۂɌ��q�͈��S�E�ۈ��@���V�݂��ꂽ�B
(1)���q�͂Ɋւ�鐻�B�A���H�A�����A�ď����y�єj���̎��ƕ��тɔ��d�p���q�͎{�݂Ɋւ���K�����̑����ꂩ��̎��Ƌy�ю{�݂̊ւ�����S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
(2)�G�l���M�[�Ƃ��Ă̗��p�Ɋւ��錴�q�͂̈��S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB
�@�킪���̌��q�͈��S�E�ۈ��@�̌������́A�d�͉�Ђ��쐬���錟�����ނ̐R�����邱�Ƃ���ŁA�����̎{�݂ɑ��Ă͕K�v�ɉ����āA�������茟���A�����A���P���ߓ����s�������ł���B
�@��ꌴ�����̂̑Ή���A����ȑO�̌����A�ēɑ����̖�肪�w�E����A�u����̍ŏI���v�ł́A�d�͉�ЂƋK�����ǂ̂�����ɂ����ݍ���Łu�K�����闧��Ƃ���闧��́w�t�]�W�x���N���A�K�����ǂ͓d�͎��Ǝ҂́w���x�ɂȂ�A���̌��ʁA���q�͈��S�ɂ��Ă̊ē@�\�͕��Ă����v�ƍ��]���ꂽ�B�����̈��S�K����S���Ă������̌��q�͈��S�ψ���ƌo�Y�Ȃ̌��q�͈��S�E�ۈ��@��'12�N9��18���������Ĕp�~�A19���ɔ����������q�͋K���ψ���ƌ��q�͋K�����ɓ������ꂽ�B

�@�A�����J���O�����q�͋K���ψ���iNRC�j�A�A�����J���O�����{�̓Ɨ��@�ւ̈�ł���A���O�����ɂ����錴�q�͈��S�Ɋւ���ēƖ��i���q�͋K���j��S������B���q�F�̈��S�ƃZ�L�����e�B�A���q�F�ݒu�E�^�]�Ƌ��̋��F�̕ύX�A���ː������̈��S�ƃZ�L�����e�B�A�y�юg�p�ς݂̊j�R���̊Ǘ��i�����A�Z�L�����e�B�A�ď����y�єj���j���ē���B
�@NRC�́A�A�����J���O���哝�̂ɂ���Ďw������A�A�����J���O����@�̓��ӂɊ�Â���5�N�̔C���ŔC�������5���̈ψ��Ƃ��A���̂���1���͑哝�̂���ψ����y�шψ���̌��I�X�|�[�N�X�}���Ƃ��Ă̔C������B
�@NRC�̑g�D�́A���V���g���x�O�ɂ���{���ƑS��4�����ɂ���n���ǂ̐��E���������Ɩ��S���A�s�������Β����������ɘA������B
�@�d�v�Ȗ�肪���t����L�҉�Ŗ��炩�ɂ����B2011�N��1�N�ԂŁA�S�Ă�200���]�̕s������ɂȂ����B�킪���̂悤�ɉB���H�삪����̂悤�Ȍ��q�̓����̑̎��͂Ȃ��B
�@NRC�̌������͌��q�͍H�w�̏C�m�ȏ�̊w�ʂ�L����l�������A�������Ƃ��Ă̌P����7�T�ԁA�K�{�͌��q�F����Ղ̃V�~�����[�^�[�̑���A�����A��펞�ɂǂ̂悤�ȑ��삪�K�v���O��I�ɏK������B�S�ے����C������ƁA����Ɍ����1�N�ԌP�����d�ˁA�X�Ɏ����ɍ��i���Č������ɂȂ�B
�@�]���Đ��E�Ƃ��āu��������NRC�̖ڂł���A���ƂȂ��āv�Ɩ���簐i���邱�ƂɂȂ�B
�@�킪�����č��̂悤�Ȍ����`�ɓO���Ȃ��ƁA����̌������̂ɂ��E�������̑卬�����J��Ԃ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�����͌������ނ�R�����邾���ł̏��ގ�`��E���A�啝�Ȋ������x�̉��v�������K�v�B
�@������ꌴ�����̂̍ۂ́A�����[�����h�B�ɂ���NRC�I�y���[�V�����Z���^�[�ɂ��ꂼ��̐��Ƃ��W�����A�������W���Ė�2�����ɂ킽�芈�������Ƃ̂��ƁA���̊ԁA���f�����̕K�v���ȂǓK�ȃA�h�o�C�X�𑗂葱�������A�u�����n�}�v���l�A�i�ߓ��s�݂̂킪���ł͊��p�ł��Ȃ������炵���B
�@����NRC�ψ����ł������O���S���[�E���c�R����2011�N10��4���A�A�����J�c��E������ŏؐl�Ƃ��ēo�d���A������ꌴ�����̂ɂ��ď،������B
�@����ɂ��ƒn�k�A�Ôg�͗\�z����Ă������Ƃł���A���̑��S�������Ă��Ȃ������̂͑Ӗ��ł��薳�ӔC�ȑ̐��ɂ����̂ŋN����ׂ����ċN�����l�Ђł���ƕ����B
�@���̌�̏����Ɋւ��Ẵ��^�c�L�͎i�ߓ��̕s�݁A�����@�̕s���A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D�̕s�����X�A�җ�ȓ��{�ᔻ���،������B
�@�����͎w�E�̒ʂ肾���甽�_���o���Ȃ����A���̒��㑦���ɉ����A���ނ̒ȂǃA�����J���̍D�ӂ���\���o���A���̂̋K�͂������o���Ȃ��܂܂ɂ��Ƃ��Ƃ��f���Ă��܂������{���{�Ɠ��d�̘����ȑΉ��ɑ����������Ă����悤���B
�@����ɂ͐��Ƃ�{������h�����Ĕ�s�@�ɂ���Ē����E���肵�č쐬���������}�b�v�����{���{�������������Ƃɑ��Ėҗ�Ɋ��݂����B
�@�����������̂̑�ɐ�O�������A���̍ۃA�����J�����̌��q�͋K���Ɋւ��A�@�K���̋�����d������A�A�����J���{�̓��{�ɑ���Ή���������������A�V�K���q�F�̐V�݂�30�N�Ԃ�ɔF�Ɋւ���ψ���ł̑Η��A�j�p���������ꌚ�v��𒆎~������Ƃ̓��̓ƒf��s���������̂��A��4��l�̐E�����E�w������̂�5�l�̈ψ������A���̃g�b�v�߂�̂��哝�̂ɂ��C���ł���ψ����ł��邪�A���̃��c�R�ψ��������̈ψ��ƑΗ����A�r�ˉ^��������A���C���������̂��A�˔@���\���o���E�������Ă��܂����B�A�����J���{�����ɂ����낢�날��̂��낤���B
�@����A���c�R�����C�̐^�������炩�ɂȂ����B01�N9��11���A�A�����J�ōq��@�ɂ�铯�������e���i9.11�����j���������B
�@���̎��͌�����_�����Ƃ͂Ȃ��������A�_����\��������A02�N�Ɂu���q�͎{�݂ɑ���U���̉\���v�ɔ��������ʂ̑�����邱�Ƃ��e�����ɋ`���t���閽�߂��o�����B���ꂪ�uB5b�v�őS�Ă̍ЊQ�ɑ���h�쥕ۈ��[�u�Ƃ����B
�@���R���̏��͉䂪���̌��q�͈��S�E�ۈ��@�ƌ��q�͈��S��Ջ@�\�Ƃɐ����ɓ`�B����A���̖h�쥕ۈ��[�u���������ꂽ���A�̐S�̌��q�͈ψ����ɂ́A���́uB5b�v��S������Ă��Ȃ������炵���B
�@B5b�̏��Ɋւ��ẮA���̌�A�����J�����炪���̑���u���Ȃ������̂��Ƌl���āA���߂�B5b�̑��݂�m���ċ������Ƃ����B
�@�c�O�Ȃ���䂪���ɂ́u���S�_�b�v���������Ă���A���オ���S�Ə�����Έ��S���ƖҐM���Ă��܂�������������A����i�J�~�j�͐_�ɒʂ�����̂�����炵���B�]���đS�Ă��u�z��O�v�Ƃ��Č��������o�܂�����B
�@�������̎��A�h��[�u�������Ă���Α�ꌴ���̎��̂͂�����x�h�����͂����ƃA�����J���{�̌����ł������B
�@�Ƃ��낪NRC�ψ����ł��������c�R���́A��ꌴ���̎��̂��Ԃ��Ɍ������ē������_�́uB5b�v�����邩��ƌ����Đ�ΓI�Ȉ��S�͕ۏ���Ȃ��Ƃ��āA�uB5b�v�̌������𐭕{�ɔ������B
�@���̂悤�Ȑ܁A�A�����J���{��34�N�U��Ɍ����̐V�݂�F�߂��BNRC�̈ψ�5�l�̂���4�l���^���A���̓��c�R�ψ�������1�l�ŁA��]�������c�R���͎��\���o����NRC���������B
�@����3�������12�N8��27���A���c�R���͈�l�ŘQ�]����K��A�h�앞�p�Ŋ��I�̒�������A���̗l�q�����ĉ��A���̌�A��{���s�ɂ���Q�]��������ɔn�꒬����K�ˁA��k�A�����͏�Ȃ��܂�30km���ꂽ�Ó��n��ɒ�����U�����������A�������ł����ː��ʂ������Ƃ��낾�����̂���Œm��A������픘�����Ă��܂������ƂɐӔC��ɐɊ����A��Y�������Ƃ��q�ׁA���c�R���͖ڂ����܂��ĕ����������Ƃ����B
�@�䂪���ɂ����c�R���̂悤�Ɉ��S�_�b�Ȃǂɘf�킳�ꂸ�A�^���ɂȂ��Ď��g��ł����l�ނ���l�ł������Ȃ�A�܂�������W�J�ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��B
�S�d���r����
�@NRC�������uB5b�v�̒��ɁA�u�S�d���r���̏ꍇ�̑�v���܂܂�Ă����B����B5b����߂��K��ʂ�̑���������Ă����Ȃ�A���͖̂h���������m��Ȃ��d�v�Ȏ����ł������B
�@�����{��k�Д����O�ɃA�����J���{������{���{�ɓ`�����Ă������q�͔��d���̑S�d���r����̏�A�ۈ��@�̒S���ے��A�����d�͂ɂ��`����ꂸ�A��ꌴ�����̊g��̈���ɂȂ�����'13�N12��16���[���ŕ�ꂽ�B
�@���̏d�v�ȏ��́A2001�N9.11���������e�����A���Ɋ�@�����������̂�9.11�̓��������e���ł͑�ςȔ�Q�������āA�����̋]���҂��o�����A����������W�I�ɂ��Ď����e�����s��ꂽ��A�S�Ăɔ�Q���y�ڂ��厖�́A�厖���ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��Ƃ������|����A���̑�Ƃ��Ă�B5b�̌v��ł���B
�@�A�����J���{���������������ɋ`���t������̓��e�ŁA�uB5b�v�ŁA���̒��̈ꕔ�Ƃ��āA�S�d���r���ɔ����A(1)�����^�тł���o�b�e���[�̔z���A(2)�x���g�ق�F�S��p���u���蓮�œ�������@�̊m���A(3)�菇���̐������ƈ��̌P���A�Ƃ����������̓I�Ɏ����Ă���B����B5b�̓��e��08�N���ɕ�����ɓn��A���̓��e����{�̌��q�͈��S�E�ۈ��@�ɓ`�����Ă����炵���B
�@�܂��ɂ��̊뜜�ʂ�̎��̂������A(1)�����^�яo����o�b�e���[�̔z���A�͑S���Ȃ���������A���̔�����A�Q�Ăӂ��߂��ĎԂ̃o�b�e���[���O������A�������Ǝ҂ɒ��B���˗�������ƁA�u��������ΗJ���Ȃ��v�̌��t�ƒʂ�ŁA���p�o�b�e���[�ݔ��͊C���Ђ��ɂȂ��Ă��܂��A�Ō�̖]�݂ł��������p�d���͑S�ł��Ă��܂��Ă����B
�@(2)�x���g�ق�F�S��p���u���蓮�œ�������@�̊m���A�S�d���������Ă��܂��A�d���ł̉ғ��͏o���Ȃ��A�������}�ɓ������Ȃ���Ί�@�͔����Ă���A�蓮�œ��������@�͂Ȃ��B����͕K���������̂��낤��������Ƃ����������A���Ɍ��E�͗��Ă��܂����B
�@(1)(2)(3)�Ƒ����ď����ł��Ă����Ȃ�A�ň��̎��Ԃ͔�����ꂽ�͂��A����ɓn��Ă����B5b��S�������A���̑��݂���������Ȃ��Ƃ������{���̊����g�D�ɃA�����J���{�����{��̂������͂Ȃ��B
�@�m���ɓ��{���͎�̂����B�Ƃ��낪�ۈ��@�͉{�����i�҂����ߊ������l�ɐ������A�S�����ׂ��ӔC�҂ɂ͉{�������Ȃ��g�D�炵���B�ł͉��̂��̂悤�Ȑ����������̂��A����͔閧������O��Ƃ��ăA�����J��������ꂽ����閧�ɂ����ƌ������Ă��邪�A�ۈ��@�̉{���҂Ƃ͉��l�Ȃ̂��m��Ȃ����A�L�����A�g�����X�ƈ����p���ł����֎q�ɂ��܂��܍����Ă��������ŁA�������܂���A���̗����x������܂���Ǝ��̈֎q�Ɉړ����������A�d�v�ȏ��͏d�v�Ȃ邪�̂ɍْf����Ă��܂����̂��B
�@�]���āA�ۈ��@�̒S���ے������̏��͑S���m�炳��Ă��Ȃ����A�������Ȃ��B����ɂ��̋M�d�ȏ��͌��q�͈ψ���ɂ������d�͂ɂ��`����ꂸ�����Ă��܂����B
�@��ꌴ�����̂̑S�d���r���ŁA����̐l�B�̓o�b�e���[���B�ɋ��z���A���Ɨp�ԁA�g���b�N���̃o�b�e���[���O���Ă��Ĕ��d���Ɍq���w�͂��d�˂��ƋL�^����Ă���A�������O��(1)�A(2)����������Ă���A���ꂾ���̑厖�̂ɂȂ炸�ɍς̂͊m�����낤�B
�@12��16���A��ꌴ�����̂������鍑��̎��̒����ψ���J����A���̓����̎��������A���̑O�͈��S�E�ۈ��@���ł������Q�l�l�������ψ��̎��X�Ȏ���ӂ߂Ɂu�����̋L���͑S���Ȃ��v�Ə،��������A�Q�l�l�،��̏퓅��Ƃ��āu�L���ɂȂ��v�̘A���Ȃ̂��A������������{���ɋL���ɂȂ��̂����m��Ȃ��B����͈��S�_�b��M����]��uB5b�v�̓e�����ӎ������A�����J���������̖��ł����āA��Έ��S�ł���䂪���ɂ͊W�Ȃ����Ƃ��Ƃ̈ӎ�����ŏ����疳�����Ă��܂����Ɛ��@�ł��邩�炾�B�������̓I�Ȏw���͉����ɂ������`����Ă��Ȃ��B
�@�m���ɁuB5b�v�́A�e�����X�g�ɂ��j��H���z�肵�ăA�����J�����̌�����@���Ɍ�邩�̐��X�����H�I�Ȗh�q����u���Ă���B
�@���̒��ɂ͑�ꌴ�����̂ŁA�������O�ɏ������Ă������Ȃ�A������������h���������m��Ȃ��B���邢�͂��̂悤�ȑ厖�̂ɂȂ�Ȃ����������m��Ȃ��A�ƍl����̂͌���ɐ��ʂ����Z�p�҂����f���邱�ƂŁA�S���W�Ȃ����n�̃L�����A�[�ɂƂ��Ă̓e�����X�g�̔j��H�삾���ŁA�䂪���ɂ͖��W�Ƃ���ɓǂ݂����Ȃ��œ�ďI���A�]���ċL���ɂȂ��̂����R�ƂȂ�B
(1)�S�d���r���F�uB5b�v�̋K��ł́A�𗬂ƒ����d�������r����z��A�������䎺���܂ރR���g���[�������̑S�ł��z��B
��Ƃ��Ď����^�щ\�ȃo�b�e���[�̏������K�肵�Ă���B
��ꌴ���ɂ��o�b�e���[���͂��������A�ŏ��ɐ��v���Ă���A����z�肵�Ă̗\���d�����Ȃ̂��A�v��������̃~�X�ɒN���C�t���Ȃ������̂��B
(2)���q�F�����̌����F�uB5b�v�̋K��A�����^�щ\�Ȓ����d���Łu�������S�فv������ŊJ���߂�����@�̏������`���t���Ă���B�o�b�e���[���^�ԑ�Ԃ�A�𗬓d�����ɕϊ����鐮����̏����������Ă���B
(3)���q�F�̗�p�F�uB5b�v�̋K��A�����d���A�𗬓d�����Ȃ���Ԃł��AIC��RCIC���蓮�ŋN���E�^�]������@�̕��������`���t����B
(4)�i�[�e��x���g�i�r�C�j�F�uB5b�v�̋K��A�x���g�ق��蓮�ŊJ���邽�߂̏������`���t���A��C�쓮�̕ق��J����̂ɕK�v�ȕ����͔�Ђ������邽�ߏ��Ȃ��Ƃ�100���[�h�i91���[�g���j���ꂽ�ꏊ�ɕۊǂ���悤���L����Ă���B
�@���������ꌴ�����̂Ŕ����������Ƃł����āA���d�͑z��O�̎��̘̂A���őΉ����Ԃɍ���Ȃ������ƕٖ����Ă������A���͑S�Ă��z����ł̎��̂ł����āA���O�ɏ������Ă����Ζh�����A���邢�͂�����x�͌y���ł����\���͂������B
�@�K���ɂ��A2011�N11�����݁A�����������̂̌�n���ɏ]�����Ă����ƈ��ɂ͊m��I�e���͌����Ă��Ȃ��B
�@������ꌴ�����̂̎��A���q�́E�ۈ��@�����̗̂���3��12���̔��\�ɂ��ƁA�u��ꌴ������t�߂̕��ː��ʂ��ʏ��8�{�A1���@�̒������䎺�Œʏ�̖�1,000�{�v������Đ������������ɁA����3km�����̏Z�������ɏo���Ă������w����10km�����Ɋg��A�����20km�����Ɋg��A15���ɂ͔��a20km����30km�͈̔͂̏Z���͉������A10�����25���ɂ́A�������̏Z���Ɂu������v���Ăт������B
�@���Z���̒n����A���~��`���Č��߂�̂ɂ͂ǂ�ȈӖ�������̂��B����Ɏ�����Ƃ͉��Ȃ̂��B
�@������ɔ����ăV�~�����[�V���������A��̍���A�}�j���A�����쐬���Ă����ׂ����{���n�������̂������Ȃ���Ԃł̂Ԃ����{�Ԃł�����A���ɂȂ�͓̂��R�̌��ʂȂ̂ł��傤�B���S�Ǘ��A���S���i���̔ߌ��ł��B
�@�������A�ۈ��@�ł͕��˔\��U�̏��V�~�����[�V�������ĉ����}�b�v���쐬���Ă����Ƃ���A���@�̓ƒf�Ő�ɔ��~��`���Ĕ��������߁A�e�����̂ɔ��v�����o�����Ƃ̂��Ƃ̂悤�ł��B
�@�ł͔��a10km�A20km�ɍL���Ă����������͉��������̂��B
�@���ː��y�ѕ��˔\�R����N���Ă��錴�����痣���Η����قǕ��˔\�𗁂т�ʂ͌��邩�炾�Ƃ̔��z����炵���B
�@���_��\���܂��ƁA���ː��̋����́A���ː�����˂�����ː������i��ꌴ���j����̋����̓��ɔ���Ⴕ�܂��B��̓I�ɂ����܂��ƁA��ꌴ������{�̋�������ĉ����֍s���Ό������ӂŗ��т���ː���1/4�Ɍ������܂��B
�@�����4�{�A8�{������1/16�A1/64�E�E�E�E�Ƃ��������l�͗��_�㐬�藧���܂��B�ł�������͈͂~�̐��l���L���Ă����Α��v�Ɨ��_��Ō��߂Ă������̂ł��傤���B
�@�Ƃ��낪�A�F�����m���Ă���ʂ�A�����͂����Ȃ��������ɏ�������ː��������y�������֔����A30km�����O���ɑ��݂��Ă����ъڑ�����5�s�������u�v��I�����v�Ɏw�肳��A�ъڑ��͑S�������B
�@�x���������������̕��������x�͍����悤�ŁA�����Ŕ�r�����ꡂ��ɋ߂��L�쒬�͌x���n�悪�����ɂȂ�܂�������A���S�~����ł̔���挈��͂��܂�Ӗ����Ȃ����ƂɂȂ邪�A�ꍏ�𑈂��ً}���Ԕ����ŁA�̐S�̃f�[�^������Ă��Ȃ��ł����������ނȂ��[�u�����������m��Ȃ��B
�@�`�����m�u�C�����̂ł́A�ŏ��ɋC�t�����̂��������ꂽ�X�D�G�[�f���ł���A�S���B����Q�������̂�����A���_�͂����܂Ŋ���̗��_�ɉ߂��Ȃ��B
�@�]���ĉ�km�ȏ㗣���Α��v�Ƃ����A��̓I�Ȑ��l���������~��`�����Ƃ͏o���Ȃ��A�ƌ������ƂɂȂ�B
�@������ꌴ�����̌�̊O���l�L�҉�ŁA�u���E�B��̔픚���ł�����{�����E��O�ʂ̌��q�͔��d����ۗL���Ă���̂͂ǂ����Ăł����H�v�Ǝ��₪����A�����āu�n�k�����{�Ƃ��Ă͈��S�Ǘ����Â������̂ł͂Ȃ����H�v�Ǝ��₳�ꂽ���A�[���̂��������͂Ȃ������B
�@���S�_�b���������d�͉�ЁA���{�����珥�����u���S�_�b�v��ӐM���Ă��܂������ʂ��A����̎��̂̔w�i�ɂ���B
���S�_�b���z
�@�u���S�_�b�v�͉����ɂł����݂���B��Ɉ��S�ł���Ɣ[�����M�����܂���ɂ́u���S�_�b�v�𗬕z���邱�Ƃɂ���B
�@���q�͔��d���́A�ǂ����Ă����q���e��A�z���A���ɔ픚�����Ƃ��Ă͂���w�̂��̌��O���傫�������B
�@�X�ɐ��ɂ����Ă��A���A�������ł���ܑ勭���������Č������̎������J��Ԃ��s���Ă������A1954�N3��1���j���[�L���b�X�����Ƃ��Đ���������쑾���m�̃r�L�j�ʁA�������ʂŕč����s�������������C��̊댯�C�挗�O�Ŗ����ꋙ�����Ă����ĒÍ`�����́u��ܕ����ہv�i140�g���j�����ƒ��A�˔@��������ׂ̍��ȊD���~���Ă��āA�u���̊D�v���b�ɍ����ς���A���Ղ��t�����Ƃ������瑊���ȗʂ̕��˔\��тт��~�D���������B
�@��g���͉����������̂��Ӗ��������炸�A�����Ⴊ�~���Ă����Ə�k�������Ă����炵���������댯�������Č��ꂩ��ق��悤�Ƃ����̂����A�g�����ƒ������������Ƃ͏\�����Ԃ�v���A���S��g��23�����b��Œ����ԍ�Ƃ��p���������߁A���܂킵���O���A�����픘�����Ă��܂����B
�@��̒����ł͏�g��23�l�����т��O���픘�ʂ́A1.7�`6.9�O���C�iGy�j�Ɛ��肳���i��ɉe�����������̏ꍇ�́A1Gy��1Sv�Ɗ��Z�Œv���ǂɋ߂��j
�@���̕��ː��ʂ͋}���Ǐo��픘�ʂɂ�����A�����S��g�����q�f�A���ɁA�畆��Q�A�E�сA�������̌����Ȃǂ̋}���Ǐo���B
�@���E���Ŋj�������������A���˔\�J���x�X���A�G���ƓÂ��ɂȂ�Ɖ\����ь����A�S�������j�A�����M�[�ł���������A���̏��ł̌������ݐ��i�͂Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ������B
�@�������A���Ẳ䍑�͌o�ϐ����������E���オ��Ő��E����������鐬���Ԃ肾�����B��������Ɠd�͏�����E���オ��ŏ㏸���A���R�d�͕s�������O����A���Η͔��d�͓�_���Y�f���œ��ł��A���͔��d���J���n�_���Ȃ��A���͔��d�A���z�����d�A���̑��̔��d��i�͋Z�p�I�ɖ��m�̐��E�ł����Ȃ��B
�@��������Ǝc��͌��q�͔��d�A��i���̃C�M���X�A�t�����X�͐ϋɓI�Ɍ��q�͔��d�Ɏ��g�݁A����ɑ����ăA�����J�����g�݂͂��߂��B
�@����ł͉䍑�ł����q�͔��d���̌��݂������i�߂悤�Ƃ̓����ɂȂ�A����ɂ͓�_���Y�f���o���Ȃ����ɃN���[���ł��邱�Ƃ������A�������o����Ɉ����ł��邱�Ƃ�O�ʂɉ����o�����B
�@�����ĉ��d�ɂ����S���u�����Ă����Ɏ��̂͂Ȃ��A�ƈ��S�ł��邱�Ƃ��������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@�ǔ��V����1955�N1��1���A�˔@�A���q�͕��a���p�L�����y�[�����n�߂��B�u�Ă̌��q�͕��a�g�߁A�{�ЂŃ|�v�L���X�����ҁA���{�̖��Ԍ��q�͍H�Ɖ��𑣐i�v���̌��o���Ř_�����������A���a30�N�����炸���Ԃ�����L�����y�[�����n�܂����̂��Ǝv�����A����͓ǔ��V���Ў傪���͏����Y���ł��邱�Ƃ��l����Δ[���ł���B
�@���͏����Y���͓��{�ōŏ��Ɍ��q�͔��d���̌��݂�����l�ł���A���̌�͍���c���ɂȂ茴�q�͒S��������b�߂āA�������݂𐄐i�����B
�@����ɋ����Đ��i�h�ɂȂ����̂��Ⴋ���̒��]���N�O��c�m�Ƃ��̓��u�B
�@�d�͋ƊE����d�͈�v���Č������i�ɋ��͂��A���̒��S�͓��d�̖ؐ�c�В��ŁA�Г��Ɍ��q�͉ۂ�V�ɐݒu���A���͂Ȑ�`�Ԑ��𐮂����B
�@�������������Ă��������V����1974�N7�����猎1��10�i�̌��q�͍L�����f�ڂ��A�����V���������^���h�ɂȂ����͓̂d�͋ƊE�ɂ�鍪������t�������̂Ǝv����B
�@���̌�A�����V�������������~�߁A�^���h�ɂ܂�����B����ŎO��V�����^���h�ɂȂ�A�唼�̃}�X�R�~���e�F�h�ɓ]���������ƂɂȂ����B
�@�O��V���̍L����͍����A�S����1�y�[�W�܂邲�ƍL���������1�疜�~�A�N�Ԃł͒n����������10���~�ɂ��Ȃ�B�����Łu����PR�\�Z�́A���ݔ�̈ꕔ�v�Ɖ�Ђ��F�߁A�L�x�Ȏ�����������Łu�������S�_�b�v������Ă������B
�@�d�͒����������Ƃ����@�ւ�����A�d�͊֘A�̌���������Ƃ���ŁA���̌�����͓d�͉�Ђ����S���Ă���A�ϑ��������w�ǂ��B������d�͉�Ђɋt�炤�����͌�@�x�Ƃ����̂��Öق̗��������ƂȂ�B
�@�������̂͐�ɂ����Ă͂����Ȃ��A�]���ĉ��d�ɂ����S������������A�����猴���̎��̂͂��肦�Ȃ��A�����̈��S�͐�ł���A�ƌ����O�i�_�@�����藧���Ă����B
�@�Ƃ������ƂőS�d���r���Ȃǂ͖�����ɂ��N���蓾�Ȃ������ŁA���̑�ȂǕ����ʂ�z��O�A������V�~�����[�V���������Ȃ��A�ܘ_�}�j���A�������݂��Ȃ��B�������K�v�Ȃ��B�]���āA�A�����J��NRC�A�t�����X�̃A���o�Ђ̂悤�ȋ@�ւ͑��݂��Ȃ������B
�@���S�_�b�̔��[�́A1980�`90�N��A�u���q�͐�����v�Ƃ������{�̌��q�͐���𐄐i���Ă��������ҁA�����A�d�͉�Ђō�������ȉ������A�����Řb������ꂽ���Ƃ͔@���ɂ��č����Ɍ��q�͂̈��S����PR�o���邩�����S�ŁA�����͋c���^�Ƃ��Ďc���Ă��邻�������A�����ł��낢���PR��킪����ꂽ�Ƃ����B��������O�s�o�Ŗ����ɂ͂��Ȃ��B
�@�d�C���ƘA����́A�����̃C���[�W�����d�邽�ߑ����̒����l���N�p���Ĉ��S��PR���s�����B�ܘ_���q�͂Ɋւ��Ă͂Ȃ�̊W���Ȃ������Ȑl�B���B
�@PR��ϋɓI�ɍs���A���S�_�b�𗬕z����͓̂��R�̂��ƂŁA�������Ƃł͂Ȃ��B�������͗]��ɂ����S�_�b����s���Ă��܂��A�̐t�̈��S�a���ɂȂ��Ă��܂������Ƃɂ���B
�@���S�_�b����{�S���ɐ��ݍ��܂���B�Ƃ�킯�d�v�Ȃ��Ƃ͌����n��Z���Ɉ��S�_�b���J��Ԃ����ݍ��܂��Ă������ƂŁA�����ғ��ɂ͒n��Z���̏��F��K�v�Ƃ���A�Ȃ�������S�_�b��M���Ă��炤�K�v���������B
�@���d�̌��q�͒S�����В��������āA1998�N�̎����}����o�n�A����\��œ��I�����Q�c�@�c���������B���͎���2004�N�̑I���ł��đI����A�����}�ł̌������i�h�̕M���Ƃ��Ċ����B
�@���̒����u�Ȃ��������v�̈�߂œ��{�̌����̈��S������������u���S�x���Q�̍����v�̏͂̒��ł̕����Љ��B
�@�u�j�ɕq����������S���������A�픚���E���{�Ȃ�ł͂̔������A���E�Ɋ�����Z�p�B�`�F���m�u�C���̎��̂́A�j������~�߂�̂Ɏ��s���A���˔\������߂邱�Ƃ����s������ŁA�v���̂ɖ�肠��A���{�ł͍l�����Ȃ��B�X���[�}�C�����̎��̂́A��₷�̂Ɏ��s������ł���B���{�ł͂��������P�Ɉ��S�m�ۑ�52���ڂ��Ƃ�܂Ƃߎ��{���Ă���v�ƁA�����̈��S�����������Ă���B
�@���܂�W�Ȃ������m��Ȃ����A��O�u���{�͐_���v�u�_�B�s�Łv�u�c���_�b�v�����w���̍�������荞�܂��A�{�C�ŐM�������ʁA���E��ɐ���Ċ����Ȃ��܂Œ@���̂߂��ꂽ���Ƃ��v���o���A�M���邱�Ƃ̕|�낵����������B
�@��O�u�哌�����h���v�u���퐋�s�v�����V�������悵�ď����Ă����B
�@������ꌴ�����̌�̊O���l�L�҉�ŁA�u���E�B��̔픚���ł�����{�����E��O�ʂ̌��q�͔��d����ۗL���Ă���̂͂ǂ����Ăł����H�v�Ǝ��₪����A�����āu�n�k�����{�Ƃ��Ă͈��S�Ǘ����Â������̂ł͂Ȃ����H�v�Ǝ��₳�ꂽ���A�[���̂䂭�����͂Ȃ������B
�@���S�_�b���������d�͉�ЁA���{�����珥�����u���S�_�b�v��ӐM���Ă��܂������ʂ��A����̎��̂̔w�i�ɂ���B
�@2011�N11��3���A�V�������A�����d�͂����z�̑������o�����̂́A�o�c�w�����S���ӂ��Ă�������ł���A�����������̂̍ő�̗v���͌o�c�w�̑Ӗ��ɂ���A�Ƃ��ē��d�̊��储�悻30�l�����̌o�c�w�ɑ��āA���v1��1,000���~�]���Ԋ҂���悤���߂銔���\�i�ׂ��������邱�Ƃɂ����B
�@����1��1,000���]�̋��z�́A���d��8���ɖ��炩�ɂ��������������̂ɂ�鑹�������z�ŁA�ߋ�20�N�̊Ԃɖ������߂Ă������悻60�l���Ώۂ��Ƃ��Ă��܂��B
�@�����Ԋ҂���Ȃ��ꍇ�́A�����\�i�ׂ��i����A�Ƃ��Ă��܂����A1���~���鐿���z�͍����ł͍ō��z�ɂȂ�B
�@��i�̗��R�Ƃ��āA�����͐�Ɉ��S���A�ƌJ��Ԃ��������Ă����B���呍��ł����S���ɋ^���悵�����A���S�����������邾���ɏI�n�������A���Ԃ��̂��Ȃ��厖�̂��N�����Ă��܂����B
�@���̂͌o�c�w�̑Ӗ��������ő�̌����ł���A���̌��Ɋւ��Ďi�@�̏�ŐӔC�Njy�����Ă��������A�Ƃ��Ă���B
�@����1���́A�č����œ��d�̌o�c�ӔC��₤�����オ���Ă���B
�@���d�͍�N9�����呝����4,000���~������č������Ƃ̎����B�������肾����ŁA���d������͌o�c�̃v���Ƃ��Ēʏ���҂����u�P�ǒ��Ӌ`���v���ʂ����Ă��Ȃ������B�X�Ɍ��q�͑��Q�����@�ɏ]���āA�����~�K�͂Ƃ�������Ӓn��̕⏞�ƂȂ�Ε��S������Ȃ�����A���{�����S���邱�ƂɂȂ�A���d�͎�����̍��L��ЂɂȂ�\���������B���z�Ԏ��͖Ƃꂸ���z�ƂȂ�Ί���̑����͌v��m�ꂸ�A���̐ӔC�͌o�c�w�������̈��S���ӂ������Ƃɂ���A�o�c�ӔC���ʂ����Ă��Ȃ��Ƃ��āA���Q�����̑�\�i�ׂ������\����ł���A���d�͍X�ɋꂵ������ɒǂ����܂��B
�@�܂��A�����������̂Ɋւ��Ή������A���J�����̑��Ɋւ��A���{���{�A���d�ɑ���}�X�R�~�A�G�R�m�~�X�g�A�w�ҁA�E�H�[���W�ҁA���̑�����̔��A�������B
�@�o�ϕ��͂́A��2�l�����i4�`6���j�̓��{�̍��������Y�iGDP�j���O�N���3���ƌ��邪��������1.5�����͓��d�ɂ��l�K�e�B�u���v���Ƃ��Ă���A����������ł͂Ȃ��̂ōX�ɗ������݂͑����ƌ��Ă���A���˔\�ɉ������ꂽ�n��̌o�ϊ����͐�������A����̗������݁A�l�S�̈ޏk���Łu���Ɏc�O�ł����A���{�͂₪�ĕn�������ɂȂ�ł��傤�v�Ƃ͕č��o�ω�c�iNEC�j�O�ψ������[�����X�E�T�}�[�Y�A�n�[�o�@�[�g��w�������j���[���[�N�s����10��23���s�����u���̈ꕔ�ŁA���E�̊�͓��{�̗������݂�\�z�����B
�@�������A���{���t�ɑւ���Ă���́A�~���h������ǂ����ɒ����ɗA�o��L���A�����Ɍi�C��������B�A���������ғ���~�ɂȂ��Ă���A����ɑւ��Η͔��d�p�̉��ΔR���A�������債�A�h�����ɓ]�������ߖf�Վ��x���������Ă�����A�����Ȃ�14�N1��14�����\������N11���̍��ێ��x�i����j�A�o���̋��z�Ⓤ�������̏o����Ȃǂ��������������u�o����x�v�͉ߋ��ő��5928���~�̐Ԏ��ɂȂ����B���{����C�O�ւ���������o���Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�@�~���ŗA���i�������ɂȂ��Ă���Ƃ���ɓ~�ɂȂ��ĔR���A���������A�A���z�̂ق����A�o�z��葽���f�ՐԎ����c����Ƃɂ��B
�@���E�̊�͓����{��k�ЂŔ�ЏZ���ɂ͓���I�ł��邩���m��Ȃ����A���d�A���{���{�ɑ�����̂͑����Ɍ��������̂�����B
�@���ɃA�����J�́u�F�B���v�ő���ȉ��������Ă��ꂽ���A���d�A���{���{�ɑ��Ă͌������A���̒���A�����̐\���o�������f���Ă��܂������s�������Ă���A���̌�̎��̑Ή��̊낤���ɓ{��S���������炵���B

�@�o�ςɊւ��Ă����E�̈�ʓI�Ȍ����́A�M���V���Ɠ����悤�Ɍ��Ă���A���E�ő�z��1�璛�~�����i10�����ő������j�����A�ԍς̌����݂͑S���Ȃ��A�o�ς͒���A�ǂ��ł���������悤�ȓ����{��ЊQ�A�����������̂ƂȂ�A���O�����猩��ΐ�]�I�Ȍ��������ł��Ȃ����A�o�ϗ��_���炢���Ă����{�o�ς̌��ʂ��͈Â��B
�@�������A���̐�]�I�ȏ���Z���ԂŐ��E���̌o�ϑ卑�ɖ��o�����т�����B���ꂩ�炪���{�����̐^���A�͗ʂ�����邱�ƂɂȂ�B
 |
 |
��\���́@��ꌴ�����͖̂h�����̂�
Q�F���̂̌����͑z��O�̒n�k�ƒÔg�ɂ�邱�Ƃ͔���܂������A�S���s�R�͂ł����Ď��O�Ɉ��S������鎖�͏o���Ȃ������̂ł����H
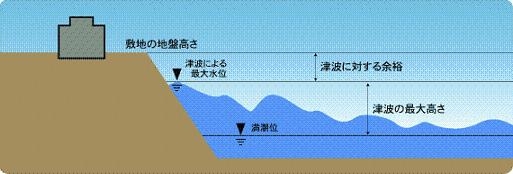 |
A�F�m���ɔ��d�����܂߂�6�n��������Ȃ���S�Ă̓d����r�����A��p���̏z�|���v����~�������߁A���q�F���̐��͕���M�ŏ����A�R���_���I�o���ă����g�_�E�����N������ŁA�c�O�Ȃ���e���V�f�͋�����܂��A���V�O���d���̓S�����n�k�ŕ��Ȃ�������A�Ôg�̏P���ɔ����Ă����ƍ���ɔ��d���p�̎{�݂��ڂ��Ă�����A��s�����m��܂��c�O�Ȏ�����ł��B
�@���쌴���A����������n�k�A�Ôg�̏����͖w�Ǔ����A���n�����������ŁA���̂���قǂ̖��Âɕ����ꂽ�̂ł��傤���B
�@���쌴���͂��k���n�ɋ߂��A���������ɗ��n���Ȃ���A�ܘ_�����ł͂Ȃ����A�t�ߏZ�������ė����ʂł�����A����قǂ̔�Q���Ȃ������B����͌��ݎ��A�{���̐v�}������荂��ɔ��d�����u��ݒu�����̂͒S����������̋Z�p�҂ł����B
�@����̔��d���͌����̒��ɂ������B�ق�̋͂��ȑ��Ⴊ�����̑傫���ɂȂ�܂����B
�@���̂̍ő�̗v���́A��n�k�Ƃ���ɔ�����Ôg�ł��邱�Ƃ͖����ł����A�������ł͂Ȃ����Ƃ��A�����V���[��������p���܂��B
 |
| ������ꌴ�� | 1���@ BWR-3GE�@1971�N3��26�������@�H��390���~ |
| 2���@ BWR-4GE�@1974�N7��18�������@�H��560���~ |
�@�����̉䍑�ł͌��q�͌��݂Ɋւ���Z�p�͂Ȃ�GE�A�A�����J�E�[�l�����E�G���N�g���b�N�Ђ̐��i�A�����t���H���A�����A�Z�p�w�����S�ăA�����J�AGE�Ђ����������Ƃ����u�t���^�[���L�[�v�ƌĂ��_��ŁA�Z�p�I�ۑ�͑S��GE�������������A�{�H��ł��铌�d���͉^�]�J�n���ɃL�[��P�邾���A���ꂪ�u�t���^�[���L�[�v�̈Ӗ��ŁA�S�Ċۓ����̍H���_��ł������B
�@�]���Ĉ��S����A�����J�d�l�ł����āA�n�k�͖w�ǂȂ��A���j�I�ɂ݂Ă��傫�ȒÔg���O�Ⴊ�Ȃ��A�����J�ł̍ЊQ�̍ő�Ȃ̂̓n���P�[���A���{�ł͑z�������Ȃ��A�A�����J�Ɠ��̋���ȃg���l�[�h�i�����j�̔�Q�A�u�̃~�T�C���v�ƌĂ��������ԕ|�낵���A�܂����������e���̏P�����̑�Ƃ��ẮA���d����d�v�t�ѐݔ��͒n���{�݂ɂ���Έ��S���Ƃ���A�A�����J���̎d�l�Őv�����B
�@�������݂�S���������ʎY�Ȋ�����������U��Ԃ��Ă̏،��ɂ��Ɓu�A�����J�d�l�ʂ�ɑ���Ȃ��ƈ��S�͕ۏ��Ȃ��ƌ����A���_�o���Ȃ��܂܂ɑ��炴��Ȃ������v�Ə،����Ă��܂��B�m���ɃA�����J�l�̋C���Ƃ��ēƑP�I�ȃ��m������܂����A���̌�A���݈ȗ�40�N�߂����o�̂ł����炻�̊ԁ@���d���Ŕ��p�d���{�݂����ł�����Ɉڂ��Ƃ��A���炩�̑������͂��ł��B

�@�ł�����A40�N���o�����݁A�A�����J�EGE���ɐv�ɕs�����������A�Ƃ���̂͒P�ɐӔC����̕ى��ɂ����܂���B
�@���S�_�b���������`���A���S���ӂ��Ă����ē����A�d�͉�Ђ̑Ӗ������ӂ߂�ׂ��ł��B
Q�F���{���ɂ͌��q�F�A���q�͔��d�����݂̋Z�p�Ȃ��A�S��GE����w�сA�ۓ�����ԂŃX�^�[�g�������{���ɂ͕s���͂Ȃ������̂ł��傤���H
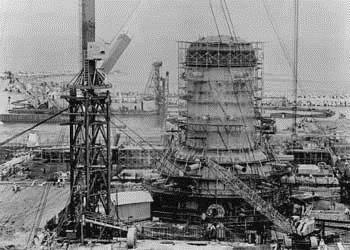 |
| �i������ꌴ���H���A���q�F�����t���H���j |
�@���̕����u�����@�̒a���v(�c�̖؉�E���d���q�͉�ҁu������ꌴ�q�͔��d��1���@�^�]�J�n30���N�L�O���W�v(2001�N����)�j�̒��ŁA������ꌴ��1���@�̃g���u���ɂ��Ă̋L�q������A�Ƃ�����1���@�̃g���u���ɂ͔Y�܂��ꂽ�ƒr�T����1969�N���d���������������Ƃ��ĕ��C�A���̌�GE�ЂƂ̌��q�F�w���Ɋւ��Ă͐ӔC�҂Ƃ��ē��d���͒������В��A�_��S���ɒr�T�����Ȃ�A����Ɍ��ꐘ���t���Ɋւ�GE���Ƃ̐ՒS���ƂȂ�A1���@�̉^�]�Ɋւ��Ă��^�]�ӔC�҂ɂȂ����B
�@������������GE���}�[�NI�^���q�F�̓X�y�C���������Ђ̔����ɂ���Đ��삳�ꂽ���m�ŁA�X�y�C���d�l�Őv���ꐻ�����ꂽ���q�F�ŁA���{�����̑ϐk�\���ł͂Ȃ������B
�@���ꂪ�X�y�C���ł̌�����̒x�ꂩ��A�}篓��{���ɔz�u�����ɂȂ������̂�����A���v�ł̑ϐk�v�ł͒n�k�����{�̊�����킸�A���ǁA���{���őϐk�\���ɂ����x���\�����̕⋭���s�����B
�@����œ�����Ԃ���襂ɐ��炴��Ȃ������̂ō\�����̓�������ƈ������蔲����̂ɖ��ʂȎ��Ԃ�������A�����ł̍�Ƃ�j�Q������肾�����A�Ƃ����B
�@�_��S���������r�T���́A�t���^�[���L�[�̌_������Ă����̂�GE���͓ƒf�ōH����i�߁A���d���̃N���[���͖�������A�o���̊Ԃɗ������r�T���͑啪��J���Ă����悤�ŁA�t���^�[���L�[�̌_�����܂ʼn����ł����悤�ł��B
�@���������n�����I���A���a46�N3��26���c�Ɖ^�]�ɓ���A�r�T�������̂܂܌���Ɏc��1���@�^�]�̐ӔC�҂ɂȂ��������ŁA�̏Ⴊ������J�����悤�ł��B
�@���̌�A�{�Ђɖ߂茴�q�͒S���̃Z�N�V����������A�ŏI�I�ɂ͌��q�͒S�����В��ɏA�C���A���҂ɕڑł悤�ł����A���X�̎��̉B���A������ₓ��X���X�̃X�L�����_��������܂������A���q�͒S�����В���煘r�ɂ�鋭�d�˔j��d�������ʂ������悤�ł��B
�@�܂�1���@�͓x�X�̏���N�����Ȃ�����A40�N�Ԃ����܂����܂��g�������Z�p�͑�ςȃ��m���ƕ]������Ă��܂��B
�@�r�T���̌��q�͊E�A���d���ł̐M�p�x�͐�傾�����悤�ł��B
Q�F���d�Ƃ��ẮA�n�k�A�Ôg�ɑ�����S��̍ő�l���ǂ̈ʂɌ��ς����Ă����̂ł����H
A�F�ڂ������Ƃ͉���܂��A���d��HP�ł͒n�k�͊֓���k�ЁiM7.9�j���ő�ł���AM8.0�ȏ�͂��蓾�Ȃ��B�Ôg�͉ߋ��̗Ⴉ��݂čő�5.6m�Ƃ��Ă����B
�@���Ƃ̒����ɂ��ƒn�k�͍ő�M8.0���x�A�Ôg�͍ő�g���@��m���x�ƌ��_�t�A���S��͏\���Ɏ����Ă���A�Ƃ��Ă����悤�ł��B
�@�A���A���߂Ē����������ʁA�l�������̋߂��Ɋ��f�w���������ꂽ��A�l���d�͂ŗB��̌����ł���ɕ������͈��Q�������������̍��������ɂ�����n��ɂ������30�N�ȏ�o�A���̍����������ɕ��s����悤�ɉ䍑�ő勉�̊��f�w�ł��钆���\���������݂��Ă��邪�A����ɒf�w���������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�f�w�̑��݂����Č��݂����̂��B
�@��C�n�k�����O����A���߂Ĉɕ������̑��݂�����Ă���B
�@�������̌�Ɂu��ϒn�k�E�Ôg�v���V���������킵�Ă���܂����A���̂悤�ȌŗL�����͗��j�̋��ȏ��ɂ͂Ȃ������Ƃ���l���唼�ł��傤�B
�@���̒�ϒn�k�i�W���E�K���j�Ƃ����̂́A1980�N��̔����A���k�d�͂����쌴���̑��݂ɔ����A�t�߂̒n���������������ʁA�Ôg�̍��Ղ������B
�@�]���A���{���Ă����n�������i�{�[�����O�����j�͒��a3cm���x�̌��ōs���Ă������Ôg�̍��Ղ����邱�Ƃ͍���ƍl���A�ʓI�Ȋg��������u�ؖx��R�v�Ƃ�����@�ŁA�n�w�̍��₻�̏㉺�ɂ���N�㑪�莑�����̕��͂�ϋɓI�ɍs�����B���ʁA��Ôg�̍��Ղ��A���̌㉽�������Œؖx��R�̒����𑱂��A�����I�ȃV�~�����[�V�����ł͐�䕽��ł͊C�݂��600�`1,500m�̓������܂ŒÔg�͂����A�͐�t�߂͍X�ɏ㗬�܂ŒÔg�͍����B�@�g���͐���A�C�݂�9�`10m�ʂƂ����B
�@��䕽��̒��S�n�A�����ɍ��{������A�����Ɏc����Ă��������̌Õ����Ɂu����邪��ꂽ�v�u��l�������ꂽ�v�u���痢���C�ɂȂ����v�Ƃ����L�q�����������A������Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă������A�Õ����̋L�^�������ł����������ؖ����ꂽ�B
�@869�N�i���11�N�j�A������1142�N���̂ŁA���������A�������S���̍��A�Ⴋ�������^���V�i�C�s�Ȋ��l�Ƃ��ēo�p���ꂽ���ł��B
�@���̑�Ôg�͕l�ʂ��т��P���Ă���A�x���C�݂���������Ήw�t�߂܂ŒÔg�̍��Ղ����邩���m��܂���B
�@���̒�ϒÔg������݂ɂłĂ���A���S��������āA�Ôg�̍ő�g����10.6m�ƏC������A���̑�Ƃ��āA����3�N�̊Ԃɑ�ψ���𗧂��グ����x�ŁA�����{�i�I�Ȋ����ɂ͎����Ă͂��Ȃ������B�Ȃɂ����N�ȏ�̂̂��Ƃł���A���j���o�ł͍��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ٔ����͑S���Ȃ������悤���B
�@���Ǝd�����ł���N�Ɉ�x�̂��Ƃ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ɠ��ق�������Ȃ̂ɁA���N�����P���Ă����B
�@�ߔN�A���O�ł̒Ôg�̏��݂Ă݂܂��傤�B1960�N5��22���̃`���C��n�k�ł͍ő�8.5���ꂩ��A������M7.0�N���X�̒n�k���A�����A�`�����݂ōő�18m�̒Ôg���P���A�n���C�E�q���p��10.5m�A�䍑�ł�22���Ԍ��5��24�������@�ő�6.0m�̒Ôg���O�����݂��P���A142�l���]���ɂȂ����B
�@2004�N12��26���@�ߑO7��58���A�C���h�E�I�[�X�g�����A�E�v���[�g�̃C���h�m�C��Ŕ�������M9.3�̑�n�k�ŒÔg���g���͕��ς�10m�����̑�Ôg�ƂȂ�A�x���K���p��тł̋]���Җ�60���l�i���A����j�ƌ����Ă���B
�@���̑��@���E�̗���݂Ă��n�kM8.0�C�Ôg���g��10m�͂��蓾�邱�Ƃł����āA�䍑���ӂł͐�ɂ��肦�Ȃ����Ƃ��ƌ��ߕt���Ă����u���S�_�b�v�͍����̂Ȃ���]�̐��E�ł����Ȃ������B
�u�����Ɉ��S�_�b�͂��肦�Ȃ��v
��������ꌴ�����̂̎��ԓI�o�߂�������x�H��܂��B
| 3��11�� | �ߌ�02��46���@�����{��k�Д��� |
| �ߌ�07��03���@���{�A���q�ً͋}���Ԑ錾 | |
| �ߌ�09��23���@3km�����̔��w�� | |
| 3��12�� | �ߑO05��44���@10km�����̔��w�� |
| �ߌ�03��36���@1���@���f���� | |
| �ߌ�06��25���@20km�������w�� | |
| 3��15�� | �ߑO11��01���@3���@���f���� |
| 3��12�� | �ߑO06�����@2���@�ŏՌ����i���f�����ł͂Ȃ������B�����s���j |
| �@�@�@�@ �@�@4���@�ł������i���f�����j | |
| �ߑO11���@20�`30km�����������w�� |
Q�F1���@������12���ߌ�3��36���A3���@������14���ߑO11��1�����f�����Ō����̏㕔�����܂������A�Ôg�ォ�甚���܂ł̊Ԃɑ�̕��@�͂Ȃ������̂ł����H

A�F�m����1���������Ôg����1����A3�������͖�3���o���Ă���A���̊Ԍ���E���̊F����͎��ɂ��̂��邢��������Ă����Ǝv���܂��B
�@�����ʂ�u�t�N�V�}�E�t�B�t�e�B�v�Ɛ��E���]�����Ă���ʂ�ł��B
�@���x���������Ă��܂������A�S�Ă̓d������~�����̂ł�����A�@���ɂ��ė�p�����z�����邩�ł����ɏW�����Ă����͂��ł��B
�@�ł͉��́A1����3���̔����Ɏ������������̂����݂Ă݂܂��B

�@�n�k�ŊO���d���ł���S�����|��A�����̊O���d����r���������߁A���p�d���ł���f�B�[�[�����d�@���N���������A�n�k����41����̌ߌ�3��27�����g�Ƃ���g��15m�������Ôg���P���A�Ȍ㐔��ɂ킽���Ôg�͖h�g����A�{�݂�j��A�n�����◧�B�ɂ��Z���A�n���ɂ�����1�`6���@�̔��p�d���͐��v�A�g�p�s�\�Ɋׂ����B
�@1���@�ł͒n�k����A���p�����킪�N���������A�}���Ȉ��͒ቺ������A�����ɒ����ɓw�͂������A�����֒Ôg�P���A�ߌ�3��50���Ւf��Ԃ̂܂ܔ��p������͎g�p�s�\�Ɋׂ�A�����Ɍv��A���ٓd���������A��͓d���Ԃ̗�����҂����Ȃ��Ȃ����B
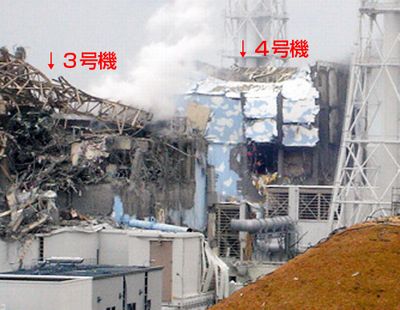 |
| 11�� �ߌ�07��30���� | 1���@�̔R���͏����ɂ�鐅�ʒቺ�őS�I�o���ĘF�S�n�����͂��܂����B�����ł̒������d���Z�ʂœ����������p��������锼��12���ߑO1��48���ɋ@�\��~�A12���̖�����6�����ɂ͑S�R���������g�_�E�������B |
| 11�� �ߌ�08��50�� | 1���@�̃����g�_�E���K���ƂȂ蕟�����m���͌������a2km�����̏Z���Ɍ��O�ւ̑������w���B |
| 11�� �ߌ�09��23�� | �������A�������m����ʂ��āA�x�����A��F���A�o�t���A�Q�]���̊e�����ցu1���@���甼�a3km�����͌��O�֑������A���a10km�����̏Z���͉������v |
| 12�� �ߑO05��44�� | 10km�����̏Z���͌��O���w�� |
| 12�� �ߌ�08��00�� | ���a20km�����Z���͌��O���w���A�ΏۏZ��17��5,000�l 1���@�A12���ߑO1��48���ɋ@�\��~�A12������6���ɂ͍��ɂ͑S�R���������g�_�E���Ɏ������B |
�@���Ԃ��o�߂���Ɗi�[�e����̈��͂��ʏ�l��y���ɒ����Ă��܂��܂��B���̂܂܂ɂ��Ă����Ɗi�[�e�펩�̂��댯�ł��B�i�[�e��͕��ː������̊g�U��h�����߁A��Ɍ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����h���ɂ͈��͂𐧌�o����悤�ɒ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���C�̈ꕔ���C�ɕ��o����Ƃ����Ή��ł��B
�@�ߑO10��17���A�x���g�J��ƊJ�n�@��C���k��̋�C�s�\���ō�Ɠ�q�B
�@�R���_���Ă���W���R�j�E���������ɂȂ蔽�����N���Đ����C���琅�f�����܂�����A�����C�̕��o�Ɠ����Ɍy�����f�͏㏸���ĕ��o����A�����̏㕔�ɑؗ����A���f�̔Z�x��4�������Ԃŋ�C���ɑ��݂���Ƌɂ߂Ċ댯�ȏ�ԂɂȂ�܂��B
�@���̂悤�ȏ�Ԃ����炭�������̂́A��C���ɑ�ʂ̐����C���܂�ł���Ɣ����͋N���Ȃ��B�����������̏㕔�͊O�C�̉e�����A�܂�3���̊������ł�������A�i�[�e����Ɣ�ׂĂ��̐�����������A�����C�͂₪�Đ��H�ɑւ��A�����C�̗ʂ��i�X�ƌ������A�����䂪�ւ���ĉ��炩�̔��Ηv��������
�@�ߌ�3��36���@1���������f����
�@�ߌ�4���@���ː���500��Sv/h������
�@���̓����A11���̓��d�{�Ђł́A�����P�v��A�ۋI�j���В��i���q�͒S���j�́u���ؖK���c�v�Ə̂���d�͉�ЁA��w�W�ҁA�}�X�R�~�W�҂ō\���A�吨�̒c������Ȃ邲��s�l�������A��Ėk���A�h�B��K�₵�Ă����B
�@�����В��͊����ʂɏo�����ŁA���̘̂A�����Ă����C���V�����͑S���X�g�b�v�A��s�@������A�������H�͑�a�A���q���̔�s�@���o���悤�v���������A�h�q������1���Ԑl�ɗ��p������͔̂@���ȃ��m���ƒf��ꖜ�������A�{�Ћ@�\�ً͋}���ԂɑΉ��ł��Ȃ��܂܉߂����Ă��܂����B
�@�������͎��q���w���Ō����̎��̌���ɂ����A�X�ɍ����m���Ɖ���Ă���B
�@2���@�A3���@�ɂ͑S�𗬓d���r�����l�����A�u���������n�iRCIC�j�E���������n�iHPCF�j�ƁA2�n���̏��C�^�[�r�����u������A2���@�̍��������n�̓o�b�e���[�����v���ċN�����܂��������A3���@�̓o�b�e���[�������Ă���HPCF���ARCI��~�����m������ւ��N������15���Ԃقljғ����F�S�ɒ����������������p�o�b�e���[���g�����Ē�~�����B
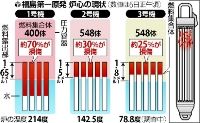
�@�a�ɂ��d���Ԃ̓����x��A�d���Ԃ̏o�͕s���A�B��̎�d�{�݂����v�Ŏg���Ȃ������B����ƊJ�ʂ������ݓd���P�[�u����6�����1���@�̐��f�����Ő��������Ă��܂����A�Ƃ����ő���̓w�͂����Ȃ�����^���̏��_�Ɏ��X�ƌ������ꂽ�悤�ȍГ�̘A���ł������B
�@13���ߑO8���@3���@�R���̘I�o�͂��܂�B
�@�ߑO11��1���@3���@�@�������f�����B
Q�F�����{��k�Ђł́A�k�В��ォ�玩�q����n�����h���A�x�@�����o�����ċ~���╜���ɏ]�����Ă���܂������A�������̂ł͉��̂������ɂ����Ă͓��d�W�҂����őΉ����Ă����悤�ŁA�����D�ɗ����Ȃ��_������̂ł����H
A�F�m���ɓ����͓��d�W�҂����őΉ����Ă����悤�ł��B�Ď��q���Œn�k�A�Ôg�ɂ���Q���ڍׂɊĎ����Ă����A�����J���{�́A���{���{�ɑ��Č��q�F��p�Ɋւ���Z�p�x���Ɋւ���\������������A�܂��t�����X�E�A���o�Ђ̋Z�p�w���F�S�n�Z�͕K���Ɣ��f���A���q�͂Ɋւ��Ă͐��E��̋Z�p�����Ǝ��F���Ă���t�����X�E�A���o�ЂɔC����A�Ɠ��{���{�ɐ\�����ꂽ�����{���{���f�����悤���A��3��18���ǔ��V�������ŕĂ���B
�@�A�����J�A�t�����X�̐��Ƃ́A�d�����~��A8���Ԉȓ��ɗ�p���z�̑������Ȃ���A�F�S�Z�����N����̂��K���Ɣ��f���Ă����B
�@���A�����J������Ă��Ă��錴�q�F�̗�p�͔p�F���O��ł�����A�܂��܂��g�p���錴�q�F��p�F�ɂ���Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��A�Ƃ����̂����d���̌����������悤�ŁA40�N�Ԏg�p���Ă���1�����q�F���܂߂Ė����g�p�ł���Ɠ��d�͔��f���Ă���A���Ɍo��팸�����d�̓����̖ڕW�ł����āA���̂��ߎ��ޕ��o�g�̐��������В��̍����̂ł�����A�p�F�Ȃǂ͂Ƃ�ł��Ȃ��I���ƂȂ�A�A�����J�̐\���o�����ہA���@�����d�̌�������u���āA�A�����J���̐\���o�́u�O�Ⴊ�Ȃ��v�u���������v�Ƃ����Ӗ��̂Ȃ����t�ŋ��ہA���d���̔��f�́A���d������ł����̂͏��m���Ă������A�o�b�e���[�������Ă��邩��A8���Ԃ͗�p���z�͊m�ۂł���A���̊Ԃɒn�k�œS�����|�����A���͂������ĊO���d�͂̕����ɂ�����Ε����\�A������F�S�̗Z�����p�v�[���ł̕���M�ȂNjN���蓾�Ȃ��A�Ɣ��f�����悤�ŁA���d�����̗͂ʼnł���ƐM���Ă����悤�ł��B
Q�F���̒���A�A�����J�A�t�����X���x���̐\���o����{���{�A���d�͒f���������ł����A���̂ł����H
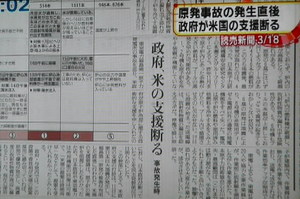
A�F�A�����J�E�N�����g�������̎x���\���o����{���{���f�����A�Ƃ����L���̍ŏ��͓ǔ��V���ł����B
�@1981�`82�N�ɂ����āA�A�����J�ɂ���I�[�N���b�W�������������A�����J���q�͋K���ψ���(�ʍ��ʼn��)�̈˗����đ傪����Ȏ����A���̃V�~�����[�V������1981�`82�N�ɌJ��Ԃ��s���A���̕��ψ���iNRC�j�ɒ�o�����B
�@���̌������́A�����̑S�Ă̓d��������ꂽ�ꍇ�̃V�~�����[�V���������{���ē���������������̂ł��B
�@���̃V�~�����[�V�����Ɏg��ꂽ���f���́uGE�А��}�[�NI�F�v�ŁA����͕�����ꌴ����1�`5���@��GE�А���A���������̂őS�������^�C�v���q�F�ł����B
�@���̕��ɂ��ƁA�S�d�����r�����Ĕ��p�o�b�e���[���l���Ԏg�p�\�ȏꍇ�A�u���ԂŊj�R���I�o�v�u���ԂŐ��f�����v�u�Z���Ԍ�ɔR���n���v�u�����Ԍ�Ɉ��͗e�퉺���������v�Ƃ����̂��A��Ȍo�߂ł����A�܂��ɕ�����ꌴ���̎��̂̌o�߂̓V�~�����[�V�����ʂ�ƂȂ�����ł��B
�@���̕�����NRC�͒����Ɉ��S�K���Ɏ����ꊈ�p�����̂ł��B
 |
�@�ł́A���d�Ƃ��Ă͂��̂悤�ȕ������邱�Ƃ�m��Ȃ������̂��A����������1���@�̌��݂�1971�N�AGE�Ђ��v�A�@�ނ��琘���t���H���܂őS�Đ��������u�t���^�[���L�[�v�_��ł�����A���̌�̐ӔC������܂��B
�@���̕�����o���ꂽ�̂�1982�N�Ȃ̂ŁAGE������͂���ANRC������A�����������悤�ŁA���̎��������邩�炱���A���ŋ߂�10��4���A�����J�c��ɂ����镟����ꌴ���Ɋւ��������ł̏،���ɗ������O���S���E���b�RNRC�ψ��������{���{�̑Ӗ�����O��I�ɂ������낵���،��������Ȃ����̂��A���������Ƃ������A���u���Ă��܂������{���ɉ䖝�ł��Ȃ������̂ł��傤���B
�@�ł͉��́A���{���͊��p���Ȃ������̂��A���������S�d�����r������悤�ȏ͋N���邱�ƂȂ��A�N���蓾�Ȃ�����z�肷��K�v�͂Ȃ��A�������͕K�v�Ȃ��B
�@�������A�����Ɍ������̂͋N���āANRC�ɂ��邱�Ƃ��N���Ă��܂����A����ł����d�͑��v���ƐM���āA�A�����J��t�����X����̉�����f�����̂́A���d���̓o�b�e���[�̉ғ�����8���ԁA���̊ԂɊO���d���͉ł���A�ƐM���Ă����悤�ł��B
�@��������A�В��A���В�(���q�͒S��)���o�����ŁA���d�̎i�ߓ��͕s�݁A�c���ꂽ�����̓}�j���A���͂Ȃ��A�I���I���������A���@�͂���܂����d����̕��Ă��A����������A���f�ł���l�ޕs���A���{�l�S�̂̊�@�Ǘ��ɑ��銴�o����������ɐi�W�����B

�@���̒���A�N�����g�������̘A���́u�����ɐ����A�����J�����A����v�ƁA����̓A�����J�̌R���q���ŕ�����ꌴ���̎��̖̂͗l���Ԃ��ɊĎ����Ă������h�Ȃ��璷���ɘA���������A����������{���{�\���o���̂ł��傤�B
�@�R���Ď��q���̉�͔\�͂͒n��1m�ȉ��̕��̂܂Ŕ���\�͂������Ă��܂�����A���̂̓��e�͐��m�ɔc�����A��p���u��ŁA�S�d���r������͂������ł��B�����炱�����̒��������ŗD��A����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��A�Ɣ��f���đ����ɐ\���o���̂����A���{���{�ł͎��̌�͏ڍוȂ��A�������̂͑z��O�Ŋ��@�̊�@�Ǘ������@�\���Ȃ��A�S�d���r���ȂǑz��O������}�j���A���Ȃ��A�]���ăA�����J�̐\���o�ł��鐅����A���鎖�̈Ӗ��������o���Ȃ��܂ܒf���Ă��܂����悤���B
�@���̌�̉ߒ�������Ή���ʂ萅�𒍓�����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ������B
�@����ɓ��{���Ƃ��Ă̓A�����J�A�t�����X�̉����������A�����̎w������D���Ă��܂��B���q�F�{�݂��O���ɔ��荞�����Ƃ��Ă��鎞���ɊO���̋Z�p����Ȃ���Ε����ł��Ȃ��A�Z�p�̖��n�������\���邱�ƂɂȂ�A��������{�������őΏ�����A�Ƃ���̂����{�A���d�̗��������������悤�ʼn�����f���Ă��܂����B
�@���Ԍo�߂Ƌ��Ɍ��q�F�Z���A���f�����ƂȂ��āA�A�����J�A�t�����X�ɏ��������߂���Ȃ��������A��ɃN�����g�����������A�t�����X�E�T���R�W�哝�́A�A���o�Б��كA���k�E���x���W�������̑����������A�킴�킴���������ɗ����킯�ł͂Ȃ��A���{�����ɔC���Ă����琢�E����ς��Ƃ̔F������ŁA��������ȏヂ�^�c���Ď������x���Ό������̉^�����������Ă��܂��ƁA������i���ł���t�����X�A�A�����J�ł͐����ێ���������Ȃ�A�����h�C�c�ƃX�C�X�͌����S�p���c�������B���̔g�������ɋy�Ԃ̂��Ȃ�Ƃ��h�������A����ɂ͈ꍏ�������������̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���{�����ł͖����Ɣ��f���Ă���ė����킯�ŁA���{�ɑ���D�ӂ����ł���ė����킯�ł͂Ȃ��B
�@�N�����g���������́u���{�̋Z�p�I�����͍������A��p�܂͕s�����Ă���͂��v�������R�@���g���ċ}�������Ɛ����\�������A��ō����ȍ��������{���{���f���Ă����̂ő���Ȃ������A�Ɣ��\�����B
�V���ɂ́u���𑗂�ƁA�A�����J���{�̐\���o�v�ƋL���ɂ��������A��p�܂̈Ӗ��͑����A�z�E�_�i�z�E�_���A�ʏ�e�{�����f�ƌĂ�ł���j�z�E�_���͊j����������}������A��������̐���_�ɐ��肤�郂�m�Œ����n�Ɏg�p���Ă���̂�����A�z������ɐ��ƌ������̂̓z�E�_���̂��Ƃ��Ǝv���B�܂��z�E�_���𒍓����Ă��p�F�ɂ��Ȃ���ΐ���Ȃ��قǘF�������t���邱�Ƃ͌����Ă��蓾�Ȃ����ƁA�p�F��S�z���Ēf�����A�Ƃ����͉̂������ő}�����ꂽ������ł��傤���B
Q�F�����d�͂́A���d�鍑�Ƃ��A�����͊��S�Ɋ�����`���ƌ����Ă��܂����A�ǂ����Ăł����H
A�F�s��̕Ћ��ɋ��鎄�Ƃ��ẮA���d�̕��Ƃ̂��t�����ȂǑS���Ȃ��A�Ј��ł͂Ȃ��ł��傤�����j�W�̕����炢�Ƃ����������������Ƃ�����܂���A���Ƃ��������܂��C�J�Ԃ̉\�b���x�Ƃ��ďq�ׂ܂��B
�@�����A�펞�̐��͑S�ĕ��A�S���̓d�͂��x�z���������͉��U�A�d�͋ƊE���ĕҐ��ƂȂ������A���M�d�͎В����i�������厁�Ɗ֓��z�d�В��V��͎����̎哱����������n�܂����B
�@�d�͂̋S�ƌ���ꂽ���i�������厁�͌c����w�o�g�A���̊W�ŕ���@�g�搶�̖����ŏ����̓d�͉��ł���������ɒ�q���肵�A����̌㊘�Ƃ��ē��M�d�͂̎В��ɏA�C�A�d�͂̋S�ƌ�����悤�Ȏ��͎҂ɂȂ��Ă������B
�@���̓d�͍ĕҐ��ł͏��i�E�V��̍R���ɒ[���A���E���������g�c�Α����̖����ł���A�����������̕��e�ł����閃������g���A���k�d�͉��TV�h���ɂ��Ȃ������_�����B���Y���A�d�͂̋S���i�������厁�ɑ���̂͐V��͎����𒆐S�Ƃ��Ē���d���В��ł���M�B�ɂ���S�Ẳ�Ђ̃I�[�i�[�ł����閼�召��ꑰ�A���ǁA���Ԃɂ���d�͑̐��̒n��Ɛ�ɂ��d�͉�Аݗ��Ɍ��܂�A���{�ő�̓d�͉�Ёu�����d�́v���ݗ����ꂽ���A�����l���ł̐l���R��������̕����J�n�B
�@�����̑�K�͓d���J���̍ŏ��͐�O����v�悳��Ȃ���R���g�����D�悳��A������ŊJ�����o���Ȃ����������쑍���J���ł������B
�@���������n�摍���J���v��ŁA1950�N�i���a25�N�j�Ɏ{�s���ꂽ���y�����J���@�Ɋ�Â��A���{���{�����߂��n��J���̖ڋʂƂ��āA�����쑍���J�������߂��B
�@������̐����͓ȖA�Q�n�A�����A�V���ɍL��������������ł��邩��A���R���ꂼ��̌����������咣�A�܂��V�����͐V�������ɐ��𗬂��Ĕ��d����V�������Ɍ��݂���B
�@�������͑����삩�爢����܂ł̎R�ԕ��̍���𗘗p���āA��ɉ����Ċ���̃_�������݂���B
�@���ꂼ��̎咣�́A��A�ڑ҂̘A���ő�����́A�^�_�m�~��Ɲ������ꂽ�B
 |
| �i�����쐅�͔��d���j |
 |
| �i�L��O�T���j |
�@���R���{���ɔg�y���A�g�c�h�A���R�h�ɕ�����Ă̍R���ɔ��W�����A���̎������̂��A�g�c�h�̎��͎҂ŁA�g�c�Ύ̉����Ƃ����Ă����L��O�T�_�ё�b�i�����j�A�������I�o�A�ΐ�S�o�g�A���̐l�̎��͂͐��������B�����Ŋ����͕̂������m���̑�|�얀���A�Ƃ��ɒ�ӂ��甇���オ������J�l�A��l�̎��͎҂𒆐S�ɂ������������̌��W�͂ɂ���ĕ���������̂ƂȂ�{���Ă��̑�����A������̑����J���ƂȂ����B
�@�����ł���z�����o�w�Ɖ�Îᏼ�w�����ԁAJR�������͌����ɘA�����Ă���_���̌i�ςɉ����đ���A2012�N�A�c�q�q���d���ĊJ�����Ƃ���������A���ɑ��̒����J���ŁA�����k�J�����J���ƕ��ԓ�H���̖��ɐ��܂�A�������ł������Ƃ��Ċ��A���̉͐�̂悤�Ƀ_�����݂ɂ�艺�������͂�ɂȂ��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��A���X�Ɛ���~�����_�����]���ł��A������Ɍq�������d���J���Ƃ��Ă͐�����ɋ�������B
�@�����Ŕ��邱�Ƃ́A�d���J���Ƃ͐������͂ɂ���Č��܂�B�d�͉�ЂƂ��Ă͗L�͂Ȑ����Ƃ�������ށA�����̎��͔h�ɂ̓R�l��t���Ă����A�_���͌���ꂽ�y�n�����A���d���͉��X�ƑI���n�Ղ�ʂ��ĕ~�݂����A�����ɌQ���鐭���Ƃ�����͓̂��R�ƂȂ�B
�@���̑����쑍���J���œ��d�͐����n�ł��鍑�������������̕~�n��4���𓌓d�����L���Ă���A�����̌v��͐������m�ۂ��邽�߂ŁA���݂͑�ςȉ��l�ƂȂ��Ă��邾�낤����ǂ��A�ЊQ�⏞�̂��߂ɂ��̍��������̕~�n�p���邱�ƂɂȂ�Α呛���ɂȂ邾�낤�B
�@�V����l���A1957�N�ʎY�Ȏ����Ό����v�����ŏ��A�햱�A���В��A��C�č������C�A�ސE��͑��k���ɂȂ�A�S���Ȃ�܂ł�34�N�ԓ��d�̖����Ƃ��ĉ߂����Ă����B
�@���̌�͑��X�ƓV���肪����ƂȂ�A�������A�ǒ��A�R�c���N���X�����d�̖����Ɏ��܂�A��E���Ȃ���ΐl�������̂Ȃ��ږ�Ɏ��܂����B
�@���̌ږ�����\����邱�ƂȂ��A�N���ږ�ɏA�C���Ă���̂��M�̒��ł��������A�������̈ȗ��������肪�����A���d��5��21�����Ɍ��\�ɓ��ݐ�A�ږ�̎����A��V�\�A���̓V����O�̊����́A�o�ώY�ƏȂ���ł͂Ȃ��A���y��ʏȁA�x�@���A�����ݏȁA���ʎY�ȁA���ۋ��͋�s���XOB���V�����̎w��Ȃ͌��܂��Ă����炵���A���ϕ�V�z��1,042���~�A�܂��ɓ��d�͓V����̓V���ł��������A�����}�����1962�N���瑱���A����̎��̂��Ĕᔻ����A2011�N4��30������}������������ق�����A���l�[�u���������B���ꂩ�犯���Ƃ̖������Ȃ��V�����W���ǂ��\�z�����̂��B
�@������Ђ̖����l���͘Z�����̊��呍��Ō��߂�̂���ʓI�����A���d�̏���В��͓��{�����d�����ق������������A��オ�֓��z�d�В����������䗺���Y�A�O�オ�i�씒�����В��������؋ψ�A�����Ďl��ڎВ��ɂȂ����̂����d�Ј��o�g�̖ؐ�c�В��܂ŏ��i�������厁�̒߂̈ꐺ�Ō��܂����B
�@���̌�͏��i�����S���Ȃ�A�ܑ�ڈȍ~���݂̏\��㐼��r�v�В��܂œ��d�Ј����p���ł���B
�@�V����̍Ő����͓c�����t�̎���A�D���������ԋ��������̖��g���������̂��c�����ŁA���d�̐V�������芠�H�������݂̎n�܂�́A���H���̗ג������R���œc�����̐��Ƃ͂����ɂ���A�x����Ղ͂����ɂ��邩��A�ؐ�c���d�В��͓c�����w�ł��J��Ԃ��A�p�n�����A���Δh��A���ׂĂ��c�����̋��O���A�����̓c�����̌���������5���A1��3,000���~�Ƃ����Ă����������ݗ����A1971�N���Ғʂ�c�����͌������݂̋��F�����錚�ݑ�b�ɏA�C�A�d���J�����i�@�ȂǓd���O�@�𐬗������A���ӎs�������܂߂��⏕������܂����x�𐬗��������B
�@�c�����͂₪�ĎɂȂ�A�����������s�������A���̍��A�o�ς͐i�W�������A���x�o�ϐ����̔g�ɂ̂��ēd�͂̏���̓E�i�M����A�d�͉�Ђ͓d���m�ۂ����o����ΒP�ꏤ�i�ł���d�C�͂�����ł������A�n��Ɛ�ł��邩�瑼�ЂƂ̋����͂Ȃ��A�������d�C�������d�����i�̓��[�J�[���ǂ�ǂY���Ĕ̔����Ă����B�Y�ƊE�͗A�o����Ɍ��Ȃ܂��ɂȂ��ēd�C���ǂ�ǂ����Ă����B
�@�����������ǂ�ǂ�㏸���A�e�O��̐_��f����ƒ�d�����i�̏[���������X�e�C�^�X�Ƃ���Ɏ�葵����Γd�C�̏�����g��A�c�Ƃɂ���ĉ�Ђ̋Ɛт��㉺�����ʉ�ЂƈقȂ�A�P�ꏤ�i�ł���d�C�Y���A���d����A�����I�ɔ���グ�ɂȂ�A���̗����͍������߂�c�Ɠw�͂���K�v�͂Ȃ��B
�@���Ƃ͊Ǘ����銯������ƂƂ̐Ղ����A����͈ꕔ�̊������S���A�ƂȂ�ΊS���͉�Ђ̓��������A�N������̒����̌n�ƂȂ�Ί����炵���Ȃ�͓̂��R�ŁA�Е��͊�����芯���炵���A�ƊO��̕]����������܂����R�̌��ʂł���A�O��̂Ђ��ݍ������������킹�Ă��邾���A�Ƃ͓��삩��̕]���B
�@�Ƃ��낪���̐�������X�����v�����������ē��R�����A���̕M���͎s���^���Ǝs��[�}�Q�c�@�c���ŁA���������j�~��i���A���̎�i�Ƃ��āA���d�����ʂɋ����d�C���������z��1�~�������������x�����Ƃ����s���^�����������A���d���͖��z�łȂ���Ύ��Ȃ��A�s�����Ȃ�Α��d��~�̑R�[�u������ƓD�����ɂȂ�A���]�͍ٔ����Ɍ����j�~��i�ׂ��鏀���𐮂��Ă����B
 |
| �i�s��[�}��c�m�Ɛ����l�N�j |
�@�s��[�}�c���̑��̍��^���ɋ����āA�葫�ƂȂ��ē����Ă����̂��A��w���o�Ă܂��Ȃ������l�N�A�s��[�}�c���Ɠ�l�œ�@�N���u�����������̂��Q�c�@�c���̐��K�j���Ō�̓����s�m���A�e�V���{���ʃz���f�[�ł̃A�I�V�}���[�f�̂ق����L�������B
�@����1�~���������^���͌���t���A���d��В�(����)���s��[�}�������ɏo�����A���d���������������l���邱�Ƃ������A��ł��ƂȂ����B
�@���d�̗��j�ɂ����ĎЉ�I���a瀂͑啪����܂������A�����I���a瀂ł����Ċ����I�ȉ����ɏI�n���܂�������A���d�̊�Ɠw�͂͐������͂⊯���Ƃ̐Ղɂ���A�����I�Ȏv�l�A���z�Ɋׂ邱�Ƃ͓��R�̗���ł��傤�B
Q�F���d�͐��{�ɑ��Č������̌��ꂩ��Ј���P�ނ��������A�Ɛ��{�ɑ��\�����ꂪ�������Ɛu���܂������A�{���ł����H

A�F���̗l�ȉ\���������͎̂����ł����A3��15�������A���d�{�Ђ���������荞���Ƃ������ł��B�����ł̌o�܂��W�҂͌���ł��薾�炩�ł͂���܂���B
�@���\����Ă͂���܂��A3��14���̐[��A�C�]�c�o�ώY�Ƒ��̂Ƃ���ɐ����В�����d�b������A�u���̌��ꂩ��Ј���P�ނ��������v�Ƃ̐\�����ꂪ����A�C�]�c��b�͑����ɋ��ہA���̌�Ăѓ������e�̓d�b���}�슯�[�����ɂ������Ƃ̂��ƁA���̂��Ƃ��������̎��ɒB���A�����̍s���ɂȂ����炵���B
�@�������́A���d�{�Љ�c���ŋ����ԓ��d�����̑O�ŁA�u�P�ނȂǂ͂��蓾�Ȃ��A���k�n������ł��Ă��܂����A���d����ł���v�Ǝ���𖽂������A���͓̕����@�l�K�e�B�u�Ș_���ŕ�ꂽ���A�Ƃ�ł��Ȃ����ƂŁA��@�Ǘ��̏d�含�𗝉��ł��Ă��Ȃ��B
�@����C�������͊��ɐ�����サ�Ă��邪�A�ݐE���͎c�O�Ȃ���ᔻ���W���������t�ł������A���A���������̈�_�͍ō��̔��f�ł���A���{���~�����ő�̌��тƌ�����B
�@���̎����͌��ꂩ��v�����������̂��A�{�ЃT�C�h�����̔��f�Ȃ̂��A����Ȃ����A�g�c�����͍�Ƃ��p�����邱�Ƃ�錾���u�t�N�V�}�E�t�B�t�e�B�v�̐擪�œ˂��i�ނ��Ƃ𐾂��Ă��邩��A�{�Ў������̔��f�Ȃ̂��A�В��A��̓ƒf�Ȃ̂��A�W�҂͒��ق����܂܁A�����В��͂��̗l�Ȑ\������͂��Ă��Ȃ��ƁA��������S�ʔے�A�^�����M�̒��A���̌�A�������F�В���3��16���`21����5���ԐS�J�ɂ��̒��s�ǂ�i���A���d���ɐݒu���ꂽ���q�ً͋}���{�������O���Ă����B���{�Ɠ��d�̊Ԃŗ����グ��������ꌴ�����̓����{���̕��{�����߂Ă������A13���L�҉�ɗ����������͎p�������Ă����B3��29���A�s���̕a�@�ɋً}���@������30�����d���甭�\���������B
�@�̒��s�ǂ͍������Ƃ߂܂��Ɣ��\���ꂽ�B����̑��w���͏�������Ƃ�A��30���̋L�҉�Ōo�܂���������B
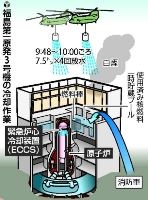
�@���d�{�Ђɏ�荞��ŁA���d�����͗���ɐ��炸�A�Ɣ��f�����͂���Ȍ�A���@���璼�ږ�p�����Ȗ��߂��ł��B
�@���̌���֎��q���̑S�ʓI�ȏo���A�e�s���{���m���ɏ��h���̏o���v���A
�@15���ߑO11�����u20�`30km�����̏Z���ɉ��������w���v
�@���a30km�̏��̔�s�֎~��
�@15���@�k��h�q��b�A�����S�������A���d�����ɂ�鋦�c�ɂ��w���R�v�^�[�����ɂ�������팈��B
�@���������f�����ŏ㕔��������сA�R���v�[���֒��ځ@������ł���悤�ɂȂ�A�w�������X���Ԃ牺���āA�R���v�[���ڂ����ĕ���������A�������A�ߔM���Ă���R���_�֒��ڐ����|������A�����C�����̕|�ꂪ���������A���̂܂ܕ��u����A�ԈႢ�Ȃ������g�_�E���ɂȂ�A�n����h�����߂ɂ͂��邱�Ƃ����Ɣ��f���A���s�����ӂ����B
�@�h�q��b�����q���x���������n���w�����ł���A���k���ʑ��ČN�˗����ɉ��߁A��������w���ɂ����������{�ƂȂ����B
�@���ォ��̕����̂��ߎ��q�����h�Ԃ̏o���A���㎩�q���������ꕐ��h�������̔h���Ŋj����A���w����ɂ�鉘����������C���Ƃ��镔�����o�������B
�@3��16��������ꌴ���A3���@�̌������甒�����オ��A����厖�̂��A�Ƌْ����܂������A����͐����C�ŁA3���������ŕۊǂ��Ă����A�g�p�ς݊j�R�������v�[���̗�p���z����~���A���ʂ��������Ďg�p�ςݔR�����I�o���A����M�ɂ�鐅���C�ł�����A���ː��Z�x�����������C�����o����Ă������ƂɂȂ�B
Q�F������ꌴ�����̂Ŕ�Q�g���h�����߁A�O������̎x���ł��鎩�q���A���h���A���̑������̐l�B������ɓ�������A���܂������@�I�����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł����H
A�F���q���@���݂Ă݂܂��B��̍�_�E�W�H��k�Ў��ɂ́A�ЊQ�~���Ɏ��q���h�����啝�ɒx��Ă��܂��A�傫�Ȕ������N����܂����B����͓����ЊQ�h���v�����Ȃ�����o���o���Ȃ��K��ɐ����Ă���A�n�������̂���͏o���v���Ȃ��A���R���t�A�����͊�@�Ǘ������Ȃ��A�o���o���ɓ����Ă�����ɍ������A�S��������炸���̈Č���R�c���Ă����Ƃ����厸�Ԃ������A�O��I�ɔᔻ���ꂽ�̂��_�@�Ƃ��Ď��q���@����������ЊQ�h�����啝�ɏo�����Ղ��Ȃ�܂����B
�@�ЊQ�h���F�n�k�A���Q���̑�K�͂ȓV�ϒn�ق�A��ʂ̎����҂̔������K�͂̎��̓��̊e��ЊQ�ɑ��ċ~����\�h�����Ȃǂ̑Ή��ɑ����E�����ꍇ�A���C��̎��q��������h�����A���̑g�D���Ȃċ~���������s���A�̂��ЊQ�h���ł��B
���@�ߖT�h���i���q���@��83��3���j
�����⎩�q���{�݂̋ߖT�ōЊQ�����������ꍇ�A�����̒���������h�����Ă��邱�Ƃ́A�s���{���m���̏o���v���̕K�v�͂Ȃ��A�����̒��̖��߂����ł悢�B
���@�n�k�E�ЊQ�h���i���q���@��83����2�j
�n�k�Ɋւ���x���錾���o����ۂɒn�k�ЊQ�x���{��������v�����ꂽ�ꍇ�ɏo������B�@���̏ł̏o���̎��т͖����Ȃ��B
����̌������̂ɏo�������͖̂k��h�q��b�A���������A���d�����Ƃ̋��c�ɂ��փ��R�v�^�[�����̏o���A���h�Ԃ̏o���ƂȂ����B
���@���q�͍ЊQ�h���i���q���@��83����3�j
���q�ً͋}���Ԑ錾���o���ꂽ�ہA���q�͍ЊQ���{���̗v���ɂ�蕔�����h�������B���CJCO�ՊE���̂���1999�N�i����11�N�j�ɐ��肳�ꂽ���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�Ɋ֘A���Ēlj����ꂽ�B������ꌴ���ł͌��q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�Ɋ�Â��h�����ꂽ�B�h�������́u���㎩�q���������ꕐ��h����v�B2008�N�n�݁A��ʌ���{���Ԓn���ɂ��镔���ŁA��200���̑����ō\���������ꕔ���ł��B
����Ƃ���͈̂������킪���ꂾ�ƌ����Ӗ��ŁA�u���ꕐ��v�Ƃ́A�j����A��������A���w���퓙���w���A���̕���ōU�����ꂽ�ۂɂ́A�������ꂽ�n�悪����u�h��v�A�܂艘�������Ɋ��镔���ł��B�@�������̂ł͏��߂�80���̑������o�����āA�ł��댯�Ȍ��ɓ����Ċ��Ă��܂����A���͂̕Ȃ��A�}�X�R�~�͖��������悤�ł��B
�@���q���@��̂��̔C���ɂ����ẮA��h�q��b�Ȃǂ̎w�����߂��K�v�Ƃ���A�s������������������Ă���܂��B
�@�ЊQ�h�������͗�O�Ƃ��āA�ЊQ�h���̗v���͓s���{���̒m���̑��A�C��ۈ��������A�Nj�C��ۈ��{�����A��`���������A���n�x�@�������v���ł��܂��B
�@�܂��A�L���ʐM���r�₦���A���n���������Ă��ĊW�@�ւɘA���ł��Ȃ��ꍇ�́A���ڎ��q���ɔh���v���A�Ⴕ���͎��q�����Ǝ��ɔ��f���ďo������̂�����h���ŁA��ɓs���{���m���̗v������Ηǂ��Ƃ��ꂽ�B
�@����h���́A���Ԓn�i�߂ł���i�����������j�̎��q���̔��f�ŁA�o���𖽂��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B
 |
 |
�@����̓����{��k�Ђł́A���k�e�n�ɒ��Ԃ��Ă��鎩�q���ł́A�e���Ԓn�Ƃ��A�n�k����15����ɂ͏o���������߁A30����ɂ͏o�����Ă���܂��B
 |
�@�e�s���{���̏��h���A�x�@���̔h���͓��t�̗v���ɂ��A�e�s���{���m���ɂ�鉺�߂ɂȂ�܂��B
Q�F�w���R�v�^�[�ɂ�����������킪�s���ATV�ŕ�������Ă��܂������A�ǂ�Ȍ��ʂ��������̂ł����B
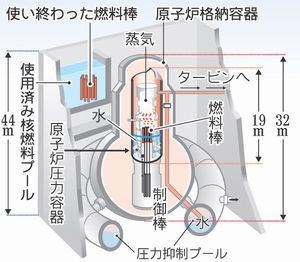 A�F�ړI��3�������ɂ���u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�ւ̗�p���z����~���A����M�Ő����������Ă��܂����A���̗�p���⋋�Ƃ��Ă̕��������A�n�ォ��̕������ł��B�����đ��̌����ɂ��������܂����B
A�F�ړI��3�������ɂ���u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�ւ̗�p���z����~���A����M�Ő����������Ă��܂����A���̗�p���⋋�Ƃ��Ă̕��������A�n�ォ��̕������ł��B�����đ��̌����ɂ��������܂����B
�@�o�����߂����A���㎩�q���E���w���R�v�^�[�c�i��t���؍X�Ê�n�j�w��2�@���Q���\�肳�ꂽ���A���̑O�ɒ�@�Ƃ��āA16���ߌ�A���̌�����̕��ː��̑�������{�������A���������\���90m���877mSv/h�̍��Z�x�ŁA��g���̔픘�����O����邽�A���̓��͒��~�B
�@��17���A�z�o�����O���Ă���_�����߁A�����^�����O�̌��ʁA1�@40�����v���������̗\�����~�߁A��s�𑱂��Ȃ��瓊�����A���������s���[�g��ݒ肵���B
�@������̑؋Ԃ͌v40�������x�A2�@�����݂Ɍv4����������Ƃ��ČߑO9��48���@3���@�̃v�[���Ɍ����ĕ��������A�v4�����ČߑO10���I���B
 |
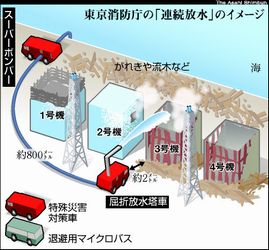 |
�@�u��̏��ցv���ƊO�����f�A�͚}�ΓI�ɕ����A�����ϋl�܂������ő��ɕ��@���Ȃ��A���Z�x�̕��ː��ʂɉ�������Ă�����֔�э���ł����Ȃ���Ε��������ł��Ȃ���a�̌��f�ł���A����ɂ���Ă���Ə��N���̂�����A�O���̃��f�A����ƁA����ɕ֏悵�đ����A�����ł����A���ӔC�Ȗ쎟�n�͉����ɂł�����̂��B
�@(��̏��ցA�Ƃ́A���Ăł͉��̖��ɂ������Ȃ��A�Ƃ����Ӗ�������B)
�@�����āA���ォ��x�����@�����A�f�������p�̍��������ԁA���q���̏��h�Ԃ��������J�n�����B���������������Ԃ̓f���p�Ȃ̂ŁA��������Ă̕����ɂ͓K���Ȃ������B
�@18���@�O���q���@���h�Ԍv6��A�v40�g�������A�ČR���h�ԑݗ^���c�͊֓d�H�E��2�g�����������B
 |
 |
Q�F�O������̕������̐�����3���@�̎g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���ɒ����ł��ā@���N�܂����B�悩�����ƃz�b�g���܂����B�ł�3�������̏㕔���j�ꂽ����㕔���ނ��o���ɂȂ�A�O������̕������\�ɂȂ����̂ł���A�������������݂�������ǂ��Ȃ�܂������H
A�F�m���ɂ��w�E�̒ʂ�ł����A���̓_�Ɋւ����ׂ܂������A���Ƃ̉���͂���܂���B�f�l������ɑz�����邱�Ƃł����A3���@�́u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�͌����̂Ȃ��ɂ���A���q�F�Ƃ͕ʂɂ���{�݂Ō����̏㕔�ɂ���܂��B
�@�R���_�͌��q�F�̒��ł̊j��������ŔM�G�l���M�[����o�������A��3�N�Ŏg�p�ς݂ƂȂ�A�V�����R���_�ƌ������܂��B�������Ď��o�����R���_���u�g�p�ς݊j�R���v�ł����A����M���o�������܂�����A������p���Ȃ���Ȃ炸�A�u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�ɓ���ė�p�����z��������M���p����̂ł����A���ꂪ�����ԂŖ�3�N������̂ł��B���̊ԗ�p���̏z���K�v�ł����A����̎��̂̂悤�ɗ�p���̏z����~����A����M�ɂ��v�[���̐��͏������Ă��܂��A�R���_�͘I�o���A�ň������g�_�E���̉\��������܂��B
�@�ł�����K���ɂȂ��ĊO������̕����ɍS�����̂ł��B�f�l���l������ł��܂��̂́A�����̏㕔���j�ꂽ����O������̕������\�ɂȂ����B�������f�������Ȃ��������j��Ȃ�����������͕s�\�A���͌����̕��Ȃ�������A�����̕K�v�͂Ȃ������̂��B�������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���q�F�Ƃ͕ʂɃv�[���ł̒����ł���A����������̂Ȃ��ނ��o���ł�����A����M�Ő��͏����A�R���_���I�o���A����M�ŗZ���͂��肤�邱�ƂŁA���̌��ʂ̔�Q�͂ǂ̂悤�ȃ��m�Ȃ̂��B���邢�͌�����1�`2m�̌����R���N���[�g�̕ǂŕ����Ă��܂�����A���݂Ȃ�Ε��˔\�͓����ŗ}����ꂽ�̂��B�܂��́A�����̊O������v�[���ɒ��ڒ����ł���{�݂��������̂��B�f�l�ɂ͔���Ȃ����Ƃ���ł��B���Ƃ̉����u�����ĉ������B
Q�F�g�p�ς݊j�R���͂ǂ̈ʂ���̂ł����H
A�F���d���\�ɂ��܂��ƁA3���@�@514�{�B�@4���@�@1,331�{�B�@5���@�@946�{�B�@6���@�@876�{�B�@���p�v�[���@6,375�{�B�@�������ł��B
Q�F�����͓d��������p���z�V�X�e���̍ĉғ��܂ő������̂ł����H
A�F3��19���@���̓�����O�����h���������{�i�I�ȕ�����킪�J�n
�@�������h���n�C�p�[���X�L���[���i���h�~���@�������j139���A���ܕ������ԁA����ЊQ��ԁA��^���w�ԁA�n�V�S�ԁA��Ǝԓ��@�v30��Q���A���ܕ������Ԃ�2��Ő���⋋���钆�p�Ԃ�A���ŘA������3.8�g������������Ƃ́A�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���ւ̗�p���z�V�X�e�����ĉғ�����܂Ōp�����A�Z����h�����Ƃɐ������܂����B
�@�ߑO0�����@�������h���n�C�p�[���X�L���[��3���@�ւ̕����J�n�A20���̕����Œ��~�B3���@����1���ԓ���3,181�}�C�N���V�[�x���g�ϑ�(�P�ʂɒ��ӁA�}�C�N���A��Sv/h)�@
�@�ߑO4��22���@5���@�̊j�R���ۊǃv�[���̗�p���z�@�\������
�@�ߌ�2��5���@�n�C�p�[���X�L���[��3���֕����ĊJ�A�A��7���ԗ\��
�@20���@�ߑO3��40���܂�13���ԕ�����������
�@�ߌ�7���@1�A2���@�ւ̔z�d�Ռ��ψ���ƊO������̑��d���Ɛڑ���Ɗ���
�@�ߌ�10���@6���@�̊j�R���ۊǃv�[���̗�p�@�\��
�@�ߌ�11���@3���@�t�߁A1���ԓ�����2828�}�C�N���V�[�x���g�i��Sv/h�j
�@20���@�ߑO8��20���A���C�q�����h��11��ɂ��4���@�ւ̕����J�n�@�@
�@�ߌ�4���@���d�����O���ƌq������2���@�̓d�͐ݔ��Œʓd���m�F
�@�ߌ�6�����@���q�����h�Ԓn�ォ��4���@�֕����J�n�A�A��6���ԗ\��
�@�ߌ�9�����@�ً}���h������(�������h���j3���@�֘A��6���ԕ����\��
�@21���@�ߑO4���@3���@�ւ̕����I��
�@3��21���@�ߑO6��40���A���q���ɂ��n�ォ��4���@�֕����J�n
�@�ߑO8��40���@4���@�ւ̕����I��
�@�ߑO11�����@5���@�̔z�d�Ղ܂Ŏ�d�A6���@�ɂ��d�C���������ԂɂȂ�
�@�ߌ�6��20�����@2�����q�F�������甒���オ��B
�@22���@�ߑO8���A�d��������ƊJ�n
�@�ߌ�3��10���@�ً}���h������3���@�֕����J�n�A�ߌ�4���I��
�@�ߌ�5��17���@���d�͐��R�������@(��������A���j���g��4���@�ۊǃv�[���֕���
�@�ߌ�10��43���@3���@�̒������䎺�ɊO���d������������A�Ɩ��_��
�@3��23���@�ߑO10���@���d���R�������@��4���@�̕ۊǃv�[���֕���
�@�ߌ�4��20�����@3���@���獕�����オ��3�A4����ƈ��ޔ�
�@3��19���`22���@�@�������h���@�@�@�@�@�Q���l���@139��
�@3��19���`22���@�@���s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@53
�@3��22���`24���@�@���l�s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@67
�@3��24���`26���@�@���s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@36
�@3��26���`28���@�@���É����h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@34
�@3��29���`30���@�@���s�s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@40
�@3��17���`4���܂Ł@���㎩�q���A�C�㎩�q���A�q�q���̏��h��
�@�������I��
�@�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���ւ̗�p���z�V�X�e�������āA����ɗ�p���o����悤�ɂȂ����B�i3��20���O���d���ƌq���������A���̌�����d�H�C�����K�v�������j
Q�F���q�F���ւ̗�p�������͂ǂ��Ȃ��Ă����̂ł��傤���H
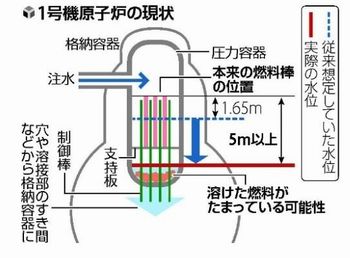
A�F1�`3���@�̌��q�F�͗Z�����Ă��肱��ȏ�̗Z���͖h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�O����������֒ʂ���p�C�v���g���ĊC���̒������s��ꂽ�B�������ȒP�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B
�@���q�F�͈��͗e��̒��ɂ���A���͗e��Ɩ��̒ʂ�A�e��̒���70�C���Ƃ������̐������͂Ȃ̂ł��B�O����1�C���ł�����A70�C���̒����𒍓����邽�߂ɂ́A70�C���ɑΉ��ł��鍂���|���v���K�v�ł��B�]���ď��h�Ԃ̗͂ł͐��������瑗���Ă������o���Ȃ��̂ł��B
�@�ł͈��͗e��̋C����������悢�ł͂Ȃ����A�Ƃ͂����Ȃ��̂ł��B���̂Ȃ猴�q�F�ł�70�C����280�x�̍����ŕ�������悤�v����Ă��܂��B
�@����1�C���ɉ�������A100�x�ŕ������邱�Ƃ͏펯�Œm���Ă���ʂ�ł��B
�@�]���ėe��̒���1�C���ɂ�����u�ԓI�ɕ������A���������璍�����Ă����肸�A���̐��������C�������o���A���˔\����юU���Ă��܂��A�����C�����̊댯������܂��B
�@�ł������ɏo���Ȃ����Ƃł����A���͂����������Đ������A���x�������Đ��̏����𑗂点��A�ƌ��������Ƃ��J��Ԃ��R���_�̓��M���M���̐���ۂ悤���삵�����悤�ł��B
�@�����Ă���ƊO���d���ł���V�����ϓd���Ɛڑ��ł����̂��A���̂���9���ڂ�20���ŁA����n���A�@�킪�C������A���̈��̉������ӂ����A���ʂ��m���߁A����Ɠd�����m�ۂ��āA���}��ƂȂ����p���z�@�\������ɂ͍X�Ɏ��Ԃ����������B
�@�����̓����́A�c��ȉ������̖��ł����A����͕��ː��ʁA���˕����A�����y�A�����̂���܂����̒ɂ��Ȃ������ł����A�������߂ĉ�����܂��B
Q�F�O���d�����r���������Ƃ͔���܂������A�ǂ����ĕ�����9���Ԃ��v�����̂ł����H(3��20���ߌ�4���O���d���ƒʓd�m�F)
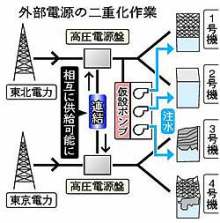
A�F�n�k�œS�������A���d�����ؒf����O���d�����r�������B���d���͑S�ĒÔg�ʼn�ł܂��͐��v�B�]���ĊO���d�͂̉ɑS�͂�s�������Ǝv���B
�@�S�������Ē����킯�ł͂Ȃ��̂�����A���}���u�Ŏ�芸���ʓd���邾���̍H��������قǂ��������̂́A�n�k�ŏ�Q�������肷���čH������s�����̂��B���˔\�����ŊO�ł̍�Ƃ���������̂��B
�@��������͒n�k�A�Ôg�Ƃ����Ɠ����悤�ɔ�Q�������A��ՓI�ɘF�S�Z���Ƃ����ň��̔�Q�͖Ƃꂽ�B���̈Ⴂ�͑S�d����r���������A���͐h�����Ĉꕔ�d���������Ă����Ƃ����K�^�ɂ����̂��A�X�Ȃ�K�^�͑��ɂ͓����d�͂Ɠ��k�d�͂���̓�n�����������A���͓����d�͂����̈�n���������B����͐v�̒i�K�Ō��܂��Ă������������A��@�Ǘ��̔F��������Αo���̓d�����m�ۂ��Ă��邾�낪�A���̔F���͂Ȃ������B�����A��ꌴ���ɂ͓��k�d�͂���̓d�����������B����͌������݊��Ԓ��A�n�����k�d�͂���H���p�̓d���Ƃ��ĕ~�݂������̂ŁA�H��������͂��̂܂ܕ��u���Ċ��p�͂��Ă��Ȃ������B
�@���̌�A���̎��ɋC�Â����k�d�͂���̍H���p�O���d���P�[�u���ɐڑ����悤�Ƃ������A�e�ʂ��s�����Ă���A���p����ɂ͎��Ԃ�������Ƃ��āA�Ăѕ������ꂽ�B
�@�e���V�Aif�f�͋�����Ȃ����A�O���d���Ƃ��ē��d�̐V�����ϓd������̌n���ƕ���œ��k�d�͂̌n�������Ă����Ȃ�ň��̘F�S�Z���A���f�����A���ː������̕��o�͉���o���������m��Ȃ��B
�@����ɂ�����A���S���ӂ������������������B10��23�������A���d��������ꌴ���̑S�d���r����h�����߁A2006�N��1�`6���@��d�C�P�[�u���Ōq���œd����Z�ʂ��������ǍH�����������Ȃ���A�Z�p�I�ȏ�Q�𗝗R�Ɍ��������o�܂��������炵���A���̓����ɂ͊��ɒ�ϒn�k�A�Ôg�����炩�ɂȂ��Ă���A���R���d�����ł͌����ۑ肾�����̂ł��傤���A�����I�Ȍ����܂ł͎����ĂȂ����B
�@��ꌴ���ł�5�`6���@�݂͌��ɘA�g���Ă���A�B��c����6���@�̔��p�f�B�[�[�����d�@1��Ō��q�F�̗�p�͏o�����B���̌㉞�}�[�u�Ƃ��Ēn�ʂ����킹���d�C�P�[�u����1�`6���@�ƘA�q�����̂�4��25���A�����A06�N�̎��_�ʼn��ǍH���𐄐i���Ă���Ύ��͖̂h������������Ȃ��B
�@�����d�����ɂ��A06�N�A���R�ЊQ�Ȃǂœd���������ĉߍ����̂Ɏ��鎖�Ԃ�����邽�߂ɁA�d���ݔ�������v�悪����ꂽ�Ƃ����B
�@�\���̓쑤��1�`4���@�݂͌��ɓd�C�P�[�u���Ōq�����Ă���A�d�������L���Ă����B�k���ɂ���5�A6���@�̊Ԃł��q�����Ă������A1�`4���@��5�A6���@�̊Ԃɂ͌q�����Ă��Ȃ������̂ŁA��������ǍH���œS�������ēd�����ː݂���v��ł��������Z�p�I�Ȗ�������f�O�����A�Ƃ��邪�A���������Ǝv���͓̂d�͉�Ђ��Z�p�I���Ƃ����̂͂ǂ��䂤���Ƃ��A���Ђ̋Z�p�͂�ډ����Ă���킯�łȂ��ł��傤����A������Ƃ������Ƃ��B�D�掖���łȂ������A�v�͑z�肷��悤�ȑS�d���r���Ȃǂ��蓾��Ȃ��A�]�v�ȋ��͎g�����Ȃ��A���S�_�b���D�悵�Ă��܂����B
�@����ɓ��d�����͌��q�͖{�����u���q�͑��v�ƌĂԕ������q�͔��d���̌��݂����߂��Ƃ��A���q�͂̐��Ƃ͂��Ȃ������B���͔��d�ƉΗ͔��d�̓d�͉�Ђł���A���̓r�̐��Ƃ͋��Ă��A���b���̊Ԃ͐�̌R�����q�͂̌������֎~�A��O�̌����{�݂͑S�ĊC�ɕ����������B
�@��w�̍H�w���ɂ����q�͉Ȃ͂Ȃ������̂�����A�����I�ɂ����Ƃ͋��Ȃ������B
�@������A���ݓ����͂���ƌ��q�͉Ȃ��J�u���A�����𑲋Ƃ�������̎�l�ɗ��炴��Ȃ������B���̂������X�ƌ��݂��ꌴ�q�͊֘A�Z�p�҂������Ă��A���q�͕���Ƒ��̕���Ƃ̐l���𗬂��Ȃ��A���邢�͎d�l���Ȃ������̂���������ꂽ����Ƃ��Č��q�͑����o���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@���q�͖{�����͐�ΓI�Ȍ����������A��A�В���M���Ƃ���o�c�w�Ƃ����ǂ����o���ł��Ȃ����悪�`������Ă�����܂��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@���{�o�ϐV���ɂ́u�č��̓d�͉�Ђɔ�ׁA���d�̌o�c�w�ɂ͌����̐��ʎ҂͂��Ȃ��A�ēd�͉�Ђł͌����̐��Ƃ��ō��ӔC�҂Ɠ����t���A�ɋ��Ĉӎu����ɐ[���W����Ă���B���d�ł͌����̐��Ƃ̑����͖{�Ђ��牓�����ꂽ�ꏊ�ɂ���v�Ƃ����L�����������B
�@���d���В��͖@�w�����o�ϊw�����A���d���ł��c�ƕ��A�������A��敔���L�����A�[�R�[�X�B11��В��������F�������߂Ď��ޕ�����В��ɔ��F���ꂽ�A����͒��т��s���œd�͏�����������ߏ��߂Č��ɓ������z�w����������r��U�邤�O�ɍГ����Ă����B12��̈����В��͊�敔�o�Ō��ɖ߂����B
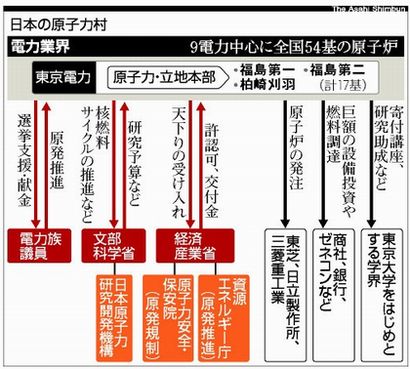
�@��͎В����ތ�̃|�X�g�����瓌�d�g�b�v�̕z�w�ɂ͑ւ��͂Ȃ��B��������Ɛ��͕����Η͕���Ƃ̃o�����X������A���ʂɌ��q�͕��傾�����d������킯�ɂ����Ȃ��A�Z�p�I�Ȃ��Ƃ�����Ȃ���A���S��̏d�v���̔��f���݂��Ȃ�A���z�������o���Ă��܂����B
�@����ɂ�����́A���̏\�N�Ԃ́A���̂ɂ���~�A�����B���A�B���H��A�������������ݏ������X���d�ɓZ���X�L�����_�������o���A�o�c�w�͂��̑�ɒǂ��A�{���̋Ɩ����a���ɂȂ��Ă��܂����̂��H
�i����������GE����̔h���Z�p�҂��A���̍ۂɓ��������������A���ݏ����Ă��܂����j
Q�F������ꌴ�����̂͌��ݎ����Ɍ����ő���̓w�͂����Ă���ł��傤���A����������A���d�Ƃ��Ă͂ǂ̗l�ɏ�������v��ł����H
A�F3��30���A���d�̍���̕��j�\�������A���̂��N����1���@�`4���@�̌��q�F�͔p�F�ƁA���d���������肵���ƁA����������\�����B
�@���̌�19�����o���Ă���Ȃ̂́A���̊ԂȂ�Ƃ��Č��ł��Ȃ����A1��3,000���~������R�X�g���o���炷��Δp�F����ɂ��S�O���ē��R�����m��Ȃ��B
�@�������A���̃R�X�g���o���������̂̌����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l�����ׂ����B
�@�p�F�̗v���Ƃ��ċ������̂́A�j�R���y���b�g�̗n���␅�f�����ɂ��ݔ��ɒ����������������Ƃ�p�F�̗��R���Ƃ����B
�@�v�撆��7���@8���@�̌��݂𒆎~����B
�@�_����������5���@�A6���@�̌��q�F�͗≷��~��Ԃɂ���A���M�@�\�͈ێ�����Ă����̂ő����͎Ă��Ȃ��A�Ƃ��Ă��邪�A���d�Ƃ��ẮA�܂��ڍׂȒ��������Ă��Ȃ��̂ŁA���ʂ͈��S�ȗ≷��~��Ԃ̈ێ��ɑS�͂�s�����B
�@���̂�1�`4���@�̌��q�F���̗�p����ː������̔�U�h�~�����S���m�ۂɗv�����p�Ƃ��āA4,262���~�B
�@��ꌴ����5���@�A6���@�A����̌��q�F�̈��S�ȗ≷��~��Ԉێ��̂��߂̔�p�Ƃ��āA2,118���~�B
�@���d��1���@�`�S���@�̔p�F�Ɋւ����p�A2,070���~�B
�@7���@�A8���@�̑��v�撆�~�ɔ�����p�A393���~�B
�@�ЊQ���ʑ����̌���ł̌��ϊz���v1��175���~�B
�@�@������ꌴ���p�F�܂ł̍H���\
���@�g�p�ςݔR���v�[������̔R�����o���E�E�E�E5�N��
���@���q�F�̎g�p�ς݊j�R�����o���E�E�E�E�E�E�E10�N��
���@�����̉�̂܂ł̌��ʂ��͊ϑ��Ƃ��āE�E�E�E���\�N��@
���@����̋Z�p�͋����Ɍ��ʂ���葁���Ȃ�\���͂���B
���@���q�F�≷��~��A�x�����k���E������T�d�Ɍ�������B�i�N����1���܂Łj
���@�Z�p�J���A���q�F���̕��ː��ʂ������邽�߂́A���u�����Z�p�̊J���i���{�b�g�j���o�����R���A���ː��������̔p�����̏����Z�p�A�܂��͕������ߋZ�p�B
���@�p�F���̑��@���ː������ɉ�������Ă��镨�̂̍ď����E�������߁A���ߗ��ē��̌����ێ����Ă��鍑���܂߂đ����I�Ȍ������K�v�ŁA���{���w������K�v������B
���ケ�̕���ł͐��E���̌����ۗL�����ď����A�ۊǁA�p�F���̑�����Ȗ��ɒ��ʂ��邱�Ƃ͖��炩�Ȃ̂ŁA���̋@��ɂƂ��Ƃ����d�ˁA�o����Ώ����\�͂Ő��E�����[�h���錴��������i���ɂȂ��Ăق����B
Q�F���̌���Ŋ��Ă���l�B�̔픘�̐S�z�͂Ȃ��̂ł����H�@��Ɗ��ɂ�������ː��ʂ̋��e���E�������ĉ������B
A�F���q�͔��d���ł̍�Ƃɂ����鍑�ۓI�ȕ��ː��픘���E��5�N�ԕ��ςŔN20�~���V�[�x���g�ł���A1�N�Ԃ�50�~���V�[�x���g���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�����J���ی쒡�ً͋}���ɑΏ�����v���́u�������Y��ی삷�邽�߁v100�~���V�[�x���g�A�u�����̐l�X�̐����������ی삷�邽�߁v250�~���V�[�x���g�܂ň����グ�����e����B
�@�䍑�ł́A���̂ɒ��ʂ����ۂ̍ő勖�e�ʂ�1�N��100�~���V�[�x���g�Ƃ��Ă������A2011�N3��15���A�����J���Ȃ͕�����ꌴ�����̂̏��ӂ݂āA�����250�~���V�[�x���g�܂ň����グ���B���ꂪ���݂̊�ł��B
�@�������A���̕��ː��ʂ͓˔@�����Ȃ邱�Ƃ�����A�펞������������A���e�͈͂���x�����瑦���ɔ���ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@2011�N3��15�����A1���ԓ���1,000�~���V�[�x���g�����o�����u�Ԃɂ́A��ƈ��B�͈ꎞ�ޔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ꂪ�ő�l�ł��̌�͋N���Ă��Ȃ��B
�@���ː��ʂ͒����ԗ��тĂ���ƌ��N�ɉe�������邪�A�u�ԓI�ȃ��m�͉e�����Ȃ��B
�@250�~���V�[�x���g�̕��ː���1�������тĂ����ꍇ�A�ɂ���Ă͑����ɒ�������ꍇ������B
�@���̒���́A�f���C�A�H�~�s�U�̏Ǐ�B�����A�����p�ߋy�B���ւ̃_���[�W������B�@��ʓI�ɂ́A1�`3�V�[�x���g�̃��x���ł͂��傫�ȉe���������C������Ȃ�\��������B3�V�[�x���g����Ɖe���͐[���ƂȂ�A�畆�̔�����o���A���B��Q�Ȃǂ������A�����A���Â��{���Ȃ���ň��̏ꍇ�@���Ɏ���ꍇ������B
�@5�V�[�x���g�ȏ�ł���A���Â��Ă��m���Ɏ��Ɏ���B
�i�P�ʂɒ��ӂ��ĉ������B1�V�[�x���g��1,000�~���V�[�x���g�A5�V�[�x���g��5,000�~���V�[�x���g�B�@���[�g����,,,1/1,000���~���im�j�B�~����1/1,000���}�C�N���i�ʁj�j
�i���Ԃ̒P�ʂ��v���ӁA1���ԁA1���A1���A1�N�j
�@������ꌴ���̎�����ƂŁA10��4���܂ł�3�l�̍�ƈ��̎��S���m�F����Ă��܂����A�픘�ɂ�鎀�S�ł͂Ȃ��A���a�����������Ɣ��\����Ă��܂����A3�l�Ƃ����̌㌻��̗p����ē����͂��߂���ƈ��̕��̂悤�ł��B
Q�F���{���{�͏����B���Ă���̂ł͂Ȃ����A�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƊO�����f�A����啪�������ꂽ�悤�ł����A�z���g�ɉB���Ă����̂ł����H
A�F�܂��ɒʐM�q������ŁA���E���ɑ���ꂽ���܂����Ôg�̉f���ɁA�e���r�̑O�ɓB�t���ɂȂ�A���E���ɏՌ����������B����ɑ����Č����̎��́B�Ď��q���ɂ�萅�f�����Ŕj�ꂽ�����̉f���ɁA�����C�����A���q�F�̔����Ɖ��߂��Ă��܂�������A���k�n���E�֓��n������ł��邾�낤���f�����悤�ł��B
�@������ݓ��O���l�͉��ɂƍ��O�ւƔ��Ă������B�ݓ��e����g�فA�̎��ق͑S�͂������ē��k�E�֓��ݏZ�̎������ɓd�b�ʼn��x�������Ăт������B
�@����͍ŏ��A�����J���{���A������������80km�����ɏZ�ރA�����J�l��ΏۂɌ��O�����A��g�ق�ʂ��ĘA�����n�߂����Ƃ���A���̍ݓ���g�ق��玩�����ɑ���Ăɔ��w�����o�����̂ł��B
�@�O�����{��25�N�O�̃`�F���m�u�C���������̂̔ߎS�����O���ɂ���A�����̃\�A���{�͎��̂����\�����A���ː��������������ɏ���ĔE�т���Ă������|�A�ŏ��ɋC�t�����̂́A�y���������ꂽ�X�G�[�f���̌����ŁA�Ď��p�̃K�C�K�@�[�J�E���^�[�̌x����A���[�^�[�̎w�j�͒��ˏオ�����B
�@�W���͓����q�F�̎��̂��Ƌ����Ē����������A���̒���Ȃ��A���̂������[���b�p�e�n�ɂ��錴���A�������A��w���ł��K�C�K�@�[�̌x�A���[�^�[�̋}�㏸�A�呛���̂����Ɋe�n�̕��ː������̔Z�W�A���̕��̕�������T��A�����_�̓\�A�������Ɠ��肵�����A�\�A���{�͒��فA�ܘ_�}�X�R�~�⒲���c�̓����͔F�߂Ȃ��A�����A��ނ͏o���Ȃ��A�]���āA�����Ŋϑ����Đ������邱�Ƃ����o���Ȃ������̂ŗ]�v�ɋ��|���������B
�@���̌��ǂ����邩�猴�q�F�����ɊS�����܂�A���x�̕�����ꌴ���́A�����{��k�ЂŒn�k�A��Ôg�Ő��E�������ڂ��Ă������ő����ċN�������߂ɐ��f�����̉f���𐢊E�������߂Ď����̂ŁA�����C�����ɂ�錴�q�F�{�̂̔����Ɗ��Ⴂ���A�`���C�u�C���̔�����1�@�ł������A���������͂R�@�ғ����Ă���A1�������A�R�������A�����A�Q�������������オ��Ƒ����A���E�����`�F���m�u�C�����y���ɑ傫�ȏd�厖�́A�ɒ[�Ɍ������̐��̏I������킹��܂ł������B
�@�]���āA���{���M�͐̕��܂����ߎS�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�A�v���Ă������A�ۈ��@�̔��\�͉��̂����{�l�������Ă��Ӗ��s���ȃV�h�����h���ȉ����A�O���l�L�҂ɂ͗����ł��Ȃ��L�҉�A�}�슯�[�����̐��{���\������͂悢���A�o�߂����̔��\�ʼn��s�����Ȃ��A��������b�ʖ�͂����Ă��A�����ʖ�͂Ȃ��Ў藎���̋L�҉�ł����B
�@������A�ۈ��@���O���l�����̋L�҉������Ă���ACNN�ł��̒��p�������B
�@�ۈ��@�̐����R�c�����S�����Ă���A�������������₪����܂������A����܂�����̈��������ɐ���Ȃ��悤�ȉ����ɏI�n�A�L�҉�ɗՂL�ҒB�͉����Ă����悤���B
�@����Ɍ���Ɏ�ނɍs���Ȃ����ǂ������v�������������̂ł��傤�B�L�҉�̌�ŁA��L�ҞH���A�{�Ђ�������ƌ@�艺�����L���𑗂�Ɩ�̍Ñ������A���\�����Ȃ��A�������o�߂����̕\�ʂ����ŁA����L�������Ȃ��̂ŁA���{���{�͉����d������B���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ�����͓̂��R�A�������̗l�ȋL���𑗂����悤���B
�@�������A���Ă̑�{�c���\�̂悤�Ȉӎ��I�ɋ��ӂ̔��\���������A�Ƃ������̓[���ł͖����ł��傤���A���Ȃ������Ǝv���B
�@�ŏ��̐��{���\�ł̓��x��4�����Ƃ��Ă��܂�������A�X���[�}�C�������̂��͒Ⴂ���炢���Ƃ����S���Ă��܂������A���̔��\�̓��x��5�ɂȂ�A����Ƀ��x��7�ƈ����グ����Ɣ��\���ꂽ�Ƃ��̓`�F���m�u�C���Ɠ������x�ƒm���ċV�����B
�@�e���r�Ō��q�͂̐��Ƃ�������Ă������A���ŗ�₵�Ă����Α��v�A�䍑�̋Z�p�͂������Ă���Ύ�������̂͋߂��ƁA���Ă������A���x��7�Ɉ����グ���Ă���͉���҂��ԑg��������Ă��܂����B
�@�O���ł̕ł́A���d�A���{���{�̐ӔC�Njy�̘_���������A���Ƀt�����X�E���f�B�A�͌������荞��ł����B���d�̃g���u���B���A�u�Ӗ��ƕs������10�N�v�A���̌�̌��ʂ��̊Â��A���{�ɂ͌��q�͂̐��Ƃ͂��Ȃ��A�Ƃ܂Œf���Ă���B�h�C�c�ł́u���̋��|�����v�u�����ɕ��ː��̉_�v�Ɣ����������悤�ȋL���������A���V�A�A�����A�؍������E�̃��f�A���������ĕ��͓̂��{���{�A���d�̌��ʂ��̊Â��A���ɉ��Ή��A�����݂̓����w�E�A�܂���萳�m�ȏ������Ȃ�A�����J���{�Ɏ�ނ��������m�����A�Ƃ̔���������������B
�@���{���{�̏�����B���̐^���͂ǂ̒��x�Ȃ̂��͕�����Ȃ����A�����̓��h�A���]��Q��|��ĉߏ��]���������炢�͂������悤�����A�܂��A���d���̂������o���ɂ���ł����悤�ŁA���̑O�ł�������ₖ��A�B���H��A�����̓������ݏ��������x����莋���ꂽ�O��������A���R���̌���������Ă��邾�낤�Ɛ�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�O�����f�A����͔ᔻ�I�ȕ����������������A����Ȃ��̂Ő��_�ő�U���ȋL�������ꂽ�̂��������B
�@��M�����Ȃ�����A���邢�͏��̌��ʁA�������ē��{�ɑ��鈫��������A�M�p�������Ă��܂������ƂɂȂ�B
�@�S�Ă̂��ƂɌ����邱�Ƃ́A���{�l�͏�M����肾�B

Q�F����������ꂽ�x�������Ƃ��čő�̊S���́A�����A���̂��A�{���Ɉ��S���ċA����������̂ł��傤���H
A�F���Ƃ����{���ʍ����̐l�ɂ��������Ȃ��������ł����A���x��7�̃`�F���m�u�C���ƃ��x��5�̃X���[�}�C�����̌��݂��q�ׂ܂��B
�@�`�F���m�u�C���F1986�N4���A�\�A(����)���݃E�N���C�i���a���̃`�F���m�u�C���ɂ��錴�q�͔��d���ō��������y���F4���F���˔@�����A���サ�R���₷�������Ђ̂���10���Ԃɂ킽�艊�サ�A���ː��������Ђ̏㏸�C���ɂ̂��Đ��烁�[�g���̏��ɒB���A�쓌�̕��ɏ���ăX�J���W�i�r�������܂ŒB���A���������ς���ċt�����Ɍ����������쉺���C�^���A�܂ŒB���A�����ȃC�^���A�Y���������ˉ����ŏ��i�ɂȂ�Ȃ������B
�@���̕��˔�Q�̓\�A�M�A���[���b�p�S�y�ɋy�B
�@�䍑�ł����ʂ̃Z�V�E��137�����o���ꂽ�B
�@���̎��g�U���ꂽ���ː�������250���e���x�N�����i�e����1���{�j�ƌ��ς����A���ی��q�͋@�ցiIAER�j�ɂ��ƁA�L���ɓ������ꂽ������400�{�Ɋ��Z���ꂽ�B
�@�������甼�a30km�����̏Z����11��6��l�͋������A���O�̎��Ӓn��ł��X�|�b�g�̍��Z�x�����n�悪����A�E�N���C�i�A�x�����[�V�A���V�A�̊e�n�Ŗ�40���l���ڏZ�������ꂽ�B
�@�����n��͖�14��5�畽��km�A�䍑�̖�4�����A���k�A�֓��A�k�C���������炢�̖ʐρA���̒n��ɏZ�ޏZ���́A��600���l�A�����ڏZ�n��͖�1������km�A���̖ʐςŁA��27���l�������ڏZ�����B
�@���̂���25�N�o�߂��܂������A���a30km�����͗�������֎~���p�������܂܂ŁA�����̌��ʂ��͗����Ă���܂���B
�@�������A�픘���邱�Ƃ����m��1���̐l�X��30km�����̌̋��A��܂����B�A�����]���邨�N���ɂ͓��ʂɋ������悤�ł��B�܂��������ɉB��Ă��Ĕ��Ȃ��܂Z�ݑ����Ă����l������悤�ł��B
�@�X���[�}�C�����F1979�N3��28���A�A�����J�E�y���V���o�j�A�B�ɂ���X���[�}�C���������Ń��x��5�̎��̂�����܂����B�X���[�}�C�����Ƃ����Ă��C�ɂ��铇�ł͂Ȃ��A�����ł����傫�Ȑ�̒��B������3�}�C���Ȃ̂ŕt����ꂽ���ŁA�����ɉ������^���q�F��2���A���̂�����1��c�Ɖ^�]����������A���̂��������A���p�F�S��p���u���蓮�Ŏ~�߂����߁A�F�S�㕔�̐����Ȃ��Ȃ�A����M�ɂ���ĔR���_���j���A�F�S�n�Z���N�������A�����ɂ���ė������������B
�@���a5�}�C���i��8km�j�����̏Z���͋������A���a5�}�C�����O�����߂��̃~�b�h�^�E���s�̏Z���͎�����Ƃ������A�唼�̎s���͔���14���l�������B
�@�A�����J�̏��E���w�Z�̐��k�̓o�X�ʊw�������ŁA�s�̉^�c����ʊw�p�Ƃ��đ����̃o�X�����L���Ă���A���e�ƒ�ŎԂ����L���Ă��邩��A�����̎ԗ����t���Ɋ��p��14���l�̔��͈�Ăɍs���A�s���͒����ɖ��l�ɂȂ����������B
�@���������̂͗����ł������A���S�m�F�̂���10����ɋA����������悤�ł��B

�@���̂��N�������q�F�͔p�F�ɂ��A���̌��q�F�͏B�ٔ����̉ғ��ĊJ�̔����čĊJ���܂������A�s���Ƃ̋���͌������A�s���ً͋}���ԊǗ�����ݒu�A���̎��ɔ����A�ً}���ꏊ�A��ʉ^���̃o�X�̉^�p���@�A�W���ꏊ�A���̎���{�ݓ��X�A���̂ɔ������������}�j���A�����쐬�A�ٔ����̗�����ŏZ���Ǝs�Ƃ̊Ԃŋ��肪�o�����B
�@���̋���̒������A���q�F�ғ��ĊJ�̏����ł����B
�@���̂��N�������q�F�����S�ɔp�F�ɂȂ�A���S�I���錾���ł��̂�14�N��ł����B
�@�x���ɋA�������w�܂萔���đ҂��Ă���̂ɓ������Ȃ��Ė{���ɂ��ƂȂ����B
�@�X�e�b�v2����������A�����͖��邢�j���[�X�����͂��ł���Ǝv���܂��B
�@�������邢�j���[�X�ł��B10��10���A�̈�̓��AJR����͋v�m�l�w�܂łł������A����ƍL��w�܂ŊJ�ʂ����B
�@�L�쒬��9��30���A�ً}��������悪�������ꂽ���A����������Ƃ͎n�܂��Ă��炸�A�����̑����͔��n����A���Ă��Ȃ��B
�@�c��s�ʋ�Ԃ͍L��`�j���̖�102km�A�،ˁ`�����Ԃ͌x�����ŗ�������֎~�A���`�j���Ԃ͕����I�ɉw�ɁA���H�������A�H���ύX�h�ƌ����h�̑Η��őS�Ă�������ԁA����S���ĊJ�ɂ͂܂��܂����Ԃ��|���肻�����B
�@�������ɂȂ��Ă��A���̎��_���珜����Ƃ��n�܂�Ƃ�����A�ǂ̈ʂ̍�ƗʁA���Ԃ�K�v�Ƃ���̂��A�A���悤�ȏZ���������̂͂��Ȃ̂��A�Ȃ�Ƃ��������܂���B
Q�F���X������Ă��ǂ����傤������܂��A�ǂ����Ă���قnj������ݗU�v�ɐϋɓI�������̂ł��傤���H
A�F���������W���Ă���̂́A�o�t�S����ł͂Ȃ��A���{�ōō��̌�������́A���䌧�̎ዷ�p���݈�сA�։�s���Ɋ��d�͂̌����Q��A���{���q�͌����J���@�\�́u����v�Ɓu�ӂ���v�i��̒��j�B�ዷ�p���ݎs�E���A���d�͂̔��l����3��A��ь���4��A���l����4����сA�o�t�S��10����������B �@���n���̋��ʓ_�́A�߂ڂ����Y�Ƃ��Ȃ��A�_�Ƃ���̂Ƃ��Ă����ȊO�ɓ��Y���Ȃ��A�o�҂��̏�K���A��҂̗��o�A�o���̂Ȃ��NJ��B
�@�����֍~���ėN�����悤�ȁA���������b�A��t���͓̂��R�ł��傤���B
�@�d���O�@��t���F�d���J�����i�Ŗ@�Ȃǂ́u�d���O�@�v�Ɋ�Â��A�v��i�K���܂߂āA���d���̗��n�����̂���ӂɍ����x������t���B
 |
�@�����̗��n���i��ړI�Ƃ��āA1974�N�ɑn�݂��ꂽ�B��ʓI�ȉƒ�Ō���10�~���d�C�����ɏ�悳��Ă���B
�@�����G�l���M�[���̎��Z�ł́A�o��135��kw�̌�����V�݂���ꍇ�A���e���]������^�]�J�n�܂ł�10�N�ԂŖ�480���~�A���̌��40�N�ԂŖ�480���~�x������B
�@���N�x�\�Z�z�őS���̎����̂ɔz�����t���́A�⏕�����܂߂�1318���~�B
�@��̓I�ɂ݂܂��ƁA�d���O�@�ɂ��d�����n���i��t���A1974�N����1984�N��10�N�Ԃɑ�F��26���~�A�o�t��33���~�A�אڒ����ɂ����z��t���ꂽ�B�܂��A�d���{�݂Ȃǎ��Ӓn���t����1981�N����1994�N�܂ő�F��10���~�A�o�t��8���~�B
�@�X�ɖ��N�m���ɓ����Ă���̂��Œ莑�Y�ŁA���̒��ɂ͐ݔ������z�̖�10���ɂ����鏞�p�Œ莑�Y�ł�15�N�Ԃɂ킽�菞�p�ɉ����Ēn�������̂ɓ���B�]���ĉ^�]�J�n�N�x����ԑ����A���p�ɏ]���Č������邱�ƂɂȂ邪�A�ݔ��̉��P�C�X�V�A�t�ѐݔ��A���݂������̂œr�₦�邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�y�n�A�����̌Œ莑�Y�ł͎����I�ɂ͑��݂�����蔼�i�v�I�Ȏ��������B
�@1996�N�x�̒��Ŏ��A��F���A�����֘A�Œ莑�Y��21���~�𒆐S�Ƃ��āA�l�A�@�l�̒����ł�S�ĕ�����Ɩ�25���~�B��F�����Œ���z37���~��65�D6�����߂�B
�@�ō��z��1975�N�x90.7���������֘A�̐Ŏ��ł������B
�@�����悤�ɑo�t����13���~�Œ��Œ���z19���~��67.5���������֘A�ł���B
�@�d���O�@�̎{�s��1974�N3���������̂�1�E2���@�͂��̑O�ɉ^�]�J�n�ł������̂ŁA���z�͓K�p����Ȃ������A���A���̌�͑S�ēK�p���ꂽ�B
�@����̕x�����E��t���͓d���O�@�̉��b�z�����B
�@�L���ȍ����̂��߂����̒��ɂ͒n����t�ł͌�t����Ă��Ȃ��Ƃ��낪�d���O�@��t���͎g�r���������ꂽ�̂ɁA�����̐����Ƃ͒��ړI�Ɋ֘A���Ȃ��}���فA�̈�فA�����ٓ��X�̃n�R���m�����X�ƌ��݂���A���̃V���{���ƂȂ������A�n�R���m�͈ێ��Ǘ��̃J�l�N�C���V�A�₪�Ē��������������邱�ƂɂȂ����̂����B
�@�����̐������������݂̑�H�����n�܂�ƁA�S������y�؍H���֘A�̊W�҂��W�܂�A�n���͈��u�[���ɗN���A�֘A�̎d���������A���R�Ȃ��璬���̏����������㏸�A1���@���ݎ���GE���u�t���^�[���L�[�v�̑S�ʐ����ł��������߁A�A�����J���瑽���̋Z�p�҂��������ăA�����J���܂ŏo�����̂�����A�n�����Ȃ���������Ȑ��������Ă��������ɂƂ��ēV�ϒn�ς̈�厖���ł������B
�@�^�]�J�n������Z���͌����̂��A�ő����̐l�X���ٗp�����@��������A��ꌴ���ł͍ő�6,000�l�������A�~�n���ɂ͊֘A��Ƃ̎�������30�Ђ�����A���̑���������300���������Ƃ����B�o�҂��̕K�v���Ȃ��Ȃ����A��҂̗��o���~�܂����A���Ɩʂ����W�����A�]���l���������Ă��Ē��Ɋ��C���h�����A���R�����̏�������������傫�������ď㏸�A���ł��ō������Ƀ����N����A�n��o�ς��㏸�A���Ɍ��\���炯�̖ʂ��������Ă����̂������ŁA��Ə鉺���A���d�l�̂��A�ł��A�Ƃ̎v�������������B
�@�o�t�����ɋ����A���̓����T��܂��B���̕����͍����͎w�����݂�Η�R�Ƃ��܂��B�Ŏ��Ȃǎ��O�Řd��������̎w���ƁA���Ƃ��čŒ���K�v�ȃT�[�r�X��d�����Ԃ̃o�����X���w��1.0�Ƃ���A��������Ŏ����Ȃ���Βn����t�ł���t�����B�t�ɒ�����Η]���������Ƃ��āA�s��t�c�̂Ƃ��T���c�̂ƂȂ�B
�@1963�N�A�������ݑO�̑o�t���̍����͎w����0.23�@�Ŏ��͕K�v�o���1/4�����Ȃ��ɕn���ł������A���A�H�����n�܂�d���O�@�̌�t��������悤�ɂȂ�ƁA�����͎w����1.0���ȒP�ɒ����A1980�N�ɂ͂Ȃ�ƍ����͎w�������ق�3.73�ɒ��ˏオ���āA���x�T�c�̂ɂȂ����B�l�܂�P�N�x�̐Ŏ��ŁA3�N���ȏ�̍������d����A���Z���u���ɂȂ����B
�@���̐Ŏ���23���~�A���̓��Œ莑�Y�ł�15���~�A����ɓd���O�@�ɂ���t�ł�����Β��A���͒����͖L���ȍ�����w�i�ɂ��ăn�R���m�₠����V�݁A�����̗v���B
�@�������A�ꎞ�I�Ɏ����������Ă����R�Ȃ���N�X���炳��A�C���t���Α�����1990�N�ɂ͍����w���͂�1.0�����荞��ł����̂����瑁������]���������B
�@�ʏ�̎����̂ł���Ό�t��������Θd���邪�A�L���ȍ����Ő��������n�R���m�����g�ƂȂ��āA���ɂ����������������ł����钬�ɕϖe�������ʂ̔ߌ����B
�@�����Œ��c���6�E7���@�̑��݁A�v���T�[�}���̑��݂Ƒ�ςȃ|�e���V�����e�B�����Ă���A��������p����Ăъ��C�ɖ��������ɑh��ƁA���ݗU�v���c�������B
�@�������A���d�́A1�x�͉����������A�������s���ŁA�d�͏���͐L�єY�݁A���v��͓��������܂܂ƂȂ��āA�������͍����Ɋׂ��Ă������B
�@���C���Ɋ������܂ꂽ�悤�Ȓ�����ł����������m��Ȃ��A�g��ɍ��������̕��݂Ɏ������̒������݂��������͂��A���j�Ɋw�сA�܂����̊�{�́e�m��f�ɂ���A�l����āA�l������n����������A�܂�������J��Ԃ��A�l�ނ̈琬�������n��U���̊�{�B
�@���̓��{���ċ��ł����̂́A�����I�Ȏ���������������ł͂Ȃ��A�l�ނƂ������������������炱���ł����āA�ő�̎��Y�͐l�Ԃɂ���B
�@�����́A���E�L���̌����n�тɂȂ�\�����߂��o�t�S�ł������A���A�n��Z���͏����A�������e��̏�f�������c���ꂽ�B
Q�F10���ɂȂ��ē��d�ɑ���V�����������������悤�ł����H
A�F2011�N11��3���@��
�@���d�ɓZ��邱�Ƃł����A�����d�͂����z�̑������o�����̂́A�o�c�w�����S���ӂ��Ă�������ł���A�����������̂̍ő�̗v���͌o�c�w�̑Ӗ��ɂ���A�Ƃ��ē��d�̊��储�悻30�l�����̌o�c�w�ɑ��āA���v1��1,000���~�]���Ԋ҂���悤���߂銔���\�i�ׂ��������邱�Ƃɂ����B
�@����1��1,000���]�̋��z�́A���d���W���ɖ��炩�ɂ��������������̂ɂ�鑹�������z�ŁA�ߋ�20�N�̊Ԃɖ������߂Ă������悻60�l���Ώۂ��Ƃ��Ă��܂��B
�@�����Ԋ҂���Ȃ��ꍇ�́A�����\�i�ׂ��i����A�Ƃ��Ă��܂����A1���~���鐿���z�͍����ł͍ō��z�ɂȂ�܂��B
�@��i�̗��R�Ƃ��āA�����͐�Ɉ��S���A�ƌJ��Ԃ��������Ă����A���呍��ł����S���ɋ^���悵�����A���S�����������邾���ɏI�n�����A���A���Ԃ��̂��Ȃ��厖�̂��N�����Ă��܂����B
�@���̂͌o�c�w�̑Ӗ��������ő�̌����ł���A���̌��Ɋւ��Ďi�@�̏�ŐӔC�Njy�����Ă��������A�Ƃ��Ă��܂��B
�@����1���́A�č����œ��d�̌o�c�ӔC��₤�����オ���Ă���܂��B
�@���d�͍�N9�����呝����4,000���~������č������Ƃ̎����B��������ł�����A���d������͌o�c�̃v���Ƃ��Ēʏ���҂����u�P�ǒ��Ӌ`���v���ʂ����Ă��Ȃ������A�X�Ɍ��q�͑��Q�����@�ɏ]���āA�����~�K�͂Ƃ�������Ӓn��̕⏞�ƂȂ�Ε��S������Ȃ�����A���{�����S���ꂱ�ƂɂȂ�A���d�͎�����̍��L��ЂɂȂ�\���������B���z�Ԏ��͖Ƃꂸ���z�ƂȂ�Ί���̑����͌v��m�ꂸ�A���̐ӔC�͌o�c�w�������̈��S���ӂ������Ƃɂ���A�o�c�ӔC���ʂ����Ă��Ȃ��Ƃ��āA���Q�����̑�\�i�ׂ������\����ł���A���d�͍X�ɋꂵ������ɒǂ����܂��B
�@�o�ϕ��͂́A��Q�l�����i�S�`�U���j�̓��{�̍��������Y�iGDP�j���O�N���3���ƌ��邪��������1.5�����͓��d�ɂ��l�K�e�B�u���v���Ƃ��Ă���A����������ł͂Ȃ��̂ōX�ɗ������݂͑����ƌ��Ă���A���˔\�ɉ������ꂽ�n��̌o�ϊ����͐�������A����̗������݁A�l�S�̈ޏk���Łu���Ɏc�O�ł����A���{�͂₪�ĕn�������ɂȂ�ł��傤�v�Ƃ͕č��o�ω�c�iNEC�j�O�ψ������[�����X�E�T�}�[�Y�A�n�[�o�@�[�g��w�������j���[���[�N�s����10��23���s�����u���̈ꕔ�ł��B
�@�č��ł̈�ʓI�Ȍ����́A�M���V���Ɠ����悤�Ɍ��Ă���A���E�ő�z��1�璛�~�����i10�����ő������j�����A�ԍς̌����݂͑S���Ȃ��A�o�ς͒���A�ǂ��ł���������悤�ȓ����{��ЊQ�A�����������̂ƂȂ�A���O�����猩��ΐ�]�I�Ȍ��������ł��܂��A����ł��Ȃ��~���Ȃ͉̂��̂Ȃ̂��A�o�ϗ��_�ɂ͂Ȃ������ł�����A���ꂩ����{�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂ł��傤���B
Q�F���q�͔��d���S�p������A��������Œ�~�������q�F�̍ĉғ�����~�����܂܁A����œd�͕s��������A�Η͔��d�̍ĉғ��A��������_���Y�f�̑���͖k�ɂ̃I�]���w�܂Ŕj�Ă��܂����B�d�͕s���͍����Y�Ƃ̍��O�ւ̓����������A���Ǝ҂̑���͕K���A���R�G�l���M�[�ւ̓]���A���d���̎��R�����X����Ȃ�������ŁA�ǂ��l����悢�̂ł��傤���H
A�F��������Ƃ��Ă͑����S�p�Ƃ������Ƃł��傤���A�����ɑւ��ׂ��d�͊m�ۂ̕��@���m�����Ă��Ȃ��A���̑���Ȃ��B
�@�ߓd�ɂ����E������A�o�ϗ͈ێ��A���W�A�����̕����I�����̈ێ��ɂ͐�ΓI�ɕK�v�ȓd�͂ł���A�d�C�͊m�ۂ���A�����͔p�~����A�ł͖��ӔC�Ȋ���_�ł����Ȃ��B
�@�d�͉�Ђ����̉Ă͈ꕔ�v���d�ƁA����҂̋��͂ŏ��������A�g�[�ŏ���ʂ��オ�邱�̓~����@��Ԃ͑����A��������d����ł͂Ȃ��S���̓d�͉�Ђ��s������Ƃ����A���������̋������{��50�w���c�A60�w���c�̋��ɕʂ�A�w���c�ϊ��\�͂͋͂������Ȃ��̂ŗZ�ʂ��������Ƃ��o���Ȃ��B
�@��d�͂͒n��ʂɓƐ肵�Ă���A����d�͂��������͑S�Č��������L���A�V���Ȑݒu���܂߂Ď��̌�͑S�ē����A�^�]���̌��q�F�����A�@��_������������Ήғ���~�A�_����ĉғ���n��Z�����獷���~�ߐ��������邾�낤���A���܂�����S�_�b�̖��͂͒ʂ��Ȃ��B
�@��������Γ��{���̌�������~�����˂Ȃ���@�����邩���m��Ȃ��B
�@�������̂��˂�̒��A�����Z���[�����ł�ꂽ��B�d�͌��C�����͍ĉғ������B
�@�}�X�R�~�͋����Ĕ�������Ă��邪�A�d�͂͐�ΓI�ȕK�v�����A�㊷�����Y�͕s�\�ƂȂ�ΓƐ��Ƃł���d�͉�Ђ𗊂炴��Ȃ��B
�@�d�͕s���������Ί�Ƃ̊C�O�i�o�ƌ������͊C�O�����ɔ��Ԃ�������A�䂪���o�ς̐�s���͈Â��Ȃ����A�������A���̊C�O���o���F����ł͂Ȃ��A�^�C�̐��Q���ʼn䂪���i�o���400�Ђ����ƒ�~�ɒǂ����܂�A�����ł��C���t���ƃo�u������̒����ɋ����ē����͒�؋C���ƂȂ��Ă���A���A����ł����̓K�n��T���x�g�i����C���h�i�o�����ڂ���Ă���B
�@�����{��k�Ђő�Ō��������k�n���Ƃ��ẮA�C�O�i�o����Ȃ瓌�k�n���ɐi�o���ė~�����A���邢�͊C�O�ō����Ă���̂Ȃ瓌�k�n���փ��^�[��������ǂ��ł����A��
�@�U�v�������̂����A����ɂ̓C���t�������ƏZ���̎����ӗ~�̖��A���ꂩ�瓌���{��ЊQ����̕����Ƃ��Đ��{���������������̂ł���A���̎������g���Ē����I�W�]�ɗ����ē��k�n���ċ���d�肽���B
�@����őS�Ă������A�p�Ђ̒����痧���オ��A20�N���炸�œ����I�����s�b�N�A�����đ�㖜���̑听���Ɛ��E�����Q�����������𐬂������A���E�ő�̋����A�����J�Ɏ������ʂ̌o�ϑ卑�ɐ��������o��������A��������������������B
�@�������A�o�u�������̒���A1�璛�~���Ă��܂����؋��卑�ɓ]�������͉̂��̂Ȃ̂��A���{�̑ǎ�肪�����̂��A�����������ӗ~���������̂��B
�@���̕������A�����{���_���f���ēo�ꂵ���r�c�E�l���t�̐����w���͌���t���A���̓���1�Ƃ�1��̎��Ɨp�Ԃ��Ə����A�����͉����Ă���̂��ƕ��ꂽ���A���Ƃ��̖����������Ă��܂����̂���������ł����B
�@��Δ���������O�ɁA�������^�Ɋ���Ă���͉̂��Ȃ̂��A���ɑς��A���������o���̂��A�s�K�ȑ�ЊQ�ł��������A������_�@�Ƃ��ĐV�����r���J���ׂ��`�����X�Ƒ����A���ɋ��������オ�낤�ł͂���܂��B��ɓr�͑�Ɗm�M���Ă��܂��B
�@4�N�ڂ��}�������A�O�i�炵�����̂͊�����ꂸ�A�ہA�ނ���n������̒���������B
��\���́@����̒��ŏI��
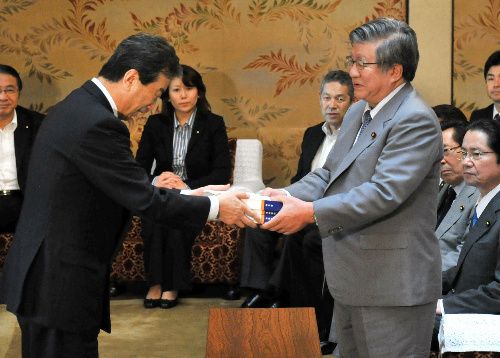 |
�@�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̂������鍑��̒����ψ���i���쐴�ψ����j�i�����{�w�p��c��j�́A7��5���A�ŏI�����O�Q���@�c���ɒ�o�����B
�@���d��K�����ǂ��n�k�A�Ôg���摗��ɂ��Ă������Ƃ��u���̂̍����I�����v�Ǝw�E���A�u���R�ЊQ�ł͂Ȃ��l�Ёv�ƒf��A���@�̏����Ή��̐ق����w�E�A���d���̐ӔC�����������e���Ă���B
�@����641�y�[�W�A���̒��͉���1,167�l��900���Ԉȏ�̒�����s���A�W�悩���2�猏�̎����āA���͂��ߊ��@�̐ӔC�ҁA�K���Ȓ����ǁA���d���A�d�C���ƘA����ȂNJW�@�ւ̐ӔC��Njy���Ă���B
�@���̕��̗v�_�A���_���ɓZ�߂�B
�u�������̂͐l�Ёv
���_
������̎��̂́u���R�ЊQ�v�ł͂Ȃ��u�l�Ёv
����Q���ŏ����o���Ȃ������ő匴���́A���@�A�K�����ǂ̊�@�Ǘ��̐����@�\�����A���Ǝ҂Ɛ��{�ӔC�̋��E���B����������
�����d�͂����ʓI�ȑΉ����o�����\��������A�g�D�I�ɂ���肠��A�o�c�w�͌�����y��
�����̋K�����ǂƓ��d�o�c�w�͈Ӑ}�I�Ȑ摗��ƕs��ׁA���ȑg�D�ɓs���̗ǂ����f�����Ă���
������̎��̂́A������Ɨ�������O�҂ɂ���Čp�����Č������Ď��A�����ׂ���
��
(1)���q�͖��Ɋւ����݂̈ψ��������ɐݒu����
(2)���{�̊�@�Ǘ��̐��̔��{�I�Ȍ��������s��
(3)���{�̐ӔC�Ŕ�Вn�̏Z���̌��N�ƈ��S���I�E�p���I�Ɏ��
(4)���{�Ɠd�C���ƎҊԂ̐ڐG�ɂ��Ẵ��[�����Ə��J��
(5)�����Ɨ����Ɠ��������������V���ȋK���g�D��ݒu
(6)�����̌��N�ƈ��S����Ƃ���ꌳ�I�Ȍ��q�͖@�K�����č\�z
(7)���Ԓ��S�̐��Ƃ���Ȃ�Ɨ����������ψ��������ɐݒu����
 |
| �i���쐴�ψ����j |
����̒����ψ�����o�[
���� ���ψ����i�����{�w�p��c��j
�� ���F�@�@�i�_�ˑ�w���_�����j
�哇 ���O�@�@�i�����A��g�j
��R �䑁�q�@�i�����ː���w������������C�������j
���� ���j�@�@�i�����������������j
�c�� �k��@�@�i���Ð��쏊�t�F���[�A�m�[�x����ҁj
�c�� �O�F�@�@�i�Ȋw�W���[�i���X�g�j
�쑺 �C��@�@�i������@�ȑ�w�@�����j
�I�{�� ��q�@�i��������F�����H���j
���R �����@�@�i�Љ�V�X�e���f�U�C�i�[�j
�u�����j��A���߂č���ɐݒu���ꂽ�Ɨ��@�ցv�Ƃ��đ��̒�����i�����d�́A���{�A���ԁj�̒����ψ�����ݍ��߂Ȃ������A���@�̏����̐ق��A���d�{�Ђ̑g�D�I�������e���u���̂͐l�Ёv�ƌ��_�t�������Ƃ͕]���ł���B
�������A�����o��������A���̕������Ă����̂��A���̌����̉𖾂ƍĔ��h�~�ɒ������ʂ��ǂ��������Ă�����̂��A����̒��̐ݒu�����ƂȂ����@���ł́A���@�c���ɕ����o����܂ł����L�ڂ���Ă��Ȃ�����A�����̐��ʂ��ǂ��������̂��͍���c���B�̎��g�ݔ@���ɂ������Ă���B
���̗v��
�@���̑O�̑�
�@�l�X�̖��ƎЉ�����Ƃ����ӔC���A�o��̌��@�����̌����ɂ���B
�@�����d�͕�����ꌴ�����̂������鍑��̒����ψ���̕��́A�ߋ��̈��S��⎖�̑Ή����������ᔻ�����B���̂�h�����\����A���{�Ɠd�͋ƊE�̑̎��ɂ��荞�B
�@�u����̎��̂͌����āw�z��O�x�Ƃ͌������A�ӔC��Ƃ�邱�Ƃ͏o���Ȃ��v
�@�n�k�A�Ôg�A�ߍ����̂̂�����̑�ɂ��Ă��A���d�A���q�͈��S�E�ۈ��@���댯����F�����Ȃ��炻�̑��摗�肵�Ă������Ƃ�˂��~�߁A���̓_���������w�E�A�����K���ɑ���u���Ă����Ȃ�u���͖̂h�����\�����傫���v�Ƃ����B
���n�k��
�@�n�k��ł́A2006�N�ɉ������ꂽ���̐V���������ϐk�w�j�ɑ��铌�d�̑Ή��̒x����w�E�����B
�@���d�́A������ꌴ����V���j�ň����グ���z��ɓK�������邽�߁A�ϐk�⋭�H���ɖ�800���~�̔�p���K�v���ƌ��ς����Ă����B�������A�ꕔ���{�����݂̂ŁA�̐S��1�`3���@�͑S�����{���Ă��Ȃ������B
�@���ւ̍ŏI������09�N6���Ɠ͂��Ă������i�܂��A������16�N1���ɐ摗�肷�邱�Ƃ����肵�Ă����B
�@�ϐk�̗]�T���[���ɂ��邱�Ƃ������̂�����������߁A�X�P�W���[���͌��\�ł��Ȃ������悤���B
�@�ē����ł��������q�͈��S�E�ۈ��@�́A�����܂ł����Ǝ҂̎���I�Ȏ��g�݂ł��邩��Ƃ��ĖٔF���Ă����B
���Ôg��
�@�Ôg��ɂ��ẮA���d�����咣����u�z��O�v�A�z�����Ôg�̔����z�ł��Ȃ������Ƃ��Ă������A�����^��������ے肵���B
�@�u�z��Ôg���ɒ����Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��v�u�㏸���͂��郌�x������ƘF�S�����Ɏ��邱�Ƃ����O���Ă���v07�N4���ɂ������d�͑��ƕۈ��@�̒Ôg��Ɋւ���ł����킹��c�ł̔����L�^�ł���B
�@06�N���_�ŕۈ��@�͓d�͉�Ђɑz�����Ôg������A�F�S�����Ɏ���댯��������Ǝw�E�����B�����������Ŏw�E���������ŕ����ɂ͂��Ă��Ȃ������炵���B�]���ĒS���ӔC�҂ɓ`����Ă��A���d�o�c�w�ɂ͓͂��Ă��Ȃ��B
�@�z��O�Ƃ����n�k�A�Ôg�̔����̉\���͑������_�Ŏw�E����A���̑���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�ۈ��@�A�d�͉�Бo�����F���A���O���Ă��������������̂ŁA���̌��O������J�̏�ŕs�����ł��������Ƃ�A��̎��{���ɖ���������A�摗�肾������ƁA�z��O�̎��Ԕ����ŋN����ł��낤�ߍ����̂ւ̑Ή����Ȃ������B����������œI�Ȏ��ۂ��N�����ł��낤���̃V�i���I�ւ̑Ή��͑S���Ȃ��Ă��Ȃ������A�ƕ��͒f���Ă���B
�@���ۓI�ɂ͂ǂ����A���ې����I�ɂ͂ǂ����B
�@���Ăł͋@��̌̏�Ȃǂ́u��������v�ɉ����A�n�k�A�^�����́u�O������v�A����ɁA�e���̂悤�ȁu�l�דI���ہv�ɕ����đ���u���Ă���B
�@�킪���́u�O������v�͒n�k�݂̂��ΏۂŒÔg�͑ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ��B�l�דI���ۂ͂��蓾�Ȃ��ƑΏۊO�ƂȂ��Ă���B
�@���������Ăł͎�ȑ�ł͍��̋K���ɂ���ċ����͂����邪�A�킪���œd�͉�Ђ̎���K���������B
�@���q�͈��S�ψ���̔��ڏt���ψ����́u�킪���ł͍��ۓI�Ȉ��S��ɑS���ǂ����Ă��Ȃ��B����Ӗ��ł�30�N�O�̋Z�p�������ň��S�R�����s���Ă���v�Ǝw�E���Ă��邪�A����܂łɈ��S�ψ���̈ψ��������{�ɑ��Ăǂ̒��x�̕����o���Ă����̂��A���{�����������̂��A���͓d�͉�Ђ��ēE�w���̌�����������Ă����̂��B
�@�u�K�����������A�Ď���������ԁA���d�̗��ɂȂ��Ă����v�ƕ��ł͎w�E���Ă���B
 |
�@���̌�
�@���d���̂���܂Œn�k�ɂ��d�v�@��̑����A�j���͂Ȃ��A���̌�̌�������ɖ��͖��������Ǝ咣���Ă����B����������̒��̕ł́A�ً}���Ɍ��q�F���₷�@�킪�n�k�ʼn�ꂽ�\��������A����ɂ���ė�p�����R���̂�|��āA�^�]�������u���~�߂��Ǝw�E�����B
 |
�@��N12��15���ɐV���ɃX�b�p�����ꂽ���A���d���͉��߂đS�ʔے�A1�`3���@�̌��q�F�̘F�S�n�Z�́A�Ôg�ɏP��ꂽ���ƂŔ��p�d�������āA���q�F����p�o���Ȃ������ׂ��Ǝ咣���Ă����B
�@�Ƃ��낪�A���d���咣����Ôg�̓��B�����́A���̒������ׂ����B�����ƈقȂ�A���d�̒Ôg�����B�����d�����j�ꂽ�Ǝ咣���鎞���ɂ́A���ۂɂ͌����̉���1.5km�ɓ��B���Ă����������Ǝw�E�����B
�@�]���āA�Ôg�����B����O�ɁA���Ɉꕔ�̔��p���d�@�͋@�\���Ȃ��Ȃ��Ă����\���������Ǝw�E�����B
�@�ŏ��̘F�S�n�Z���N������1���@�̔��p������iIC�j�ɂ��Ă����d�͒n�k�ɂ��j���͖��������Ǝ咣�A�n�k����Ɍ��q�F�̈��͂��}���ɉ������Ă��Ȃ����Ƃ��疾�炩���Ƃ����B
�@�������A����̒��̕��ɂ́AIC�̔z�ǂŏ����Ȕj�f���N���Ă����\���������Ǝw�E�A�����Ȕz�ǔj�f�Ȃ爳�͉͂�����Ȃ��Ƃ������q�͈��S�@�\�̉�͂������u���d�̐����͕s�����ł��邱�Ƃ͖����v�Ƃ����B
�@����IC�ɂ��āA�^�]���͒n�k�ƒÔg���P���ė���Ԃɉ^�]�ƒ�~���J��Ԃ��Ă����B���̎�IC���~�߂��ɓ����������Ĉ�C�ɘF�����₵�Ă����玖�̂̊g���h�����\�����������Ǝw�E�A���������d�͎菇���ɏ]���čs�����������Ŗ��͖����Ƃ����B����������̒��͂����ے�A�^�]����IC�̔z�ǂ����p�����R��Ă���̂ł͂Ȃ����ƐS�z���m�F�����邽�߂Ɏ~�߂��Ɛ��肵���B
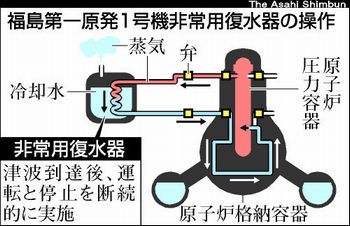 |
�@�܂��A1���@�̌��q�F�̈��͂����������C�����ق��쓮���Ȃ������\�����w�E�B�^�]���̒�����蒲���ŁA�ق̍쓮����N�������Ă��Ȃ����Ƃ������B�n�k�Ŋ��ɔz�ǂ��j�����A�ق������Ȃ������\��������Ƃ����B
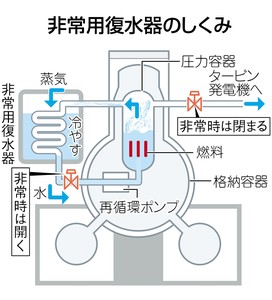
�@�i�[�e��̈��͂�������r�C�i�x���g�j�́A����P���͈�x���Ȃ��A�d���̂Ȃ����ŏ\���Ȑ}�ʂ��Ȃ�����͓�������Ƃ����B
�@���ʂƂ��Đ��f������h�����Ƃ͏o���Ȃ������ƌ��_�t�����B
�@���q�F���͕��ː��ʂ������A���㐔�\�N�ɂ킽���Č��q�F���̏����ڊm���߂��Ȃ��ɂ��S��炸���d������������Ôg�����ɋ��߂āA�n�k�̉e�����ߏ��]������̂́u���ݘF�ւ̉e�����ŏ������悤�Ƃ����l�������d�o�c�w�ɂ��邩�炾�v�ƒf�߂����B
�@���́u�n�k�ʼn�ꂽ�v�Ƃ���̂��\���������������ŁA�f�肷��ɂ͖����m�͂Ȃ��B
�@�����̈ȑO�̔���
�@�@�C���|���v���@�\�r�����F�S�����Ɏ���댯���͕ۈ��@�����d���F�����Ă������A��̌�����扄���ɂ��Ă����B
�@�����̂̎�Ȍ���
�@�@���̋K�����ǂɂ�铌�d�ւ̊Ď��@�\������Ă����B���O�ɑ���u����@��͂�����ł����������A�P�ɐ扄�����邾���ł������B
�@�@���̂̌�����Ôg�݂̂Ɍ��肷�ׂ��ł͂Ȃ��A�n�k�ɂ�鑹���̉\�����ے�ł��Ȃ��B
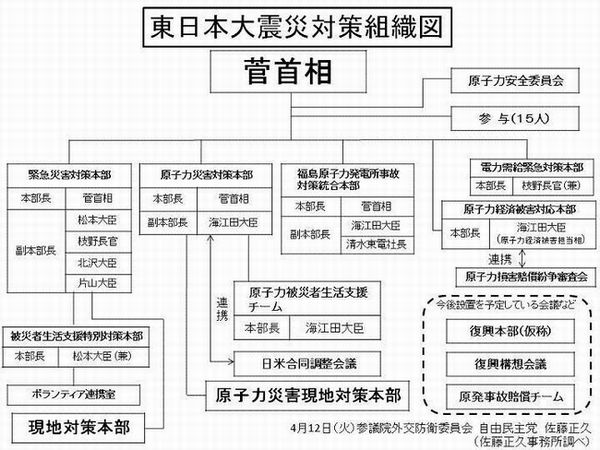 |
���@�̉ߏ���
�@��Вn�Z���̖h���̑S�͂�s�����ׂ����@�E���{�����̖�����F�������A���`�I�Ɏ��Ɠ����҂��ӔC���ׂ����̔��d�����ɓ���A���̑Ή��ւّ̐��ȉ�����J��Ԃ��A��������������A���d�̓����҈ӎ����Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����B
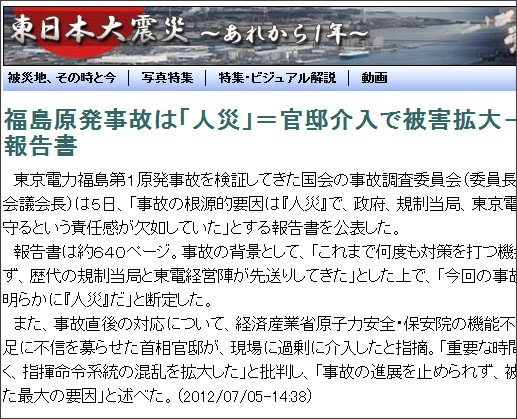 |
 |
 |
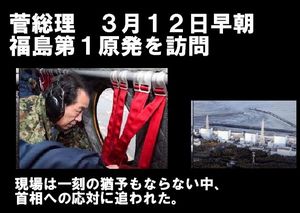 |
�@�Ƃ��낪������ꌴ�����̂̏��̎��W�͍��������炵���B�n�k�ƒÔg�Ŋ̐S�̒ʐM�����j�f�A�d�����j��A�I�t�T�C�g�Z���^�[�͋@�\���Ȃ��ASpeedi���@�\���Ȃ��A������Ă��Ȃ��A�����Ċ�@�Ǘ��̂�����Ƃ��č��{�I�ԈႢ��Ƃ����͍̂ō��ӔC�҂ł���A�ō��w����������ЊQ����ɔ�яo���čs���Ă��܂������Ƃɂ���B�d�厖�̔������A���{���𗯎�ɂ���Ƃ͎Ƃ��Ă̎��o�����@���Ă����Ƃ����v���Ȃ��B���������[�������K���ɂȂ��Ď~�߂��̂�U����čs���Ă��܂����s�ׂ͔ᔻ����ē��R�ł���A�ō��w�����Ƃ��ĕs�K�ł��邱�Ƃ�����ؖ������悤�Ȃ��̂��B
�@���̏d��Ȏ��ԑтɎ��Ȃ�厖�̂��i�s���ł���A���̑�̎��Ԃ�D���Ă��܂������Ƃ͏d��ȉߎ��ɂȂ�B���̍s�ׂɑ��ē����d�͖{�Ђ��ᔻ����͓̂��R��������̒������Ŏ̍s�ׂ͌y��������Ɣᔻ����̂����R���B
�@��_�W�H��k�Ђł́A���̍ɑ��ł��������R�̑Ή��͗]��ɂ��ݏd�����Ĕᔻ���W���������A����͌y�X����������肷���Ĕᔻ���ꂽ�B
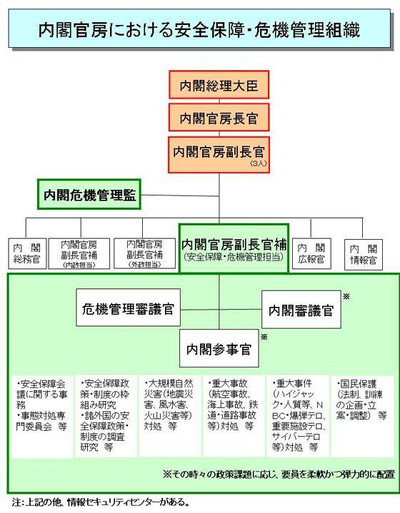 |
�P�ޖⓚ
�@�������Ӕ�Вn�Z���ɑ�����U���Ɋւ���w���▽�߂̏o�����⎞���ɂ��Đ��{�̂�������������������ɂȂ��Ă���B
 |
�@�������̔����A��p���u�̔��d�����S�Ĕj���A��~�������_�A�����Ôg�P���̎��_�ōň��̎��ԂɊׂ邱�Ƃ͖��炩�ł������B���R���̏��͑��A���d�{�ЁA���t��@�Ǘ��Z���^�[�ɓ͂��Ă���͂������A���d�ł͉�A�В��Ƃ��o�����ŕs�݁A���t�͍���������̂ő��Ή������炵�����A�n�k�ƒÔg�̑Ή��ɖZ�E���ꂽ�̂��A�������̂̑������Ĕ��f�~�X���d�Ȃ��Ă���B
�@���̒��̒����ł́A�������̎��ӂ�12�s������2��1�琢�т�ΏۂɃA���P�[�g���������{�A���̂����̂�������1�����т̓��v�ł́A���{�̎��̓����i11,3,11�j�̌ߌ�7��3���ɋً}���Ԑ錾�߂������A���̎��_�Ŏ��̔�����m�����̂͏Z���̖�1�������B
�@��12���ߑO5��44���ɔ��a10km�����ɔ��w�����o�����ɂȂ��Ė�2�����x�B�ߌ�6��25����20km��2�g�債�����ł͘Q�]�A��F�A�o�t�̊e���ł͑唼���m��悤�ɂȂ����B�x���ł͒����̉p�f�őS������������ɔ��A20km���Ɋg���m�����̂͐�����ɏW�������ゾ�����̂ōX�ɎO�t�����������B
�@�����ɗאڂ��Ă���e�����̂ł͗����[�ɂ�8�������̂�m��悤�ɂȂ���w�����`�B���ꂽ���A��̓I�Ȏw���͂Ȃ������B
�@�܂��ĉ������ꂽ�������̏Z���̑唼�͔픘�̊댯���ȂǑS�����m���Ă��Ȃ������B�������S�~�̔��~�����̋����������������炾�B���˔\�����̉Ȋw�I���l�Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ŁASpeedi�ɂ��ϑ����l�A�A�����J���{�������Ă��ꂽ�u�����n�}�v������@�Ǘ��Z���^�[�ɓ͂��Ă��Ȃ������B���邢�͕���Ă��Ȃ������͎̂����炵���B�̐����̂��̂��m������̂��B
�@���⌧�̎w����҂��������̔��f�Ŏ���I�ɔ����͉̂p�f�ƌ����ׂ����B
�@�������f�������̗�͌���20�`30km�����̏Z���ɉ������̎w�����o��10���ԏo�����܂܂ɂ������Ǝ���v�����ɕύX�����Ή�����́u���̔��f���Z���l�Ɋۓ��������Ƃ������A�����̐�����a����ӔC����������ƒf������Ȃ��v�Ǝw�E�����B
�@���Ɍ����̖k�����ɂ�����ɔ�������Q�]���̉��n���ʂ͔��w��n���������Z�x�������ɂ��S��炸���u���Ă����B
�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬�����������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v����ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎�������{���{�͌��\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����A�Ȃ�̂̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B
�@�X�Ɍ���20km�����̕a�@����V�l�{�݂ł͍�N3�����܂ł�20���ŁA���A����ɗe�̂��������S���Ȃ����l�����Ȃ��Ƃ�60�l�ȏア�������A���O�ɖh�ЌP����h�Ќv��̕s�����������ƕ��͂����B
�@�������̌���������{��k�Ђ����������ɑ̒�������ĖS���Ȃ����u�k�Њ֘A���v���A��Ë@�ւ̋@�\��~�A����̊��̈�����12�̍��ڂɕ������͂������ʂ�7��12�����\�����B
�@�֘A���ƔF�肳�ꂽ1632�l�̂����A���A�{��A����3����529�l�̎����͂������A�ł����������̂́u�����̔��v��47���B�������̂Ɍ��肷��Ɓu���ւ̈ړ����̔��v��56���ƍő��ƂȂ�����]�X�ƕς������A�����Ȉړ����d�Ȃ�����ƉՍ��ȏ��������肷�������Ƃɂ��B

�@���̒���̏Z���̌��N��Q�ōł��S�z�Ȃ̂����ː����E�f�̉e�����B���⌴�����ӂ̎����̂ɂ͉e����h�����ߏ\���ȁu���胈�E�f�܁v����~���Ă����͂��A�������p�͓����픘�O�łȂ���ΈӖ����������߁A���̕��p�͊댯���@�m�����璼���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������p�����͕̂x�����A�o�t���A��F���A�O�t���̂݁A���̎s�����͍��⌧�̎w����҂��Ă��Ď������킵�Ă��܂��Ƃ����厸�Ԃ����Ă��܂����B
�@�������45km���������ꂽ�O�t���������������胈�E�f�ܕ��p�ɓ��ݐ����̂͋��R�̏o�����炵���B13���ɕx���Ƒ�F�̏Z����2��l���O�t���ɔ��Ă����B���̎����̕ی��t�����������N��Ԃ��`�F�b�N���Ă����Ƃ���A���Ă����l�B���ς����������Q���Ă��邱�ƂɋC�t�����B2�����V�[�g�ɓ��������F�̊ۖ�A�u���E���J���E���ہv�ƂȂ��Ă����B�����Œ����̖�ǂɊm�F�����Ƃ���A��t���b��B�������胈�E�f�܂��낤�Ƃ̓���������A������ɕ��A����������F���̒S���҂ɖ₢���킹���Ƃ���A�n���ł͖h�Ћ���ň��胈�E�f�܂̕��p�͏펯�����Ă���A�ڂ������̌��p����������B
�@�O�t���͋}篈��胈�E�f�܊m�ۂɓ����A���ɖ₢���킹���Ƃ��됔���m���ߎ��ɗ���Ȃ�n���Ƃ̂��ƁA�����p�\�R���ŕK�v�����v�Z���Ď��ɍs�����B
�@���胈�E�f�܂̕��p�̃^�C�~���O�ō��̎w���A���m���̔��f�ŕ��p���邱�ƂɂȂ��Ă����B
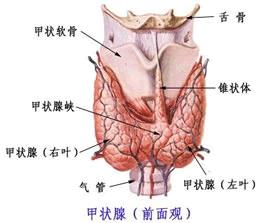
���f���
�@(1)�����̔���
�@(2)���̎��̕�����
�@(3)�~�J�����邩
�@���̂悤�ȏ���c���ł���͍̂��̋@�ւ����Ȃ��B�����ɂ���Speedi���{�݁E�^�p���鉿�l������̂����A���̂����͏��𗬂��Ȃ��������A���p�̎w�����o���Ȃ������B
�@��������������Ă�������Ƃ���������͒ʗp���Ȃ��B
�@�w�����钆�������݂����A�e�Ȓ����o���o���ɓ��������Ƃɂ���c����s���̌��ׂ����炯�o�����������B
�@�A�ɂ���b��B�́A���E�f����荞�݂₷���B�������̂��N����ƁA��C���ɕ��ː����E�f�����o����A������z�����ނƍb��B�Ɏ�荞�܂��B�����ŕ��ː����o���A�b��B���������N���������ɂȂ�B
�@���胈�E�f�܂p���A�b��B����ː��ɂȂ����ʂ̃��E�f�܂Ŗ������Ă����A�ォ������Ă������ː����E�f�͍b��B�ɋz�����ꂸ�̊O�֔r�o�����B
�@���͕��p����^�C�~���O�ŁA���p���Ă���24���Ԍo�ƍb��B���̗\�h���ʂ͂Ȃ��Ȃ�A����p�̕|�ꂩ��A2�x3�x�̕��p�͏o���Ȃ��B�����瑁�����镞�p�����߂��B
�@���ː����E�f�͖��F���L�A�@��ő��肵�Ȃ��ƁA�Y���Ă���̂��͉���Ȃ��B
�@�����炱���I�m�ȃ^�C�~���O�������w�����o�����ƂɂȂ��Ă���A���m���̔��f���邱�ƂɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�����������p�̎w���͂����Ă��Ȃ��B���̎w���Ɋւ��ẮA���{�̌��q�͍ЊQ���{���⌴�q�͈��S�ψ���Ȃǂ̊ԂŐӔC�]�ł̘_�����������������B
�@�S�Ă̎��Ԃ́u���S�_�b�v�Ƃ������̂̒m��Ȃ������Ɏ��߂���Ă������{�A�Ȓ������O�̌P���A�w���n���̊m�F�A�č\�z���̑��S�Ă��Ȃ�������ɂ��Ă����t�����ꋓ�ɐ����o���Ă����B
�@�Ƃ��낪��F���E���͕��˔\�g�U�\�z�̏����l�̃p�\�R�����瓾�Ă����B
�@��F�A�x���A�O�t�̎q���B�����p�̃^�C�~���O��͂߂��̂͂��̏��ɂ��B
�@�����1986�N�̃`�F���m�u�C���������̂����������Ƃ��āA���[���b�p�����͕��˔\�������̍��ɉ����A�ǂ̈ʂ̗ʂ����ł��邩��\������Ď��̐����\�z���A�Z�p���Ă����B
�@�����Ƀt�N�V�}�������̑�����ƊĎ��̐������߁A�킪���̋C�ے��ɃA�N�Z�X���ċC�ۃf�[�^�����W����Ό�͌������̂̔����K�͂Ǝ��Ԃ�m��Όv�Z�͏o����B�킪���ɂ͐��E��Ə̂���C�ۊϑ��V�X�e��AMeDAS�iAutomated Meteorological Data Acquisition System�j���S��1,300�����Ɏ����ϑ����u��ݒu���~���ʁA�C���A���Ǝ��ԁA�����A�������ϑ����ēd�b����Ŗ����C�ے��̃R���s���^�[�ɓ���A��͂���ċC�ۗ\��̃f�[�^�ɂȂ�B
�@���̃V�X�e���ɉ������ꂽ�m���E�F�[�ƃI�[�X�g���A�̋@�ւ��A�N�Z�X���ė\���}��C���^�[�l�b�g�Ō��J�����B
�@�킪���̊ϑ��{�݂ł���Speedi��AMeDAS���A�����Ă���A�R���Ȃǂׂ̍����n�`���������ė\����o�����ƂɂȂ��Ă����B���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�Speedi�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B
�@���������Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B
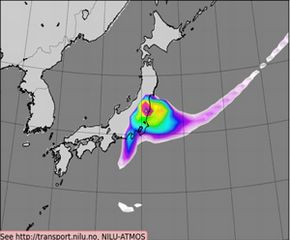
�@�K���Ȃ��Ƃɂ͑�F���E���̋@�]�Ńm���E�F�[�ƃI�[�X�g���A�̃l�b�g�ɃA�N�Z�X�ł��ďd�v�ȏ������o�����B���AMeDAS�̐��m�ȏ��Ŕ��f����Ηǂ�14���͖k���œ�ɗ���A15���ɂ͓쓌�̕��ɂȂ�A�O�t���͓����������Ί댯���Ɣ��f������̉���ŕ������ϑ����ĕ��p�̃^�C�~���O�f�����炵���B
�i�m���E�F�[�Ńl�b�g�Ɍ��J���ꂽ�\�z�}�̈ꖇ�A���������\���ꂽ�j
�@�܂��ЂƂ��Ԃ�����݂ɏo���B7��11�������A��ꌴ�����̂ɂ��ߗׂ̎q���B�A�����ΏۂɂȂ���1,080�l�̐��U����12�~���V�[�x���g�A�ő�42�~���V�[�x���g�Ɛ��v����邱�Ƃ��A���ː���w�����������̕��͂Ŕ������B
���d�P�ޖ��
�@���d�̍ō��ӔC�҂ł��鐴���В����A���@�֑S���P�ނ�\���o���Ƃ������ŁA���@���͂����������A���d���͂��̂悤�Ȑ\������͂��Ă��Ȃ��ƑS�ʔے�ł��������A������ς̎Q�l�l���v�ōő�̏œ_�ɂȂ����̂́A��N3��14���邩��15�������ɂ����Ă̊��@�Ɠ��d�����В��̂��Ƃ�ŁA���ł́u����͑S�ʓP�ނ���؍l���Ă��Ȃ������v�Ƃ������R�������A�S�ʓP�ޖ��͊��@���̑��Ƃ���ɂ�����ł������ƌ��_�t�����B
�@15�������A���͓��d�{�Ђɓ{�荞��ōs�������Ƃ͑傫�����ꂽ���A���̈�A�̍s���ɂ���āu�S�ʓP�ނ�j�~�����v�Ƃ��������͔F�߂��Ȃ��A�������Ȃ���Γ��{�͐[���Ȋ�@�ɔ�����Ă����Ƃ����X�g���[�͕s���R������B�Ɛ�̂āA����Ɂu���d�ɓ������{����ݒu���Ă܂ʼn���𑱂������@�̎p���͗�������v�Ƌ����ᔻ���Ă���B
�@�����̊��@��K�����ǂ̊�@�Ǘ��ӎ��̒Ⴓ���M��ᔻ���āA�u�@�Ǘ��̐��͋@�\���Ȃ������v�Ɗ��@���̑Ή��̐ق���ᔻ�����B
�@���������d���̐����В��̑S�ʓP�ޖ��Ō���ő�̌����́A�u�����В��̃R�~���j�P�[�V�����̎����ɂ��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������Łu�Œ���̐l���͎c���v�Ƃ����d��Ȏ�����`����ꂸ�A�B���ŗv�̂Ȃ������ɏI�n�������Ƃ�����ő�̗v���ł���B
�@�u���d�̍ō��ӔC�҂Ƃ�������ł���Ȃ���A�����Ǝ��g�ނ��Ƃɂ���ĐӔC��]�ł���X�������������d�̍����I�Ȍo�c�̎�����B���ȘA���ɏI�n�����v�Ƃ����Ƃ��ē��d�̌o�c�̎��܂œ��ݍ��B
�@����ɓ��d�ƋK�����ǂ̂�����ɂ����ݍ�����u�K�����闧��Ƃ���闧��́w�t�]�W�x���N���A�K�����ǂ͓d�͎��Ǝ҂́w���x�ɂȂ�A���̌��ʁA���q�͈��S�ɂ��Ă̊ē@�\�͕��Ă����v�Ǝ��Ǝ҂ƋK�����ǂ������ꂠ���Ă���\�}�ɓ��ݍ��B
���w��
�@��_�W�H��k�Ў��A����t�ɋ������ė��Ȃ��A�~�������̔��߂��啝�ɒx��Ă��܂������ƂȂ��A�V�������@�̒n��1�K�ɃI�y���[�V�������[����݂��A���������@��@�Ǘ��Z���^�[�Ƃ����i�A���A�g�D���ł͂Ȃ��j
�@��������ɉ^�p���Ă���͓̂��t������W��Z���^�[�B24���ԑ̐��i5��20�l�j�ŏd�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɔ����x�@���A�x�����A���h���A�C��ۈ����ȂNJ�@�Ǘ��ɊW����Ȓ��ƃz�b�g���C���Ō���Ă���B
�@�������Ǘ����Ă���̂́u���t��@�Ǘ��āv�i���ł͂Ȃ��w�āx�j���̓��t��@�Ǘ��Ă͑啨�x�@����OB���A�C���Ă���B�i�x�����Čo���ҁj
�@�L���̏ꍇ�͑����������A�e���q���i���C��j���������Q�d�Ƃ��ē���B
�@�����{��k�ЁA������ꌴ�����̂��������������ɂ͊��@���{�����ݒu����A��@�Ǘ��Z���^�[�ɓ����Ă������͂���đ��{���ɕ����B
�@���R�Ōv�Z�����A���ׂ��q����55���̕ی�҂Ɍv�Z�O�̃f�[�^������`���A�u�[���v�ƒʂ��Ă����B
�@7��10���A��t���ōs��ꂽ���ۃV���|�W�E���Ŕ��\���ꂽ���Ƃɂ��ƁA�b��B�̔픘���ʂ��v�Z����ɂ͂܂��A���ː����E�f����荞�b��B��1���Ԃɏo�����ː��𑪒肷��B���̎����l����l�̔N���픘�����Ȃǂ��l�����āA���U�픘���ʂ��v�Z����B
�@���{�͍�N3�����{�A���킫�s�A�얓���A���������̋������~�O�̂��킫�s�얓���A����������10�s�����ȏ�ɏZ��ł���15�Έȉ���1080�l��Ώۂɂ���1���ԓ�����̐��ʂ����������B�������A���{�́u�����̖ړI�́A���胈�E�f�܂����ޕK�v�����邩�ǂ����f���邽�߁v�Ƃ��āA�ꕔ�����q�������̐��ʌv�Z�����A���͂��Ȃ������B
�@�ی�҂ɂ͍�N8���A1���ԓ�����̎����l�����`�����A55���̕ی�҂ɂ́A�v�������ꏊ�ƍb��B�̎����l�̍��������Ȃǂ̗��R�Łu�[���v�A��30���ɂ́u����0.01�}�C�N���V�[�x���g�v�ƒʒm�����B
�@����A���ˑB��w�����������̌����`�[���́A���Ԃ��͂����肵�Ȃ����̒���̍b��B�픘���𖾂��邽�߁A1080�l�S����1���ԓ�����̎����l���琶�U�̔픘�B�ʂ��v�Z���Ȃ����A�����ꏊ�ƁA�b��B�����l�̍����ő�ɂȂ�Ƒz�肵�ċ��߂��B
�@���̌��ʁA�ō���42�~���V�[�x���g�A30�~���V�[�x���g�䂪3�l���邱�Ƃ����������B�ъّ��A���킫�s�ł͍����X���ɂ������B
�@�b��B�픘��h�����߂ɂ͈��胈�E�f�܂����ލ��ی��q�͋@�ցiIAEA�j�̊�́A1�Ύ���50�~���V�[�x���g�ƋK�肳��Ă���A����̒����ł͍K���ɂ����̊������q�������Ȃ��������猒�N�ʂł̉e���͒Ⴂ�Ɛ��Ƃ݂͂Ă���B
�@����̌��ʂɂ��Đ��{�W�҂́u�����҂������ړI�Ōv�Z�������̂ł����āA����Ƃ��l�X�ɐ��ʂ�ʒm�����Ă��͂Ȃ��v�Ƃ����B
���胈�E�f��
�@���ː��ł͂Ȃ����E�f�����E���J���E���̌`�Ő��܂������́A���E�f�́A�b��B�z�������̍\�������Ƃ��ĕK�{�̔��ʌ��f�ł���B�b��B�ɂ̓��E�f����荞�ݒ~�ς��A�����p���ăz����������������Ƃ����@�\�����邽�߁A�����������̂���������ɕ��o���ꂽ���ː����E�f���ċz����H���ɕt�����đ̓��ɋz�������ƁA�b��B�ɔZ�W���A�b��B�g�D���ň����ԕ��ː�����˂��������̌��ʍb��B��Q���N����A��r�I�Ⴂ���ʈ�ł͍b��B�����A�����ʂł͍b��B�@�\�ቺ�ǂ������N�����B
�@�����̏�Q��h�����߂ɁA���ː����E�f����荞�ޑO�ɍb��B�����E�f�ŖO�a���Ă����̂����胈�E�f�ܕ��p�̖ړI�ł���B���������Ĉ��胈�E�f�܂̕��p�̌��ʂ͂��̕��p�̎����ɂ���A���ː����E�f�z�����O�̓��^���ł����ʂ��傫���B�܂��A���胈�E�f�܂͕��ː����E�f�̐ێ�ɂ������픘�̒ጸ�ɂ̂��ʂ�����B�]���Ĕ픘�㕞�p���Ă����ʂ͂Ȃ��B
�@���胈�E�f�܂�z�z�����ۂɁA���̕��p�Ɋւ���K��͗\�ߊe�����̂ɒʒB���Ă������͂��A���A���m���̎w���𒉎��Ɏ���ĕ��p�̃^�C�~���O���Ă��܂����e�����̂ɐӔC�͂Ȃ��̂��B
�`�F���m�u�C���������́i1986�N4��26���j
�@1990�N�ȍ~�A�x�����[�V�A�E�N���C�i�A���V�A�̎O�����ɂ����鏬���̍b��B���̒������������m�F����Ă���B
�@1995�N���܂łɎO�����Ŗ�800�l�̏������b��B���̎��Â��A���̂����������A�x�����[�V���a���ɏW�����A�O�Ȏ��Â��Ă���B
�@�����̓\�A�M�ł����ă\�A���{�͌������̂��̂��̂����\�����ɂ����̂ŁA���̎O�����͈��胈�E�f�܂̕��p�w���͏o���Ă��Ȃ������B
�@���̈���A�|�[�����h���{�͌������̂̑�����₢�Ȃ⍑���Ɍ����Ԑ���z���A�q������邽�߂ɑS����ĂɈ��胈�E�f�܂�z�z�����p�������B���̌��ʂ̓|�[�����h�����Ŏq���̍b��B�����Ǘ�͂Ȃ������Ƃ����B
 |
 |
�@�b��B���̎��Â����̂�800�l�Ƃ��邪�A����͌��\���ꂽ���̂ŁA���A�̒����ɂ��ƁA�q���𒆐S�Ƃ��Ė�6��l���b��B���ɂȂ����Ɣ��\���ꂽ�B
�@�`�F���m�u�C�����̂ł̔��̍b��B�픘�͕���490�~���V�[�x���g�������ƍ��A�͔��\�����B50�~���V�[�x���g�ȏ�ŁA�b��B���̃��X�N���オ��Ƃ���Ă���A���ۓI�ɖh��܂p������50�~���V�[�x���g�ɐݒ肳��Ă���B
�@�b��B�픘���A�S�g�ւ̌��N�e���Ɋ��Z����ƁA�S�g�͍b��B��1/20�ȉ��ɂȂ�B
�@�x�����[�V�ł͍b��B���̊O�Ȏ�p���s��ꂽ���A��w�I�������Ⴍ�A�ɑ傫�ȏ��Ղ��c���ĉ����ɂ͓�d�̋ꂵ�݂�^���Ă��܂����B
 |
�@�����ŗ����オ�����̂��b��B����p�̑��l�҂������M�B��w��w���y�����̐��J�����m�ŁA�E�������ĒP�g�x�����[�V�֕��C���A�ŐV�̈�p���w�����A������������ď��Ղ��c��Ȃ���p���s�����B
 |
| �i���J�����͌��ݒ��쌧���{�s������ځj |
�@����̒����ς̌`�ŕł́A�ً}���̏��`�B�Ɏ��s�������{����Ôǂƈ��S�ψ���A���^�f�����������ɂ��S��炸���p�w�����o���Ȃ��������m���ɁA�����픘�����炷�������Ȃ������ӔC�͏d�傾�Ǝw�E�����B
�@���⌧�́u100mSv�ȉ��̔픘�ł͖��炩�Ȍ��N��Q�͕���Ă��Ȃ��v�Ƃ��A�N20mSv������̌�������Ƃ���B���������́A100mSv�ȉ��ł����ʂɉ����Č��N�ɉe���͏o��Ƃ�������ŏZ���̌��N�h��������ׂ����Ɩ��L�B���Ɏq����D�w�ɂ��Ă̓`�F���m�u�C���������ӂ̊�ɔ�ׂĂ��u20mSv�͍�������v�Ɣᔻ�����B
�@���݁A���͌����̎��̌�̊O���픘���ʂ̐��v��18�Έȉ��̎q�̍b��B�����Ȃǂ̌��N�Ǘ����������{���Ă���B�������A�����픘�̒����͍��������u�ˑR�Ƃ��Ăقږ���̂܂܁v�Ǝw�E�����B
�@���̍ŏI�������\�����ƁA�C�O����傫�Ȕ������������B����͎��̒����ς̕������{���Ɖp���̓�킠��A�p���̕��ɂ́u���{�����͓��{�ɐ��݂����K���╶���ɂ���v�ƋL�ڂ���Ă������A���̓_���d�������p�Ẵ��f�B�A�́u���̖̂{��������点��v�Ɣᔻ�����B
�@�����u�l�Ёv�f�肵�����Ƃ͕]��������u�N���~�X��Ƃ����̂�����肵�Ă��Ȃ��v�u�W�c��`�������v�u�ӔC���闧��ɑ��̓��{�l���A���Ă����Ƃ��Ă��A�������ʂɂȂ�\���͏\������v�ƍ���̑�S���ł��ꂼ��̕���ŐӔC���闧��ɏA���Ă����l�B�̐ӔC��Nj����邱�ƂȂ��A�������ėi�삷��悤�ȕ��ɔᔻ���W�������B
�@�u���{�����ɍ��������K����K���A���Ђɏ]���ȓ��{�l�̍����������̂��g�傳�����v�Ƃ���_���������A�u���{�I�ȑ�S���v�Ƃ���_�������������B
�@�^�C���Y���́u���ɓ��{�I�ȑ�S���v�̌��o�����f���A�u�߂��͓��{�����S�̂ŋN���������̂ł͂Ȃ��A�l���ӔC���A�ނ�̕s��ׂ���������ׂ����̂��B�W�c�ŐӔC�������ł͖������z���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƙ_�����B
�@�K�[�f�A�����u�t�N�V�}�̎S���̒��S�ɂ��������{�����̓����v�Ƒ肵�A�����̊��K�⌠�ЂɐӔC����Ȃ��p�������̌����̈�[�ɂ��邱�Ƃ��������A�ӔC�̏��݂�L�떳��ɂ��Ă��܂����{�����̓��������e���Ă���B
�@�s��ׂ͔ƍ߂ł���A�Ƃ����@���̋K�肪����ɂ��S��炸�A�S�����̐ӔC��₤���ƂȂ����e���Ă��܂����{�ɍ��t���������O���l�ɂ͕s�v�c�ȕ����Ɗ����Ă���B
�@�m���Ɋ댯����F�����Ă��Ȃ���摗�肵�Ă������d�����A���̎�����ٔF���Ă������q�͈��S�E�ۈ��@�A�ꕔ�����ƁB�N��l�Ƃ��ĐӔC�����邱�ƂȂ��A���z�̑ސE������ɂ��āA�������V�����܂ŗp�ӂ��đՂ������čs�������d�����A�������͐�ɐӔC�����邱�Ƃ͂Ȃ��A����ٓ��ŋ����čs�����B�Ɩ��W�Q�̂悤�ȋ��s�������������邾���̍s�ׂł����������Ƃ��j�R���J�j�ɂ��Ĕ��Ȃ̐F�T���ɂȂ��B�ӔC�ϔO�Ȃ킪���̓��������ɕ��ꂽ�Ƃ����������B�������u�ӔC���闧��ɑ��̓��{�l���A���Ă����Ƃ��Ă��A�������ʂ������\���͏\������v�Ƃ����L�q�ɂ͐ӔC�̂���ł����Ȃ��Ǝa��̂Ă��B�����͓��{�l�Ƃ͂��̒��x�ł����Ȃ��Ǝ��s�I�Ȍ����������Ă��邾���Ȃ̂������ɋꂵ�ށB
�@�u�`�F���m�u�C���������̂̌�ŁA�ߌ��I�ɂ��A���{�̐����ƁA�ēȒ��A�d�͉�Ќo�c�ҁA�Z�p�҂͎��̌������\�A�̐v��^�p�ɂ���Ɣ��f���A���{�̌����̈��S���������邱�Ƃ�ӂ������B���E�̌����̓t�N�V�}�������̂Ɋw�сA���̉߂����ɌJ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ���ł���B
�@�X�ɂ�����_�A���̕��Łu�l�Ёv�ł��邱�Ƃ��������꤈�ʍ����͗ǂ������Ă��ꂽ�Ƃ��̕���]����������O���ł̎����͈���Ă����B
�@�l�Ђ��������邱�Ƃ́uHuman error�v���������Ă��܂��A�����̋@��E���u�͐���ɉғ����Ă������A�^�p���Ă����l�ԂɃ~�X�����������玖�̂��N�����̂��Ǝ��ꂩ�˂Ȃ��A�^�p�҂��m��Ǝ��g��ł����玖�̂͋N���Ȃ������ƂȂ�A���̌����̋����Ɋւ��l�Ђɔ�d���ڂ��Ă��܂��Ƌ@��E���u�̋����E�������a���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����O�����B
�@�l�Ђ͖ܘ_�����A�����@��E�{�݁E�ۈ��E���S�̑S�Ăɑ��Ă��T�d�ȍČ����E�ē_�������肢�������B
�@���������Ɣ�s�@���̂̏ꍇ�A�ė�������������Ƃ̒����ψ����I�C���꒲�������邪�A�R�N�s�b�g�̑S�������S���Ă���Ⴊ�����A�ő�̎�|����̓{�C�X���R�[�_�[�����ɂȂ��Ă��܂������͓�q���邪�A�ߋ��̗�Ƃ��ďI�ǓI�ɂ̓p�C���b�g�̑��c�~�X�������Ƃ���������������B����Human error�ł���B
����̒����ψ���ψ����@���쐴
�@1936�N���A������w��w�����A��w���m�A�J���t�H���j�A��w���T���[���X�Z��w�������A�����w�������A���C��w��w�������A���{�w�p��c19�����C�B���{���t�A���c���t�ł͓��t���ʌږ�߁A2011�N�A����݂��������d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̒����ψ���̈ψ����ɔC�����ꂽ�B
�@���A������w�@��w�A�J�f�~�b�N�t�F���[�B
�@�h�T
�@1999�N�@�����J��
�@2011�N�@�����d���́@���
 |
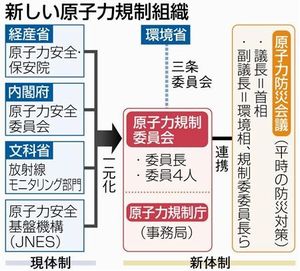 |
 |
�NjL
�����o�������w��
�@3��11���@�ߌ�9���@��ꌴ������3km�����ɔ��w����
�@3��12���@�ߑO2���@���p�Ƃ��ē���100��̃o�X�m�ۂ��w��
�@3��12���@�ߑO3���@1���@�̊i�[�e����̈��͂������邽�ߕ��ː��������܂�
�@�@���C���z���ɕ��o����u�x���g�v���s���Ɣ��\
�@3��12���@�ߑO5���@���a10km�����Ɋg�傷��Ɣ��\
�@3��12���@�ߑO6���@�ז�⍲�������ڑ�F�������10km�������w��
�@3��12���@�ߌ�3��36���@1���@�ōŏ��̐��f�����A�t�ߏZ���͏d��Ȏ��̂��N�������ƂŊ������B
�@3��12���@�ߌ�6��18���@���w���͈͂a20km�����܂Ŋg��
�@����ȍ~�A14��15���ɂ����āA3���@�A2���@�A4���@�����X�Ɣj��ʂ̕��ː����������o���ꂽ�A�����w����15���ߑO11���Ɂu20km�`30km�����̏Z���͉����Ҕ��v�̎w�����lj����ꂽ�̂݁B
�@���{�Ƃ��Ă͒n�}��ɔ��a20km�A30km�̐�����������ŗǂ������m��Ȃ����A���w���𖽂���ꂽ�����̂ɂ��݂�ΐ��m�Ȑ����ǂ�����Ĉ����Ηǂ��̂�����͂����Ȃ��A���w�����o���Ȃ�s����P�ʂŏo���̂����R�����A�ً}�����}�b�v���������Ă����ׂ��͂��̊�@�Ǘ��̊ϔO�͂Ȃ��B
�@�X�ɐ��{��20km��30km���̒����Ɏw�����o�����Ƃ��Ă��邪�A���ۂ͓��Y�����̂̒��͂��̂悤�Ȏw�����Ă��炸�A�e���r����̋ٔ����������Ă���̂����ď��߂Ēm�����Ƃ������u��Ԃ������炵���B
�@�d�b������n�k�ʼn�ŁA��펞�̖����d�b���g�p�s��ԂƂȂ�ΘA����i���Ȃ��A�ً}���̑�̒x�ꂪ����܂�邾���B
��\��́@�ڂ݂�
�@�u�����j��A���߂č���ɐݒu���ꂽ�Ɨ��@�ցv�Ƃ��đ��̒�����i�����d�́A���{�A���ԁj�̒����ψ�����ݍ��߂Ȃ������A���@�̏����̐ق��A���d�{�Ђ̑g�D�I�������e���u���̂͐l�Ёv�ƌ��_�t�������Ƃ͕]���ł���B
�@�������A�����o��������A���̕������Ă����̂��A���̌����̉𖾂ƍĔ��h�~�ɒ������ʂ��ǂ��������Ă�����̂��A����̒��̐ݒu�����ƂȂ����@���ł́A���@�c���ɕ����o����܂ł����L�ڂ���Ă��Ȃ�����A�����̐��ʂ��ǂ��������̂��͍���c���B�̎��g�ݔ@���ɂ������Ă���B
���̗v��
�@�l�X�̖��ƎЉ�����Ƃ����ӔC���A�o��̌��@�����̌����ɂ���B
�@�����d�͕�����ꌴ�����̂������鍑��̒����ψ���̕��́A�ߋ��̈��S��⎖�̑Ή����������ᔻ�����B���̂�h�����\����A���{�Ɠd�͋ƊE�̑̎��ɂ��荞�B
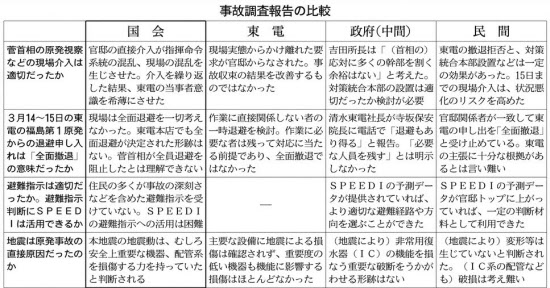 |
�������̂͐l��
�@�u����̎��̂͌����āw�z��O�x�Ƃ͌������A�ӔC��Ƃ�邱�Ƃ͏o���Ȃ��v
�@�n�k�A�Ôg�A�ߍ����̂̂�������̑�ɂ��Ă��A���d�A���q�͈��S��ۈ��@���댯����F�����Ă��Ȃ��炻�̑��摗�肵�Ă������Ƃ�˂��~�߁A���̓_���������w�E�A�u�����K���ɑ���u���Ă����Ȃ�Ύ��͖̂h�����\�����傫���v�Ƃ����B
�@�u���d�̍ō��ӔC�҂Ƃ�������ł���Ȃ���A�����Ǝ��g�ނ��Ƃɂ���ĐӔC��]�ł���X�������������d�̍����I�Ȍo�c�̎�����B���ȘA���ɏI�n�����v�Ƃ����Ƃ��ē��d�̌o�c�̎��܂œ��ݍ��B
�@����ɓ��d�ƋK�����ǂ̂�����ɂ����ݍ�����u�K�����闧��Ƃ���闧��́w�t�]�W�x���N���A�K�����ǂ͓d�͎��Ǝ҂́w���x�ɂȂ�A���̌��ʁA���q�͈��S�ɂ��Ắ@�ē@�\�͕��Ă����v�Ǝ��Ǝ҂ƋK�����ǂ������ꂠ���Ă���\�}�ɓ��ݍ��B
���n�k��
�@�n�k��ł́A2006�N�ɉ������ꂽ���̐V���������ϐk�w�j�ɑ��铌�d�̑Ή��̒x����w�E�����B
�@���d�́A������ꌴ����V���j�ň����グ���z��ɓK�������邽�߁A�ϐk�⋭�H���ɖ�800���~�̔�p���K�v���ƌ��ς����Ă����B�������A�ꕔ���{�����݂̂ŁA�̐S��1�`3���@�͑S�����{���Ă��Ȃ������B
�@���ւ̍ŏI������09�N6���Ɠ͂��Ă������i�܂��A������16�N1���ɐ摗�肷�邱�Ƃ����肵�Ă����B
�@�ϐk�̗]�T���[���ɂ��邱�Ƃ������̂�����������߁A�X�P�W���[���͌��\�ł��Ȃ������悤���B
�@�ē����ł��������q�͈��S�E�ۈ��@�́A�����܂ł����Ǝ҂̎���I�Ȏ��g�݂ł��邩��Ƃ��ĖٔF���Ă����B
���Ôg��

�@�Ôg��ɂ��ẮA���d�����咣����u�z��O�v�A�z�����Ôg�̔����z�ł��Ȃ������Ƃ��Ă������A�����^��������ے肵���B
�@�u�z��Ôg���ɒ����Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��v�u�z��O�ł��郌�x������ƘF�S�����Ɏ��邱�Ƃ����O���Ă���v07�N4���ɂ������d�͑��ƕۈ��@�̒Ôg��Ɋւ���@�ł����킹��c�ł̔����L�^�ł���B
�@06�N���_�ŕۈ��@�͓d�͉�Ђɑz�����Ôg������A�F�S�����Ɏ���댯��������Ǝw�E�����B�����������Ŏw�E���������ŕ����ɂ͂��Ă��Ȃ������炵���B�]���ĒS���ӔC�҂ɓ`����Ă��A���d�o�c�w�ɂ͓͂��Ă��Ȃ��B

�@�z��O�Ƃ����n�k�A�Ôg�̔����̉\���͑������_�Ŏw�E����A���̑���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�ۈ��@�A�d�͉�Бo�����F���A���O���Ă��������������̂ŁA���̌��O������J�̏�ŕs�����ł��������Ƃ�A��̎��{���ɖ���������A�摗�肾������ƁA�z��O�̎��Ԕ����ŋN����ł��낤�ߍ����̂ւ̑Ή����Ȃ������B
�@����������œI�Ȏ��ۂ��N�����ł��낤���̃V�i���I�ւ̑Ή��͑S���Ȃ��Ă��Ȃ������A�ƕ��͒f���Ă���B
�@���ۓI�ɂ͂ǂ����A���ې����I�ɂ͂ǂ����B
�@���Ăł͋@��̌̏�Ȃǂ́u��������v�ɉ����A�n�k�A�^�����́u�O������v�A����ɁA�e���̂悤�ȁu�l�דI���ہv�ɕ����đ���u���Ă���B
�@�킪���́u�O������v�͒n�k�݂̂��ΏۂŒÔg�͑ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ��B�l�דI���ۂ͂��蓾�Ȃ��ƑΏۊO�ƂȂ��Ă���B
�@���������Ăł͎�ȑ�ł͍��̋K���ɂ���ċ����͂����邪�A�킪���œd�͉�Ђ̎���K�������������B
�@���q�͈��S�ψ���̔��ڏt���ψ����́u�킪���ł͍��ۓI�Ȉ��S��ɑS���ǂ����Ă��Ȃ��B����Ӗ��ł�30�N�O�̋Z�p�������ň��S�R�����s���Ă���v�Ǝw�E���Ă��邪�A����܂łɈ��S�ψ���̈ψ��������{�ɑ��Ăǂ̒��x�̕����o���Ă����̂��A���{�����������̂��A���͓d�͉�Ђ��ēE�w���̌�����������Ă����̂��B
�u�K�����������A�Ď���������ԁA���d�̗��ɂȂ��Ă����v
�ƕ��ł͎w�E���Ă���B�@
�@���̍ŏI�������\�����ƁA�C�O����傫�Ȕ������������B����͎��̒����ς̕������{���Ɖp���̓�킠��A�p���̕��ɂ́u���{�����͓��{�ɐ��݂����K���╶���ɂ���v�ƋL�ڂ���Ă������A���̓_���d�������p�Ẵ��f�B�A�́u���̖̂{��������点��v�Ɣᔻ�����B
�@�����u�l�Ёv�f�肵�����Ƃ͕]��������u�N���~�X��Ƃ����̂�����肵�Ă��Ȃ��v�u�W�c��`�������v�u�ӔC���闧��ɑ��̓��{�l���A���Ă����Ƃ��Ă��A�������ʂɂȂ�\���͏\������v�ƍ���̑�S���ł��ꂼ��̕���ŐӔC���闧��ɏA���Ă����l�B�̐ӔC��Nj����邱�ƂȂ��A�������ėi�삷��悤�ȕ��ɔᔻ���W�������B
�@�u���{�����ɍ��������K����K���A���Ђɏ]���ȓ��{�l�̍����������̂��g�傳�����v�Ƃ���_���������A�u���{�I�ȑ�S���v�Ƃ���_�������������B
�@�^�C���Y���́u���ɓ��{�I�ȑ�S���v�̌��o�����f���A�u�߂��͓��{�����S�̂ŋN���������̂ł͂Ȃ��A�l���ӔC���A�ނ�̕s��ׂ���������ׂ����̂��B�W�c�ŐӔC�������ł͖������z���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƙ_�����B
�@�K�[�f�A�����u�t�N�V�}�̎S���̒��S�ɂ��������{�����̓����v�Ƒ肵�A�����̊��K�⌠�ЂɐӔC����Ȃ��p�������̌����̈�[�ɂ��邱�Ƃ��������A�ӔC�̏��݂�L�떳��ɂ��Ă��܂����{�����̓��������e���Ă���B
�@�s��ׂ͔ƍ߂ł���B�Ƃ����@���̋K�肪����ɂ��S��炸�A�S�����̐ӔC��₤���ƂȂ����e���Ă��܂����{�ɍ��t���������O���l�ɂ͕s�v�c�ȕ����Ɗ����Ă���B
�@�m���Ɋ댯����F�����Ă��Ȃ���摗�肵�Ă������d�����A���̎�����ٔF���Ă������q�͈��S�E�ۈ��@�A�ꕔ�����ƁB�N��l�Ƃ��ĐӔC�����邱�ƂȂ��A���z�̑ސE������ɂ��āA�������V�����܂ŗp�ӂ��đՂ������čs�������d�����A�������͐�ɐӔC�����邱�Ƃ͂Ȃ��A����ٓ��ňڂ��čs�����B
�@�Ɩ��W�Q�̂悤�ȋ��s�A������������邾���̍s�ׂł����������Ƃ��j�R���J�j�ɂ��Ĕ��Ȃ̐F�T���ɂȂ��B�ӔC�ϔO�Ȃ킪���̓��������ɕ��ꂽ�Ƃ����������B�@�������u�ӔC���闧��ɑ��̓��{�l���A���Ă����Ƃ��Ă��A�������ʂ������\���͏\������v�Ƃ����L�q�ɂ͐ӔC�̂���ł����Ȃ��Ǝa��̂Ă��B
�@�����͓��{�l�Ƃ͂��̒��x�ł����Ȃ��Ǝ��s�I�Ȍ����������Ă��邾���Ȃ̂������ɋꂵ�ށA�Ƃ܂Ō��y���Ă���B
�@�u�`�F���m�u�C���������̂̌�ŁA�ߌ��I�ɂ��A���{�̐����ƁA�ēȒ��A�d�͉�Ќo�c�ҁA�Z�p�҂͎��̌������\�A�̐v��^�p�ɂ���Ɣ��f���A���{�̌����̈��S���������邱�Ƃ�ӂ������B���E�̌����̓t�N�V�}�������̂Ɋw�сA���̉߂����ɌJ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ���ł���B
�@�X�ɂ�����_�A���̕��Łu�l�Ёv�ł��邱�Ƃ���������A��ʍ����͗ǂ������Ă��ꂽ�Ƃ��̕���]���������A�O���ł̎����͈���Ă����B
�@�l�Ђ��������邱�Ƃ́uHuman error�v���������Ă��܂��A�����̋@��E���u�͐���ɉғ����Ă������A�^�p���Ă����l�ԂɃ~�X�����������玖�̂��N�����̂��Ǝ��ꂩ�˂Ȃ��A�^�p�҂��m��Ǝ��g��ł����玖�̂͋N���Ȃ������ƂȂ�A���̌����̋����Ɋւ��l�Ђɔ�d���ڂ��Ă��܂��Ƌ@��E���u�̋����A���x�A�̐��̒������a���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����O�����B
�@�l�Ђ͖ܘ_�����A�����@��E�{�݁E�ۈ��E���S�̑S�Ăɑ��Ă��T�d�ȍČ����E�ē_�������肢�������B
�@���������Ɣ�s�@���̂̏ꍇ�A�ė�������������Ƃ̒����ψ����I�C���꒲�������邪�A�R�N�s�b�g�̑S�������S���Ă���Ⴊ�����A�ő�̎�|����̓{�C�X���R�[�_�[�����ɂȂ��Ă��܂������͓�a���邪�A�ߋ��̗�Ƃ��ďI�ǓI�ɂ̓p�C���b�g�̑��c�~�X�������Ƃ���������������B����Human error�ł���B
�@��������ƍq��@���̂������ׁA���邢�̓V�X�e���̌��ׂ����߂�����Ă��܂����Ƃ������B
�@�����C��R���Ɍg����Ă������A�C��̂̏ꍇ�A����A�����ꂽ��A�؋������͊F���̏ꍇ�������A�X�ɑS������A�܂��͓����Ҏ��S�̏ꍇ�������R������a���邪�A���D�~�X�iHuman error�j�Ō��R����̂ɂ͒�R�����������B
���d�P�ޖ��
�@���d�̍ō��ӔC�҂ł��鐴���В����A���@�֑S���P�ނ�\���o���Ƃ������ŁA���@���͂����������A���d���͂��̂悤�Ȑ\������͂��Ă��Ȃ��ƑS�ʔے�ł��������A������ς̎Q�l�l���v�ōő�̏œ_�ɂȂ����̂́A��N3��14���邩��15�������ɂ����Ă̊��@�Ɠ��d�����В��̂��Ƃ�ŁA���ł́u����͑S�ʓP�ނ���؍l���Ă��Ȃ������v�Ƃ������R�������A�S�ʓP�ޖ��͊��@���̑��Ƃ���ɂ�����ł������ƌ��_�t�����B

�@15�������A���͓��d�{�Ђɓ{�荞��ōs�������Ƃ͑傫�����ꂽ���A���̈�A�̍s���ɂ���āu�S�ʓP�ނ�j�~�����v�Ƃ��������͔F�߂��Ȃ��B�������Ȃ���Γ��{�͐[���Ȋ�@�ɔ�����Ă����Ƃ����X�g�[���[�͕s���R������B�Ɛ�̂āA����Ɂu���d�ɓ������{����ݒu���Ă܂ʼn���𑱂������@�̎p���͗�������v�Ƌ����ᔻ���Ă���B
�@�����̊��@��K�����ǂ̊�@�Ǘ��ӎ��̒Ⴓ���M��ᔻ���āA�u�@�Ǘ��̐��͋@�\���Ȃ������v�Ɗ��@���̑Ή��̐ق���ᔻ�����B
�@���������d���̐����В��̑S�ʓP�ޖ��Ō���ő�̌����́A�����В��̃R�~���j�P�[�V�����̎����ɂ��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������Łu�Œ���̐l���͎c���v�Ƃ����d��Ȏ�����`����ꂸ�A�B���ŗv�̂Ȃ������ɏI�n�������Ƃ�����ő�̗v���ł���B
�@�u���d�̍ō��ӔC�҂Ƃ�������ł���Ȃ���A�����Ǝ��g�ނ��Ƃɂ���ĐӔC��]�ł���X�������������d�̍����I�Ȍo�c�̎�����B���ȘA���ɏI�n�����v�Ƃ����Ƃ��ē��d�̌o�c�̎��܂œ��ݍ��B
�@����ɓ��d�ƋK�����ǂ̂�����ɂ����ݍ���Łu�K�����闧��Ƃ���闧��́w�t�]�W�x���N���A�K�����ǂ͓d�͎��Ǝ҂́w���x�ɂȂ�A���̌��ʁA���q�͈��S�ɂ��Ắ@�ē@�\�͕��Ă����v�Ǝ��Ǝ҂ƋK�����ǂ������ꂠ���Ă���\�}�ɓ��ݍ��B
���̌�
�@���d���̂���܂Œn�k�ɂ��d�v�@��̑����A�j���͂Ȃ��A���̌�̌�������ɖ��͖��������Ǝ咣���Ă����B����������̒��̕ł́A�ً}���Ɍ��q�F���₷�@�킪�n�k�ʼn�ꂽ�\��������A����ɂ���ė�p�����R���̂�|��āA�^�]�������u���~�߂��Ǝw�E�����B
�@11�N12��15���ɐV���ɃX�b�p�����ꂽ���A���d���͉��߂đS�ʔے�A1�`3���@�̌��q�F�̘F�S�n�Z�́A�Ôg�ɏP��ꂽ���ƂŔ��p�d�������āA���q�F����p�o���Ȃ������ׂ��Ǝ咣���Ă����B
�@�Ƃ��낪�A���d���咣����Ôg�̓��B�����́A���̒������ׂ����B�����ƈقȂ�A���d�̒Ôg�����B�����d�����j�ꂽ�Ǝ咣���鎞���ɂ́A���ۂɂ͌����̉���1.5km�ɓ��B���Ă����������Ǝw�E�����B
�@�]���āA�Ôg�����B����O�ɁA���Ɉꕔ�̔��p���d�@�͋@�\���Ȃ��Ȃ��Ă����\���������Ǝw�E�����B
�@�ŏ��̘F�S�n�Z���N������1���@�̔��p������iIC�j�ɂ��Ă����d�͒n�k�ɂ��j���͖��������Ǝ咣�A�n�k����Ɍ��q�F�̈��͂��}���ɉ������Ă��Ȃ����Ƃ��疾�炩���Ƃ����B
�@�������A����̒��̕��ɂ́AIC�̔z�ǂŏ����Ȕj�f���N���Ă����\���������Ǝw�E�A�����Ȕz�ǔj�f�Ȃ爳�͉͂�����Ȃ��Ƃ������q�͈��S�@�\�̉�͂������u���d�̐����͕s�����ł��邱�Ƃ͖����v�Ƃ����B
�@����IC�ɂ��āA�^�]���͒n�k�ƒÔg���P���ė���Ԃɉ^�]�ƒ�~���J��Ԃ��Ă����B���̎�IC���~�߂��ɓ����������Ĉ�C�ɘF�����₵�Ă����玖�̂̊g���h�����\�����������Ǝw�E�A���������d�͎菇���ɏ]���čs�����������Ŗ��͖����Ƃ����B
�@����������̒��͂����ے�A�^�]����IC�̔z�ǂ����p�����R��Ă���̂ł͂Ȃ����ƐS�z���m�F�����邽�߂Ɏ~�߂��Ɛ��肵���B
�@�܂��A1���@�̌��q�F�̈��͂����������C�����ق��쓮���Ȃ������\�����w�E�B�^�]���̒�����蒲���ŁA�ق̍쓮����N�������Ă��Ȃ����Ƃ������B�n�k�Ŋ��ɔz�ǂ��j�����A�ق������Ȃ������\��������Ƃ����B
�@�i�[�e��̈��͂�������r�C�i�x���g�j�́A����P���͈�x���Ȃ��A�d���̂Ȃ����ŏ\���Ȑ}�ʂ��Ȃ�����͓�������Ƃ����B
�@���ʂƂ��Đ��f������h�����Ƃ͏o���Ȃ������ƌ��_�t�����B
�@���q�F���͕��ː��ʂ������A���㐔�\�N�ɂ킽���Č��q�F���̏����ڊm���߂��Ȃ��ɂ��S��炸���d������������Ôg�����ɋ��߂āA�n�k�̉e�����ߏ��]������̂́u���ݘF�ւ̉e�����ŏ������悤�Ƃ����l�������d�o�c�w�ɂ��邩�炾�v�ƒf�߂����B
�@���́u�n�k�ʼn�ꂽ�v�Ƃ���̂��\���������������ŁA�f�肷��ɂ͖����m�͂Ȃ�
����^���̂̐���

�@������ꌴ�����̂������Ă݂�B�����̋K�͂Ƃ��Ă̓`�F���m�u�C�����̂ŕ��o���ꂽ���ː������̗ʂ̖�1�����x�ł��������A���ێЉ�ɗ^�����Ռ��̓`�F���m�u�C�����̂���ꡂ��ɑ傫�ȏՌ���^�����B����́A�`�F���m�u�C�����̂�1��̔��j�ł���A���������̏u�Ԃ𐢊E�͊֒m�ł����A�\�A���{�i�����j�̔��\���Ȃ���������A���̍ŏ��͖k���e�n�̌��q�͔��d���ɐݒu���ꂽ���ː����m��̌x��ɂ����̂ŁA���̌�̓̕\�A���{�����E�̃}�X�R�~�Ƃ̐ڐG�����ہA����t�߂ւ̗�����������₳�ꂽ�̂ŁA�ɂ����E�����������Ƃ͊m���ł���B
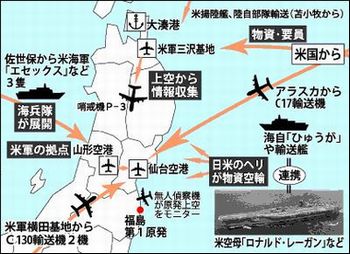 |
 |
�@�Ƃ��낪������ꌴ�����̂́A�����{��k�Ђł̋���ȒÔg�̐��܂����f�������A���^�C���Ő��E���ɔz�M����A���E���̐l�X���e���r�̑O�ɓB�t���ɂȂ��Ă����B�@�X�Ɏ����̋~���������X�Ɣh������A�����̋~���������f���炵����������Ă���邾�낤�Ɗ��҂������Ă��ꂼ��̍����͒������Ă����B
�@�����֑��̏Ռ��Ƃ��Č��q�͔��d�������̉f���������ꂽ�̂ŁA�e���͔픘��|��~�����������Ԃ�����Ƃ̔ߖ��グ���B������]�v�Ɍ������̂̉ߏ蔽�������������ƂɂȂ�B
�@���̑�ꌴ�����̂͌���^�̎��̂ŁA���E�������ڂ��钆�Ŏ��̂̐i�W������A���E��������J���Ă������̂�����A���{���{�A�����d�͂̑�̋����]�v�ɖڗ����A���������B
�@�䂪���̕����Z�p�͐��E�ł��ꗬ�̋Z�p�Ɛݔ���L���Ă��邩��24���ԃ��A���^�C���ł��������E�ɔz�M����A�܂��ɐ��E�������{�Ɠ������ԁA�����f�����e���r�Ō��邱�Ƃ��o�����̂�����A�܂��Ɍ���^�̎��́A�����ł������B
�@����������ɋ����킹����Ў҂�����J�����Ў�ɒÔg�̏�i���B�e�����̂��������W�܂�A������ҏW���ĕ��f��������A�܂��Ɍ��ꒆ�p�̂悤�ȃ��A�����Ő��E�ɓ͂���ꂽ�B
�@�O������̎�ސw�����������ɂ���Ă������A����ɂ͋߂Â����Ƃ��o���Ȃ��A���{���\�ł���ۈ��@�̃X�|�[�N�X�}���̉�̓V�h�����h���A�������I�h�I�h�Ɨ]�قǔ��\�̓��e����������Ă���̂��A�㕔����̈��͂��������̂��A�����������ʖ�͂Ȃ��B���{�l�����Ă��Ă��C���C������悤�Ȓt���ȑԓx�A�O���l���h�����ސw�����͓̂��R�A�̓��e���ᔻ�I�ɂȂ�̂�����܂����R���B
�@�ő�ɋ����͊O���l�̋L�҂��吨�l�߂Ă���̂ɂ�������炸�ʖ��p�ӂ��Ȃ��s��ۂ��A�җ�ȓ��{���{�ᔻ�������Ă����R�A�Ƃ��낪�X�Ɏ�ނ�i�߂�ƁA���{���{�̏����J���������s�����ł������̂́A���{���{�������B�����Ă����킯�ł͂Ȃ��A���{�͂�����������c���ł��Ă��Ȃ������̂��^���A�ƒf�����A���{���{�̖��\�Ԃ肪�\�I���ꂽ�B
�@�����ĊO�����f�C�A�͎��ɂ�����͍̂ň��̎��ԁA�����g�_�E���Ǝ��Ă����B�����炱���A���̏��ɂ����Ă�����𗣂ꂸ�A�撣��uFUKUSHIMA 50�v���p�Y�Ǝʂ����̂��낤�B

�@���{�l���猩��ΐE��Ŋ撣��͎̂��ɓ��R�̂��ƁA�Ɨ�߂����������Ă������A�O���l���猩��ΖŎ�����͋��قł����Ȃ������B�����琢�E�����uFUKUSHI 50�v�ɔM�������𑗂�A�����Ē����������Ԃ��o�ĂȂ�Ƃ����܂肻�����Ƃ̌������������Ƃ��A���E�����uFUKUSHIA 50�v�ɂ܂��ɃX�^���f�B���O�I�x�[�V���������B
�@�uFUKUSHIMA 50�v�̊F����u�A���K�g�E�v

�@�j���[���[�N�^�C���Y���̓A�����J���������{�l����w�Ԃׂ����ƁA�Ƃ��ĕ�����1�����̎��̏����̍�Ƃ���l�X���u�����̐��_�A���ȐS�ƋK���v�Łu�s�������킸�A�����̍�ƈ��v���A�����ɔ�Q���y�Ԃ̂�h�����ߖ���q���Ď����ɗ����������Ă���A�Ɛ�^���A�����ɓ����{��k�Ђ̔�Ў҂̐��R�Ƃ��������A�܂��������̂ƒÔg�̓�d�̔�Ђ����n��Z���������Ɏ���I�ɒ����ǂ������B
�uFUKUSHIMA 50�v�̃^�C�g���Ő��E���̃��f�B�A����^���A�����A���q���A�x�@�A���h�̑�\���X�y�C���ɏ��҂��c���q�܂����^���A���̌��g�I�ȍs����\�������B
�uFUKUSHIMA 50�v�i�t�N�V�}�E�t�B�t�e�B�j��A�u������50�l�v�̈Ӗ������A������ꌴ�����̔����̌������Ɏc���Ď��̂̊g���H�~�߂悤�ƕK���ɂȂ��ē����Ă���l�X�A50�l�̍�ƈ����Ӗ����邪�A50�l�Ƃ͉��Ẵ��f�B�A���^�����ď̂ŁA���ۂɌ���Ŋ����l���Ƃ͖��W�A��C���킹�Ƒ����ɑ��h�̔O���܂߂�50�ɂ����炵���B
�@���Ẵ��f�B�A�́A����Ɏc���č�Ƃ𑱂��������̍�ƈ��̗E�C���q�[���[�Ǝ]���A�gFukushima 50�h�ƏЉ�A���E���ɒm��n�����B
���t�����X�uJapan's Faceless Heroes�v�i���{�̊炪�m��Ȃ��p�Y�B�j
���C�M���X�uOther nuclear power employee, as well as the wider population, can only look on in admiration.�v
�@�i���̌��q�͔��d���ɏ]�����Ă���ҒB�́A���̑����̐l�X�Ɠ��l�ɁA�����^�������Ă݂Ă��邱�Ƃ����ł��Ȃ��B�j
���h�C�c�ł́A�Ȃ�ƒ��b���́g�l�\���m�h�ɂ��Ƃ��āA���̌��g�U����^�����B
���A�����J�A�E�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i���́u�t�N�V�}50�v�����g�n��̐��h�Ǝ]�����B
 |
| �i�E�[�n���x���u���̎��o�t�����v�j |
��������̃j���[�X�T�C�g�͔ޓ����g����50���m�h�Ɩ��t�����B�i�ō��̗_�ߌ��t�j
���X�y�C���A���̉p�Y�I�s�ׂɁA2011�N9��7���A�X�y�C���c���q�܁i�A�X�g�D���A�X�c���q�܁j���܂����߂��B������ꌴ�����̂̈��S�錾���ł�A�m�[�x���܁i���a�܁j�̑I�l�L�͌��ɋ����邱�Ƃ͊m���ƕ��
�@���̂��炢���E�������ڂ��A��^���Ă��艢�Ăł̕]���͍����B
�@�܂��������ĂȂ����A�u�t�N�V�}�E�t�B�t�e�B�v���E����˔\��������~���A���E�ɗE�C���������������̐�m�B�ł��邱�Ƃ͊m���ŁA���E����^���Ă���A���N�̃m�[�x�����a�܂̗L�͌�₾�ƁA����͉��Ăł̉��n�]�����A�����ł̎^���̔����͑S���Ȃ��B
�@�u�t���̒��ŗE�C��g�����𐢊E�Ɏ������v�Ƃ��āA�X�y�C�������̍��c����ɂ��镽�a�W�̏܂��u�t�N�V�}�̉p�Y�v���\����`�ŁA���̌���Ŋ������q���A���h�A�x�@�̌���ӔC��5�l����\�ɑI��A11�N10��21���ɃX�y�C���E�I�r�G�h�ŊJ���ꂽ�����ɏo�ȁA�������x�{������͓n�Ӑ����x�����\�������B
�@���㎩�q����F�^�i�ꍲ�A�������i�A�x��������T���x���A�������x�n�Ӑ����x���A�������h���x���L�F���h�i�߁B
�@������ꌴ���̎��̌���ł́A�ǂ̈ʂ̐l�B�������Ă���̂��B
�@2011�N10��20���̕ɂ��ƁA���̎�����ƂƂ��ĘA����2,700�l�������Ă���܂��B
�@���S�͓��d�Ј��ł����A���̑��֘A�@�탁�[�J�[�A���ŁA�����AIHI�A�֘A��Ƃ̊֓d�H�A���d���G���W�j�A�����O�A�����d�͋��͊�ƁA�e�d�͉�ЁA���̑��A����̔h���A�x���̐l�B�A�ƕ�ꂽ�B
�@���̐l�B�𑩂˂Ă����̂��A�g�c���Y������ꌴ�q�͔��d�������ŁA�v���t�B�[�����Љ�܂��B

�@���a30�N���{���܂�A�����H�Ƒ�w�H�w�����ƁA�����H�Ƒ�w��w�@�A���q�j�H�w�A���a54�N�C���A�����d�͓��ЁA���q�͂̋Z�p������݁A�������A��d���̕ێ�ہA���j�b�g�ۂ��o�ĕ���19�N�ɖ{�X�i�{�Ёj�̌��q�͐ݔ��Ǘ������ɏA�C���܂������A����ɐV�������z�n�k�Ŕ��芠�H���q�͔��d�����������A���̎�����Ƃ̐ӔC�҂ɂȂ�A����ŕ����A���̌�A����22�N6���A������ꌴ�������Ƃ��Ċ҂��Ă����B���̐E��������悤�ɓO�ꂵ�Č����`�Ŕ|��ꂽ�Z�p�ҍ��ł��傤�B
�@�g��180cm�̑啿�ȑ̊i�Ŋw������̓{�[�g���Ŋ���A�����A�����ɂ͕����e�����A�\�����̂Ȃ�����̒��̂悤�ł��B
�@������`�ɓO���Ă����{�Њ�������́A�u���M�ߏ�v�u�{�Ђɏ|�˂��������z�v�ƌ����̂��]���������悤�ŁA�{�Ђ̂����Ƃ���B�Ɨ̒n���x�z����n���̂悤�ȊW�������̂��B
�@�����̘A�z�ł����A���풆�ߎS�Ȑ��ƂȂ����e�C���p�[�����f�ɂ������31�t�c�i��j�͍őO���ŃC�M���X�R�Ɛ���Ă������A�⋋���S���Ȃ��A�e��A�H�ʂ��s���A�Ǝ��̔��f�œP�ނ��n�߂����߁A�t�c�������K�������͑�15�R�i�ߊ����c�����璆���ɂ���čR���߂����A�e��E�ł���ɂ�������炸��E���ČR���ٔ��ɂ����悤�Ƃ����B�i�R�i�ߊ��ɂ��̂悤�Ȍ����͂Ȃ��j
�@31�t�c�͎t�c�����������܂܁A�P�ލ��ƂȂ������A���̓a�i����j��������c���ł������{��ɎO�Y����(�����A�㒆��)�������A���c����ۂƂȂ��Č����ȍ��Ő펀�ҁA�쎀�҂��������A���̗��s�s���܂���ʂ������{���R�ɂ����āA���R����ꕺ���܂ň�v�c�����Č������𐋍s�ł����̂͋{�藷�c���̍˔\�A�l���ɂ���A�����͂��̐l�̂��߂Ȃ牽���ł����˂�A�Ǝv���Ă������̓����͂����������炱���S�������҂ł����A�Ƃ������Ƃł����B
�@���A��15�R�i�ߎ�c�������͐��҂��A�V���Ŏ����������A���̕�͓x�X�Ђ�����Ԃ���鎖���������悤���B���҂��������m�B�́A��F��Ŗ��c���������b��ɂȂ�����ԑS������̔@���{��o���A�{�藷�c���̎����b��ɂȂ�Ɠr�[�ɑS�����a�₩�ɂȂ����A�Ƃ̂��ƁB
�@�S���֑̎��ł����A�{�菫�R�Ɋւ��āA�A�҂��ꂽ���R�͓s�����k��ŏ����ȏ��X���J�Ƃ��ꂽ�B���݂̂悤���n���ȏ��X�X�ł͂Ȃ��A���̈Ŏs�̂悤�ȓ���g�I�n�̂悤�ȋ������H������ŏ����Ȍl���X������A�ˁA���̈�p�ɂ����������ȓX�Ə����ȏ��V�̓X�傪�X�Ԃ����Ă���A�X�̑O���s�����藈������J��Ԃ��`�����Ă�������B���R�s�����̂ł͂Ȃ��A���Ă���d�Ԃ����p���ŏ��c�}���̉��k��ɏo�����A�̑�Ȃ鏫�R�Ƃ͂��̂悤�ȕ��Ȃ̂��Ɩ����ɖ������A�䂪�l���̋�����t�͂��̐l�ƌ��߂����Ƃ����݂ł��N���Ɏv���o���B
�@�g�c�����A�{�菫�R�A������E�����S���قȂ邪�A���̂��d�˂čl���Ă��܂��B���̋g�c�����̐l���Ɠ����͂������Đ�Ɏ�������Ɗm�M���Ă������A�a�C�������Ȃ̂��A�{�ЂƂ��a瀂Ȃ̂��A�^���͂킩��Ȃ����Â��Ɉ��ނ��Ă��܂����B���R���{�l�Ƃ��Ė����Ȃ��p�Y�Ɋ��ӂ��A�����h�_�܂����^������̂Ƒz���Ă������A�A���߂���̗Ⴆ�ʂ�A���S�ɖY�p�̔ޕ��ւƏ����Ă��܂����B������������炵���B
�@�������A��c���������E�̎��Ɏ��܂�����ׂ��ł��������A�]��ɂ������̂��Ƃ��d�Ȃ葽�Z�����čl���̉ɂȂ��̏A�����鍑��c���̒��ł��߂������Ȓ����̂͒Җ{�����c���B��l�B
�@���{���t�ɑւ������A�Ӓ��̐l���������ƌ��߂Ă��܂����B
�@�����ċ����ׂ��]�������B�g�c���Y��������13�N7��9�� �ߑO11��32���A�s���M�Z���c���a�@�ŐH�����̂��ߋ}���i���N58�ˁj���ꂽ�B

�@���̌�A�Ɍ���Ԃ̌����������悤�ƕK���̓����̘A���A�X�Ɍ���𗝉����Ă��Ȃ����d�{�ЂƊ��@����̎w���A�v���Ƃ̓����ł����������ł�9�����ŁA���̂̍X�Ȃ�g���h�������т͑�ł������B
�@�c�O�Ȃ���̂̕s���ɂ��11�N11���ɋً}���@�A�i������ޔC�j12�N7���ɂ͔]�o���ŋً}��p����ꂽ�B�]��ɂ������̃X�g���X���������̂��낤�B
�Ɠ������n���l�ʂ�o�g�̖����̐�m�B�Ɋ��ӂ̈ӂ�\������@�͂Ȃ����̂��낤���B

�@���{����𐡑O�ŐH���~�߂Ă��ꂽ�g�c���Y�����ȉ��A�葫�ƂȂ��Ċ撣���Ē�������m�̊F�l�A�{���ɗL���������܂����B
�@������l�A����̑��c���G�����ȉ��E���̊F�l�A��ꌴ���Ɠ��l�ɒn�k�A�Ôg�Ɠ����A��ՓI�ɐ����̎c����1�{�̊O���ōň��̎��Ԃ𖢑R�ɖh���Œ��������т͐r��ł��B�[�����ӂ̈ӂ�\���܂��B
���S�_�b���z
�@�u���S�_�b�v�͉����ɂł����݂���B��Ɉ��S�ł���Ɣ[�����M�����܂���ɂ́u���S�_�b�v�𗬕z���邱�ƁB
�@���q�͔��d���́A�ǂ����Ă����q���e��A�z���A���ɔ픘�����Ƃ��Ă͂���w�̂��̌��O���傫�������B
�@�������A���Ẳ䍑�͌o�ϐ����������E���オ��Ő��E����������鐬���Ԃ肾�����B��������Ɠd�͏�����E���オ��ŏ㏸���A���R�d�͕s�������O����A���Η͔��d�͓�_���Y�f���œ��ł��A���͔��d���J���n�_���Ȃ��A���͔��d�A���z�����d�A���̑��̔��d��i�͋Z�p�I�ɖ��m�̐��E�ł����B
�@��������Ǝc��͌��q�͔��d�A��i���̃C�M���X�A�t�����X�͐ϋɓI�Ɍ��q�͔��d�Ɏ��g�݁A����ɑ����ăA�����J�����g�݂͂��߂��B
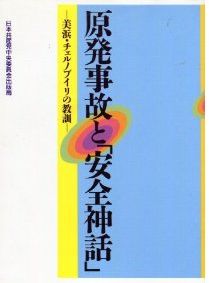
�@����ł͉䍑�ł����q�͔��d���̌��݂������i�߂悤�Ƃ̓����ɂȂ�A����ɂ͓�_���Y�f���o���Ȃ����ɃN���[���ł��邱�Ƃ������A�������o����Ɉ����ł��邱�Ƃ�O�ʂɉ����o�����B
�@�����ĉ��d�ɂ����S���u�����Ă����Ɏ��̂͂Ȃ��A�ƈ��S�ł��邱�Ƃ��������o�����B
�@�ǔ��V����1955�N1��1���A�˔@�A���q�͕��a���p�L�����y�[�����n�߂��B�u�Ă̌��q�͕��a�g�߁A�{�ЂŃ|�v�L���X�����ҁA���{�̖��Ԍ��q�͍H�Ɖ��𑣐i�v���̌��o���Ř_�����������A���a30�N�����炸���Ԃ�����L�����y�[�����n�܂����̂��Ǝv�����A����͓ǔ��V���Ў傪���͏����Y���ł��邱�Ƃ��l����Δ[���ł���B
�@���͏����Y���͓��{�ōŏ��Ɍ��q�͔��d���̌��݂�����l�ł���A���̌�͍���c���ɂȂ茴�q�͒S��������b�߂āA�������݂𐄐i�����B
�@����ɋ����Đ��i�h�ɂȂ����̂��Ⴋ���̒��]���N�O��c�m�Ƃ��̓��u�B
�@�d�͋ƊE����d�͈�v���Č������i�ɋ��͂��A���̒��S�͓��d�̖ؐ�c�В��ŁA�Г��Ɍ��q�͉ۂ�V�ɐݒu���A���͂Ȑ�`�Ԑ��𐮂����B
�@�������������Ă��������V����1974�N7�����猎1��10�i�̌��q�͍L�����f�ڂ��A�����V���������^���h�ɂȂ����͓̂d�͋ƊE�ɂ�鍪������t�������̂Ǝv����B
�@���̌�A�����V�������������~�߁A�^���h�ɂ܂�����B����ŎO��V�����^���h�ɂȂ�A�唼�̃}�X�R�~���e�F�h�ɓ]���������ƂɂȂ����B
�@�O��V���̍L����͍����A�S����1�y�[�W�܂邲�ƍL���������1�疜�~�A�N�Ԃł͒n����������10���~�ɂ��Ȃ�B�����Łu����PR�\�Z�́A���ݔ�̈ꕔ�v�Ɖ�Ђ��F�߁A�L�x�Ȏ�����������Łu�������S�_�b�v������Ă������B
�@�d�͒����������Ƃ����@�ւ�����A�d�͊֘A�̌���������Ƃ���ŁA���̌�����͓d�͉�Ђ����S���Ă���A�ϑ��������w�ǂ��B������d�͉�Ђɋt�炤�����͌�@�x�Ƃ����̂��Öق̗��������ƂȂ�B
�@�������̂͐�ɂ����Ă͂����Ȃ��A�]���ĉ��d�ɂ����S������������A�����猴���̎��̂͂��肦�Ȃ��A�����̈��S�͐�ł���A�ƌ����O�i�_�@�����藧���Ă����B
�@�Ƃ������ƂőS�d���r���Ȃǂ͖�����ɂ��N���蓾�Ȃ������ŁA���̑�ȂǕ����ʂ�z��O�A������V���~���V���������Ȃ��A�ܘ_�}�j�A�������݂��Ȃ��B�������K�v�Ȃ��B
�@�]���āA�A�����J��NRC�A�t�����X�̃A���o�Ђ̂悤�ȋ@�ւ͑��݂��Ȃ������B
�@���S�_�b�̔��[�́A1980�`90�N��A�u���q�͐�����v�Ƃ������{�̌��q�͐���𐄐i���Ă��������ҁA�����A�d�͉�Ђō�������ȉ������A�����Řb������ꂽ���Ƃ͔@���ɂ��č����Ɍ��q�͂̈��S����PR�o���邩�����S�ŁA�����͋c���^�Ƃ��Ďc���Ă��邻�������A�����ł��낢���PR��킪����ꂽ�Ƃ����A��������O�s�o�Ŗ����ɂ͂��Ȃ��B
�@�d�C���ƘA����́A�����̃C���[�W�����d�邽�ߑ����̒����l���N�p���Ĉ��S��PR���s�����B�ܘ_���q�͂Ɋւ��Ă͂Ȃ�̊W���Ȃ������Ȑl�B���B
�@PR��ϋɓI�ɍs���A���S�_�b�𗬕z����͓̂��R�̂��ƂŁA�������Ƃł͂Ȃ��B�������͗]��ɂ����S�_�b����s���Ă��܂��A�̐t�̈��S�a���ɂȂ��Ă��܂������Ƃɂ���B
�@���S�_�b����{�S���ɐ��ݍ��܂���A�Ƃ�킯�d�v�Ȃ��Ƃ͌����n��Z���Ɉ��S�_�b���J��Ԃ����ݍ��܂��Ă������ƂŁA�����ғ��ɂ͒n��Z���̏��F��K�v�Ƃ���A�Ȃ�������S�_�b��M���Ă��炤�K�v���������B

�@���d�̌��q�͒S�����В��������āA1998�N�̎����}����o�n�A����\��œ��I�����A���[���j�Q�c�@�c���������B���͎���2004�N�̑I���ł��đI����A�����}�ł̌������i�h�̕M���Ƃ��Ċ����B
�@���̒����u�Ȃ��������v�̈�߂œ��{�̌����̈��S������������u���S�x���Q�̍����v�̏͂̒��ł̕����Љ��B�u�j�ɕq����������S���������A�픚���E���{�Ȃ�ł͂̔������A���E�Ɋ�����Z�p�B�`�F���m�u�C���̎��̂́A�j������~�߂�̂Ɏ��s���A���˔\������߂邱�Ƃ����s������ŁA�v���̂ɖ�肠��A���{�ł͍l�����Ȃ��B�X���[�}�C�����̎��̂́A��₷�̂Ɏ��s������ł���B���{�ł͂��������P�Ɉ��S�m�ۑ�52���ڂ��Ƃ�܂Ƃߎ��{���Ă���v�ƁA�����̈��S�����������Ă���B
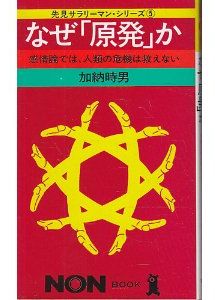
�@���[�c���̓G�l���M�[�����{�@���c�����@�Ő���������̂ɋ��z�A���d�̌��q�͔��d�������ɋc���̗͂��ő�����p���Đ��Ȃ鍑���̉����c���Ƃ��Ċ����B
�@����Ő��E�����ށA���̌�̓e���r�Ō��q�͔��d���i�h�̘_�q�Ƃ��ēx�X�q�����Ă������A���̌�͂Ȃ�Ɣ������邩���҂��Ă������p�������Ȃ��Ȃ����B
�@���S�_�b���J��Ԃ��Ă��邤���ɁA���S��������O�̂��ƂɂȂ�A�Ȃ�̋^�O���s���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂́A��ʖ��O������ɓ����ҒB�ŁA�������Ă��܂����̂��A���ȈÎ��Ȃ̂��A���蓾�Ȃ��z��O�̈��S��Ȃl����K�v�͂Ȃ��A���S�_�b�������̂悤�ɏ����Ă������ł��ނ��Ƃ��B
�@���܂�W�Ȃ������m��Ȃ����A��O�u���{�͐_���v�u�_�B�s�Łv�u�c���_�b�v�����w���̍�������荞�܂��A�{�C�ŐM�������ʁA���E��ɐ���Ċ��������܂łɒ@���̂߂��ꂽ���Ƃ��v���o���A�M���邱�Ƃ̕|�낵����������B
�@��O�u�哌�����h���v�u���퐋�s�v�����V�������悵�ď����Ă����B
�@���̎���ATV�͖��������A�ܘ_�l�b�g���Ȃ��B����̂�NHK���W�I�����A���̂悤�Ȏ���ł͐V���̈З͂͐����A���S�ȃI�s�j�I�����[�_�[���������琢�_��U�����Ă��܂����B
�@������ꌴ�����̌�̊O���l�L�҉�ŁA�u���E�B��̔픚���ł�����{�����E��O�ʂ̌��q�͔��d����ۗL���Ă���̂͂ǂ����Ăł����H�v�Ǝ��₪����A�����āu�n�k�����{�Ƃ��Ă͈��S�Ǘ����Â������̂ł͂Ȃ����H�v�Ǝ��₳�ꂽ���A�[���̂䂭�����͂Ȃ������B���S�_�b��PR���Z�����߂�������A�Ƃł�������ׂ��������̂�������Ȃ��B
����ł����̂͋N���Ă���
�@���C�� JCO �ՊE���� ���x��4
�@���̎��̂͌����̎��̂ł͂Ȃ����A1999�N9��30���@�픘���̂��N���A2�����S�A1���d�ǂƂ������q�͎��́i�ՊE���́j�ŁA���{�������̎��̔픘�ɂ�鎀�S���̂ł���B
�@1957�N�A��錧�߉όS���C���ɉ䍑�ōŏ��̓��{���q�͌��������ݒu����A���q�FJRR�[1���ՊE�ɒB���Ĉȗ��A���q�͊֘A�̎{�݂̊J�݂��������A13���̎{�݁A��Ƃ��������B
�@��錧�C�ݕ��ɂ���A���ˎs�Ɠ����s�̒��Ԃɂ��鏃�_���n�тł��������̑��ɓ��{���̌��q�͎{�݂̊J�݂������������߁A���a45�N�@���̐l��1��8960�l�A����22�N�l��3��7430�l�A�Z�����т�7�������q�͎Y�Ƃɏ]���A���ɂ́u�n���v�u�����v�u���q�͉��v�ƌ��������t�����邭�炢�A���q�͂Ɉˑ������n��ƂȂ����B
�@���̌��q�͎{�݂�1��ƂƂ��ďZ�F�����z�R�̎q��Ђ̊j�R�����H�{�݁A������ЃW�F�[�E�V�[�E�I�[�iJCO�j������A���̎{�ݓ��Ŋj�R�������H���ɁA�E�����R�����ՊE��ԂɒB���j�����A�������������A���̏�Ԃ���20���Ԏ��������B����ɂ�莊�ߋ����Œ����q���𗁂т���ƈ�3�����A2�����S�A1���d�ǂ̑厖�̂ƂȂ�A���̑�667���̔픚�҂��o�����B
���@���ی��q�͎��ە]���ړx�iINES�j���x��4�̎��̂Ƃ��ꂽ�B�i���Ə��O�ł͑傫�ȃ��X�N�͂Ȃ��j
�@9��30��10��35���@�]���������Ōx�A�x�߁A������JCO�͗ՊE���̂̉\������Ɛ��{�@�ցi�Ȋw�Z�p���j�֕�
�@�@11��52���@�픘��ƈ�3�������̂��ߋ~�}�Ԃ̏o���v��
�@�@12��30���@���C�������ʂ��ďZ���̉����ޔ��̌Ăт����L��J�n
�@�@12��40���@�����b�O�i�����j�֕�������B
�@�@�@���̌�A���̌��ꂩ�甼�a350m�ȓ��̏Z����40���т֔��v���B
�@�@�@�i�j�R�����H�{�݂̕t�߂ɂ����Ƃ��������j
�@�@�@500m�ȓ��̏Z���ւ͔����A
�@�@�@10km�ȓ��̏Z����10�����сi��31���l�j�͉����ޔ�
�@�@�@���C���u�g�p�֎~�̌Ăт����B
�@�@�@����t�ߍ���6�����A������֓��A���������AJR����A���ˁ`�����A���S���A���ˁ`�헤���c�Ԃ̉^�]�����킹�A���㎩�q���ЊQ�h���v���i��101���w�h����A���������ꕐ��h����j
�@�@�@��10��1�� 16��30���A����
���̌���
�@�{���̂̌����́AJCO���s���Ă����m��ɂ܂�Ȃ���ƍH���Ǘ��ɂ��邱�Ƃ����������B�����R�����������������B�F�̌����F�u��z�v�p�j�R�������H���Ă���ۂɋN�����B
�@�j�R�������H����̂ł��邩��A�����K�肵���������Ǘ��K�肪����A���̋K��ɉ����č�Ƃ���`��������B�܂�JCO�̊Ǘ��ӔC�҂͋K��ɏ]���č�Ƃ��s�킹��`��������B
�@�Ƃ��낪�u���}�j���A���v�Ə̂���H����Z�k������A�ȑf������}�j���A�������݂��A��ƈ��Ƃ���Γ��R�A��Ƃ��y�ȕ���I�ԁA�ēӔC�҂��ٔF���Ă����Ƃ����B
�@���̎��ɂ����̗��}�j���A���ł̍�ƒ��ŁA����ɗ��}�j���A�������������ň��̎菇�ōs��ꂽ�Ƃ����B
�@�����ł���E�����������̕�����n������H���ł͐��K�̃}�j���A���ł́u�n�𓃁v�Ƃ������u���g�p����菇�ł��������A���}�j���A���ł̓X�e�����X���o�P�c��p����菇�ōs���A��̓I�ɂ́A�ŏI�H���ł��鐻�i�̋ώ�����ƂŁA�ՊE��ԂɎ���Ȃ��悤�`�����Ȃ��ꂽ�e��i�����j���g�p����Ƃ�����A��Ƃ̌�������}�邽�߁A�ʂ́A�w��̒Ⴍ�A���a�̍L���A��p���̃W���P�b�g�ɕ�܂ꂽ�e��i���a���j�ɕύX���Ă����B
�@���̌��ʁA�Z�k�x18.8���̏Ɏ_�E���j�����n�t��s���ɑ�ʂɒ��������e��̎���ɂ����p���������q�̔��ˍނƂȂ��ėn�t���ՊE��ԂƂȂ�A�����q��������ʂɕ��˂��ꂽ�B
�@���̌��ۂ͐���s�\�Ɋׂ������q�F�̂悤�Ȃ��̂ŁA�X�e�����X���o�P�c�ŗn�t�������Ă�����ƈ��́u�E�����n�t��n�𑅂Ɉڂ��Ă��Ƃ��������݂��v�ƌ�����B
�@���̂ɋ�����JCO�̐E���͓��������A���Â������Ƃ͒N�����Ȃ������A�Ƃ����B
�@�{�������͋�����Ɩ��߂��o���AJCO�������u���Ђ��N�������̂́A���Ђŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɠ��АE��������ɓn��A���œ����ɓ����ė�p�����A�z�E�_�𓊓�����Ȃǂ̍�Ƃ��s���āA�A��������H�~�߂邱�Ƃɐ��������B
�@�����q���ʂ����o���E�ȉ��ɂȂ����̂��m�F���ꂽ�̂́A�ՊE��Ԃ̊J�n����20���Ԍo������10��1��6��30�����ł������B
���̔픘��
�@���̎��̂�3���̍�ƈ����픘�������A���̂���2���͑�ʂ̕��ː��i�����q���j�𗁂тĂ���A��ƈ��̓w���R�v�^�[�ŕ��ː���w�����������ɔ�������A����2���͑����זE�̈ڐA�̊W���瓌��a�@�֓]�@���W�����Â��ꂽ�B
�@���̎����т����ː��ʂ͍�ƈ��������i����35�j�́A16�`20�O���C�E�C�N�C�o�����g�i����16�`20�V�[�x���g�ȏ�j�B�Z���Ԃ̂����ɑS�g��8�O���C�ȏ�̕��ː��𗁂т��ꍇ�A���݂̈�w�����ł͖w�ǎ�̎{���悤���Ȃ��A�ƌ����Ă��邪�A���ۂ�6�`7�V�[�x���g���v���ʂ��������B
�@���̔{�ȏ�̋���ȕ��ː��ʂ�픘�����̂�������F�̔j��ɂ��V�����זE�������ł��Ȃ���ԂɂȂ�A�������������ł��Ȃ��Ȃ������ߎ���������ꂽ�����זE�̈ڐA���s���A�ڐA��p�͐������A�������������̌X���ɂ��������A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɐV�זE�̐��F�̂Ɉُ킪��������A���������Ăь����ɓ]���A59�����11��27���A�S��~�A�~�����u�ɂ��h���������̂́A�S�x��~�ɂ��_���[�W�Ŋe����̋@�\���������ቺ�A�ŏI�I�Ɏ��Î�i���Ȃ��Ȃ�A���̂���83�����12��21���A������s�S�ɂ�莀�S�B
�@��ƈ�������i����40�j6.0�`10�O���C�E�C�N�C�o�����g�i����6�`10�V�[�x���g�j��ʔ픘�ɂ����F�̔j�ꂽ���A�����זE�̈ڐA���������A�ꎞ�I�Ɍx�@�̒������Ƃ����ɉ��������A���A���ː���Q�ŏ��X�ɗe�Ԃ��������A�����MRSA�����ɂ��x�������i���`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہj�A���̂���211�����2000�N4��27���A������s�S�ɂ�莀�S�B
�@������l�̔픘�҂́A���S������l�̍�ƈ����ē��Ă�������ӔC�҂�C���i54�j��������ł������A��������Ă����̂Ő���1�`4.5 �O���C�E�C�N�C�o�����g�픘���āA�ꎞ�͔��������[���ɂȂ������A���㌤�̖��ێ��ɂ����č����ڐA���ĉ��A12��20���A���㌤��މ@�����B
�@�v���ʂƌ�����6�`7Sv��2�{�ʂ̔픘�ł���A���Î��̂����߂Ă̂��ƂȂ̂Ŗ����̂悤�ɔ�������V�����Ǐ�Ɏ��s���낵�Ȃ��玡�Âɓ�����83�������������͈̂�w�I���n����͏^�ɒl����Ƃ̉��Ĉ�w�E�̕]�����������B
�@�ՊE��Ԃ����������Ƃ��s����JCO�̐E��7�����N�ԋ��e���ʂ���픘�������B
�@�܂��A���̂�119�Ԓʕ���ďo�������n�����h���~�}�����ɑ���JCO���́A���ː����̂ł��邱�Ƃ�m�点���A�~���ɂ�������3���̑������픘���Ă��܂����B
�@���̂��Ƃ͌�ň�錧������JCO�ɑ��Č��d�ȍR�c���������B
�@������3���ȊO�ł̔픚�҂́A�ō��픘����120mSv�A50mSv�����̂�6���������B
�@���ӏZ���̔픘�҂�207���A�ő��25mSv�A�N�Ԕ픘���ʌ��x1mSv�ȏ�̔픚�҂�112���A�픚�ґ�����667����F�肵���B
�@���a�@350m�@�����@���v���@�@���a�@500m�����́@�����B
�@���a�@10km�@�����@�������v���@�Ώہ@9�s�����@��31���l
�@�����������@��8,000���@��150���~�A���q�͑��Q�����@���K�p���ꂽ�B
�@��Ђ͌Y���ӔC�����A��Ђ̖Ƌ�����������A���U�����B
���x��3�ȉ��̎���
�@���ی��q�͎��ە]���ړx�iINES�j�@���x��3�F�d��Ȉُ펖�́A���x���Q�F�ُ펖�́A���x���P�F��E
�@�����ŋN�������q�͊֘A���̗�@�N�㏇
��1973�N3���@���d�͔��l�����R���_�j������
���l1���F�ɂ����Ċj�R���_���ܑ����鎖�̂������������A���d�͂͌��\�����铽�����B���̂����炩�ɂȂ����͓̂��������ɂ��B
��1974�N9��1���@���q�͑D�u�ނv�i8,246�g���j�͌��q�͂ōq�s����D�����J�����悤�Ƃ̍��̕��j�ŐX�����̑����m�������q�s���A���˔\�R��̎��̂��N�����B���̌�������q�s���J��Ԃ������A�̎Z�_�Ŗ����Ɣ��莎���͒��~����A���q�F��P�����A�ʏ�̓��R�@�ւōq�s����C�m�n�������D�u�݂炢�v�ɂȂ��Ċ��Ă���B
��1978�N11��2���@�����d�͕�����ꌴ��3���@���́A�䍑�ŏ��̗ՊE���̖߂�ق̑���~�X�Ő���_5�{�����A7���Ԕ��ՊE���������Ƃ����B
���̌����ł������悤�Ȏ��̂����������A���͋��L���ꂸ�A���ɂ��Ȃ��A���̂���29�N���2007�N3��22���ɔ��o�����B
��1989�N1��1���@���x��2�A�����d�͕������3���@����
���q�F�ďz�|���v���������A�F�S�ɑ��ʂ̋����������o�����B
��1990�N9��9���@���x��2�A�����d�͕�����ꌴ��3���@����
����C�u���ق��~�߂�s������ꂽ���ʁA���q�F���͂��㏸���āu�����q�����v�̐M���ɂ�莩����~�����B
��1991�N2��9���@���x��2�A���d�͔��l����2���@����
���C������̓`�M�ǂ�1�{���j�f�A���p�F�S��p���u�iECCS�j�쓮
��1991�N4��4���@���x��2�A�����d�͕l������3���@����
��M���ɂ�茴�q�F�����ʂ��������A���q�F��������~�����B
��1995�N12��8���@���x���P�A���͘F�E�j�R���J�����ƒc�������B�F�u����v
�i�g���E���R�k���́A2�����p�n�̉��x�v�̏₪�܂�A�i�g���E�����R�k���R�Ă����B���̎��̂ɂ��u����v��15�N�Ԓ�~�A2010�N4���ĉғ������B
��1997�N3��11���@���x��3�A���́E�j�R���J�����ƒc���C�ď����{�݃A�X�t�@���g�Œ�{�݉Д������́A��x�����ː��������ʼn�����{�݂ʼnД����A����
��1998�N2��22���@�����d�͕�����ꌴ���@4���@�A���������137�{�̐���_�̂���34�{��50���ԁA�S�̂�25��1�������B
��1999�N6��18���@���x��1-3�A�k���d�͎u�ꌴ��1���@���̒���_�����ɕ������^���q�F�iBWR�j�ّ̕���̌��ŘF���̈��͂��㏸��3�{�̐���_�������A������ՊE�ɂȂ�A�X�N�����M�����o���B�蓮�ŕق𑀍삷��܂ŗՊE��15���������B���̎��̂͏����ʼnB�����A�^�]�����L�ڂȂ��A�{�Ђւ̕Ȃ��A�����֘A�̕s�ˎ��̑����ɔ���2006�N11���A�ۈ��@�w���ɂ��Г����_�����A����݂ɏo�āA2007�N3�����\����A����2�Ԗڂ̗ՊE���̂ƔF�肳�ꂽ�B
��2004�N8��9���@���d�͔��l����3���@2���n�z�ǔj�����́A2����p�n�̃^�[�r�����d�@�t�߂̔z�ǔj���ɂ�荂�������̐����C����ʂɕ��o�A�i�j���������C�p�C�v�j�����x�ꂽ��ƈ�5�����M���Ŏ��S�B
��2007�N7��16���A�V�������z���n�k�����A�����d�͔��芠�H��������
�O���d���p�̖���p���ψ���ʼnД����A���ʂ̕��ː������R�k�����o�B
�k�Ќ�̍��g�ŕ~�n���������A�g�p�ς݊j�R���_�v�[���̗�p���̈ꕔ�����o�����B���芠�H�����͂��炭�̊ԁ@�S�ʒ�~�ƂȂ����B
��2010�N6��17���A�����d�͕�����ꌴ���@2���F�ً}������~
�����C�H���~�X�A��p�d���Ɣ��p�d������O���d���ɐ�ւ�炸�A��p�n�t�@������~���A�ً}������~�����B�d����~�ɂ�萅�ʂ�2m�ቺ�����B�R���_�I�o�܂�40cm�ł��������A�ً}������~����30����ɔ��p�f�B�[�[�����d�@��2��쓮���A���q�F�u������p�n���쓮���A���ʂ͉����B
���O���ł̌��q�͊֘A����
�@1979�N3��28���A�A�����J�A�X���[�}�C���������F�S�n�Z���̃��x��5
�@1986�N4��26���A�E�N���C�i���a���i�����\�A�j�`�F���m�u�C�������A�����A���A��ʂ̕��ː���������o�A�j��ň��̌������̃��x��7
�@�`�F���m�u�C�����̂Ɋւ��A���ڂ̋]���҂͍�ƈ��A�~�������A���h�m�A���m���A���\�l�����Ɣ��\����Ă��邪�A���Ȃǂ̎��a���܂߂�ƁA�������琔�\���ɂ̂ڂ�Ƃ���Ă���B2005�N�̐��E�ی��@�ցiWHO�j���̕����g�D�ɂ�鍑�ۋ��������̌��ʂł́A���̎��̂ɂ�钼�ړI�Ȏ��҂͍ŏI�I�ɂ�9,000�l�Ƃ����B
�@2000�N4��26���ɍs��ꂽ14���N�Ǔ����T�ł́A���̏����ɏ]��������ƈ�85���l�̂����A5��5,000�l�����S�����Ɣ��\���AWHO�̔��\�Ƃ͑傫���H������Ă���A���̎��̂��_�@�Ƃ��č��ۓI�Ȍ��q�͏������̏d�v�����F������A���E���q�͔��d���Ǝҋ���iWANO�j�������i1986�N�j���ꂽ�B
�@�Q����35�����A132���q�͎��Ǝ҂��Q��
�@�n��Z���^�[�A�p���A�A�g�����^�A���X�N���A������4�����Ɏ����ǂ�����B
�O���ɂ������\�I�Ȏ��̗�
��1957�N9��29���@�E�����j�S���A�\�A�E�����n���J�X���s�ɋ߂��Ɍ��݂��ꂽ�u�`�F�����r���X�N65�v�Ƃ����Í��ŌĂꂽ�閧�s�s�̒��ɕ���H��i���q���e�p�̃v���g�j�E���Y�j�������Č��q�F5��y�эď����{�݂�����v�����g�Ŏ��̂��N�����B
�@�\�A���{�͑S�����ق��Ă��邽�߂��܂��ɐ^���͔���Ȃ����A�唚���������ā@�v���g�j�E�����܂�200���L�����[�̕��ː���������U�����炵���B
�@�������������̌����́A���炩�̌����ŗ�p�s�\�Ɋׂ�A�唚�����N�������A�����A�\�A���{�͎��̂��ɔ�ɂ��A�����ł����m���Ă��Ȃ������B
�@�\�A�̉Ȋw�҃W�����X�EA�E���h�x�[�W�F�t����1976�N�@�����֖S�����A�p�Ȋw���u�j���[�E�T�C�G���e�B�X�g�v�ɘ_�����f�ڂ��A���̒��Ŏ��̂�����Ă����̂Ŗ���݂ɂł����A���̂̏ڍׂ͕s���̂܂܁B
��1957�N10�N10���@�E�B���Y�P�[���Ў��́A���E���̌��q�F�d�厖�́B�C�M���X�k�����̌R���p�v���g�j�E���Y����E�B���Y�P�[�����q�͍H��i���Z���t�B�[���h�j�̌��q�F�Q��̘F�S�ō����i�Y�f�j�����ނ̉ߔM�ɂ��Ђ������A16���ԔR�������A���ʂ̕��ː��������O���ɕ��o�����B�����̃}�N�~�������t�͔��߂����ɔ�ɏ������悤�Ƃ������߁A�n��Z���͐��U���e�ʂ�10�{�ȏ�̕��ː����A���\�l�������a�Ŏ��S�����B���݂ł����̒n��̔����a���a���͑S�����ς�3�{�ȏ�Ƃ����B
�@�܂��Ђɑ��Đ���������Ɛ��f�����̕|�ꂪ����A���Ɏ�Ԏ���Ă��܂������Ƃ���Q��傫�����Ă��܂����B
��1961�N1��3���@SL-1���́iStationary Low-Power Reactor Number One�j�̓A�����J�̃A�C�_�z�t�H�[���Y�ɂ������C�R�̌R���p�����F�ł���B
�@�^�]�o�͂͌R����n���̒g�[�Ƃ��Ă̔M�G�l���M�[400kw�A�d�C�o�͂Ƃ���200kw�̍��v600kw�̂ł��������A�v���3Mw�ł������Ƃ����A3�l�̉^�]���͎��S�������߁A�����͕������Ă��Ȃ����A����_���^�]��������Ĉ������������߂Ɍ��q�F���\�������Ɛ��肳��Ă���B
�@���̂��N�����̂��ߌ�9�����ŁA�t�߂ɂ͐l�����Ȃ��ĉ^�]���ȊO�̔픘�҂͂��Ȃ������B���̔����������ɋ~�}�������삯�������A���ː��ʂ��������Č���ɋ߂Â����A1���Ԕ���ɋ߂Â�������̘̂I�o���͉����x���������A�ؒf���ĕ��ː��p�����Ƃ��ď��������B���������~�}�Ԃ������������A�p�������ɂ����قǂ��B
��1963�N10���@�t�����X�̃T���E���[�����E�f�E�]�[���q�F�ŔR���n�Z����
��1966�N10��5���A�G�����R�E�t�F���~1���F�@�F�S�Z�����̃G�����R�E�t�F���~�F�̓A�����J�A�f�g���C�g�x�O�ɂ��鍂�����B�F�����F�A�F�S�n�Z���N���ĕ����ꂽ�B���q�F�̘F�S�n�Z���̂��N�����ŏ��̗�B
��1973�N11���@�o�[�����g�����L�[�����F�S�ՊE���́A�@�A�����J�A�o�[�����g�B�A�����̂��ߔ�������Ԃ���������_�ׂ̗̐���_������Ĕ����Ă��܂��A�F�S�̈ꕔ���ՊE�ɒB�����B
��1976�N11���@�~���X�g������1���@�@�ՊE���́A�A�����J�A�R�l�e�B�J�b�g�̌����ŗՊE�ɂȂ�F�S�X�N�����Œ�~�����B
��1987�N7���@�I�X�J�[�V��������3���@�i�X�E�F�[�f���j
����_�̌��ʂׂ鎎�����ɐ���_�����Ƃ���z��O�̗ՊE��ԂɂȂ������A�^�]�����C�t���̂��x��A�ՊE��Ԃ��������B
��2008�N7��7���@�g���J�X�^���������́A�t�����X�A�A���B�j�����k���{���[�k�s�x�O����g���J�X�^�������ɂ����āA�E�����n�t�����^���N�̃����e�i���X���A����ă^���N����E�����n�t��3�����b�g�������o�ė���o���A�E��100�l�]�肪�픘���A���t�߂̉͐��74kg�̃E���j�E��������ł��B�����͈ꎞ������A�������̎g�p��͐�̍q�s�A�������肪�֎~���ꂽ�B
���̑��̎���
��1987�N9���@�S�C�A�j�A�픘���́A�u���W���A�S�C�A�j�A�s�Ŕ����������ː��������́A�����ꂽ�a�@�̒��ɕ��u����Ă������ː��Ö@�p�̈�Ë@�킩����ː��������܂�A�����n���̃X�N���b�v�Ǝ҂��������A��̂����Ƃ���œ����ɂ������Z�V�E��137���I�o�A�Èłł��������钿�������̂Ƃ��Ĕ̔����A�D��S���玩��Ɏ����A���ď����Ēu�����Ƃ���A�������L����2�����ʌo�������ɔ픘�ǏłāA�����̌��ʁA��250�l���픘���Ă������Ƃ����������B4�l���@�}�����ː���Q�Ŏ��S�A�����������Ɖ�7������́A�j�����ꂽ�B
�@�O���ł̔픘���̂̂ق�̈ꕔ���Љ���ɉ߂��Ȃ��B����ɑ����̂͌R�����q�͂ɂ�鎖�̂ł����A�R�̈АM�ɂ����ČR���@�����|�Ɍ��\���Ȃ��̂ŁA�������Ă��Ȃ������ŁA�R���֘A���q�͎��̂��R�ς��Ă��邱�Ƃ͐������邪�A1���l�Ƃ��ďo���������̊e�핶����T��͂��ɓ���ł��������Ԃ�܂����A�X�R�̈�p�ɉ߂��Ȃ��B
�@���Ɍ��q�͐����͂̎��̗Ⴊ�����A�\�A�C�R�A�ĊC�R���ɑ����̌��q�͐����͂�����z���ɕt���Ă������߂ɁA���̂��̑��Ō��q�F�A���ڊj�����z�������܂ܒ��v�A�s���s��������������B
�@�\�A�C�R�͕ă\��풆�A���q�͐�����250�ǂ������A�q���������A���̂���160�ǂ������}���X�N�𒆐S�Ƃ����R����������̂Ɋ�n�����k�m�͑��ɔz������A90�ǂ��E���W�I�X�g�b�N���ӂ���n�Ƃ��鑾���m�͑��ɏ������Ă������A�\�A�M����ɂ��V�����������q�͐����͂����̂܂ܕ��u���ꂽ���A���q�F���͗Z��M�����邩�痤�ォ��̓d������d�C���������ďz������]���Ȃ���Ȃ炸�A�Ƃ��낪���̓d�C�オ�����Ȃ��قǍ������Ă���A���������{���͂��߂Ƃ�����Ӎ��ƂŁA�}篎�������āA�Ȃ�Ƃ��H���~�߂����Ƃ�����B
�@�V�������̉��ǂ��͖����ɓ��{�C��I�z�[�c�N�C�Ɉ���A���v�������炵���B
����̌����^�p�̌��ʂ�
�@�������̂̌�A���炭�̊ԁA�E�����E�����S�p�����߂�l�X���l�b�g��FB�̌Ăт����ɉ����Ė������@�O�ɏW�܂�A�������V���v���q�R�[����f�����J��Ԃ���Ă������A���̈ȗ�2�N�����߂��Đ����S�����������A��c�����A���������Ƒւ�A���@�̎���ɂ͖w�ǐl�e�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�������ł͑S���̌������ғ���~�ɂ������A6��16���A��c���t�͊��d�͑�ь��q�͔��d��3�A4���@�ĉғ������߂��B
�@�֓d�͓����ߌ�2��������ĉғ��Ɍ�������Ƃ��J�n�A7�����{����8����{�ɂ�����3�A4���@�Ƃ��t���ғ����錩���݁A���{�̓t���ғ������ɂ߂������ŁA�ց@�d�Ǔ��̐ߓd�ڕW�����������Ƃɂ��Ă���B
�@�֓d�ɂ��ƁA�u�����������߂̔z�ǂ̐���ق̓_�������K�v�Ȃ���3�A4���@�Ƃ��t���o�͂Ŕ��d����܂ł�5�`6�T�Ԃ�����B�t���ғ��͐�ɍ�Ƃɓ���3���@��������7��8�`13���A�ォ���Ƃɓ���4���@��7��24���`8��2���̌��ʂ��A�^�Ă̍ő�d�͏�����ɂ��肬��ŊԂɍ������ʂ��ƂȂ����B�v�Ɠ����̐V���͕��B
�@���{�͌������ĉғ����Ȃ��ꍇ�A�֓d�Ǔ���8���̃s�[�N����14.9���̓d�́@�s���ɂȂ�Ƃ��āA15���̐ߓd�i�ҏ�������2010�N��j�����߂Ă����B
�@�֓d�ɂ���3�A4���@���t���ғ�����A���̔��d�ʂƁA���̓d�͂Ő������ݏグ�čs���g�����d�����v446��kw�ɂȂ�A�s�[�N���̕s���������Ƃ��₦�錩�ʂ����Ƃ����B
�@��������œd�͖�肪���������킯�ł͂Ȃ��B�b��I�Ȉ��S��Ő^�Ă̓d�͍ő���v�������Ƃ����낤�ƍĉғ��ɓ��݂������̂ł����đ����̍������[��������ł͂Ȃ��B
�@�����ɐ�̈��S�͂Ȃ��B�����͏o���邾�������[���ɂ��ׂ������A�����d�͕s�������퐶�����������A�Y�Ƌ��A�o�ϊ�����j�Q����ƂȂ�Γ���ɂ͐T�d�ɂȂ炴��Ȃ��B
�@�S�����́u�d�����v���ǂ�����̂��A������ꌴ���̋��P���ǂ��������Ă����̂��A���P�f�������V���Ȉ��S����e�������n�����Ɋ�Â��A���̑���m��ƍu���A�X�ɂ͊댯���̍������q�F�r���f�����Ȃ�Δp�F�𖽗߂���B
�@���̏�ŗL���̑�O�ҋ@�ւ��K�v�ŏ����̌������i��A�����̗��������߂�B
�@8���ɔ������錴�q�͋K���ψ���Ƃ��̎����ǂɂȂ錴�q�͋K�������ǂ��܂œ��ݍ��߂�̂��B
�@�V�����g�D�����{�I�ɐ��܂�ւ���̂��A�K���ψ�5�l�̐l�����ŏd�v�ɂȂ�B�����Ȏg�������o���A��O�ҋ@�ւƂ��Č��������A�ǐS�ɏ]���Č������q�ׂ���M���ł���l�ނ��ψ��Ƃ��đI�т����B
�@�K�����͖�1��l���x�̋K�͂ɂȂ�炵�����A�����͖��ۈ��@����S�ρA�����Ȋw�ȂȂǏ]���̌��q�͊֘A�g�D�����̈ڐБg���낤���A���q�̓����̈ӎ���ς��Ȃ����苭�łȌ��q�̓����̒��ǂ��N���u�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̂��߂ɋK�����́A5�N�ォ��S�E���ɏo�g�����ւ̕��A��F�߂Ȃ����Ƃɂ����B���̊ԂɐE���̈ӎ����v��O�ꂵ�A��̂̈ӎ������߁A���̂��߂ɂ͐V�K�̗p�̐l�ނ��m�ۂ��琬�ɓw�߂�K�v������B
�@���̋K�����������Ȉ��S������肵�A����Ɋ�Â��đS�Ă̌����̕]�����������A�X�g���X�e�X�g�̌��ʂɉ����Ĕp�F�ɂ��ׂ����������X�g�A�b�v���A�ĉғ��\�Ȍ����͊��������߂ĉғ��ɓ��ݐ�ׂ����B
�@5��5���ȍ~�A�S���̌������ғ���~���A����Ƒ�ь����̍ĉғ������܂������A����ɑ����ĉғ��͉����ɂȂ�̂��A�e�d�͉�Ђ͕K���ɂȂ��Đ��{��n���o�g�̋c���ɒ���J��Ԃ��Ă��邪�A����͓d�͕s������ł͂Ȃ��B���q�͋K���ψ���̐ݒu�@�Ă𐬗������A�X�g���X�e�X�g���o��1���ł������ĉғ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��؉H�l�܂������R������B
�@����͓d�͉�Ќo�c�̍������x������������Ă��邩�炾�B����1���܂�A����ɉΗ͔��d�Ŕ��d����Γ��R�R���Ƃ���LPG�A�Ζ��A�ΒY���̉��ΔR�����g��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�R�����1���������2���`3���~�A�ĉғ����Ȃ���A�R����ɑ������͓d�͉�БS�̂ŔN��3���~�̕��S���ɂȂ�B
�@���������d��9�Ђ̐Ԏ��z�́A��N�x���Z�Ōv1.5���~�ɂȂ����B���̐Ԏ�����₤�ׂ̓d�C��l�グ�Ȃ��Ȃ��F�߂��Ȃ��B
�@��s����̗Z���̏����́u�d�C��l�グ�ƁA�����ĉғ��̓���t���邱�Ɓv���̂̑�ꌴ���ȊO�͐���ɉғ����Ă����̂��������_�ɉ����ꂽ���{���ĉғ������߂���Ă���̂�����A��s���Ƃ��Ă͍ĉғ����Čo�c���O���ɏ悹��̂������Ƃ���̂����R�̐���s���ɂȂ�B �@����Ŕp�F�̕��j�������i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����܂�����Ȏ��Ăł����āA�p�F�ɌW���p���c��ł��邪�A����ȏ�Ɍ����Ɉˑ����Ă����n���o�ς��ǂ��~�ς���̂��A���ĐΒY�Y�Ƃ����̊�Y�ƂƂ��Đ��{�̎�����ی�̂��Ɛ��Ƃ��Ă������A�G�l���M�[�������d��ȐΖ��ɑւ��A�₪�ĐΒY�Y�Ƃ͐��{�ɂ���Ĉ��y���������A�����������������������B
�@���Ɏ��B�͒n���ɏ�֒Y�c������������A�����Y�z����1�A�܂�1�A���}��������A�Y�Z�̓��������A�Ō�ɔ֏�n���̃V���{���ł�������֒Y�z�������ꂽ���͊o��͂��Ă������̗̂܂����ڂ��قǂ̎⛌�����������B
�@�ΒY�͎Y�o�n������̒n��ɂ��������A�����͒n���ɋ�����܂��A�����I�ȈӖ��������܂߂Ė����ɉ������Ă������̂ł��邩��A�p�F�����߂Ă��n�C�T���E�i���Ƃ͂����Ȃ��B�������p�F���犮�S�ɕ�������܂ł�40�N�ȏ��������ƌ����Ă���A���̊Ԓn���̌ٗp�A�����ւ̎x���A����ɂ͎g�p�ς݊j�R�����A�����̌ł܂�ł���p�F���X���͎R�ς��Ă���A�ǂ������������Ȃ����t�Ȃ�Ή�����͌�ƂƂ���ɐ摗�肪����ƍl���Ă���Ή����ɂ͂قlj����B
�@���q�͋K���ψ����6��19���A�����̐V�����K����𐳎��Ɍ��߂��B
�@������ꌴ���̎��̂܂��A�ߍ����́A�n�k�ƒÔg�A�q��@�e�����̑��啝�ɋ��������B���q�F���K���@�̋K���Ƃ���7��8���Ɏ{�s����B
�@�V��́A�d�͉�Ђɉߍ����̑���`�����A���̎��ɂ����q�F���p�ł���d���Ԃ���h�Ԃ�z���̂ق��A��C���ւ̕��ː������̔�U��}����t�B���^�[�t�x���g�i�r�C�j�ݔ������t����B���˔\�R�ꎖ�̂��N�����Ă�������Ƃ��ł���悤�Ɛk����˔\�h��̋@�\��������ً}���̐ݒu���K�v�ɂȂ�B
�@�n�k�A�Ôg��ł́A�e�����ŋN���肤��ő勉�̊�Ôg��z�肵�Ėh���瓙��B
�@���f�w���I�o���Ă���n�Ղ̐^��Ɍ��q�F�����Ȃǂ̐ݒu�̋֎~�L�A�ΎR�◳�����ɑ�����߂�B
�@�q��@�e����Ƃ��Ă͒������䎺���j��Ă����u����Ō��q�F���₹��ً}�����䎺�̐ݒu���`���t�����B�ً}�����䎺�ȂLjꕔ�̐ݔ��͐ݒu�Ɏ��Ԃ�������Ƃ���5�N�Ԃ̗P�\��F�߂��B
�@�����͐V������A���̐R���ɍ��i���Ȃ��ƍĉғ��͏o���Ȃ��B
�@���d�͂Ȃ�4�Ђ́A7��8���̎{�s�㒼���ɂ��A6����12��ɂ��čĉғ��\������\���������A���q�͋K���ψ���̐R���͔��N�قǂ����錩�ʂ��Ȃ̂ŁA�N���̍ĉғ��͓���ɂȂ�B
�@������40�N�Ŕp�F�ɂ���ꍇ�A��������50��̂���8�d�͉�Ђ�34��ΏۂɂȂ�B���q�͋K���ψ����7��8���ɐV�����K������X�^�[�g�����A�����̉^�]���Ԃ��u����40�N�v�ɂ����B
�@�o�Y�Ȃ͂���܂ł��A�^�]�J�n����40�N�����Ĕp�F�ɕK�v�ȋ��z��d�͉�Ђ��ςݗ��ĂĂ����悤�Ɏw�����Ă����B
�@�������A���̋��z�Ŕp�F�ɕK�v�Ȍo��d�����Ȃ��Ǝ��Z����A34���1,700���~�s���ƂȂ�炵���B�s���z�̌����߂͓d�C�����ɏ�悹���邱�ƂɂȂ�B
��l�̋ƐсA�̋�

�@�n�k�A�Ôg�A�������́A�܂��ɑz��O�̑�ЊQ�A�厖�̂����đ����ɋN���A���{�͍��ƓI��@�Ɋׂ����B
�@�䂪���j��ő�̎��������������m��Ȃ��B�ߋ���U��Ԃ�Α�n�k�A��Ôg�͉��x���P��ꂽ�L�^������B���̓s�x痂��������𐋂��A�����̔ɉh�Ɍq�����Ă��������Ƃ͊m�����B
�@�����Ȍ�̑�n�k�ЊQ�ɑΏ����Ă�����l�̈̋Ƃ��ڂ݂邱�Ƃɂ���āA���ꂩ��̕����̑��������͍����Ă��錻�݁A��l�̋Ɛт��w�Ԃׂ����Ƃ͑����B
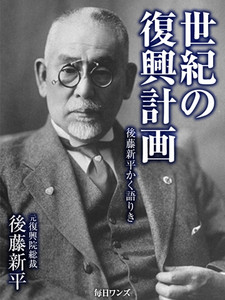
�@�u�x���������{���v�̍��ŏq�ׂ����A�����{��k�ЁA������ꌴ�����̂ɑ��鏉���A�~�ϊ����ւ̓����͓݂��A�K�ȑΏ��������̂��͋^�₪����B�X�ɖ{�i�I�ȑ��{���̐ݒu�͗]��ɂ��x���������A�K�ȍs��������Ȃ��������Ƃ������ŁA�l���ʂł�����������A�l�ޕs���ł��������Ƃł��������������B
�@�ߋ��̍ЊQ���̑Ή��̎����U��Ԃ��Ă݂Đ�l�̈̑傳�ɐG��Ă݂����B
�@�֓���k�ЁA1923�N�i�吳12�N�j9��1��
�@�֓���k�Ђ̕����ڒS�������͓̂�����b�㓡�V��
�@���̐l�͗����t�ŏd�v�Ȋt���Ƃ��Ċ��Ă����l�ŁA�s�s�v��@�A�s�X�n���z�@�Ƃ��������@�߂����A�O�ߑ�I�ȊX���݂����B��i�����̋ߑ�I�ȓs�s�낤�Ɗ��Ă����l���B
�@�吳9�N����k�БO�̑吳12�N4���܂ł͓����s����煘r��U����Ă���A�s��Ȍv��A�Ȗ��Ŏ����Ȍv��{�s�A�����������́e�啗�C�~�f�ł�������A�R�{�������K�ޓK���Ƃ��Č㓡����C�������̂�������B
�@������b����s�����@���قɏA�C���A��s�����v��Ɠy�n��搮�����Ƃ𗧈Ă��A��K�͂ȋ�搮���ƁA�����A�������H�̐��������̂ŁA�\�Z�Ƃ���13����v���A�S��ł̕����v��ł�30����v�������B
�@�����1922�N�i�吳11�N�j�̍��Ɨ\�Z�A��ʉ�v�\�Z��14��7�疜�~������A���Ɨ\�Z��2�N�����ɂȂ�B
�@30���~�����݂̍��Ɨ\�Z�K��93���~�Ŋ��Z����Ɩ�2�N���̖�180���~�ƂȂ�A���̗v���ɂ͖����������āA�c��͖ܘ_�A���E������җ�Ȕ�������A����5��7500���~�����F�߂��Ȃ������A���A����������ł����Ɨ\�Z�z��1/3�������猻��̋��z��30�����~�Ƃ��������\�Z�z�ɂȂ�B

�@�X�ɂ��̕����\�Z�ɂ͉������������B���݂ł͑z�������Ȃ����Ƃ������R��������A���ꂾ���̗\�Z������Ȃ�A�����\�Z�S�Ă��R���g���Ɏg���A�A�����J�Ƃ̐푈���������A���E�̔e�҃A�����J��|���Ă���A���E�̉��҂ɂȂ������{�����E�����玑�����W�߁A���z�I�Ȓ�s�����݂���Ηǂ��A�Ɩ{�C�Ŏ咣����Q�d�B���������A���W�I�A�e���r�̂Ȃ�����A�S���ŗ��R��Â̍u������e�n�ŊJ�Â����̎|�̎咣���J��Ԃ��A�������^���҂����������炵���B
�@���̒��S�l���́A��ɖ��B���ς������N�����A15�N�푈�̌����������Ό��Ύ������i���B���ϓ����̊K���j���B
�@���̂悤�Ȗ\�_��{�C�œf���Ă����G���[�g�Q�d�����R�����ɂ����̂�����A��N�̗��R�̖\���͂��̍�����萶���Ă����̂��낤���B
�@���̂悤�ȗl�X�Ȉ��͂Ɠ����Ȃ���㓡���ق�煘r��U�邢�A�������葫�̔@�����p���A���X�ƕ����x���@�Ă��o���A���@�����Ă��������A�啨�����Ƃ��̋��͂Ȋt�����z�w���ăT�|�[�g�ł������Ƃ��K�����Ă���B
�@�吳����ɂȂ����Ƃ͂����A�����푈�A���I�푈�A��ꎟ���E���Ɛ헐�������A�ƂĂ��C���t�������ɗ\�Z����炸�A���̓����̓��H�͍]�ˎ���Ɩw�Ǖς��Ȃ��ׂ��H�n�����G�ɓ���g�����̓s�s�̂悤�ȊX����������A�㓡���̌��f�ɂ���ċߑ�s�s�����E���l���a�������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@���̎����肵�������̌�Ղ̖ڂ̂悤�ȓ��H�A���a�ʂ�A�R�̎�ʂ�A�����ʂ�A�����ʂ蓙���݂ł����p����Ă����ʂ�͂��̎����肳�ꂽ���̂ŁA�㓡��b�̐挩�̊�Ɍh������B
�@�X��20���N��̑���œs�s�͏Ă��삪���ɂȂ�A��㕜���v��Ƃ��Č㓡��b�����肵�����@�ĂɊ�Â��ē����ȍ��y�njv��ے��ł������勴���v���𒆐S�Ƃ��Đ�Е����v��𗧈āA��ɐ�Е����@�v��ǒ��ɏA�C���āA�S���̐�Гs�s�����̎w�����Ƃ��Ă���B
�@���É��s�̋v����ʁA�L���s�̕��a��ʁA���s�̐t��ʂ蓙�A���̎��̌v��@�Ɋ�Â����̂ŁA�勴���v���͕l���Y�K���̖����ŁA�r�c���t�J����b�A�������t���ݑ�b���C����㕜���Ɋ��Ă���B
�@��㕜���v��̕�̂͌㓡��b�̈�Y�Ƃ������邭�炢�������̂ł����B
�@�]���Č��݁A�g�㓡�V�����h�Җ]�_�������N����̂����ɓ��R�A��������̕����@���قɏA�C���Ă����炫���Ƒf���炵���d������萋���Ă��ꂽ���ƂƎv���B
�@����Ɍ㓡���̐����́A���قƂ��Ċ����̂͋͂��Ȋ��Ԃł����Ȃ��A�����N��12���ɗL���ȌՃm�厖�����N���āA�ӔC���Ƃ�����R�{���t�͎��C�A�㓡�����t�O�ɋ����Ă��邪�A����ł����ɑ�������������A���̐������`����Ă���B�@�㓡���ɂ��ďq�ׂ�ƁA��茧�_��S�������i�����B�s�j�ɐ��܂�A���쒷�p�͑�f���A���ɒŖ��x�O�Y��������B
�@�ꐡ�����������Ƃ��ւ�肪����A�������߂ł���������ۘa���𗊂��ĕ����ɂ��āA�{���ɂ����������␣�a�@�̕t���Ƃ��Ė���6�N�{����w�Z�����݂���A���ꎁ�̐��E�ɂ��17�˂ň�w�Z�ɓ��w�i���̈�w�Z�̌�g������������ȑ�w�ɂȂ�j�A��t�ɂȂ����B
�@�֓���k�БO�㍠�̐��E���܂��s���Ȏ���ł������B
�@�吳11�N6��12���@�����������t���������F��̓����Ɋ�Â��t���s����Ŋ��������̂������p���ł̑g�t�ŁA�������t�͋͂����N���炸�̍~�A���̑O�͑吳10�N11��4���@���h�������w���Ńs�X�g���ɂ��_���ňÎE����A�}篍������������t������b��q�������̂�����A�Z�����t���������ǂ͕s����ł����B
�@���̗l�Ȓ��A��21��������t�����������̂ł����A1�N2������̑吳12�N8��24���a�����Ă���A���t�͑����E�A�����Ƃ��Č��C�R�叫�R�{�����q�ɓ�x�ڂ̑喽�~���ƂȂ����B
�@�������A���������ɑg�t���F�����킯�ł͂Ȃ��A�g�t���Ɋ֓���k�Ђ��������Ă��܂��A�s�݂̎����������̂ŁA���̎��̐V���L���u��\���������������䉺��ɑ��R�{�����q����t�E�����錋�ʁA���쎘�]���͓�\�����ߌ�O���\���A�R�{�������ւ̎��@�ɖK��A���|��`���A���̌��ʎR�{���͌ߌ�l���O�\�l���ԍ◣�{�Ɏf��A�ې��{�a���ɔq�y�e������p���t�g�D�̑喽��q���A�����Ԃ̂��P�\����Č�O��މ������B�v�i�吳12�N8��29���u���������V���v�j
�@���̂��ߊO����b���c�N�Ƃ����t������b�Վ��㗝�Ƃ��ċ}������̂��ً}���[�u�������Ă���A�k�Ў��ɂ͐����ȓ��t�͑��݂��Ă��Ȃ������B
�@���̐����Ԃ̗P�\��Ղ������Ƃ̑t�オ�A���ʓI�ɂ͑�ςȍK�^�������炵�Ă���B
�@����͐ې��{�a���i���a�V�c�A�吳�V�c���a�C�×{���ׁ̈A�N��ɑ����Ă��̔C�����s���̂��ې��j�͓��t�̐e�C�����I��莟��×{�̂��ߔ����̕ʓ@�֕�������\��ɂȂ��Ă���A�k���n�����͘p�̃T�K�~�g���t�ł�����A�ԋ߂ȔM�C�┠���͉�œI�ȑŌ����Ă����̂ł��B
�@�k�Д�����@�ې��{�̏����ɂ��A�Վ�������b���c�N�ƁA��������Y������b�A�Ԓr�Z�x�����Ă����ʂ̐ӔC�҂ƂȂ��ėՎ��t�c���J���āA��2���@�Վ��k�Ћ~�쎖���ǂ�ݒu�A��펞�ɂ�����g�t���}���A2���ߌ�7���@�e�C���͐ԍ◣�{�֎R�{���ȉ����Q�����A�[�Ŕ����s�̍�������钆�ł̐V�C���ł����B
�@�u�҉Β��̐e�C���A�ې��{�ɂ͑O��̎l���Ɍ�엧���点���A�������e�C�����s�͂���ꂽ�v�ƁA�V���̋L���ɂ���A�l���Ƃ���܂�����A�����]�k�̋��鍠�Ȃ̂Œ뉀�ɂ���e�����܂�f�ł̐V�C���������悤�ł��B
�@��ꎟ�R�{���t�͊O���̎����ł������A�o�g��̂ł���C�R��h�邪���V�[�����X�����������̂ŐӔC�����A���t�͑������Ă��܂��Ă����B
�@�ł������̖��\�L�̓�ǂɑΏ��o����͎̂R�{�����q�������Ȃ��A�ƌ��V�ł��鏼�����`�̋������E������������ł��B
�@�喽�~���ɂ��āA�������@����̓��t������b�̑I�C�͑I���ł͂Ȃ��A�V�c�̎��m�ɓ�����`�Ŏ�nj������V�ƌĂ��l�B���t�E���喽�~���ƂȂ�܂��B
�@���V�Ƃ͖������{�Ŋ������c�E�R���E�ɓ��E�����E���E��R�E�j�E�������E�����Ƃ������l�B�Ŗ����V�c���C�����Ă���܂����B
��_��W�H��k��

�@����7�N1��17���A��_�W�H��n�k�́A���R���t���������Ĕ��N���������ĂȂ��A�����������A�Љ�A���������Ƃ����O�}�ɂ��A�������A��@�ɍۂ��ēK���v���ɑΉ��ł��Ȃ��A��@�Ǘ��s�݂ƌ����Ă��d�����Ȃ��悤�ȑΉ��̒x�����w�E����Ă���B
�@���R���t�����̔w�i�ɂ́A�א���t�̐����A�܌ܔN�̐��̕���ɂ͂��܂鐭�E�ĕҐ��̑傫�Ȃ��˂�̒��A�����}�̕���A���������ɂ��啨�����Ƃ̑ߕߑ��o�A�����}�ƈ��h�ɂ��A�����t�����A�������s���a������ŕ���A���̌�͒Z�����t�������A�����Ă���ƎЉ�E�����E���������O�}�ɂ��Љ�}�}�����ǂƂ���E���g��C�̗l�ȗ���Z�ŁA�Η����C���r������j���đ��R�x�s���i���{�Љ�}�j����ǂƂȂ����B

�@���R���t�i1994�N�i����6�N�j6��30���`1995�N8��8���j�������������������炩��Ƃ�������Ȃ���D�o�������肾�����B
�@���t�������N��ɍ�_�W�H��k�ЁA�X�ɂ���2�������3��20���u�n���S�T���������v�������A����ɑ����I�E���^�����ɂ�鎖�������X����݂ɏo�ē��{���肩�A���E�������������������������B
�@1995�N�i����7�N�j1��17���ߑO5��46��52�b�A��_��W�H��k�Д����AM7.3�k���n�A���ΊC���[��16km�A�s�X�n�����k�ɏP���A����6,402�l�A�s���s��3�l�A������43,792�l�A�Z���Q�S��104,906���A��Q���z��10���~�K�́B
�@�e���r�͒n�k���������ォ�瑬��ŕ��A���ꒆ�p���������B
�@�ܘ_�A���������ɂ��������A�e�Ȓ��Ƃ���Џ͏������Ă����B
�@�������A���t�ɂ͕���Ă��Ȃ��B���̎����܂��܌���ɋ����킹���c�����t���̈�l�ɒ��ڌg�ѓd�b�ŕ����炵�����A�傰���ɉ��������Ă���̂��Ǝ��グ�Ȃ������炵���A���̎��グ�Ȃ������̂����̗��R�́A�������ꂾ���̑�n�k�Ȃ���t���[�ɐ����ȕ�����͂��A���ꂪ�Ȃ��̂͂����������Ƃ͂Ȃ��Ɩ��������炵�����A�̐S�̑��R�����ɂ͂ǂ̏Ȓ�������S�����Ȃ������炵���B
�@���̂��ߒn�k�����������������ɂ�������炸�A�ߑO���t�c�������āA�S���W�̖����c�肪���グ���Ă����Ƃ���������ꂽ�X�Ԃ��B
�@���̂��ߏ����~�ϊ������啝�ɒx��Ă��܂����B���ɂ��̓������q���͏o���v�����Ȃ�����o���ł����A���Ԓn���ŏo���ҋ@�Ԑ�������A���肶�肵�Ȃ���o���߂�҂��Ă����Ƃ̂��ƁA�s�X�n�̃r�������A���H���ǂ��ł��܂������ߏ��h�ԁA�~�}�ԁA���X�L���[�ԗ��������s�ł����A���q�������L���^�s���̎ԗ��������s�ł��Ȃ������̂����珮�X�����̒x�ꂪ����܂��B

�@���̂��߁A���q���@�������s���A�o���v�����Ȃ��Ƃ��A���n�����w�����̔��f�ŏo���o���悤�ɂȂ����B
�@�����{��k�Ђł́A���q���̋~���o���͑f�����A�劈�����Ƃɂ���Ď��q���ɑ���F�����S�����߂�ꂽ�B
�@�����嗘�c�������n�_�ˎs�����@���A�����Ɂu����͖������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ��ӁA��������S�����ɂȂ邱�Ƃ�\���o�A�n�k���S������C������Ă���A���n�ɒ���t���w���w�����������B�u������v�����b�g�[�ɂ��āA�����̈��͂��͂˂̂��A���ɂ͒��@�K�I�ȃE���g����@�ł��ꂫ�̓P������n�܂����B
�@�܂����ɂȂ�̂͊��I�̏W�Ϗ��A�Z�b�R�̗����A�_�ˍ`�ɏW�Ϗ���ݒu�A�X�і@�A�_�n�@�̎葱�͈�؎��炸�A�ӔC�̓I��������Ƌ��s�����B
�@���ݏZ��݂����n�����̂���3���ˌ��݂̗v�]������ƁA4���ˌ��݂����߁A�S���̌��Ǝ҂̎В����ꓰ�ɏW�߁A�u�y���ԏ�ŋ}�s�b�`�ł��v�ƞ������A�����Ȏ�r��1�N�ŕ����������B
�@������x�����̂́A�쒆�L���c���Ɠ��t���[�������̐Ό��M�v���͒��N���[�������Ƃ��ė��̓��t�Ɏd�����x�e�����ŁA�@�����ɂ͖��S��s���A�����S�������T�|�[�g�����B
�@�܂����R�����͑S�Ă�C���A��Ɍ��o�����Ȃ��̂����������B
�@�k�Ќ��40���̊Ԃ�11�{�̕����֘A�@�Ă��o�A���������A���̌������ƌv16�{���������Ă���B�e�ȊԂ����Ď���������Ґ��A���̉��Ɋe�Ȃ̊��[���N���X��z���āA�ォ��̎w�����e�ȂɃX�g���[�g�ɓ`���d�g�݂�n���āA�Z���Ԃŕ����ւ̕����Ɠ����\�z�����B
���Ƃ���
�@2011�N3��11���A�o�t�n���̊F����̐����͈�ς��Ă��܂��A�M��ł͕\�킹�Ȃ��قǂ̋�ɁA���𖡂���Ă������Ƃł��傤�B
�@�Ԃ߂̌��t�Ȃlj��̖��ɂ��������Ȃ����Ƃ��d�X���m�ł����A�x���n�悪�ꕔ������3�����狖�Ȃ��ł�����o����悤�ɂȂ����̂�4��16���u���x���F�̉�v�̃����o�[�Ƌ��ɂӂ闢�x����K�ꂽ���A���̎S��ɑ���ۂ݁A���̏�Ԃōċ��͉\�Ȃ̂��낤���Ǝ��⎩�����J��Ԃ��Ȃ���A�A��̃o�X�̒��Ŏ��Ȃ�̕����Ă�������B
�@���̊F���Y��ł�����̂̂����ő�̂��̂͋A�Ҍ�̐�����i���낤�Ə���ɑz�����A���ɍk��n���ǂ��Ȃ�̂�����Ȃ��_�Ƃ̊F����̕s���͐[���Ȃ��̂Ǝv���A�A�������p�\�R���ɑł����݁A���̊F����̏����ł����ꂩ��̎w�j�ɖ𗧂ĂƎv���Ȃ��珑���グ�܂����B
�@����Ȍ��t�Ő\����Ȃ����A���C�R�[�������ɂȂ肩�˂Ȃ����Ƃ��뜜���Ă���A�@�Y���̂���������������݂Ă��A���͉̂ߋ��̂��̂ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@���{�̓C���t�������⏜�����m�����ɑS�͂�s�����Ƃ͌������A���̐����ɖ߂�邱�Ƃ�ۏႵ�܂��Ƃ͐�Ɍ���Ȃ��B�����������ė~�����̂͂��̌��t�ł���A���R�߂���v�����Ǝv���邪�A����������Ζ������ƍl������ł��܂��B
�@�o�t�n���ł̎�ȎY�Ƃ͈ꎟ�Y�Ƃł����āA�y�n�Ƃ͐�ɐ藣�����Ƃ��o���Ȃ��Y�Ƃł��邩��A���̓y�n�����˔\�������ƂȂ��ĉ����n����l�X���A�ӔC�������Ĕ����邱�Ƃ͏o���Ă��A�����n��𐳏�n��ɖ߂����Ƃ͕s�\�ł����Ȃ��B�܂��Ď��Ԃ̋t�߂�͏o���Ȃ��B����ł͒��߂�Ƃ����̂��B�����n��ł����Ă����p�ł������͂Ȃ��̂��A���⎩���̐��E�Ɋׂ����B
�@�o�t�n����1000㎢�ɋy�ԉ����n�тɂȂ��Ă��܂��A�ꎞ����10���l�ɂ��y�Ԑl�X���������A2�N�ȏソ�������݂ł�5���l�ȏ�̐l���s���R�Ȕ�����]�V�Ȃ�����Ă��邪�A��Ԃ̕s���͂��ꂩ��̐������ǂ����邩�ł��傤�B
�@������������������Ă����ɖ߂��͕̂����I�ɕs�\�Ƃ̌��_�ɂȂ��Ă��܂��Ɓu�o�t�n���̈ꎟ�Y�Ƃ͕����v�Ɛ鍐���邩���m��Ȃ��B���̊����S���̋x�k�n��������ꂽ�c�����������邩�瑴���Ɉڂ�Ƃł�������Ă��o�������m��Ȃ��B
�@�n���̒n���A�����A�R�~���j�P�[�V�����̘a�A�ցA�������ՁA�n��̍s���A�n��Љ�̌��т��͋����A���̕��������������A�ċ��̎n�܂�ƂȂ�B
�@�����炱���\�[�V�����L���s�^�����d�����A����ɂ��n���Đ������Ă����ӂ闢�������������Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��āA�y�n�𗣂ꂸ�A���������ꂽ�k��n������������p������@�Ƃ��Đ��k�͔|���Ă����B
�@����ɃR�~�P�[�g������A�����̃��Y���A���ʂ��̗ǂ���������{�Ƃ����W���𒆐S�Ƃ��A���S�ɏ������ꂽ�l�������̐V��Ǔs�s���݂��Ă����B
�@���z�����p�̉����͔|�A���z���Ɛl�H�����p�̉����n�E�X�͔|�A���S����^�̐A���H�ꓙ���Ă������A��������v���t������ł͂Ȃ��B
�@�I�����_�ɂ͒��݈��Ƃ��đ؍݂��A���b�e���_���ߍx�̏����ȑ��ɏZ��ŁA�s���ɂ���I�t�B�X�ɒʋ��Ă������Ƃ�����̂ŁA�g�߂ɉ����͔|���������Ă���A�������瓭���Ă���_���̊F�����Ɉꌬ��������p��������ɒ��H�̃p�����ɊJ�X�O������B�����p�����ɍs���Ɗ猩�m��ɂȂ蒩�̈��A�����킷�悤�ɂȂ������A�܂��Ηq�Ő̂Ȃ���̐��@�ŏĂ��p���͑f�p�Ȗ��Ŏ��ɂ��������A�ׂ̔_�Ƃ������Ă����i�肽�Ă̋����ƕ����L�ȃo�^�[�̑����͊i�ʂŁA�y�̍���L���Ȋy���������B
�@�܂��A�X�y�C���̃A���_���V�A�������ŊC��̂�����A�S���ی��ϕt�̊C��̂������̂ŁA���炭�؍݂��Ē����������Ƃ��������B
�@���̎��͕ʂɈӎ����Ă�����ł͂Ȃ����s��ȃr�j�[���n�E�X�Q�̘A�Ȃ�Ɉ��|����A��Ƒ��o�œ����l�B�߁A�P�g���C�ňً��̒n�œ����䂪�g����Ȃ����Ȍ����̎v�����������B
�@�������v���Ԃ��A������������o�t�n���̋~�ςɖ𗧂̂ł͂Ȃ����Ǝv�����菑���Ԃ��Ă݂��B
�@���E����]�X�Ƃ��闷��̂悤�Ȕ����������̂ŁA�����A�A�t���J�A�J���u�C�̓��X�A���B�Ɠn������A���̒n�ɍ��t���͋���������l�X�𐔑����ςĂ��邤���ɁA�������Ⴂ���ɐ�U���������l�ފw�̕���ł�����x�����邱�Ƃɒ��킵�Ă݂悤�Ǝv�������A�����떈���̐������t�B���h���[�N�̂悤�Ȃ��̂ŁA����ɂ�����̂͑S�ċ��ނƂ������Ɋ������A���������ɉ��K�������B
�@���A�ŏ����Ԃ����ʕ����G���Ɍf�ڂ���A���ɒ����ł̌��n���������|�[�g�����̂��D�]�������炵���B
�@�@���̐��E�ł͐M�Ɠ��퐶������̉����Ă���A�����̃C�X�������ƃA�t���J�嗤�ł̃C�X�������̈Ⴂ�A�J���u�C�ł̃L���X�g���Ɖ��B�ł̃L���X�g���̈Ⴂ�ȂǁA���̓y�n�ƏZ���͎��ɖ��������y���M�Ɩ{���̏@���Ƃ̗Z�a������A�l�̘a�A�ցA�J�����т��Ă�����̂͐M�������B
�@�������Đ��܂ꂽ�����E�K���͒����N�����o�Ĕ|���Ă����̂������ł���A���̕����̍��肪�Y���y�n�������ӂ闢�ɂȂ�B�ǂ��ɋ��悤�Ƃ��A���{�\�͏�ɂӂ闢�Ɍ������B
�@�������A���̂ӂ闢������̂܂ܐ��ڂ���ƁA�������o�ɂ�A�҂���߂�l�������Ȃ��Ă���̂���ނȂ��B���ɎႢ�l�قǏA�E�A�]�E�̋@�����A�����ɐ����̖{�����ڂ����낤���A������~�߂��ɂ������Ȃ��B
�@���ꂩ�牽�N�A�҂ł��Ȃ��̂�����Ȃ����A�₪�Ă͑o�t�n���͕s�т̒n�ɉ����Ă��܂��|�ꂪ����B
�@�����炱���A�l������ۂƂȂ��čċ��āA���ꂩ��̐ʐ^�A�r�W������n��A�N���Ɍf����ׂ��ł����āA���̎w�j��ق��đ҂��Ă���ׂ��ł͂Ȃ��B
�@��Ў҂̊F�������ɂ��Ď����B�̊�]�A��]�����Ԃׂ����B�ӂ闢�͎����B�̂��́A�����B���n���Ă������̂Ȃ���B
�@���n�̊F����A�ǂ������C���o���ċ��˕Ԃ��ĉ������B�����Ƃ����Ɖ��������ӂ闢�A��܂��B�݂�Ȃƈꏏ�ɂ����ƋA��܂��B
�@�g��h�͑o�t���F���h�o�t�̗��́A�A�҂����F����̎�őf���炵���ӂ闢��n�����ĉ������B�����炱�����[���̂����r�W�������F����̉b�q�ŕ`���܂��傤�B�����Əo����Ɗm�M���Ă��܂��B
�@���̊F����A�ӂ闢�ċ��̐ʐ^��`���܂��傤�B��������ɒ�Ă��܂��傤�B�r�����m�Ȓ�Ă��Ȃǂƃo�J�ɂ���邩���m��܂��A�n�����҂������ɂ��ċ��Ȃ���A�ӂ闢�͏��ł��Ă��܂��^���ɂ���܂��B�������ݎv�Ăł͑O�i�͂Ȃ��B�n���������ׂΕK�����^�҂͗����オ���Ă���܂��B
��
�@�@�l�������̏��߁A�i�o�t�s�j
�A�@�V��Ǔs�s���݁i���˔\������h�䂷��j�l���������Z��
�B�@�������ꂽ�c���Ɋ����A���k�͔|�H��̐V��
�C�@�o�t�`���݁i�����c�y�����������ɍs���j�A�R���̏W�ϒn����
�D�@�Η͔��d���̐V�݁A����
�E�@�C�㕗�͔��d�A�e��C�m���d�A��d�͐��Y�n�A�C�m�q��̊J��
�F�@�d�͓����V�݁A��d�͏����ƁA�H���U�v
�G�@��ꌴ���𒆐S�Ƃ����A�p�F�A�j�S�~�������q�͊֘A�̌����{�݂̏[��
�H�@�������͐ϋɓI�ɐA�т��A��X�ь����Ƃ���
�I�@���ݐi�s���Ă���l�X�����v���W�F�N�g���X�Ɋg�債�A���𒆐S�Ƃ����c�c�W���̑��ԂƎ��̑�������A�s�y�n�̌���
�J�@����̑����S�ʊJ�ƁA���킫�`����Ԃ̊��S�������A�X�ɂ͏�V����
�K�@������֎����ԓ��̊����A�J��
�L�@�l�ʂ�ɂ���`���s���A������Y��ϋɓI�ɕی�E�ۑ��ɖ��߁A�X�ɑS���I�ȕ�����Y�Ƃ���PR���A���E�ɓo�^�������i�ᑊ�n��n�ǍՂ�j
�M�@��ςȍЊQ�Ɍ������A��Вn�͗�̏�ԂɂȂ��Ă��܂����B�]���Č��݂͑S���̔����Ƃ������Ԃɂ���B���̐^�����ȃL�����o�X�ɂǂ̂悤�ȊG��`���̂��A�q�A���A�\���Ƒ����q�����o�t�̒n�ɐ��܂�ĉ��������Ǝv���悤�ȊG��`�������B����͊F����̉b�q�ɂ���Đ��܂�A��Ă܂��傤�B
�Q�l
�����q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@��10���@
�@���q�͖h�ЊǗ��҂̒ʕ�`���ɂ��ċK�肵���@���A�@
�@���q�͖h�ЊǗ��҂́A���q�͎��Ə��̋��̋��E�t�߂ɂ����Ē�߂�ꂽ��ȏ�̕��ː��ʂ����o���ꂽ��A���͒�߂�ꂽ���q�͎��ۂ̔����ɂ��Ă̒ʕ�����Ƃ��A���͔��������Ƃ��́A�����Ɏ喱��b�A���ݓs���{���m���A���ݎs�������y�ъW�אړs���{���m���i���Ə��O�^���ɌW��鎖�ۂ̔����̏ꍇ�ɂ����ẮA�喱��b���тɓ��Y���ۂ����������ꏊ���NJ�����s���{���m���y�юs�������j�ɒʕȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ݓs���{���m���y�ъW�אړs���{���m���́A�W���ӎs�������ɂ��̎|��ʕȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���̏ꍇ�ɁA�喱��b�́A�s���{���m�����͎s�������̗v���ɂ��A���̎��ۂ̔c���̂��ߐ��m����L����E����h�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�����q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@��15��
�@���q�ً͋}���Ԑ錾�ɂ��ċK�肵�����́A�喱��b�i�o�ώY�Ƒ�b�A�����Ȋw��b�����͍��y��ʑ�b�j�́A�ʕꂽ���ː��ʂ��A���A�ޔ����K�v�ɂȂ�Ɨ\�z�����ُ�Ȑ����̕��ː��ʈȏ�̕��ː��ʂ����o���ꂽ��A���́A���q�ً͋}���Ԃ����������ƔF�߂���Ƃ��́A���t������b�ɕ��s���B���t������b�́A���q�ً͋}���Ԑ錾�y�ыً}���ԑ�����{���ׂ����A���q�ً͋}���Ԑ錾�̊T�v�A�����̋��Z�ҁA�؍ݎ҂��̑��̎ҋy�ь����̒c�̂ɑ����m������ׂ������̌������s���B���q�ً͋}���Ԑ錾�̉������{�����ɂ��B
�@����̎��̂ɂ��āA�{�@10���ɂ��ʕ�`��������
�@���q�͖h�ЊǗ��ҁi�����d�́j�ˌo�ώY�ƏȁA���q�́E�ۈ��@�ˎ喱��b�˓��t������b
�@�ʕ�i�j���ꂽ���e�́A���[�����ɂ���Č��\����A����ɂ���Đ��{�̌����������֍��m���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�{�@15���ɂ��A���q�ً͋}���Ԕ�����F�߁A���t������b�͌��q�ً͋}���Ԑ錾�����āA�����̋��Z�ҁA�؍ݎ҂��̑��̎҂̔���c�̂̒��i�����j�ɖ�
�@�Q�l�����A����
�@���d�A�������q�͎��̒�����
�@����E���d�������q�͔��d�����̒�����
�@���{�A���d�A�������q�͔��d���ɂ����鎖�̒����A���؈ψ���ԕ�
�@�����V���A�@���o�V���A�ǔ��V���A��������A�e��ƊE���A�������A�T����
�@�厭�N���A�u�����g�_�E���v�u�k��
�@���㐳�N�A�}�����l�A�����m���Y�A�u���������ʼn����N�����̂��v�����H�ƐV��
�@���J��Y�A�u�������̕��̐^���ƃE�\�v���t�V��
�@�����h���v�u���������̐^���v���}�V��
�@���o�T�́A�u�������̂Ɣ_�̕����v�L�@�_�ƋZ�p��c
�@���o�T�́A�u�B���ꂽ���q�͊j�̐^���v�n�j��
�@���q�͎������A�u���A���d�����g���u���B���v��g�V��
�@��荎�n�A��c�q��A�u�����픘�v��g�V��
�@�����V�����ʕ��A�u�v�����e�E�X��㩁v������Њw��
�@���J��c���Y�A��J�A�u�V�F�[���K�X�v���Ő��E�͌��ς���v���m�o�ϐV���
�@�����h���v�A�u�m�����E�v���}��
�@�}���A�u���E�̔_�ƂƐH�����v�i�c����
�@���Ґ���A�u�}��A���H��v�����H�ƐV����
�@�������A���|�t�H�A13�N6�����u�����Ƒ����m�푈�v
�@���ԗ��A�u�c���p�h�����v�������A���|�t�H�A�f��
�@���ʗ���A�u�҂����z�R��̏����v��g�V��
�@�c������Y�A�u���ő�̍ɑ��c���p�h�A���b�L�[�h�����͖��߁v�u�k��
�@����ΎO�A�u���O�̌n���v���m�o�ϐV���
�@���{�o�ϐV���ЕҁA�u�������ρv���o�V���o�Ŏ�
�@�u�Ζ��̐푈�ƃp���X�`�i�̈Łv�A���b��
�@�z�A�u�㓡�V���E��k�Ђƒ�s�����v�}���V��
�@�Җ{�Ö��A�u�R�{�����q�_�v
�@���o�V���A2010�N9��2���[���A�u��@�̌��f�A�����嗘�v�L��
�@���؏r�Y�A�u�C���p�[���v���t����
�@���R�ˑ��Y�A�u�����e���c�A�t�[�R�����v
