コラム
「ふたば創生」片寄 洋一さん(高6回)
あの大惨事から4年が経過した。避難生活は未だ続き、何時になったら避難指令解除になるのか誰も判らない闇の中にある。また避難指示解除の令がでても、以前と同じような生活が戻ってくる保証は全く無い。それどころか新たな苦難の始まりになりかねない。
ふる里の人々は苦しみ、悩み、絶望の淵にいる。このような時に安閑として傍観している場合ではない。ふる里の惨状を救済したい、手助けの方法は何かないか、恩返しをしたい。双高OBとして思いは同じ、東京栴檀会として何か出来ないか。ここに各種の資料を提供し、OB諸兄姉の叡智と行動を期待したい。
高6回 片寄 洋一
第25章 我が国の電力事情
「我が国電気事業」

我が国の電気事業は1882年(明治15年)に藤岡市助(日本のエジソン)(電力の父)とも呼ばれた発明王、実業家。東芝の創業者の一人でもある。同氏による東京電燈の設立請願がなされた時をもって電気事業が誕生し、その後1887年(明治20年)に東京・日本橋に発電所が建設され、付近のごく限られた地域だけに電気が供給され、初期の発電は機材一斉を外国から輸入したもので発電機は小規模な火力発電で蒸気機関による発電でしたから町中に造られ、かつ送電能力がなかったのでごく近隣だけに供給されるだけだから、各地に発電所を造る必要があった。
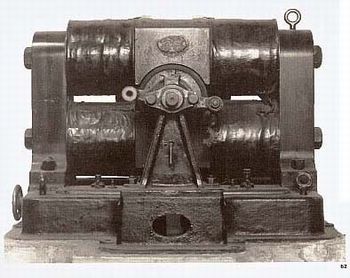 |
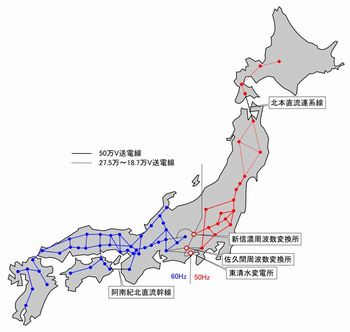 |
その後は地方に電力会社、発電所が開設され、日清戦争を契機として全国的に電気事業が普及した。
電気事業の初期は小規模の火力発電であったから、発電機を輸入した最初は直流発電であったが交流の優位性の高まりによって交流発電、交流送電にドイツ・AEG社製発電機(50Hz、AC3kv、265kVA)を購入し1893年)浅草発電所を建設した。
これに対して関西では1888年大阪でアメリカ・GE社製発電機(60Hz、AC2、3kv150kW)を採用したことによって、これらを中心として次第に東日本は50Hz、西日本は60Hzが定着してしまい、国内的には50Hz、60Hz二統があり、その境界線は糸魚川静岡構造線にほぼ沿い、東側が50Hz、西側が60Hzで周波数の違いがあるが、実用的な弊害はあまりなかった。
第二次大戦後、復興に併せて商用電源周波数を統一しようとする構想があったが、復興事業が優先され、立ち消えとなってしまった。
事実上統一する必要性は殆ど無いが、今回の東日本大震災のような大規模災害が起きた場合、発電施設が被害を受け、電力不足に陥った場合、西日本から緊急に電力、送電してもらうことは出来ない。
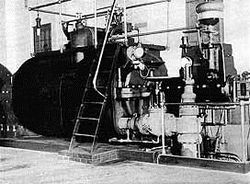 |
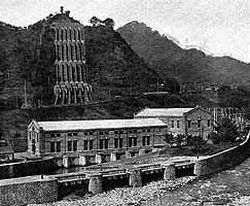 |
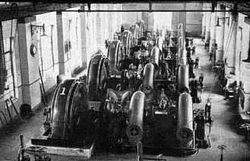 |
但し周波数交換所を設ければ東西間の電力供給は可能であり、一部交換所が設置されている。
交換できる電力は100万kw(東清水変電所)があるが、フル操業でも120万kwと少ない。大規模災害などの場合を除いて需要に投資が追いつかないので統一の必要性があまりないまま今日に至ってしまった。
一般家庭での電化製品では電気時計、レコードプレイヤー、電子レンジ、蛍光灯、洗濯機等には不都合が起きることがあるので糸魚川・富士川ラインを挟んでの東日本~西日本への転居の時は要注意となる。
1907年[明治40年]には東京電灯が山梨県に本格的な水力発電所である駒橋発電所を稼働させ、富国強兵の観点からも電気事業は重要な政策の課題であった。
よって1910年(明治43年)には全国の河川を対象にして包蔵水力の調査を組織的、かつ大規模に実施した第一次発電水力調査が行われ、同時に翌1911年には電気事業法が施行され電気事業者の公益性が確立。同時に発電用水利権や土地立入権、山林伐採権などあらゆる権利が保障された。
同法の成立以後、各電力会社は競って大規模なダム式水力発電所の建設を行い、福沢桃助による大井ダムの建設など全国各地で建設が行われた。
福島県においては1914年(大正3年)猪苗代第一水力発電所が建設され、東京・田端まで約225km区間の長距離高圧送電に成功し、送電技術が確立した。
東京発送電(現在の東電)・猪苗代第一発電所が福島県最初の水力発電所で、それ以来今日に至るまで首都圏の貴重な電源となって、電気を送り続けてきた。
大正3年(1914年)10月、運用開始
発電形式、水路式(有効落差:105.67m)
水車:立軸フランシス水車×4台、最大出力:62,400kw、常時出力:13,000kw
この発電所は建物や内部の発電設備は何度か新替が行われてきたが、場所は同じ所で現在も活躍している。
猪苗代湖を始め裏磐梯の秋元湖、小野川湖、檜原湖、その周辺の河川等には数多くの水力発電所が設置された。大正後期から昭和初期には首都圏の電気のふる里と言われていた。
猪苗代湖は、湖の東岸をほぼ南北に川桁断層に伴う陥没によって形成された湖盆の西側が、その後の磐梯山や猫魔ヶ岳の噴出物や泥流で堰き止められできた湖だから会津盆地の東側に位置し、会津盆地の中心よりは標高が高いところに位置する故に、この標高差が水力発電には好適となった。
猪苗代湖の堪水面積:104k㎡、最大深度94m、湖面標高514m、による国内では琵琶湖に次ぐ巨大な湖となる。また猪苗代湖の北に位置する磐梯山の北山麓には裏磐梯湖沼群と呼ばれる多くの湖沼がある。
これらは明治21年(1888年)の磐梯山大爆発に伴って泥流が北側に流れ、多くの河川や谷を堰き止め、檜原、小野川、秋元の湖が形成され、また泥流が窪地を埋め、溢れた水が五色沼等の沼、湿地帯を形成し、それらの水力を活用して多くの水力発電所が施設され、猪苗代湖周辺は当時としては水力発電所の一大集積地帯となった。
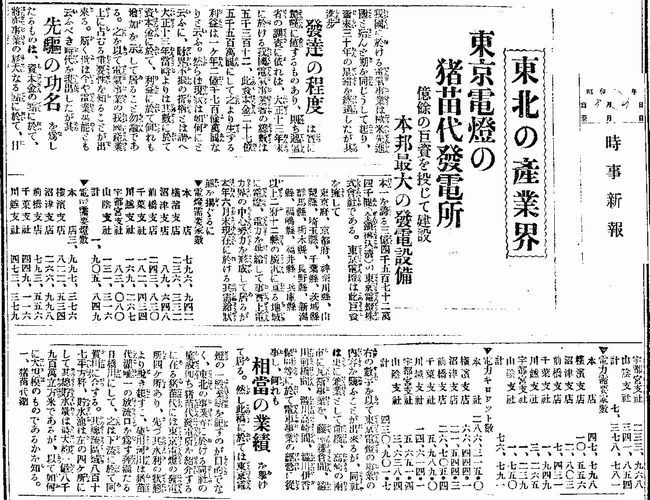 |
|
 |
 |
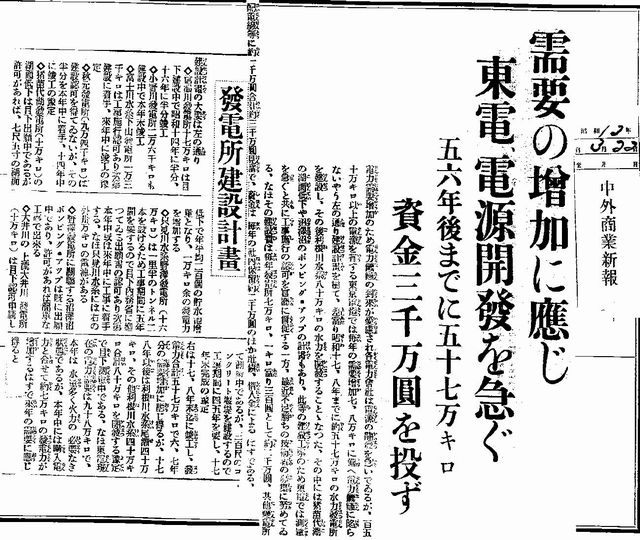 |
|
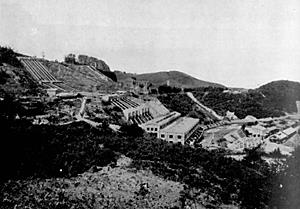 |
|
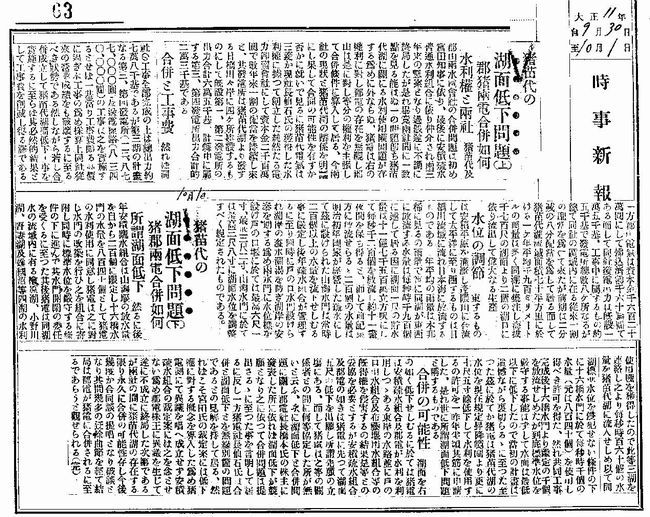 |
|
 |
 |
大正時代や昭和初期に建設された水力発電所は、内部の機材は新替えされたが、初期に建設された同じ場所で外観が同じ現役の水力発電所として活躍している。
安積疎水
現在、富岡町をはじめとして多くの避難者が郡山市や周辺の仮設住宅や借り上げ住宅に住んで居られるが、富岡町仮設役場がある近くに開成山公園があるが、嘗ては安積疎水の中心地であった。
安達太良山の噴火で溶岩や噴火灰で不毛の大地が広がって安積原野と呼ばれた不毛の地であった。その原野を潤したのは安積疎水と呼ばれる猪苗代湖から取水し、奥羽山脈を超えて安積原野に農業用水、工業用水、飲料水として供給した疎水が完成したからで郡山市周辺発展の礎となった。
水力発電にも活用されている。この疎水は那須疎水、琵琶湖疎水、安積疎水の日本三大疎水の一つに数えられる程の大工事であった。
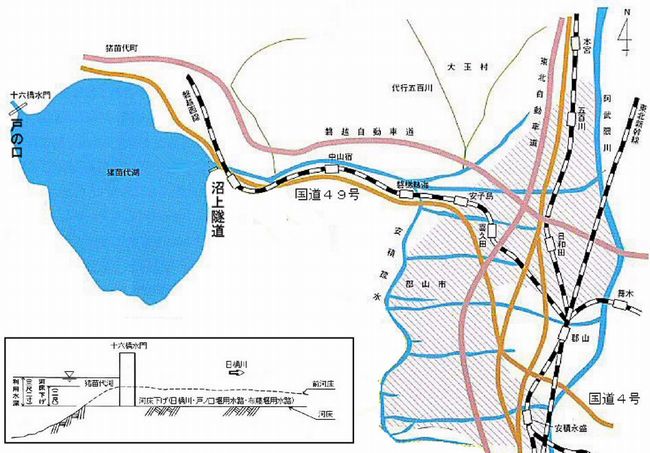 |
|
 |
 |
こうしてみると、会津地方や中通地方は比較的早くから投資が行われ、新しい企業・産業化が行われていたことが良く判る。双葉地方の後進性は地形的なものなのか、地元を引っ張る有能な人材が不足していたのか。
全国の発電ブーム
技術的成功をみて大正時代は電力企業のブームとなって、電力会社が新たに参入してきたが、やがて政府による整合が行われ、東京電灯、東邦電力、大同電力、宇治川電力、日本電力のいわゆる「五大電力会社」に統合された。
これらの会社を中心として木曽川、信濃川、飛騨川、天竜川、庄川等で大規模なダム式水力発電所が建設された。
ところが江戸時代からあった農業用水の慣行水利権が一方的に侵害され、下流域農民との対立が尖鋭化してきた。例えば農業用水の取り入れ口がダムで水没して流水が極端に減少して河川の漁業がだめになり、山林からの木材の搬流ができなくなった等の弊害が出るのは当然であって紛争の続出に悩まされた政府は、河川管理の一元化として内務省が一括管理することになった。
1926年(大正15年)8月26日河川行政監督令を発令。ダムや水力発電所、及びそれに関連する施設で河川に設置する全ては内務大臣の許認可を必要とすることで、国家管理を強化し、内務省による電力行政の介入、後に電力国家統制への端緒はこの時造られた。
昭和の時代に入ると電力業界の監督権は内務省より逓信省電気局に移り、1939年[昭和14年)から1951年[昭和26年]までの間、即ち戦中、戦後の激動期我が国の電力事業を司って特殊法人が「日本発送電株式会社」国家総力戦体制を構築しようと当時の日本政府の電力国家管理政策に基づき、日本電灯、日本電力など、全国の電力会社の現物出資や合併によって設立された半官半民のトラストであった。「電力国家統制法案」は第一次近衛内閣において内閣調査局より1938年(昭和13年)1月、国家総動員法などともに提出され、日中戦争が次第に激化するに従い、戦時体制が強化され軍部の意向が強く反映する様になった。
「電力国家統制法案」は三つの法案からなる「電力管理法案」・「日本発送電株式会社」・「電力管理に伴う社債処理に関する法案」である。
これらの法案は、電力会社、道府県、民間企業の全てを対象に、日本に存在する全ての電力施設を国家が接収・管理するという法案であって、その接収した電力施設は半官半民の「日本発送電株式会社」によって管理・運営を行う「一元運営」である。
その裏にいるのは軍部、特に陸軍が存在した。
この法案成立には当然電力業界は猛反発、特に東邦電力社長の松永安左右衛門氏は猛烈に噛みついた。戦後「電力の鬼」と呼ばれ電気事業の復興を担ったあの松永氏である。
怒った陸軍は憲兵隊を使って抑圧・弾圧を加えてきたので、同氏の命の危険を心配した企画院総裁鈴木禎一氏(予備陸軍中将)が身柄をあずかり、全ての役職を辞任させ隠遁させた。
以後、軍の圧力によって正面切って法案に反対する勢力はなくなり、軍部独走に拍車がかかった。
国会での審議でももめたが衆議院・貴族院(当時)の両院協議会で調整されて1938年3月26日に成立、国家総動員法とともに4月1日から施行され戦時体制は整った。
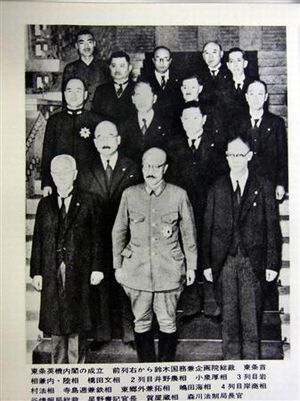
こうして発送電事業に続いて配電事業も国家統制が推進され、太平洋戦争直前の1941年(昭和16年)8月、配電統制令が公布、即日施行された。(この当時の議会は大政翼賛会の1党独裁、即ち軍部の意向の賛成機関になる)
全国各地の配電事業者は統合され、五大電力会社をはじめ、多くの電気事業者は解散、代わりに全国九ブロック(北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州)に新たな設立され、この九配電事業体制の下で日本発送電株式会社と連携して配電事業を行う、即ち日本の電力事業は全て政府の管理下に置かれることになり、軍部宿願の電力国家統制が実現した。
組織としては総裁が置かれその下の幹部社員の任命権は内閣にあり、経営の意思決定機関は事実上内閣にあり、主務大臣は逓信大臣・内務大臣であったが後に軍需省が新設され軍需大臣が主務大臣になった。
1941年(昭和16年)10月18日 ~ 1944年(昭和19年)7月22日
東条内閣(東条英機陸軍大将)
内務大臣(安藤紀三郎予備役陸軍中将)
逓信大臣(寺島健予備役海軍中将)
軍需大臣(東条首相の兼任)
その後内閣改造はあったが軍人が担当大臣になった。改造破綻と大臣職の入れ替えはあったが後任も軍人が登用され、東条首相が内務、外務大臣・陸軍大臣・軍需・文部・商工・参謀総長・主要大臣で半数以上を一人で兼任、陸軍独裁政権となった。
1945年(昭和20年)8月15日 ポツダム宣言受諾、無条件降伏
只見川開発の歴史

只見川の開発は、猪苗代湖開発において初めて水力発電事業が計画されたのは1910年(明治43年)で日露戦争が終わってやっと一息ついた頃になる。
岩代水力電気事業として発起人として太田黒重五郎等が只見川と伊南川の各1カ所に導水路式発電所を計画、河川管理者である宮田光男福島県知事(当時)が最初で、それ以降様々な電力会社が只見川、阿賀野川、沼沢湖等の発電用水利用水利権取得申請が出され、これらを受理した福島県、新潟県、群馬県において水利権獲得のための闘いが始まった。
また源流である尾瀬沼についても水利権獲得の申請がなされ、関東水電株式会社を設立、尾瀬沼にダム式水力発電所を建設し、水は利根川に放流するという計画で群馬県知事に申請し認可された。
この他にも数々の水力発電計画により水利権の申請が福島県、新潟県、群馬県の各知事に提出され認可されたから利権あるところ必ず政治家や資本家や地方の有力者が群がり、それぞれの思惑が衝突し合った。
また水力発電には最高の立地条件が揃っていることは険しい山岳地帯、過酷な気象条件が揃っていることになり投下資本も膨大なものになるから会社側も1社では負担しきれず吸収合併が繰り返される結果となった。
戦前、只見川の水力発電事業には長大なトンネルによる水路式発電所・野沢発電所が東北電力によって進められていたが、東北電力は尾瀬沼ダム建設を進めていた関東水電とともに信越電力株式会社に吸収された(昭和3年)。
この信越電力会社も合併後、東京発電株式会社と名称を改め、更にほどなく東京電燈株式会社と合併するという目まぐるしい電力会社の変遷があった。
従って只見川、阿賀野川流域の水力発電所は東京電燈株式会社が一つ手に握ることに成り、さらに猪苗代湖や裏磐梯三湖の水力発電事業を行っていた猪苗代水力発電も吸収合併したから、福島県内の水力発電は全て東京電燈株式会社の支配下にあったことになる。
ところが1929年(昭和4年)世界恐慌が起こり、日本経済は深刻な影響を受け、それに伴い電力需要が急速に落ち、反面需要を見込んで電力増強に力を注いだが、それがかえって裏目に出てしまい、不況は更に深刻なものになってしまった。
その後は不況打開として「帝国の生命線は満蒙にあり」のスローガンを掲げた陸軍は、満州事変、シナ事変、ノモハン事変、太平洋戦争へと15年戦争へと突き進むことになり、我が国はどん底の悲哀を味わうことになった。
戦時態勢を進めていた軍閥政府は電力の国家統制を決め、電力業界に暗雲が立ちこめてきた。
1938年(昭和13年)東条英機中将(当時)を中心とした陸軍統制派は第一次近衛内閣に猛烈な圧力をかけ、戦時体制を遂行するためには電力の国家管理も病むなし、としたため松永安左右衛門氏を筆頭とする電力業界挙げて猛反発した。
怒った陸軍は憲兵隊を使って抑圧・弾圧を加えて、更には特高を使って思想弾圧まで加え、同氏の命の危険を心配した企画院総裁鈴木禎一氏が身柄をあずかり、全ての役職を辞任させ隠遁させた。
以後、軍の圧力によって正面切って法案に反対する勢力はなくなり、軍部独走に拍車がかかった。
第73回帝国議会に「電力国家管理法案」を上程、1939年4月1日、「国家総動員法」と共に電力管理法・日本発送電株式会社法が成立。これに伴い特殊法人として発足した日本発送電株式会社は出力5000kw以上の水力発電所、出力1万kw以上の火力発電所をほぼ例外なく管理下に置き、日本全土の発電所を支配し、かつ同規模の新規電力開発を田の電力会社が実施することを禁止した。
かくして電力業界の監督権は内務省より逓信省電気局に移り、1939年[昭和14年)から1951年[昭和26年]までの間即ち戦中、戦後の激動期我が国の電力事業を司って特殊法人が「日本発送電株式会社」国家総力戦体制を構築しようと当時の日本政府の電力国家管理政策に基づき、日本電灯、日本電力など、全国の電力会社の現物出資や合併によって設立された半官半民のトラストであった。
「電力国家統制法案」は第一次近衛内閣において内閣調査局より1938年(昭和13年)1月、国家総動員法などともに提出され、日中戦争が次第に激化するに従い、戦時体制が強化され軍部の意向が強く反映する様になった。
「電力国家統制法案」は三つの法案からなる「電力管理法案」・「日本発送電株式会社」・「電力管理に伴う社債処理に関する法案」である。
これらの法案は、電力会社、道府県、民間企業の全てを対象に、日本に存在する全ての電力施設を国家が接収・管理するという法案であって、その接収した電力施設は半官半民の「日本発送電株式会社」によって管理・運営を行う「一元運営」である。
国会での審議でももめたが衆議院・貴族院(当時)の両院協議会で調整されて1938年3月26日に成立、国家総動員法とともに4月1日から施行され戦時体制は整った。
こうして発送電事業に続いて配電事業も国家統制が推進され、太平洋戦争直前の1941年(昭和16年)8月、配電統制令が公布、即日施行された。(この当時の議会は大政翼賛会の1党独裁、即ち軍部の意向の賛成機関になる)
全国各地の配電事業者は統合され、五大電力会社をはじめ、多くの電気事業者は解散、代わりに全国九ブロック(北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州)に新たな設立され、この九配電事業体制の下で日本発送電株式会社と連携して配電事業を行う、即ち日本の電力事業は全て政府の管理下に置かれることになり、軍部宿願の電力国家統制が実現した。
 |
終戦、国家体制の崩壊

1945年(昭和20年)8月15日、ポツダム宣言受諾、無条件降伏、軍閥の呪縛から解放された。
しかし全ての国家体制が崩れ、全てを失ってしまった。残されたのは焼け尽くされた国土と飢えに苦しむ国民だった。
戦後の我が国を襲ってきたのは猛烈な飢餓で、終戦直後、東京には都民の食糧が3日分しか倉庫にはなかった。GHQは日本国民の半数、政府は1千万人の餓死を見込んでいた位の凄まじい食糧不足であった。
従って戦後の政府の最大の仕事は如何にして食糧増産の方策をたてるかにあり、それが傾斜生産方式を編み出し、化学肥料の増産、そのための電力確保にあり、電力産業振興が最重点政策になった。なんといっても電力は国家の原動力である。
我が国の電力事情を遡って検証する必要がある。
戦後
1945年(昭和20年)8月15日、ポツダム宣言受諾、無条件降伏
1946年、日本発送電は只見川、阿賀野川の総合開発的な水力発電計画を企画、独自の調査を開始、南会津郡伊北村に調査事務所を設置して、只見川の流量や地形、気象、水分等の綿密な調査を開始した。
さらに、翌1947年には商工省が只見川、尾瀬原・利根川総合開発計画を策定し、只見川流域の調査を日本発送電に依頼し、この調査所も上流と下流域担当を二分・強化拡大して調査を継続した。
1948年10月に「東北地方電力復興計画案」を纏め、北上川、十和田湖、田沢湖、猪苗代湖と共に只見川が最重要地点として挙げられ、特に只見川復興計画にある水力発電計画の87%に及ぶ約247万kwを只見川流域だけで新規開発可能との調査結果が報告された。
これを受けて1947年「只見川筋水力開発計画概要」が発表された。
この計画概要によれば只見川と阿賀野川に連続して15ヵ所にダム式発電所を設け、既設5発電所と出力増強を謀ることで235万kwに及び、年間増加発電量は55億kw時にも上がるとして開発の有効性を主張した。
この中での根幹事業として只見川最上流部に4ヵ所、伊南川の1ヵ所に巨大ダムを建設し大容量の貯水池を建設することとし、ここに初めて奥只見ダム、田子倉ダムの二大ダム計画が登場した。これに伴い尾瀬原ダムはこの計画で揚水発電から一般水力発電に修正され、縮小された。その結果、利根川への分水も無くなり、ダムの規模も縮小された。この案は後に「只見川本流案」となった。
本流案は只見川・尾瀬原・利根川総合開発計画案を審議する「只見川・尾瀬原・利根川総合開発審議会」に1948年提出され審議開始となった。
ところが同時期新潟県側から只見川の豊富な水量を信濃川水系に導水して灌漑を行い、水田耕作を一挙に拡大しようとする「只見川分水案」が提出された。
また、尾瀬分水案に関する群馬県の主張があり、福島県、新潟県、群馬県の三つ巴の争いが火種となり長期の抗争の始まりとなった。
ところがこれらの水力発電総合開発計画を策定した日本発送電は1948年、GHQより戦時体制に協力した独占資本であると断定され過度経済集中排除法の指定を受け解散を命じられた。
終戦の翌年である1946年、日本発送電は只見川、阿賀野川の総合開発的な水力発電計画を企画、独自の調査を開始、南会津郡伊北村に調査事務所を設置して、只見川の流量や地形、気象、水分等の綿密な調査を開始した。
さらに、翌1947年には商工省が只見川、尾瀬原・利根川総合開発計画を策定し、只見川流域の調査を日本発送電に依頼し、この調査所も上流と下流域担当を二分・強化拡大して調査を継続した。
日本発送電の解体
電気事業は軍需省が廃止され、商工省(現通産省)に移管されたが、経済政策全般は経済安定本部で審議され、1947年、経済安定本部は河川総合開発調査審議会を発足させ河川開発に関する調査を行ったが、この中で商工省は新規水力発電開発を行うため7河川2湖沼を対象地域として開発計画を検討した。同時に日本発送電も独自に大規模な水力発電開発の計画を立案し、電力不足を根本的に快復させようと乗り出した。
そのようなときに1948年、GHQの指令が下され日本発送電が解散させられたが、各電力会社も公職追放により多くの幹部職員が職を解かれていた。
そして軍閥政権から隠遁を余儀なくされていた松永安左右衛門氏が再登場し、活躍が始まった。電気事業再編成審査委員長に松永氏が就任、1950年に電気事業再編成が発令され、日本発送電が所有していた地方の発電所は全国9ブロックに分割され、全国九電力会社に分割・民営化が図られた。
この中で東京支社は東京電力になり、東北支社は東北電力に改組・発足した。
東京電力は東京電燈時代から只見川開発に深く携わっており、只見川開発のノウハウは蓄積している、と主張。一方、東北電力は東京電燈時代も日本発送電の時も只見川開発に携わっており、しかも流域である福島県は東北であるから東北電力がその継承者であると主張した。
その対象になったのが田子倉ダム(只見川・福島県)、朝日発電所(飛騨川・岐阜県)長沢発電所(吉野川・高知県)、上椎葉発電所(耳川・宮崎県)の実施調査が行われた。
ここに只見川総合開発が脚光を浴びることになり、電力不足を補い、経済復興の重要な鍵を握る総合開発と期待を持って遂行されることになった(次章で只見川総合開発を述べる)。
連合国の占領という事態となり、「オキャパイドジャパン」という国名で呼ばれ、全ての指令は、最高司令官マッカサー元帥の指令下にあり、GHQの命令は絶対服従であった。
このGHQ指令が次々と下令されたが、その中に軍人追放令、あらゆる分野における公職追放令、戦争に協力した独占資本の解体(財閥解体)、地主制度の解体(土地解放)、明治政府樹立後に築かれてきた社会機構、制度が根本から覆され、アメリカ式価値観が押しつけられた。
 |
| (右端吉田首相と白州次郎氏GHQのパーティー) |
このような社会情勢下で電力業界も例外ではなくGHQから日本発送電の解体、商工省電力局から電力会社への管理権能を剥奪、経営に関与しない調整機関の設置、この二つの条件を強行に要求してきた。さらには電力再編成を占領軍命令で強行する準備を進めており、これを察知した第二次吉田内閣はGHQの介入を阻止すべく、先手をうって電気事業再編成審議会を設置し、電力事業再編成は我が国政府主導で行うことを宣言した。この件に関しGHQと粘り強く交渉を続け、日本側に有利な再編計画を認めさせたのは、鬼才白州次郎氏の努力に依るもので、吉田首相を援けGHQとの難しい交渉は抜群の語学力をもって対等に渡り合った同氏の功績によるものです。GHQの高官が「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた人材で、その活動の模様は(白州次郎氏の活躍は2009年、NHKで放送されたテレビドラマの特別番組全3回「ドラマスペッシャル・白州次郎」主演・伊勢谷友介、妻正子・中谷美紀、その他有名俳優が演じ、重厚かつ見応えのあるドラマだった。)
電気事業再編審議委員会には復興金融公庫理事長・工藤昭四郎、慶応大学教授小池隆一、日本製鉄社長三鬼隆、国策パルプ副社長水野成夫、そして審査委員長は「電力王」「電力の鬼」と云われた松永安左右衛門氏が任命され、審議の結果「電気事業再編成法案」「公益」事業法案」として提出した。だが国会では反対意見が相次ぎ国会審議は紛糾した。
だが再編制を急ぐGHQは早急な成立がなければあらゆる許可を停止すると強硬な態度を示し、追い詰められた政府は第九国会に再提出を検討したが、成立する可能性は全くなく、煮え切らない政府に怒ったGHQは1950年(昭和)25年11月24日、伝家の宝刀であるポツダム政令を発して電力再編制のための二法令、即ち「電気事業再編成令」「公益事業令」を公布した。
ここにおいて集排法指定から三年にわたって紛糾した日本発送電と九配電会社の分割、民営化問題に決着をみたのである。
しかし、利権が絡む諸問題が山積し、それは日本発送電施設の分与、及び水力発電における発電用水利権の帰属等、複雑多岐にわたる難題を解決していったのは電力の鬼・松永安左右衛門氏の功績は大きい。
基本的には属地主義として各地に存在する施設は新たに設立した九電力会社(北海道電力、東北電力、関東電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力)に移管すると定められた。(沖縄電力は当時未だ占領下にあり、日本復帰後設立した)
そして電力九分割後、松永安左右衛門氏は電力技術の研究開発を効率的かつ外圧に影響されることなく実施するため、九電力会社の合同出資でありながら、完全中立を堅持する公益法人として、民間初のシンクタンク電力中央研究所を設立し、自ら理事長に就任、電力業界全体に影響を及ぼす文字通りのシンクタンクになった。
この電力再編に関して、活躍した「電力の鬼」松永安左右衛門氏と吉田首相のブレーンであった白州次郎氏の二人が中心となった。白州氏は終戦連絡中央事務局を造り難しいGHQとの交渉を得意の語学力で一手に引き受け、吉田内閣を支え中心となって活躍した。そしてこの時に培った人脈、政治力が只見川総合開発において大いに発揮され、福島県・東北電力の連合が主張した只見川本流開発案に決定に至る原動力となった。
戦後の我が国を襲ってきたのは猛烈な飢餓で、終戦直後東京には都民の食料3日分しか倉庫には残っていなかったという。
GHQは日本国民の半数、日本政府は1千万人の餓死を見込んでいた位の飢餓状態にあって凄まじい食糧不足に悩まされた。
したがって戦後の政府の最大の仕事は如何にして食糧生産野方策を立てるかにあり、それが傾斜生産方式を編み出し、化学肥料の増産、そのためには電力の確保にあり、電力産業振興が最重点政策となった。
国力を左右する電力事情を遡って検証する必要がある。
九電力編成

1950年、日本発送電がGHQ指令により解体され、電力再編成が行われた。基本的には属地主義として各地に存在する施設は新たに設立した九電力会社(北海道電力、東北電力、関東電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力)に移管すると定められた。沖縄電力は当時未だ占領下にあり、日本復帰後設立したので実際は十電力体制になる。
経済復興の原動力となるのは豊富な電源であって、電力確保が絶対必要要件であり、この電力確保の為、政財界が慌ただしく動き始めた。
極端に不足している電力に対し、占領時代の電力に対するGHQの介入はどうであったか。まず全国の電力を管轄していた日本発送電の解体、商工省(現通産省)電力局から電力会社への管轄権能を剥奪、経営に関与しない調整機能の設置、この二つの条件を強硬に求めてきた。
さらに電力再編成をGHQ指令で強行すべく準備を進めており、これを察知した第二次吉田内閣はGHQの介入を阻止すべく、先手を打って電気事業再編成審議会を設置し、電力事業再編成は我が国政府指導で行いたいとGHQと粘り強い交渉が行われた。
この時活躍したのが吉田首相の懐刀といわれていた鬼才白州次郎氏で、抜群の語学力、巧みな交渉術でGHQ高官と対等に渡り合い、「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた人材で、GHQとの交渉で難題は全て同氏が担当した。
かくして電力再編成のための二法令、「電気事業再編成令」「公益事業令」を公布した。
しかし、利権が絡む諸問題が山積し、それは日本発送電施設の分与、水力発電のおける発電用水利権の帰属等、複雑多岐にわたる難題を解決していったのは電力の鬼といわれていた松永安左右衛門氏の功績は大きい。
この松永氏の活躍を手助けしたのが当時東京電力の一課長であった木川田一隆氏で、派遣されて松永氏の秘書となり、松永氏が驚嘆するほどの大活躍をし、電力界の次世代を背負うのは木川田氏だと太鼓判を押したほどであった。
確かに見込み通りとなって、やがて東京電力社長となり、福島原発建設の大号令はこの人によって発せられた。
 |
次世代の基本的には属地主義として各地に存在していた電力会社が独立した民営化した九電力会社となって(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、四国電力、九州電力)移管された。沖縄電力は当時米軍の占領下にあり、軍政が敷かれており電力も軍政下にあり、沖縄電力が創立されたのは日本復帰後となった。
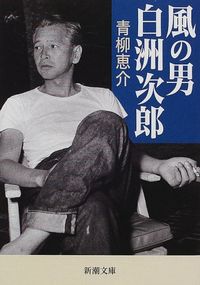
電力九分割後も松永安左右衛門氏は電力技術の研究開発を効率的かつ外圧に影響されることなく実施するため、九電力会社の合同出資でありながら、完全中立を堅持する公益法人として、初の民間シンクタンク、電力中央研究所を設立、自ら理事長に就任、電力の業界全体に影響を及ぼす文字通りのシンクタンクとなった。
一方、白州次郎氏は終戦連絡中央事務所を創立し、GHQとの交渉を担当し、吉田内閣を援ける原動力となった。
昭和25年、講和条約問題で渡米しジョン・フォスター・ダレス氏と会談して日本独立のための平和条約締結の準備を開始し、翌1951年(昭和26年)9月、サンフランシスコ講和条約が締結され、新生日本が独立をはたした。

吉田内閣退陣後は、実業界に戻り、この同じ年、昭和26年、日本発送電分割問題で大紛糾しているとき、松永安左右衛門氏と共に活躍したのが白州次郎氏。
この時、東北最大の開発可能水力発電としては只見川流域が最大で、この水利権の3/4の権利を有していた水利権を巡って、古くからの権利を主張して徹底抗戦を挑んできた東京電力の主張を、当時の野田卯一建設大臣を説得して、水利権を東北電力に移し、東北電力繁栄の基礎を築いた、この功績により白州氏は東北電力会長になった。
白州氏は東北電力株式会社会長に就任し、只見川特定地域総合開発計画に指定されたことから、1959年(昭和34)会長職を退任するまで約8年間、只見川流域の電源開発事業に精力的に働き、奥只見ダムの建設を推進した。
 |
GHQの指示で造られた過度経済集中排除法野指定を受けて日本発送電が解体、地域電力会社荷分割された.しかし分割された当初の地域電力会社は資本力が余りにも弱く、復興に必要な電力を確保する力はなかった。そこで国内の電力需要の増加に合った体制を整えるため制定されたのが電源開発促進法により、1952年(昭和27年)9月6日国の特殊会社として「電源開発株式会社」が創設され、資本構成は67%が財務大臣、残りを9電力会社が保有した。
電源開会社の最初の大事業は佐久間ダムの建設であるが、これを僅か3年で完成させた。この成功によって関西電力は黒部峡谷にダムを建設することを決意したと当時の電力事情は水主火従の時代で、1950年に国土総合開発法に基づき地域開発計画の一つとして施行されたのが、只見川特定地域総合開発計画で、福島県と新潟県を流れる阿賀野川水系最大の支流である只見川を中心として阿賀野川下流域に至るまでの間に大小様々なダムを建設して水力発電所を造ろうという壮大な計画であった。
只見川の水源は福島県、群馬県、新潟県の三県にまたがる尾瀬国立公園の一つである尾瀬沼を水源とし、湿地の水を集めながら三条の滝を経て深い谷を刻んで南會津郡只見村を流れ、ここで伊南川と合流し、険しい山岳地帯である蒲生岳を過ぎると次第に北東に向きを換え大沼郡金山町で野尻川と合流、大沼郡三島町、柳津町、會津坂下町を過ぎて會津盆地を流れ、喜多方市高鄕町付近で阿賀野川に合流する。
流路延長146キロ、流域面積2,800k㎡。水量は豊かで、年間降雨量2,500~3,000mmに達する多雨地帯であり、冬季は豪雪地帯でも知られており、春季の融雪、更には源流から阿賀野川合流点までの落差が1500メートルもあり、急流、豊富な水量、高落差という水力発電に必要な三点の条件が揃っていたため、国内では最も有望な電源開発地帯として、古くは明治43年には小さな水力発電所が開設された。
只見川電源開発計画
尾瀬沼を水源とし、阿賀野川に注ぐ只見川は、有数の豪雪地帯であり、かつその流域は山間地帯で、その水量は豊富、急流であるため、古くから水力発電として最適地として、明治後期より電源開発計画がなされていた。
 |
戦後、荒廃した国土を復興するための電源開発の重要性が一段と高まり、既に只見川は1947年に「只見川筋水力発電開発要項」日本発送電によって纏められており、内容は戦前の案と同様に只見川に11ヶ所、阿賀野川6ヶ所、伊南川3ヶ所、大津岐川1ヶ所に水力発電用のダムを建設、総貯水量580,000,000立方メートル、認可出力385,000kWのダム式発電所として計画され、この発電計画で行われると、当時全国で開発可能な水力発電は1,960,000kWであり、東北地方だけで云えば当時発電計画のあった発電水力の3/4は只見川水系だけで占めることになり、俄然只見川への注視が集中してきた。
利に敏いのは人の世の常、利権の亡者が集中してきた開発主導権を争う、東京電力と白州次郎氏が代表する東北電力、地域的な利権として水源である尾瀬沼は群馬・栃木・福島・に拡がり、かつ流域である奥只見は福島と新潟の県境、そうなると尾瀬高原の土地を所有する東京電力は尾瀬沼にダムを建設して利根川への分水案、新潟県は奥只見から新潟県十日町方面への分水案、福島県は本来の只見川総合開発案、三巴以上に絡み合った政争になった。陳情合戦、接待合戦で只見川は‘タダノミガワ’と揶揄される程であった。
1950年に国土総合開発法に基づき地域開発計画の一つとして施行されたのが、只見川特定地域総合開発計画で、福島県と新潟県を流れる阿賀野川水系最大の支流である只見川を中心として阿賀野川下流域に至るまでの間に大小様々なダムを建設して水力発電所を造ろうという壮大な計画であった。
只見川の水源は福島県、群馬県、新潟県の三県にまたがる尾瀬国立公園の一つである尾瀬沼を水源とし、湿地の水を集めながら三条の滝を経て深い谷を刻んで南會津郡只見村を流れ、ここで伊南川と合流し、険しい山岳地帯である蒲生岳を過ぎると次第に北東に向きを換え大沼郡金山町で野尻川と合流、大沼郡三島町、柳津町、會津坂下町を過ぎて會津盆地を流れ、喜多方市高鄕町付近で阿賀野川に合流する。流路延長146キロ、流域面積2,800k㎡。
水量は豊かで、年間降雨量2,500~3,000mmに達する多雨地帯であり、冬季は豪雪地帯でも知られており、春季の融雪、更には源流から阿賀野川合流点までの落差が1,500メートルもあり、急流、豊富な水量、高落差という水力発電に必要な三点の条件が揃っていたため、国内では最も有望な電源開発地帯として、古くは明治43年には小さな水力発電所が開設された。
終戦、日本中を震撼させる命令が連合軍最高司令官総司令部(GHQ)から次々と発せられ、戦争犯罪人の逮捕、裁判、軍人追放、あらゆる分野での公職追放、独占資本解体(財閥解体)、地主制度の解体(土地解放)等々、明治政府樹立以来築かれてきた社会機構、制度が根本から覆され、アメリカ式価値観の押しつけとなった。
このような状況下で電力業界も例外ではなく、極端に不足している電力に対し、GHQは切り込んできた。まず全国の電力を管轄していた日本発送電の解体、商工省(現通産省)電力局から電力会社への管轄権能を剥奪、経営に関与しない調整機能の設置、この二つの条件を強硬に求めてきた。さらに電力再編成をGHQ指令で強行すべく準備を進めており、これを察知した第二次吉田内閣はGHQの介入を阻止すべく、先手を打って電気事業再編成審議会を設置し、電力事業再編成は我が国政府指導で行いたいとGHQと粘り強い交渉が行われた。
この時活躍したのが吉田首相の懐刀といわれていた鬼才白州次郎氏で、抜群の語学力、巧みな交渉術でGHQ高官と対等に渡り合い、「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた人材で、GHQとの交渉で難題は全て同氏が担当した。
かくして電力再編成のための二法令、「電気事業再編成令」「公益事業令」を公布した。
しかし、利権が絡む諸問題が山積し、それは日本発送電施設の分与、水力発電のおける発電用水利権の帰属等、複雑多岐にわたる難題を解決していったのは電力の鬼といわれていた松永安左右衛門氏の功績は大きい。
基本的には属地主義として各地に存在していた電力会社が独立した民営化した九電力会社となって(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、四国電力、九州電力)移管された。沖縄電力は当時米軍の占領下にあり、軍政が敷かれており電力も軍政下にあり、沖縄電力が創立されたのは日本復帰後となった。
電力九分割後も松永安左右衛門氏は電力技術の研究開発を効率的かつ外圧に影響されることなく実施するため、九電力会社の合同出資でありながら、完全中立を堅持する公益法人として、初の民間シンクタンク、電力中央研究所を設立、自ら理事長に就任、電力の業界全体に影響を及ぼす文字通りのシンクタンクとなった。
一方、白州次郎氏は終戦連絡中央事務所を創立し、GHQとの交渉を担当し、吉田内閣を援ける原動力となった。
昭和25年、講和条約問題で、吉田氏の密命を受け、渡米してジョン・フォスー・ダレス氏と会談して日本独立のための平和条約締結の為の草案創りの準備に参加し、翌年昭和26年9月サンフランシスコ平和条約が締結された。
吉田内閣退陣後は実業界に戻ったが、日本発送電分割で大紛糾していたが、松永安左右衛門氏と白州次郎氏が中心となって解決に導いたが、それはGHQとの交渉の際に培われた人脈、政治力が大いに効をそうした。
日本発送電問題が解決すると、次にくるのは電源開発問題で、国土総合開発法に基づく、只見川特定地域総合開発法に基づく開発だが、この只見川総合開発がすんなりと決まったわけではない。日本政府、GHQ、福島県、新潟県、東京電力、東北電力、本流案、分流案、それぞれの利害得失が輻湊し、水利権を巡り、行政訴訟合戦が続き泥沼化した。
戦前からこの地域の水利権を持つ東京電力が徹底抗戦の構えを切り崩したのは、当時の野田建設大臣と白州次郎氏で、水利権を東北電力に移し、東北電力繁栄の基礎を築き、只見川総合開発への途を開けた。
しかしそれでも紛争は続き、福島県側は大竹作摩知事(摩耶郡北塩原村出身)、福島県選出代議士、県議団、地方自治体の大陳情団が結成された。
吉田首相のブレーンの一人だった広川廣禅衆議院議員(石川郡玉川村出身)が側面から援助した。
政府は妥協点を探るために度々電源開発調整審議会を開催、電源開発による奥只見・田子倉などの奥只見川上流域開発の方針を固めて地域紛争を排除し、かつ新潟県側が納得する妥協点を探った。

こうした度重なる協議の末、佐梨川への導水を廃止する代わりに奥只見ダムから信濃川水系の黒又川二只見川の水を分水し、黒又川に黒又第一ダム、第二ダムを始めとする合計4箇所の水力発電所の建設、ダムに貯水した水で越後平野の灌漑を行うという「黒又川分水案」を提示、昭和28年、吉田首相は、総理官邸に福島県知事、新潟県知事を招いて、最終案として「黒又川分水案」を提示、これを同意すするよう求めた。
福島県知事は県幹部、議員団とも協議の末、緒方竹虎副総理に了解の旨を伝え、新潟県側もこれ以上紛糾すればかえって分流案が不利になると判断して同意に踏み切り、かくして長かった抗争も終了した。
しかし、これで全てが収まって訳ではない。福島県、東北電力の本流案と新潟県、東京電力の分流案が対立し行政訴訟が更に続き、国会内でも二派に分かれ暗闘が続いた。
その他では中部電力の佐久間ダム、関西電力の黒部ダム建設と大型水力発電所の建設が続いた。
只見特定地域総合開発であるから、奥会津の山岳地帯に巨大ダムと発電所を建設であるから、資材運搬が最大の問題で、当時は鉄道輸送が主流で、当時施設されていた国鉄は、上越線小出駅からの支線で県境の大白川駅まで、福島県側は会津若松駅から會津宮ノ下駅までが開通しているだけで、肝心のダム建設地には鉄道はなし、JR只見線は、この時の資材運搬の為に建設された路線を払い下げで開通した。
 |
道路も劣悪な条件下にあり、冬季は豪雪で通行が遮断され孤立するのが通例であった。現在JR只見線は'11年の豪雨により災害を受け、会津川口駅と只見駅の間が不通となっており復旧の見通しは次章で述べたい。
1959年田子倉ダム完成、1960年奥只見ダム完成、その後続々とダム、水力発電所が完成、総合開発の夢は実現した。
第26章 只見川総合開発
福島県の地勢を見ると、面積では北海道、岩手県に次いで第三位(1万3,783平方キロ)、 特異な地勢で福島県は完全に三地方に分けられる。
特異な地勢で福島県は完全に三地方に分けられる。
会津地方、中通り、浜通りの三地方で会津地方は会津盆地を中心であり、かつて江戸幕府親藩としての雄藩会津藩の本拠地であり、その伝統は色濃く残る地方であるが、福島県の中心である中通り地方とは奥羽山脈で完全に隔離されており、猪苗代湖を源流とする阿賀野川は日本海に注ぐ、その支流である只見川が日本有数の水力発電所の集中地帯で戦後の日本の電力事情を支えてきた。
奥羽山脈と阿武隈山脈に挟まれた中通りは東北地方の入り口である白河の関の近くの山間を源流とする阿武隈川は福島県の中央を南から北へ流れ、宮城県に入ってから岩沼市付近で太平洋に流れ出る。
阿武隈川の流れに沿って東北本線、新幹線、東北高速道、国道が走り、白河市、郡山市、福島市がある。
浜通りは、太平洋岸に広がる海岸平野で南からいわき市、双葉郡、相馬郡があり、県央とは阿武隈山脈で完全に遮られ、三地方がそれぞれ独自な文化を育んできた。歴史を辿れば、三地方にはそれぞれの領主がいて治政にあたっていたが、近隣相互との領地争いのような事件はなく、村一揆や逃散のような悪政もなく貧しいながらも平穏な日々を送り、長閑な農村地帯だったらしい。
山脈で遮られていた当時は現在のような県地方としての交流はなく、大事件は時々中央の権力者から動員令がくるくらいであった。
その中でもっとも大きな勢力は会津藩で、江戸幕府と結び付き大きく東北地方の雄藩として栄えてきた。

會津藩の歴史
會津藩は、二代将軍秀忠の実子政之が大領を貰い、會津23万石を領したことに始まる。
家康の血筋としては最も優れた頭脳と政治能力があったと伝えられている。藩政は独特の政治学を持って整え、藩士を教育し、好学と尚武の藩風を造り、当時としては完璧と言えるほどの藩組織を造り上げた。
八代藩主容敬には子がなく、縁戚に当たる美濃高須の松平家から養子を貰い受け、嗣子とした、九代藩主松平容保である。
この順風満帆であった會津藩に悲劇がやって来た。尊皇攘夷に揺れていた京都の治安を護る為京都守護職を15代将軍慶喜から命じられ、一旦は断ったが、藩是が宗家に対する絶対服従であることから断り切れずに遂に承諾し、藩兵1千名を従え、京での任務を果たそうと、治安に励んだが、長州藩や脱藩浪士との激し闘いが続き、尊皇攘夷に傾く西国諸藩との間に軋みを生じてきた。
この會津藩の手先として京都の治安を担ったのが新撰組である。
この活躍が悲劇の始まりで、その仕返しというべきか、140年前、官軍と称した薩摩・長州・土佐連合軍と奥羽越列藩同盟は覇権を賭けて戦った戊辰戦争、特に会津攻めは官軍総力を挙げて猛攻、白虎隊の最後に見られるような悲惨な野戦の末、会津鶴ヶ城に立て籠もり最後まで奮戦したが、遂に落城。
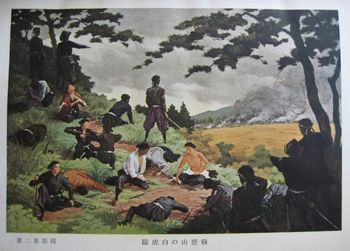
その結果、生き残った會津藩士とその家族約1万8千人は、會津の地を追われ、当時は全くの未開地であった北海道と青森・下北地方へと流刑同然に移住させられたのが斗南藩であったが、不毛の火山灰地、冷たいヤマセが吹き荒れ、作物は育たず、冬は季節風が吹き荒れ極寒、極貧の生活を強いれ、寒さと餓えに苦しみ、多くの会津の人々が西国人を呪いながら斃れていった。
更に廃藩置県によって青森県となってからは斗南藩としての碌もなくなり、辺境の棄民として過酷な運命にあった。
「白河以北一山百文」という言葉があるが、賊軍と罵られた東北地方は、薩長土を中心とした明治新政府からは徹底的に政治的・経済的全てにおいて無視、蔑視、差別されまさに「白河以北一山百文」の仕打ちを受けた。
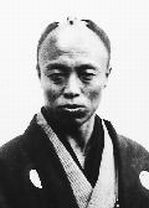 |
| (長岡藩 河合継之助) |
幕末の戊申戦争で長岡藩が薩長の猛攻を受け、勇者河合継之助が指揮する長岡藩は奮闘虚しく破れ、傷を負いながら会津藩を頼って魚沼より新潟県と福島県境界である秘境六十里越えをして只見村に至り、この時の詠んだのが「八十里 腰抜け武士の超す峠」(当時は八十里と称していた)。
会津藩より派遣されてきた藩医松本良庵が会津藩領内である只見村まで迎えにきており、そこで治療を受けたが、会津城下で本格的な治療を受けなければ危険な状態だ、との診断で急ぎ会津向け出発したが、途上会津塩沢村で絶命、破傷風だったらしい。
河合継之助が長岡藩の闘いに敗れ、落ち延びてきた足跡が、奥只見の山岳地帯で、周辺の山岳地帯からの豊富な水量が水力発電の宝庫として明治時代から着目されていた。

河合継之助は只見村で會津藩医松本良庵に付き添われ、担架に寝せられ會津を目指したが、會津塩沢村で落命、塩沢村の寺に仮埋葬された。JR只見線會津塩沢駅には案内の看板があった。
現在でも険しい山道が続き、JR只見線が開通したが、残念ながら水害で不通になったまま、再開の見込みはたっていない。そして現代、福島県双葉郡に原発が建設され、会津藩士が流刑された下北地方、その中心地である六カ所村に核処理関連諸施設が集中して建設されている。

親藩旧桑名藩も矢張り賊軍の汚名を着せられていたが、その飛び地領であった柏崎に原発が建設された。たまたま偶然なのだろうか。単なるこじつけだと否定されるだろうが、東京電力という他所様の危険施設を受け入れなければ活きていけないほど追い詰められていた過疎地、その遠因は「白河以北一山百文」にあるに違いない。
過酷な運命に翻弄された會津の人々が、會津人の誇り、會津藩魂を矜持、藩校日新館で学んだ教育の尊さを忘れず、如何なる苦難の中にあっても子弟の教育を最優先として熱心に取り組んだ。その結果は、各界で後世に名を遺すような数多くの逸材を輩出、逆賊の汚名を払拭し、「會津」の名を復活させ、名誉を恢復、會津魂を世に誇示した。
薩長明治新政府の政治的、経済的な差別政策に対し、ただひたすら恭順の意を表し、白河以北には政府のめぼしい投資はなし、反面、西南の役、佐賀の乱等の明治新政府に楯突く内乱も数多くあったが、白河以北での反攻は戊辰戦争最後の闘いとなった箱舘での闘い最後にしてその後は全くなく、ただひたすら明治新政府の意に従い、従順な僕として政府の意のままになった。
従って、東北地方では従順さこそが身の安全とする風潮が生まれ、不平不満は内に秘めることにしたのかもしれない。
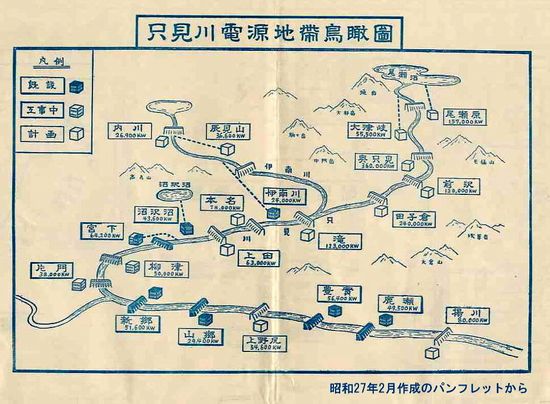 |
只見川開発の歴史
只見川において初めて水力発電事業が計画されたのは1910年(明治43年)のことで、岩代水力電気発起人として太田黒重五郎等が只見川と伊南川の各1カ所に壽水路式発電所を計画、河川管理者である宮田光男福島県知事(当時)が最初で、それ以降様々な電力会社が只見川、阿賀野川、沼沢湖等の発電用水利権取得申請がなされ、これらの申請は福島県、新潟県、群馬県の知事に提出されて水利権獲得競争は激化した。
また源流である尾瀬沼についても水利権申請が行われ、関東水電株式会社を設立尾瀬沼にダム式水力発電所を建設し、水は利根川に放流するという計画で、群馬県知事に水利権を申請し認可された。
この他にも数々の水力発電計画により水利権の申請が福島県、新潟県、群馬県の各知事にだされそれぞれ認可されたから、利権があるところ必ず政治家や資本家、地方の有力者が後に群がり、それぞれの思惑が衝突し合った。
また水力発電には最高の立地条件が揃っているが険しい山岳地帯、過酷な気象条件であるから投下資本も莫大なものになるため会社側でも1社では負担できず、吸収合併が繰り返された。
戦前、只見川の水力発電事業は長大なトンネルによる水路式発電所・野沢発電所が東北電力によって進められていたが、東北電力は尾瀬沼ダム建設を進めていた関東水電とともに信越電力株式会社に吸収合併された(昭和3年)。
この信越電力会社も合併後、東京発電株式会社に名称を改め、更に程なく東京電燈株式会社と合併するというめまぐるしい電力会社の変遷があった。
従って只見川、阿賀野川流域の水力発電所は東京電燈株式会社が一つ手に握ることになり、更に猪苗代湖や裏磐梯三湖の水力発電事業を行っていた猪苗代水力発電も吸収合併したから、福島県内の水力発電は全て東京電燈株式会社の支配下にあった。
ところが1929年(昭和4年)世界恐慌が起こり、日本経済は深刻な影響を受け、それに伴い電力の需要が急速に落ち、反面需要を見込んで電力増強に力を注いたが、それがかえって裏目に出にでてしまい、不況は更に深刻化してしまった。
その後は不況打開として「帝国の生命線は満蒙にあり」と陸軍が叫びだし、満州事変、シナ事変、ノモハン事件、太平洋戦争と15年戦争へ突入してしまい、わが国はどん底へと突き進んだ。
戦時体制を進める軍閥政府は電力の国家統制を決め、電力業界は暗雲が立ちこめてきた。
1938年(昭和13年)東条英機を中心とする陸軍統制派は第一次近衛内閣に猛烈な圧力をかけ、戦時体制を遂行するためには電力の国家管理もやむなし、としたために松永安左右衛門氏を筆頭とする電力業界挙げて猛反発したが、憲兵、特高による凄まじい弾圧があり、松永氏は生命の危険にさらされたため隠遁し、第73回帝国議会に「電力国家管理法案」を上程、1939年4月1日、国家総動員法とともに電力管理法・日本発送電株式会社法が成立。これに伴い特殊法人として発足した日本発送電株式会社は出力5000kw以上の水力発電所、出力1万kw以上の火力発電所をほぼ例外なく管理下に置き、日本全土の発電所を支配し、かつ同規模の新規電力開発を他の電力会社が実施することを禁止した。
只見川や日橋川、猪苗代湖等の水力発電所を保有若しくは計画していた東京電燈は既存の施設の大半を日本発送電に接収され、只見川で計画していた11発電所も施行実施継続は差し止められた。
一方、尾瀬原ダムの利根川への分水計画であるが、1944年9月16日、軍需省電気局長は日本発送電に対して「尾瀬沼から」利根川水系片品川への流域変更(分水)による発電計画を直ちに図ること」という指令を下し、石井英之助群馬県知事、石井政一福島県知事に対して水利権使用の許可を直ちに出すよう指示した。福島県は分流案には絶対反対の立場であったが、戦時下の軍閥政権に対して抗命することは不可能で、やむなく許可した。翌年終戦となり中止になると福島県は判断したが、軍需省廃止後の電力行政を継承した商工省は「国土復興のため」として分水工事を継続することを決め、尾瀬沼から三平峠をトンネルで越えて片品川への分水事業は1949年に完成し、福島県としては無念の結果となった。
戦後
1946年(昭和21年)日本発送電は只見川・阿賀野川の総合的な水力発電計画を企画、独自に調査を開始、南会津郡伊北村に調査事務所を設置して、只見川の流量や地形、気象、水文等の調査をした。
さらに、翌1947年には商工省が只見川・尾瀬原・利根川総合開発計画を策定し、只見川流域の調査を日本発送電に依頼し、この調査所も上流担当と下流担当に二分・強化拡大して調査を継続した。
1948年(昭和23年)10月に「東北地方電力復興計画案」を纏め、北上川、十和田湖、田沢湖、猪苗代湖と共に只見川が最重要地点として挙げられ、特に只見川は復興計画にある水力発電計画の87%に及ぶ約247万kwを只見川流域だけで新規開発出来ると報告された。
これを受けて1947年「只見川筋水力開発計画概要」が発表された。
この計画概要によれば只見川と阿賀野川に連続して15カ所野ダム式発電所を建設設、既設5発電所の出力を増強させることで
235万kwに及び、年間増加発電量は55億kw時にも上がるとして開発は有用性を主張した。
この中での根幹事業として只見川最上流部に4ヵ所、伊南川の1ヵ所の巨大ダムを建設し大容量の貯水池を建設することとし、ここに初めて奥只見ダム、田子倉ダムの二大ダム計画が登場した。これに伴い尾瀬原ダムはこの計画で揚水発電から一般水力発電に修正され、縮小された。その結果、利根川への分水も無くなり、ダムの規模も縮小した.この案は後に「只見川本流案」となる。
「本流案」は只見川・尾瀬原・利根川総合開発計画案を審議する「只見川・尾瀬原・利根川総合開発審議会」に1948年に提出され審議開始となった。
ところが同時期新潟県側から只見川の豊富な水量を信濃川水系に導水して灌漑を行い、水田耕作を一挙に拡大しようとする「只見川分水案」が提出された。
また「尾瀬分水案」に関する群馬県の主張があり、福島県、新潟県、群馬県の三つ巴の争いの火種があり、長期の抗争があった。
ところがこれらの水力発電総合開発計画を策定した日本発送電は1948年GHQよりより戦時体制に協力した独占資本である、と断定され過度経済集中排除法の指定を受け解散を命じられた。
只見川特定地域総合開発計画
1950年(昭和25年)に施行された国土総合開発法に基づき日本政府が定めた地域開発計画の一つとして施行された。
福島県と新潟県にまたがって流れる阿賀野川水系最大の支流である只見川を中心として阿賀野川下流域に至まで大小様々なダムを建設して水力発電所を造ろうという壮大な計画であった。
只見川の水源は群馬県、福島県、新潟県の三県にまたがる尾瀬国立公園の一つである尾瀬沼がその水源で、湿地の水を集めながら三条の滝を経て深い谷を刻んで南会津郡只見町を流れ、ここで伊南川と合流する。険しい山岳地帯である蒲生岳を過ぎると次第に北東に向きを換え大沼郡金山町で野尻川と合流、大沼郡三島町、柳津町、会津坂下町を過ぎて会津盆地を流れ、喜多方市高郷町付近で阿賀野川に合流する。流路延長146km、流域面積2,800k㎡水量は豊かで、年間降雨量は2,500~3,000mmに達する多雨地帯であり、冬季は豪雪地帯でも知れており春期の融雪、更には源流から阿賀野川合流点までの落差が1500mもあり、急流・豊富な水量・高落差という水力発電に必要な三点の好条件が揃っていたにあった。
従って只見川は水力発電には日本で最も有望な開発地域だと古くは明治時代から電力会社としては注目していた。しかし、文字と通りの「宝の山」も、険しい山岳地帯と厳しい気象条件がそれを阻んでおり、資本と技術力で二の足を踏んでいた。この只見川流域はまさに秘境ともいえる険しい山岳地帯で、黒部峡谷にも匹敵するもので、勿論国道252号線のような道路は当時なかった。あるのは新潟から会津盆地に抜ける山道があるだけだった。
計画案の変遷
只見特定地域総合開発計画では複数の事業者・自治体、地権者によって様々な計画案が提示された。
只見川本流案:福島県と東北電力が推した計画、本案の骨子は只見川源流である尾瀬から最下流の阿賀野川まで一貫して水力発電所を建設するものであって、只見川、阿賀野川、支流の伊南川に階段式にダムを21ヶ所にダム式水力発電所を建設し可能な限り水力を利用する総合開発案である。只見川上流には尾瀬ヶ原、奥只見、前沢、田子倉の四つのダム、伊南川には内川ダムという有効貯水量が1億?を超えるダムと大容量貯水池を建設して大規模発電を行い、下流域には新たに滝、本名、上田、柳津、片門、上野尻のダム式発電所と沼沢沼揚水発電所を建設する等の計画で、既にある水力発電所を総合的に活用する。
只見川分流案(流域変更案)
新潟県が発表した計画案で、最大の特徴は只見川の水を、越後駒ヶ岳を隔てた信濃川水系に分流させ、水力発電を行うと同時に有数の穀倉地帯である越後平野の田畑に灌漑用水として活用する多目的河川総合開発計画案であった。
当時は食糧難で特に米穀不足は深刻で、従ってこの案は非常に説得のある案とされた。この計画案では、奥只見、田子倉ダムを計画の中心に据えているが、本流案(福島県案)との違いは奥只見・田子倉ダムから放流の後、トンネルを通じて信濃川の支流・魚野川に導水することで、その間で水力発電所を建設する計画であったが、その後の調査で商工省や開発調査審議会から水田や油田(当時新潟県内では少量であるが原油が生産された)があり、再開発は困難と評価され、そこで新潟県川は計画を修正し、遠大な計画案は導水に必要な総延長40kmにも及ぶトンネルを建設し、水力発電と灌漑用水に利用することを目的とするが、40kmものトンネルは青函トンネルにも匹敵するもので、当時は未だ青函トンネルの計画案もない時代だから、理想としては良いかも知れないが、現実的には無理な計画であった。

尾瀬分水案(利根川分流案)
この案は日本発送電の頃に計画されていたもので、日本発送電の関東地盤を受け継いだ東京電力と群馬県の連合が提起した計画案で、最大の特徴は尾瀬原ダムの水を利根川水系に分水し、85mの落差を利用して大規模な発電を行い、更に利根川上流に三つのダムを建設、京浜工業地帯に送電すると共に流水は水道水として活用する案である。
野口研究所案
野口研究所とは、日窒コンツェルン創業者・野口遵氏が私財を投じて設立した、財団法人野口研究所で内容はコンサルタンで、この研究所が作成した案は、只見川総合開発に関する私案として提出された。
内容は電力開発であるが、同時にその水量を利用して、日本海と太平洋を結ぶ運河を、河川を利用してパナマ運河のようなドック式で繋ぐという遠大な計画で、水力発電しても最大出力327万7000kWと計算しており、この出力は本流案の約10倍になる。
最終決定は政府にあり、陳情合戦、本流案を主張する福島県、東北電力連合は大竹作摩知事、福島県選出国会議員で吉田内閣の懐刀といわれていた農林大臣廣川弘禅代議士、(会津選出の伊東正義・新潟の田中角栄氏の実力者はまだ代議士には選出されていなかった)
福島県の東北電力会長白州次郎氏の政治力で推したが決着が付かず、暗闘が続いた。
各案が出そろったところで、電気事業再編成令と同時に施行された公益事業令に基づき組織された公益事業委員会は1951年(昭和26年)、アメリカ海外技術調査団(Oversea Consultants Ink)、即ち‘OCI’に只見川特定地域総合開発計画案の策定を依頼。依頼を受けたOCIは来日し、各計画案を比較検討し、野口案は余りにも壮大すぎて実用的ではないと却下し、三案の比較検討をしたうえで、現地での実地調査に赴き、新潟案は地質調査やトンネルの技術的な調査や膨大な費用を捻出する根拠を無視した。
基礎的データの不足が指摘され、希望的な観測が多すぎるとされた。
利根川分流案も同じように計画として最良であるが、建設費用の投資と経済効果の点について若干疑問があるとした。
福島県・東北電力の本流案も完全ではないが、他の案よりは経済効果が期待できる、と評価され、さらにOCI案を付帯して、本流案が推奨された。
この答申に対して新潟県側は猛反発し、自らの分流案に固執してOCIの結論は電源開発だけを目的としたもので、総合開発という本来の目的にはそぐわないものだとし、水力発電と食糧増産の灌漑用水との二輪とする新潟分水案こそが最良なものであると、新潟県知事を中心とする陳情団が中央政界に働きかけた。当時の与党である自由党内部では吉田派と鳩山派が熾烈な抗争をしていたが、新潟県選出の自由党議員は吉田総理に対し「分流案」を呑めと迫り、もし呑まなければ全員脱党するとした。これは、吉田首相は「本流案」支持であったためで、これにより一方の雄であった同じ自由党の鳩山一郎氏に陳情、鳩山派へ鞍替えすることも検討された。
一方、福島県側は大竹作摩知事・福島県選出の代議士、県会議員、地方自治体の大陳情団が上京、これを側面から応援したのが吉田総理の懐刀・元農林大臣廣川弘禅代議士(福島県選出、福島県石川郡玉川村出身(1902年生))、東京交通労組を母体として東京市議、府議を経て1940年衆議院議員に選出され、戦後は吉田首相の側近になり農林大臣に登用されたが、やがて吉田派を離れ、新しく台頭してきた官僚出の勢力に押され力を失っていった。
この2県の対立は後に水利権問題、保障問題でしこりを残すことになった。
政府は妥協点を探るため度々電源開発調整審議会を開催、電源開発により奥只見・田子倉などの奥只見川上流開発を行う方針を固めて地域紛争を排除し、かつ新潟県が納得する妥協点を探った。こうした度重なる協議の末、佐梨川への導水を廃止する代わりに奥只見ダムから信濃川水系の黒又川に只見川の水を分水し、黒又川に黒又川第一ダム、黒又川第二ダムを始め合計4個所の水力発電所を建設、ダムに貯水した水で越後平野の灌漑を行うという「黒又川分水案」を提示し、1953年(昭和28年)7月28日、吉田首相は首相官邸に大竹福島県知事、岡田新潟県知事を招いて、「黒又川分水案」による妥協案に同意するよう求めた。
これに対して大竹知事は県幹部、県議団と協議の末、緒方竹虎副総理の了解の旨を伝え、新潟県側もこれ以上紛糾すればかえって分流案が不利になるとの判断から同意を表明し、長かった抗争は終了した。
8月5日「黒又川分水」を含めた奥只見・田子倉発電所の着工が決定した。
かくして、福島県・東北電力による本流案に付随した黒又川分流、その他の分流案を包括した案が採決された。しかしそれで全てが収まったわけではない。
水利権問題・補償問題
福島県と新潟県の対立、東京電力と東北電力の対立、これは水利権の複雑さにあり、そもそも日本発送電が所有していた水利権、複雑に分割され、河川行政を司る野田卯一建設大臣、池田勇人通産大臣の中央政界と県、電力会社、地方自治体の対立となって、訴訟合戦、新潟県選出の自由党塚田十一郎代議士の国会での追求、改進党栗田英男代議士の反吉田演説等、国会は大荒れ、参考人招致で大竹知事、東京電力、東北電力社長が呼び出され、白州次郎氏が参考人として呼び出されるなど只見特定地域総合開発計画は「只見川本流案」をベースとして計画が着手されることになっていたが、しかし様々な利害関係が輻輳しており、多くの対立を生んだ。特に政治的な対立反体制運動など複雑怪奇な諸問題が絡み合った。
ここで中心的な働きをしたのが大竹作摩福島県知事であった。
「只見川分流案」を推していた新潟県は「只見川本流案」の採用後も頑強に自らの計画案を推し、政府や福島県に猛反発をした。
新潟県はOCIの結論に対し「本流案を最も有利であると前提した上で比較検討している」として公平性に欠ける暴挙だと批判。また本流案は電源開発のみを中心としており、河川総合開発事業の見地に立っていない。新潟県が主張する分流案は水力発電とともに農地開発、特に水田開発に力を注ぎ、米の増産を図る。更に只見川・阿賀野川の治水においても有利であり、緊急の課題である食糧増産と水力発電が同時に遂行できる極めて有効な案である、と従来の主張を繰り返し述べ、更に技術面、水没地補償の面でも本流案に比べ負担が少ない利点がある、とした。
この新潟県の反発は中央政界にも波及し、当時与党であった自由党内部で首相である吉田派と政敵であった鳩山派の対立、吉田首相の懐刀、廣川弘禅農林大臣が福島県選出であり、鳩山派との熾烈な闘いがあった。
新潟県選出の与党議員団は分流案を採用しなければ与党を集団脱党すると脅しをかけ、一方、福島県側は県議50名が上京し陳情を繰り返した。
この両県の対立の原因は水利権に関する根強い対立に原点があった。
水利権の対立
OCIの勧告で「只見川本流案」による開発が決定した後、東京電力の前身である東京電燈が保有していた只見川の水利権を行使すべく、1952年本名発電所と上田発電所の水利権使用許可を大竹知事に申請したところ、「両発電所の水利権は東北電力に認める」として東京電力の申請を却下した。
河川行政を司る野田卯一建設大臣と電力行政を司る池田勇人通産大臣に閣議で東北電力への水利権使用許可を認めるよう働きかけ、8月には閣議でこれを承認し、東京電力に対して水利権の失効を通達した。
大竹知事はこれを受けて東北電力に両発電所の水利権使用を許可した。
背景には「本流案」決定後も「分流案」の優位性を訴える続ける新潟側に対して「本流案」に基づいて開発を進め既成事実を構築してしまいたい福島県側の思惑もあった。
これに納得のいかない東京電力は福島地裁に「水利権使用許可取消処分の取り消し」と「東北電力への水利権使用許可の執行停止」を求めて行政訴訟を起こした。
吉田首相は「執行停止されれば只見川の電源開発に重大な支障を及ぼす」として行政事件特例法を行使して「異議申し立て」を福島地裁に申し立てた。これが認められ東京電力の「執行停止」は却下された。
この一連の動きに新潟県選出の議員が激怒し、特別国会衆議院予算委員会で水利権問題が議論され、東京電力から東北電力へ水利権が変更された一連の行為は不明朗で、背後には吉田首相の側近であり、東北電力の会長でもある白州次郎氏の策謀があるのではないかという疑問が呈され、福島県に圧力をかけ、かつ吉田首相をはじめとする閣僚をも動かしたのではないかとの疑惑である。
特に追求が厳しかったのは改進党栗田英男議員、新潟県選出、自由党塚田十一郎議員で、国会内でビラまで撒かれている。
その後参考人招致で、大竹福島県知事、東北・東京の両電力社長、白州次郎氏も招致された。
その後も争いは続き、通産省主催で仙台市において関係する当事者・利害関係者を集めて聴聞会を開催、両発電所の所属について聴聞を行った。
この中には東北六県の知事・県議会・商工会議所・仙台市長・市議会、東北地方の工場を有する企業、そして只見川流域住民は東北電力を支持し、京浜工業地帯に工場を持つ企業204社、神奈川県、群馬県、新潟県は東京電力支持。膨大な只見川の電力を巡るこの問題は更に東北地方と関東地方の対立を生み、行政訴訟合戦が」2カ年も続き「水利権問題」は泥沼化した。
この問題の根底にあるものは日本発送電分割後の水利権所属が複雑であり、戦前より只見川開発していた東京電燈の流れをくむ東京電力と地元の河川開発を開発し、地元に電力を供給してきた東北電力か、これに利害関係者の思惑が錯綜して複雑な事態になってしまった。
これ以上の紛糾は肝心の電源開発事業の停滞を招くことになり政府が強力に調停を行い、最終的には東京電力が東北電力の水利権を認め、その代わり東北電力は東京電力に相応の電力を供給することで両社は妥協、1954年(昭和29年)1月22日、東京電力が福島地裁に行政訴訟を取り下げることで解決した。
しかしその後は、補償問題で地元が紛糾し、大竹知事と地元住人と平行線を辿る話し合い補償額を上げれば建設省・通産省が圧力をかける、県議会は分裂、電源開発公社総裁と県幹部との衝突、膨大な資料があるが本論では関係ないのでこれ位にしておきます。
只見特定地域総合開発計画では多数のダムが建設されたが、それに伴い住民が永久に土地を失う犠牲があったが、1952年東北電力調べでは只見川筋水没対象戸数679戸、従って補償問題が浮上する。しかし戦後間もないこの頃は土地収容法も補償に関する関連法も未整備であったため最大の紛糾が起きてしまった。
特に田子倉ダムの場合、ダム建設には田子倉集落50戸が水没することになり、住民の猛反発あり反対運動が激化した。更に当時レッド・バージ(GHQ指令)によって非合法化された日本共産党がこの部落に潜り込み思想的扇動工作を行い、住民との共闘態勢を造った。
田子倉ダム幅462m 高さ145m総出力39万kw
水力発電所としては国内第2位の規模を誇る。1959年に運転開始。福島第一原発より12年早い開始、豪雪地帯を流れる只見川の水量は豊かで山間なので傾斜も急なので水力発電には適していた。
敗戦直後は9,000人だった只見町の人口は、建設が始まると急速に人口が増え13,000人になった。
 |
| (奥只見開発阻止、住民の抵抗) |
しかし補償交渉は難航を極めた。
この補償交渉の前面に立ち、対峙したのが大竹知事と電源開発田子倉建設所長の北松友義氏であった。
大竹知事は地元に入って住民の説得に当たり、土地収用法による強制収容勧告には福島県議会は消極的だった。
大竹知事の努力に依って50戸中45戸までが電源開発側が提示した補償基準額で妥協した。残り5戸は共産党の支援を受けており、しかも非合法化されている共産党が存在価値を示す絶好の機会と捉えており、ここで負けるわけには行かない事情があった。
更に紛糾したのは大竹知事が直接住民と対話し、電源開発が提示した補償基準での妥協であったが、この補償額が当時のダム補償額が他のダム建設による補償額相場よりも大幅に高額であったため、他のダム建設に波及することを怖れた建設省と通産省が猛反発し、結局相場通りの補償額に落とさざるを得なかった。
このため住民は再び硬化し、さらに全国ダム建設予定地で補償金額の増額を求める事態が発生、各地で紛糾が相次いだ。これが「田子倉ダム補償事件」として名高い。
しかし、長引く闘争に疲弊しきった住民は共産党指導に引きずられていることに疑問を感じ、日本農民組合・日本社会党福島県連と裏で接触を試み、共産党に発覚しないよう極秘裏に藤井電源開発総裁、大竹知事、県幹部と接触・交渉を行い、1956年(昭和31年)7月25日、大竹知事との東京最終交渉により最後まで残った5戸を含む50戸が全戸妥協した。
共産党の活動は、結局は混乱に拍車をかけるだけに終わった。交渉の矢面に立たされ通しだった北松建設所長は過労と心労が重なり、体調を崩し職半ばで退職してしまった。
しかし、これで収まったわけではない。滝ダム建設では再び補償交渉が難航した。ダム建設によって水没する住民は177戸あり、田子倉ダムの前例もあり慎重に補償交渉を進めてきたが、ここに予想外の事態が進展した。それは「新戸」問題で、地元とは縁もゆかりもない外来者がダム建設予定地に入り込んで、バラック小屋を建て転入届けをだした。その数は65戸・84棟に及び新住民となり、これを「新戸」と呼んだ。
この新住民の多くは補償金目当ての暴力団員や韓国人その他のアウトローが多かった。
補償交渉は最終的には大竹知事及び福島県に一任され、大半は解決したが、新戸は補償金の吊り上げを狙って頑強に抵抗したが、最終的には2戸だけ抵抗を続けたが、最後は土地収用法による強制収容を受け解決した。
この新戸問題は北山ダム、小森ダム(和歌山県)でも発生し、土地収用法の不備を突かれたもので、その後土地収容法の規制強化が図られ現在ではそのような事態はおきない。
「真の文明は山を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし」鉱毒問題と闘った田中正造が言った。

◎大竹作摩福島県知事(1895年~1976年)
福島県麻耶郡北塩原村で中農の長男として生まれ、地元の高等小学校を卒業後は農業に従事、1927年、北塩原村村議に当選後、1931年から4期県会議員を務めた、が政党解散(大政翼賛会に統一)に反対して憲兵隊に拘束された。
1950年(昭和25年)自由党から福島県知事選に出馬し、当選、2期7年努めた。知事になって直ぐに只見川特定地域総合開発計画に基づく只見川開発に尽力、只見川の水を分水しようとする新潟県岡田正平知事と対立、政界を巻き込んだ大紛争に福島県の先頭に立って本流案を強硬に主張、ついには本流案を採決させた。
本流案決定後は、水利権問題、補償問題が続出し、訴訟が続いた。
特に紛争があったのは田子倉ダム建設の際の農家への補償金問題(田子倉ダム補償事件)では国と電源開発公社と鋭く対立、土地収用法を適用して強気の姿勢で臨み、住民側には低姿勢で交渉、補償問題解決に尽力した。2期で知事退任後は衆議院議員(1960~1963年)を1期努め、1976年7月16日 脳卒中と肺炎を併発して81歳で逝去。
◎初代福島県知事石原幹一郎(知事の期間1947~1949)
岡山県出身、東大法卒後、1926年 内務省入省、当時行政の中心は内務省に集中、公務員としての始まりは北海道警視(警察行政は内務省所属)、その後も都道府県の役職を歴任、1946年、官選知事として福島県知事に就任(当時は内務省より派遣)
1947年公職選挙法が施行され、官選知事から民選の初代知事に横滑りで当選した。その後は参議院議員選に民主自由党公認で出馬、国会議員となった。
従って、純粋の民選知事は大竹作摩氏が初代となる。
◎白州次郎(1902年2月17日~1985年11月28日)
兵庫県武庫郡精道村(現芦屋市)生まれ、神戸一中からケンブリッジ大学クレア・カレッジに留学。1925年、ケンブリッジ大学卒業後帰国。
駐イギリス大使であった吉田茂との交流があり、これが戦後東久邇宮内閣の外務大臣に就任した吉田氏に懇請され終戦連絡中央事務局の参与に就任、得意のキングズイングリィシュでGHQとの交渉に渡り合い、主張すべきことははっきりとものを言い、GHQ高官から「従順ならざる唯一の日本人」や「マッカーサーを怒鳴りつけた唯一の日本人」などと言われている。
GHQとの連絡交渉がスムースにいったのはこの人の活躍に負うことが多い。1948年12月1日、初代貿易庁長官に就任、1950年渡米しアメリカ側代表ジョン・フォスター・ダレスと会談し平和条約の原案を作成、翌年の1951年、サンフランシスコ講和会議にも全権団顧問として活躍した。この時吉田首相が英語で演説しようとしたが、日本のディグニティ(尊厳)の為にも日本語で演説すべきだと主張、このため日本語の文章を毛筆で書き巻紙がないので用紙を繋ぎ合わせ、その長さ30mにもなった。
これがトイレットペーパースピーチとして有名になった。
その後も活躍は続き、公社の民営化推進に尽力し、日本専売公社が発足している。
特筆すべきは、福島県に対し最大の功労は、日本発送電の9分割によって誕生した9つの電力会社のうちの東北電力会長に就任、福島県が主張する本流案を強力にバックアップし、電力の鬼松永安左右衛門氏と対立したが、本流案を勝ち取り、只見川流域の電源開発事業に精力的に取り組んだ。
1959年、東北電力会長を退任してからは、数々の事業に携わり、83歳で病没した。
ドラマ NHKドラマスペシャル2009年(平成21年)2月28日放送
白州次郎(伊勢谷友介)、妻正子(中谷美紀)、近衛文麿(岸部一徳)、吉田茂(原田芳雄)その他豪華キャストで見応えがあった。他局でも数多くの伝記のドラマが制作された。
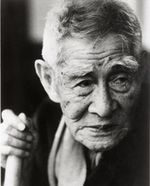
◎松永安左右衛門(1875年(明治8年)12月1日生~1971年(昭和46年)6月16日没)
長崎県壱岐で生まれ、1893年慶応義塾入学、在学中福沢桃介と知り合う、しかし中退し、福沢桃介と共同で石炭や材木商等様々な仕事に手を出し、やがて電力の有望性に眼を付け、東邦電力の副社長に就任、後社長になる。
東邦電力は九州、近畿、中部に及ぶ勢力を持っていた。更に東京進出を図り、東京電力を設立した。当時東京を支配していたのは東京電燈であったが、これと激しく覇権争いをしていたが、株を買い占め、東京電燈を吸収合併する形で新たな東京電力を設立、その取締役になった。
松永氏は徹底した官僚、軍人嫌いで、電力は民間主導の電力再編を主張して、「電力王」「電力の鬼」と呼ばれるようになった。
軍閥政治、特高、治安維持法により何時逮捕されてもおかしくない状況になり、時の企画院総裁であった鈴木禎一氏の計らいで、身を隠し長らく茶道三昧の生活をしていたらしい。
東条内閣は国家総動員法に合わせて電気事業を国家管理下に置くことになり、特殊法人日本発送電会社が設立され、9の会社が配電事業行うことになった(1発電9配電体制)
戦後、GHQの政策として、日本発送電会社の民営化が課題になると、電気事業再編成審議会会長に選ばれ、日本発送電側は独占体制を維持しようとしたが、反対の勢力が強く、9電力体制を実現した。さらに電力事業の発展を見込み強引に電気代値上げを強行し、電力業界を牽引したため「電力の鬼」と呼ばれ続けた。

◎廣川弘禅(1902年(明治35年)3月31日生~1967年1月7日没)
石川郡玉川村曹洞宗の寺に生まれる。曹洞宗大学中退(現駒澤大学)道路人夫、郵便配達、東京市電に入り東京労働組合を結成して労働争議を指導、労組執行委員から東京市議に当選、東議会議員を経て、1940年衆議院議員補欠選挙で初当選、通算当選6回。戦前は鳩山派、戦後は鳩山一郎氏が公職追放になったため、吉田茂氏に接近、第三次吉田内閣の農林大臣に就任した(1951年)。この頃、奥只見電源開発が始まり故郷福島のために奔走した。
政治的にも吉田首相に重宝され約30名余を率いる廣川派を結成し、大物議員になったが、党内に敵が多く、政治基盤を脅かされていた。最終的には吉田首相の激怒を買い、鳩山派に接近したが、総選挙で落選、次の総選挙で日本民主党から出馬し当選、1967年の総選挙に出馬予定でいたが選挙直前の1967年1月7日急死、享年64歳。
 |
 |
| (多くの集落が湖底に沈んだ) |
インフラ整備
只見特定地域総合開発において巨大なダム、水力発電所建設計画であるから、資材の運搬が最大の問題になる。当時は鉄道による運送が主流であった。鉄道が敷設されていたのが上越線小出駅から県境の大白川駅までの僅か7駅区間だけ。福島県側は会津若松駅から会津宮下駅までが開通していたが、肝心のダム建設地点は鉄道路線は無く、道路も劣悪な条件下にあり、豪雪地帯なるが故に冬季は只見町を中心として完全に交通が遮断され孤立するのが通例であった。
そこで交通路・運搬路の整備が重視され、最初は建設資材輸送ルートとして只見川下流よりのルート、会津鉄道の会津田島駅から駒止峠を越えて田子倉へ向かうルートの建設が検討されたが、工事が長期間を要し、かつ膨大な建設費用を要することで見送られ、そこで国鉄に依頼し会津宮下駅から会津川口駅まで開通させ、更にここを起点として只見町のダム建設現場までの32kmに資材運搬専用の田子倉専用鉄道の施設を建設することを運輸省に申請した。運輸省は「電源開発に使用した後は撤去せずに国鉄に譲渡して営業路線とする」ということで鉄道敷設の許可を下した。
敷設の費用は電源開発側が負担し、計画・工事は国鉄が直接行い、総工費29億円、1957年8月に完成した。
この開通によって1編成貨物列車で1200屯の資材が運搬され、1日4往復のピストン輸送を行い、工事の進捗に貢献した。
1959年 田子倉ダム完成。1960年 奥只見ダム完成。その後続々とダム・水力発電所完成、総合開発の夢はかなった。
その後は運輸省の承認条件通り国鉄に譲渡され、1963年(昭和38年)8月、会津若松駅から只見駅まで営業路線として開通した。
1971年 田子倉トンネル・六十里越トンネルが完成し、只見駅と大白川駅が繋がったため、会津若松駅と上越線小出駅との間の只見線が開通した。
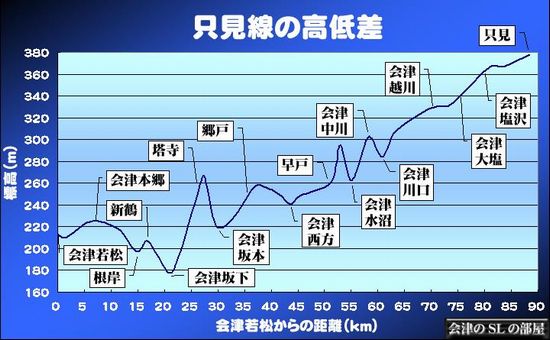 |
 |
JR只見線 (会津若松駅から新潟県小出駅135.2km 駅数38駅)
会津若松駅を出ると会津坂下駅までは会津盆地の南方をU字型に大迂回し、その先、塔寺駅付近からは山間部に入り屈曲しながら小ダムの多い只見川沿いの上流へと谷間を縫うように遡り田子倉湖付近から長大な六十里越えトンネルを出ると新潟県大白川駅でこの付近から谷を下り銘柄米の魚沼コシヒカリ産地魚沼平野に入り破間川が魚野川に合流する上越線小出駅に至。
途中の駅は大半が只見川沿いにある山村の無人駅でロ-カル色の濃い渓谷美溢れる絶景の秘境を旅する歓びを感じる。
但し会津若松~小出間は全線単線、非電化、急行なし、各駅停車のみ、しかも全線を走るのは1日上下各2本だけ、後は会津若松近郊、小出近郊に限られ乗車するときは時刻表を確認する必要がある。
全通所要時間3時間10分
使用車両はキハ58系 気動車
全通開業は1971年(昭和46年)8月29日、赤字路線なので廃止を検討したが、並行する国道252号線が県境である六十里越え付近が豪雪のため通行止めになることが多く、只見線はトンネルで繋がっており只見地区と新潟県魚沼地区を結ぶ唯一交通手段となるため、国鉄再建法による赤字ロ-カル路線廃止対象外になり、現在に至るまで廃止を免れてきた。それでも豪雪、豪雨、上越地震等で長期不通にしばしばなっている。
現在も2011年7月の豪雨で会津坂下駅と小出駅が不通になったが、2012年4月現在で会津川口駅と大白川駅は不通のまま。
道路事情と鉄道
一方、道路に関しては、只見町までは田子倉専用鉄道が敷設されたが、奥只見ダムはさらに奥地で険阻な山岳地帯、銀山平に建設予定であったが、当時の銀山平は小出町から片道3日もかかる峻険な山道を歩かなければならない僻地にあり、途中には枝折峠という難所があり、冬季間は如何なる交通手段もないほどの豪雪地帯で、資材運送は不可能であった。そこでダム建設に先立ち、湯之谷温泉付近から全長22kmに及ぶ工事専用道路建設を1954年12月に着工、雪崩や事故で54人の犠牲者を出す難工事であったが、3年の歳月をかけて1957年11月に完成した。
全長22kmのうち18kmがトンネルで占められ、雪の影響を受けないように工夫されていた。
ダム完成後はしばらく管理用道路として使用されていたが、1969年に新潟県に譲渡され有料道路として供用、1977年からは無料となって、奥只見観光道路(シルバーライン)として活用されることになった。
奥只見ダム・田子倉ダムを含むこの地域一帯が「越後三山只見国定公園」に指定された。「シルバーライン」の名称は銀山平で江戸時代銀がこの地で産出され事に由来し、銀山平の名称も銀の産出に由来するものである。
また、国道252号線、通称「六十里越」が1973年に六十里越トンネルが完成して、魚沼と只見が結ばれ、六十里越、シルバーライン共に冬期間は豪雪のため完全通行止(11月下旬から翌年5月中旬迄の約半年間)になるため、唯一の交通機関はJR只見線のみとなってしまう。このため完全な赤字路線でも廃止の対象にならなかったが、豪雨の被害で路線が寸断され、只見線は部分運休し折り返し運転となっている。
 |
 |
2011年7月、新潟・福島豪雨により只見線は甚大なる被害を受け、鉄道橋梁の大半を流出し、一時小出~会津川口間113.6kmが不通となり、徐々に復旧したが、会津川口駅~只見駅は(現在2015年4月)不通のまま、復旧工事は未着工。
不通区間はバスを運行1日7往復しているが利用客は少ない。当該地域ではこのまま廃線になってしまうのか、との危機感が強い。
2013年、福島県知事及び周辺自治体首長が、JR東日本に対し只見線の復旧・存続を要請した。また福島県は国に対して、JR東日本への財政援助が出来ないかと打診した。ところがJR東日本は東日本大震災で管内路線に大きな被害があり、大きな財政負担があったが、2013年、JR東日本が黒字経営であり、黒字経営の会社には鉄道軌道整備法の災害復旧援助法が適用されないことになり、援助は無理と判断され、そこで福島県は独自に復旧費用の援助ができないか検討している。
但し、JR東日本社側の調査では復旧費用85億円との試算が出ている。
さらに着工から復旧までは約4年を要するとされ、JR単独での復旧は無理との結論が出された。

今回の只見線橋梁流失の原因となった大洪水被害として、只見線と只見川は平行しており、その只見川には10カ所のダムがあり、そのうちの一つ滝ダムは堆積する土砂が貯水量の38%に達しており、本名ダム19%、その他のダムも土砂が堆積しており貯水容量が低下している分が洪水となって溢れ出て被害を拡大してしまった。
この点に関しては管理責任のある電源開発側も認めていることであって、堆積した土砂はこれからも増え続けるものであり、もしこのままにしてJR只見線だけを復旧しても再び洪水に襲われ、崩壊してしまう怖れが大である状況下では復旧に二の足を踏むことになる。
この洪水被害は只見線ばかりではなく、金山町では約150軒の全・半壊するなどの被害があり、その他の集落でも被害があり、山間の狭い耕地は流されてしまった。
このため地元金山町役場は被害状況の調査を専門家(芝浦工大・守田教授・都市工学)に依頼していたが、'14年3月、町として纏め「金山町調査報告書」を公表した。
それによると只見川にあるJパワー(電源開発)と東北電力が所有するダムで堆砂が進んでおり、それが洪水の一因になった可能性があると結論付けた。
ダムは上流から流れてくる水を堰き止めるが同時に土砂も堰き止めてしまう。その土砂が溜まる「堆砂」が進むと、ダムの上流域の川床に土砂が堆積し、川の水位が上昇し、豪雨があると氾濫してしまい付近一帯が洪水の被害を受けることになる。
従って電力会社は定期的に堆砂の除去をする義務があるが、どうも怠っていたらしい。また治山治水は国の責任であるがこれも怠っていたらしい。
このためJパワーは、金山町と隣接する只見町の一部地区の住民には豪雨被害の補償金を支払った。
同社のシミュレーションで、この地区に限ってはダムの堆砂が原因であることが明らかになったからだとしている。
ダムの堆砂を巡っての補償は過去に例がないと担当者は言う。
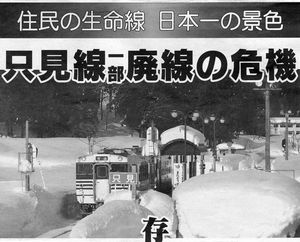
被害を受けた金山町の住民約40人は、'14年7月18日、Jパワーと東北電力を相手取り約3億円の損害賠償請求訴訟を福島地裁会津若松支部に起こした。
堆砂を除去しなければ再び洪水が起こる可能性大であり、「将来の安全のためにも、電力会社はきちんと堆砂を取り除いてほしい」と訴えた。
Jパワー側は「対策に乗り出す矢先だった。今回の災害は基本的には自然災害だ」東北電力は「ダム管理は適切にやってきた」とコメントした。
ところが発電用ダムは堆砂があっても発電能力が落ちるわけではない。このことが堆砂の除去には消極的にしてしまい、全国的に発電用ダムの堆砂が放置されたままだ。
戦後、電力供給を最優先事業として、水主火従の時代であったから水力発電ダムが各地に建設され、大半が40年を経過している。
全国発電ダムの堆砂の調査では05年全体で平均8%であったが、10年度では13%に上昇、更に今年度では平均28%に上昇している。
だが山間部にあるダムからの土砂運搬は困難で、莫大に費用がかかる。電力会社から言わせれば土砂が川に流れ込むのは「自治体の治山に問題があり、単純に電力会社の責任だとされても困る」としている。

こうなると責任の擦りあいとなり、問題解決を長引かせるばかりであり、地域住民の不安は増すばかりとなり、根本的解決がなければJR只見線の復旧にも着工できないことになる。
被災者の会は只見川流域の安全対策を怠ったダム災害だと訴え、堆砂の除去を訴え、また一方で堆積した土砂除去のために、かつて資材運搬用に敷設した只見線を堆積土砂除去の運搬に鉄路を復活させてはどうかとの意見がある。
これは全国にあるダムは山間僻地にあるが、只見川と並行して建設された只見線であるから土砂運搬手段として有効な活用となる。
この土砂の捨て場として、後で詳細を述べるが、大熊・双葉両町に建設予定の中間貯蔵施設の建設工事で排出する土砂4,000万噸を双葉沖合い防波堤兼アイランド建設のために埋め立てと山砂活用を提案したが、只見川の土砂も貨物列車運送でこの地に埋め立てることができるのではないか。同じく中央リニア新幹線工事で排出する土砂約5000万噸も埋め立てに使用することを提案した。
洪水の原因となる根本的な対処がなければ再び洪水が繰り返すことになるばかりだ。
人跡未踏のような峻険な山岳地帯を克服して電源開発を成功させたのだから、その力を持ってすれば後始末をどうするかくらいは楽にできるものと思われるが、着工できないでいるのは何故なのだ。黒部ダムのように現役発電施設、観光資源として健在だ。ならば只見川発電所ラインと観光資源開発も充分開発資源として健在のはず、あとはどう開発するか、どう活用するか、どう知恵を絞り出すかにかかっている。
一方、道路に関しては、只見町までは田子倉専用鉄道が敷設されたが、奥只見ダムはさらに奥地で険阻な山岳地帯、銀山平に建設予定であったが、当時の銀山平は小出町から片道3日もかかる峻険な山道を歩かなければならない僻地にあり、途中には枝折峠という難所があり、冬季間は如何なる交通手段もないほどの豪雪地帯で、資材運送は不可能であった。そこでダム建設に先立ち、湯之谷温泉付近から全長22kmに及ぶ工事専用道路建設を1954年12月に着工、雪崩や事故で54人の犠牲者を出す難工事であったが、3年の歳月を1957年11月に完成した。
全長22kmのうち18kmがトンネルで占められ、雪の影響を受けないように工夫されていた。
ダム完成後はしばらく管理用道路として使用されていたが、1969年に新潟県に譲渡され有料道路として供用、1977年からは無料となって、奥只見観光道路(シルバーライン)として活用されることになった奥只見ダム・田子倉ダムを含むこの地域一帯が「越後三山只見国定公園」に指定された。「シルバーライン」の名称は銀山平で江戸時代銀がこの地で産出され事に由来している。
また、国道252号線、通称「六十里越」が1973年に六十里越トンネルが完成して、魚沼と只見が結ばれ、六十里越、シルバーライン共に冬期間は豪雪のため完全通行止(11月下旬から翌年5月中旬迄の約半年間)になるため、唯一の交通機関はJR只見線のみとなってしまう。このため完全な赤字路線でも廃止の対象にならなかったが、豪雨の被害で路線が寸断され、只見線は部分運休し折り返し運転となっている。
土砂の捨て場は未定、そこで突堤の埋め立てに使用することを提案した。
只見川は洪水の原因となる根本的な対処がなければ再び洪水が繰り返すことになるばかりだ。そこで金山町の住民有志32人が「ダムの堆砂が水害の原因」として只見川にダムを設置する東北電力と電源開発(Jパワー)に約3億円の損害賠償求める損害訴訟を福島地裁会津若松支部に提訴した。
同時にJパワーの滝ダム、東北電力の本名ダム、上田ダム、宮下ダムの計4ダムで堆砂浚渫工事が終了するまで発電稼働の差し止めを求めた。
人跡未踏のような峻険な山岳地帯を克服して電源開発を成功させたのだから、その力を持ってすれば後始末をどうするかくらいは楽にできるものと思われるが、着工できないでいるのは何故なのだ。黒部ダムのように現役発電施設、観光資源として健在だ。ならば只見川発電所ラインと観光資源開発も充分開発資源として健在のはず、あとはどう開発するか、どう活用するか、どう知恵を絞り出すかにかかっている。

黒部ダムは観光ルートとして最高の人気を呼び、JR五能線も観光スポットとて観光列車が走り、人気をはくしているし、会津鉄道・野岩線も人気がある。
大津波で全線に被害を受けた三陸鉄道も復活した。
春の新緑、秋の紅葉、冬の豪雪地帯と水と山の連続で只見線沿線は都会人にとって素晴らしい観光資源だが何故かあまり人気は無い。豊富な観光資源を有しながらJR只見線沿線は過疎化が進み、寂しげな赤字ローカル線でしかない。観光開発・地域開発の余地は充分あると思うが、素人考えでしかないのだろうか。

一方、道路に関しては、只見町までは田子倉専用鉄道が敷設されたが、奥只見ダムは更に奥地で険阻な山岳地帯、銀山平に建設されたが、当寺の銀山平は小出から片道3日もかかる峻険な山道を歩かなければならない僻地にあり、途中には枝折峠という難所があり、しかも冬季はいかなる交通手段でも不可能という厳しさで、資材運搬は不可能であった。そこでダム建設に先立ち、湯之谷温泉付近から全長22kmに及ぶ工事専用道路建設を1954年12月に着工、雪崩や事故で54人の犠牲者を出す難工事であったが、3年の歳月をかけ1957年11月に完成した。全長22kmのうち18kmがトンネルで占められ、雪の影響を受けないように工夫されていた。が、開発の推進とのかねあいは難しい課題だ。
 |
 |
甦れJR只見線
東北観光推進機構が2015年2月18日、中国版ツイッター、微博(ウェイボー)に只見線の雪景色の写真を3葉掲載したところ、「福島の只見線は世界で最もロマンチックな鉄道」と絶賛され、「私はもうその美しさに泣いてしまった」などのユーザーの書き込みが続いた。
 |
 |
 |
福島の只見線は世界で最もロマンチックな鉄道と言われている。
皆さんもどうぞ観光へ
中国での反応、書き込み
「美しさに涙が出た…生きているうちに行けたらいいなー」
「雪国列車だ」
「息もつけないほど美しい」
「鉄道ファンなら行かないわけにはいかない。是非行きたい。」
「本当に美しい」
「アニメのようだ」
「お金を貯めて日本に行くぞ」
「仙人の棲まいに入った感じがする」
「路線の名前も素敵だ」
 |
世界最高の観光鉄道、ロマンチックトレーンが走るJR只見線、観光立国日本の目玉になり得る観光資源開発を是非やって貰いたい。
日本初のクルーズトレイン「ななつ星in九州」「新たな人生に巡り逢う、旅をお楽しみ下さい」をキャッチフレーズにして売り出した観光列車が大ヒット、まさにアイデアの勝利。観光バスにはない全く新しい究極の観光旅行を編み出した。
 |
二番煎じかも知れないが、東北は温泉、観光地、リゾート地、郷土料理、新鮮で豊富な食材、そしてなによりも豊富なのは沿線の雪景色、新緑、紅葉、山、海、海岸等全てが揃う観光のパラダイス。
JR東日本は赤字ローカル線の再生、活用するためにも超豪華なクルーズトレインの開発に取り組むべきだ。
1週間位かけ、JR只見線、JR五能線、三陸鉄道、その他ローカル線を繋いで、ゆっくりと観光を楽しむ豪華列車の旅、これまでの列車のように目的地に早く着く発想はない。生活が豊かになれば旅を楽しむ余裕が出来てきた。
国内ばかりを対象とするのではなく、広く世界に宣伝して、観光客を募ろう。中国人の皆さんも爆買いの次はゆっくりとした観光を楽しむはず、途中下車の温泉ホテル、スキー場、夏は海での行楽、森林浴等開発すれば地元も潤うことになる。
JR東日本、東北各県の担当者の皆さん、研究してみて下さい。
 |
 |
 |
|
 |
 |
| ななつ星in九州(JR九州) | |
JR東日本もやがて豪華観光列車が管内を走り、日本一風光明美な観光地、JR只見線を走行する日も近いと夢みたい。陸路を走る豪華客船のクルーズ、その時こそ奥只見の真価を発揮し、観光地として開発されるときだ。
速報
2017年、JR東日本は超豪華観光列車を、東日本管内を走らせる計画を持っている。
「TRAIN SUITE四季島」がその名で、四季島と我が国の古い国名「敷島」を元に、美しい四季と伝統を感じながらの旅を連想させ、時間と空間の移り変わりを楽しむ列車であるという想いを込めて命名したという。
2017年春に東北各地を超豪華観光列車が走るわけだが、常磐線や只見線をこの列車が巡航出来るようになった時こそ福島県が完全復活を遂げたときだ。
 |
|
 |
 |
 |
|
第二十七章 原子力発電への途
福島第一原発諸考
1930年代に人類は核エネルギーの存在を発見し、1942年、シカゴ大学のエンリコ・フェルム教授が、実験炉で原子力発電の原理となる核分裂の連鎖反応を行うことに成功、1945年にアメリカで核分裂反応を利用した原子爆弾が開発され、広島、長崎に投下、史上最悪の悲劇をもたらした。

次に実用化されたのが空気を必要としない動力源として潜水艦の動力として活用され、原爆開発から9年後の1954年最初の原子力潜水艦が進水し、原子力は軍事用として開発が進んだ。
民需としての原子力は、史上初の原子力発電は、1951年アメリカで実験炉、EBRー1から始まる。EBRー1の当初の発電量は1kw弱で、200wの電球4個を発光させた。
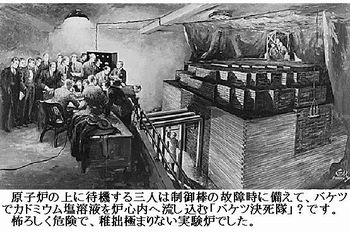
本格的に原子力発電への途が開かれたのは1953年12月8日、アイゼンハワー米大統領が国連総会で行った原子力平和利用に関する提案がその起点となった。
これは核兵器開発だけに力を注ぎ、核兵器の怖ろしさを感じていた核先進国に対して原子力発電という平和利用に向けさせる大きな政策転換があった。
1959年に原子力エネルギー法が修正され、アメリカ原子力委員会が原子力開発の推進と規制の両面を担当することになった。
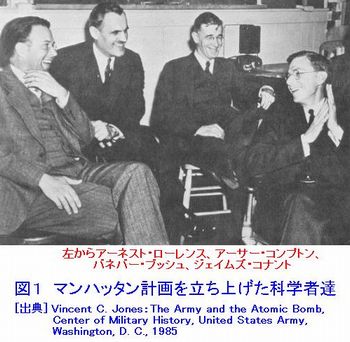
原子力発電を実用化したのは国家を挙げて開発に邁進したソ連の方が先で、1954年6月オブニンスク発電所が営業運転を始めた。
また同年原子力潜水艦を就航させ、米ソ対立が激化、熾烈な核開発競争が始まり、世界は二極分解、対立構造の世界となって、西側(アメリカを中心とした資本主義的自由経済諸国)、東側(ソ連邦を中心とした社会主義統制経済諸国)と僅かな中立国(第三勢力)に色分けされた。
西側で最初の商用原子力発電は、イギリスのコールダーホール1号炉である。運転開始は1956年10月17日、出力6万kW、炉の形式は黒鉛減速炭酸ガス炉(GCR)であった。
アメリカでは、シッビングボート発電所が最初で、1957年12月18日、操業開始、出力10万kW、炉の形式は加圧水型原子炉(PWR)であった。
フランスでは、1964年2月に運転開始、シノンA1号炉、出力8万4千kW、炉の形式はGCRであった。
1957年、欧州共同体(EEC)諸国により欧州原子力共同体(ユートラ)が発足、同年国際原子力機関(IAEA)も発足した。
原子力発電が発足した初期には、夢の発電と喧伝され、「Too cheap To meter」と言われた。この意味は「原子力で発電すると、余りにも安価で計量する必要が無い」という意味で、夢の発電方法だとされ、世界の各国は原子力発電の導入を急がねば世界の趨勢から取り残されるとの危機感が生じた。
しかし現実はそう甘くはなかった。厳重なバックアップ装置や何重もの安全装置が必要であり、その建設費が膨大であり、かつ検査や点検に非常に時間がかかる。
原子力発電が他の発電方法に比べ設備費の割合が非常に高く、必ずしも安価で理想的発電方法とは言えない面もあることに気付いていたが、趨勢を換えることは出来ず、原子力発電所建設は国家の威信をかけ世界に拡がっていった。
1977年、アメリカは民主党のジミー・カーターが大統領に就任すると、カーター政権は1977年核拡散防止を目的としてプルトニウムの利用の凍結する政策を発表した。
これによりアメリカでは高速増殖炉の開発が中止され、核燃料サイクル開発を断念したことになる。これ以降核燃料は再処理されずワンスルーとなった。このような世界情勢の中でわが国の原発は54基を数え、世界第三位の原発を保有国になっていた。
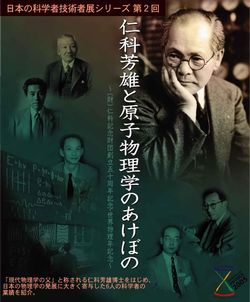
1979年3月28日、スリーマイル島原子力発電所事故発生、この事故は世界の原子力業界に大きな衝撃を与え。原子力の新規受注が途絶えた。
1986年、人類史上最悪の原発事故、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生、自国ばかりでなく、近隣諸国、ヨーロッパ諸国が被害を被った。
日本の原子力政策
戦前からわが国のサイクロトロンの研究開発は世界最先端の研究を行っており、研究の中心であった理研工学の仁科芳雄博士が中心となりグループには湯川博士、朝永博士のような戦後ノーベル賞を受賞した逸材が輩出している。
1945年8月15日、ポツダム宣言受諾、敗戦国になり連合軍の占領下にあったわが国は「オキャバイトジャパン」となり、当然ながら原子力の研究は全て禁止になって研究施設のサイラトロンその他全ての研究施設は全て東京湾に投棄、または破棄され、占領下にあった7年間はまったくの冬の時代であった。
1952年4月、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)が締結され、念願の独立を果たした。
独立をもって原子力研究も解禁されたが、広島、長崎の被爆が余りにも大きな衝撃であったため、原子力研究への意欲を失わせてしまい、わが国の原子研究平和利用の面でも世界水準からも大きく遅れをとってしまった。
1952年7月 日本学術会議において茅誠司、伏見康治の両東大教授を中心としたメンバーが「国際的に遅れを取った日本の原子力研究の巻き返し」をどうするかという議案が提出したが、この提案に対し被爆地であった広島大学、長崎大学から核研究が兵器開発に繋がるのではないかとの懸念が表明され、全国的に議論が巻き起こり、そのため日本学術会議内に文系、理系、法学等幅広く各部門の専門家が参加する「第39委員会」を設置、議論を重ねたが、なかなか議論を煮詰めることができなかった。

この動きとは別に政界では、もと国務大臣であった後藤文夫代議士を中心とした政官界有志による原子力政策推進の動きがあり、1952年に財団法人電力経済研究所が設立された。
世界の趨勢としては、1953年12月、国連総会の席上、アイゼンハワー米大統領が行った演説の中で「平和のための原子力」を提案、これは当時、原子力発電はソ連が世界初の原子力発電を行い、核爆弾競争でも水素爆弾を開発したのもソ連でしたから、核開発競争ではソ連が1歩リードしており、アメリカは焦っていたので、演説の骨子は、国際的な枠組みで核の燃料を保管・監視し、必要に応じて各国に分け与えよう、とする内容であった。この構想は若干の修正があったが、国際原子力機関(IAEA)として実現し、この機関は現在でもイランや北朝鮮の査察問題で報じられているように活躍した。
この演説を契機としてわが国でも「新しい時代に乗り遅れては大変だ」との気運が政財界に高まり、アイゼンハワー大統領演説から3ヶ月後には自由党・改進党・日本自由党の共同提案、その中心は当時改進党に所属して青年将校ともて囃されていた若き日の中曽根康弘、稲葉修、斎藤憲三、川崎秀二、前田正男氏等の議員が結束して原子力研究開発予算を国会に提出した。当時、与党は衆院で過半数の議席を持たず、どうしても予算案を通過させたい吉田内閣は改進党提出である原子力研究開発予算を抱き合わせで通過させた。
アイゼンハワー大統領の「平和のための原子力」の演説こそがわが国の原子力に関する活動に火を付けていたことになる。
水力発電の只見川総合開発で福島案、新潟案、東京電力案が複雑に交差し、てんやわんやの大騒ぎをしている同時期に原子力発電の可能性をさぐる動きがあったのだから如何に電力不足が深刻であったかが推察される。
そのときの予算請求額は予算2億3,500万円、ウラン235に因んだ予算額請求であるから、予算額だけが一人歩きする未明の世界であったのかもしれない。
突然の予算成立に主管官庁である通産省は当惑したが、1954年5月に、内閣の諮問機関として「原子力平和利用準備委員会」が設置したが、これに猛反発したのが日本学術会議で、原子力研究・開発が政治主導になることに危機感を強め、当時の日本では原子炉の建設は時期尚早と批判したが、電力の絶対量不足に対応するためには絶対必要とする政・官・財の勢力に屈し、第39委員会は慎重意見が相次いだが公聴会の意見を集約し、原子力利用は日本国民による民主的、かつ研究成果を公開することを条件にしてその運営方針を了承した。
先に通過した原子力予算の使い道として、小型原子炉の建設と放射能障害の研究の二項目に絞って原子利力平和利用を目標として設定した。
その頃、国際的な関心事はロシア、イギリスの実用的な動力炉の成果が注目され、同時に米ソ対立による世界の二極化が明らかとなって、わが国は防共の砦としての役割を担わされ、否応なしに米ソ対立の最前線に立たされてしまった。
こうなるとアメリカとしてはわが国が1日でも早く経済復興し西側諸国の一員として活躍できるようにと期待するようになり、電力回復に多大な期待を寄せ、原子炉建設を全面的にバックアップすることを申し出、燃料供給から炉の設計・建設まで請け負うことを約束した。ところが1954年3月、ビキニ環礁での水爆実験、第五福竜丸被曝事件となり、世論は一気に反原発となって、反原発運動が全国的になって広まった。
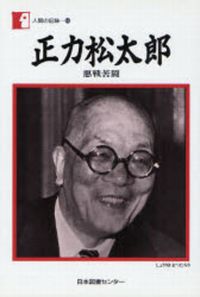
そこで、活躍したのがマスコミ界の実力者で読売新聞の社主、しかも現職の国会議員であった正力松太郎氏で、原子力推進の一大キャンペーンを行い、アメリカの原子力平和利用使節団(団長・ジョン・ホプキンス、ゼネラル・ダイナミックス社長)を日本に招いて各地で講演を開催、読売新聞がこれを全国に報道した。
またCIAと組み原子力平和博覧会を日本各地で開催した。この動きに反発していた学術会議や被曝協等も原子力利用が日本の戦後復興には電力確保が絶対の命題であることから次第に軟化し協調するようになった。
1955年自民・社会の両党は協力して、「原子力基本法」「原子力委員会設置法」「原子力局設置法」といわれる原子力三原則の三法案がスピード可決され、政府は『原子力平和利用準備委員会』を解消し、「原子力委員会」を発足させた。
1 研究の民主的な運営
2 日本国民の自主的運営
3 一切の情報の完全公開
そして基本法成立を受けて1956年1月1日、原子力委員会が設置され、初代委員長に正力松太郎氏が就任、原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに1957年5月には新設された科学技術庁の初代長官にも就任、「原子力の平和利用」および「原子力の国際協力」を基本として、日本として従来の研究テーマであった「アイソトープ利用の実用化」に加えて「5年以内に原子力発電を実現させる」という目標を掲げた。
さらに正力委員長は目標達成には産業界の協力が不可欠として「原子力産業会議」を開催し、2月に首相官邸に71名の財界代表を招いて広く周知し、さらに3月には日本工業クラブに「日本原子力産業会」が発足、初代会長は、電気事業連合会の菅禮之助(東京電力会長)氏が就任、原子力発電所建設への路は開けた。
一方、動力としての濃縮ウラン燃料はアメリカから貸与されることになり、保管場所および研究所の設置が急務となり、受け入れ機関として1954年7月に「財団法人日本原子力研究所」が急遽発足し、研究所の候補地を求めたところ、当時の国内の世論は原子力歓迎ムードで、数多くの候補地があったが、最終的に茨城県東海村が選ばれた。

1956年に日本原子力研究所、現・独立行政法人研究開発機構が特殊法人として設立され研究所が茨城県東海村に設置され、これ以降、東海村はわが国の原子力研究の中心となった。
当初は原子力基礎研究を優先すべきとの主張があったが、先ずは電力需要を鑑み、原子炉建設をして運転しながら研究をする同時進行型を決め、1957年12月に原子力委員会は1975年までに、700万kwの原子炉稼働する目標を掲げた。
1957年11月1日には、電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発公社が共同で最初の原子力発電が行われたのは1963年10月26日、東海村に建設された実験炉であるJPDRが臨界に達し初発電を行い、ここにわが国初の原子の灯がともったことになった。
かくしてわが国にも原子力発電の路が開かれ、日本原子力発電株式会社(民間出資8割)が誕生し、日本原電東海原子力発電所(日本初商用原子炉)にはイギリス製のコールダーホール改良型炉の導入が決まった。
ただし性能が悪く、採算面でも火力発電に劣るとの検証結果があり、更には耐震性にも問題ありと検証されたが、原子力委員会と財界の牽引力は大きく、原子力政策が大きく前進したのは中曽根康弘代議士が科学庁長官に就任してから「新・長期計画20年」が発表され、最初の10年間で商用原発の発電規模は3基100万kw、後の10年で火力発電量の30%程度(650~850万kw)、多分20基程度を予定していたのでしょう。

ただしこの構想は中曽根長官の独創であって正式な路線ではなかった。このような時、アメリカ側から甘い囁きがあった。アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE社)から魅力的な価格の軽水炉と「ターンキー契約」の申し出である。これは最初に固定化された契約金額が提示され、契約すると建造から臨界までの作業は全て契約者であるGE社が全てを請負、その後事業者はマニュアルに従って運用するだけという契約方式で、自力で建設・臨界までの技術がなかったわが国原子力業界は飛びついた。
原子力発電の路が開かれれば、あとは建設場所の選定になる。原電は東海発電所に続く第二号炉として、1961年福井県敦賀市を選び、建造はGE・東芝・日立のグループが請け負う契約を結んだ。契約者は関西電力であった。
以上のような経過を辿ってわが国原子力発電は誕生し、急速に発展を遂げ、福島第一原発事故を契機として全国的な反原発、脱原発の大きなうねりがおきて、大飯原発を除き全国の原発は停止、再稼働の許可待ち状態になっている。
原子力発電設置の端緒を創ったのは若き日の中曽根康弘代議士であり、正力松太郎氏であったが、原発を全国的に建設し、設置数を急速に増やしたのは田中角栄氏の力によるものが大きい。

原子力発電所、田中角栄、中東戦争、ロッキード事件、この四題は一見関係なさそうだが、落語の三題噺のようにこの四題は結びつくから強烈な絡みつきがある。
この四題噺はリレー式連載で月刊誌に書いたことがある。さわりだけを一寸述べると、中東情勢がおおいに関わってくる。第三次中東戦争(1967年6月5日)、イスラエル空軍がエジプト、シリア、イラク、ヨルダンの四ヶ国の空軍基地を爆撃、これを壊滅させてから地上軍を攻撃、6日間で戦闘を終結「六日戦争」。
第四次中東戦争(1973年10月6日)、エジプト機甲師団が周到な準備の後、「失地回復」を狙って、シリア軍と連携してイスラエルを先制攻撃したが、猛烈な反撃に遭ってスエズ運河まで押し戻されてしまった。
この時、石油輸出国機構(OPCD)加盟産油国のうちペルシャ湾岸の六ヵ国が、原油価格を大幅値上げ、かつ原油輸出の大幅削減、イスラエルを支持するアメリカをはじめとする西欧諸国への経済制裁として石油輸出禁止を通告した。
これが第一次石油ショック(オイルショック)、更に第二次石油ショック、第三次石油ショック。イラン・イラク戦争とまさにペルシャ湾、ホルムズ海峡、シャットゥルアラブ河は戦乱のまっただ中にあった。
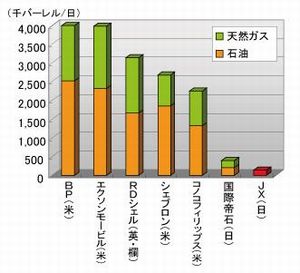 |
 |
我が国もオイルョックをもろに受け、明日の運命はどうなるのか全く判らない情勢にあったが、この時は田中内閣があって、独自の外交を展開した。即ち「アブラ寄り」と言われたアラブへの迎合政策である。
田中内閣の政策とアメリカ政府激怒の背景に触れてみたい。
石油産業にはアップストリュウム(上流)とダウンストリュウム(下流)があり、アップとは石油探査、採掘、生産まで、ダウンは運輸、精製、配送、販売に分かれ、このアップ、ダウンの両方を支配しているのがスーパーメジャー(石油メジャー)で、セブンシスターズ(エクソンモビール、ローヤル・ダッチ・シェル、BP、シェブロン、トタル、コノコフィリップス)がソ連圏を除き世界の石油を支配しているのが7社なのでセブンシスターズと言われていた。(ユダヤ財閥系が多い)
わが国にある石油会社はダウンの精製・販売だけなので原油の確保にはいたってはいない。かつては出光興産やアラビア石油がサウジアラビアに鉱区を持ち原油を採掘していたことがあるが現在では全ての鉱区が契約期限切れで失ってしまった。
田中角栄氏の構想としては和製メジャーを組織して石油を確保しようとした壮大な構想を持っていた。
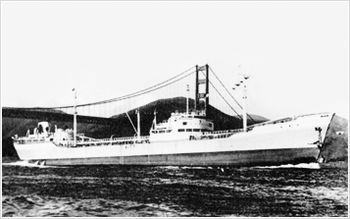
特にオイルショック時、イスラエルとの親交の度合いを諮る「踏み絵」を突きつけられた時、アラブ寄りを表明し、特使がアラブ諸国を歴訪しアラブ寄りを誓い石油物乞いを演じた[特使は三木武夫副総理]。
この行為にアメリカ政府、石油メジャーが激怒、危険なモノは芽のうちに摘んでしまうのが基本。この背景にあるのは、独立してまもない昭和28年、中東の石油はメジャーが支配していた頃、日本の独立資本である出光興産が石油メジャーの監視の目をかい潜って独立してまもないイラン政府から直接石油を買い付けたことがある。【出光興産に関しては『海賊と呼ばれた男』上下、百田尚樹著、アマゾン、2013年本屋大賞受賞。
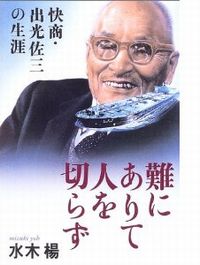
1953年イランからイギリス海軍の封鎖線をかいくぐり直接石油を買い付けた実話、日本側は快挙、石油メジャーは激怒した。この実話は東宝・三橋達也主演で映画化されたことがある。
横道に逸れるが、戦後史を語る上で重要な「日章丸二世事件」に触れてみたい。
第二次大戦後、世界の植民地は独立の気運に燃えていたから、中東も同じく独立運動に火が付き、これと同時に石油資源も自国の財産にしようとの気運が盛り上がった。
さらに宗主国であったイギリスやフランスが第二次大戦で戦勝国になったとはいえ、大きな痛手を蒙っているので、植民地支配に大きな力を加えることが出来ない。
これぞ好機と捉えるのが当然で、独立運動が活発化し、独立が相次いだ。
当時世界最大の産油国と言われていたイランは石油メジャー英資本の完全支配下にあったが、カジャール朝時代に王族であった廷吏の血をひくモサデックは留学先のスイスで法学博士の学位を取得した有能な若者が政界に入り、国会議員、閣僚を経験しやがて首相に選ばれた。

しかし、イラン政情は不安定で、モサデックはバーレビ王政下の1951年、国民の圧倒的人気で首相に選ばれ、持論であった「自国の石油なのに利益を外国にもっていかれるのはおかしなことだ」と主張し、民族主義の高まりを背景に、英資本の支配下にあった石油産業を国有化しようと活動したが、英資本と石油メジャーの反撃に遭い、国王は英米資本に籠絡されており、国王と首相の対立に発展したが、シャーを一時期亡命に追いやるほどであって、モサデック首相は更に自信を得て共和国を宣言するが、ところがこの亡命には裏工作があり、シャーは自分の意志で亡命したと見せかける策謀をCIAとMITが仕掛け、モサデック首相を罠にかけた。
トリックに気付かなかったが、既に軍部は国王に忠誠を誓っており、1953年軍事クーデターで失脚、反逆罪で逮捕され、3年間服役、釈放後は自宅軟禁、外に出ることも許されず失意のままに病没した。
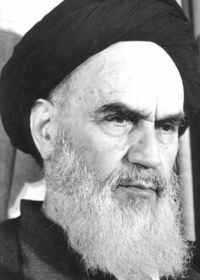
このモサデックが首相に就任し、石油資源国有化で英資本と対立していた頃、我が国が独立をはたした翌年の1953年(昭和28年)極秘に来日した特使が当時は小さな石油会社であった出光興産を訪ね、創業者出光佐三社長と直談判に及んだ。
出光社長自身も直接の買い付けを狙っていたので、商談は極秘に行われて成立、出光興産は新造したタンカー1隻だけ所有する小さな会社だが、出光社長の度量は大きく、社船のタンカー日章丸二世(1万8774トン、当時は日本最大の大型タンカーであったが、現在の基準では小型になる)を通常運航している港には入らず、神戸港に隠れ、夜間行先サウジアラビアとして出港(昭和28年)、(多分クリアランス[出港許可書](税関発行)も行き先サウジアラビアになっていたと考えられる。(この許可書が無いと外国の港に入港できない)。また、もしイギリスの艦艇による臨検を受けても行く先はサウジアラビアと主張できる。
ペルシャ湾ではイギリスの駆逐艦が見張っており、また常時タンカーの発信する無線電信を傍受しており、もしイランへ向かうことが判明すれば拿捕も辞さないと公表していた。もし1隻しかないタンカーが拿捕されれば倒産確実の中での決断だから社長の度量の問題だ。
日章丸二世は無線通信を封印して、無言のままホルムズ海峡を抜け、シャットゥルアラブ河を遡航して4月11日、積出港アバダンに横付けガソリン・軽油2万2千キロリットルを満載し無言で出航、ペルシャ湾に出たところで警戒中のイギリス海軍駆逐艦に発見され追跡、停船命令の旗旒信号(L旗)と発光信号を発信し続けたが、公海航行自由の原則に基づく無害航行権の権利を返信し停船必要なしと応答、戦争当事者ではないので拿捕は出来ない、拿捕すれば国際法違反になる。
この駆け引きで見事ホルムズ海峡を抜け、1ヶ月後川崎港に還ってきた。
かんかんに怒ったイギリス政府は外務省に厳重な抗議を申し込むと同時に、アングロイラニアン社は積み荷の所有権を主張して東京地方裁判所に即時積み荷の引き渡しを要求し提訴した。
しかし法的には無理な請求で、出光興産の行為は純粋な商取引であって法違反や国際慣行に違反したわけではない。さすが強気のアングロイラニアン社も不利を悟って提訴を取り下げた。
またイギリス側の行為は、1私企業の権益を護る為にイギリス海軍が出動するという行為は当然とする植民地主義時代の名残があった。
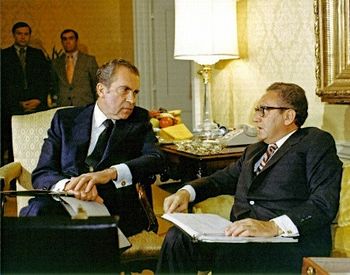
出光興産社長出光佐三氏は一躍時の人となり、戦勝国イギリスと堂々と渡り合い勝利したその行為に敗戦でしょぼくれていた日本国民を奮い立たせた。
そして苦しいイラン政府財政を助けてくれた恩人として出光社長を処遇し、その後の石油確保には数々の盡力があって出光興産は大きく伸び、唯一の民族資本の石油会社として成長した。
この事実は世界初の快挙と言われているが、石油メジャーから見れば痛恨の一撃であった。その怨みも重なって、石油最大の輸入国であった日本の動向如何が石油メジャーにとっても大きな影響があるため、実力者田中角栄氏封じ、あるいは排除に動くのは当然の動きであったかも知れない。
当時日米には経済摩擦が頻発し、繊維交渉、続いて家電製品、自動車と日米貿易不均衡で貿易摩擦が頻繁に起きていた。アメリカ議会は反日ムードが満ちあふれており、当時のアメリカ大統領はニクソンとキッシンジャー国務長官と言う布陣。
日米経済摩擦の交渉が度々開かれ、その時の日本代表は通産大臣であった田中角栄氏でアメリカ側からみれば目障りな存在であったことは確かで、歴代アメリカ大統領と石油メジャーは非常に近い関係にあることは明らかである。
石油危機対応で時の田中首相は大きく舵を切ったエネルギー政策が「脱石油」、即ち原子力発電への移行・推進であった。
一方では、アラブ寄り、和製メジャーの構築、アメリカとの間に距離を置く政策とアメリカ側は見ていた。
1973年12月の参院予算委員会で、田中首相は「石油問題がここまで来たら、原子力発電が必要なことは議論の余地がない」「電力会社だけに任せず、抜本的な対策を政府が責任を持って行う」と答弁した。
決断するのが早い田中首相は即座に首相指示で原発立地地域にお金を回す為の「電源三法」の制定を急いだ。
電源三法(発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法)は、1973年末から法案ずくりに入り、‘74年3月に国会提出、6月成立というスピードでできあがり、その後は原発建設ラッシュとなって全国に54基の原発を擁する世界第三位の原発国になった。
昭和30年代から40年代年には好景気になり神武景気、神代景気と言われた右肩上がりの好調な景気の為、若い労働力は都会に吸収され、壮年の労働力も出稼ぎという形態で同じく都会に吸い寄せられた。
結果は地方の衰退がはじまり、国の骨幹であるはずの一次産業の衰退に繋がった。
そこで地方への工場分散、奨励が行われ、地方都市に工業団地の造成、誘致合戦があり、新産業都市が誕生した。
当時の双葉郡、あるいは福島県は何とか企業を誘致したい、と願うのは当然で、お隣のいわき地区が新産業都市に指定され生まれかわっていくのを目にすれば双葉郡に焦りが生ずるのも自然の流れだ。
これまでの陳情や運動が空振りに終わっていたのが、電源三法により雇用が生まれ、関連企業が誘致でき、何よりも眼を見張るような交付金がある、嫁入り持参金に眼が眩んでも無理はない。
安全性への懸念は勿論あったが政府も電力会社も絶対大丈夫と保障しており、この頃から「安全神話」は公認されたものとなっていた。
電源三法が無ければ原発誘致、建設のテンポはかなり遅れていたと思われる。
石油危機に見舞われ、それに続く狂乱物価、その対応に追われ、対外的にはアメリカとの繊維、車、家電製品等の交渉が縺れ、さらにはフランスからのウラン調達、アラブよりアブラと言われた中東寄りの外交、アメリカに先んじた日中国交正常化などアメリカ政府との対立がめだった。特にキッシンジャー国務長官の激怒は凄かったらしい。
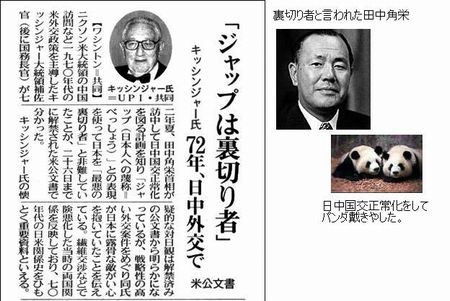
この当時、米中関係は激しく対立しており毛主席は本気でアメリカとの戦争を想定したようであったが、キッシンジャー国務長官がパキスタン訪問中、突如姿を消し、密かに北京を訪れ米中関係の打開を謀った。これがキッシンジャーの忍者外交、頭越し外交といわれ我が国政界を仰天させた。
そうすると田中氏は、総理になるや即座に中国を訪問、日中国交正常化を樹立してしまった。
アメリカは未だ首脳会談にまで至っていなかったため先を越されたキッシンジャー国務長官の怒りは凄まじかったと伝えられた。
羊のように柔順に装いノラリクラリとしていた日本政府が初めて明確に逆らったことに戸惑いがあったのだろうか。
田中内閣は外交では独自のエネルギー源政策、全方位外交を目指し、国内では国土改造論を掲げ、土建屋的な政策を推進した。
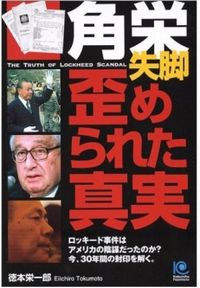
‘出る杭は打たれる’の喩え通り内外からの批判が集中し、特に金権政治の汚名は付きまとっていたが、1974年10月、月刊誌「文藝春秋」で(田中角栄研究)と(淋しき越山会の女王)が掲載(著者立花隆)され、金脈問題が追求された。
東京に日本外国特派員協会という社団法人があり、ここに所属する外国人ジャーナリスト達は週に1、2回内外の政治、実業、スポーツ等の様々な時の人を呼んで主催記者会見を行うのを慣例としていた。著名人を招待していたが、時の人、田中角栄首相が招待され、外国人記者から立花隆氏の文藝春秋誌上に発表された「田中角栄研究」に関する献金問題に関する質問が集中し、その模様が内外メデアに流された結果、国内のメデアは情報を把握していながら発表を躊躇していたが、一斉に記事にしたため内閣崩壊に繋がってしまった。
エネルギー確保を独自に展開しようとする政策で、当然世界の石油企業を支配するセブンシスターズの怒りを買うことになる。また原油の消費を出来るだけ減らそうと原子力発電の奨励で、電源三法が生まれるのはこのような社会情勢が背景にあった。
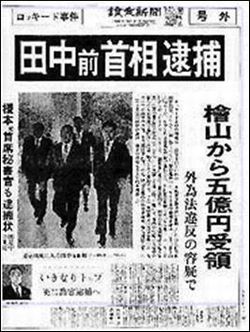
アメリカ政府はニックソン大統領、キッシンジャー国務長官の時代であったから、田中内閣とは悉く対立することになり、その報復がアメリカ議会でリークされたロッキード事件、田中首相包囲網は確実に布石された。
この時金大中拉致事件(1974年8月)もあった。
立花隆氏の金脈追求の論文が「文藝春秋」に掲載され、田中内閣崩壊。その後ロッキード事件で、5億円の受託収賄罪で逮捕され、一審有罪、控訴中に病死した。
このロッキード事件の特異さ複雑さは、発震源がアメリカ上院チャーチ委員会での公聴会、ロッキード社副会長アーチボルド・カール・コーチャン、元東京駐在代表ジョン・ウィリアム・クラッター両氏が公聴会に召喚され、司法取引によって免責されていたからあらゆる証言を表明した。
その複雑さは工作資金のルートが多岐に渡り、会社、組織よりも私的な秘密機関を通じていたこと、その最大は行動右翼の児玉誉士夫氏、占領時代のCIAと関係があった日系アメリカ人シグ片山、GHQの諜報担当トップのチャールス・ウィロビーの片腕だった福田太郎氏等が暗躍していたことが公聴会で証言された。
この事件の複雑さはロッキード社から日本ルートとして30億円の工作資金が流入していることは証言さているが、前総理田中角栄氏に流れた5億円だけが表に出て起訴されたが、他の多くの工作資金の使途は明らかにされなかったから「政治主導裁判」ではないかとの多くの批判があった。
その理由は、事件の核心を握る児玉氏が衆議院予算委員会に証人喚問に応ずる予定であったが病気として自宅に籠もり、その間、軽飛行機が私宅に突入するという自爆テロがあったが、別の部屋に寝ていて間一髪で無事だった。その後大学病院に入院し、口を噤んだまま1984年病没、真相は胸に秘めたままだった。
捜査の開始は首相三木武夫、法務大臣稲葉修三がャーチ委員会の証言内容を検討し、直々に捜査開始を指示、同時に米・ジェラルド・フォード大統領に対して捜査の協力を依頼、日本側は最高検察庁、東京高等検察庁、東京地方検察庁、警視庁、国税庁の合同捜査態勢を整えた。
更には、三木首相の密使として元NHK解説委員、外交評論家の平沢和重氏が渡米し、キッシンジャー国務長官と会談させ、アメリカ側の資料提供を求めた。
また東京地検からは担当検事が渡米、アメリカ検事局の資料提供を要請した。
捜査開始と同時にマスコミが過熱し、連日新聞や週刊誌で報道され、テレビでは国会中継で証人喚問という吊し上げのような映像に度肝を抜かれ、超一流の人物が打ちし折れ、緊張で震えているような異様な光景に驚かされた。
そして政界では宿敵田中角栄を抹殺しようとする三木派の陰謀だと田中派は猛り狂い、自民党の長老椎名悦三郎氏は「三木ははしゃぎすぎ」とたしなめるような言動があった。

結果は他の派閥も田中派を支援し、三木派は孤立、総選挙で自民党が8議席を失う敗北で、三木政権は責任を取らされて首相を辞任、三木おろしの急先鋒福田赳夫内閣が誕生した。
しかし、田中派が最大派閥で福田内閣は「角影内閣」と呼ばれ、大平、鈴木、中曽根も「直角内閣」「田中曽根内閣」と揶揄されるような田中氏のリモコンに操られたような政治になってしまったのは、田中氏が無罪を勝ち取るためには権力を集中させておく必要があり、闇将軍と言われながらも隠然たる権力を維持した。しかし、これが我が国の権力構造が歪になりやがて与党である自民党の活力を奪うことになる。
それはまた日本の活力の停滞、次第に衰退の始まりもこのロッキード事件が切っ掛けといえる。
そしてまた田中角栄氏再起の夢を打ち砕いた。
追い打ちをかけるようにリクルート事件が政界を総なめにして自民党のレギュラー選手が追いやられ、控えの選手が第一線に出ざるをえなくなり政界は更に小粒内閣・短命内閣が連続することにうなった。
ロッキード事件の不気味さは政界ばかりではない、経済界、裏社会までもが揺れ動き、取材中の日本経済新聞の高松康雄記者が急死(1976年2月14日)。渦中の元GHQ要員福田太郎氏急死(1976年6月9日)。
田中角栄氏の自家用運転手兼私設秘書・笠原正則氏が命じられて運んだダンボールの箱に札束が入っていたとの検察の筋書きによって取り調べを受けていた直後の1976年8月2日、埼玉県比企郡山中の林道で変死体で見つかった。

この三氏は病死なのか、事故死なのか、証拠隠滅を謀る組織による暗殺なのか、闇の中に消えてしまったが、警察発表は病死と自殺で捜索は打ち切られた。
また児玉誉士夫ルートこそが本命であるにもかかわらず、病気を理由に事情聴取を拒み続け、検察もまた深追いすることなく、真相を秘めたまま病没した。
この暗闇こそが巨大な力による陰謀説を裏付けるもので、田中氏個人への集中攻撃の様相があったが全ては藪の中、やがて田中派は分裂、竹下派の旗揚げとなったが、怒りがこみ上げたのか田中氏は脳梗塞で倒れ、事実上田中派は消滅、最高裁で審議中に死去、ロッキード事件5億円収賄事件は被疑者死亡で終審した。
しかし、無罪ではない、それは同じ罪状で起訴されていた秘書の榎本敏夫氏が有罪判決であったから、結果的に5億円収受を認定されたことになって「宰相の犯罪」は消えることはなかった。
従って首相在位1年以上の経験者に贈られるのが慣例であった大勲位菊花大授章に叙せられることはなく巨星は消えた。
この事件はアメリカ上院委員会が発震源であり、その基はアメリカの大企業、政府高官、企業責任者が関わっていながら司法取引で法に問われた人物はなし、日本国内だけが大騒動で政府も経済界も大打撃を受け、人の命も奪われた。
どのような組織がどう動いたのか、真相は闇の中、ケネディ大統領暗殺事件のようにすべてが闇の中に葬られたのか、人の噂も75日、いまでは思い出す人も少ないし、全く知らない人も多いだろう。

政界はロッキード事件、リクルート事件と政界を揺るがす事件が起き、次期総理・総裁ともくされたり、大物政治家として期待されていた人達は事件に何らかの関わり合いがあったりして、表舞台から消えてしまい、二軍から急に引き揚げられた議員が晴れ舞台では戸惑うばかりで短命でおわるのはヤムを得なかった。
政治が弱体になれば経済も下降するばかり、国民は意気消沈、誰が仕掛けた罠なのか、踊りすぎた日本が悪いのか、踊らせる罠を仕掛けた方が悪いのか、表面的な外交はにこやかにシャパングラス片手に談笑しながら日々動き、国際的な陰謀もまた深く静かに日々動いているのもこれが現実。
ロッキード事件のアメリカ陰謀説を唱えた最初は評論家の田原総一朗氏で1976年7月号の「中央公論」「アメリカの虎の尾を踏んだ田中角栄」だった。
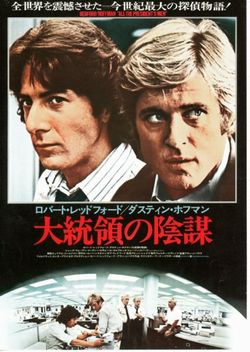
ニクソン大統領は1974年9月8日、ウォーターゲート事件の責任を執って任期途中で辞任した(歴代大統領が刑事事件で、任期途中での辞任は初めて)(ウォーターゲートとはワシントンDCにあるビルの名で、ここに部下が侵入し、政敵に対する何らかの工作の目的があったらしいが、事前に逮捕され、最初はコソ泥程度と思われていたが、侵入を命じたのがニクソン大統領であったことが判明)『後に「大統領の陰謀」というハリウッド映画が公開された。ダスティン・ホフマン、ロバート・レッドフォード主演、アカデミー賞で助演男優賞(ジェイソン・ロバーズ)、脚本賞、美術賞、録音賞の4部門を受賞した』
この映画を観たが大統領執務室で練られる陰謀の数々がリアルに描かれており、思わず引き込まれてしまった。もしかしたらロッキード事件もこのようにして仕組まれたのかも知れないと想像は果てしなく拡がっていったが、後刻、種々の背景が浮かび上がってくると確信に代わってきた。
従って田中内閣の評価は金権政治の反発で評価は低いが、実際は日中国交回復、オイルショックを乗り切る全方位外交等プラス面を再評価すべきだ。
田中内閣が原発建設に積極的だったのも、電源三法の成立も世界的背景を見れば全てが納得できる。
しかし両首脳とも策に溺れすぎたのか、共に法の裁きを受け晩年は寂しかった。「現代史が解ればニュースが読める」歴史は大いに学ぶべきで、特に第二次大戦前後である20世紀中頃から今日に至る世界の動きに注目したい。
実に複雑で世界中が連日変化している。世界中のニュースが新聞やTVによる官製報道ばかりではなく、ネットを通じて生のニュースが飛び交っていて、パソコンに触れるだけで世界中のニュースを入手出来、取捨選択自由自在、3台を駆使して、時間たっぷりの隠居の身には最高の快楽、持病もなし、毎日が楽しい。
もっと楽しかったのは、あの頃、中東で働いており、危機襲来で必死に逃げ回っていたが、事件に遭遇、現場に居合わせた偶然の暁光と高揚感がもの凄かった。
原発設置構想
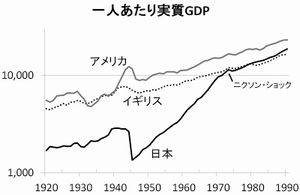 |
 |
右肩上がりの高度成長期、電力消費も当然右肩上がり、旺盛な需要に生産は追いつかない、発電所建設が追いつかない。しかも水力発電は国内の適切な建設地はもう飽和状態、火力発電は世界的な地球温暖化問題で二酸化炭素は敵視され、それを排出する火力発電所の建設も住民運動の激化で進まない。
風力発電、太陽光発電、地熱発電等、最近脚光を浴びているが、当時は全く問題にならない位に発電単価は高過ぎ性能も悪かった。
残るは原子力発電だけ、発電単価は遙かに安価、空気を汚さない、騒音もなし、煤煙もなし、理想的なクリーンエネルギー等、これが原子力発電のうたい文句で、当然国策として原子力発電推進プロジェクトとして通産省主導で動きだし、国内最大の電力消費地をエリアとする東京電力も増大する電力需要に対応して、原子力発電に関心を持つのは当然だ。
ところが記録によるとアイゼンハワー米大統領が「平和の為の原子力」が国連で行われて頃(1954年)、後に東電社長として原子力発電を推進した木川田一隆氏は当時まだ副社長であったが「原爆の悲惨な洗礼を受けた日本人が、あんな悪魔のような代物を受け入れてはならない」と語ったことが記録されている。
この米大統領の国連演説があった頃からわが国政府内では原子力推進の議員が活発に動き出し、終戦から僅か10年後の昭和30年(1955年)読売新聞社社主であり衆議院議員で正力松太郎を中心とした議員連盟が導入推進運動を始め、一方、改進党の若手議員であった中曽根康弘議員、川崎秀二議員党数名の議員が連盟で原子力推進の法案を提出、予算を要求した。
原子力開発の主導権争いが起こり日本発送電を分割民営化した9電力を所管する通産省と電源開発公社の間で熾烈な争いがあった。
この件に関しては調停があり、国・民間両者の出資で原子力発電導入のパイロット機関として日本原子力発電株式会社を設立した。
1957年12月05日 日本原子力発電株式会社は茨城県東海村の海岸段丘上の空き地を原子力発電所敷地の候補地と決定、土地取得にかかった。
1959年03月16日 東海発電所原子炉設置許可申請
1959年12月14日 東海発電所原子炉設置許可
1959年12月22日 東海発電所の購入契約を日本原子力発電株式会社と英国GEC社と締結
1960年01月16日 東海発電所建設着工
1966年07月25日 東海発電所営業運転開始
日本原子力発電の初仕事は高度経済成長と共に電力需要急増に対処するための原子力発電テストケースとして、茨城県東海村の海岸に日本初の商業用黒鉛炉かつ商業用原子力発電所を建設、炉型は英国製の黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉(GCR)で、これにわが国独自に耐震強度の増強など、英国にはない設計をやり直し、日本独自の改良を加えた原子炉を建設し、1960年1月に着工し、1965年5月4日、臨界に達し、日本初の商業用原子炉となった。その後27年間営業運転をしたが、1998年3月31日、営業運転停止、現在日本初の廃炉工事が進行中である。

これらの研究・開発期間を過ぎてから、立地に合わせた建設計画を練る段階にきて、各候補地を実際に訪ね、土地選定に入った。
候補地は東電の原発課の社員が現地を視察し比較検討した。
条件としては、(1)周辺は過疎であること、(2)冷却水が得られ易い、(3)地盤がしっかりしている、(4)外来電力が確保できる、(5)交通が便利なこと。⑦労働力が確保できる等が条件であった。
最初は東電管内の土地に限られ伊豆半島の東伊豆方面、東京湾の姉ヶ崎、外房の鹿島(鹿島臨港開発以前)、東海村(後に、日本原子力発電が東海原子力発電を建設)、水戸射爆場跡地(現在国営ひたち海浜公園、敷地約160ha(東京ドーム約32個分)、ここは旧海軍の射爆場で、海軍航空隊の爆撃訓練が行われていた。ハワイ真珠湾攻撃訓練は、雷撃は鹿児島錦江湾、水平爆撃と急降下爆撃訓練はこの射爆場で行われ、戦後は一部開拓民が入植したが大半が砂地のため放置され荒れ地になっていた。
候補地のうち伊豆半島はフィリピンプレートでトリプルジャンクションが近くにあり、しかも伊豆箱根火山帯が通る地震多発地であるから除外。
姉ヶ崎は東京湾内にあり人口密集地帯だから除外(現在姉ヶ崎には東電の火力発電所が建設され稼働している)
鹿島と水戸射爆場は地盤に問題があり除外、東海村は日本原子力発電の方が早くこの地に原発建設を決めてしまった。
そうすると東電管内では適地が見付からなかったことになってしまった。
一方、福島県の動きを見ると、佐藤善一郎福島県知事(1957年~1964年)が原子力の平和利用に非常に関心を持ち、在職中の1958年には商工労働部課に命じて原子力発電所設置の可能性に関する調査研究を命じ、1960年には日本原子力産業会議に入会し、企画開発担当部門のスタッフにより、県独自の立場から浜通り各地を調査し、結論は双葉郡内に絞り、最適地として太平洋に面した海岸段丘上の旧陸軍飛行場跡地(大熊町)を推した。
ところが具体的な計画を推進する前に、佐藤知事は急性肝臓萎縮症で現職のまま急逝してしまった。従って東電との接触は未だ無かった。享年64歳。
この佐藤知事の行動は「東京電力三十年史」(1983年)に記載されている。
また1958年3月14日付け「福島県議会議事録」によると自民党所属の県会議員大井川正巳氏は、火力発電所の誘致に関する質問をし、そのついでのように、将来原子力発電所を誘致するなら双葉郡が良い、また電力会社は東北電力にすべきだ。との趣旨の質問をしたところ、知事の答弁は小名浜、勿来地区に火力発電所を誘致するが、石炭は常磐炭ではなく北海道炭を使用する予定なので、小名浜港を整備しなければならないが、原子力発電所誘致に関しては全く考えていないと答弁した。
この時点では関心がなかったようだが、この質問を契機として原子力発電に関心が向くようになり、部下に調査研究を命じている。
知事急逝後は、国会議員のうちから原発に関心を持っていた木村知事に代わったから、より一層原発建設に前進しだした。
原発誘致の芽生え
昭和30年代は‘反原発’の動きも少なく、それよりも過疎化対策、地域振興の決め手となると歓迎されており、県知事の推薦、さらに自民党の長老である、元幹事長の斉藤邦吉代議士は地元(福島三区)選出(相馬市出身)。自民党電源立地推進調査会会長のお墨付きとなれば、斉藤代議士の絶対的影響下にあった双葉郡、相馬郡としては町議会が誘致決議をするのも自然の流れだったのだろう。
そして大熊町・双葉町にまたがる海岸地帯の約350万平方m(約100万坪)に及ぶ広大な敷地には更に7・8号基建設計画があったほどの広さがあった。
1971年3月(昭和46年)東京電力とって初の原発が稼動するまではいろいろあったが、もう一人原発推進の主役がいた。
当時の東電社長は木川田一隆氏、生まれが福島県伊達郡梁川町、父は医者、旧制角田中学(宮城県)、旧制山形高校から、東京帝国大学経済学部卒業、当時の東京電灯会社入社、戦後は東京電力株式会社となり、やがて社長に就任、木川田天皇と言われるくらいの実力者で辣腕を振るった。
原子力発電所建設が決まると、その建設地として浜通りを推奨し、当時の福島県知事佐藤善一郎(福島市出身)福島県議を経て、衆議院議員二期連続当選後、1957年知事に当選。この頃から木川田東電社長が福島県庁を訪れ、非公式な会談を重ねていたらしい。
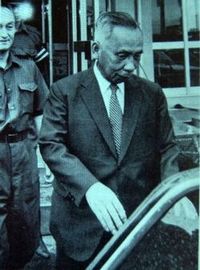 |
 |
ところが、佐藤知事は在任中の1964年、急性肝臓萎縮症で急死、その時点では未だ福島原発の調査も始まっていなかった。
次の知事は、木村守江氏、四倉町(現いわき市)の開業医から1950年参議院議員に当選、1958年衆議院議員に当選、1964年佐藤知事急死による知事選で当選した。
木村氏は四倉町で代々の開業医(木村医院)、木川田社長も父、兄共に開業医で元々医者として親交があったらしい。そのような関係で原発問題は急進展した、といわれている。
確かに木川田社長は月に1回は福島へ出向いて知事と会談、地元町長や議会関係者と会談していたことは明らかになっている。
県トップの知事、地元選出で原発推進派の斉藤邦吉代議士、東電のトップが全て福島県人であり、地元町長、町議会も賛成となれば意志の疎通は完璧で、反原発の運動が疎らにあった程度ですんなりと決定した。
福島第一原子力発電所
双葉郡には、第一原発が6基、第二原発が4基、計画中が2基あり、さらに東北電力が浪江・小高地区に沸騰型原子炉建設を予定しており、2020年運転開始の計画であった。これだけ集中しているのは若狭湾沿岸に次いで日本で二番目の集中度になる。
では何故双葉郡だったのか?
そもそも福島県は東北電力の電気供給区域であって、東京電力ではない。表現は悪いがいわば縄張り外のはず。
そこで生産、供給し、需要は関東地方の東京電力管内に限るとは、一寸ムシが良すぎませんか、と言うのが県民感情、しかも奥会津の水力発電も大半は関東地方へ送電されている。
原発建設地の前提条件としては、海岸に立地する、過疎地である、需要地になるべく近いこと、地域住民の反対運動が少ないだろと思われる等が前提になる。
この結果、東京湾沿岸、神奈川県、房総地区で広大な土地を入手することは、人口密度、立ち退き料、設計震度などの関係から立地困難とされ、需要地に比較的近く、前提条件を満たす候補地として、茨城県、福島県沿岸部が対象となり、調査・検討が行われた。
福島県浜通りを選んだ根拠を探ると、「関東の電気事業と東京電力、電気事業の創始から東京電力50年への軌跡」(東京電力50年史)に次のような記述がある。「原子力発電課を設置し、極めて早い時期に原子力開発への取り組みを始めた東京電力は、その直後から具体的な発電所立地候補地点の選定を進めてきた。世界的にみると、50年代後半には火力発電の大容量化と原油価格の下落によって、火力発電のコストが大幅に低下する見通しがついたため、原子力開発のスローダウン傾向が生じた。しかし、東京電力は、長期的には原子力発電の必要性は明かであるとの認識に立ち、広範囲にわったて立地調査を継続してきた」
「当時、福島県双葉郡では地域振興を目的に工業立地を熱心に模索しており、また福島県としても双葉郡に原子力発電所誘致に積極的であった。こうしたなか、1960年5月、福島県の佐藤善一郎知事から東京電力に対して、双葉郡大熊町と双葉町にまたがる、旧陸軍飛行場及び周辺地域が原子力発電所建設には最適であるとの打診があった。」

この立地条件としては全ての前提条件を満たしており、東京電力は同地点に建設の方針を固め、1960年8月に福島県に対して正式に建設の意志を表示した。
1961年9月19日、大熊町議会が原子力発電所誘致促進決議
1961年10月22日、双葉町議会が原子力発電所誘致決議、東京電力は福島県側からの要請により、用地買収、漁業権交渉を開始し、約310万平方メートルを買収、これは東京ドームが66個分の広さだとのこと。
以上が東京電力社史の一節であり、あくまでも福島県側から積極的は誘致運動の結果であるとしておるが、これは事実で、当時の佐藤善一郎知事は早くから原子力発電の将来について着目しており、県商工労働部に命じて調査に着手していた。

そこで着目されたのが太平洋に面した大熊、双葉両町にまたがる標高35mの台地で、戦時中陸軍飛行隊の飛行場跡地で、終戦後は付近の農家が‘塩焚き’といっていた海水を煮詰めて塩を生産する小屋、何処の海岸砂浜にもこの小屋が乱立していて、戦後しばらくの間、塩が絶対量不足していたのでよく売れた。
これも一時的な現象で、まもなく外国産の塩が輸入されると直ぐに駄目になり、広大な荒れ地として放置されていたのを県が眼を付け、原発立地として最適と判断し、東京電力に意向を打診した。
この旧陸軍飛行場跡地で放置されていた広大な荒れ地があったことが、最大の決め手となって、原発建設のゴーサインとなった。
 |
第28章 原発と福島県
太平洋戦争の日本敗戦後、GHQの指令により過度経済力排除法により全国の電力会社を傘下に収めていた日本発送電が解体、9ブロックに地域電力会社が分割された。しかし、分割された電力会社は資本蓄積も貧弱で復興に必要な電力を供給することも出来ず、発電所新設の投資もままならない状態にあった。
政府としても傾斜生産方式による重点政策も遂行できず、国内の電力需要を増加に対処するため電源開発促進法を制定し、1952年9月16日、国による特殊法人電源開発を設置(資本構成財務大臣66.69%、残りを9電力会社保有)した。
電源開発が手懸けた最初の大事業が佐久間ダム、続いて前述した‘OTM’と呼ばれた奥只見ダム、田子倉ダム、御母衣ダム等大規模な只見地域総合開発を完成させ、他の地域でも次々と水力発電所を完成さ、戦後復興に電力供給面で大いに貢献した。
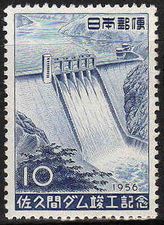 |
 |
高度成長期、大きく伸びる電力需要に合わせて、財務を立て直した電力会社が独自に供給を伸ばしてきた。しかし地域間格差や昼夜の需要のギャップ、50~60?解決の佐久間周波数変換所の連携設備、長距離直流送電、大規模揚水発電所の建設、国内炭鉱産業支援の為の国内炭専用の火力発電所の建設(現在は海外炭を使用)国策的事業を行ってきたが、1997年、特殊法人合理化の中で5ヶ年準備期間をおいて民営化することが閣議決定され、2003年に電源開発法は廃止された。
民営後は東京証券取引所第一部に上場され「JーPOWER」の名称にした。
電源開発初代総裁高崎達之助は時の総理吉田茂の懇請により就任したもので、電源開発には大きく貢献した。
特殊法人電源開発が発足間もない頃、当時工事を行っていた木曽川の丸山ダムを高崎総裁が視察に訪れ、戦前からの方式による旧態然とした工事現場に唖然とし、余りにも人力だけにたよる工法に呆れ、幹部技術者を引き連れアメリカのダム建設現場を視察し、建設機械が縦横に走り回る光景をみせた。
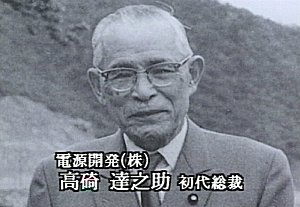
これによりアメリカ式の工法を取り入れた。
佐久間ダム工事では大幅に大型土木建設機械を導入し、十年はかかる難工事とされていたが、日本一の佐久間ダム建設を僅か3年で完成させ、その後のダム建設の先駆けとなった。
次の電力開発は原子力発電に移行する。
火力発電との差異
一般的には「原子力も火力発電でも、蒸気タービンによる発電方式ということでは同じである」しかし、様々な相違がある。
タービンを回す蒸気が原子力発電では約284度、6.8MPa(メガパスカル)であり、石炭化両区発電では蒸気の約600度、25MPaよりも温度、圧力が低く設計されている。その理由は核燃料棒に使用されているジルニコウムが比較的高温に弱いために一次冷却水を高温には出来ないためで、また、火力発電所では超臨界流体である超臨界蒸気が使用されている。
超臨界蒸気とは、液体の性質と気体の性質を持った非常に濃厚な蒸
気であり、熱を効率よく運ぶことが出来るが高温高圧状態が必要なため、原子力発電ではこれを利用できない。これらの理由から一般的に火力発電所の熱効率は47%程度であるのに対し、原子力発電における熱効率は約30%程度にすぎない。
 |
| (1942年世界最初の原子炉実験) |
世界の原子力発電への途
1930年代に人類は核エネルギーの存在を発見し、1942年、シカゴ大学のエンリコ・フェルム教授が、実験炉で原子力発電の原理となる核分裂の連鎖反応を行うことに成功、1945年にアメリカで核分裂反応を利用した原子爆弾を開発され、広島、長崎に投下、史上最悪の悲劇をもたらした。
次に実用化されたのが空気を必要としない動力源として潜水艦の動力として活用され、原爆開発から9年後の1954年最初の原子力潜水艦が進水し、原子力は軍事用として開発が進んだ。
民需としての原子力は、史上初の原子力発電は、1951年アメリカで実験炉、EBRー1から始まる。EBRー1の当初の発電量は1kw弱で、200wの電球4個を発光させた。
本格的に原子力発電への途が開かれたのは1953年12月8日、アイゼンハワー米大統領が国連総会で行った原子力平和利用に関する提案がその起点となった。
これは核兵器開発だけに力を注ぎ、核兵器の怖ろしさを感じていた核先進国に対して原子力発電という平和利用に向けさせる大きな政策転換がった。
1959年に原子力エネルギー法が修正され、アメリカ原子力委員会が原子力開発の推進と規制の療法を担当することになった。
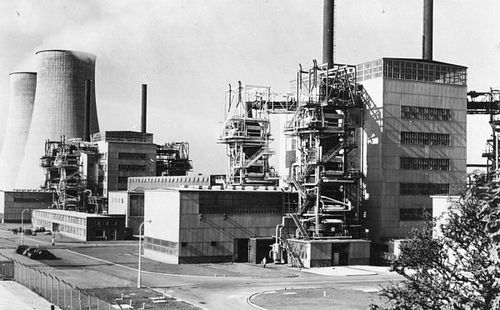 |
| (コールダーホール1号炉) |
原子力発電を実用化したのは国家を挙げて開発に邁進したソ連の方が先で、1954年6月オブニンスク発電所が営業運転を始めた。また同年原子力潜水艦を就航させ、米ソ対立が激化、熾烈な核開発競争が始まり、世界は二極分解、対立構造の世界となって、西側(アメリカを中心とした資本主義的自由経済諸国)、東側(ソ連邦を中心とした社会主義統制経済諸国)と僅かな中立国(第三勢力)に色分けされた。
西側で最初の商用原子力発電は、イギリスのコールダーホール1号炉である。運転開始は1956年10月17日、出力6万kW、炉の形式は黒鉛減速炭酸ガス炉(GCR)であった。
アメリカでは、シッビングボート発電所が最初で、1957年12月18日、操業開始、出力10万kW、炉の形式は加圧水型原子炉(PWR)であった。
フランスでは、1964年2月に運転開始、シノンA1号炉、出力8万4千kW、炉の形式はGCRであった。
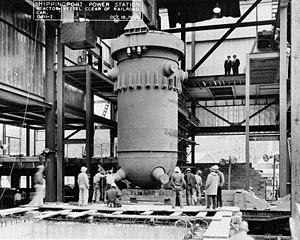 |
| (コールダーホール1号炉据え付け工事) |
1957年、欧州共同体(EEC)諸国により欧州原子力共同体(ユートラ)が発足し、同年国際原子力機関(IAEA)も発足した。
原子力発電が発足した初期には、夢の発電と喧伝され、「Too cheap To meter」と言われた。この意味は「原子力で発電すると、余りにも安価で計量する必要が無い」という意味で、夢の発電方法だとされ、世界の各国は原子力発電の導入を急がねば世界の趨勢から取り残されるとの危機感生じた。
しかし現実はそう甘くはなかった。厳重なバックアップ装置や何重もの安全装置が必要であり、その建設費が膨大であり、かつ検査や点検に非常に時間がかかる。
原子力発電が他の発電方法に比べ設備費の割合が非常に高く、必ずしも安価で理想的発電方法とはいえない面もあることに気付いていたが、趨勢を換えることは出来ず、原子力発電所建設は国家の威信をかけ世界に拡がっていった。
1977年、アメリカは民主党のジミー・カーターが大統領に就任すると、カーター政権は1977年核拡散防止を目的としてプルトニュウムの利用の凍結する政策を発表した。これによりアメリカでは高速増殖炉の開発が中止され、核燃料サイクル開発を断念したことになる。これ以降核燃料は再処理されずワンスルーとなった。
このような世界情勢の中でわが国の原発は54基を数え、世界第三位の原発を保有国になっていた。

1979年3月28日、スリーマイル島原子力発電所事故発生した。この事故は世界の原子力業界に大きな衝撃を与え、原子力の新規受注が途絶えた。
1986年、人類史上最悪の原発事故、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生、自国ばかりでなく、近隣諸国、ヨーロッパ諸国が被害を被った。
このようなこれらの事故を傍観するだけで、我が身を省みず「安全神話」だけが一人歩きしていたわが国で12011年3月11日、地震、大津波、それに続く福島第一原発事故があり、大きな打撃を受け、4年以上経過しても回復にはほど遠い状態にあり、被害をもろに受けた皆さんと共に1日でも早い回復の日を祈りながら、これまでの経過を考察していきたい。
日本の原子力政策
戦前からわが国のサイクロトロンの研究開発は世界最先端の研究を行っており、研究の中心であった理研工学の仁科芳雄博士が中心となりグループには湯川博士、朝永博士のような戦後ノーベル賞を受賞した逸材、輩出している。
1945年8月15日ポツダム宣言受諾、敗戦国になり連合軍の占領下でオキャバイトジャパンとなり、当然ながら原子力の研究は全て禁止になって研究施設のサイラトロンその他全ての研究施設は全て東京湾に投棄、または破棄され、占領下にあった7年間はまったくの冬の時代であった。
1952年4月、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)が締結され、念願の独立を果たした。
独立をもって原子力研究も解禁されたが、広島、長崎の被爆が余りにも大きな衝撃であったため、原子力研究への意欲を失わせてしまい、わが国の原子研究平和利用の面でも世界水準からも大きく遅れをとってしまった。
1952年7月、日本学術会議において茅誠司、伏見康治の両東大教授を中心としたメンバーが「国際的に遅れを取った日本の原子力研究の巻き返し」をどうするかという議案が提出したが、この提案に対し被爆地であった広島大学、長崎大学から核研究が兵器開発に繋がるのではないかとの懸念が表明され、全国的に議論が巻き起こり、そのため日本学術会議内に文系、理系、法学等幅広く各部門の専門家が参加する「第39委員会」を設置、議論を重ねたが、なかなか議論を煮詰めることができなかった。
この動きとは別に政界では、元国務大臣であった後藤文夫代議士を中心とした政官界有志による原子力政策推進の動きがあり、1952年、財団法人電力経済研究所が設立された。
世界の趨勢としては、1953年12月、国連総会の席上、アイゼンハワー米大統領が行った演説の中で「平和のための原子力」を提案。これは当時、原子力発電はソ連が世界初の原子力発電を行い、核爆弾競争でも水素爆弾を開発したのもソ連でしたから、核開発競争ではソ連が1歩リードしており、アメリカは焦っていたので、演説の骨子は、国際的な枠組みで核の燃料を保管・監視し、必要に応じて各国に分け与えよう、とする内容であった。この構想は若干の修正があったが、国際原子力機関(IAEA)として実現し、この機関は現在でもイランや北朝鮮の査察問題で報じられているように活躍しております。
この演説を契機としてわが国でも「新しい時代に乗り遅れては大変だ」との気運が政財界に高まり、アイゼンハワー大統領演説から3ヶ月後には自由党・改進党・日本自由党の共同提案、その中心は当時改進党に所属して青年将校ともて囃されていた若き日の中曽根康弘、稲葉修、斎藤憲三、川崎秀二、前田正男氏等の議員が結束して原子力研究開発予算を国会に提出した。当時、与党は衆院で過半数の議席を持たず、どうしても予算案を通過させたい吉田内閣は改進党提出である原子力研究開発予算を抱き合わせで通過させた。
水力発電の只見川総合開発で福島案、新潟案、東京電力案が複雑に交差し、てんやわんやの大騒ぎをしている同時期に原子力発電の可能性をさぐる動きがあったのですから如何に電力不足が深刻であったかが推察されます。
そのときの予算請求額は予算2億3500万円、ウラン235に因んだ予算額請求であるから、予算額だけが一人歩きする未明の世界であったのかもしれない。
突然の予算成立に主管官庁である通産省は当惑したが、1954年5月に、内閣の諮問機関として「原子力平和利用準備委員会」が設置したが、これに猛反発したのが日本学術会議で、原子力研究・開発が政治主導になることに危機感を強め、当時の日本では原子炉の建設は時期尚早と批判したが、電力の絶対量不足に対応するためには絶対必要とる政・官・財に勢力に屈し、第39委員会は慎重意見が相次いだが公聴会の意見を集約し、原子力利用は日本国民による民主的、かつ研究成果を公開することを条件にしてその運営方針を了承した。
先に通過した原子力予算の使い道として、小型原子炉の建設戸放射能障害の研究の二項目に絞って原子利力平和利用を目標として設定した。
その頃、国際的な関心事はロシア、イギリスの実用的な動力炉の成果が注目され、同時に米ソ対立による世界の二極化が明らかとなって、わが国は防共の砦としての役割を担わされ、否応なしに米ソ対立の最前線に立たされてしまった。
こうなるとアメリカとしてはわが国が1日でも早く経済復興し西側諸国の一員として活躍できるようにと期待するようになり、電力回復に多大な期待を寄せ、原子炉建設を全面的にバックアップすることを申し出、燃料供給から炉の設計・建設まで請け負うことを約束した。ところが1954年3月、ビキニ環礁での水爆実験、第五福竜丸被爆事件となり、世論は一気に反原発となって、反原発運動が全国的になって広まった。
そこで、活躍したのがマスコミ界の実力者で読売新聞の社主、しかも現職の国会議員であった正力松太郎氏で、原子力推進の一大キャンペーンを行い、アメリカの原子力平和利用使節団(団長・ジョン・ホプキンス、ゼネラル・ダイナミックス社長)を日本に招いて各地で講演を開催、読売新聞がこれを全国に報道した。
またCIAと組み原子力平和博覧会を日本各地で開催した。この動きに反発していた学術会議や被曝協等も原子力利用が日本の戦後復興には電力確保が絶対の命題であることから次第に軟化し協調するようになった。
1955年自民・社会の両党は協力して、「原子力基本法」「原子力委員会設置法」「原子力局設置法」といわれる原子力三原則といわれる三法案がスピード可決され、政府は『原子力平和利用準備委員会』を解消し、「原子力委員会」を発足させた。
 |
| (正力松太郎氏) |
1、研究の民主的な運営
2、日本国民の自主的運営
3、一切の情報の完全公開
そして基本法成立を受けて1956年1月1日、原子力委員会が設置され、初代委員長に正力松太郎氏が就任、原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに1957年5月には新設された科学技術庁の初代長官にも就任、「原子力の平和利用」および「原子力の国際協力」を基本として、日本として従来の研究テーマであった「アイソトープ利用の実用化」に加えて「5年以内に原子力発電を実現させる」という目標を掲げた。
さらに正力委員長は目標達成には産業界の協力が不可欠として「原子力産業会議」を開催し、2月に首相官邸に71名の財界代表を招いて広く周知し、さらに3月には日本工業クラブに「日本原子力産業会」が発足、初代会長は、電気事業連合会の菅禮之助氏(東京電力会長)が就任、原子力発電所建設への路は開けた。
一方、動力としての濃縮ウラン燃料はアメリカから貸与されることになり、保管場所および研究所の設置が急務となり、受け入れ機関として1954年7月に財団法人日本原子力研究所が急遽発足し、研究所の候補地を求めたところ、当時の国内の世論は原子力歓迎ムードで、数多くの候補地があったが、最終的に茨城県東海村が選ばれた。
1956年に日本原子力研究所、現・独立行政法人研究開発機構が特殊法人として設立され研究所が茨城県東海村に設置され、これ以降、東海村はわが国の原子力研究の中心となった。
当初は原子力基礎研究を優先すべきとの主張があったが、先ずは電力需要を鑑み、原子炉力炉建設をして運転しながら研究をする同時進行型を決め、1957年12月に原子力委員会は1975年までに、700万kwの原子炉稼働する目標を掲げた。
1957年11月1日には、電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発公社が共同で最初の原子力発電が行われたのは1963年10月26日、東海村に建設された実験炉であるJPDRが臨界に達し初発電を行い、ここにわが国初の原子の灯がともったことになった。
かくしてわが国にも原子力発電の路が開かれ、日本原子力発電株式会社(民間出資8割)が誕生し、日本原電東海原子力発電所(日本初商用原子炉)にはイギリス製のコールダーホール改良型炉の導入が決まった。
ただし性能が悪く、採算面でも火力発電に劣るとの検証結果があり、更には耐震性にも問題ありと検証されたが、原子力委員会と財界の牽引力は大きく、原子力政策が大きく前進したのは中曽根康弘代議士が科学庁長官に就任してから「新・長期計画20年」が発表され、最初の10年間で商用原発の発電規模は3基100万kw、後の10年で火力発電量の30%程度(650~850万kw)、多分20基程度を予定していたのでしょう。
ただし、この構想は中曽根長官の独創であって正式な路線ではなかった。このような時、アメリカ側から甘い囁きがあった。アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE社)から魅力的な価格の軽水炉と「ターンキー契約」の申し出である。これは最初に固定化された契約金額が提示され、契約すると建造から臨界までの作業は全て契約者であるGE社が全てを請負、その後事業者はマニュアルに従って運用するだけという契約方式で、自力で建設・臨界までの技術がなかったわが国原子力業界は飛びついた。
原子力発電の路が開かれれば、あとは建設場所の選定になる。
原電は東海発電所に続く第二号炉として、1961年福井県敦賀市を選び、建造はGE・東芝・日立のグループが請け負う契約を結んだ。契約者は関西電力であった。
 |
| (東海原子力発電所) |
1960年代、高度経済成長とともに国内の電力消費は増大し、エネルギーの活路を原子力発電に求めるのは世界的な趨勢であった。
わが国でも当然原子力発電への関心が高く、世界唯一の原爆被災国として躊躇、若しくは明らかな反対勢力もあったが、政官と電力会社は原発導入に積極的であった。
軽水炉の導入も検討されたが、当時まだ実績が十分ではなかったため、世界初の商用発電炉であるイギリスで開発された黒鉛減速ガス冷却炉(コルダーホール型)を輸入することになった。
しかし、地震のないイギリスでの設計と、地震多発のわが国では当然耐震性が求められ、設計を根本的に見直す必要があった。
炉心を構成しているのは、およそ1600tにも及ぶ黒鉛ブロック(減速材)で、イギリス製の黒鉛の断面は正四角だったが、この黒鉛ブロックを正六角形に改め、更に凹凸でかみ合わせることにより耐震性を大幅にアップさせ、関東大震災の3倍の震度でも耐えられるように改良した。
これにはイギリス側は機密を理由に資料を示さず、工事にも協力しなかったため、わが国の技術者は原子炉理論が良く分からず相当に苦労したらしい。
その後1960年1月着工、1965年5月4日、初臨界に達し、日本初の商業原子炉となった。
その後27年間営業運転を経て、1998年3月31日営業運転を停止、廃炉になった。これは黒鉛炉特有の経済性の悪さが理由で、隣にある第二東海原子力発電所は同じ規模で100万kwであったのに対し、第一原発は16万kwに過ぎなかった。
その計画から日本発の原子炉解体に至まで、この原子炉で得られた数々のデータは貴重な財産となっている。
福島県の歴史
1950年末頃の福島県は高度経済成長に乗り遅れ、産業近代化率も全国平均270%と比較して126%と低位であった。このため福島県は産業誘致のため電源開発に努力して只見川・阿賀野川総合地域開発に成功したが、地域の雇用には繋がらず、浜通り方面ではエネルギー革命で、安い原油が輸入されるようになり、石炭も豪州から安価な石炭が大量に輸入されるようになると、常磐炭田は急速に斜陽となり1961年42の炭鉱で248萬トンの生産高があったが急速に落ち込んでいった。
常磐炭確保の為に常磐共同火力発電所が設立され、1971年には72万kwの出力で操業していたが、やがて安価な輸入炭に押されるようになり、何か別のエネルギー革命を模索していた。
但し、これは昭和30年代のことであり、その後は有力企業の誘致に成功し、2011年3月11日の東日本大震災、福島第一原発事故以前では世界の国の国内総生産(GDP)と福島県県内総生産を比較しても世界の国別70位以内にランクインしており、県単独で世界の過半数の国と同等あるいはそれ以上の経済規模を有していることになる。
第一次産業では米作、果物の宝庫であり、水産物では世界的な漁場である常磐沖、相馬沖を有し、首都圏へ大量の水産物を出荷している。
第二次産業では首都圏に隣接する至便性のため首都圏より福島県に進出企業が多く製造品出荷額では宮城県を抑えて東北一の工業県である。
会津若松市一帯は半導体、郡山市一帯はプリント基板関連、電子部品、福島市一帯電子機器、いわき市周辺では電子機器、化学製品、自動車エンジン工場群があり福島県一の工業地帯を形成している。

第二次製品出荷額でも1位はいわき市で唯一1兆円を越えている。2位郡山市9千億円代、3位福島市、4位会津若松市、5位白河市と常連が続く。
特にいわき市が突出しているのは平市周辺5市7町村と双葉郡から分離併合した2町村でいわき市を形成、福島県内で最大の人口(仙台市に次いで東北地方で第二位)、面積は東北地歩第三位、小名浜港の国際港化に伴い小名浜地区、勿来地区に多くの企業、生産工場が首都圏から進出し雇用を生み出し繁栄をもたらした。
5隣接する双葉郡では第一次産業の出荷額で浪江町が19位にあるが、第二次産業では双葉郡全体が原発以外は何もない状態で低位に甘んじている。
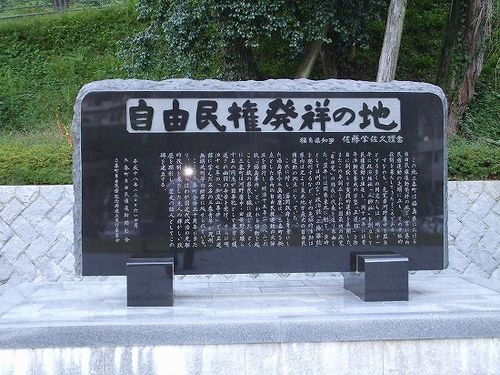 |

福島県政
明治新政府樹立後、権令として中央政府から派遣された官選権令が赴任。
初代権令 清岡公張 明治2年7月20日
3代目から権令が県令と呼称が代わった(明治5年10月23日)
5代 県令三島通庸の高圧的施策に反抗した歴史上名高い「福島事件」発生
7代 県令から知事と呼称変更
41代 石井政一知事の時に終戦(1945年8月15日)

43代 石原幹市郎知事(1946年~1947年)
44代 阿賀正美知事(1947年、在任1ヶ月で公選知事に代わる)
歴代の権令、県令、知事は内務省高級官僚から選ばれ、その大半は西国出身で、初期の頃は意識して薩長出を任命したらしく戊辰戦争の影響が色濃く出て「福島事件」がある。
一寸触れてみる、5代県令三島通庸は薩摩(鹿児島県)出身、戊申戦争にも参加しており、白河以北一山百文の意識が強く、権令として悪政、暴政の限りを尽くし県民を苦しめた。これに反抗したのが河野広中(三春藩郷士)、三春藩で100石取りの郷士であったが、家業が呉服商・造り酒屋。・魚卸商を営む豪商であったので、幼いときから学問を授けられた。

戊辰戦争では、三春藩は当初奥羽越列藩同盟に加盟していたが、河野広中は兄と語らい明治政府に帰順を申し出、三春藩も帰順した後、土佐藩兵とともに二本松藩攻略、会津戦争でも官軍側についた。
その後は自由民権運動に参加し、民権運動の先駆けとなった。
同時に国会の開設、福島県議会開会の準備に奔走した。
1882年(明治15年)県令三島通庸の暴政を許しがたく、藩閥専制政府に抗議するために連判状を同志と取り交わしたため、内乱陰謀の容疑で明治15年12月に検挙され7年の刑を宣告され、刑に服した。
出獄後は第一回衆議院議員性依拠に出馬し当選、国会議員として活躍した。
最初の公選知事は43代知事を務めた石原幹市郎氏が知事選に立候補し当選した。
初代公選知事も石原幹市郎が立候補し当選、官選、公選に2期を努めた。
○石原幹市郎:岡山県出身、東京帝大法卒、高文合格、内務省入省、警察畑を歴任、その後各県の経済面の課長、部長を経て東京都経済局長時代、食糧調達に辣腕を振るった。その手腕を買われ、終戦後の1946年、食糧生産県である福島県知事に就任、前任者であった42代増田甲子七知事を北海道知事に送り、首都圏の食糧確保が目的の人事だと言われている。確かに石原知事は食糧増産に尽力している。1期勤めたが、公選制に替わり、初代公選知事となり、食糧増産は勿論、その頃から調査が始まった只見川電源開発の誘致に辣腕を振るった。
知事引退後は参議院議員補欠選挙で福島選挙区から民主自由党から立候補し当選。岸改造内閣で国家公安委員長・自治庁長官に任じ、第二次岸内閣では自治大臣で入閣した。
○45代大竹作磨知事:公選二代目だが石原知事は官選知事であったから、純粋に公選であるのは、大竹知事が初代であると言える。
福島県耶麻郡北塩原村で中農の長男として生まれ(1895年)。
地元の高等小学校卒業後、家業を手伝っていたが、鎌で左手の人差し指を誤って切断、農業を断念、その後村の村会議員に当選、1931年福島県会議員になり、4期勤めた。第二次大戦中、東条首相が定めた政党解散、大政翼賛会に反対し、憲兵隊に逮捕、拘束された。
1950年、自由党から知事選挙に立候補し、2期連続7年間46、47代の知事を務めた。
只見特定地域総合開発計画に基づく只見川開発に尽力し、本流案採用を県民挙げての願いを込めて先頭にたって、分流案の新潟県岡田正平知事と鋭く対立、中央政界、吉田内閣を巻き込んだ政争となったが、吉田茂首相の調停により本流案を主とし、分流案にも配慮した案で決着し、只見特定地域総合開発は着工された。
それに続く、田子倉ダム建設でダム予定地の湖底に沈む村落の補償金問題がこじれ、泥沼の闘争となったが、県知事が矢面に立ち、国都電源開発側が土地収容法の適用を主張したのに対し、これを否定、農民側に対しては自分も同じ農民であるとして低姿勢で臨んだためやがて胸襟を開き妥協にこぎ着けた。
次のダム問題では、地元住民でない、補償金目当てのよそ者が多数ダム予定地に小屋を建て、住みつき大問題となった。この人達は暴力団組員や韓国人が多く、当時わが国は占領下にあり、韓国人は戦勝国民として特権を与えられており、その対応には苦慮した。
この時も大竹知事が先頭に立って交渉を行い、なんとか妥協したが、最後に残った2軒だけは交渉に応ぜず、土地収用法の適用があった。
只見特定総合開発計画が成功したのは、大竹知事の奮闘が最大の功績になる。
知事引退後、1960年から1963年まで衆議院議員を務めた。
1976年7月16日、脳卒中と肺炎を併発して81歳で逝去。
柳津町に銅像がある。
○48代 佐藤善一郎:福島市で生まれる(1898年)
政治家としては1937年旧清水町町長に就任、福島県議を務めたが、戦後公職追放されたため、1952年福島県経済連の初代会長に就任、財政を立て直した。この手腕を買われ、衆議院議員選挙で2期連続当選。
1957年、自民党の公認を得られず農業団体、社会党、労働団体と政策協定を結大竹作磨知事が1957年に引退するに当たり、後任知事に推薦したのが厚生次官であった斉藤氏で自民党公認として福島県知事選に立候補した。
ところがもう一人自民党所属で現職の国会議員であった佐藤善一郎氏が立候補、当然同党で二人の公認はあり得ず、佐藤候補はヤムを得ず社会党推薦で県知事選を闘い当選した。
福島県知事選に出馬、当選。2期目、1961年、自民党、社会党、民社党推薦と労働、農業、商工など各団体の指示を得て再選された。
農業、工業、観光に均衡ある発展を願う政策をとっていた。この頃、原子力発電所の建設が持ち上がり、双葉郡に誘致することを決めたが、計画が具体化される前に病に倒れ、在任中の1964年、急性肝臓萎縮症で逝去。享年64歳。
○50代 木村守江:石城郡四倉町生まれ(1900年 旧制磐城中学、慶応義塾大医学部卒、四倉町で代々開業医(木村医院))
1950年、第二回参議院議員通常選挙に福島選挙区から立候補、当選、参議院議員を1期勤めた後、衆議院に鞍替えし、1958年第28回衆議院議員総選挙で旧福島3区から立候補、自民党公認、当選。3期連続当選後、1964年、佐藤知事が現職で急逝したため、その後任を選ぶ選挙に出馬した当選、福島県知事となる。以後4期連続して知事に就任。この間全国知事会会長にも就任している。
知事として県内のインフラ整備には重点を置き、地元いわき市を周辺市町村の大合併を行い、当時では全国最大の面積を誇るいわき市を誕生させた。
小名浜を中心とする周辺各地に首都圏から企業誘致に力を注ぎ、大工業地帯を建設した。
前任者、佐藤知事が着手した双葉郡への原子力発電所建設計画にも積極的に活動し、東京電力側と度々接触し、旧知の東電木川田一隆社長は福島県出身で木村知事とも旧知であり、計画が具体的になる前から接触していた。
浪江・小高の原子力発電所建設計画はこの頃よりあり、本格的に誘致に動いたのは木村知事が最初で、1968年1月5日のテレビの年頭挨拶でこの件について抱負を述べている。
1976年8月6日、土地開発に絡む収賄罪容疑で逮捕され、8月11日 知事辞任 1979年1月、仙台高裁で懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の判決が確定し、公選知事として初めて収賄で有罪になった。
晩年は自宅でゴルフや登山に親しみ、1996年11月3日老衰で死去、96歳没。
○54代 松平勇雄:会津藩主松平容保の次男の松平健雄(伊佐須美神社宮司]の次男として大沼郡会津高田町で生まれる(1907年)。松平容保の孫にあたる。
1933年、早稲田大学商学部卒、三菱商事に入社し商社員として活躍していたが、1951年2月12日の参議院議員補欠選挙に福島地方区から立候補し、当選、1988年9月18日までの3期12年間務めた。
その間、第一次佐藤栄作内閣の行政管理庁長官として初入閣した。
1976年9月19日、木村守江知事が贈賄事件で逮捕され、知事を辞任したため行われた知事選に立候補して当選、1988年9月18日まで3期12年務めた。
任期中は図書館、美術館、博物館等の文化施設面に力を入れ「文化の知事」と言われた。
1983年、勲一等旭日大綬章を受賞した。
2006年4月1日、老衰のため自宅(東京都世田谷区野毛)死去。98歳没。
殿様の末裔らしく、常に笑みを浮かべ「松平スマイル」と呼ばれ、温厚、高潔な人物だったと言われている。
○57代 佐藤栄佐久:1934年、郡山市生まれ、安積高校、東京大学法学部卒。
1983年の第13回 参議院議員通常選挙に自由民主党公認で福島県選挙区から出馬、初当選を果たした。
1988年、松平勇雄知事が引退に伴う福島県知事選挙に福島県選出の有力議員 伊東正義、斉藤邦吉両議員の支援を受け、参議院議員を辞職して出馬、当選を果たし、以降4回連続当選したが、5期目の2006年9月、実弟が関与したと言われている汚職事件で知事自身にも捜査の手が伸び、福島県議会の承認を得て職を辞した。
後日、自身も収賄の容疑で逮捕され、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の判決であった。二審の東京高裁の判決では懲役2年、執行猶予4年となった。
佐藤知事が取り調べを受けていた同じ2006年には11月15日和歌山県知事木村良樹、12月8日宮崎県知事安藤忠恕が同じ官製談合事件で逮捕起訴された。
僅か3ヶ月の間に、全く関連のない官製談合事件が起き、起訴されたことに何か裏を感じるは当然で、この背景に興味があり、より詳細な資料を集めてから報じたいと思い、福島原発に関する様々の事件、事象と絡ませて考察します。
佐藤栄佐久前知事はクリーンさを売り物にして最長5期をつとめた名物知事で県民に信頼されていた。
一方、国が推進する原子力発電のプルサーマル計画に絶対反対、事実上これを中止させた。地方主権を主張して中央政府に反旗を翻すなど、中央政界、電力、ゼネコンなどの有力企業にとっては邪魔な、目障りな人物であったことは確かだ。
判決当時は佐藤知事一人の闘争の様相で世間一般からは余り注目されなかったが、この判決の中身を詳細に検討すると、どうしてこれが有罪の根拠になるのだと法学を志す者なら一読して考える必要がある。
そして村木裁判にみる検察の怖ろしさ、原発安全検査のデータ改竄問題、福島第一原発事故における「安全神話」が如何に脆かったのかが明るみに出てきた現在、この裁判の本質を考察する必要がある。(第13章 福島県知事の叛旗、参照)
○62代 佐藤雄平:南会津郡下郷村生まれ(1947年)
田島高校、神奈川大学経済学部卒 卒業後叔父である政界の「黄門様」渡部恒三議員の秘書を長く務める。
1996年第18回参議院議員通常選挙に無所属(民主、社会民主、公明党推薦)福島県選挙区で出馬、初当選、2004年の第20回参議院議員通常選挙で再選。
2006年、佐藤栄佐久知事の辞任に伴う福島県知事選挙に参議院議員を辞して、出馬し、自由民主党が擁立した森雅子(弁護士)を破り当選した。
森候補は当初、民主党公認で出馬を予定していたが、告示直前自民党から出馬することを決めたため、民主党は急遽佐藤雄平氏を擁立したらしい。
2010年10月、2期目は政党からの推薦を受けなかったが、民主、社民両党の支援を受け、自民党もプルサーマル計画を受け入れるなら支援するとの確約でき、共産党公認の佐藤克朗氏を大差で破って再選した。
長年に渡って福島県を振り回してきたプルサーマル計画とは何だったのか。
原子力政策は国策である、とする政府、電力確保は企業にとっては死活問題とする実業界、何としても電力増強が絶対的命題である電力会社、利益確保を願う地元双葉郡、福島県議会、安全面で懐疑的にならざるを得なかった県知事。
2011年3月11日 以降、原発問題はどうなるのか、もう一度検証してみたい。
○64代、内堀雅雄、長野県生まれ、長野高校、東大経済学部、自治省入省、福井県庁出向、大蔵省出向・主計局法規課課長補佐、福島県庁出向・企画調整部部長、福島県副知事。
| 公選知事(1代から44代までは官選知事) | ||||
| 代 | 氏名 | 期間 | 出身 | 期 |
| 45代 | 石原幹市郎 | 1947年04月12日~1949年11月30日 | 岡山県 | 1期 |
| 46代 | 大竹作磨 | 1950年01月28日~1954年01月27日 | 福島県 | 1期 |
| 47代 | 1954年01月27日~1957年07月25日 | 2期 | ||
| 48代 | 佐藤善一郎 | 1957年08月25日~1961年08月24日 | 福島県 | 1期 |
| 49代 | 1961年08月25日~1964年03月23日 | 2期 | ||
| 50代 | 木村守江 | 1964年05月16日~1968年05月15日 | 福島県 | 1期 |
| 51代 | 1968年05月16日~1972年05月15日 | 2期 | ||
| 52代 | 1972年05月16日~1976年05月15日 | 3期 | ||
| 53代 | 1976年05月16日~1976年08月11日 | 4期 | ||
| 54代 | 松平勇雄 | 1976年09月19日~1980年09月18日 | 福島県 | 1期 |
| 55代 | 1980年09月19日~1984年09月18日 | 2期 | ||
| 56代 | 1984年09月19日~1988年09月18日 | 3期 | ||
| 57代 | 佐藤栄佐久 | 1988年09月19日~1992年09月18日 | 福島県 | 1期 |
| 58代 | 1988年09月19日~1992年09月18日 | 2期 | ||
| 59代 | 1996年09月19日~2000年09月18日 | 3期 | ||
| 60代 | 2000年09月19日~2004年09月18日 | 4期 | ||
| 61代 | 2004年09月19日~2006年09月28日 | 5期 | ||
| 62代 | 佐藤雄平 | 2006年11月12日~2010年11月11日 | 福島県 | 1期 |
| 63代 | 2010年11月12日~2014年10月30日 | 2期 | ||
| 64代 | 内堀雅雄 | 2014年11月12日~ | 長野県 | 1期 |
原発建設へ始動
右肩上がりの高度成長期、電力消費も当然右肩上がり、旺盛な需要に生産は追いつかない、発電所建設が追いつかない、しかも水力発電は国内の適切な建設地はもう飽和状態、火力発電は世界的な地球温暖化問題で二酸化炭素は敵視され、それを排出する火力発電所の建設も住民運動の激化で進まない。
風力発電、太陽光発電、地熱発電等、最近脚光を浴びているが、当時は全く問題にならない位に発電単価は高過ぎ性能も悪かった。
残るは原子力発電だけ、発電単価は遙かに安価、空気を汚さない、騒音もなし、煤煙もなし、理想的なクリーンエネルギー等、これが原子力発電のうたい文句で、当然国策として原子力発電推進プロジェクトとして通産省主導で動きだし、国内最大の電力消費地をエリアとする東京電力も増大する電力需要に対応して、原子力発電に関心を持つのは当然だ。
ところが記録によるとアイゼンハワー米大統領が「平和の為の原子力」が国連で行われて頃(1954年)、後に東電社長として原子力発電を推進した木川田一隆氏は当時まだ副社長であったが「原爆の悲惨な洗礼を受けた日本人が、あんな悪魔のような代物を受け入れてはならない」と語ったことが記録されている。
この米大統領の国連演説があった頃からわが国政府内では原子力推進の議員が活発に動き出し、1955年読売新聞社社主であり衆議院議員で正力松太郎を中心とした議員連盟が導入推進運動を始め、一方、改進党の若手議員であった中曽根康弘議員、川崎秀二議員党数名の議員が連盟で原子力推進の法案を提出、予算を要求した。原子力開発の主導権争いが起こり日本発送電を分割民営化した9電力を所管する通産省と電源開発公社の間で熾烈な争いがあった。
この件に関しては調停があり、国・民間両者の出資で原子力発電導入のパイロット機関として日本原子力発電株式会社を設立した。
| 1957年12月05日 | 日本原子力発電株式会社は茨城県東海村の海岸段丘上の空き地を原子力発電所敷地の候補地と決定、土地取得にかかった。 |
| 1959年03月16日 | 東海発電所原子炉設置許可申請 |
| 1959年12月14日 | 東海発電所原子炉設置許可 |
| 1959年12月22日 | 東海発電所の購入契約を日本原子力発電株式会社と英国GEC社と締結 |
| 1960年01月16日 | 東海発電所建設着工 |
| 1966年07月25日 | 東海発電所営業運転開始 |
日本原子力発電の初仕事は高度経済成長と共に電力需要急増荷対処するための原子力発電テストケースとして、茨城県東海村の海岸に日本発の商業用黒鉛炉かつ商業用原子力発電所を建設、炉型は英国製の黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉(GCR)で、これにわが国独自に耐震強度の増強など、英国にはない設計をやり直し、日本独自の改良を加えた原子炉を建設し、1960年1月に着工し、1965年5月4日、臨界に達し、日本初の商業用原子炉となった。その後27年間営業運転をしたが、1998年3月31日、営業運転停止、現在日本初の廃炉工事が進行中である。
| 1998年03月31日 | 営業運転終了 |
| 2001年03月 | 燃料搬出完了 |
| 2001年10月04日 | 解体計画書提出 |
| 2001年12月 | 解体作業開始、使用済み燃料冷却のプール洗浄 |
| 2003年 | タービン建屋内の機器撤去、タービン発電機解体 |
| 2004年11月 | 燃料取換機、建屋の解体開始 |
| 2006年06月 | 熱交換機撤去工事開始 現在は周辺機器及び建屋の撤去工事中 |
| 2014年 | 原子炉解体工事開始 |
廃止措置工程
原子炉領域解体前工程(16年間)1998~2013年
原子炉領域解体撤去 (5.5年間)2014~2019年
原子炉建屋解体撤去 (1.5年間)2019~2020年
原子炉領域以外の撤去(18.3年間)2001~2020年
放射性廃棄物の短期処理(23年間)1998~2020年
原発廃止後の高レベル放射性廃棄物の恒久的処理・隔離・管理に関しては未定であり、今後何万年単位での工程になる。
原発建設へ始動
政府内で原子力に関する動きがあり、日本原子力発電会社設立構想があった頃、東京電力内でも原子力発電の可能性を探るべく社内に原子力発電課が発足した(1955)課が新設されたと言っても具体的な動きはなく、もっぱら原子力先進国から文献を取り寄せ読み耽る程度だった。
この頃、東京電力内部で従来の水主火従の関係から転換し、水力と火力が均衡し、やがて火力は主、水力が従になりつつあった頃で、火力も石炭が殆どで、石油を燃やそうなんて内部でやっと検討しだした頃で、ガス(LPG)は考えてもいなかった時代だ。だから原子力の方が石油やLPGよりも早い時期に検討されたことになる。
1955年11月1日、東京電力は副社長であった木川田一隆が社長に昇進し、社長室直々に原子力発電課を1956年6月に新設、原発建設へとシフトした。原発に対して関心が無い、あるいは反原発であった木川田社長の内心の変化は判らないが、原子力発電を肯定する立場になり、以降は積極的に活動することになる。
社長命令により原発建設のための特別プロジェクトチームが編成された。
この頃、1955年8月にスイスのジュネーブで「第一回ジュネーブ会議」が開催され、当時核先進国とされたアメリカ、イギリス、フランス等の国々が研究成果を披露した。
この会議でBWRの原型になるアルゴンヌ国立研究所のEBWRの他、PWRやGCRも紹介されたが、それ以上重要だったのは、各種の炉の物理学的見地、原子炉設計に関する各種データが公開されたことに関心は集まった。
わが国が占領されていた時代、GHQの指令により原子力研究施設は完全に破壊され、東京湾に遺棄、かつ全ての研究機関は閉鎖され、研究することも全面禁止になっていたから、原子力に関しては完全に空白時代になった。
したがって、「ジュネーブ会議」で公開された資料は大変価値あるモノで、膨大な資料が新設の原子力発電課に持ち込まれ、若手技術者で語学に堪能な社員が手分けして翻訳し、それを分類して分担を決め、政策、経済性、安全性、設計、計画放射線遮蔽、計装制御、廃棄物等に区分し、それぞれが研究を進めた。
原子力発電計画に関する動きは東京電力ばかりではなく、各電力会社にあり、
関西電力は東電よりも早い1956年4月には社長命令で原子力発電に関する課を新設し研究、開発の作業を開始した。この時の社長が太田垣士郎で黒部第四発電所(通称クロヨンダム)建設の総指揮を執ったのが太田垣社長その人で、それを補佐したのが、後に社長になる副社長芦原義重この両名を中心としてホッサマグナ(中央破砕帯)地帯の超難工事をやり遂げた。
1970年11月28日関電最初の原発、美浜発電所第一号機運転開始
関西電力は電力構成に占める原子力発電の割合は他社よりも高く、同社のCMなどでも「関西の電気の半分は原子力」とキャッチフレーズを流していたが、福島第一原発事故以後は沈黙している。
同社の原発への取り組みは積極的で福井県美浜町、美浜発電所3基、同県おおい町、大飯発電所4基、高浜町、高浜発電所4基、計11基の原発を所有している。
原発は全て加圧水型原子炉(PWR)で、立地は福井県若狭湾に面した狭い場所に集中しており「原発銀座」と言われている。さらに敦賀市には日本原子力発電の敦賀発電所、日本原子力研究開発機構の有する高速増殖炉「もんじゅ」、新型転換炉「ふげん」(現在は運転停止、廃炉作業中)、株式会社原子力発電訓練センター(三菱重工系列)がある。
現在(2012年5月現在)関電11基の原子炉は全機定期検査中で稼働停止状態にあり、再稼働に関して地元と対立している。
立地している若狭地方は福井県であるが琵琶湖の北端で北陸本線近江塩津駅からトンネルを抜けると2駅で敦賀駅(福井県)、更に若狭地方は京都府にも接しており、再稼働には周辺地域の 同意が必要とし、その周辺地域の線引きで滋賀県と大揉めし新聞紙面を賑わせている。
現在(2014年5月)大飯原発再稼働問題で政府は認可、周辺府県は絶対反対と対立を深め、原発に依存している関電は窮地に立っているが、電力消費が多くなる夏が近づきつつあり、付近住民の判断はどう下すのか。
関西電力の大消費地であり、かつ関電最大の大株主である大阪市の市長である橋下市長が再開を認めない方針を打ち出したが、電力不足は明らかであり、安全性とは何なのか、京都・大阪の水瓶である琵琶湖をどう護るのか、危険をおかしても原子力発電に頼らなければならない理由は何なのか、替わるべき手段はないのか。
全国民に課せられた問題提起だ。
原発建設への指導に戻ると、東電の次なるステップはメーカーと共同研究、作業を行うことで、パートナーとして東芝グループ三社(東芝、石川島播磨重工、石川島芝浦タービン)と日立グループと組み「東電原子力発電共同研究会」(TAP)と称し、積極的に研究を綿密に進め、テーマを期毎に区切って進化、高度化させていった。
第1期:いきなり実用炉を設計するのではなく、1万kw発電炉の設計研究を採り上げ、要素別に分科会を形成した。
当時はメーカー、電力会社も原子力発電研究の端緒についたばかりで暗中模索状態であったが、抜け出していたのが日立製作所で、これは同社の拠点「日立中央研究所」で原子力に関し既に研究を開始していた。
東芝は一歩遅れていたので炉内構造物が複雑で核計算が困難なので軽水炉を避け、重水利用の均質炉を選択した。これが幸いし東電の方向と一致したために共に研究しようという気運が醸成され連帯感が生まれた。
1957年1月には各電力会社が設立したメーカーなどが一堂に集めて日本学術会議主催で第一回原子シンポジウムが開かれ、TAPはBWRの関する研究結果を発表した。
| 第2期: | BWRのドレスデン発電所を東芝と、PWRのヤンキーポイント発電所をモデルに実施した。 |
| 第3期: | 日本原子力発電が手懸けたコールダーホールについてもTAPとして研究対象にしたが、余り性能は良くないことが判った。 |
| 第4期: | 立地点の研究が開始、建設方式は地下式、崖を切り崩して半地下式、台地上が考えられた。 |
このTAPの活動と並行して、1957年11月には東電と関電から1名ずつデトロイト・エンジン(米・ミシガン州にあった発電会社で水力・火力の発電所を所有する会社で原子力発電も手懸けるようになり、日本にも売り込むための準備として、東電・関電のエンジニヤーを招聘したらしい)1959年2月まで滞在し研修した。
1958年9月になると、GEとWH(アメリカの大手電機メーカー、原子力関連機器も製造していた)で将来の受注を見越して国内の各電力会社から技術者を招聘して、原子力訓練コースを設けて受講(3ヶ月)させた。東電からも交代で受講するために渡米した。
ここには原子炉の選定に関する思惑が蠢いていた。PWRの将来性の疑問、それの対抗するBWRの問題、1960年、アメリカ原子力委員会(AEC)が作成した「ビットマン資料」によるレポートでは、軽水炉が10年以内に石油による火力発電よりも経済性で上回る、と予測していた。
もうひとつの動きは、日本原子力発電が建設した東海原子力発電の原子炉に採用したコールダーホールの高騰で資金が逼迫していた日本原子力発電に国家資金の導入を提案、特殊法人化して官営主導で進める構想が通産官僚間で練られているとの情報があり、戦前の挙国一致体制のもと一元化の日本発送電のような悪夢の再現かと東電や関電その他の電力会社は緊張した。
電力民営論者であった東電木川田社長は通産省側の思惑の前に先手を打ってBWRの採用を決め、関電はPWRの採用を決めた。
○PWR(Pressurized Water Reactor)加圧水型原子炉、原子炉の1種、核分裂反応によって生じた熱エネルギーで、一次冷却材である加圧水(圧力の高い軽水)を300℃以上に熱し、一次冷却材を蒸気発生器に通じて、そこにおいて発生した二次冷却材の軽水の高温高圧蒸気によりタービン発電機を回す方式。発電炉としては原子力発電の大型プラントの他、原子力潜水艦、原子力空母等の小型プラントに採用されている。
わが国の商用炉は、北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力各社の全発電所、日本原子力発電の敦賀発電所の(2号機)がPWRを採用している。
○BWR(Boiling Water Reactor)沸騰水型原子炉、核燃料を用いた原子炉のうち、純度の高い水が減速材と一次冷却材を兼ねた軽水炉の1種。
わが国における商業炉としては、東北電力、東京電力、中部電力、中国電力各社の全発電所でBWRを採用しており、日本原子力発電の東海第二発電所、敦賀発電所の1号機(2号機は加圧型)がそれぞれBWR型を使用している。
東電原発建設適地探し
これらの研究・開発期間を過ぎてから、立地に合わせた建設計画を練る段階できて、各候補地を実際に訪ね、土地選定に入った。
候補地は東電の原発課の社員が現地を視察し比較検討した。
条件としては、(1)周辺は過疎であること、(2)冷却水が得られ易い、(3)地盤がしっかりしている、(4)外来電力が確保できる、(5)交通が便利なこと。(6)労働力が確保できる等が条件であった。
最初は東電管内の土地に限られ伊豆半島の東伊豆方面、東京湾の姉ヶ崎、外房の鹿島(鹿島臨港開発以前)、東海村(後に、日本原子力発電が東海原子力発電を建設)、水戸射爆場跡地(現在国営ひたち海浜公園、敷地約160ha、東京ドーム約32個分、ここは旧海軍の射爆場で、海軍航空隊の爆撃訓練が行われていた。ハワイ真珠湾攻撃訓練は、雷撃は鹿児島錦江湾、水平爆撃と急降下爆撃訓練はこの射爆場で行われ、戦後は一部開拓民が入植したが大半が砂地のため放置され荒れ地になっていた。)
候補地のうち伊豆半島はフィリピンプレートでトリプルジャンクションが近くにあり、しかも伊豆箱根火山帯が通る地震多発地であるから除外。
姉ヶ崎は東京湾内にあり人口密集地帯だから除外(現在姉ヶ崎には東電の火力発電所が建設され稼働している)
鹿島と水戸射爆場は地盤に問題があり除外、東海村は日本原子力発電の方が早くこの地に原発建設を決めてしまった。
そうすると東電管内では適地が見付からなかったことになってしまった。
関東地方に適地がないとなれば、福島県の浜通り地方に着目するのが自然の流れだ。
海に拘る理由は冷却水確保で、原子力発電は核分裂による放熱を利用し、水蒸気を作り、その水蒸気の力でタービンを回転させることによって発電する火力発電と同じ仕組みになる。その水蒸気を冷却して水に戻し、それを再び水蒸気にするという循環が行われている。
この水蒸気の冷却は海水による間接冷却であるから大量の海水が使い捨てられる。このため外海に沿岸に建設する必要があった。
アメリカやヨーロッパでは内陸にあるが、これは大陸を流れる大河があり、海に匹敵するくらいの大量の水を使い捨てても流れにはほとんど影響がないことによる。
 |
我が国の原子力発電所は全て海岸に立地している。
そうなると浜通に着目し、いわき地方や相馬地方より過疎地であり、最適と着目されたのが、大熊町の海岸に放置されていた旧陸軍飛行場跡地で、原発建設の計画の情報を入手した土地の所有者である大手不動産会社である「国土計画」は猛烈な売り込みをしてきた。
国土計画のオーナーは、政界の大物議員であり、国会議長でもあった堤康二郎氏であったからその売り込みは政治絡みであった。
一方、福島県の動きを見ると、佐藤善一郎福島県知事(1957年~1964年)が原子力の平和利用に非常に関心を持ち、在職中の1958年には商工労働部課に命じて原子力発電所設置の可能性に関する調査研究を命じ、1960年には日本原子力産業会議に入会し、企画開発担当部門のスタッフにより、県独自の立場から浜通り各地を調査し、結論は双葉郡内に絞り、最適地として太平洋に面した海岸段丘上の旧陸軍飛行場跡地(大熊町)を推した。
ところが具体的な計画を推進する前に、佐藤知事は急性肝臓萎縮症で現職のまま急逝してしまった。従って東電との接触は未だ無かった。享年64歳。
この佐藤知事の行動は「東京電力三十年史」(1983年)に記載されている。
また1958年3月14日付け「福島県議会議事録」によると自民党所属の県会議員大井川正巳氏は、火力発電所の誘致に関する質問をし、そのついでのように、将来原子力発電所を誘致するなら双葉郡が良い、また電力会社は東北電力にすべきだ。との趣旨の質問をしたところ、知事の答弁は小名浜、勿来地区に火力発電所を誘致するが、石炭は常磐炭ではなく北海道炭を使用する予定なので、小名浜港を整備しなければならないが、原子力発電所誘致に関しては全く考えていないと答弁した。
この時点では関心がなかったようだが、この質問を契機として原子力発電に関心が向くようになり、部下に調査研究を命じている。
知事急逝後は、国会議員のうちから原発に関心を持っていた木村知事に代わったから、より一層原発建設に前進しだした。
地元双葉郡住民の動きを見ると、昭和30年代は‘反原発’の動きも少なく、それよりも過疎化対策、地域振興の決め手となると歓迎されており、県知事の推薦、さらに自民党の長老である、元幹事長の斉藤邦吉代議士は地元(福島三区)選出(相馬市出身)。自民党電源立地推進調査会会長のお墨付きとなれば、斉藤代議士の絶対的影響下にあった双葉郡、相馬郡としては町議会が誘致決議をするのも自然の流れだったのだろう。
また、佐藤知事が現職のまま病没し、次に選ばれた木村知事はいわき市四倉町出身、しかも原発推進派であり、いわき市を工業都市に成長させた功績は大きい。
そうすれば出稼ぎが常態化し過疎に悩まされていた双葉郡としては次の開発は双葉郡になると期待の方が大きかった。
かくして大熊町・双葉町にまたがる海岸地帯の約350万平方m(約100万坪)に及ぶ広大な敷地が確保され、更には7・8号基建設計画があったほどの十分な広さが確保された。
一方、東電側の動きは1971年3月(昭和46年)東京電力とって初の原発が稼動するまではいろいろあったが、もう一人原発推進の主役がいた。
当時の東電社長は木川田一隆氏、生まれが福島県伊達郡梁川町。父は医者、旧制角田中学(宮城県)、旧制山形高校から、東京帝国大学経済学部卒業、当時の東京電灯会社入社、戦後は東京電力株式会社となり、課長時代出向、前にも述べたが、電力会社再編成で松永安左右衛門氏の右腕として辣腕を振るい、見事全国を九電力会社に区分し再編成をやり遂げた。やがて東京電灯から東京電力に衣替えした本社に戻り、やがて社長に就任、木川田天皇と言われるくらいの実力者で東京電力ばかりではなく、九電力全体を牽引する位の辣腕を振るった。
原子力発電所建設が決まると、その建設地として浜通りを推奨し、当時の福島県知事佐藤善一郎(福島市出身)福島県議を経て、衆議院議員二期連続当選後、1957年知事に当選。この頃から木川田東電社長が福島県庁を訪れ、非公式な会談を重ねていたらしい。
ところが、佐藤知事は在任中の1964年、急性肝臓萎縮症で急死、その時点では未だ福島原発の調査も始まっていなかった。
次の知事は、木村守江氏、四倉町(現いわき市)の開業医から1950年参議院議員に当選、1958年衆議院議員に当選、1964年佐藤知事急死による知事選で当選した。
木村氏は四倉町で代々の開業医(木村医院)、木川田社長も父、兄共に開業医で元々医者として親交があったらしい。そのような関係で原発問題は急進展した、といわれている。
確かに木川田社長は月に1回は福島へ出向いて知事と会談、地元町長や議会関係者と会談していたことは明らかになっている。
県トップの知事、地元選出で原発推進派の斉藤邦吉代議士、東電のトップが全て福島県人であり、地元町長、町議会も賛成となれば意志の疎通は完璧で、反原発の運動が疎らにあったが、それも地元住民ではなく労働組合の関係者程度であったからすんなりと決定した。
福島第一原子力発電所
何故双葉郡だったのか?
そもそも福島県は東北電力の電気供給区域であって、東京電力ではない。表現は悪いがいわば縄張り外のはず。
そこで生産、供給し、需要は関東地方の東京電力管内に限るとは、一寸ムシが良すぎませんか、と言うのが県民感情、しかも奥会津の水力発電も大半は関東地方へ送電されている。
原発建設地の前提条件としては、海岸に立地する、過疎地である、需要地になるべく近いこと、地域住民の反対運動が少ないだろと思われる等が前提になる。
この結果、東京湾沿岸、神奈川県、房総地区で広大な土地を入手することは、人口密度、立ち退き料、設計震度などの関係から立地困難とされ、需要地に比較的近く、前提条件を満たす候補地として、茨城県、福島県沿岸部が対象となり、調査・検討が行われた。
福島県浜通りを選んだ根拠を探ると、「関東の電気事業と東京電力、電気事業の創始から東京電力50年への軌跡」(東京電力50年史)に次のような記述がある。「原子力発電課を設置し、極めて早い時期に原子力開発への取り組みを始めた東京電力は、その直後から具体的な発電所立地候補地点の選定を進めてきた。世界的にみると、50年代後半には火力発電の大容量化と原油価格の下落によって、火力発電のコストが大幅に低下する見通しがついたため、原子力開発のスローダウン傾向が生じた。しかし、東京電力は、長期的には原子力発電の必要性は明かであるとの認識に立ち、広範囲にわったて立地調査を継続してきた」「当時、福島県双葉郡では地域振興を目的に工業立地を熱心に模索しており、また福島県としても双葉郡に原子力発電所誘致に積極的であった。こうしたなか、1960年5月、福島県の佐藤善一郎知事から東京電力に対して、双葉郡大熊町と双葉町にまたがる、旧陸軍飛行場及び周辺地域が原子力発電所建設には最適であるとの打診があった。」
この立地条件としては全ての前提条件を満たしており、東京電力は同地点に建設の方針を固め、1960年8月に福島県に対して正式に建設の意志を表示した。
1961年9月19日、大熊町議会が原子力発電所誘致促進決議
1961年10月22日、双葉町議会が原子力発電所誘致決議、東京電力は福島県側からの要請により、用地買収、漁業権交渉を開始し、約310万平方メートルを買収、これは東京ドームが66個分の広さだとのこと。
以上が東京電力社史の一節であり、あくまでも福島県側から積極的は誘致運動の結果であるとしておるが、これは事実で、当時の佐藤善一郎知事は早くから原子力発電の将来について着目しており、県商工労働部に命じて調査に着手していた。
そこで着目されたのが太平洋に面した大熊、双葉両町にまたがる標高35mの台地で、戦時中陸軍飛行隊の飛行場跡地で、終戦後は付近の農家が‘塩焚き’といっていた海水を煮詰めて塩を生産する小屋、何処の海岸砂浜にもこの小屋が乱立していて、戦後しばらくの間、塩が絶対量不足していたのでよく売れた。
これも一時的な現象で、まもなく外国産の塩が輸入されると直ぐに駄目になり、広大な荒れ地として放置されていたのを県が眼を付け、原発立地として最適と判断し、東京電力に意向を打診した。
この旧陸軍飛行場跡地で放置されていた広大な荒れ地があったことが、最大の決め手となって、原発建設のゴーサインとなった。
原発候補地は双葉郡
浜通りに集中したのは海岸であることが条件で、原発は火力発電と同じ蒸気の力でタービンを回して発電する。その水蒸気を冷やして水に戻して再び水蒸気になるよう加熱をするわけですが、水に戻す作業として復水器という装置にはパイプが張り巡らされていて、そのパイプには海から取水した水が通っている。
復水器を経た水はまた圧力容器に戻って循環するが、水蒸気を冷却に使用された海水はパイプから放出され海に戻される。
従って海の沿岸に設置しなければならない理由がこれで、では外国では内陸に設置されているのはどうゆう理由だと反論されるかもしれないが、アメリカ、ソ連、ヨーロッパでは、大きな河川があり、河川の岸に原発を建設すれば海と同じくらいに冷却水を確保できるからです。
原子力発電所建設計画が具体化し、東京電力と福島県が独自に調査した結果、最適地が3地点に絞られた。
●大熊町・双葉町(両町にまたがる)
●双葉町
●浪江町
この調査結果は1959年、東電の常務会で報告され、木川田社長自身が現地を身分を隠して隠密裏に視察をし、更に専門家に現地調査を依頼している。
福島県としては、この時点以前から原発誘致を計画しており、当時の佐藤善一郎知事は過疎地双葉郡に原発を誘致することを考えており、県独自の調査を命じて原発誘致の可能性を探っていた。
調査を重ねて、当初は東北電力に打診したが、当時は奥只見電源開発で多額の費用を要しており、更に当時の東北地方は首都圏ほどの電力需要が見込めず、余り乗り気ではなかった。
それに替わるべき売り込み先は東京電力であるが、その行動を起こす前に知事は病に倒れ、急死した。
替わって登場したのが木村守江知事(四倉町出身)で、知事は衆議院議員時代から知己であった東電社長木川田氏にこの誘致を持ちかけ、福島県出身の木川田社長も乗り気になり、しかも東電としても原発建設候補地を物色している最中であったから、話は一挙に進んだ。
地元選挙区で自民党の大物斉藤邦吉衆議院議員、東大法学部から労働事務次官、1958年第28回衆議院議員選挙で初当選、第二次田中内閣で厚生大臣就任(1972年)、自由民主党幹事長就任(1978年)、自民党の重鎮であり、地元の原発誘致には深く関わった。
福島県議(1959年~1969年)後1969年から衆議院議員になった渡部恒三氏は選挙区が会津だったので只見川開発に尽力し電力業界と強いパイプがあった。
従って双葉地方の原発誘致には県議時代から衆議院議員と続いて活躍し、更に田中派入りしてから電源三法成立に尽力、交付金の威力を充分に活用した。
事故時には政権与党であった民主党の長老だった同氏は、黄門様の尊称での政治力をもって被災地救済にあたった。
また地元福島県でも絶大な力を持っており、甥の佐藤雄平知事を実現させた。
笠原太一県議(双葉町出身)は福島県議会で最初に原発誘致を提唱し、原発を誘致できれば経済効果は甚大で、関連企業の誘致、水資源の確保、常磐線の電化、国道6号線の完全舗装等を挙げ、双葉町、大熊町を中心として富岡町、浪江町を包した双葉郡の総合的な開発を企画していた。
誘致に活躍した人々
○50代知事 木村守江:石城郡四倉町生(1900年4月6日~1996年11月3日)
旧制磐城中学、慶応義塾大医学部卒、四倉町で代々開業医(木村医院)
1950年、第二回参議院議員通常選挙に福島選挙区から立候補、当選、参議院議員を1期勤めた後、衆議院に鞍替えし、1958年第28回衆議院議員総選挙で旧福島3区から立候補、自民党公認、当選。3期連続当選後、1964年、佐藤知事が現職で急逝したため、その後任を選ぶ選挙に出馬した当選、福島県知事となる。以後4期連続して知事に就任。この間全国知事会会長にも就任している。
知事として県内のインフラ整備には重点を置き、地元いわき市を周辺市町村の大合併を行い、当時では全国最大の面積を誇るいわき市を誕生させ小名浜を中心とする周辺各地に首都圏から企業誘致に力を注ぎ、大工業地帯を建設した。
前任者、佐藤知事が着手した双葉郡への原子力発電所建設計画にも積極的に活動し、東京電力側と度々接触し、旧知の東電木川田一隆社長は福島県出身で木村知事とも旧知であり、計画が具体的になる前から接触していた。
浪江・小高の原子力発電所建設計画はこの頃よりあり、本格的に誘致に動いたのは木村知事が最初で、1968年1月5日のテレビの年頭挨拶でこの件について抱負を述べている。
1976年8月6日、土地開発に絡む収賄罪容疑で逮捕され、8月11日 知事辞任 1979年1月、仙台高裁で懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の判決が確定し、公選知事として初めて収賄で有罪になった。 晩年は自宅でゴルフや登山に親しみ、1996年11月3日老衰で死去、96歳
○木川田一隆 東京電力社長(1899年8月23日~1977年3月4日)
福島県伊達郡梁川町生まれ、父は医師三男、宮城県との県境にあるので旧制角田中学校に進学(現宮城県角田高等学校)卒業後、陸軍士官を目指すも2浪で断念、旧制山形高等学校へ進学、東京帝国大学経済学部、河合栄治郎教授に心酔、労働問題に興味を持つ、卒業時三菱鉱業を希望したが面接で落とされ、第二志望の東京電灯(後、東京電力)に入社、当時の電力会社は自由競争であったため、多くの企業が乱立しており吸収・合併が相次ぎ、東京電灯もそのような中で次第に肥大化していって五大電灯と言われる日本最大の電力会社に成長した
1937年、電力国有化法案「電力国策要綱案」が閣議で可決され、1940年の第二次電力国策要綱により、電力会社は9つに統合された。東京電灯は関東配電株式会社となる。この時木川田氏は秘書課長。
1946年12月8日、太平洋戦争に突入、1945年8月15日終戦、戦後、電力再編につき各界から様々な異論が出て収拾が付かなかった時、「電力の鬼」松永安左右衛門が辣腕を振るい混乱を収めた。
この時松永氏を補佐したのが木川田一隆氏で、この時松永氏は次の電力界を背負うのは木川田氏であると確信したという。
1961年、東電社長に就任、福島第一・第二原発、新潟柏崎原発建設に奔走する。経済同友会代表幹事にも就任
日中関係改善にも力を注ぎ、周恩来首相と会談したこともある。
社長在任中は木川田天皇と呼ばれたくらいのやり手
1971年、水野久男氏に社長譲り会長に退く、会長時代参議院議員市川房枝氏の要請を受けて政治献金を全面的に廃止したのは有名、アメリカの新聞から「Business Statesman」と褒め称えられた。
1976年 体調を崩し、会長職を引退、1977年(昭和52年)3月4日死去、 享年77歳
○斉藤邦吉(1909年6月26日~1992年6月18日)福島県3区選出衆議院議員 旧制相馬中学、旧制一高、東京帝国大学
旧内務省、戦後内務省解体、厚生省に移り厚生次官
大竹作磨知事が1957年(昭和32年)に引退するに当たり、後任知事に推薦したのが厚生次官であった斉藤氏で自民党公認として福島県知事選に立候補した。ところがもう一人自民党所属で現職の国会議員であった佐藤善一郎氏が立候補、当然同党で二人の公認はあり得ず、佐藤候補はヤムを得ず社会党推薦で県知事選を闘い当選した。
1958年(昭和33年)衆議院議員選挙(福島3区)自民党公認で出馬、当選 連続12期当選
1964年07月 第三次池田改造内閣 内閣副官房長官
1972年12月 第二次田中内閣厚生大臣
1978年12月 自民党幹事長
1980年07月 鈴木内閣厚生大臣
1982年11月 第一次中曽根内閣行政管理庁長官
1992年06月18日 死去、享年82才
○渡部恒三(1932年5月24日)福島県選出 衆議院議員 南会津郡田島町生まれ(現・南会津町)県立会津高校、早稲田大学卒
卒業後 八田貞義国会議員(会津出身、福島2区)の秘書となる。
1959年4月福島県議会選挙に自民党公認で出馬、当選、県議となる。
笠原太吉県議と共に双葉郡の原発誘致に動き県に働きかける。
県議在職中、公職選挙法違反で逮捕され、有罪判決を受けて県議を辞任。
1969年、第32回衆議院議員総選挙に福島2区から出馬、自民党は公認しなかったので、無所属であったが当選。幹事長であった田中角栄氏は不明を詫び、追加公認したので即田中派に入った。
田中派で王道を歩み、厚生大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、通商産業大臣を歴任、その後竹下派に属し、経世会では竹下派七奉行の一人になる。
原発問題では双葉郡への誘致に県議時代から積極的に働き、厚生大臣であった1984年1月、原子力関係者だけの内輪の会合で「原発を造れば造るほど国民は長生できる。日本のエネルギー問題の解決は原発だというのが私の政治哲学だ」と述べて事が新聞で報道され、反原発グループから猛烈な反撃があった。
真意は判らないが、当時、公害問題で火力発電が行詰り、原発容認の流れにあっったことは確かで、その流れに乗って口を滑らせたのか、ともかく原発建設積極派であったことは確かで、福島第一、第二原発誘致に活躍し、いわゆる口利きで大いに潤ったとの噂は絶えない。
前知事の佐藤雄平氏は同氏の甥(実姉の子息)
佐藤雄平氏は大卒後、叔父渡部恒三議員の秘書を長年勤め、1998年第18回参議院議員選挙に福島選挙区から出馬、勿論渡部恒三氏の絶大なる後援があり、当選、
2006年 佐藤栄佐久氏の知事辞任に伴う県知事選に出馬、自民党が擁立した弁護士の森雅子氏を破って当選したのは、叔父渡部恒三氏の力は大きかった。
2012年の解散総選挙では出馬を辞退し、政界を引退した。
 |
第29章 地元誘致の動き
地元の誘致運動
福島県の中でも後進地域であった双葉郡の開発には県としても頭を悩ましていたらしい。
最初に原発誘致を思いついたのは佐藤善一郎知事であったと記録されているが、実際に県技術職員に適地がどうか現地での調査を命じている。
この流れの中で双葉郡選出の山村基議員が原発誘致に関する質問を県議会でしたのが最初だと言われている。
1958年頃、福島3区選出の木村守江衆議院議員が地元浜通りの自治体各市町村長との接触で最大の願望は地域活性化としての企業誘致で、一次産業しかない地域としては切実な思いがあった。
木村議員は地元いわき地方の活性化のため、地方の漁港に過ぎなかった小名浜港を一大国際貿易港に昇格させ、いわき地方を東北一の工業都市に成長させた。
次は過疎に悩む双葉地方を活性化することにあり、地元もそれを熱望した。
そこで旧知の東電副社長木川田一隆氏(当時)に相談したところ、曖昧な態度でそのまま別れてしまったが、東電としては当時、まだ原子力発電所建設は全く想定外であったらしい。それどころか木川田副社長の個人的感情としては、当時の世間一般の感情と同じく原爆関連の後遺症として、原子力発電には懐疑的であったらしい。
ところが1961年になると原子力発電が世界的なブームとなり、国内でも政界、財界でも急速に関心が高まってきた。
東電内にも流れに乗って、原発建設のための調査課が設けられ、原発建設適地調査が始まり、東電管内の適地として伊豆半島、東京湾の内房、太平洋岸の外房(千葉県)、茨城県の太平洋沿岸の各地を探索したが適地が見当たらなかった。
次の段階として東北電力管内ではあるが首都圏に比較的近く、外海に面し、しかも過疎、理想的な候補地として双葉郡が浮上するのは自然の流れで、しかも以前、木村議員から推薦のあった地域であったから、1960年、社長に昇格していた木川田氏から木村議員に接触があり、この情報を当時の佐藤善一郎福島県知事に伝え、さらに地元を選挙区(福島3区)とする当時は未だ1年生議員であったが、後に自民党の大物議員になる斉藤邦吉氏(相馬市出身)も同席、福島県知事と東電社長の会合の席が設けられ、接触が始まった。
さらにもう一箇所は新潟県で田中角栄氏との絡みは別項で考察する。
双葉郡では地元民を刺激しないように東電社長や県知事は高級車を用いず、ジープに乗り、普通の作業衣姿で浜通りの各地を視察したらしい。
また当時の佐藤知事は原発に関心を持ち、県として独自に県職員の技術職員を派遣して原子力発電事業の適地選定作業を行い小名浜地区、相馬地区よりも海岸線が平坦で30m位の断崖が続く双葉郡内が適地と報告されていた。
同時に東電側でも独自に土地選定チームが浜通り各地を調査した。県と東電の調査結果は完全に一致し、大熊町の海岸にある荒れ果てた台地、旧陸軍飛行場跡地を指した。
東電が土地選定の最大の懸案は地盤の問題で、原発の立地は地震に耐えうる地盤が必要で、この調査も専門の企業が調査した。しかし、現在考えると地震、津波に関する調査も大分甘いと言わざるを得ないし、現在問題になっている双葉断層は学術的にも判らなかったから話題にもならなかった。
 |
津波も三陸地方のリアス式海岸だから津波が起きる、平坦な海岸線である浜通りには起きるわけがない、貞観地震(869年)も文献上にあるだけで実際の調査はボーリング調査で小さな穴から地層を分析するだけだから、地層の調査は可能でも津波の痕跡の調査は面でやらなければ判る訳がないので、最大7m位と報告され、富岡海岸、富岡川河口付近を遡った最大21m超えの津波など全く想像も出来なかった。
県の判断、東電の判断も全てが旧陸軍飛行場の跡地が最適との判断が下された。
この旧飛行場跡地を不動産として所有していたのが大手不動産会社である「国土計画」旧飛行場跡地を政府から払い下げを受けたのが、堤康次郎氏で現役の衆議院議員、政界の実力者であり、衆議院議会議長という要職にあり、「大西武」を率いる財界の実力者である同氏が猛烈な売り込みをしてきた。
この旧飛行場を不動産として所有していた経緯は、戦後猛烈な食塩不足に悩まされ、浜通りの海岸各地では平らべったい長方形の鉄釜で海水を直接に煮詰め、塩を採る原始的な「塩炊き」と称した製塩の小屋が乱立して、毎朝大勢の塩の担ぎ屋が買い出しにやってきて、浜通り沿岸の一大産業となった。
そこに目を付けた大手の都市開発業者であった同社は、都下中央線沿線の国立、小平市等の学園都市開発で急成長した西武グループの中核企業であった「都市計画」(コクドと改名後倒産)は放置されていた旧飛行場を政府から払い下げを受け、ここに塩田を作り瀬戸内海地方のような製塩業を開設しようとして準備していたが、国際貿易が再開され、安価な塩が輸入されるようになって原始的な製塩は全て廃業となってしまい元の砂浜に戻った。
国土計画も土地を入手したが目的であった製塩業が崩壊してしまい、旧飛行場の一部に小屋が建てたくらいで、再び放置され不毛の大地と化した。ただし、不動産の登記は国土計画のままであったから政治家の早耳で、原発建設予定の情報を入手、好機到来とばかり売り込みに熱中するのは当然であった。
何かを建設する場合は用地の買収が最もてこずることであるが、この場合は逆に猛烈な売り込みであったから、用地の確保はすんなりと決まってしまった。
旧飛行場跡地以外の土地も、農家が僅かにある程度で農地としても適していなかったから土地に対する執着はそれほど無くなく、すんなりと買収に応じた。
原発を起爆剤として双葉地方総合開発の必要性を訴え、他の議員も同調して原発誘致は「本県の開発に関して一大福音になる」として双葉地方総合開発計画を推した。
出稼ぎが常態化してしまった後進性にあり、何とか脱却したいとの住民の悲願が、原発誘致に込められ原発建設が本決まりとなり、土地の買収は県開発公社が中心となり、町当局、町議会の協力を得て反対運動もなく、短期間で買収は完了した。
1963年12月1日、買収交渉開始、県開発公社が担当した。
一般民有地の交渉は大熊、双葉の両町合同開発特別委員会が結成され、町長が代表として地権者との折衝に当たるという基本方針が示され、それを町の特別委員会と県開発公社がバックアップすることにしていた。
地権者全員を公民館に集め、公社の話を聴き、質疑応答の末、個々の買収交渉に入った。
一般民有地第一期購入、30万1042坪、福島県開発公社購入
一般民有地第二期購入、31万7670坪、福島県開発公社購入
合計66万8712坪、66万8712坪×270円=約1億8000万円
国土計画所有分30万5840坪は国土計画と東電が直接交渉で購入。
 |
 |
国土計画は戦後まもなく製塩業を営む計画を立て、旧陸軍飛行場跡地であった荒れ果てた国有地に目を付けた。国土計画は堤康二郎氏が統率する西武グループの中核企業で、その時30万坪に及ぶ土地をなんと3万円で払い下げを受けた。
しかし製塩業は挫折、荒れたまま放置され、国土計画としては次期計画もなく、堤氏の三男義昭氏が早大卒後、1957年、国土計画に入社、1965年に社長就任だから、1963年の買収交渉には専務としてこの交渉を担当、3万円で払い下げを受けた30万坪の土地が東電には3億円で譲渡するという買値の1千倍の売値が付いたまさに強運の交渉が成立した。
だから原発誘致に最も熱心だったのは堤氏だと言われており、ともかく土地購入は非常にスムースにいったことになる。買収総額の予算5億円、その予算内で無事買収は成功した。
原発建設誘致に関して福島県議会で最初に発言したのは1958年3月14日の議会で質問したのが大井川議員であったことは述べたが、この時は主に火力発電所建設を常磐地方に誘致したい、という趣旨であったが、将来原発を建設するなら常磐地方を推薦するとした。その時、答弁に立った佐藤知事は火力発電所建設には積極的に誘致する旨を答弁しているが、原発に関しては全く考えておらず白紙だと答弁している。ただこの時の答弁が原子力発電に関心を持つきっかけになったことは事実らしい。
しかし県議会としては原発に関する発言はなく、関心も余りなかったらしい。
1960年代になると東京電力が原発建設で双葉郡に関心を持っていると噂が流れ出すと、双葉郡選出の県議山村基が原発誘致を県会で積極的に発言をした。
ところが、1963年4月の県議選で落選し、替わって当選したのが笠原太一氏で、同氏は双葉町出身、熱心に誘致運動に参加した。
笠原議員が議会で構想を述べた質問事項「先に開発只見川総合開発は地元に及ぼした経済効果は単に電気水使用料と資産税だけでの恩典だけで、企業誘致は全くできなかった。
双葉に百万キロの原子力発電所が出来れば、経済効果としてこれに関連する産業の誘致、そのためには水資源開発・確保が重要課題になる。常磐線の電化、国道6号線の完全舗装、企業誘致は双葉・大熊だけの運動では駄目で、少なくとも富岡、浪江等包括した双葉郡全体の産業構造を描かねばならない」としている。
その念頭には奥只見電源開発が首都圏に電力を送るだけの施設になり企業誘致が出来ず地元における経済効果は交付金、固定資産税のような金銭だけだったことによる無念さがあり、双葉地方では絶対に奥只見の轍は踏まないぞ、という意思の表れがある。
この時強調したのは、原発建設を起爆剤として双葉郡全体が一致協力して工業化を謀らなければならないとして双葉市構想を熱心に説いた。
これはお隣いわき市が常磐炭鉱倒産に見られるように石炭産業の崩壊、中心産業を失ったいわき市が、平市を中心とした五市、石城郡全体と双葉郡の久ノ浜町、大久村を含めた大合併を成功させ、有数の工業都市に変貌していった「いわき市」の大躍進が心底にあり、今度は双葉市の躍進と念願するのは当然の帰結だろう。
この原発を起爆剤として双葉地方を総合開発地域にしたい、その用意はあるかと議会で質問を繰り返している。
他の自民党県議も同調して、「原発誘致は本県の開発に関して一大福音になる」と持ち上げている。
1961年9月30日、双葉町町議会原発誘致決議
1961年10月22日、大熊町町議会原発誘致決議
その後は原発建設の為の土地買収に関する進捗状況、その後は建設の進捗状況が知事と議員の間で活発な議論が繰り返された。
土地の買収に関しては、県開発公社が中心になり町当局、町議会の強力を得て反対も無く、短期間で買収を完了した。これは双葉郡民が県を信頼し、知事の手腕を全幅の信頼を置き、後進性脱却の悲願が達成できると熱望しているのであった、その願いを実現して欲しいと訴え続けた。
この土地購入がスムースにいった根本的理由は双葉郡民がこの原子力発電所の将来を期待して、後進地域からの脱却を願う悲願が込められている。
原発が稼働した暁には本県は勿論、わが国経済に大いに貢献するものと信ずる。従って東電、県としても双葉郡民、地域住民の福祉向上、地域開発に力を注いで欲しい、力を貸して欲しい、これが切実たる願いであると笠原議員は訴えた。
そして、双葉郡発展のための双葉地方地域開発計画構想を描き、そのためには水資源確保が必要で、ダム建設を推進したい自治体統合を含めて総合的な双葉郡の開発を、原発建設を契機として行うべきだ、と主張した。
この頃は佐藤善一郎知事が病没し、木村守江知事に代わっており、木村知事もまた総合開発の悲願を持っており、その点では笠原議員の持論と一致した。
確かに木村知事の手腕は優れ五市を含む石城郡全体の町村、双葉郡からも久之浜町、大久村を含む世紀の大合併と言われたいわき市を誕生させ、東北一の大工業地帯を造りあげた。
笠原議員の双葉郡統合(双葉市構想)による総合的な地域開発と位置付け、水資源確保の構想に対して、木村知事も全面的に賛成し、県としても積極的にバックアップすることを表明したが、ところが双葉郡下の町村は笠原議員の構想にはついていけず、小さな合併はあったが、全体的な合併構想は進まず、総合開発も画餅になってしまい夢は虚しく消えてしまった。
その原因ははっきりしており、国と東電から地元優先で資金が流入し、更にその後原発三法の成立により膨大な原発交付金が町にもたらされたから、双葉市構想よりも我が町繁栄にこそ関心が移るのも自然の帰結だろう。
その結果は町にメンツをかけた公共施設建設に巨費を費やしながら、‘空の城’ハコモノ建設に注ぎ込み、最も理想的な町予算が組めたはずの双葉町が真っ先に財政赤字に転落したのだから世間は唖然とした。かくして双葉市の夢は消えた。
今になって後悔することは双葉市構想が実現していれば町の面子を懸けての競争での公共施設の建設、「空の城」に過ぎなかった数々の事業もなかったはず、極端な財政赤字もなかったはず、と悔やまれる。
事故後の対策も各町の思惑の違い、足並みは揃わない。残念ながらこのままでは衰退の一途辿る双葉郡に陥ってしまう。
福島原発誘致に活躍した人々
○笠原太吉:双葉郡選出県議(双葉町、旧制双葉中学2回生、第10同窓会会長)

原発建設誘致に関して福島県議会で最初に発言したのは1958年3月14日の議会で質問したのが大井川議員であったことは述べたが、この時は主に火力発電所建設を常磐地方に誘致したい、という趣旨であったが、将来原発を建設するなら常磐地方を推薦するとした。その時、答弁に立った佐藤知事は火力発電所建設には積極的に誘致する旨を答弁しているが、原発に関しては全く考えておらず白紙だと答弁している。ただこの時の答弁が原子力発電に関心を持つきっかけになったことは事実らしい。
しかし県議会としては原発に関する発言はなく、関心も余りなかったらしい。
1960年代になると東京電力が原発建設で双葉郡に関心を持っていると噂が流れ出すと、双葉郡選出の県議山村基が原発誘致を県会で積極的に発言をした。
ところが、1963年4月の県議選で落選し、替わって当選したのが笠原太一氏で、同氏は双葉町出身、熱心に誘致運動に参加した。
笠原議員が議会で構想を述べた質問事項「先に開発只見川総合開発は地元に及ぼした経済効果は単に電気水使用料と資産税だけでの恩典だけで、企業誘致は全くできなかった。
双葉に百万キロの原子力発電所が出来れば、経済効果としてこれに関連する産業の誘致、そのためには水資源開発・確保が重要課題になる。常磐線の電化、国道6号線の完全舗装、企業誘致は双葉・大熊だけの運動では駄目で、少なくとも富岡、浪江等包括した双葉郡全体の産業構造を描かねばならない」としている。
その念頭には奥只見電源開発が首都圏に電力を送るだけの施設になり企業誘致が出来ず地元における経済効果は交付金、固定資産税のような金銭だけだったことによる無念さがあり、双葉地方では絶対に奥只見の轍は踏まないぞ、という意思の表れがある。
この原発を起爆剤として双葉地方を総合開発地域にした、その用意はあるかと議会で質問を繰り返している。
他の自民党県議も同調して、「原発誘致は本県の開発に関して一大福音になる」と持ち上げている。
○岩本忠夫:双葉町生まれ、実家は酒販業、青年団活動を経て1971年4月社会党公認で県議選に出馬し当選、その時、既に福島第一原発の1号機は運転を開始していたが、「双葉地方原発反対同盟」を結成、その委員長になる。
県議時代は原発阻止の反対運動に没頭し、1974年には、電源三法の国会審議に参考人として招致され「危険な原発を金で押しつける法案だと、解せざるを得ない」と証言した。
その活動は第一原発の正門の座り込み、原発作業員の労働組合結成の働きかけをした。しかし、原発交付金で地元は潤い、下請け企業に働き口を見付け、あるいは関連企業が活動してくると、当然ながら反対運動を続ける岩本議員の支持は低下し、1982年に反対同盟は解散、1983年の県議選に立候補したときは、反対運動については全く触れなかったが、落選。社会党を離党した。
その後は家業の酒販売店の主として家業に励んでいたが、田中清太郎町長が下水道工事を巡る不正支出問題で町長を辞任した。
その後任に多くの町民から推され、1985年12月の双葉町町長選に出馬し当選。
当選後の抱負では、「町民が望むのなら原発は推進する」と発言し、「反原発運動の経験を生かし、安全な原子力行政に取り組む」としている。
更に「町民が望むのなら増設誘致も行う」とエスカレートしている。
事実、電源3法交付金や東電の寄付を財源として、町総合運動公園(40億円)保健福祉(16億円)等、公共事業の枠を広げ過ぎた結果、町財政は急速に悪化、1989年には財政破綻一歩手前の「早期健全化団体」に転落している。
1991年9月の町議会が7、8号増設促進を求める決議をして、全国版の新聞に掲載されたから驚いたが、同時によほど町財政が苦しいのだろう、と交付金はどこへ行ってしまったのか全国民が疑問に思った。
この間、全国原子力発電所所在市町村協議会副会長も務めた。
2005年に町長を辞め、静かな余生となったが人工透析を週二回受ける身になり、やがて認知症が進行。2011年3月の第一原発事故で一家は避難地、福島市へ。2011年7月17日 慢性腎不全で死去。
○田中清太郎:双葉町町長(1963年~1985年)

(旧制双葉中7回生、第12代同窓会会長)
「追想・町長在職二十二年の軌跡」
「双葉町訪中団中国大陸を行く」
田中氏は「田中土建」という会社のオーナーで当然ながら地元への原発誘致は熱心であり、東電としても地元懐柔のためにも地元業者優先の関連工事発注があった。
地元最大の土建業である田中土建が中心となって業者への割り振り、談合等入札を会社内で取り仕切った、と告発文があるが、但し真偽は不明。
受注額は5億円というのは確からしい。
その後、町の下水道工事を受注したが、赤字を出してしまい、それを町の予算から付帯工事名目で支出し秘密裏に処理しようとしたが発覚、警察の捜査になったが、辛うじて逮捕は免れた。
しかし、下水道工事を請け負ったのが田中土建で、そのオーナーと町長が同一人物となれば町民の信用を失うのは自然の流れであって、その後引責辞任した。
その町長選で岩本氏が町長に就任した。
○50代知事 木村守江:石城郡四ツ倉町生まれ(1900年)
旧制磐城中学、慶応義塾大医学部卒、四倉町で代々開業医(木村医院)
1950年 第二回参議院議員通常選挙に福島選挙区から立候補、当選、参議院議員を1期勤めた後、衆議院に鞍替えし、1958年第28回衆議院議員総選挙で旧福島3区から立候補、自民党公認、当選。3期連続当選後、1964年 佐藤知事が現職で急逝したため、その後任を選ぶ選挙に出馬した当選、福島県知事となる。以後4期連続して知事に就任。この間全国知事会会長にも就任している。
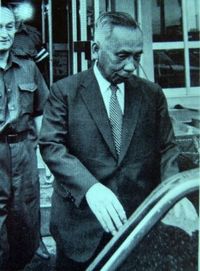
知事として県内のインフラ整備には重点を置き、地元いわき市を周辺市町村の大合併を行い、当時では全国最大の面積を誇るいわき市を誕生させ小名浜を中心とする周辺各地に首都圏から企業誘致に力を注ぎ、大工業地帯を建設した。
前任者、佐藤知事が着手した双葉郡への原子力発電所建設計画にも積極的に活動し、東京電力側と度々接触し、旧知の東電木川田一隆社長は福島県出身で木村知事とも旧知であり、計画が具体的になる前から接触していた。
浪江・小高の原子力発電所建設計画はこの頃よりあり、本格的に誘致に動いたのは木村知事が最初で、1968年1月5日のテレビの年頭挨拶でこの件について抱負を述べている。
1976年8月6日、土地開発に絡む収賄罪容疑で逮捕され、8月11日に知事辞任。1979年1月、仙台高裁で懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の判決が確定し、公選知事として初めて収賄で有罪になった。
晩年は自宅でゴルフや登山に親しみ、1996年11月3日老衰で死去、96歳没。
○木川田一隆:東京電力社長

1899年(明治32年)8月23日福島県伊達郡梁川町生まれ、父は医師三男、宮城県との県境にあるので旧制角田中学校に進学(現宮城県角田高等学校)卒業後、陸軍士官を目指すも2浪で断念、旧制山形高等学校へ進学、東京帝国大学経済学部、河合栄治郎教授に心酔、労働問題に興味を持つ、卒業時三菱鉱業を希望したが面接で落とされ、第二志望の東京電灯(後、東京電力)に入社、当時の電力会社は自由競争であったため、多くの企業が乱立しており吸収・合併が相次ぎ、東京電灯もそのような中で次第に肥大化していって五大電灯と言われる日本最大の電力会社に成長した
1937年、電力国有化法案「電力国策要綱案」が閣議で可決され、1940年の第二次電力国策要綱により、電力会社は9つに統合された。東京電灯は関東配電株式会社となる。この時木川田氏は秘書課長。
1946年12月8日、太平洋戦争に突入、1945年8月15日終戦。
戦後、電力再編につき各界から様々な異論が出て収拾が付かなかった時、「電力の鬼」松永安左右衛門が辣腕を振るい混乱を収めた。この時松永氏を補佐したのが木川田一隆氏で、この時松永氏は次の電力界を背負うのは木川田であると確信したという。
1961年、東電社長に就任、福島第一・第二原発、新潟柏崎原発建設に奔走する。経済同友会代表幹事にも就任。
日中関係改善にも力を注ぎ、周恩来首相と会談したこともある。
社長在任中は木川田天皇と呼ばれたくらいのやり手。
1971年、水野久男氏に社長譲り会長に退く、会長時代参議院議員市川房枝氏の要請を受けて政治献金を全面的に廃止したのは有名、アメリカの新聞から「Business Statesman」と褒め称えられる。
1976年 体調を崩し、会長職を引退、1977年(昭和52年)3月4日死去、享年77歳
○斉藤邦吉:福島県3区選出 衆議院議員

1909年(明治42年)6月26日1992年6月18日
旧制相馬中学、旧制一高、東京帝国大学
旧内務省、戦後内務省解体、厚生省に移り厚生次官
大竹作磨知事が1957年(昭和32年)に引退するに当たり、後任知事に推薦したのが厚生次官であった斉藤氏で自民党公認として福島県知事選に立候補した。ところがもう一人自民党所属で現職の国会議員であった佐藤善一郎氏が立候補、当然同党で二人の公認はあり得ず、佐藤候補はヤムを得ず社会党推薦で県知事選を闘い当選した。
1958年(昭和33年)衆議院議員選挙(福島3区)自民党公認で出馬、当選。連続12期当選
1964年7月、第三次池田改造内閣内閣副官房長官
1972年12月、第二次田中内閣厚生大臣
1980年7月、鈴木内閣厚生大臣
1982年11月:第一次中曽根内閣行政管理庁長官
自民党幹事長
○渡部恒三:福島県選出 衆議院議員

1932年5月24日南会津郡田島町生まれ(現・南会津町)
県立会津高校、早稲田大学卒
卒業後 八田貞義国会議員(会津出身、福島2区)の秘書となる。
1959年4月福島県議会選挙に自民党公認で出馬、当選、県議となる。
笠原太吉県議と共に双葉郡の原発誘致に動き県に働きかける。
県議在職中、公職選挙法違反で逮捕され、有罪判決を受けて県議を辞任。
1969年、第32回総選挙に福島2区から出馬、自民党は公認しなかったので、無所属であったが当選。幹事長であった田中角栄氏は不明を詫び、追加公認したので即田中派に入った。
田中派で王道を歩み、厚生大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、通商産業大臣を歴任、その後竹下派に属し、経世会では竹下派七奉行の一人になる。
原発問題では双葉郡への誘致に県議時代から積極的に働き、厚生大臣であった1984年1月、原子力関係者だけの内輪の会合で「原発を造れば造るほど国民は長生できる。日本のエネルギー問題の解決は原発だというのが私の政治哲学だ」と述べて事が新聞で報道され、反原発グループから猛烈な反撃があった。
真意は判らないが、当時、公害問題で火力発電が行詰り、原発容認の流れにあっったことは確かで、その流れに乗って口を滑らせたのか、ともかく原発建設積極派であったことは確かで、福島第一、第二原発誘致に活躍し、いわゆる口利きで大いに潤ったとの噂は絶えない。
現知事の佐藤雄平氏は同氏の甥(実姉の息子)
佐藤雄平氏は大卒後、叔父渡部恒三議員の秘書を長年勤め、1998年第18回参議院議員選挙に福島選挙区から出馬、勿論渡部恒三氏の絶大なる後援があり当選。
2006年 佐藤栄佐久氏の知事辞任に伴う県知事選に出馬、自民党が擁立した弁護士の森雅子氏を破って当選したのは、叔父渡部恒三氏の力は大きかった。
原発建設決定
東電は慎重で県の提示した調査結果に難点があったので、東電は福島県に再度調査箇所を示し、詳しい調査を依頼した。
これを受けて1961年発足したばかりの県開発公社では初仕事として工業用水調査、航空撮影調査、地質調査などを実施した。
この原子力発電所建設計画は、本決まり前に大熊町、双葉町に伝えられており、1961年9月30日双葉町議会は誘致を議決し、10月22日大熊町議会が議決した。
更に協議は続けられ、最終的には旧陸軍飛行場跡地である、大熊町・双葉町にまたがる海岸台地に決定した。
福島第一原子力発電所建設計画が東電常務会でも承認され、本決まりとなった。
この地に決定した技術的な理由として僻地である事を最大の要件とし、更に開発後進地域で現地当事者の要望が多かったことを挙げている。
敷地の概況として、
「福島原子力発電所の立地点は、東京から北方約220km、原子炉の設置地点から最寄りの人家までの距離は約1kmで、周辺の人口分布も希薄であり、近接した市街地としては約8.5kmに昭和40年10月現在人口2万3千人の浪江町がある。」
原子力産業会議の報告書である。
原子力発電所設置の考え方として「万が一の原子炉設備の破壊事故により放射性物質の大気拡散時に周辺公衆に重大な災害を及ぼさないために発電所敷地を高い人口地帯から出来るだけ離す事を必要」としたからである。
この報告書が東京で出されたから別に問題視されなかったが、地元としてはいささか‘ムッ’とすることで、隣接する地元大熊町の人口7629人(当時)、7117人の双葉町、1万1948人の富岡町が、この説明からは完全に抜け落ちており、考慮の対象外だと説明しているようなもので、首都圏から離れていればそれで良しとする考えの表れだと判断する。
その他の表現でも過疎地、僻地が多用されおり、だから多少の事故なら心配する必要が無いとしていたらしい。その結果は最大の事故を起こしてしまった。
本発電所の立地点は相双地帯南部の海岸段丘地帯に位置し、急峻な断崖もある.地質としては下層に砂岩、その上層に富岡層に属するシルト岩が主体で、更にその上を砂礫からなる段丘堆積層が覆っているが、その層厚は不整合で、富岡層の層厚は200~400mである。
前面の海の海底地形は複雑な地形であるが、海底勾配が全体として沖合450m付近まで1/60の急勾配、それより沖合は1/130の緩やかな勾配になっている。海底の基層である泥岩の上に深いところでは2~3mの砂層が堆積し、水深が深くなると砂層の堆積は薄くなる傾向にあった。
この調査結果として報告されている地質調査には双葉断層に関する記述は全くないので、双葉断層の存在は判っていても、当時は未だ十分な調査が行われていなかったので全く影響はないと判断していたようだ。
また地震災害に関する対策はあっても、津波に関して波高5m位までで、平坦な海岸線である浜通りには津波はあり得ない、が共通認識だったらしい。
木村氏は、現在はいわき市だが旧四倉町出身、その四倉町で代々続く医院で、ご自身も医者であった。
知事としては地元いわき市の大合併を指導し、企業誘致に奔走した。
衆議院議員時代、東電の副社長だった木川田氏を訪ね、双葉郡への原発誘致を持ちかけている。その時は、東電はまだ正式には原子力発電所建設計画もなかったので話を聴く程度だったらしい。
木川田副社長は福島県伊達郡梁川町出身、実家は開業医なので旧知だったらしい。
戦後、先に述べた電力再編問題で各界から数々の異論が飛び出し、終始が着かなくなった時、松永安左右衛門氏が快刀乱舞と辣腕を振るったが、その時松永氏を助けたのが東電から出向として派遣されていた秘書課長であった木川田氏で、電力界の鬼といわれていた松永氏を唸らせるほどの活躍をしたらしい。舌を巻いた松永氏は、次世代の電力界を背負うのは木川田氏だと確信したという。
かくして知事になった木村氏と東電社長になった木川田氏は福島県庁内で再会することになった。
勿論、原子力発電所建設の候補地として双葉郡大熊町の旧陸軍飛行場跡地である。
東電としては事前に地元には悟られないようにして地質調査をしており、最大の懸案は地盤の問題で、原発の立地は地震に耐えられるかが最重要となり、専門の企業が調査し、結論として堪えられる地盤だと報告したらしい。
現在問題になっている双葉断層は、その当時は未だ判らなかった。また地震に関しては地層を入念に調査しているが、津波に関しては全く問題にせず、貞観地震(869年)も文献にあるだけで、現実としては考慮していない。
従って津波の可能性に対する調査も対策も執っていなく、海抜30メートルあった台地を削って岩盤に直接杭を打てるようにしてから工事を進めており、結果論に過ぎないが海抜30メートルあれば津波の影響は防げたかも知れない。
ともかく本命は双葉郡大熊町旧陸軍飛行場跡地となった。
用地買収
用地買収の当該地は大熊町の旧陸軍磐城飛行場跡地で、戦後これらの土地は民間に払い下げられたが、余り利用価値がない海岸段丘の荒れ地で、その一部は製塩のための塩田として活用するとして国土計画興業が買収したが、製塩業は一時的なブームであって、直ぐ下火になってしまい、国土計画興業が製塩のための工事を始めたが途中で放棄してしまい、そのまま放置されていた。
まさか後年、高額で東電が買収してくれるとは、いくら日本一の不動産業で名を馳せた国土計画興業でも見通せた訳ではないから、大西武グループの創始者堤康次郞氏の強運と言うべきで、原発誘致に関しては堤氏が最大の誘致促進派だった。
国土計画興業は堤康次郎氏が設立した不動産開発業で昭和初期国立市や小平市の西武グループの中核をなす会社でしたが、現在は「株式会社コクド」になった。
社長は創業者堤康次郎氏の三男義明氏、買収当時1963年頃は、1957年早大卒後、国土計画興業に入社、1965年に社長に就任しているから、買収に関しては交渉から調印まで重役として立ち会ったようだ。
この土地取引は東京電力と国土計画興業との直接交渉で行われた。
1963年12月1日より買収交渉開始、所用面積96万坪
○旧陸軍飛行場跡地30万5840坪
○一般民有地第一期30万1042坪 福島県開発公社が実務を執る
○一般民有地第二期31万7670坪 福島県開発公社が実務を執る
国土計画興業と東京電力とは直接交渉で買収が行われたが、一般民有地との交渉は大熊・双葉の両町合同開発特別委員会を造り、町長が表立って地権者との折衝にあたるのを基本方針にして交渉にあたり、それを町の特別委員会と公社がバックアップする。更には公社と町が共同で交渉に当たる、を基本としたが、地権者全員を公民館に参集を求めたところ、地権者全員が出席し、公社の説明を聴き、質疑応答と要望があった。
○放射能の安全性に関する懸念
○薪炭採草の喪失、代わりの国有林払い下げる
○開拓農家の営農経営の援助、代金以外の補償金
○買収土地価格の格差は原則として格差をなくす
○税関係では、特定公共事業の認定を受ける
○東電が直接買収した国土計画興業所有の買収価格と同一価格を確約する
開発公社としては交渉が長引けば問題が出て交渉が困難になるとの判断から1964年7月に大熊町地権者290名を公民館に集め、町長立ち会いで個々の地権者と折衝し、全員から承諾書を取り付けたが、金額に関しては低すぎるとの要望もあり若干の上乗せもあって第一期の買収交渉は1965年8月までに完了した。
更に双葉町の30万坪の買収交渉に入り、大熊町に準じた内容で1967年7月までに全てが完了した。
この二期に渡った約96万坪約320万㎡の買収には約5億円を要したと言われている。
この他にも宅地や付帯設備の用地として約8万㎡が買収された。
水田:110反
畑地:324反
山林原野:2688反
その他:18反
その他の交渉として漁業補償の問題があった。この海域は相馬沖と常磐沖の好漁場の中間にあり、この海域も好漁場であるが、小さな漁港しかなく、魚市場もないため地区以外の一本釣りや、小型延縄、刺し網など他地区からの入り会い漁船が多く、漁業権が成立するのか法的な疑問点が多く、大いにもめたが、発電所の沖合約5.4万㎡の海面の共同漁業権消滅として地元3漁業組合、入会漁業5組合、近隣1組合との間で合意が成立し、約1億円が支払われた。
1966年6月1日、造成工事着工、
1966年7月、原子炉施設設置願申請、同年12月設置許可、
1971年3月26日、原子炉1号機、運転開始
1979年の6号機運転開始まで、大工事が続き、全国から作業員が集まり、勿論地元も求人ブームに沸き、作業員のハウスと呼ばれた作業員用の宿舎が建設、増設、食事、仕出し、消耗品の販売、果ては紅灯の巷まで出現、原子炉建設を請け負ったGE社は多数の技術者が建設監督にあたり、家族も同伴したから大熊町にはアメリカ村まで出来上がった。
地元におちる金も膨大で、静かすぎた田舎町は突如湧き上がった好景気に酔い、有頂天になるのも当然の結果であるが、一過性の嵐のようなもの、来るのも早いが、去るのも早く、札束が舞った一夜の夢でしかなかった。
第一原発建設予定地の買収も済み、漁業補償問題があったが、この海域は相馬沖、磐城沖の好漁場の中間点にあり、この海域も好漁場であるが、沿岸に小さな漁港はあるが、市場がないため地区以外の一本釣りや小型延縄、刺し網等他地区からの入り会い漁船が多く、地元漁業権が成立するかどうか法的には疑問だが、この問題を巡り大いに揉め、発電所の沖合い約5.4万㎡の海面の共同漁業権消滅として、3漁業組合、入会漁業5組合、近隣漁業1組合との間で合意が成立し、約1億円が支払われた。
第一原発建設工事は、敷地造成は東電、原子炉の設置はGE社の「フルターンキィー契約」の方式で契約であったから、東電はGE社にプラント建設一式を発注した。
※「フルターンキー契約」:主に電源施設の海外契約に於いて、プラントの設計から建設に関する全ての役割を請け負い、完全に稼働可能になってから引き渡す受注形態
※「GE社」:ゼネラル・エレクトリック社、世界最大のコングロマリット複合企業本社アメリカ・コネチカット。
プラントの建屋設計については、アメリカ・Ebasco社が、基本・詳細設計を受注・施工を担当した。
従って原子炉設置の安全基準は、災害防止の基準としてアメリカの安全基準を適用した。即ちアメリカの自然災害の最大はハリケーン、トルネード(大旋風)に対する対策、テロ対策であるから、地震と津波対策は想定にはない。
この想定をそのまま日本に持ち込んでしまったから、非常用電源設備の設置は低地、あるいは地下の方が安全と考えた。タンクは小型油槽船の接岸の近くに設置するのが効率的と津波対策は念頭にない。
日本側もその点を危惧したらしいが、それなら引き渡し後に高台に移転すればよいものを、30数年の間、何も対策を執っていない。
津波の危険性は何度も指摘されたようだが、1000年に1度の危険性の対処は消極的で先送りされ、長い間安全神話だけが優先していた。
更に言えば3号機以降は国内メーカーの原子炉であるが、それでも補助電源設備を高台に施設しようとはしなかった。
従って、僅かな出費を惜しんで高台移転を行わなかった東電と強力に高台移転を指導しなかった保安院の責任は重大で、想定外の不可抗力だったとは単なる詭弁に過ぎないことになる。
東北電力・女川原発では、建設時の設計図とは異なり、現場の判断で、1段高いところに補助電源設備を設置したが故に、震源地がより近いところにありながら、津波の被害を免れた。また付近住民は津波を避けるため原発に逃げ込んだ。
稼働開始後も順調にいった訳ではない。1973年6月25日、放射性廃液漏洩事故から始まって、数多くの事故、データ改竄、虚偽報告等数々の事件・事故があった。
初期に建設された1号機の不具合が特に多くかったと記録されており、事故の詳細は原子力施設情報公開ライブラリーを参照したが、第一原発全ての原発に関して事故の余りの多さに驚いたが、本論では割愛する。
そして2011年3月11日となる。
敷地造成
敷地造成工事は、東京電力の施工範囲。原子炉に関する工事は全てGEのターンキー契約に分けられての契約だから、東電の指示でゼネコンが土地造成工事を請け負った。
・熊谷組:敷地造成、冷却水路関係、物揚げ場護岸
・間組:原石山骨材プラント
・前田建設:バッチャープラント、コンクリーブロックト
・五洋建設:防波堤
工期は1966年6月1日より1967年3月までの10ヶ月、
プラント施工工事は全て鹿島建設が請け負った。
現時点での関心は、このプラント建設に関し当初地震、津波等の自然災害に対してどのような安全基準で対策を講じていたのか、資料はどうだったのか知りたかったが、残念ながら各調査会社に分散して委託しており、僅かな資料しか入手できなかった。
通常のプラント施工工事であれば建屋設備の配置、建設作業に必要な用地を経済的に造成できる事が必要とされていたが、海岸段丘に建設する原子力発電所であるから、
(1)原子炉建屋の設置に適する場所であるかの検討。
(2)高潮、津波への危害を回避する。
(1)は地震対策であるが、その基準は強震(震度5)以上、150年に1度
烈震(震度6以上)400年に1度、最大でM7.5~8クラスを基準としていたので、東日本大震災のようなM9.0の大地震は全くの想定外であった。
考慮したのは1936年に宮城県沖で発生した金華山沖地震時の記録であるが、それを参考にして金華山の内側の地震発生機構を討議した。
耐震性
耐震性に関する解決策は強固な岩盤に直接杭を打ち込むことで耐震強化を図るもので、このため海岸段丘海抜約30m程度あったが1号機建屋を整地面より14mほど掘り下げ岩盤上に建設した。これは地震対策だけを考慮しており、津波に対する考慮していないから、14mも掘り下げてしまった。
(2)高潮、津波回避
防波堤
防波堤の設計基準は、海象調査や近隣のデータを基に検討の結果、設計波高6.5m(1/3有義波、周期16秒、波向東北東)を基準にしている。
港としての役割は、3000トン級の船舶の入港が可能なこと、そうすると水深6mが必要であり、港口100m、港内面積も計算できる。
(有義波:海岸で打ち寄せる波を観測し、一定の時間、波の高さを観測し、例えば一定時間内に100回の波の波高を観測したら、波高の高い順番に1/3を選び、その波高の平均値を計算したのが「有義波」の意味、波の高さはまちまちで、時には2倍の波が打ち寄せ場合が有り、例えば100回の波を観測すると有義波の1.6倍の波高の波が必ず1波ある。)
防波堤6.5mの基準は高潮、津波を考慮して最大6.5m(平均海面上)あれば充分に防げると判断したようだ。(日本港湾コンサルテング)
三陸地方には多くの津波の記録はあるが、浜通り沿岸では津波の記録は殆ど無い
○貞観地震 869年9月26日 M8.3~8.6 震度不明 津波10m以上 死者約1000人 震源地 宮城県沖、福島県沖らしい、特定できない。
○慶長三陸地震 1611年10月28日 M8.1~8.5 震度4~5 津波20m以上 三陸沿岸、陸前 死者約2000~5000人 震源地不明
○延宝地震 1677年11月4日 M8 震度不明 震源地常磐沖 津波発生、 小名浜、中之作、江名、豊間、四ツ倉 死者130人以上
○寛政地震(宮城県沖地震)1793年2月17日M8.0~8.4詳細不明
○天保地震 1835年7月20日 M7 青葉城石垣崩壊、城下町崩壊、 津波被害は発生した記録はあるが、詳細不明
明治以後は記録があるので省略するが、浜通り沿岸でも過去に津波が発生した記録はあるが、検証はしていない。従って防波堤6.5mの根拠は有義波高だけが基準となったと思われる。
今回の大津波は第一、第二原発付近の津波、波高は15~16mであり、富岡川、富岡港付近では最大21m超えが調査・記録されているから、予想の3倍以上の波高であり、まさに想定外の大津波であった。
想定外とは記録にないから、想定しないという暴論で、記録にないからと実際にないとは絶対に言えないことだし、過疎の地に記録なんかある訳がない。
貞観地震の記録として多賀城に古文書として残っていたが、学術書として利用されたが、津波の記録としてそれに基づく津波の痕跡調査はしていなかった。
10mを超す津波が海岸から仙台平野を1000m以上遡上したと推測されるが、ボーリング調査は行ったが、これは目的が地質調査で、津波の痕跡は「坪堀り抗」という幅広く穴を掘らないとその痕跡は判らない。
(東日本大震災後、津波被害の検証と同時に「坪堀り抗」の調査を行い、貞観地震によると思われる津波の痕跡を多数発見した。)
福島原発建設に関して耐震性は考慮されたが、津波に関して事前調査は殆どなされておらず、大波はあっても津波はないとする、前提で設計されたと思われる。さらに燃料運搬のタンカーに合わせて燃料タンクを岸壁近くに設置し、それに合わせて非常用発電施設を設置していたのが致命的欠陥となった。
これはGEが「ターンキー契約」方式の契約であったから、東電はGE社にプラント建設一式を発注した。このことは責任分担の明確化、工期短縮の思惑も有り、将来の国産化を見据えてのもので、GE社が主体となり東芝、日立、鹿島が下請けとなって工事契約を結んだ。
プラントの建屋設計についてはアメリカ・Ebasco社が基本・詳細設計を受注・施工した。
原子炉設置の建設設計に関し災害防止はアメリカの会社が受注したのだから本国での安全基準を準用したらしい。即ちアメリカの自然災害の最大はハリケーンとトルネード(大旋風)に対する対策、それとテロ対策であって、その思想をそのまま日本に持ち込んでしまったようだ。
日本の様に地震、津波の経験は全くなし、地震は一部カルホルニャ州にあるだけ。
その発想からして非常用電源設備の設置は低地あるいは地下の方が安全と考え、その通りにした。
日本側がそこに危惧を抱いていたのなら、引き渡し後に高台に移せば良いものを30数年以上も放置しておいたのは何故なのだ。
津波の危険性は何度も指摘され、非常用発電装置の高台移転は検討されたらしいが、1000年に1度の危険性の対処には消極的で、先送りこそ賢明な措置と見送ってきた経緯がある。
従って基本設計したGE社側には文句は言えない。地震や津波の危険性を指摘されながらも先送りして、長い間何の安全対策を執らず「安全神話」だけを流し続けてきた東京電力と監督官庁全体の責任で有り、怠慢であったことを責めるべきだ。
更に言えば3号機以降は国内メーカーであり、非常用発電機も増設したが高台に設置しようとはせず、矢張り低地に設置しているのだから、津波対策の発想は欠落していた。全てが日本側の責任による措置であって、後悔先に立たずの教え通りで、悔いても悔いても無念と虚しさがこみ上げてくるだけだ。
東北電力・女川原発では建設時、現場の判断で設計図より一段高いところに補助電源設備を建設していたために、震源地に最も近かったにも拘わらず、辛うじてだが津波災害を回避できた。
1号機の建設計画が公表された1966年当時、原子炉建屋建設を受注したのは鹿島建設であるが、GE社が元請け社であり、日本的な談合文化とは全く無縁で、応札はゼネコン各社が本気で見積もりを出し徹底的に叩き合いが迫られるから、鹿島建設内部では応札を敬遠していたらしいが、創業者鹿島守之助会長が、赤字覚悟で受注しろと命じ、JRRー1、JDPRの建屋建設をも赤字で受注しており、3回連続での受注は、日本最初の原子炉建屋建設であるから、GEから技術を学びたいという思惑があっての受注であったらしく先行投資だ。
さすが創業者の読みは鋭く、技術を習得した結果、その後の1989年まで日本国内での原子炉建屋建設はBWR19基のうち16基を鹿島建設が請け負うことになった。
原子炉、炉型正式決定
原子炉は、アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE)によって設計されたものを基本とした。1号機はGE社製
1号機原子炉:当初1970年10月にGEより東電に引き渡す予定にしていたが、実際に引き渡しを受け営業運転を開始したのは1971年3月であって約5ヶ月の遅れであった。これはGE社の工場で1969年にストイキが起き、約3ヶ月間操業が停止した影響で納期に間に合わなかったことによる。
このため発電機の取り付け作業には二交代制で行われた。この時の原子炉がスペイン公社に納入するはずの原子炉を、スペインでの建屋建設が遅れたので代わりに日本に納入したのだとの噂がながれた、が勿論真偽はわからない。
ただ、据え付け工事を急いだため不備があったらしい。
1971年3月26日、GEから東電へ正式に「キー」が渡され、1号機は公式にも運転に入った。
原発建設の資金は、原子炉購入資金としてGE社に発注する際に東電はアメリカ輸出入銀行からその都度借款を申し入れ資金調達をした。
1号機の場合は、GE社が主契約者であり、1967年5月、東電木川田社長が渡米し輸出入銀行総裁のもとを訪れ、借款を締結、3913万ドル、年利6%、償還20年であった。資金用途はアメリカ製品買い付けに限られた。
| 原子炉形式 | 運転開始定 | 定格電気出力 | 原子炉 | タービン | 建設工事費 | |
| 1号機 | 軽水炉 | 1971年 | 40.0万kW | GE | GE | 約390億円 |
| 2号機 | 軽水炉 | 1974年 | 78.4万kW | GE | GE | 約560億円 |
| 3号機 | 軽水炉 | 1976年 | 78.4万kW | 東芝 | 東芝 | 約620億円 |
| 4号機 | 軽水炉 | 1978年 | 78.4万kW | 日立 | 日立 | 約800億円 |
| 5号機 | 軽水炉 | 1978年 | 78.4万kW | 東芝 | 東芝 | 約900億円 |
| 6号機 | 軽水炉 | 1979年 | 110万kW | GE | GE | 約1750億円 |
福島第一原発工事
東電では大熊町と双葉町にまたがる敷地に原子力発電所を建設することを決め、1966年7月に内閣総理大臣に原子炉施設の設置許可申請を提出、同年12月に設置許可が出された。
この時の計画書では原子炉には沸騰型軽水炉(GE社製)熱出力122万kW、電気出力40万kW、
総工費384億円、敷地は太平洋に面した海岸段丘で標高30~35mの比較的平坦な台地 広さ約300万㎡
整地作業、防波堤、岸壁等はゼネコン各社、熊谷組、間組、前田建設、五洋建設、その他が請け負い、原子炉建屋は全て鹿島建設が請け負った(但し、第二原発4号機建屋だけは清水建設が請け負った)
主原子炉機器、タービン発電機等の主要機器、原子炉再循環系の主要部分、その付帯工事はGE社が元請けとなり、国内各社が下請けとなった。
下請け各社は、東芝、三菱重工、日立製作所、石川島播磨重工(現IHI)
総工費福島第一原発5020億円第二原発1兆2390億円。
日本全国で建設された原子炉54基、総建設費実費約13兆、消費者物価指数による現在価値に換算すると14兆5千億円の巨額になる。
甘い蜜があれば寄ってくるのは人の世の常、下請け、孫請け、ともかく仕事を受注したい企業は国会議員から村会議員、有力者の口利き料なる摩訶不思議な金弦(カネズル)に群がった。しかも公共事業の口利きは禁ぜられているが東電は民間企業、従って口利き料は何のお咎めなし。
地元企業はその点有利で、東電も地元懐柔策として地元有力者が係わる建設会社に対しては、「お約束事」として東電が直接仕事を発注してくれた。
一例を挙げると、双葉町に田中土建という会社があり、オーナーは双葉町町長を1963年から1985年まで6期も務めた田中清太郎氏で、町長任期中と原発建設と重なるのであるから特別に優遇するのは当然で、東電からの受注額は5億円にのぼったとのこと、裏を探り出して暴露しているわけではない。
田中氏の自著「追想、町長在職十二年の軌跡」の中の記述に誇らしげに約5億円の受注があったと書かれている。更に推薦文として元東電会長で日本経済界の重鎮平岩外四経団連会長(当時)が「田中氏は、その任期中福島第一、第二原子力発電所に係わる誘致に、地元の責任者としてご尽力されて参りました。(中略)感謝の念に堪えないところであります」という推薦文を贈って本の表紙の帯に書かれている。
その他枚挙は数限りなく存在し、ゼネコンは荒利20%あると豪語した位だから札束が乱れ飛んだのだろう。しかも幾ら経費がかかろうが、独占企業である電力会社は必要経費として電気料金に上乗せすることが出来る。しかも電気料金は主管庁の認可事項であるから、電力会社は発電所を建設し、電気を造るだけ、送るだけ、それで利益が保障される殿様商売だ。
地元はどうであったか。日本代表する大会社が主体とした大工事であるから、全国から作業員が集まり、勿論地元も求人ブームに沸き、作業員のハウスと呼ばれていた宿舎建設、増設、食事、仕出し弁当、消耗品の販売、果ては紅灯の巷まで出現しGE社の技術者が多数現場の据え付け工事で働いていたから、その家族も来日して大熊町にはアメリカ村まで出現した。アメリカの家庭生活は3ヶ月以上留守をすると離婚訴訟の要件になり、高額な慰謝料を負担しなければならないから家族同伴は常識だ。
地元に落ちる金もまた膨大で、静かすぎる田舎町に突如湧き上がった好景気の訪れに有頂天になるのも当然のことだが、一過性の旋風のようなもの、来るのも早いが、去るのも早い、札束が舞ったのは一夜の夢でしかなかった。
電源三法の魔力
電源開発に関し、電力に関する法に電源三法がある。
○電源開発促進法
○特別会計に関する法律(旧 電源開発促進対策特別会計法)
○発電用施設周辺地域整備法
以上の三法を指す。
これらの法律の主な目的は、電源開発が行われる地域に対して補助金を交付し、これによって電源開発の建設を促進し、運転を円滑に行えるようにしようとするもので、奥只見電源開発事業 の頃は未だ制定されてはいなかった。
終戦後のわが国復興のために傾斜経済再建法式では電力開発に全力を注ぎ、只見川・阿賀野川総合地域開発によって首都圏の電力を確保でき再建の第一歩が踏み出した。
再建の経済復興は順調に進み、やがて神武景気と称されるような成功を収めたるが故に、電力不足は水力発電だけでは追いつかず、1960年に入ると火力発電開発に比重を強めてきたが、さらなる危機は火力発電の方式が石炭から重油、LPGに移りながら、その生産地である中東情勢が不安定であり、さらにタンカー輸送でもホルムズ海峡、マラッカ海峡の封鎖問題、米ソ対立による第三次世界大戦の危険性、事実1973年にはオイルショックと言われる第一次石油危機が発生、イラン革命、米領事館占拠、イラ・イラ戦争、湾岸戦争、イラク侵攻と続き、現在もイランの不気味な動きに世界中が神経を尖らせている。
従って火力発電に大きく依存するわが国電力事情はその都度大いに混乱してきた。
それを受けて電力を火力発電から、他の何らかのエネルギーから生産しようと模索するのは当然で、思い至るのは世界的趨勢であった原子力、原爆の苦い思いとバスに乗り遅れまいとする心情の葛藤であったが、背に腹は替えられずリスク分散と政界、官界、実業界も原子力開発に傾いた。
電力は不足になってからでは生産するのでは追いつかない、事前に早めに手を打っておかなければならない厄介もので、電力消費の地である都市近郊では建設余地はなく、電力消費とは無縁な過疎地が適地になる。
さらに発電所建設が地域のメリットどころかデメリットの方が多い、だから建設反対運動が起きて当然と考えられた。
だからこそ反対運動が起きる前にアメを提示しようというのが電源三法の意義が此処にある。
発電所建設にはいろいろなデメリットがあるが、原子力発電には放射能漏れというとんでもないマイナス要因がある。だからこそ電源三法で大判振る舞いをして地域の反対運動を封じ込めようとする、が、案ぜられていたことが現実となってしまったが、後悔しても後にはもう戻れない、これからどう解決していくのか、故郷存亡の危機にある。
2004年度での電源三法交付金は約824億円に上がるとされている。うち、福島第一、第二原発を抱える福島県では約130億円、柏崎刈羽原発を抱える新潟県では約21億円、敦賀、美浜、大飯、高浜原発を抱える福井県は約113億円、玄海原発を抱える佐賀県が約100億円、六ヶ所村核燃料再処理施設や放射物管理施設を抱える青森県は約89億円となっている。
2002年までは交付金の使用用途は一部公共施設に制限されていたが、2003年以降は交付金の使途は地場産業振興、福祉サービス提供事業、人材育成等の事業への資金活用が認められた。
福島県内に交付された約130億の額は単年度当たりの交付金であって、1970年代初頭から原発を立地してきた福島県の場合、1974年に制定された「電源3法交付金」の累積額は巨大なものになる。
さらに原発が稼働した後は、固定資産税、事業税等が長期間税収として約束されたものだから、町の税収も約束された額だから予算も立て易く、町の事業も意欲的に取り組むことが出来た。 資源エネルギー庁のモデルケースとしての試算によると、最新型の原発を誘致した場合、その基礎自治体は45年間で2455億円もの巨費を受け取ることになる。
ただし、交付金の額は一定ではなく原発の着工から運転開始までの7年間が総額433億円だが、それを過ぎると、8年目以降は前年の4割程度に削減される。
そうすると思わぬ高額の補助金があった自治体は例外なく公共施設建設に走り、維持費が増大する頃、補助金は削減されるから自治体の方から2号機、3号機の建設を同じ所に増設を願ってくることになる。
国、電力会社にとってはうまい方法で、政府中枢には凄い知恵者がいるものだと感心する。これが原発立地依存症の本質で、小さな自治体程陥り易いアリ地獄になるが、まさにその通りになってしまった。
双葉郡の狭い地域に双葉町と大熊町の福島第一原発。富岡町と楢葉町に福島第二原発。広野町には東京電力火力発電所が立地し、まさに発電所ベルト地帯となった。
平成21年度総務省財政力指数。全国平均0.55、福島県0.44、双葉町0.87、大熊町1.50、富岡町0.92、楢葉町1.12、広野町1.25。ところが同じ双葉郡内でも原発、火力発電が立地していない川内村0.27、浪江町0.47、葛尾村0.14、飯館村0.24、(相馬郡)全国平均0.55をも大幅に下回っている。これだけの格差があると町村合併による双葉市構想も画餅になったし、交付金が各町に交付されたため地域全体で取り組まなければならない総合開発も夢として終わってしまった。
県の計画としては広野町から浪江町までをアトムポリス計画を策定している。これは原発関係建設労働者が建設終了後 (1)農業に戻れるようにする。(2)豊富な電力を利用しての工場を誘致して地元の雇用活性化を図る。(3)東電の原発運転要員を地元の人材に委ねることを働きかける等を決めていた。
他所の例を見ると北海道電力唯一である泊原発がある泊村の財政力指数は1.17原子燃料サイクル施設などの原子力施設がある青森県六ヵ所村1.17、東北電力女川原発のある宮城県女川町1.41、 日本原子力研究開発機構、日本原子力発電所等数多くの原子力施設のある茨城県東海村は1.78、東京電力柏崎原発のある新潟県刈羽村1.53、北陸電力敦賀原発のある福井県敦賀市1.11、九州電力玄海原発、玄海町1.49、全国平均0.55を大幅に上回り、2倍以上の町村もある。
福島第一原発
1号機 1971年3月26日
2号機 1974年7月27日
2号機が運転開始時点までは、電源三法による原発地元町への交付金は制度化されておらず、原子力発電所建設による経済的メリットは当初は大土木工事による地元雇用の増大、全国から集まる作業員の宿舎、消費財の売り上げ、法人、固定資産税収の増加等、この地方始まって以来の好景気に沸いた。
そして電源3法の交付金が制度化されたのが、F1の3号機から6号機まで、1988年までで双葉町23億5000万円、大熊町13億8600万円、楢葉町7800万円、富岡町3億7000万円などとなっており、総額では62億600万円であった。
町の税収が福島県内でも最低クラスにあった大熊町が、1976年には地方交付税非交付団体になり、基準財政需要以上の税収があり、逆に県に納入する状態になった。

だが1981年には発電所関連の固定資産税が長期低落していく先細りになることは承知しており、町として財政調整基金として30億円を積み立て、ポスト原発を模索し、工場団地整備に力を注いだが、誘致に応ずる企業はなかった。
町の予算規模は、昭和44年度2.8億円、48年度8.2億円、50年度21.2億円、56年度42.6億円。50年度予算は原発関係税収が90.7%を占めた。
電源三法では昭和49年~58年間で25億円が入り、そのうち11.4億円をかけて道路を整備した。
原発関連の固定資産税の収入は昭和57年がピークである。固定資産は15年間で償却されるが、改修が繰り返されるのでゼロにはならない。
財政調整基金30億円を積み立てているが、再び交付団体に転落するだろう、と予測されていた。
公共投資
総合スポーツセンター、町営グランド3ヶ所、農村改善センター、文化センター、宅地造成、町営住宅建設等

双葉町
1980年以降 財政指数は1.0を超え、1982年には2.02を記録したが、近い将来固定資産税減少、交付金打ち切りは判っており財政調整基金として積み立てを開始したが、道路整備、箱物行政等両町が競い合うように公共投資に力を入れた。
交付年限を区切っていた発電所関連の交付金が打ち切られ、固定資産税収入低下した1990年、未だ世間はバブル景気を謳歌しているにも拘わらず、1990年、双葉町は財政力指数が1.0を下回ってしまって交付団体に転落したのだから、余りにも短い豊かな時代であった。
町の予算規模、昭和47年度、1.0億円、49年度3.6億円、50年度16.60億円、57年度23.0億円、と10年間で23倍強の急増。
原発関連税収が町予算のそれぞれ8.2%、27.1%、84.9%、84.4%を占め、昭和55年以降、財政指数が1を超え、57年には2.02となったのだから、超健全財政となり全国的に見ても高位にあった。
しかし好事魔多し、夢実現のための豪勢な公共施設投資へ走りすぎてしまって、早くも平成2年には財政力指数が1.0を下回ってしまったのだから唖然とする。
更に1985年まで続いた田中清太郎町政では、1981年から始めた町の下水道工事で大幅な赤字を出し、穴埋めに町予算の付帯工事費名目で支出して秘密裏に処理しようとした事が発覚、警察の捜査が入ったが逮捕はされなかった。
この下水工事を請け負ったのが田中土建で、オーナーは町長自身であったから騒ぎは大きくなり、町民の信用を失い辞任した。
1985年 町長選挙で選ばれたのが岩本忠夫氏で、この人はかつて原発誘致反対運動のリーダーで、後に県会議員を務めたが、落選後は家業に励んでおり、後援者から是非町政を預かってくれと懇願され町長選に出馬し当選した。
町長に就任したときは反対運動の面影は全くなく、反対に7、8号機建設推進の旗振りを始めたので前の活動を知る人々は唖然としたらしい。しかし、1991年(平成3年)9月25日、双葉町議会は原発増設要望を議決した。
現在原発1基で1兆円相場と言われており、そうすると国や電力会社は1%程度の地元見返りがあるという.それが2基となれば町の予算の何年分になるのか、そうすればまた豊かな町財政になる。一度味わってしまった甘美な酒に酔い、工程上の7、8号機運転開始を念頭に公共事業実施ベースを落とさず、先行投資を続けてしまった。
ところがバブル崩壊、電力消費の落ちこみ、東電の虚意の報告、トラブル隠しが次々と明るみに出て、その対応に追われるまま7、8号機建設は先送りされ、結局「捕らぬ狸の皮算用」になってしまい、負債だけが残った。
2008年(平成20年)双葉町は福島県内で財政状態がワーストワンの汚名を着ることになった。
この小さな町にいったい何が起こったのか?
戦後最大の電源開発を行った奥只見は半世紀を経た現在どうなっているのか、火力発電、原子力発電と推移していく中で只見川流域の町村は過疎化が進み、医者までもがいなくなってしまった。
福島県内で最高に恵まれた財政になった同じ町が二十数年後には最低に落ち込んだのだから、まさに中毒症状だったといえる。
2005年 井戸川克隆町長に代わり、財政政策立て直しのため超緊縮財政にし、町長の給与ゼロとして頑張ってやっと2010年度決算で実質公債比率を25%以下にしたが、事故が起きてしまった。 事故災害時には陣頭指揮に立ち、埼玉県に避難、仮町役場を埼玉県に移し、国との折衝等活躍したが、町民との軋轢が生じ、その後町長を辞任した。
公共投資、役場庁舎新築・周辺緑化、中学校1、小学校2、鉄筋コンクリート新築、コミュニティーセンター1、地区公民館・分館5、老人福祉会館1、プールや体育館、夜間照明のある町民グランド、図書館、「ヘルスケアふたば」。

富岡町
予算規模だけを検証する。
昭和49年度2.8億円、52年度8.2億円、56年度41.5億円と増加した。
56年度の税収は44.2%が電源三法による交付金、町税は23.5% 昭和60年以降15年間は第二原発の固定資産税が入ってきた。
日常的にも立地基礎自治体では電気料金が大幅に割引され、原発立地の元地主には特定の商売の独占権が与えられ、地元の人々に就職の機会が与えられ、下請けの仕事も増えた。飲み屋も商店も潤った。景気の良い話ばかりが満ちあふれると、いつかそれが当然事のように感覚が麻痺して、大企業である電力会社の城下町として出稼ぎからも解放され、人口は増え、町は繁栄し、住民は安定した日常の生活に満足した。

楢葉町
双葉郡内最大のコミュニティーセンター、町総合グランド、天神岬スポーツ公園等を建設、維持・管理費だけでも年一億円以上になる。
2012年度、電源立地地域対策交付金 大熊町:19億円、双葉町:8億2千万円、富岡町:10億5451万円、楢葉町:8億2千万円。4町の交付金と固定資産税の合計97億3594万円、予算の42.9%を占める。
事故後も歳入の4割強を原発マネーに頼ることになる。
廃炉
福島第一原発の1~4号機は廃炉が決定したが、未だ沈静化したわけではないから工事開始は先のことになる。1~3号機原子炉内に1496体、1~4号機の使用済み核燃料プール内に計3106本の核燃料があった。
原子炉内の燃料は「デブリ」(塊の残骸)と言われ、金属などと混じり合って固まったとみられる。燃料は1体約300キロ、散らばった放射性物質の塊約450トンを遠隔操作で切断、回収するには高度な技術を要する。
未知の技術が多く、これから技術開発しながらの作業が多くなる。
原子炉の廃炉解体によって生ずる廃棄物は、110万kw軽水炉としての廃棄物の総量は50~54万トン、そのうち放射性廃棄物は1万トンと見積もられる。これらも放射能レベルに応じて処理しなければならない。処理費用は1機1千億円程度が見込まれ、約40年の歳月が見込まれる。
関係自治体は「廃炉交付金」の創設を国に要望している。
この幸せをもたらした電源三法交付金の趣旨は、原発を受け入れる自治体に多くの補助金を交付することによって原発建設を促進することを主眼として1974年6月田中角栄元総理が策定したものだ。
その財源はどうやって捻出したかというと、さすが錬金術の達人田中首相は電源開発促進税として電力会社か販売電力量に応じて促進税を徴収し東電管内の標準家庭の場合、電気料金6650円のうち116円が促進然として徴収され、それを特別会計の予算としてプールし、発電所自治体には「電源立地促進対策交付金」という「迷惑料」を支払い黙らせることになる。
原発1基当たりの交付金として、建設から運転開始までの10年間、約450億円、運転開始から35年間、約750億円、総額約1200億円
経済成長期でしたから、電力消費は右方上がりで販売電力量は増え続け、従って促進税収入も増え続けるのであるから国、電力会社とも投資意欲は旺盛となった。
1956年(昭和31年)頃から、もはや戦後ではない、という言葉出るくらい戦後復興は順調に進み、戦後しばらくの間は焼け野が原で住民もそれほどいなかったが、住宅も回復し首都圏に急に人が集まりだし、産業も復活、工場群も動き出した。
東電の販売電力量は1960年(昭和35年)222億kw/hだったが、僅か10年の1970年(昭和45年)には700億kw/hを超え、約3倍強に膨れあがった。
電力会社の収入は膨らむが、反対に電力不足が懸念されその対策が急務となる.ところが水力発電は全国的に見ても開発され尽くされて既に適地なし。
火力発電社はその頃急速なモータリゼイションで車の排気ガス問題とあいまって
火力発電が石炭、石油などを燃料とするため窒素酸化物を排出することが問題となり、光化学スモックの原因だと世の糾弾を受け、火力発電所建設は著しく困難になった。
東電の電力供給エリアは東端が茨城県、千葉県、西端は静岡県富士川の東側で伊豆半島、神奈川県となる。(50Hz)
残るは原子力発電所だが建設予定地の探索は前に述べたように双葉郡に収斂した。
原発が密集しているのは、双葉郡ばかりではなく、日本で最高の原発銀座は、福井県の若狭湾沿岸一帯、敦賀市内に関西電力の原発2基、日本原子力研究開発機構の「もんじゅ」と「ふげん」(解体中)。若狭湾沿岸市・町、関西電力の美浜原発3基、大飯原発4基、高浜原発4基が並び、双葉郡の10基よりも多い。
両地方の共通点は、めぼしい産業がない、農業が主体としても稲作以外に特産物なし、出稼ぎの常習化、若者の流出、出口のない閉塞感。
そこへ降って湧いたような、美味しい話、飛付くのは当然でしょう、となる。
電源三法交付金:電源開発促進税法などの「電源三法」に基づき、計画段階を含めて、発電所の立地自治体や周辺に国が支払う交付金。
原発の立地促進を目的として、1974年に創設された。一般的な家庭で月約10円が電気料金に上乗されている。
資源エネルギー庁の試算では、出力135万kwの原発を新設する場合、環境影響評価から運転開始までの10年間で約480億円、その後の40年間で約480億円支払われる。
今年度予算額で全国の自治体に配られる交付金は、補助金を含めて1318億円。
具体的にみると、電源三法による電源立地促進交付金、1974年から1984年の10年間に大熊町26億円、双葉町33億円、隣接町村にも同額交付された。また、電源施設など周辺地域交付金が1981年から1994年まで大熊町10億円、双葉町8億円。
更に毎年確実に入ってくるのが固定資産税、この中には設備投資額の約10%にあたる償却固定資産税が15年間にわたり償却に応じて地元自治体に入る。従って運転開始年度が一番多く、償却に従った減少することになるが、設備の改善、更新、付帯設備、増設が続くので途絶えることはない。
土地、建物の固定資産税は実質的には存在する限り半永久的な収入源だ。
1996年度の町税収、大熊町、原発関連固定資産税21億円を中心として、個人、法人の町民税を全て併せると約25億円。大熊町町税調停額37億円の65.6%を占める。最高額は1975年度90.7%が原発関連の税収であった。
同じように双葉町は13億円で町税調停額19億円中67.5%が原発関連である。
電源三法の施行は1974年3月だったので1・2号機はその前に運転開始であったので、満額は適用されなかった、が、その後は全て適用された。
第二原発の富岡町・楢葉町は電源三法の恩恵を満額享受した。
豊かな財政のためこれらの町に地方交付税は交付されていない。ところが電源三法交付金は使途が制限された故に、町民の生活とは直接的に関連しない図書館、体育館、資料館等々のハコモノが続々と建設され、町のシンボルとなったが、ハコモノは維持管理のカネクイムシ、やがて町財政を圧迫することになったのだが、町民の生活も原発建設の大工事が始まると、全国から土木工事関連の関係者が集まり、地元は一大ブームに湧き、関連の仕事が増え、当然ながら町民の所得水準も上昇、1号機建設時はGEが「フル・ターン・キー」の全面請負であったため、アメリカから多数の技術者が来日してアメリカ村まで出来たのだから、貧しいながらも平穏な生活をしていた町民にとって天変地変の一大事件であった。
運転開始からも住民は原発のお陰で多くの人々が雇用される機会があった、第一原発では最大6000人が働き、敷地内には関連企業の事務所が30社もあり、その他下請けが300もあったという。出稼ぎの必要がなくなった、若者の流出が止まった、商業面も発展した、転入人口も増えてきて町に活気が蘇った、当然町民の所得も県水準を大きく上回って上昇、県でも最高水準にランクされ、地域経済も上昇、誠に結構だらけの面も満ち溢れていたのも事実で、企業城下町、東電様のお陰です、との思いも強かった。
双葉町を例に挙げ、その内情を探ると、町の浮沈は財政力指数をみれば歴然とする。税収など自前で賄える財源の指数と、町として最低限必要なサービスを賄える状態のバランスを指数1.0とすれば、これを満たす税収がなければ地方交付税が交付される。逆に超えれば余剰財源ありとして、不交付団体とし裕福団体となる。
1963年、原発建設前の双葉町の財政力指数は0.23、税収は必要経費の1/4しかない極貧町であった、が、工事が始まり電源三法の交付金が入るようになると、財政力指数は1.0を簡単に超え、1980年にはなんと財政力指数が驚異の3.73に跳ね上がって、超富裕団体になった。詰まり単年度の税収で、3年半以上の財政が賄える、超セレブ町になった。
町の税収は23億円、その内固定資産税は15億円、さらに電源三法による交付税があれば町、或いは町民は豊かな財政を背景にしてハコモノやあらゆる新設、整備の要求、町議会も同調、俄成金の陥る方程式に嵌まってしまった。
一時的に収入があっても当然ながら年々減らされ、気が付けば早くも1990年には財政指数力が1.0を割り込んでいたのだから早すぎる転落だった。
通常の自治体であれば交付金があれば賄えるが、豊かな財政で整備したハコモノが足枷となって、何にも無かった町が何でもある町に変貌した結果の悲劇だ。
そこで町議会は7、8号機の増設、プルサーマルの増設と大変なポテンシャリティを内包しており、これを活用すれば再び活気に満ちた町に蘇ると、建設誘致を議決、国が想定していた通りのアリ地獄に堕ち入っていた。
東電は、1度は快諾したが、長引く不況で、電力消費は伸び悩み、建設計画は凍結したままとなって、町財政は困窮に陥っていった。
乱気流に巻き込まれたような町造りであったかも知れない、身丈に合った牛の歩みに似た息の長い歩みがあったはず、歴史に学び、まずその基本は‘知育’にあり、人を育て、人が町や地域を牽引し、またそれを繰り返す、人材の育成こそが地域振興の基本。
戦後の日本が再興できたのは、物質的な資源があったからではない、人材という資源があったからこそであって、最大の資産は人間にあり。
将来は、世界有数の原発地帯になるはずだった双葉郡であったが、地域住民は消え、虚しく‘空の城’だけが朽ち果てる地帯になってしまった。
 |
 |
 |
|
第30章 磐城飛行場
双葉郡熊町村大字夫沢字長者ヵ原という海岸に近いやや台地になった荒地があった。

帝国陸軍部は飛行機の活用に目覚め1935年〔昭和10年〕熊谷陸軍飛行学校を創立、陸軍飛行隊の操縦士育成に本腰を入れた。
この熊谷飛行学校を中心として大刀洗飛行学校、白城子飛行学校、宇都宮飛行学校の3校を分校にし、飛行兵科幹部候補生、下士官候補生の育成にあたった。
昭和12年、盧溝橋事件以来中国大陸で戦火が拡大し、どこまで続くぬかるみぞ、といわれた位の戦線拡大に頭を悩ましていた陸軍はその頃やっと飛行機の有能性に着目し、その拡充に積極的になった。(陸軍は飛行機(陸軍飛行隊)、海軍は航空機(海軍航空隊)と呼称した)
 |
長者ヵ原飛行場若しくは磐城飛行場に関する大半の資料は海軍航空隊所属と解説してあり、陸軍としてあるのは少数なので、防衛省資料保管室と戦史編纂室を訪ね資料を拝見し、かつ熊谷飛行隊戦友会に所属しており、元特攻隊員として磐城飛行場で訓練中に終戦になり、生き残った操縦士(陸軍少尉)の方を訪ねましたが、高齢のため記憶が薄れてしまっていましたが、戦友会の機関紙を拝見させてもらいました。
 |
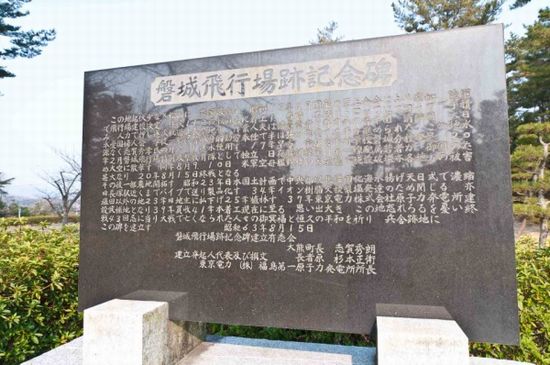 |
その資料に基づきます
1939年(昭和14年)6月、熊町村夫沢海岸段丘焼約3,000haが飛行場用地として軍命令による買収命令、民家11戸が移転。
帝国陸軍熊谷飛行隊磐城分校として滑走路建設
当時の土木建設は人力によるものでツルハシ、スコップ、モッコ等、軌道によるトロッコが主流で、作業員は請負人夫、地元青年団、消防団、大日本愛国婦人会、一般民勤労奉仕団で半ば強制的に勤労奉仕を義務付け、滑走帯1,300m×1,200m当時の練習機飛行場は全面芝生で滑走路はなかった。
1941年4月、滑走帯完成、熊谷飛行隊の宇都宮飛行学校、磐城分校として開校
飛行訓練が始まる。約60機の練習機が配置された。
 |
| (九五式1型練習機) |
1945年2月、磐城飛行場特別攻撃教育隊として独立教育隊に昇格。
沖縄戦に対応する特別攻撃隊の操縦士養成の教育隊
3月には練習機を集結させ約100機で猛烈な訓練をした。
1945年8月9日、10日の2日に渡る艦載機多数による集中攻撃により完全に壊滅した。
陸軍飛行隊操縦士の養成機関の一つに陸軍宇都宮飛行学校があったが、養成人員が拡充されたため、宇都宮飛行学校の分校を造ることになり、飛行訓練だけの飛行場を作ることを決定し、その場所を選定したところ、大熊町(当時は熊町村)の海岸にある荒地に目を付け、昭和15年4月陸軍飛行場建設が決定された。

長者ヶ原にあった農家11戸が移転させられ、トロッコ、つるはし、シャベル等により地元の農家、青年団、消防団等が勤労奉仕として建設に参加、昭和17年早春完工、陸軍飛行隊宇都宮飛行学校磐城分校(長者ヶ原飛行場)として発足、95式中間練習機(機体が明るいオレンジ色の布張、翼が二枚翼だったので俗称赤トンボ)が初期には60機が配備され訓練に励み、特別攻撃隊訓練隊に昇格してからは指定されてからの最盛期には95型1式、95型3式が総数約100機位の練習機が配備され前期練習生の訓練が行われた。この赤トンボは練習機としては性能が良かったので陸軍飛行隊初期練習機として広く採用された。
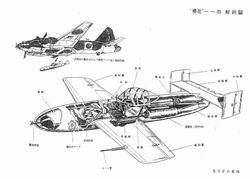 |
 |
敗色濃くなった昭和20年2月、陸軍特別攻撃隊編成のための訓練が始まり、磐城飛行場特別攻撃隊教育隊として独立した陸軍飛行隊となり、95型1式機に加え95型3式機が配備されて総数100機位が準備され、特攻隊要員として国家総動員令により大学、高専に在学中の学生が、特別幹部候補生飛行見習士官として入隊、この磐城飛行特別攻撃隊訓練隊に送り込まれ、隊舎が不足し近くの双葉中学(双高)の校舎が臨時の兵舎として徴用され、大勢の特攻隊操縦要員が送り込まれ、付近の小学校校舎を米航空母艦に見立て、急降下体当たりの訓練に励んでいた。
このうち一部の隊員は‘桜花’(人間爆弾)の乗員になるための訓練にまわされたとのこと、神雷部隊出撃の時の隊員の中に加わっていたかは不明。
体当たりの特別攻撃隊は昭和19年10月25日、フィリピン、マバラカット東飛行場を飛び立った神風特別攻撃隊敷島隊が最初で、編成は爆装ゼロ戦5機〔250k爆弾1個〕直援機ゼロ戦1機、編隊長〔1番機〕関行男大尉〔2階級特進中佐〕、2番中野磐雄1等飛行兵曹〔2階級特進少尉〕原ノ町出身〔旧制相馬中学卒)、レイテ沖の米機動艦隊に突入、空母セントロー炎上、後沈没、他にも戦果あり、これが神風特別攻撃隊による体当たり攻撃が最初であるが、全て海軍機が出撃した。何故なら当時の陸軍のパイロットは天文航法の教育を受けておらず洋上を飛ぶことが出来なかった。
これは不思議な話で、戦前対米戦争になれば3ヶ月でアメリカを屈服させることが出来ると豪語していた陸軍首脳は陸軍の飛行機は洋上を飛べない教育しかしていないのに気付いていなかったようで、主戦場になるであろう太平洋の存在を考慮に入っていなかったのか、どの程度勝つべき秘策があったのか疑問だが、実際は単に精神論だけで、対米戦争にたいする具体的な準備は全く出来ていなかったことになる。
ちなみにアメリカ陸軍のパイロットは洋上飛行の訓練は十分に受けており、海軍機のパイロットと同程度の技量があった。山本連合艦隊司令長官が戦線視察の途上で双胴の悪魔、ロッキードP38の襲撃を受け、搭乗していた1式陸攻が撃墜され戦死されましたが、このP38は陸軍機だ。
フィリピン戦では一部陸軍機も洋上攻撃に参加したが、四式重爆撃機と九九式軽爆撃機に限られたのは洋上航行可能な航法士が乗組んでいたのと、浜松陸軍飛行学校で艦船雷撃の訓練を積んできたからです。
ところが沖縄戦になると九州の基地を飛び立って開聞岳の上空で集結し編隊を組んで奄美列島の島伝えで飛べる地文航法なので洋上であっても飛行でき、特攻攻撃に陸軍の戦闘機隼、飛燕、も参加できるようになり、磐城飛行隊の飛行訓練も激しくなった。
この頃の操縦士養成は大半が学徒動員で建前は志願制であったが、実際は総動員令による強制的な徴兵であり、学業半ばで大学、高等専門学校の学生が引っ張り出され、速成の飛行訓練でやっと水平飛行が出来る程度で戦場へ送り出されたのだから人間爆弾となって体当たりを義務付けられた学生諸氏は国家のエゴの犠牲者でしかない。
 |
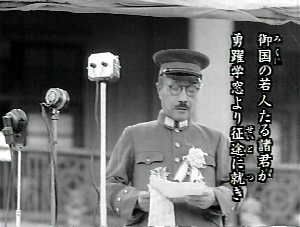
未だ一人前の操縦士になってない未熟なパイロットのまま洋上を飛び死地に追いやられたわけですが、敵艦隊が集結している海域近くまでベテランパイロットが操縦する戦闘機が誘導する作戦でしたが、対空レーダーが発達していたため、開門岳付近まで探知でき、編隊を組んでいる頃から機動艦隊に察知され、三段構えで邀撃戦闘機が待ち構えていましたから、艦隊上空に達する前に洋上に散華してしまった。
ですから作戦を変え、単機ばらばらに低空で散在する島々を抜けるような航法を執ったのですが、性能の悪い飛行機、松根油混じりの粗悪な燃料、250k爆弾を抱えてよたよたと飛行するまだ半人前のパイロット、まして洋上低空飛行は高度な技術を要しますから、それをあえて命令した上層部は単に人間爆弾、人間ミサイルとして考えていたようで、誠に痛恨極まりない至上命令であるが、上官の命令は陛下の命令であるとした職業軍人の思い上がりが悲劇を生んだ。
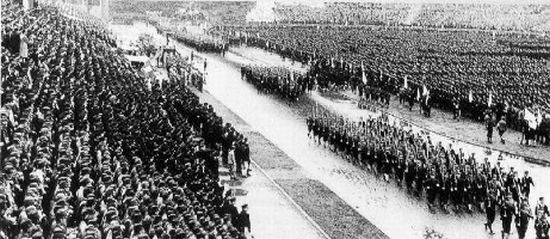 |
| (昭和18年10月国家総動員令により大学・高専の学生、陸・海軍に入隊) |
昭和20年4月のある日、富岡小学校に急降下の訓練をしていた赤とんぼ1機が、降下角度が入りすぎたのか、機首を上げるのが遅れ、校門の脇にあった大きな柳の木に翼が接触して仏ヶ浜の砂浜に不時着したことがあった。
教育訓練が終了すると、宇都宮、熊谷、明野基地等で実戦特攻機の操縦訓練を短期間行ってから九州の知覧特攻基地へ送られ沖縄戦へと飛び立って護国の盾となった。
富岡国民学校(小学校)の上空を練習機が編隊を組み、翼を振りながら南を目指し飛び去っていくのを校庭で懸命に手を振って見送ったことが今でも鮮明だ。
8月15日、終戦、双葉中学の兵舎では訓練中の予備学生と本チャンである上官との間で軋轢があり、日本刀を振り回しての騒動があったらしい、その時の刀傷が教室の柱にあり、当時から教師をしていた教頭の半沢先生が授業中、教室の柱の疵を示して教えてくれたことがあった。

幕末の池田屋騒動のような乱闘があったらしい。
また同じ頃、特攻隊員に選ばれ出撃命令が出ると、郷土訪問飛行が許可され(出身地の上空を旋回して別れを告げる)、富岡町出身のパイロットは前日富岡署に連絡が入り、警察から家族に知らされ、地上すれすれに飛び、我が家や小学校の上空を旋回し、パイロットの顔が見えるくらいの低空で、多分10代後半の若人だったのでしょう、やがて翼を振りながら南の空へ飛び去った。
1945年6月下旬頃、沖縄戦が終わると、空母を中心とした米海軍と英海軍の連合機動部隊が日本近海を遊弋、7月の初旬、危険を察知した磐城飛行隊は練習機を飛行場から夜ノ森公園の桜並木の下に隠すため、田舎道を人力だけで押してきたが、その人力は付近の国民学校の生徒をかき集めての作業で富岡国民学校の生徒も参加させられた。
 |
この桜並木の下に95式1型・3型練習機を1列に並べて隠し、飛行機の上には切ってきた木の枝を被せて上空から見えないように偽装した。
飛行場は空爆で壊滅した、が避難した練習機は無事でしたが、8月15日終戦、10月頃米軍の部隊がやってきて、ガソリンをかけて全機焼却処分にした。
あれからもう68年経った今日、再び襲ってきた災害に全町民は避難、無人の町でも春が来れば桜は満開、防護衣を纏っての観桜会?マスコミ取材の人?
満開の桜の下で美酒を酌み交わせる日がきっときます。
7月に入ると東北、北海道が攻撃の目標になった。
7月10日 B29重爆撃機による 仙台大空襲、仙台大炎上、焼け野が原。
7月14日 航続距離の関係でB29による空爆がなかった三陸沖から北海道に機動艦隊が押し寄せ戦艦群(サウスダコタ、インディアナ、マサチューセッツ)重巡洋艦(シカゴ、クインシー)駆逐艦9隻からなる機動艦隊
日本製鉄釜石製鉄所と釜石市壊滅
7月15日 北海道はそれまで空襲がなかったので室蘭市周辺には鉄鉱石の鉱山や炭鉱が散在しており、しかも良好な港湾があったことから工業地帯として発達し日本製鉄輪西製鉄所、日本製鋼所室蘭製作所等の重工業があり、戦略上も重要な地域とし港湾の入り口付近を要塞化し、陸軍の室蘭防衛隊隷下第8独立警備隊が15㌢カノン砲を配備し砲身を内浦湾に向けて万全の配備としていたが、米艦隊戦艦(アイオワ、ミズリー、もう一隻は艦名不明)の3隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦8隻の計13隻の主砲により艦砲射撃を登別方面から遠距離砲撃(戦艦主砲40㌢射撃範囲40km)を行い、1000発以上の砲弾が襲い、室蘭工場群は完全に壊滅、多数の犠牲者が出た。
陸軍防衛隊の要塞砲は砲身が内浦湾を向いていたため反撃することは出来なかった。米軍側は陸軍の防御要塞の情報を正確に把握しており諜報網がいかに凄かったか、ということになる。
7月17日 米第三艦隊戦艦16隻が日立沖に現れ2時間にわたって主砲40cm530発撃込み、7月19日から20日にかけて艦載機による焼夷弾13900発が投下され火の海となった。大機動艦隊空母16隻を中心として機動艦隊が太平洋沿岸を北上し、勝田にあった日立製作所の工場、常陸多賀と日立の間にあった大工場群が艦砲射撃で木っ端微塵に吹き飛んだ。
この機動艦隊が浜通り沖合を遊弋していたが、日本軍からの反撃は全くなし。
8月9、10日 磐城飛行場は艦載機による猛攻撃を受け全くの廃墟と化してしまった。(この飛行場跡地が福島第一原発の敷地になったが、建設工事中小型爆弾の不発弾があり、陸上自衛隊爆弾処理班が出動、処理したことがあった)
これは常磐沖から相馬沖にかけて米英連合の空母16隻を中心とした大機動艦隊が遊弋し、小浜の崖の上からは沖合の大機動艦隊が遙かに望見できたから、20海里(約35km~40km)以内位の沖合だったのでしょう。空母を飛ぶ立った艦載機は、即浜通り上空に達し機銃掃射、焼夷弾、小型爆弾による空襲を行ったが、軍事施設が皆無の浜通り沿岸町村ですから、もっぱら民家に対して機銃掃射を浴びせるだけ、住民は山に逃げ込んだので犠牲者は少なかった。
住民は山に隠れて我が物顔で飛翔する敵戦闘機に憎悪の目で眺めるだけ、中には日本刀や竹槍で突くまねで悔しさを紛らわせていた。
浜通り沖を遊弋していた大機動艦隊は艦載機による空襲を行ったが、艦砲射撃はなかったのは重要施設が皆無の純農村地帯であることを承知しており、艦砲射撃の必要は無いと判断したからでしょう。
川内村では艦爆の2機が飛来し焼夷弾を投下、藁葺き屋根だから一挙に燃え上がり十数軒が全焼した。
郡山空襲で被弾した英国海軍艦爆1機(機種は多分バラクーダ)が阿武隈山中に墜落、乗員二名(20歳前後の英国人学生が召集され操縦士になったらしい)は落下傘で無事降下、山中で寝ていたところを付近住民の山狩りによって捕らえられた。その時山狩りを行った警防団の人達は先祖伝来の日本刀と槍で武装しての山狩りであって、まさに江戸時代の農民一揆のような武装であった。
捕らえられてから富岡警察署に連行され、その後原ノ町にあった憲兵分隊に引き渡されたが、3日後に終戦でしたから多分処刑はなかったと思う。
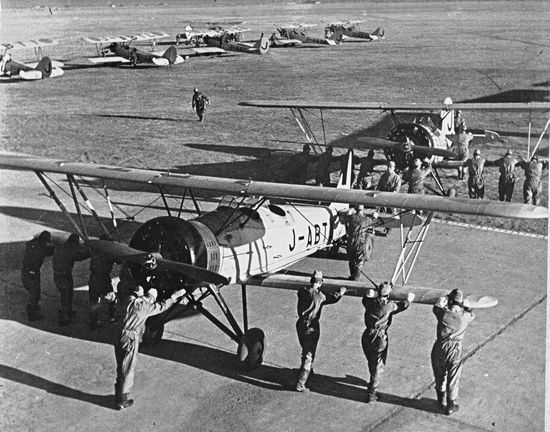 |
磐城飛行場は8月9、10日に集中爆撃と機銃掃射が繰り返され木造の兵舎、格納庫、その他の付帯設備は完全に破壊され、焼失した。8月15日終戦と同時に軍隊としての機能を失い、学徒動員の飛行訓練生から順に復員したらしい。
残務整理の隊員も9月中旬頃には全員が姿を消した。
荒れ果てた飛行場跡地は放置されていたが、瀬戸内海地方の塩田が空襲の被害を受け破壊されたため、全国的に塩が不足した。塩不足を補うため俄か製塩所(塩焚き)が急増したが、海水を直接焚く効率の悪い方法であったが、塩はでき上がり、これが飛ぶように売れたのだから物資不足は凄まじいものがあった。
これに目を付けたのが日本国土計画で、塩田を作り海水を天日干しにして濃縮、これを長塚駅前までパイプで送る事業を始めたが、より安価に製塩出来る方法が開発されたり、安価な外国産の塩が輸入されたりしたため直ぐに廃業となり。飛行場跡地は再び荒地として放置され、原発誘致の下地ができた。
磐城飛行場跡記念碑 碑文
この地起伏少なき松山に、農家散在す.昭和15年4月国家の至上命令により突如、陸軍で飛行場建設決定、住民11戸移転直ちに着工す。当時、工法はトロッコにスコップで手積み、人力で押し逐次軌道延長整地す。作業人夫は請負業者と郡内外の青年団、消防団、大日本愛国婦人会、学徒一般民等献身的勤労奉仕で半ば強制作業で工事が進められた。この地水源がなく志賀秀孝氏の井戸より送水使用す。
17年早春、宇都宮飛行学校磐城分校発足。20年2月 磐城飛行場特別攻撃教育隊として独立。日夜猛特訓を受け第一線配属若者が、御国のため大空に散華す。
20年8月9、10日、米軍空母艦載機の大空襲で施設破壊亦各地方の被害甚大なり。20年8月15日、終戦となる。
その後一部農地開拓す。昭和23年、日本国土計画で中部以北塩田化海水揚げ天日式濃縮で、旧長塚駅近くまでパイプで送り製品化す。34年イオン樹脂交換製塩発達のため閉じる。亦塩田以外の地23年旧地主に払い下げ25年植林す。
37年東京電力株式会社原子力発電所建設候補地となり、39年買収、41年本着工現在に至る。思い出大き、この地忘れるるを憂い終戦43回忌に当たり大戦で亡くなられた人びとのご冥福と恒久の平和を祈り、兵舎跡地この碑を建立す。

昭和63年8月15日
磐城飛行場跡記念碑建立有志会
大熊町長 志賀秀郎
建立発起人代表及び撰文
長者原 杉本正衛
東京電力(株)福島第一原子力発電所長
 |
| (九五式一型練習機) |
磐城飛行場に配備されていた練習機は九三式練習機が60機配備されたとありますが、93式は海軍の練習機で土浦にあった予科練で初歩練習機として使用されておりましたが、磐城飛行場は陸軍ですから、多分九五式練習機の間違いだろうと思い、防衛省戦史編纂室で調べ確認したところ、矢張り九五式一型練習機が配備されていた。
九五式練習機は、1934年(昭和9年)4月。陸軍飛行隊は石川島飛行機に対して、エンジンを換装することにより機体は同じでも初歩練習機にも中間練習機にもなる機体開発を指示した。
石川島では鋭意研究・開発を行い僅か5ヶ月の短期間で開発し同年9月には試作1号機を完成させ、続いて試作2号機、3号機を完成した。
木製骨組み合板・羽布張りの主翼と鋼管骨組みに羽布張りの胴体を持つ複座の複葉機で、脚支柱は直接胴体に取り付けられていた。
機体の色が橙色であったので、複葉機の形と相まって「赤トンボ」と愛称された。陸軍の審査により、試作3号機が合格採用され、九五式一型練習機乙型(キ9)として制式採用された。昭和10年から量産され、陸軍飛行学校に練習機として配備された。
太平洋戦争末期には九五式三型練習機になり、特攻機として使用するため色彩も迷彩化され、実際に爆弾を抱いて沖縄戦に突入した。
艦載邀撃戦闘機のスピードが600km/hの性能を持っているところへ、爆弾を抱えて飛行するが故に公式時速240km/hより遙かに遅い速度の練習機が突入するのだから悲壮以外なにものでもない。
磐城飛行場に配備されていたのは大半が九五式一型練習機で一部九五型三式が配備されていたらしい。記録は残っていないが、色彩が異なる複葉機が並んでいたのを望見した記憶がある。
九五型三式機は特攻機として沖縄戦で突入した記録が残っている。

スペック
全長:7.53m
主翼面積:24.5㎡
自重:900kg
全備重力:1,400kg
エンジン:日立ハ13 空冷9気筒エンジン350HP
最大速力:240km/h
乗員:2名(前席 訓練生、後席 教官)(操縦桿は連動)
生産機数 石川島 2,398機 + 日本国際航空 220機 合計2,618機
特別攻撃隊

特別攻撃隊とは、海軍・陸軍の航空機、小型艇、潜水艇等を用いて、敵艦船その他へ体当たりを以て攻撃することで、勿論生還する可能性はゼロの決死の攻撃。
海軍が最初に海軍航空隊が「一機一隻撃沈」を目指して戦闘機に250k爆弾を装備し敵艦に体当たりする攻撃を命じた。(当初は形式的な志願制)
1944年10月第五航空艦隊司令として着任した大西瀧次郎中将は、艦隊司令とは言え航空母艦は既に無く、陸上航空隊基地司令でフィリピンのマバラカット基地。稼働機数はわずか40数機の戦闘機があるだけになってしまった。
1942年6月 ミッドウィー沖海戦で第一・第二航空艦隊の空母4隻を一挙に失う大失態の敗北があり、それ以来艦船、航空機の喪失が続く大消耗戦に悪戦苦闘。
1944年2月 マーシャル諸島の陥落、海軍の基地トラック島が大空襲を受けた。
1944年6月 マリアナ沖海戦で、やっと再建した海軍航空隊が壊滅的損害を被り、台湾沖海戦10月のレイテ沖海戦で連合艦隊は壊滅敵打撃を受け、艦隊として機動する能力を失った。
しかし何事があってもフィリピンは死守しなければならない理由があった。それは東南アジアからの原油、その他の軍需物資を運ぶための輸送船の航路を失うことになり、継戦能力を失い、自滅しなければならない瀬戸際にあったからで、海軍は全連合艦隊を投入、陸軍は関東軍総司令官山下奉文大将をフィリピン方面軍総司令官に任命し、関東軍の大半を移動配備した。
 |
| (第一回神風特別攻撃隊(敷島隊) マバラカット基地から出撃、別れの水杯) |
従って、残された手段は「1機1艦撃滅」の特別攻撃しかなかったと言える。
それともう一つ、特攻攻撃を最初に命じた大西瀧次郎中将の心情には、これが最後の手段であって後はもうなにも無いことを最高指導者層とそれを越え天長に達し早期講和に傾いて欲しい、と現場指揮官として悲痛な叫びであったとも伝えられている。
しかし、上層部にはそのような心情を全く関知することはなく、聖戦遂行を叫び、全軍特攻を命じ、本土決戦、神国死守を叫び続けた。
従って特攻作戦は1944年10月25日、海軍は敷島隊特別攻撃隊に始まり、1945年8月15日、宇垣纏海軍中将座乗の自決特攻機出撃で終わった。
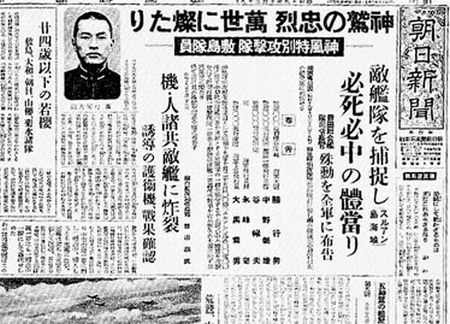 |
陸軍において特別攻撃作戦の導入を検討したのは海軍より早く1944年2月頃には本格的な検討が始まったと推定される。しかし航空本部長であった安田武雄陸軍中将は、特攻導入は絶対反対したが、3月に更迭され後任には導入賛成の後宮淳大将が任命された。この人事の策謀は東条英機陸軍大臣、参謀総長によるもので、東条の意を受けた後宮司令官は積極的に体当たり攻撃の可能性を研究させた。
1944年8月中旬には四式重爆撃機「飛龍」と九九式双発軽爆撃機を体当たり用に改修が極秘裏に進められた。

浜松基地で編成、訓練を受けた四式「飛龍」は富嶽隊、鉾田基地で編成、訓練された九九双軽の部隊を万朶隊と命名してフィリピン戦線に投入され、フィリピン陸軍飛行隊は第四航空軍で指揮官は富永恭次中将、東条首相の腰巾着と言われた位の側近であったが、19年東条首相が失脚し、富永中将も中央から追い出され、フィリピン戦線で陸軍特別攻撃隊の総指揮を航空軍に関する履歴も知識もない将軍を任命したのだから、軍の方針はどうだったのか、この将軍は航空に関する知識のない参謀を集め、軍人としての精神論だけに終始し、操縦士達の反発を買っていたが、反論は絶対に許されない上意下達の世界、命令だけが絶対であった。
1944年11月5日、第一回の特別攻撃万朶隊の出撃日であったが、出発直前米戦闘機の襲撃にあい、操縦士地上で戦死により中止。
11月7日 早朝 富獄隊初出撃、しかし戦果は未確認、鈍重な爆撃機であるから途中待ち受けでいた敵戦闘機の餌食なったらしい、教導機の掩護がなかったため未確認になってしまったが、戦後アメリカ側の記録にも何の記載もなく、途中で全滅したものと推測される。
その後、万朶隊、富獄隊の出撃があったが、海軍のような戦果はなかったらしい。しかも最後には富永軍司令官と参謀は残った飛行機で台湾に脱出してしまった。
勿論、フィリピン陸軍方面軍総司令官山下奉文大将には申告もなしの脱出で明らかな敵前逃亡である。
同じようにインパール作戦を自分で作戦立案、作戦遂行した牟田口廉也中将が失敗と判ると10万の将兵を置き去りにして逃げた例があるが、当然銃殺刑に値する、が、陸軍首脳はこれを予備役にした。これは罰どころか生かす為の温情であり、下級兵士なら銃殺を強行したが将官には大甘な温情だった。
ヒットラーやスターリンは多数の軍幹部を粛正、銃殺刑に処し、自決強要でかえって戦力が低下してしまった例もあるが、わが国では温情に終始した結果、兵士から猛烈な反感を買い、戦後になっても怨みは募るばかり、墓石がひっくり返す憂さ晴らしは近年まで続いていた。
1945年1月12日 在フィリピン陸軍飛行部隊、最後の特攻隊出撃
1945年1月25日 在フィリッン海軍航空隊、最後の特攻隊出撃
特攻出撃 陸軍202機 戦死者252名
海軍333機 戦死者420名
戦果:空母(護衛空母を含む)撃沈2、撃破18、戦艦撃破5、巡洋艦撃破8
駆逐艦撃沈3、撃破22、上陸用舟艇撃沈14、撃破53、
この数値は戦後アメリカ側の記録として発表したもので公式記録となっている。但し、アメリカ軍が蒙った損失だけで、その他イギリス海軍、豪州海軍、ニュージランド海軍の艦艇も参加ノしていたが、これらの海軍は損害を公表していない。
1945年2月19日、アメリカ陸、海軍硫黄島上陸作戦開始、硫黄島周辺艦船に対し特攻攻撃、千葉県香取基地第六0一海軍航空隊で編成、八丈島海軍基地に集結し、硫黄島周辺艦船に突入した。(映画、硫黄島からの手紙)
| 1945年3月11日 | 海軍鹿屋基地からウルシー環礁へ長距離特攻隊「梓隊」出撃、米空母1隻撃破 |
| 3月21日 | 第一神雷桜花隊出撃、「桜花」実戦初出撃、桜花15機 母機である一式陸攻機18機参加、途中待ち伏せた戦闘機により全機撃墜されたらしく、全機未帰還、戦果なし。 |
| 4月1日 | 連合軍沖縄上陸作戦開始 |
| 4月5~6日 | 菊水一号作戦開始、陸・海の航空機による全面的な特別攻撃開始、第二艦隊戦艦大和以下沖縄突入作戦、九州ノ坊岬海戦で沈没、第二艦隊壊滅、帝国海軍連合艦隊は消滅。 |
| 7日以後連日 | 特攻機が陸軍機は知覧基地から、海軍機は鹿屋基地から出撃、沖縄海域に遊弋する大機動艦隊に突入した。 |
| 5月24日 | 義烈空挺隊(陸軍)沖縄米軍飛行場に胴体着陸して空挺特攻が突入した。 |
| 6月23日 | 陸軍23軍司令官 牛島満中将、参謀長 長勇中将、共に摩文仁の丘で自決、沖縄戦の組織的戦闘は終る。 |
| 7月1日 | 第180振武隊が都城から出撃、陸軍沖縄方面航空特攻終わる。 |
| 8月11日 | 喜界が島より海軍爆戦隊2機が沖縄沖の艦船に特攻出撃 海軍航空隊の沖縄方面海域への特攻出撃終わる。 |
沖縄海域への航空特別攻撃隊:海軍 1,026機 戦死者 1,997名
陸軍 886機 戦死者 1,021名
| 終戦 8月15日 | 正午玉音放送 |
| 8月15日 | 玉音放送後の午後 海軍航空隊司令宇垣纏中将の命により大分基地から11機が沖縄向け出撃したが、自決の為の出撃で途中の岩礁めがけて突っ込み8機が自爆した。 |
 |
| (知覧特攻隊基地からの出撃、磐城飛行場で訓練を受けた特攻隊員は鹿児島県にあった知覧基地から沖縄海域に遊弋する敵艦隊へ向け出撃した。飛行場には付近の女学生が多数勤労奉仕に動員されており、桜の枝を振って見送った。) |
陸軍は少年飛行兵出身、将校は幹部候補生、特別幹部候補生、特別操縦見習士官出身者で、大学、高専の学生を徴集した速成の予備学生。
海軍の全航空特攻作戦に於いて士官クラス(少尉候補生以上)の戦死は769名、そのうち飛行予備学生は648名、全体の85%が予備学生であった。
海軍兵学校出身を温存し、予備学生は消耗品扱いであったことがよく判る。
陸軍も同じ扱いで航空士官学校出の操縦士は指揮官として地上にいた。
沖縄戦で突入した特攻隊機のうち陸軍機886機、戦死者1,021名
磐城特別攻撃教育隊で訓練を重ねた特別操縦見習士官であった予備学生の皆さんがどのようにして死地に赴いたのかを知りたくて防衛省戦史編纂室で調べましたが、記録としては残っておりませんでした。
8月9、10日の集中攻撃で兵舎、その他の建物は完全に吹き飛ばされてしまったし、最後の特攻基地であった知覧基地の記録を調べても臨時編成が多く、詳しくは記録されていません。しかし、特攻隊員として飛び立った操縦士の何割かは磐城飛行場で訓練を受けた人達であることは確かです。
“謹んで御冥福をお祈り申し上げます。”
その後フィリピン戦は日本軍の全滅でおわり、沖縄沖に米機動艦隊が集結、沖縄戦が始まった。
陸軍は台湾にあった第八飛行師団所属 誠飛行隊が中心となって特別攻撃隊を編成、福岡にあった第六飛行師団所属 振武隊が特別攻撃隊を編成し、鹿児島県知覧と都城の飛行場を特攻基地として、ここから特攻隊は飛び立った。
従って、磐城飛行場で赤トンボの基礎訓練を受けた後、宇都宮、熊谷基地等で、実戦機で訓練した後、知覧に集結、此処を最後の沖縄海域に飛び立った。
知覧には飛行場はなく畑になっているが、その一隅に特別攻撃隊記念館がり遺書や遺品が展示されている。
 |
海軍は鹿屋基地から飛び立った。〔現在、海上自衛隊基地〕
特別攻撃隊員戦死者(2010年8月までの確認)
海軍
・海軍航空特攻隊員:2531名
・特殊潜航艇(甲標的・海竜)隊員:440名
・回天特攻隊員:104名
・震洋特攻隊員:1,081名
合計:4,156名
陸軍
・陸軍航空特攻隊員:2,531名
・丹羽戦車特攻隊員:9名
・陸軍海上挺身隊員(マルレ):263名
合計:1,689名
四式重爆撃機について説明すると、重爆撃機というと米国機のB29のような4発の大型機を連想してしまうが、双発の爆撃機(三菱製)として設計されたが、飛行性能が良く、急降下爆撃も可能であり、後には雷撃装備も出来るように改造し、陸軍に属しながら海軍と共同して艦隊攻撃に加わるべく、その訓練を豊橋海軍航空隊と浜松陸軍飛行学校とで共同で行った。
その結果、1944年10月の台湾沖海戦には海軍航空部隊に加わって出激した。
従って陸軍飛行隊の中で洋上航法が出来る唯一の部隊であった。乗員は8名、航法士が必ず1名乗機していた。
双発の爆撃機であるから速度が遅く、邀撃戦闘機や対空砲火の餌食になってしまうため、夜間や薄暮の特攻を行ったが戦果は確認できなかった。
 |
九九式双発軽爆撃機:1937年10月、陸軍は九三式の後継機としてキ48の試作を川崎航空機に命じた。ドイツ空軍の急降下爆撃機の活躍をみた陸軍幹部は、この機を急降下可能な機体強度を持つことを要求したので、二型からはスノコ状のエアブレーキを装備し、急降下爆撃が可能な機種となり量産に入った。
非常に性能が良く、爆撃機でありながら滑走が短く、小規模の飛行場でも離陸可能なので最前線部隊に配属され、フィリピン戦にも投入された。欠点は搭載爆弾が少ないこと、燃料槽がむき出しで銃撃されると直ぐ火を吹いてしまった。
やがて特攻機として改造された。
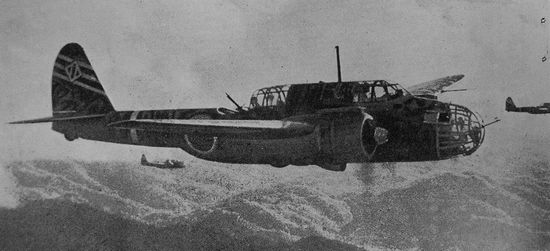 |
海軍機は戦闘機を特攻機としたが、陸軍機は双発の爆撃機を投入したのは洋上航法が可能であったことが条件となった。
特攻に使用した戦闘機には爆弾を抱えられるように戦闘機の下部操縦席の真下に爆弾を抱える装置を取り付けた。
陸軍九九式軽爆と四式重爆は爆撃機なので機内に爆弾倉があった。
九九軽爆は、爆弾倉は機体の腹部分が膨らんだように見えるが、これが爆弾倉で操縦士達は愛称として‘金魚’と呼んでいた。
この膨らんだ爆弾倉に爆弾を最大限積み込み、機首に3本の細い管を突き出していて、これが信管で爆弾と直結しており、体当たりと同時に爆発するように改造した。従って爆弾投下器は外された。
“敷島の大和心を人問わば 朝日に匂う山桜花”(本居宣長)
この和歌から編隊名が名付けられました。
敷島隊編隊長 関行男海軍大尉(二階級特進海軍中佐)
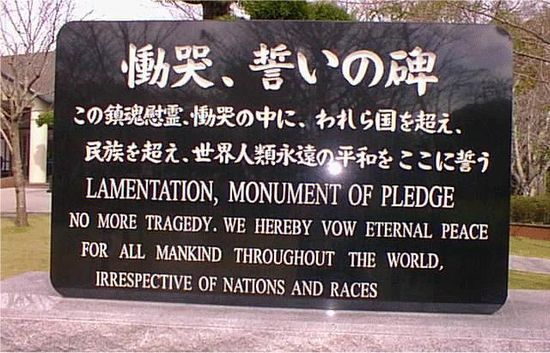 |
愛媛県西条市・楢本神社にある敷島隊の碑文
人類6千年の歴史の中で、神風特別攻撃隊ほど人の心をうつものはない。
「壮烈鬼神を哭かしむ」とはまさにこのことである。
この種の攻撃を行ったものは、我が民族を除いて見当たらないし、日本民族の歴史においても、組織的な特別攻撃は、国の命運旦夕に迫った大東亜戦争末期以外にはない。
 |
 |
憂国の至情に燃える若き数千人の青年が自らの意思に基づいて、絶対に生きて還ることのない攻撃に赴いた事実は、真にわが武士道の精髄であり忠烈萬世に燦たるものがある.神風特別攻撃隊第一陣は、第一航空艦隊司令長官大西瀧次郎中将(終戦時自決)の命により、昭和19年10月20日、敷島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊をもって編成、その指揮官が海軍大尉関行男であった。
この攻撃隊18機(うち半数は直掩隊機)は10月25日、出撃し、6機は敵護衛空母に命中し、3機は至近弾となって敵艦を損傷した。
中でも関行男大尉は敵の護衛空母セント・ロー(1万400屯)に命中、同艦は火薬庫の誘爆を起こし、艦体二つに折れて轟沈するという偉攻を奏した。
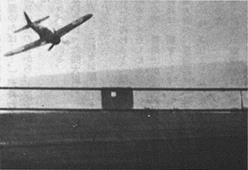 |
 |
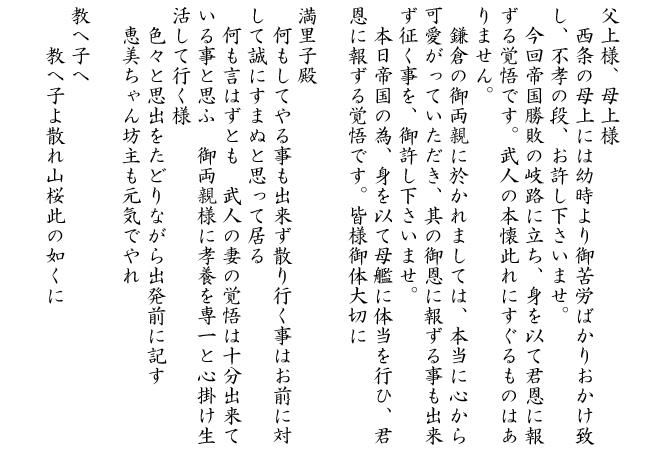 |
 |
フィリピン・ルソン島・マバラカット
神風東飛行場平和記念碑、碑文
本場所は、第二次世界大戦中、日本最初の神風特別攻撃隊が飛び立ったマバラカット東飛行場の跡である。1944年10月20日、神風特別攻撃隊は海軍中将大西瀧次郎により此処ルソン島バンバンガ州マバラカットに於いて創設された。
同攻撃隊の最初の志願隊員は、当時マバラカットに駐留していた日本帝国海軍第一航空艦隊・201航空隊に所属する玉井浅一中佐麾下の23名のパイロット達であり、敷島隊・大和隊・朝日隊・山桜隊の4隊に分けられ、関行男大尉が全体の隊長に任命された。
1944年10月25日朝7時25分、関行男大尉、2番機中野盤雄一飛曹、3番機谷暢夫一飛曹、4番機永峰肇飛長、大黒繁男上飛の敷島隊を率いてこの東飛行場から飛び立った。
同日午前10時45分、レイテ島沖の米機動部隊に対して同敷島隊は攻撃開始、関機が最初に米空母セント・ローに体当たりした。同艦は炎上、20分後沈没。他の隊員も全員体当たりを果たし、米空母カリニン・ベイ、キトカン・ベイ、サンティー、スワティー、スワニー及びホワイト・ブレーを大破あるいは中破させ、米軍に多大な損害を与えた。
成功裡に終わったこの最初の神風特別攻撃を掩護・誘導した西沢広義飛曹長(日本の撃墜王と言われた名パイロットによって目撃され報告された)
戦後、多くの戦争歴史研究者が関行男大尉を世界最初の人間爆弾であったことを公に認めている。
(注記)
マバラカット観光局(MTO)が神風鄭和記念廟の建立を推進させた理由は、神風特別攻撃隊の栄光を称賛するためではなく、その歴史的事実を通して世界の民族に平和と友好の尊さを訴える為である。
マバラカット観光局長 ガイ・インドラ・ヒルベロ

この碑はフィリピン・ルソン島・バンパンガ州マバラカット東飛行場跡地に建立されており、コンクリートの鳥居と廟があり、そこに碑があって英文と日本文で書かれております。
第二次大戦後、マバラカット東基地は放置され、一時放牧場になっていましたが、現在は畑地として開拓しているようです。
20年位前に訪れたことがありますが、飛行場としての痕跡は全くありませんでした。一隅に記念碑があり、最近コンクリート製の鳥居ができたようです。
 |
 |
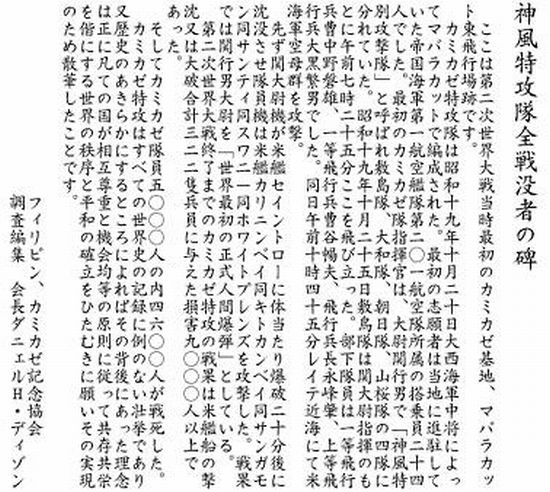 |

多分滑走路があった辺りにこの看板がありました。
もうひとつマバラカット西飛行場跡地がありますが、此処も日本海軍が建設、戦闘機が駐留しておりましたが、集中攻撃を受け、完全に破壊され両飛行場とも痕跡はなし、一部畑地でしたが、大半は荒れ地のままでした。
“敷島の大和心を人問わば 朝日に匂う山桜花”(本居宣長)
敷島隊編隊長 関行男大尉(2階級特進)海軍中佐 愛媛県西条市出身 行年23歳
2番機、中野磐雄一飛曹(2階級特進)海軍少尉 福島県原町出身 行年19歳
3番機、谷暢夫一飛曹(2階級特進)海軍少尉 京都府舞鶴市出身 行年20歳
4番機、永峰肇二飛曹(2階級特進)海軍飛行兵曹長 宮崎県宮崎市出身 行年19歳
5番機、大黒繁男二飛曹(2階級特進)海軍飛行兵曹長 愛媛県新居浜市出身 行年20歳
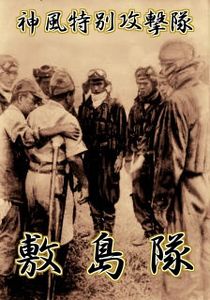 |
 |
| 出撃 |
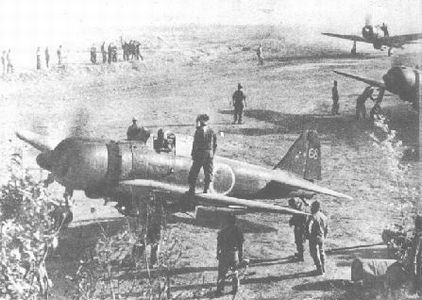 |
 |
| 翼の上に立つ関隊長 |
敷島隊二番機 中野磐雄一飛曹(二階級特進海軍少尉)
 |
 |
中野磐雄少尉 略歴
大正14年1月1日 福島県原の町生まれ
昭和17年3月 旧制福島県立相馬中学校卒業
昭和17年4月 海軍土浦航空隊飛行予科練習生入隊(予科練甲飛10期生)
昭和18年 三沢海軍航空隊配属
昭和19年 グァム島海軍航空隊基地全滅により、転属
昭和19年 201航空隊編入(在フィリピン・ルソン島・マバラカット基地)
昭和19年10月25日 神風特別攻撃隊敷島隊二番機として出撃
レイテ海沖で体当たり敢行 散華19歳
家への最後の書簡
「お父さん、お母さん、私は天皇陛下の赤子として、お父さんお母さんの子として立派に死んでいきます。喜んで参ります。お身体を大切に送らしください」
原の町[現南相馬市]夜の森公園に胸像と碑が建立されている
碑文
中野少尉名は磐雄、大正十四年原町に生る 父は松太郎 母はひでよ
昭和十七年 報国の志をたてて土浦海軍航空隊に入る。やがて戦況逆転国運の危殆に頗するを見、概然身を以て弾丸として壮烈なる戦死を遂げたり 時に昭和十九年十月二十五日未明 享年十九歳 二階級特進海軍少尉に任じ、その戦功を表彰せられたり 小中学校同級の友人追慕の情に堪えず相謀りて記念碑を建て永く忠烈を伝えんとす
文学博士 平泉 澄撰
 |
| 南相馬市夜の森公園内に建立 |
 |
| 中野磐雄海軍少尉像 |
日本側の記録では関編隊長の機は護送空母「セント・ロー」に体当たりし炎上した後沈没とあるが、二番機以下の記録はない、アメリカ側の資料を読むと一番機に続いて突込んできた多分二番機は対空砲火で火を噴きながら護送空母「カリニン・ベイ」の飛行甲板に命中、爆弾が爆発し破孔が出来たが沈没は免れたと記録がされている。多分この機が中野一飛曹操縦の機と思われる。
他の機は護送空母「キトカン・ベイ」の艦の外側にある通路に激突したが機体は跳ね上がり海中に没した。多分五番機は護送空母「ホワイト・ブレイズン」を目掛け対空砲火を浴び、白煙を吐きながら機銃を艦橋へ向け掃射して突入してきたが、操縦不能となり艦橋をかすめ海面で大爆発を起こした。と記録されている。
【謹んでご冥福をお祈り申し上げます】
第31章 福島第一原発建設開始
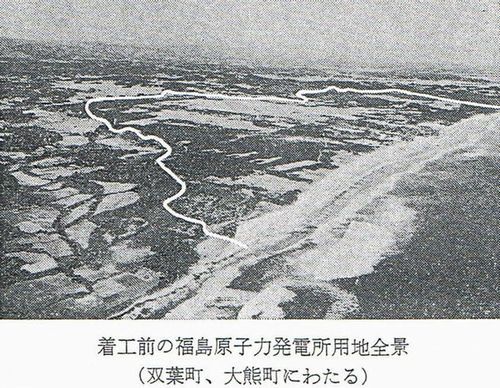 |
 |
原子力発電所建設計画が具体化し、東京電力と福島県が独自に調査した結果、最適地が3地点
●大熊町・双葉町
●双葉町
●浪江町
に絞られた。
この調査結果は1959年、東電の常務会で報告され、木川田自身が現地を、身分を隠して隠密裏に視察をし、更に専門家に現地調査を依頼している。
福島県としては、この時点以前から原発誘致を計画しており、当時の知事佐藤善一郎氏は過疎地双葉郡に原発を誘致することを考えており、県独自の調査を命じて原発誘致の可能性を探っていた。調査を重ねて、当初は東北電力に打診したが、当時は奥只見電源開発で多額の費用を要しており、更に当時の東北地方は首都圏ほどの電力需要が見込めず、余り乗り気ではなかった。
それに替わるべき売り込み先は東京電力であるが、その行動を起こす前に知事は病に倒れ、急死した。
替わって登場したのが木村守江知事(四倉町出身)で、知事は衆議院議員時代から知己であった東電社長木川田氏にこの誘致を持ちかけ、福島県出身の木川田社長も乗り気になり、しかも東電としても原発建設候補地を物色している最中であったから、話は一挙に進み、地元選挙区で自民党の大物斉藤邦吉衆議院議員、福島県議後に衆議院議員になる渡部恒三氏、笠原太一県議等の諸氏が賛同、推進に働いた。
東電は慎重で県の提示した調査結果に難点があったので、東電は福島県に再度調査箇所を示し、詳しい調査を依頼した。
これを受けて1961年発足したばかりの県開発公社では初仕事として工業用水調査、航空撮影調査、地質調査などを実施した。
この原子力発電所建設計画は、未だ本決まり前に大熊町、双葉町に伝えられており、1961年9月30日に双葉町議会は誘致を議決し、10月22日に大熊町議会が議決した。
更に協議は続けられ、最終的には旧陸軍飛行場跡地である、大熊町・双葉町に拡がる海岸台地に決定した。
福島第一原子力発電所建設計画が東電常務会でも承認され、本決まりとなった。
この地に決定した技術的な理由として僻地である事を最大の要件とし、更に開発後進地域で現地当事者の要望が多かったことを挙げている。
敷地の概況として、
「福島原子力発電所の立地点は、東京から北方約220km、原子炉の設置地点から最寄りの人家までの距離は約1kmで、周辺の人口分布も希薄であり、近接した市街地としては約8.5kmに昭和40年10月現在人口2万3千人の浪江町がある。」
原子力産業会議の報告書である。
原子力発電所設置の考え方として「万が一の原子炉設備の破壊事故により放射性物質の大気拡散時に周辺公衆に重大な災害を及ぼさないために発電所敷地を高い人口地帯から出来るだけ離す事を必要」としたからである。
この報告書が東京で出されたから別に問題視されなかったが、地元としてはいささか‘ムッ’とすることで、隣接する地元大熊町の人口7629人(当時)、7117人の双葉町、1万1948人の富岡町が、この説明からは完全に抜け落ちており、考慮の対象外だと説明しているようなもので、首都圏から離れていればそれでよしとする考えの表れだと判断する。
その他の表現でも過疎地、僻地が多用されおり、だから多少の事故なら心配する必要が無い、としていたのか、その結果は最大の事故を起こしてしまった。
本発電所の立地点は相双地帯南部の海岸段丘地帯に位置し、急峻な断崖もある.地質としては下層に砂岩、その上層に富岡層に属するシルト岩が主体で、更にその上を砂礫からなる段丘堆積層が覆っているが、その層厚は不整合で、富岡層の層厚は200~400mである。
前面の海底地形は、海底地形は複雑な地形であるが、海底勾配が全体として沖合450m付近まで1/60の急勾配、それより沖合は1/130の緩やかな勾配になっている。海底の基層である泥岩の上に深いところでは2~3mの砂層が堆積し、水深が深くなると砂層の堆積は薄くなる傾向にあった。
この調査結果として報告されている地質調査には双葉断層に関する記述は全くないので、双葉断層の存在は判っていても、当時は未だ十分な調査が行われていなかったので全く影響はないと判断していたのでしょう。
また地震災害に関する対策はあっても、津波に関して波高5m位までで、平坦な海岸線である浜通りには津波はあり得ない、が共通認識でした。
用地買収
用地買収の当該地は大熊町の旧陸軍磐城飛行場跡地で、戦後これらの土地は民間に払い下げられたが、余り利用価値がない海岸段丘の荒れ地で、その一部は製塩のための塩田として活用するとして国土計画興業が買収したが、製塩業は一時的なブームであって、直ぐ下火になってしまい、国土計画興業が製塩のための工事を始めたが途中で放棄してしまい、そのまま放置されていた。
まさか後年、高額で東電が買収してくれるとは、いくら日本一の不動産業で名を馳せた国土計画興業でも見通せた訳ではないから、大西武グループの創始者堤康次郞氏の強運と言うべきで、原発誘致に関しては堤氏が最大の誘致促進派でした。
国土計画興業は堤康次郎氏が設立した不動産開発業で昭和初期国立市や小平市のような学園都市を東京近郊に建設した土地造成、建設したのが国土計画興業で西武グループの中核をなす会社ですが、現在は「株式会社コクド」になりました。
社長は堤康次郎氏の三男義明ですが、買収当時1963年頃はどうだったのでしょうか。堤義明氏は1957年早大卒後、国土計画興業に入社、1965年に社長に就任していますから、買収に関しては交渉から調印まで重役として立ち会ったようです。
この土地取引は東京電力と国土計画興業との直接交渉で行われた。
1963年12月1日より買収交渉開始、所用面積96万坪
○旧陸軍飛行場跡地30万5,840坪
○一般民有地第一期30万1,042坪 福島県開発公社が実務を執る
○一般民有地第二期31万7,670坪 福島県開発公社が実務を執る
国土計画興業と東京電力とは直接交渉で買収が行われたが、一般民有地との交渉は大熊・双葉の両町合同開発特別委員会を造り、町長が表立って地権者との折衝にあたるのを基本方針にして交渉にあたり、それを町の特別委員会と公社がバックアップする。更には公社と町が共同で交渉に当たる、を基本としたが、地権者全員を公民館に参集を求めたところ、地権者全員が出席し、公社の説明を聴き、質疑応答と要望があった。
・放射能の安全性に関する懸念
・薪炭採草の喪失、代わりの国有林払い下げ
・開拓農家の営農経営の援助、代金以外の補償金
・買収土地価格の格差は原則として格差をなくす
・税関係では、特定公共事業の認定を受けう
・東電が直接買収した国土計画興業所有の買収価格と同一価格を確約する
開発公社としては交渉が長引けば問題が出て交渉が困難になるとの判断から1964年7月に大熊町地権者290名を公民館に集め、町長立ち会いで個々の地権者と折衝し、全員から承諾書を取り付けたが、金額に関しては低すぎるとの要望もあり若干の上乗せもあって第一期の買収交渉は1965年8月までに完了した。
更に双葉町の30万坪の買収交渉に入り、大熊町に準じた内容で1967年7月までに全てが完了した。
この二期に渡った約96万坪約320万㎡の買収には約5億円を要したと言われている。
この他にも宅地や付帯設備の用地として約8万㎡が買収された。
水田:110反
畑地:324反
山林原野:2,688反
その他:18反
その他の交渉として漁業補償の問題があった。この海域は相馬沖と常磐沖の好漁場の中間にあり、この海域も好漁場であるが、小さな漁港しかなく、魚市場もないため地区以外の一本釣りや、小型延縄、刺し網など他地区からの入り会い漁船が多く、漁業権が成立するのか法的な疑問点が多く、大いにもめたが、発電所の沖合約5.4万㎡の海面の共同漁業権消滅として地元3漁業組合、入会漁業5組合、近隣1組合との間で合意が成立し、約1億円が支払われた。
 |
敷地造成
敷地造成工事は、東京電力の施工範囲。原子炉に関する工事は全てGEのターンキー契約に分けられての契約だから、東電の指示でゼネコンが土地造成工事を請け負った。
・熊谷組:敷地造成、冷却水路関係、物揚げ場護岸
・間組:原石山骨材プラント
・前田建設:バッチャープラント、コンクリーブロックト
・五洋建設:防波堤
工期は1966年6月1日より1967年3月までの10ヶ月、プラント施工工事は全て鹿島建設が請け負った。
現時点での関心は、このプラント建設に関し当初地震、津波等の自然災害に対してどのような安全基準で対策を講じていたのか、資料はどうだったのか知りたかったが、残念ながら各調査会社に分散して委託しており、僅かな資料しか入手できなかった。
通常のプラント施工工事であれば建屋設備の配置、建設作業に必要な用地を経済的に造成できる事が必要とされていたが、海岸段丘に建設する原子力発電所であるから、
(1)原子炉建屋の設置に適する場所であるかの検討。
(2)高潮、津波への危害を回避する。
(1)は地震対策であるが、その基準は強震(震度5)以上、150年に1度
烈震(震度6以上)400年に1度、最大でM7.5~8クラスを基準としていたので、東日本大震災のようなM9.0の大地震は全くの想定外であった。
考慮したのは1936年に宮城県沖で発生した金華山沖地震時の記録であるが、それを参考にして金華山の内側の地震発生機構を討議した。
耐震性
耐震性に関する解決策は強固な岩盤に直接杭を打ち込むことで耐震強化を図るもので、1号機建屋は海岸段丘海抜約30m程度あった整地面を14mほど掘り下げ岩盤上に建設した。
 |
防波堤
防波堤の設計基準は、海象調査や近隣のデータを基に検討の結果、設計波高6.5m(1/3有義波、周期16秒、波向東北東)を基準にしている。
港としての役割は、3,000トン級の船舶の入港が可能なこと、そうすると水深6mが必要であり、港口100m、港内面積も計算できる。
(有義波:海岸で打ち寄せる波を観測し、一定の時間、波の高さを観測し、例えば一定時間内に100個の波高を観測したら、波高の高い順番に1/3を選び、その波高の平均値を計算したのが「有義波」の意味、波の高さはまちまちで、時には2倍の波が打ち寄せ場合が有り、例えば100個の波を観測すると有義波の1.6倍の波高の波が必ず1波あります。)
防波堤6.5mの基準は高潮、津波を考慮して最大6.5m(平均海面上)あれば充分に防げると判断したのでしょう。(日本港湾コンサルテング)
三陸地方には多くの津波の記録はあるが、浜通り沿岸では津波の記録は殆ど無い
 |
○貞観地震 869年9月26日 M8.3~8.6 震度不明 津波10m以上 死者約1,000人 震源地 宮城県沖、福島県沖らしい、特定できない。
○慶長三陸地震 1611年10月28日 M8.1~8.5 震度4~5 津波20m以上 三陸沿岸、陸前 死者約2,000~5,000人 震源地不明
○延宝地震 1677年11月4日 M8 震度不明 震源地常磐沖 津波発生 小名浜、中之作、江名、豊間、四倉 死者130人以上
○寛政地震(宮城県沖地震)1793年2月17日 M8.0~8.4 詳細不明
○天保地震 1835年7月20日 M7 青葉城石垣崩壊、城下町崩壊 津波被害は発生した記録はあるが、詳細不明
明治以後は記録があるので省略するが、浜通り沿岸でも過去に津波が発生した記録はあるが、検証はしていない。従って防波堤6.5mの根拠は有義波高だけが基準となったと思われる。
今回の大津波は第一、第二原発付近の津波、波高は15~16mであり、富岡川、富岡港付近では最大21m超えが調査・記録されているから、予想の3倍以上の波高であり、まさに想定外の大津波であった。
 |
貞観地震の記録として多賀城に古文書として残っていたが、学術書として利用されたが、津波の記録としてそれに基づく津波の痕跡調査はしていなかった。
10mを超す津波が海岸から仙台平野を1,000m以上遡上したと推測されるが、ボーリング調査は行ったが、これは目的が地質調査で、津波の痕跡は「坪堀り抗」という幅広く穴を掘らないとその痕跡は判らない。
東日本大震災後、津波被害の検証と同時に「坪堀り抗」の調査を行い、貞観地震・津波の痕跡を発見したようです。
福島原発建設に関して耐震性は考慮されたが、津波に関して事前調査は殆どなされておらず、大波はあっても津波はないとする、前提で設計されたと思われる。
さらに燃料運搬のタンカーに合わせて燃料タンクを岸壁近くに設置し、それに合わせて非常用発電施設を設置していたのが致命的欠陥となった。
これはGEが「ターンキー契約」方式の契約であったから、東電はGE社にプラント建設一式を発注した。このことは責任分担の明確化、工期短縮の思惑も有り、将来の国産化を見据えてのもので、GE社が主体となり東芝、日立、鹿島が下請けとなって工事契約を結んだ。
プラントの建屋設計についてはアメリカ・Ebasco社が基本・詳細設計を受注・施工した。
原子炉設置の建設設計に関し災害防止はアメリカの会社が受注したのだから本国での安全基準を準用したらしい。即ちアメリカの自然災害の最大はハリケーンとトルネード(大旋風)に対する対策、それとテロ対策であって、その思想をそのまま日本に持ち込んでしまったようだ。
日本の様に地震、津波の経験はなし、地震は一部カルホルニャ州にあるだけ。
その発想からして非常用電源設備の設置は低地あるいは地下の方が安全と考え、その通にした。
日本側がそこに危惧を抱いていたのなら、引き渡し後に高台に移せば良いものを
30数年以上も放置しておいたのは何故なのだ、基本設計したGE社側には文句は言えない。何故なら長い間何の安全対策を執らず「安全神話」だけを流し続けてきた東京電力と監督官庁全体の責任で有り、怠慢であったことを責めるべきだ。更に言えば3号機以降は国内メーカーであり、非常用発電機も増設したが高台に設置しようとはせず、矢張り低地に設置しているのだから、津波対策の発想は欠落していたようで、後悔先に立たずの教え通りで、悔いても無念と虚しさがこみ上げてくるだけだ。
1号機の建設計画が公表された1966年当時、原子炉建屋建設を受注したのは鹿島建設であるが、GE社が元請け社であり、日本的な談合文化とは全く無縁で、応札はゼネコン各社が本気で見積もりを出し徹底的に叩き合いが迫られるから、鹿島建設内部では応札を敬遠していたらしいが、創業者鹿島守之助会長が、赤字覚悟で受注しろと命じ、JRR-1、JDPRの建屋建設をも赤字で受注しており、3回連続での受注は、日本最初の原子炉建屋建設であるから、GEから技術を学びたいという思惑があっての受注であったらしく先行投資だ。さすが創業者の読みは鋭く、技術を習得した結果、その後の1989年まで日本国内での原子炉建屋建設はBWR19基のうち16基を鹿島建設が請け負うことになった。
原子炉、炉型正式決定
原子炉は、アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE)によって設計されたものを基本とした。1号機はGE社製
1号機原子炉:当初1970年10月にGEより東電に引き渡す予定にしていたが、実際に引き渡しを受け営業運転を開始したのは1971年3月であって約5ヶ月の遅れであった。これはGE社の工場で1969年にストイキが起き、約3ヶ月間操業が停止した影響で納期に間に合わなかったことによる。
このため発電機の取り付け作業には二交代制で行われた。この時の原子炉がスペイン公社に納入するはずの原子炉を、スペインでの建屋建設が遅れたので代わりに日本に納入したのだとの噂がながれた、が勿論真偽はわからない。
ただ、据え付け工事を急いだため不備があったらしい。
1971年3月26日、GEから東電へ正式に「キー」が渡され、1号機は公式にも運転に入った。
原発建設の資金は、原子炉購入資金としてGE社に発注する際に東電はアメリカ・輸出入銀行からその都度借款を申し入れ資金調達をした。
1号機の場合は、GE社が主契約者であり、1967年5月、東電木川田社長が渡米し輸出入銀行総裁のもとを訪れ、借款を締結、3913万ドル、年利6%、償還20年であった。資金用途はアメリカ製品買い付けに限られた。
| 原子炉形式 | 運転開始定 | 定格電気出力 | 原子炉 | タービン | 建設工事費 | |
| 1号機 | 軽水炉 | 1971年 | 40.0万kW | GE | GE | 約390億円 |
| 2号機 | 軽水炉 | 1974年 | 78.4万kW | GE | GE | 約560億円 |
| 3号機 | 軽水炉 | 1976年 | 78.4万kW | 東芝 | 東芝 | 約620億円 |
| 4号機 | 軽水炉 | 1978年 | 78.4万kW | 日立 | 日立 | 約800億円 |
| 5号機 | 軽水炉 | 1978年 | 78.4万kW | 東芝 | 東芝 | 約900億円 |
| 6号機 | 軽水炉 | 1979年 | 110万kW | GE | GE | 約1,750億円 |
 |
福島第一原発工事
東電では大熊町と双葉町にまたがる敷地に原子力発電所を建設することを決め、1966年7月に内閣総理大臣に原子炉施設の設置許可申請を提出、同年12月に設置許可が出された。
この時の計画書では原子炉には沸騰型軽水炉(GE社製)熱出力122万kW、電気出力40万kW、総工費384億円、敷地は太平洋に面した海岸段丘で標高30~35mの比較的平坦な台地 広さ約300万㎡
整地作業、防波堤、岸壁等はゼネコン各社、熊谷組、間組、前田建設、五洋建設、その他が請け負い、原子炉建屋は全て鹿島建設が請け負った(但し、第二原発4号機建屋だけは清水建設が請け負った)
主原子炉機器、タービン発電機等の主要機器、原子炉再循環系の主要部分、その付帯工事はGE社が元請けとなり、国内各社が下請けとなった。
下請け各社は、東芝、三菱重工、日立製作所、石川島播磨重工(現IHI)
総工費福島第一原発 5,020億円 第二原発 1兆2,390億円。
日本全国で建設された原子炉54基、総建設費実費約13兆、消費者物価指数による現在価値に換算すると14兆5千億円の巨額になる。
甘い蜜があれば寄ってくるのは人の世の常、下請け、孫請け、ともかく仕事を受注したい企業は国会議員から村会議員、有力者の口利き料なる摩訶不思議な金弦(カネズル)に群がった。しかも公共事業の口利きは禁ぜられているが東電は民間企業、従って口利き料は何のお咎めなし。
地元企業はその点有利で、東電も地元懐柔策として地元有力者が係わる建設会社に対しては、「お約束事」として東電が直接仕事を発注してくれた。
一例を挙げると、双葉町に田中土建という会社があり、オーナーは双葉町町長を1963年から1985年まで6期も務めた田中清太郎氏で、原発建設と重なるのであるから特別に優遇するのは当然で、東電からの受注額は5億円にのぼるとのこと、裏を探り出して暴露しているわけではない。田中氏の自著「追想、町長在職十二年の軌跡」の中の記述に誇らしげに約5億円の受注があったと書かれている。更に推薦文として元東電会長で日本経済界の重鎮平岩外四経団連会長(当時)が「田中氏は、その任期中福島第一、第二原子力発電所に係わる誘致に、地元の責任者としてご尽力されて参りました。(中略)感謝の念仁堪えないところであります」という推薦文を贈って本の表紙の帯に書かれている。
その他枚挙は数限りなく存在し、ゼネコンは荒利20%あると豪語した位だから札束が乱れ飛んだのだろう。しかも幾ら経費がかかろうが、独占企業である電力会社は必要経費として電気料金に上乗せすることが出来、しかも電気料金は主管庁の認可事項であるから、電力会社は発電所を建設し、電気を造るだけ、送るだけ、それで利益が保障される殿様商売だ。
地元はどうであったか、日本代表する大会社が主体とした大工事であるから、全国から作業員が集まり、勿論地元も求人ブームに沸き、作業員のハウスと呼ばれていた宿舎建設、増設、食事、仕出し弁当、消耗品の販売、果ては紅灯の巷まで出現しGE社の技術者が多数現場で、据え付け工事で働いていたから、その家族も来日して大熊町にはアメリカ村まで出現した。アメリカの家庭生活は3ヶ月以上留守をすると離婚訴訟の要件になり、高額な慰謝料を負担しなければならないから家族同伴は常識だ。
地元に落ちる金もまた膨大で、静かすぎる田舎町に突如湧き上がった好景気のうねりに有頂天になるのも当然のことだが、一過性の旋風のようなもの、来るのも早いが、去るのも早い、札束が舞ったのは一場の夢でしかなかった。
しかし、更なる旋風があった。電源三法の魔力に魅入られてしまった。
電源開発に関し、電力に関する法に電源三法がある。
○電源開発促進法
○特別会計に関する法律(旧電源開発促進対策特別会計法)
○発電用施設周辺地域整備法
以上の三法を指す。
これらの法律の主な目的は、電源開発が行われる地域に対して補助金を交付し、これによって電源開発の建設を促進し、運転を円滑に行えるようにしようとするもので、奥只見電源開発事業の頃は未だ制定されてはいなかった。
この三法によって補助金の大判振る舞いにより再び地元は酔い痴れてしまい、俄成金になった町当局の行動パターンは「空の城」を次々と築きあげ、そして行詰まってしまった。
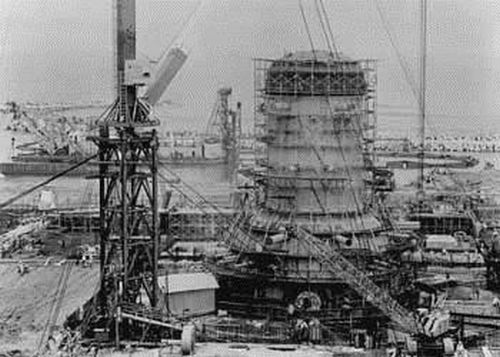 |
 |
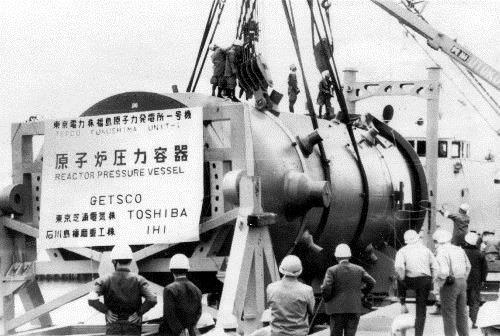 |
 |
 |
 |
 |
 |
第32章 原発建設の必要性
福島第一原発事故後に外国人特派員だけの記者会見が行われた。その際一人の記者が質問に立ち、「日本は世界唯一の原爆の被曝国である。その日本が原子力発電所を世界第三位の55基を有する原発王国になったのはどういうことなのか」と質問されたが、明快な答はなかった。
おそらく日本国民全てが答えられないことで、いつの間にか55基も有する原発王国になっていたことに気が付いた、というのが実情ではないだろうか。
また、第一原発事故以来、事故の5基以外の50基は全て運用停止となったが、全国が停電になったわけではない。隅々まで送電され、一時期混乱はあったが、事故以前と同じような常態で日常生活に支障はなかった。
では原発は必要なかったのではないかという疑問になるが、それ以上の追求には至っていない。電気はスイッチを入れれば点灯するもの、家電は作動するものとだけに関心があり、それ以上のことは無関心となる。
原発停止の不足分を補っているのは、休止していた火力発電設備をフル再活用し、苦心惨憺な思いで電力供給を続けているのであって、現在電気を生産しているのは火力発電が大半で、高価な天然ガスや石油ガスを燃焼させ、かつ二酸化炭素を排出している。嘗ては排出ガス問題で大騒ぎし、地球温暖化問題を本気で憂いていたが現在はどうだろうか、決して正常な状態ではないことを理解すべきだ。
究極の問題は、果たして我が国にとって原子力発電所建設は必要だったのか?という問題に突き当たる。
事故後に悔やんでもどうしようもないことかも知れないが、水力発電や火力発電でも良かったのではないかとの思いはある。
我が国の発電事情として、「水主火従」から「火主水従」となり、そこに原子力が加わってきた発電の歴史、社会的背景を探る必要がある。
開国以来、明治政府の目指すは工業立国であり、富国強兵こそが悲願であった。無資源国である我が国の動力源は水力と粗悪な石炭が生産できる程度で、工業立国を国是として富国強兵を目指すが、無資源国である我が國の取るべき途は、当時は西洋列強の弱肉強食の時代、植民地支配が当然とされていた時代であるから、もし弱國とみられると植民地支配にされてしまう怖れは充分にあった。
アジアを観れば、その大半は列強の植民地になっており、辛うじて植民地支配を免れていたのはタイ王国と日本だけで、中国は複数の列強が蚕食し、満身傷だらけになっていた。
従って自國を自国民が護る必要があり、富国強兵が国是になるのも当然であり、国民もまたそれを望んだ。従って貧しい生活に耐えても我慢強く國に尽くし、青少年の夢は立派な軍人になり、國にご奉公することであった。 富国強兵の第一は軍備拡張であり、工業立国は最新の兵器を自前で生産することにある。
そのためには電気と原材料が必要となる。しかし狭い国土、貧弱な天然資源、ならば近隣諸国が力を併せて極東の平和を築こうとの手前勝手な発想から動き出し、その結果として朝鮮半島の併合、その後は「満蒙は日本の生命線」をスローガンに領土拡張主義に陥った。
そうなると領土拡張主義のソ連政府と争うことになり、我が国の近・現代史はソ連との対立、小競り合い、事実上の戦争状態の連続であって、我が国の運命はソ連に握られていたような常態にあった。
その関わり合いを歴史の流れの中で覧れば、帝政ロシア、ソビエト連邦、ロシア共和国と隣接する国として江戸時代から関わり合いを持ち、関係良好な時代もあったが、その大半は全面衝突の日露戦争、シベリア出兵、蘇満国境を巡る小競り合い、張鼓峰事件、ノモハン事変、第二次世界大戦末期には日ソ不可侵条約を一方的に放棄し、大戦末期の漁夫の利を狙って、突如蘇満国境からソ連極東軍が進撃開始、大戦まっ付の、と数限りない武力衝突を繰り返してきた日蘇、日ロ関係史でもある。
大戦後においても満州国の蹂躙、関東軍軍人、民間人をシベリアに連行しての強制労働、北方四島の不法占拠、数限りない対立の連続で、第二次大戦後70年近くなるが、未だ平和条約が締結できていない隣人ソ連、新生ロシアに代わっても対立は続いている。
嘗ての帝国陸軍の護りもソ連赤軍に対してであり、陸軍大学校の主要研究課題はソ連軍対抗作戦研究にあり、無敵関東軍といわれるような巨大な戦力を満州の地に配備、軍備拡張に努めてきた。
その最大は昭和15年の関東軍特別大演習に看られ、陸軍の絶頂期であった。
それがナチスドイツの快進撃に惑わされ急遽南下政策に転じ、結局は無敵関東軍を南方作戦に転用して、満州の護りが空になったところをソ連極東軍に衝かれ僅かな期間で壊滅してしまった。その関わり合いを歴史の流れの中で覧れば、帝政ロシア、ソビエト連邦、ロシア共和国と隣接する国として江戸時代から関わり合いを持ち、関係良好な時代も僅かにあったが、その大半は全面衝突か、数限りない武力衝突を繰り返してきた日蘇、日ロ関係史でもある。
従って我が国の工業史もソ連との関わり合いが多く、工業化に最も多く影響する発電の歴史も対ソがらみとなる。
明治新政府の恐怖はロシア帝国の動向にあった。北方の白熊と怖れ、南下政策如何によっては何時呑み込まれてしまってもおかしくない状況にあった。
中国の清朝も、朝鮮半島の李王朝もロシア帝国の南下を食い止める力はなく、風前の灯火であった。従って次の侵略は我が国になる怖れは充分にあった。
李王朝の内の対立が日清戦争となり、瞬間的に遼東半島は帝政ロシアによって占拠されてしまった。
この地を要塞港にして、次に狙うは我が国になってしまった。これが日露の全面戦争で、日露戦争になった。
日露戦争で一応勝利を収めたことになっていたが、実は引き分け程度の勝利であり、当時のロシア帝国の本国を占領した訳ではない。
当時ロシアでは、反帝政運動に火が付き、それが拡大しつつあるが故に、日露戦争は早期にけりを付ける必要があった。そこでアメリカ大統領を仲介として講和条約を結び、戦争を終結、内政に専念しようとしたが、反帝政運動は燎原の火のように拡大して、やがて帝政が滅亡する。
日露戦争で苦戦中の1905年1月、首都サンクトペテルブルクで生活の困窮をツァーリに訴える労働者の請願デモに対し軍隊が発泡し、多数の死傷者を出した「血の日曜日事件」。この事件が契機として労働者や兵士の間で革命運動が活発化した。その後、二月革命(1917年)、十月革命と続き、第一世界大戦の最中でもロシア国内の革命運動は続き、ロシア国内は四分五裂の状態で、数々の内乱、分裂の繰り返しで、その詳しくは次章のロシア革命で述べる。
日露戦争後、富国強兵に本腰をいれた日本政府、帝国陸軍は朝鮮半島、満州の大地を兵站基地にするため、工業・鉱業の開発に取り組んだ。その第一は発電能力開発することにあった。
そこで眼を付けたのが朝鮮半島北部の鴨緑江で、ここに世界一の水力発電所を造り上げ、工業化の根幹とした。当時の我が国には世界一を造り上げる技術と資力があったことになる。
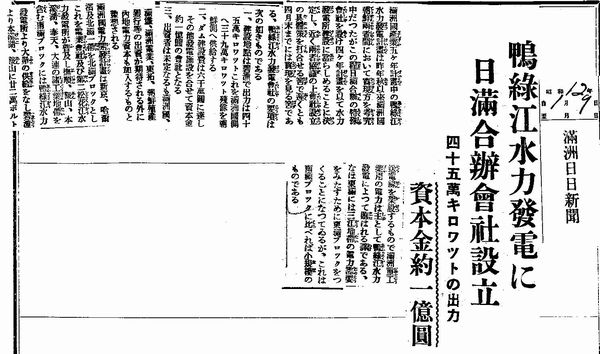 |
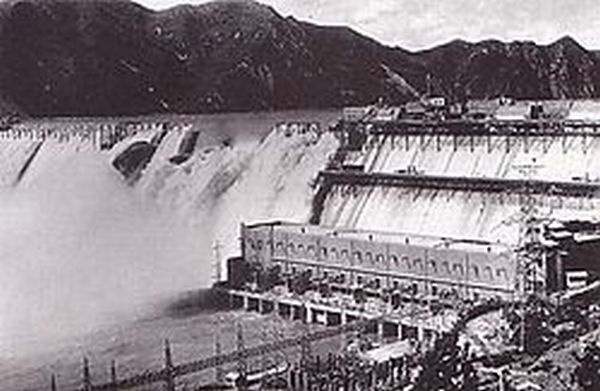 |
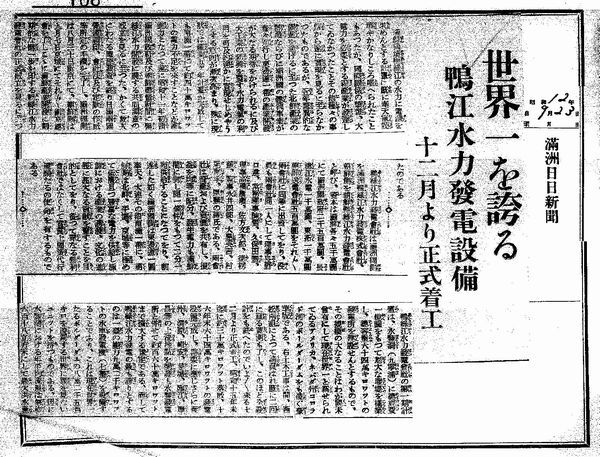 |
この鴨緑江水源開発を手始めにして総合開発が行われ、北朝鮮は工業地帯になり、かつ満州国成立後は鉱業の開発が活発化し、露天掘りで豊富に産出する石炭による火力発電所が各所に施設され、満州鉄道が各地に延びると同時に工業化が行われた。
即ち鉄路が敷設されると、警備のため関東軍の部隊が各所に駐屯し、日系の工場、商業施設が設けられ、満鉄が誇るアジア号が走行する地が、日本領土となっていった。
 |
 |
| 関東軍司令部 |
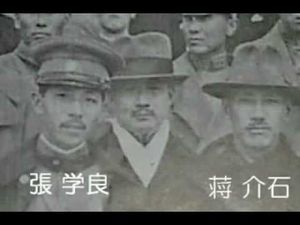 |
 |
陸軍の野望は底知れず、北朝鮮、満州を工業地帯として発展させ、兵站基地としてやがてあるであろう世界大戦に備えるという戦略があった。
1945年8月、第二次世界大戦は我が国の大敗で終了、海外での投資は全て無となり、再び狭い4つの島に閉じ込められた。
焼け野が原になってしまった我が国、一億もの人々は今日の糧さえないような惨めな生活に陥った。 そのような絶望的な日々を送っていたが、GHQでは日本国民の半数は仮死するだろうとの試算していた位の食糧不足であった。ともかく政府が第一にやることは食糧を増産することにあった。
そのためには農業の振興であるが、のためには化学肥料の増産を計った。そのためには電気が必要とし戦災で破壊された火力発電を復旧させ、石炭を増産することにあった。そのため傾斜生産方式を採用し、戦後復興の目玉として石炭産業を重点的に資本投入を謀り、このため石炭は黒ダイヤと称され、一時期に過ぎなかったが石炭産業のみが好況の波に乗った。
終戦から5年後、またもやソ連が動いた。1950年北朝鮮政府の金政権を唆し、ソ連製戦車を先頭に韓国の首都ソウルへ北朝鮮軍が侵攻してきた。
僅かな戦力しかない韓国軍と駐留アメリカ軍は総崩れとなり、南の釜山市近郊まで追い詰められてしまった。朝鮮動乱の開戦である。
その時援軍として駆け付けたのが、連合國軍総司令官であったマッカーサー元帥指揮下のアメリカ軍を中心とした国連軍で、仁川逆上陸で反攻開始を謀った。
その後は中国との国境付近まで追い詰めたが、今度は林彪将軍指揮下の中国正規軍の大軍が凍結した鴨緑江を徒歩で渡って傾れ込んできた。
それからは1進1退の大激戦となり、我が国は突如国連軍の兵站基地と成り、あらゆる戦争必需品を生産する工場地帯となった。
このため不況に喘いでいた我が国産業界は一挙に息を吹き返し、設備投資に狂奔し、生産工場は回復していった。まさに神風が吹いたような経済復興であった。
その後は順風満帆で経済復興を成し遂げていったが、その背景にあったのは、激しい米ソの対立で、世界はまさにアメリカを中心とした資本主義国家群とソ連を中心とした社会主義国家群の対立で、第三次世界大戦は避けられない情勢と思われた。
そのため我が国は自由主義國群の最前線にあるとされ、自由主義を護るためにも防波堤としての日本の役割は重要視され、「防共の砦」論が盛んとなり、日本を独立國とする必要から講和条約が結ばれ、晴れて新生日本國として自由主義連盟の一員となった。
その後は目覚ましい復興を遂げることが出来たのは逆説的に言えば、米ソ対立による冷戦の激化であると考えられる。
工業化が進めばさらに電気が必要になる。そのため佐久間ダム、奥只見川総合開発、黒部秘境の開発等、水資源開発、水力発電所開発をし尽くし、適所は日本国内になくなるまで開発し尽くした。
残るは火力発電だが、都市近郊の至る所に火力発電所を施設したが、新たな問題が発生した。それは二酸化炭素の排出、地球温暖化問題、時まさにモータリゼェションと重なり、新たな都市公害、喘息公害として世の糾弾を浴びた。
そのような世相の中、注目されたのが、無公害の理想的な発電方法として原子力発電が脚光を浴びることになってきた。これも世相の為せる技だ。
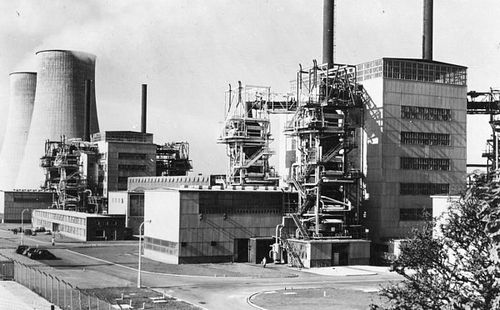 |
世界の原子力発電への途
1930年代に人類は核エネルギーの存在を発見し、1942年、シカゴ大学のエンリコ・フェルム教授が、実験炉で原子力発電の原理となる核分裂の連鎖反応を行うことに成功、1945年にアメリカで核分裂反応を利用した原子爆弾を開発され、広島、長崎に投下、史上最悪の悲劇をもたらした。
次に実用化されたのが空気を必要としない動力源として潜水艦の動力として活用され、原爆開発から9年後の1954年最初の原子力潜水艦が進水し、原子力は軍事用として開発が進んだ。
民需としての原子力は、史上初の原子力発電は、1951年アメリカで実験炉、EBRー1から始まる。EBRー1の当初の発電量は1kw弱で、200wの電球4個を発光させた。
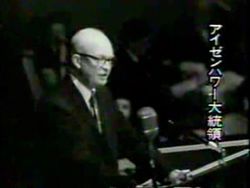
本格的に原子力発電への途が開かれたのは1953年12月8日、アイゼンハワー米大統領が国連総会で行った原子力平和利用に関する提案がその起点となった。
これは核兵器開発だけに力を注ぎ、核兵器の怖ろしさを感じていた核先進国に対して原子力発電という平和利用に向けさせる大きな政策転換がった。
1959年に原子力エネルギー法が修正され、アメリカ原子力委員会が原子力開発の推進と規制の療法を担当することになった。
原子力発電を実用化したのは国家を挙げて開発に邁進したソ連の方が先で、1954年6月オブニンスク発電所が営業運転を始めた。また同年原子力潜水艦を就航させ、米ソ対立が激化、熾烈な核開発競争が始まり、世界は二極分解、対立構造の世界となって、西側(アメリカを中心とした資本主義的自由経済諸国)、東側(ソ連邦を中心とした社会主義統制経済諸国)と僅かな中立国(第三勢力)に色分けされた。
西側で最初の商用原子力発電は、イギリスのコールダーホール1号炉である。運転開始は1956年10月17日、出力6万kW、炉の形式は黒鉛減速炭酸ガス炉(GCR)であった。
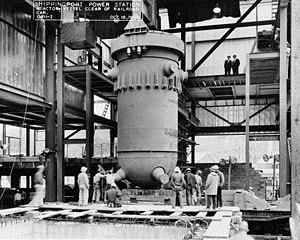
アメリカでは、シッビングボート発電所が最初で、1957年12月18日、操業開始、出力10万kW、炉の形式は加圧水型原子炉(PWR)であった。
フランスでは、1964年2月に運転開始、シノンA1号炉、出力8万4千kW、炉の形式はGCRであった。
1957年、欧州共同体(EEC)諸国により欧州原子力共同体(ユートラ)が発足し、同年国際原子力機関(IAEA)も発足した。
原子力発電が発足した初期には、夢の発電と喧伝され、「Too cheap To meter」と言われた。この意味は「原子力で発電すると、余りにも安価で計量する必要が無い」という意味で、夢の発電方法だとされ、世界の各国は原子力発電の導入を急がねば世界の趨勢から取り残されるとの危機感が生じた。
しかし現実はそう甘くはなかった。厳重なバックアップ装置や何重もの安全装置が必要であり、その建設費が膨大であり、かつ検査や点検に非常に時間がかかる。
原子力発電が他の発電方法に比べ設備費の割合が非常に高く、必ずしも安価で理想的発電方法とはいえない面もあることに気付いていたが、趨勢を換えることは出来ず、原子力発電所建設は国家の威信をかけ世界に拡がっていった。
1977年、アメリカは民主党のジミー・カーターが大統領に就任すると、カーター政権は1977年核拡散防止を目的としてプルトニュウムの利用の凍結する政策を発表した。これによりアメリカでは高速増殖炉の開発が中止され、核燃料サイクル開発を断念したことになる。これ以降核燃料は再処理されずワンスルーとなった。
このような世界情勢の中でわが国の原発は54基を数え、世界第三位の原発を保有国になっていた。

1979年3月28日、スリーマイル島原子力発電所事故発生した。この事故は世界の原子力業界に大きな衝撃を与え。原子力の新規受注が途絶えた。
1986年、人類史上最悪の原発事故、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生、自国ばかりでなく、近隣諸国、ヨーロッパ諸国が被害を被った。
このようなこれらの事故を傍観するだけで、我が身を省みず「安全神話」だけが一人歩きしていたわが国で12011年3月11日、地震、大津波、それに続く福島第一原発事故があり、大きな打撃を受け、1年以上経過しても回復にはほど遠い状態にあり、被害をもろに受けた皆さんと共に1日でも早い回復の日を祈りながら、これまでの経過を考察していきたい。
また、今後原子力発電をどう展開するのか、今後原発の新設、増設はないのか、あるいは全てを廃炉、廃止に向かうのか。我が国原子力政策は如何なる方針なのか注目したい。
日本の原子力政策
戦前からわが国のサイクロトロンの研究開発は世界最先端の研究を行っており、研究の中心であった理研工学の仁科芳雄博士が中心となりグループには湯川博士、朝永博士のような戦後ノーベル賞を受賞した逸材、輩出している。
1945年8月15日ポツダム宣言受諾、敗戦国になり連合軍の占領下でオキャバイトジャパンとなり、当然ながら原子力の研究は全て禁止になって研究施設のサイラトロンその他全ての研究施設は全て東京湾に投棄、または破棄され、占領下にあった7年間はまったくの冬の時代であった。
1952年4月、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)が締結され、念願の独立を果たした。
独立をもって原子力研究も解禁されたが、広島、長崎の被爆が余りにも大きな衝撃であったため、原子力研究への意欲を失わせてしまい、わが国の原子研究平和利用の面でも世界水準からも大きく遅れをとってしまった。
1952年7月 日本学術会議において茅誠司、伏見康治の両東大教授を中心としたメンバーが「国際的に遅れを取った日本の原子力研究の巻き返し」をどうするかという議案が提出したが、この提案に対し被爆地であった広島大学、長崎大学から核研究が兵器開発に繋がるのではないかとの懸念が表明され、全国的に議論が巻き起こり、そのため日本学術会議内に文系、理系、法学等幅広く各部門の専門家が参加する「第39委員会」を設置、議論を重ねたが、なかなか議論を煮詰めることができなかった。
この動きとは別に政界では、もと国務大臣であった後藤文夫代議士を中心とした政官界有志による原子力政策推進の動きがあり、1952年 財団法人電力経済研究所が設立された。
世界の趨勢としては、1953年12月、国連総会の席上、アイゼンハワー米大統領が行った演説の中で「平和のための原子力」を提案、これは当時、原子力発電はソ連が世界初の原子力発電を行い、核爆弾競争でも水素爆弾を開発したのもソ連でしたから、核開発競争ではソ連が1歩リードしており、アメリカは焦っていたので、演説の骨子は、国際的な枠組みで核の燃料を保管・監視し、必要に応じて各国に分け与えよう、とする内容であった。この構想は若干の修正があったが、国際原子力機関(IAEA)として実現し、この機関は現在でもイランや北朝鮮の査察問題で報じられているように活躍しております。
この演説を契機としてわが国でも「新しい時代に乗り遅れては大変だ」との気運が政財界に高まり、アイゼンハワー大統領演説から3ヶ月後には自由党・改進党・日本自由党の共同提案、その中心は当時改進党に所属して青年将校ともて囃されていた若き日の中曽根康弘、稲葉修、斎藤憲三、川崎秀二、前田正男氏等の議員が結束して原子力研究開発予算を国会に提出した。当時、与党は衆院で過半数の議席を持たず、どうしても予算案を通過させたい吉田内閣は改進党提出である原子力研究開発予算を抱き合わせで通過させた。
水力発電の只見川総合開発で福島案、新潟案、東京電力案が複雑に交差し、てんやわんやの大騒ぎをしている同時期に原子力発電の可能性をさぐる動きがあったのですから如何に電力不足が深刻であったかが推察されます。
そのときの予算請求額は予算2億3500万円、ウラン235に因んだ予算額請求であるから、予算額だけが一人歩きする未明の世界であったのかもしれない。
突然の予算成立に主管官庁である通産省は当惑したが、1954年5月に、内閣の諮問機関として「原子力平和利用準備委員会」が設置したが、これに猛反発したのが日本学術会議で、原子力研究・開発が政治主導になることに危機感を強め、当時の日本では原子炉の建設は時期尚早と批判したが、電力の絶対量不足に対応するためには絶対必要とる政・官・財に勢力に屈し、第39委員会は慎重意見が相次いだが公聴会の意見を集約し、原子力利用は日本国民による民主的、かつ研究成果を公開することを条件にしてその運営方針を了承した。
先に通過した原子力予算の使い道として、小型原子炉の建設戸放射能障害の研究の二項目に絞って原子利力平和利用を目標として設定した。
その頃、国際的な関心事はロシア、イギリスの実用的な動力炉の成果が注目され、同時に米ソ対立による世界の二極化が明らかとなって、わが国は防共の砦としての役割を担わされ、否応なしに米ソ対立の最前線に立たされてしまった。
こうなるとアメリカとしてはわが国が1日でも早く経済復興し西側諸国の一員として活躍できるようにと期待するようになり、電力回復に多大な期待を寄せ、原子炉建設を全面的にバックアップすることを申し出、燃料供給から炉の設計・建設まで請け負うことを約束した。
そして基本法成立を受けて1956年1月1日、原子力委員会が設置され、初代委員長に正力松太郎氏が就任、原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに1957年5月には新設された科学技術庁の初代長官にも就任、「原子力の平和利用」および「原子力の国際協力」を基本として、日本として従来の研究テーマであった「アイソトープ利用の実用化」に加えて「5年以内に原子力発電を実現させる」という目標を掲げた。
さらに正力委員長は目標達成には産業界の協力が不可欠として「原子力産業会議」を開催し、2月に首相官邸に71名の財界代表を招いて広く周知し、さらに3月には日本工業クラブに「日本原子力産業会」が発足、初代会長は、電気事業連合会の菅禮之助(東京電力会長)氏が就任、原子力発電所建設への路は開けた。

一方、動力としての濃縮ウラン燃料はアメリカから貸与されることになり、保管場所および研究所の設置が急務となり、受け入れ機関として1954年7月に「財団法人日本原子力研究所」が急遽発足し、研究所の候補地を求めたところ、当時の国内の世論は原子力歓迎ムードで、数多くの候補地があったが、最終的に茨城県東海村が選ばれた。
1956年に日本原子力研究所、現・独立行政法人研究開発機構が特殊法人として設立され研究所が茨城県東海村に設置され、これ以降、東海村はわが国の原子力研究の中心となった。
 |
 |
しかし、原発への途は平坦であったわけではない。世論は広島、長崎の惨禍を忘れたわけではないし、原爆症で苦しむ同胞を視ており、さらに米ソの激しい原水爆実験を繰り返し、大気は核のチリで汚染され、降雨があると大気の汚染チリ混じりの雨が降ってきて、新聞が汚染度を速報していた。
度重なる汚染降雨に、濡れると「頭が禿げる」という奇妙な噂が広がり、雨の日は極力外出を控えた。
実質的な被曝被害もあった。1954年3月、ビキニ環礁での水爆実験、その環礁の危険範囲の外で、大分離れた海域で操業していた鮪延縄漁船・第五福竜丸が被曝してしまった。計算されていた爆発よりも更に大きな爆発で、広範囲な海域が爆発の影響を受け、被曝範囲が広がった。このため第五福龍丸ばかりではなく、多くの漁船が被曝した。また島々に住む多くの人達も被曝した。
このため原水爆実験の中止を求める動きが活発となり、連日国会議事堂付近でのデモが続いた。同時に原発建設反対の陳情も活発となった。
しかし、経済復興は目覚ましく右肩上がりのまさに絶好調、当然電気の需要も右肩上がり、しかし水力発電は既に手詰まり、火力発電は二酸化炭素問題、地球温暖化、喘息等の健康被害、諸々の公害問題の噴出、更には国際問題として石油、天然ガス等の調達不安、産油国の政情不安、輸送ルートの不安等々数限りない不安が付纏ってきた。
アイゼンハワー大統領演説から3ヶ月後には自由党・改進党・日本自由党の共同提案、その中心は当時改進党に所属して青年将校ともて囃されていた若き日の中曽根康弘、稲葉修、斎藤憲三、川崎秀二、前田正男氏等の議員が結束して原子力研究開発予算を国会に提出した。当時、与党は衆院で過半数の議席を持たず、どうしても予算案を通過させたい吉田内閣は改進党提出である原子力研究開発予算を抱き合わせで通過させた。
アイゼンハワー大統領の「平和のための原子力」の演説こそがわが国の原子力に関する活動に火を付けていたことになる。
この時代、原子力研究開発予算案が通り、原子力発電への途が開けたと同時に第五福龍丸事件を契機に反原子力、反原発の市民運動が激しくなり、原発建設への岐路はまさにこの1954年代の時期にあった。
しかし、反原発を主張しても、水力発電は頭打ち、火力発電は公害問題を抱え、さらに原油や天然ガスはその生産国に問題があり、輸入が円滑に行えるかその保証は全くなかった。確かにその後オイルショック、原油価格の暴騰があり、その都度経済危機に陥り、国民はトイレットペーパー騒動や、買い占め騒動に巻き込まれた。
そこで、活躍したのがマスコミ界の実力者で読売新聞の社主、しかも現職の国会議員であった正力松太郎氏で、原子力推進の一大キャンペーンを行い、アメリカの原子力平和利用使節団(団長・ジョン・ホプキンス、ゼネラル・ダイナミックス社長)を日本に招いて各地で講演を開催、読売新聞がこれを全国に報道した。
またCIAと組み原子力平和博覧会を日本各地で開催した。この動きに反発していた学術会議や被曝協等も原子力利用が日本の戦後復興には電力確保が絶対の命題であることから次第に軟化し協調するようになった。
1955年自民・社会の両党は協力して、「原子力基本法」「原子力委員会設置法」「原子力局設置法」といわれる原子力三原則といわれる三法案がスピード可決され、政府は『原子力平和利用準備委員会』を解消し、「原子力委員会」を発足させた。
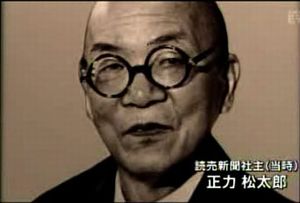
1、研究の民主的な運営
2、日本国民の自主的運営
3、一切の情報の完全公開
そして基本法成立を受けて1956年1月1日、原子力委員会が設置され、初代委員長に正力松太郎氏が就任、原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに1957年5月には新設された科学技術庁の初代長官にも就任、「原子力の平和利用」および「原子力の国際協力」を基本として、日本として従来の研究テーマであった「アイソトープ利用の実用化」に加えて「5年以内に原子力発電を実現させる」という目標を掲げた。
さらに正力委員長は目標達成には産業界の協力が不可欠として「原子力産業会議」を開催し、2月に首相官邸に71名の財界代表を招いて広く周知し、さらに3月には日本工業クラブに「日本原子力産業会」が発足、初代会長は、電気事業連合会の菅禮之助氏(東京電力会長)が就任、原子力発電所建設への路は開けた。
一方、動力としての濃縮ウラン燃料はアメリカから貸与されることになり、保管場所および研究所の設置が急務となり、受け入れ機関として1954年7月に財団法人日本原子力研究所が急遽発足し、研究所の候補地を求めたところ、当時の国内の世論は原子力歓迎ムードで、数多くの候補地があったが、最終的に茨城県東海村が選ばれた。
1956年に日本原子力研究所、現・独立行政法人研究開発機構が特殊法人として設立され研究所が茨城県東海村に設置され、これ以降、東海村はわが国の原子力研究の中心となった。
当初は原子力基礎研究を優先すべきとの主張があったが、先ずは電力需要を鑑み、原子炉力炉建設をして運転しながら研究をする同時進行型を決め、1957年12月に原子力委員会は1975年までに、700万kwの原子炉稼働する目標を掲げた。
1957年11月1日には、電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発公社が共同で最初の原子力発電が行われたのは1963年10月26日、東海村に建設された実験炉であるJPDRが臨界に達し初発電を行い、ここにわが国初の原子の灯がともったことになった。
かくしてわが国にも原子力発電の路が開かれ、日本原子力発電株式会社(民間出資8割)が誕生し、日本原電東海原子力発電所(日本初商用原子炉)にはイギリス製のコールダーホール改良型炉の導入が決まった。
ただし性能が悪く、採算面でも火力発電に劣るとの検証結果があり、更には耐震性にも問題ありと検証されたが、原子力委員会と財界の牽引力は大きく、原子力政策が大きく前進したのが中曽根康弘代議士が科学庁長官に就任してから「新・長期計画20年」が発表され、最初の10年間で商用原発の発電規模は3基100万kw、後の10年で火力発電量の30%程度(650~850万kw)、多分20基程度を予定していたのでしょう。

ただしこの構想は中曽根長官の独創であって正式な路線ではなかった。このような時、アメリカ側から甘い囁きがあった。アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE社)から魅力的な価格の軽水炉と「ターンキー契約」の申し出である。これは最初に固定化された契約金額が提示され、契約すると建造から臨界までの作業は全て契約者であるGE社が全てを請負、その後事業者はマニュアルに従って運用するだけという契約方式で、自力で建設・臨界までの技術がなかったわが国原子力業界は飛びついた。
原子力発電の路が開かれれば、あとは建設場所の選定になる。原電は東海発電所に続く第二号炉として、1961年福井県敦賀市を選び、建造はGE・東芝・日立のグループが請け負う契約を結んだ。契約者は関西電力であった。
以上のような経過を辿ってわが国の原子力発電は誕生し、急速に発展を遂げ、福島第一原発事故を契機として全国的な反原発、脱原発の大きなうねりがおきて、大飯原発を除き全国の原発は停止、再稼働の許可待ち状態になっている。
原子力発電設置の端緒を創ったのは若き日の中曽根康弘代議士であり、正力松太郎氏であったが、原発を全国的に建設し、設置数を急速に増やしたのは田中角栄氏の力によるものが大きい。
田中角栄内閣(1972年9月~1974年2月)は数々の業績を残したが、スキャンダルも数多く、まさに風雲児であり日本国中に旋風を巻き起こし、国際的にも電光石化の中国との国交回復、エネルギー問題を巡るアメリカとの対立、日本列島改造論等々、戦後最高の話題性に富む内閣であったことは確かだ。
「原子力発電、中東戦争、ロッキード事件」三題噺で田中角栄氏を表すことができる。
この背景には中東諸国と独自の外交を結び直接原油や天然ガスを輸入するルートを創ろうと画策した。これがアメリカ政府の激怒にあってしまった。
石油産業にはアップストリュウム(上流)とダウンストリュウム(下流)があり、アップとは石油探査、採掘、生産まで、ダウンは運輸、精製、配送、販売に分かれ、このアップ、ダウンの両方を支配しているのがスーパーメジャー(石油メジャー)で、セブンシスターズ(エクソンモビール、ローヤル・ダッチ・シェル、BP、シェブロン、トタル、コノコフィリップス)がソ連圏を除き世界の石油を支配しているのが7社なのでセブンシスターズと言われていた。(ユダヤ財閥系が多い)
わが国にある石油会社はダウンの精製・販売だけなので原油の確保にはいたってはいないばかりか、このセブンシスターズの配下にあった。
かつては出光興産やアラビア石油がサウジアラビアに鉱区を持ち原油を採掘していたことがあるが現在では全ての鉱区が契約期限切れで失ってしまった。
田中角栄氏の構想としては和製メジャーを組織して石油を確保しようとした壮大な構想を持っていた。
特にオイルショック時、イスラエルとの親交の度合いを諮る「踏み絵」を突きつけられた時、アラブ寄りを表明し、特使がアラブ諸国を歴訪しアラブ寄りを誓い石油物乞いを演じた[特使は三木武夫副総理]。

この行為にアメリカ政府、石油メジャーが激怒、危険なモノは芽のうちに摘んでしまうのが基本。この背景にあるのは、独立してまもない昭和28年、中東の石油はメジャーが支配していた頃、日本の独立資本である出光興産が石油メジャーの監視の目をかい潜って独立してまもないイラン政府から直接石油を買い付けたことがある。【出光興産に関しては『海賊と呼ばれた男』上下、百田尚樹著、アマゾン、2013年本屋大賞受賞。1953年イランからイギリス海軍の封鎖線をかいくぐり直接石油を買い付けた実話、日本側は快挙、石油メジャーは激怒した。この実話は東宝・三橋達也主演で映画化されたことがある】
横道に逸れるが、戦後史を語る上で重要な「日章丸二世事件」に触れてみたい。
第二次大戦後、世界の植民地は独立の気運に燃えていたから、中東も同じく独立運動に火が付き、これと同時に石油資源も自国の財産にしようとの気運が盛り上がった。
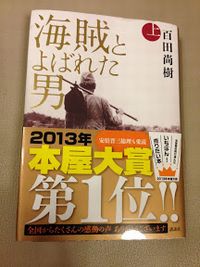
さらに宗主国だったイギリスやフランスが第二次大戦で戦勝国になったとはいえ、大きな痛手を蒙っているので、植民地支配に大きな力を加えることが出来ない。
これぞ好機と捉えるのが当然で、独立運動が活発化し、独立が相次いだ。
この好機と捉えたきっかけは日章丸の直接買い付けの成功であり、セブンシスターズの怒りは頂点に達し、日本に対する報復はこの時芽生えたといえる。
当時世界最大の産油国と言われていたイランは石油メジャー英資本の完全支配下にあったが、カジャール朝時代に王族であった廷吏の血をひくモサデックは留学先のスイスで法学博士の学位を取得した有能な若者が政界に入り、国会議員、閣僚を経験しやがて首相に選ばれた。

しかし、イラン政情は不安定で、モサデックはバーレビ王政下の1951年、国民の圧倒的人気で首相に選ばれ、持論であった「自国の石油なのに利益を外国にもっていかれるのはおかしなことだ」と主張し、民族主義の高まりを背景に、英資本の支配下にあった石油産業を国有化しようと活動したが、英資本と石油メジャーの反撃に遭い、国王は英米資本に籠絡されており、国王と首相の対立に発展したが、シャーを一時期亡命に追いやるほどであって、モサデック首相は更に自信を得て共和国を宣言するが、ところがこの亡命には裏工作があり、シャーは自分の意志で亡命したと見せかける策謀をCIAとMITが仕掛け、モサデック首相を罠にかけた。
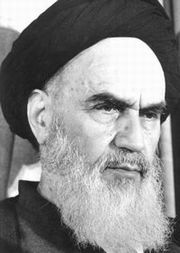
トリックに気付かなかったが、既に軍部は国王に忠誠を誓っており、1953年軍事クーデターで失脚、反逆罪で逮捕され、3年間服役、釈放後は自宅軟禁、外に出ることも許されず失意のままに病没した。
このモサデックが首相に就任し、石油資源国有化で英資本と対立していた頃、我が国が独立をはたした翌年の1953年(昭和28年)極秘に来日した特使が当時は小さな石油会社であった出光興産を訪ね、創業者出光佐三社長と直談判に及んだ。
出光社長自身も直接の買い付けを狙っていたので、商談は極秘に行われて成立、出光興産は新造したタンカー1隻だけ所有する小さな会社だが、出光社長の度量は大きく、社船のタンカー日章丸二世(1万8774トン、当時は日本最大の大型タンカーであったが、現在の基準では小型になる)を通常運航している港には入らず、神戸港に隠れ、夜間行先サウジアラビアとして出港(昭和28年)、(多分クリアランス[出港許可書](税関発行)も行き先サウジアラビアになっていたと考えられる。(この許可書が無いと外国の港に入港できない)。また、もしイギリスの艦艇による臨検を受けても行く先はサウジアラビアと主張できる。
ペルシャ湾ではイギリスの駆逐艦が見張っており、また常時タンカーの発信する無線電信を傍受しており、もしイランへ向かうことが判明すれば拿捕も辞さないと公表していた。もし1隻しかないタンカーが拿捕されれば倒産確実の中での決断だから社長の度量の問題だ。
日章丸二世は無線通信を封印して、無言のままホルムズ海峡を抜け、シャットゥルアラブ河を遡航して4月11日、積出港アバダンに横付けガソリン・軽油2万2千キロリットルを満載し無言で出航、ペルシャ湾に出たところで警戒中のイギリス海軍駆逐艦に発見され追跡、停船命令の旗旒信号(L旗)と発光信号を発信し続けたが、公海航行自由の原則に基づく無害航行権の権利を返信し停船必要なしと応答、戦争当事者ではないので拿捕は出来ない、拿捕すれば国際法違反になる。
この駆け引きで見事ホルムズ海峡を抜け、1ヶ月後川崎港に還ってきた。
かんかんに怒ったイギリス政府は外務省に厳重な抗議を申し込むと同時に、アングロイラニアン社は積み荷の所有権を主張して東京地方裁判所に即時積み荷の引き渡しを要求し提訴した。
しかし法的には無理な請求で、出光興産の行為は純粋な商取引であって法違反や国際慣行に違反したわけではない。さすが強気のアングロイラニアン社も不利を悟って提訴を取り下げた。
またイギリス側の行為は、一私企業の権益を護る為にイギリス海軍が出動するという行為は当然とする植民地主義時代の名残があった。
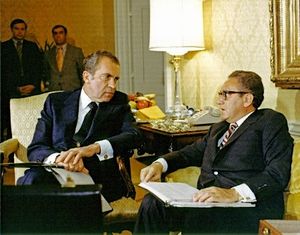
出光興産社長出光佐三氏は一躍時の人となり、戦勝国イギリスと堂々と渡り合い勝利したその行為に敗戦でしょぼくれていた日本国民を奮い立たせた。
そして苦しいイラン政府財政を助けてくれた恩人として出光社長を処遇し、その後の石油確保には数々の盡力があって出光興産は大きく伸び、唯一の民族資本の石油会社として成長した。
この事実は世界初の快挙と言われているが、石油メジャーから見れば痛恨の一撃であった。その怨みも重なって、石油最大の輸入国であった日本の動向如何が石油メジャーにとっても大きな影響があるため、実力者田中角栄氏封じ、あるいは排除に動くのは当然の動きであったかも知れない。
1970年代初頭、佐藤内閣の頃、我が国経済は猛烈な右肩上がりで、輸出が大きく伸び、その主要相手国はアメリカ、結果日米間には経済摩擦が頻発し、繊維交渉、続いて家電製品、自動車と日米貿易不均衡で貿易摩擦が頻繁に起きていた。アメリカ議会は反日ムードが満ちあふれており、日本叩きが公然と行われるようになった。当時のアメリカ大統領はニクソンとキッシンジャー国務長官と言う布陣。
日米経済摩擦を避けようと交渉が度々開かれ、アメリカ側の要求を呑ませようと度重なる日米交渉が行われた。

しかし、その交渉は難航した。それまでの日本は戦勝国アメリカの強大な力に服する従順な國と看做されていたが、この時初めて強硬な交渉相手になった。その時の日本代表は佐藤内閣の通産大臣であった田中角栄氏で、アメリカ側からみれば、初めて対等に渡り合う交渉相手に驚き、更には首相に就任するやいなやアメリカ側に相談もなく中国との国交回復を成し遂げてしまったことに激怒、更には独自の全方位外交、石油資源への独自の開拓、アメリカ側から視れば非常に危険な兆候に見視えて当然かも知れない。特に石油メジャーの観点からすれば「日章丸事件」で煮え湯を呑まされたセブンシスターズから視れば「憎き日本政府」となる。
歴代アメリカ大統領と石油メジャーは非常に近い関係にあることは明らかである。
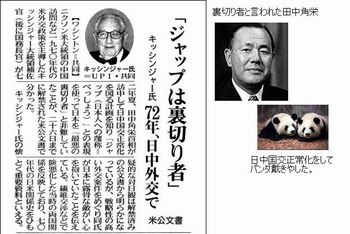
さらにキッシンジャー氏はユダヤ系のドイツ人で、ナチスが政権を取り、ユダヤ系の人々を迫害しだした初期の頃、危険を感じてアメリカへ一家は亡命、その時キッシンジャー氏は13才の少年であった。
当然ユダヤ系資本の石油メジャーには思い入れが強く、またアメリカ政府に執っても目障りな田中角栄氏の政治的な抹殺を狙っても不思議ではない。
外交とはグラスを片手に談笑と握手の繰り返しで行われているわけではない。様々な駆け引きと陰謀が渦巻くヤミの世界でもある。
(注、ジャップとは:Japジャップ、対日戦争中Japは反日プロパガンダで多用された日本人を辱める用語で、日本語で言う「アメ公」的な用語であるが、それよりも辱める程度の侮日的な用語である。キッシンジャー氏は1972年日中国交正常化交渉に激怒し、Japを用いて非難した。)
世界の動きを見なければ国内問題を考察することはできない。産油国である中東地域は常に戦乱の中にあった。
我が国もオイルショックもろに受け、明日の運命はどうなるのか全く判らない情勢にあったが、この時は田中内閣があって、独自の外交を展開した。即ち「アブラ寄り」と言われたアラブへの迎合政策である。
田中内閣の政策とアメリカ政府激怒の背景に触れてみたい。
石油産業 第三次中東戦争(1967年6月5日)、イスラエル空軍がエジプト、シリア、イラク、ヨルダンの四ヶ国の空軍基地を爆撃、これを壊滅させてから地上軍を攻撃、6日間で戦闘を終結「六日戦争」。
第四次中東戦争(1973年10月6日)、エジプト機甲師団が周到な準備の後、「失地回復」を狙って、シリア軍と連携してイスラエルを先制攻撃したが、猛烈な反撃に遭ってスエズ運河まで押し戻されてしまった。
この時、石油輸出国機構(OPCD)加盟産油国のうちペルシャ湾岸の六ヵ国が、原油価格を大幅値上げ、かつ原油輸出の大幅削減、イスラエルを支持するアメリカをはじめとする西欧諸国への経済制裁として石油輸出禁止を通告した。
これが第一次石油ショック(オイルショック)、更に第二次石油ショック、第三次石油ショック。イラン・イラク戦争とまさにペルシャ湾、ホルムズ海峡、シャットゥルアラブ河は戦乱のまっただ中にあった。
第五次中東戦争(レバノン戦争)、レバノン国内で起きた内戦。
1981年6月7日 イスラエル空軍、イラク原子力炉爆撃(バビロン作戦)

数々の闘いがあったが、クリントン・アメリカ大統領の仲介により1993年オスロ合意で、PLOのパレスチナ暫定政府が認められ、オスロ合意のイスラエルのラディン首相とPLOアラファト議長の二人はこの年のノーベル平和賞に輝いた。
しかし、その後まもなくラディン首相は暗殺され、アラファト議長は毒殺されてしまった。
その後は更に複雑になった中東情勢で、現在に至るも更に複雑になり、新たなISISが暴れだし、日本人が2人もの犠牲者を出してしまった。
我が国から遠く離れた中東問題で一喜一憂するのは我が国経済を左右しかねない原油の産出地域であるからで、田中角栄氏がアメリカ政府と対立したのも石油資源確保の方針に違いがあったからだ。
我が国もオイルョックをもろに受け、明日の運命はどうなるのか全く判らない情勢にあったが、この時は田中内閣であって、独自の外交姿勢を示し、即ち「アラブ寄り」の姿を鮮明にし、「アラブ寄り」の本心は「アブラ寄り」と揶揄されたが、背に腹は替えられない、といわれるようにアラブへの迎合政策である。田中内閣の政策の変化はアメリカ政府が激怒することは承知の上では承知上で背を向けざるを得なかった苦衷の選択であった。
石油危機対応で時の田中首相は大きく舵を切ったエネルギー政策が「脱石油」、即ち原子力発電への移行・推進であった。
この政策を執ることは、戦後一方的に支配してきた日本政府がでは、アメリカ政府の庇護が離れ、アラブ寄り、和製メジャーの構築、アメリカとの間に距離を置く政策とアメリカ側は見ていた。
1973年12月の参院予算委員会で、田中首相は「石油問題がここまで来たら、原子力発電が必要なことは議論の余地がない」「電力会社だけに任せず、抜本的な対策を政府が責任を持って行う」と答弁した。

決断するのが早い田中首相は即座に首相指示で原発立地地域にお金を回す為の「電源三法」の制定を急いだ。
電源三法(発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法)は、1973年末から法案ずくりに入り、‘74年3月に国会提出、6月成立というスピードでできあがり、その後は原発建設ラッシュとなって全国に54基の原発を擁する世界第三位の原発国になった。
昭和30年代から40年代年には好景気になり神武景気、神代景気と言われた右肩上がりの好調な景気の為、若い労働力は都会に吸収され、壮年の労働力も出稼ぎという形態で同じく都会に吸い寄せられた。
結果は地方の衰退がはじまり、国の骨幹であるはずの一次産業の衰退に繋がった。
そこで地方への工場分散、奨励が行われ、地方都市に工業団地の造成、誘致合戦があり、新産業都市が誕生した。
当時の双葉郡、あるいは福島県は何とか企業を誘致したい、と願うのは当然で、お隣のいわき地区が新産業都市に指定され生まれかわっていくのを目にすれば双葉郡に焦りが生ずるのも自然の流れだ。
これまでの陳情や運動が空振りに終わっていたのが、電源三法により雇用が生まれ、関連企業が誘致でき、何よりも眼を見張るような交付金がある、嫁入り持参金に眼が眩んでも無理はない。
安全性への懸念は勿論あったが政府も電力会社も絶対大丈夫と保障しており、この頃から「安全神話」は公認されたものとなっていた。
電源三法が無ければ原発誘致、建設のテンポはかなり遅れていたと思われる。
石油危機に見舞われ、それに続く狂乱物価、その対応に追われ、対外的にはアメリカとの繊維、車、家電製品等の交渉が縺れ、さらにはフランスからのウラン調達、アラブよりアブラと言われた中東寄りの外交、アメリカに先んじた日中国交正常化などアメリカ政府との対立がめだった。特にキッシンジャー国務長官の激怒は凄かったらしい。
この当時、米中関係は激しく対立しており毛主席は本気でアメリカとの戦争を想定したようであったが、キッシンジャー国務長官がパキスタン訪問中、突如姿を消し、密かに北京を訪れ米中関係の打開を謀った。これがキッシンジャーの忍者外交、頭越し外交といわれ我が国政界を仰天させた。
そうすると田中氏は、総理になるや即座に中国を訪問、日中国交正常化を樹立してしまった。
アメリカは未だ首脳会談にまで至っていなかったため先を越されたキッシンジャー国務長官の怒りは凄まじかったと伝えられた。
羊のように柔順に装いノラリクラリとしていた日本政府が初めて明確に逆らったことに戸惑いがあったのだろうか。
 |
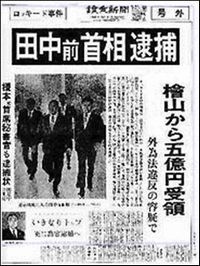 |
田中内閣は外交では独自のエネルギー源確保政策、全方位外交を目指し、国内では列島改造論を掲げ、土建屋的な政策を推進した。
近隣諸国との摩擦は減少したが、‘出る杭は打たれる’の喩え通りアメリカとの摩擦は大きくなってきた。
また国内でもあまりにも金権政治による強引さが目立ち始めると、反田中の動きが活発化するのもやむを得ない。
内外からの批判が集中し、特に金権政治の汚名は付きまとっていたが、1974年10月、月刊誌「文藝春秋」で(田中角栄研究)と(淋しき越山会の女王)が掲載(著者立花隆)され、金脈問題が追求された。
東京に日本外国特派員協会という社団法人があり、ここに所属する外国人ジャーナリスト達は週に1、2回内外の政治、実業、スポーツ等の様々な時の人を呼んで主催記者会見を行うのを慣例としていた。著名人を招待していたが、時の人、田中角栄首相が招待され、外国人記者から立花隆氏の文藝春秋誌上に発表された「田中角栄研究」に関する献金問題に関する質問が集中し、その模様が内外メデアに流された結果、国内のメデアは情報を把握していながら発表を躊躇していたが、一斉に記事にしたため内閣崩壊に繋がってしまった。
エネルギー確保を独自に展開しようとする政策で、当然世界の石油企業を支配するセブンシスターズの怒りを買うことになる。また原油の消費を出来るだけ減らそうと原子力発電の奨励で、電源三法が生まれるのはこのような社会情勢が背景にあった。
アメリカ政府はニクソン大統領、キッシンジャー国務長官の時代であったから、田中内閣とは悉く対立することになり、その報復がアメリカ議会でリークされたロッキード事件、田中首相包囲網は確実に布石された。
この時金大中拉致事件(1974年8月)もあった。
立花隆氏の金脈追求の論文が「文藝春秋」に掲載され、田中内閣崩壊。
その後ロッキード事件で、5億円の受託収賄罪で逮捕され、一審有罪、控訴中に病死した。
このロッキード事件の特異さ複雑さは、発震源がアメリカ上院チャーチ委員会での公聴会、ロッキード社副会長アーチボルド・カール・コーチャン、元東京駐在代表ジョン・ウィリアム・クラッター両氏が公聴会に召喚され、司法取引によって免責されていたからあらゆる証言を表明した。
その複雑さは工作資金のルートが多岐に渡り、会社、組織よりも私的な秘密機関を通じていたこと、その最大は行動右翼の児玉誉士夫氏、占領時代のCIAと関係があった日系アメリカ人シグ片山、GHQの諜報担当トップのチャールス・ウィロビーの片腕だった福田太郎氏等が暗躍していたことが公聴会で証言された。
この事件の複雑さはロッキード社から日本ルートとして30億円の工作資金が流入していることは証言さているが、前総理田中角栄氏に流れた5億円だけが表に出て起訴されたが、他の多くの工作資金の使途は明らかにされなかったから「政治主導裁判」ではないかとの多くの批判があった。
その理由は、事件の核心を握る児玉氏が衆議院予算委員会に証人喚問に応ずる予定であったが病気として自宅に籠もり、その間、軽飛行機が私宅に突入するという自爆テロがあったが、別の部屋に寝ていて間一髪で無事だった。その後大学病院に入院し、口を噤んだまま1984年病没、真相は胸に秘めたままだった。
捜査の開始は首相三木武夫、法務大臣稲葉修三がャーチ委員会の証言内容を検討し、直々に捜査開始を指示、同時に米・ジェラルド・フォード大統領に対して捜査の協力を依頼、日本側は最高検察庁、東京高等検察庁、東京地方検察庁、警視庁、国税庁の合同捜査態勢を整えた。
更には、三木首相の密使として元NHK解説委員、外交評論家の平沢和重氏が渡米し、キッシンジャー国務長官と会談させ、アメリカ側の資料提供を求めた。
また東京地検からは担当検事が渡米、アメリカ検事局の資料提供を要請した。

捜査開始と同時にマスコミが過熱し、連日新聞や週刊誌で報道され、テレビでは国会中継で証人喚問という吊し上げのような映像に度肝を抜かれ、超一流の人物が打ちし折れ、緊張で震えているような異様な光景に驚かされた。
そして政界では宿敵田中角栄を抹殺しようとする三木派の陰謀だと田中派は猛り狂い、自民党の長老椎名悦三郎氏は「三木ははしゃぎすぎ」とたしなめるような言動があった。
結果は他の派閥も田中派を支援し、三木派は孤立、総選挙で自民党が8議席を失う敗北で、三木政権は責任を取らされて首相を辞任、三木おろしの急先鋒福田赳夫内閣が誕生した。
しかし、田中派が最大派閥で福田内閣は「角影内閣」と呼ばれ、大平、鈴木、中曽根も「直角内閣」「田中曽根内閣」と揶揄されるような田中氏のリモコンに操られたような政治になってしまったのは、田中氏が無罪を勝ち取るためには権力を集中させておく必要があり、闇将軍と言われながらも隠然たる権力を維持した。しかし、これが我が国の権力構造が歪になりやがて与党である自民党の活力を奪うことになる。
それはまた日本の活力の停滞、次第に衰退の始まりもこのロッキード事件が切っ掛けといえる。そしてまた田中角栄再起の夢を打ち砕いた。
追い打ちをかけるようにリクルート事件が政界を総なめにして自民党のレギュラー選手が追いやられ、控えの選手が第一線に出ざるをえなくなり政界は更に小粒内閣・短命内閣が連続することにうなった。
ロッキード事件の不気味さは政界ばかりではない。経済界、裏社会までもが揺れ動き、取材中の日本経済新聞の高松康雄記者が急死(1976年2月14日)。渦中の元GHQ要員福田太郎氏急死(1976年6月9日)。
田中角栄氏の自家用運転手兼私設秘書・笠原正則氏が命じられて運んだダンボールの箱に札束が入っていたとの検察の筋書きによって取り調べを受けていた直後の1976年8月2日、埼玉県比企郡山中の林道で変死体で見付かった。

この三氏は病死なのか、事故死なのか、証拠隠滅を謀る組織による暗殺なのか、闇の中に消えてしまったが、警察発表は病死と自殺で捜索は打ち切られた。
また児玉誉士夫ルートこそが本命であるにもかかわらず、病気を理由に事情聴取を拒み続け、検察もまた深追いすることなく、真相を秘めたまま病没した。
この暗闇こそが巨大な力による陰謀説を裏付けるもので、田中氏個人への集中攻撃の様相があったが全ては藪の中。やがて田中派は分裂、竹下派の旗揚げとなったが、怒りがこみ上げたのか田中氏は脳梗塞で倒れ、事実上田中派は消滅。最高裁で審議中に死去、ロッキード事件5億円収賄事件は被疑者死亡で終審した。
しかし、無罪ではない、それは同じ罪状で起訴されていた秘書の榎本敏夫氏が有罪判決であったから、結果的に5億円収受を認定されたことになって「宰相の犯罪」は消えることはなかった。 従って首相在位1年以上の経験者に贈られるのが慣例であった大勲位菊花大授章に叙せられることはなく巨星は消えた。
この事件はアメリカ上院委員会が発震源であり、その基はアメリカの大企業、政府高官、企業責任者が関わっていながら司法取引で法に問われた人物はなし。日本国内だけが大騒動で政府も経済界も大打撃を受け、人の命も奪われた。
どのような組織がどう動いたのか、真相は闇の中。ケネディ大統領暗殺事件のようにすべてが闇の中に葬られたのか、人の噂も75日、いまでは思い出す人も少ないし、全く知らない人も多いだろう。

政界はロッキード事件、リクルート事件と政界を揺るがす事件が起き、次期総理・総裁ともくされたり、大物政治家として期待されていた人達は事件に何らかの関わり合いがあったりして、表舞台から消えてしまい、二軍から急に引き揚げられた議員が晴れ舞台では戸惑うばかりで短命でおわるのはヤムを得なかった。
政治が弱体になれば経済も下降するばかり、国民は意気消沈、誰が仕掛けた罠なのか、踊りすぎた日本が悪いのか、踊らせる罠を仕掛けた方が悪いのか、表面的な外交はにこやかにシャパングラス片手に談笑しながら日々動き、国際的な陰謀もまた深く静かに日々動いているのもこれが現実。
ロッキード事件のアメリカ陰謀説を唱えた最初は評論家の田原総一朗氏で1976年7月号の「中央公論」「アメリカの虎の尾を踏んだ田中角栄」だった。
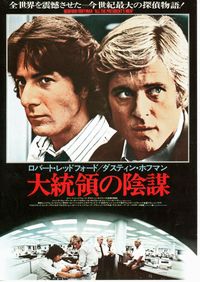
ニクソン大統領は1974年9月8日、ウォーターゲート事件の責任を執って任期途中で辞任した(歴代大統領で刑事事件で任期途中での辞任は歴代初めて)
(ウォーターゲートとはワシントンDCにあるビルの名で、ここに部下が侵入し、政敵に対する何らかの工作の目的があったらしいが、事前に逮捕され、最初はこそ泥程度と思われていたが、侵入を命じたのがニクソン大統領であったことが判明)『後に「大統領の陰謀」というハリウッド映画が公開された。ダスティン・ホフマン、ロバート・レッドフォード主演、アカデミー賞で助演男優賞(ジェイソン・ロバーズ)、脚本賞、美術賞、録音賞の4部門を受賞した』
この映画を観たが大統領執務室で練られる陰謀の数々がリアルに描かれており、思わず引き込まれてしまった。もしかしたらロッキード事件もこのようにして仕組まれたのかも知れないと想像は果てしなく拡がっていったが、後刻、種々の背景が浮かび上がってくると確信に代わってきた。
東西古今、政治の世界は闇の中。清廉潔白な政治などあるわけがない。あれば即座に崩壊する。理想と現実の狭間は厳しい。
角栄流政治は終わったが、国内政治は更に混乱し、外圧はさらに強まり、その最大はエネルギー源確保に苦慮することになる。
我が国の繁栄、国民が安心して暮らせる環境ずくりは安定したエネルギー源確保にある。しかし原油や天然ガスの8割以上が中東地区に頼っている。その地域が常に政情不安定で揺り動き、原油の生産も価格も不安定で、何時、何が起きるか全く読めない危険さがある。
田中内閣の動きは、なんとか独自のルートを開拓したい。あるいは石油に頼らない新しいエネルギー源確保への焦りだった。
その後の内閣も中東政情不安をもろに受けて薄氷を踏むような思いの舵取りとなった。
 |
| (OPEC石油輸出機構加盟国) |
そして現在(20015年3月)の世界は大きく様変わりして、あれほど悩まされてきた原油価格が大幅値下がりして、原油がだぶつくという現象が起きてきた。
原油価格の大幅値下がりの原因は何か。原油価格はここ数年は1バレルあたり100ドルで推移していたが、昨年秋頃から下落が始まり、特にOPEC(石油輸出機構)が2014年11月27日、開催された総会で減産を見送ったことを受けて原油価格が急落しだした。
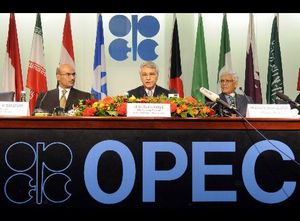
NYの原油先物市場では、代表的な油種であるWITは1バレル=65ドルまで下げ、2010年5月以来の安値を付けた。
このような原油値下げの背景は世界的な原油の供給過多にあり、この供給過剰の最大の原因は、アメリカを中心としたシェール革命にあり、従来はその存在は識っていたが、地中深い岩盤のシェール層(日本語では頁岩)と呼ばれる地層の中から原油や天然ガスを採掘することが困難であったが、近年採掘できる技術が開発され、採算がとれるようになって、急速に生産が増大してきた。
そうすると原油との価格競争となり、OPECは当然減産して価格維持を謀ると思われたが、かえって増産に踏み切った。
その思惑はなにか、増産し原油の価格破壊によりシェール革命であるシェールの生産を妨害する狙いがある。すなわち原油価格が暴落することによって、シェール生産の採算割れを狙ってのことだが、この影響は即座に現れ、シェール生産が減産し、かつ開発の速度が大幅に減退してきた。
このような影響は消費国にとっては原油価格の値下がりは歓迎すべきことだが、石油会社は経営が苦しくなってきたところもある。
OPECとは石油輸出國機構のことだが、このOPECは生産量と価格の決定権を持ち、世界経済の命運を左右するほどの存在であった。
世界で初めて中東から直接買い付けた出光丸事件の頃は、この機構はなく、1バレル=1ドル以下であった。
1971年、イスラエルとアラブ諸国による第三次中東戦争が勃発すると、この原油を質としてアラブ原油生産国が結束して機構を結成、オイル経済戦争を挑んできた。これにより当時1バレル=3ドル程度であったのが、一挙に1バレル=12ドルに跳ね上がり、さらにイスラエルを支持する欧米諸国への供給削減を通告、第一次石油危機が始まった。我が国にもどちらを支持するかの踏絵が突き付けられ、石油が欲しい我が国はアラブ寄りを表明、これがアラブよりもアブラよりと言われた所以だ。
そうなるとイスラエル国の最大の支持国であるアメリカと対立してしまうのもやむを得ない。特にユダヤ系のキッシンジャー氏が烈火のごとく怒りだし、「ジャップは裏切り者だ」と罵ったが、我が国は黙りを決め込んだ。
その後、OPECは1979年~1980年には原油価格をさらに3倍に引き上げた。これが第二次石油危機で、それには中東における混乱が原油価格を高騰させた。
最終高値は1バレル=100ドルに高騰したが、現在は60ドル前後に落ち着いた。
これからしばらくは高騰することはないと思われる。また、シェール革命も安定して推移するものと思われる。
次なる時代は日本近海に存在するメタンハイドレートのような海底資源開発や、海洋そのものを活用した海洋再生可能エネルギー発電システムのような我が国独特のエネルギー源確保に全力を注ぐべきだ。
今こそ外国のトラブルや思惑に左右されない確固たるエネルギー源確保に向かうべきだ。
第33章 中東情勢と原発
我が国の経済は右肩上がりが続き、電力はいくらあっても足らない位の状況が続いた。
原発を55基まで増設したが、これ以上の建設は適地が見付からない。国民感情として更なる増設は否定的であり、頭打ち状態になり、火力発電への傾斜となったが、ここで立ち塞がるのは二酸化炭素排出問題、温室効果ガス問題、地球温暖化問題。世界的には温室効果ガス削減問題が深刻化し、国連での討議、京都議定書、先進国と途上国の対立、火力発電への風当たりも強かった。
一方、再生可能自然エネルギーによる発電は研究課題ではあるが、理想の段階で、実用化としては遙か彼方の目標でしかなかった。
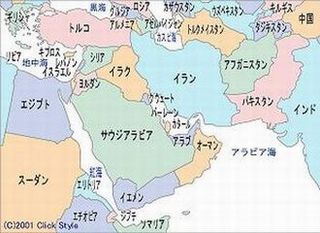
矢張り最後の頼りの綱は自動車産業を含めて石油と天然ガスの化石系のエネルギー源しかなかった。
しかし、問題は政情不安な産出国であり、危険性を孕む輸送ルートにあった。
大半の人々は、中東の歴史など興味もないし、世界史の教科書ではペルシャ文明、アレキサンダー大王の活躍等ホンの僅か触れるだけ。しかも紀元前の歴史であり現代の中東など全く触れないから中東に関する知識は殆どなく、また関心もない。

しかし、我々の日常生活には不可欠な石油の90%が中東から、しかも最も危険なペルシャ湾、ホルムズ海峡を経て運ばれてくる。もし石油の供給が絶たれれば、我々の生活は成り立たないことは承知しているが、石油危機で石油の供給が途絶する寸前までいって関係者を震撼させた事実を一般国民には余り知られていない。
その危険性を少しでも回避するために原油消費の縮小化、原油輸入ルートの多様化、化石燃料依存の縮小、新しいエネルギーの開拓等へのシフトとして原発があり、これはまた二酸化炭素排出削減の切り札でもあった。

この化石燃料依存を少しでも削減しよう、新エネルギーへのシフトを少しでも早く切り換えよう、石油輸入のルートを多様化しようと果敢に挑戦し悪戦苦闘した田中角栄氏の奮闘も虚しく返り討ちのような形で消えてしまったことを国民は余り興味もなく評価もしていない。
中東戦争、石油戦略、原油高騰、原油生産削減、親イスラエル国への原油輸出禁止、世界の産業界は混乱の極致、物価高騰、モノ不足、狂乱物価、特に我が国のように原油輸入の90%以上を中東に依存するという経済構成ではモロに影響を受け、国の浮沈に関わる大問題として捉えられた。
そこで執られたのが新エネルギーへの転換政策として原子力発電所の依存を高めることで急速に設置数を増やし、世界第三位の54基となった。
それが今、反原発、脱原発で連日国会議事堂周辺でのデモや集会が行われ国中が騒然となっているが、原発に替わるべき新エネルギーは確立していない。
自然エネルギーへの切り替えは理想であるが、未だ1%程度、発電能力が30%以上になるまでには幾多の壁を乗り越えなければならないし、後何十年かかるのかも見通せない状況の中で、脱原発だけが一人歩きすれば化石燃料依存に逆戻りするだけの異常事態になってしまう。現在辛うじて酷暑の夏を乗り切ろうとしているのは休眠中だった火力発電所を全面的に急遽復活して最大限活用しているからであって、既存の発電設備で間に合っている訳ではない。国民感情としてそれでも?とするのか、冷静に考えるべきなのではないか。
12年上期(1~6月)貿易赤字過去最悪2.9兆円
財務省が7月25日発表した12年上期(1~6月)の貿易統計速報(通関ベース)によると、製品や原材料の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2兆9158億円の赤字(前年同期は9632億円の赤字)となり、第二次石油危機後の80年上期2兆6217億円の赤字を上回って半期ベースでは過去最大の大幅赤字となった。
輸出は前年同期比1.5%増の32兆5956億円で、3期ぶりに増加したが、一方で輸入が7.4%増の35兆5113億円と5期連続の増加、これは液化天然ガス(LNG)が49.2%増と急伸したほか、価格の高止まりが続く原油も15.7%と急増した。
原発の稼働停止に伴い、火力発電向け燃料の輸入が膨らみ続け収支は悪化の一途を辿る。
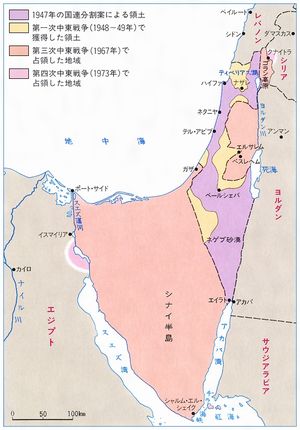
◎中東情勢
○第一次中東戦争:1948年5月14日イスラエル建国独立戦争、イスラエル対周辺国家(エジプト、イラク、レバノン、シリア、ヨルダンのアラブ連盟5ヶ国、サウジアラビア、イエメン、モロッコの3ヵ國は大混乱。
イギリス、フランスは義勇軍を派遣、イスラエルが勝利した。
○第二次中東戦争:1956年10月29日スエズ運河争奪戦争、フランス、イギリス、イスラエル軍がエジプト侵攻、アメリカの調停で停戦
○第三次中東戦争:1967年6月5日、イスラエル空軍がエジプト、シリア、ヨルダン、イラクの空軍基地を同時に空襲し壊滅させたから、地上軍が侵攻し短期間で占領した。
○第四次中東戦争:1973年10月6日、エジプトの機甲師団が周到な準備をしてから隠密裏に近づき国境線を超えてイスラエルに侵攻したが、緒戦は勝利したが、直ぐに反撃にあい、反対にスエズ運河まで押し戻され、エジプトの領地を失ってしまった。
○この時、アラブ産油国OECDは結束して原油価格の値上げ、新イスラエル国への原油供給削減、禁止等を通告、世界は大混乱となる。
○イラン・イラク戦争:1980年~1988年、イラクがイラン侵攻から始まり、一進一退の硬直状態のまま推移し、その間イラン、イラクからの原油輸出は停止。
○湾岸戦争:1990年8月2日イラク正規軍がクウェートを侵攻、同国全土を占領支配、王室は辛うじてサウジアラビアへ脱出した。
アメリカ軍を中心とした国際連合が34ヶ国からなる多国籍軍を結成し1991年1月17日:アメリカ海軍空母から飛び立った攻撃機による空襲から始まった「砂漠の嵐作戦」。
○イラク侵攻;2003年3月20日 正規軍同士の戦争は1ヶ月程度で終結したが、治安が悪化し、地下組織の抵抗があり2010年8月31日オバマ米大統領がイラク パレスチナは長い間イスラーム国家の支配下に置かれていたが,この地に居住するイスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒の三者は共存共栄の関係を維持してきた。
しかし、20世紀初頭オスマン帝国が第一次世界大戦に敗れると,帝国が支配していたパレスチナはイギリスの委任統治領として植民地化した(イギリス委任統治領パレスチナ)
この頃既にドレフュス事件等の影響もあり、ヨーロッパではパレスチナ帰還運動(シオニズム)が起きていて、ヨーロッパやアメリカ,その他の地方に離散生活していたユダヤ民族のパレスチナ入植がはじまり、イギリス政府も入植を黙認していた。
しかし、入植者が増えれば現地のアラブ人との摩擦は増え、アラブ人はイギリス政府に入植の制限を求め、アラブ人とユダヤ人との争いにイギリス軍が仲介で入ることの連続で,次第に三者は対立するようになり、ナチスドイツが台頭するとユダヤ人迫害があった。第二次大戦が始まるとエスカレートして強制収容所、集団殺害という異常事態に直面したユダヤ系住民はこれを遁れるためあらゆる手段をもってアメリカや「約束の地」パレスチナへの帰還しようとし、無事入植したユダヤ人と現地アラブ人との対立がより鮮明になった。
大戦後、事態収集が困難とみたイギリスは,戦後に成立した国際連合に提訴し、国連は1947年11月に、パレスチナを分割しアラブとユダヤの二国を建設することを決議(パレスチナ分割決議)し採択した。
しかしこの決議に反発したアラブ人はユダヤ人との武力紛争(暴動、テロ、民兵同士の武力衝突)が頻発
○1948年5月14日、第一次中東戦争(イスラエル独立戦争)
イギリスはパレスチナ委任統治の放棄を宣言、ユダヤ人はイスラエル建国を宣言(イスラエル独立宣言)。しかし翌日イスラエルの独立を認めない,周辺アラブの国々(エジプト、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、シリア、レバノン、その他パレスチナのアラブ人部隊総計15万人以上の兵士)がパレスチに侵攻、イスラエル軍は僅か3万弱の兵士、第一次中東戦争が勃発したが、近代兵器で武装したイスラエル軍の必死の反撃で、アラブ連合軍を破り、より多くの領土を確保、一方で、多くのパレスチナ難民が発生してしまった。
この第一次中東戦争を、イスラエルでは独立戦争と呼んでいる。
この戦闘にアラブ連合軍のエジプト陸軍ナセル少佐は敗北の原因として満足な軍装備がないからだ、軍事予算を国王ファールーク1世が勝手に流用しているからだと、自由将校団を結成してクーデターを起こして、国王を追放し、王政を廃止した。軍部が政権を握り第一次中東戦争で活躍した将軍ムハマンド・ナキブを首班とする政権にし、ナセルは副首相兼内務大臣になった。
しかし、革命後の権力争いは歴史が教える通りで、首班ナキブ将軍と自由将校団が対立、更にムスリム同胞団によるナセル暗殺未遂事件があり、ナキブ将軍解任、追放、1956年6月25日ナセル大統領が誕生した。
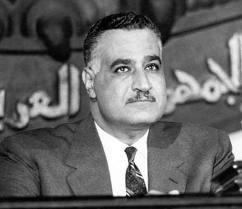
ナセル大統領の目指す社会はアラブ社会主義政策であり、外交は汎アラブ主義政策を標榜し、主力産業や銀行の国有化を謀った。さらにアラブ諸国の団結を唱え主導権を握り、やがては第三世界を構築してそのリーダーになることであった。
その第一は国民生活を安定・向上させるためイギリスが統治していた時代にナイル河の上流を堰き止めて灌漑、発電、流量調整するダム建設の計画があったがエジプト革命が起きたので中止された。
ナセル大統領の理想はアラブ社会主義政策を進めることであり、外交面では汎アラブ主義で、西ヨーロッパ諸国とは対立するものであって、ソ連圏に近づく素因があった。
ナセル大統領の悲願は、ナイル川を上流で堰き止めダムを建設して電力を確保して工業生産の拡大、灌漑によって農業の振興。砂漠から豊かな農地への変換にあった。最初ヨーロッパ諸国へ借款を申し出ていた政策的に西ヨーロッパ諸国とは対立関係になってしまい、そこでソ連政府に資金援助と技術援助を求めたが、ソ連側はエジプトと要衡の地とスエズ運河の権益を手にすれば、西ヨーロッパ諸国とアジアを結ぶ重要な回路を支配できれば西ヨーロッパ諸国に大きな圧力をかけることが出来ると判断し、積極的にナセルを支援した。
そのためか意を強くしたナセル大統領はスエズ運河国有化宣言を出した。
スエズ運河は1869年、フランス人レセップスの努力とフランス、イギリスをはじめとする多くの資本を集めて完成した。が完成のために予定より倍以上の資金を要したため完成直後から経営難に陥り、持ち株を大量に放出したのでイギリス政府がこれらを買い付け、株の44%を保有する筆頭株主になった。
このことによってスエズ運河は事実上イギリス政府が支配することに長年運河経営に携わってきた。それが突如エジプト政府の国有化宣言だからイギリス政府が激怒するのも無理はない。
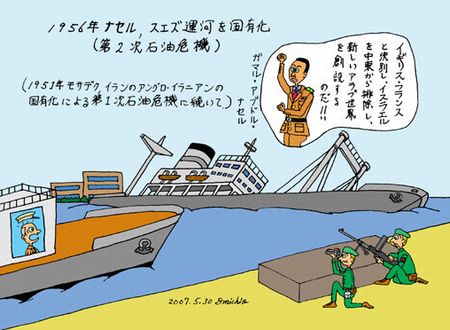
○第二次中東戦争(スエズ動乱)1956年10月29日
即刻、スエズ運河地帯にイギリスとフランスの空挺旅団が舞い降りて、陸路をイスラエル軍が進撃しスエズ動乱が始まった。
一方、エジプト軍はスエズ運河に船を沈めて運河使用不能にする作戦に出て、かつ同盟にあったアラブ諸国連合軍が蜂起、また世界の世論が植民地支配の再来と英仏を非難したため、アメリカが中立の立場から和解を仲介し、結局イギリス、フランス両軍は撤兵、スエズ運河のエジプト政府国有化を認めた。

その結果、スエズ運河からイギリスが撤退、運河で働いていた多数のパイロットはヨーロッパ系の白人が多く、全員が職を解かれ追放された。
ところがエジプト人のパイロットはおらず,パイロットが零の期間があった。
ただし多数の沈船が運河を塞いでいたので、その除去にしばらく時間を要した。その間、ナセル新政府にソ連政府が急速にアプローチし、多額の資金援助を申し出た。これは、スエズ運河は西側資本主義国々の大動脈であり、これをソ連圏の支配下に置けば西側資本主義国々を分断できるとほくそ笑んだ。またアスワンハイダムはソ連政府の多額の援助で完成した。エジプトとソ連は蜜月となり、西ヨーロッパ圏とソ連圏との対立は鮮明になってきた。
ナセル大統領は国民の生活を向上させるためナイル河の上流で堰き止め、発電と灌漑に活用しようと巨額な融資をソ連に求め、ナセル湖を建設、偉大なる文化遺産,「王家の谷」は、世界中が反対したが、この時水没した。
また沈船の引き揚げと運河航路の浚渫工事は実績のあったわが国の五洋建設が請け負った。現在でも運河全域の浚渫・改修工事は五洋建設が受注している。
ナセルは反イスラエルの感情から元ナチスの高官や技術者達が戦後逮捕を免れるため第三世界に逃亡し潜伏していたが、この人達を積極的に探し出し、エジプト国内での安住を保障して政権拡充の為の大幅な権限を与え国家再建に協力させようとした。しかし一方でソ連からも政府顧問団、技術者、軍事顧問団がきており、更にアスワンハイダム建設やその他国家再建の為の資金をソ連からの援助に頼っていたから元ナチス高官とソ連顧問団が対立するのは当然の帰結であて、何しろ独ソ戦が終結して間もない頃でしたから不倶戴天の敵同士であって、力を合わせてエジプト再建のために協力しようなどとは思いも及ばない。結果としてナセル大統領への突き上げが激しくなるばかりであった。
○ 第三次中東戦争 1967年6月5日
ゴラン高原にユダヤ人入植地を巡りアラブ側とユダヤ側の間で緊張が高まっていた1967年6月5日、イスラエル空軍の攻撃機が(レッド・シード作戦)はエジプト、シリア、イラク、ヨルダンの各国へ同時に超低空で侵入し各空軍基地への先制攻撃を挙行し,多数の作戦機を破壊した。第三次中東戦争は始まったが、緒戦でアラブ側作戦機410機が破壊されたため制空権を失ったアラブ側は,地上戦でも完全に敗退し、ヨルダン側西岸、エジプト・ガザ地区とシナイ半島、シリアのゴラン高原を迅速に占領し、領土は4倍にも拡大した。
この戦闘は6日間という短期間で占領してしまったので「六日戦争」と称している。この時の大統領は引続きナセルであったが第三次中東戦争では惨敗、領土の一部はイスラエルに奪われたため、責任を執って大統領辞任を宣言したが国民の熱い支持に支えら辞任を思いとどまった。
イスラエルに対しては強硬策に終始し「承認しない」「交渉しない」「和平しない」「パレスチナ人の権利回復」を叫び続け国民の喝采を浴びていたが、スエズ運河閉鎖によって航行手数料の収入は零、外国からの観光客は皆無でエジプト国の二大収入源が零になってしまい、国内経済は破滅、加えてアスワンハイダム建設、軍事力の整備その他でソ連から多額の借款があった。加えてソ連から多数の技術者、軍事顧問団が国内に集結、一方、「反イスラエル」の観点からナチス高官や技術者を多数匿って、その大半を軍事力強化、公安機関、秘密機関の養成や反ユダヤ主義プロパガンダに活用しようとした。
例を挙げると元ナチ党宣伝活動をしたヨハン・フォンレ・レールスはエジプト国内で反イスラエルの宣伝活動を指導。ゲシュタポ幹部だったレオポルド・グライムはエジプト国家公安局を指導、元ナチス国防軍の技術者多数が参加して弾道ミサイル開発に携わり危機を察知したイスラエルの諜報機関モサドが潜り込み暗殺・排除等闇の中での独ソ戦の延長戦のような暗闘がけり広げられた。
同時にソ連とナチスは不倶戴天の敵であるからエジプト政府内でトラブルが起きるのは当然であり、それに加えてヨルダン内戦の仲裁や、北イエメン内戦への軍事介入等々事件が重なり、自分が撒いた種とういえ、余りにも多くの心労が重なったせいか、1970年1月15日、ナセル大統領は心臓麻痺により52歳の若さで急死した。理想に燃えて革命を成功させた若きナセル陸軍少佐も、余りにも過激な手法で革命に取り組んだが故に、ソ連、ナチスを利用し、イギリス、フランスを相手に闘おうとしたが、反対に翻弄され、調整が就かないままあっけなく世を去ってしまった。

残ったのは混乱したままのエジプト情勢で、ナセルのあとを継いだのはサダト副大統領、1970年9月28日、正式にエジプト大統領に就任した。
アンワル・アッ=サーダート(1918年12月25日~1981年10月6日)
○第四次中東戦争 1973年10月6日、前戦争で完敗したエジプト軍は周到な準備を進め、隠密裏に砂漠を前進した機甲師団がイスラエル軍の防衛戦を攻撃した。反対側からは示し合わせていたシリア軍が侵攻してきた。

この日はユダヤ教徒にとって重要な贖罪日(ヨム・キブール)の期間であり、イスラエルの休日であったため、不意を突かれたイスラエル軍が初期防衛に失敗し、国民皆兵のイスラエルでは通常は各種の職業に従事しているため、ラジオ放送が予備役軍人の非常呼集の番組を流し、小さな国故に即座に軍務に復した軍人達は予め決められていた軍務に就いた。おそらく世界一訓練されているイスラエル軍は強力で、僅か4日で予備役の兵士を非常呼集し、予め決められている兵役に就くと反撃の態勢が整え10月11日、一斉に反撃に転じ、エジプト機甲師団は退却をはじめスエズ運河周辺まで簡単に押し返されてしまった。
シリア軍を中心としたモロッコ、サウジアラビア、イラク軍からなる義勇軍はゴラン高原を攻撃してイスラエル軍を撃退して占領したが、イスラエル軍の本格的な反撃がにあうとこれもまた簡単に撃退されてしまった。
この敗退がエジプト軍の限界を悟りアメリカを中心とした国際調停団により10月23日には休戦協定に調印した。
緒戦で勝利したエジプト軍と反撃で何とか食い止めたイスラエル軍とが休戦協定により和解したが、エジプト軍が何故弱体なのか、国内経済が弱体なのは何故なのか、サダト新大統領の悩みは尽きなかったことだと思う。そして辿り着いたのはナセル前大統領が敷いた政策の全面的な見直しである。ソ連型社会主義の疑問、ソ連顧問団との軋轢、ソ連製の戦車その他で装備された機甲師団が絶対的な自信を持って攻め込みながらアメリカ製の兵器で装備されたイスラエル軍に簡単に押し返され、退却に次ぐ退却でスエズ運河まで短期間で押し戻された屈辱。何が原因なのだと自問自答したとき結論はナセル大統領の外交路線を全て破棄、新しい路線としてソ連社会主義を破棄、ソ連人顧問団、技術者を追放、アメリカへ急接近、というサダト大統領の政策変換を発表。

驚いたのはアラブ諸国でサダト大統領をアラブの裏切り者として糾弾したが、サダト大統領として破綻してしまったエジプト経済を救済する手段としてはアメリカをはじめとする西側諸国との経済交流のみがエジプト経済を救済しうる唯一の手段であるとの信念で思い切った路線転換を行った。
1977年イスラエルのメナヘム・ペギン首相の招きでエルサレムを訪問、エジプト・イスラエル間の和平交渉が開始され、翌1978年、アメリカ・ジミー・カーター大統領の仲介でキャンプ・デービット合意にこぎつけ、平和条約が結ばれた。
この合意は、長年の仇敵であったエジプト・イスラエルとの和解をもたらすばかりでなく、第三次中東戦争で失ったシナイ半島の返還も含まれていた。
これによって1978年のノーベル平和賞はサダト大統領、ベンギン首相のダブル受賞となって、世界からは高く評価された。
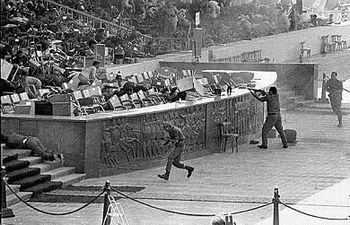
しかし、この行為は「パレスチナのアラブ人同胞に対する裏切り」とされ、アラブ諸国からは非難が集中し、さらに国内的にもイスラム教徒の民衆の反感は凄まじかった。さらに、1979年、イラン革命が勃発するとイラン国王モハンマド・レザー・バフラヴィー一家のエジプト亡命を認めたが、イスラム教徒の民衆はこれにも反対した。イラン革命はイスラム教の革命であり、イスラム教徒は反国王であったから、エジプト国内のイスラム教徒も反発した。
また資本主義経済の導入により自由経済の結果貧富の差が強まり、ナセル時代の社会主義の方が良かったとする知識層の反発も加わり、反サダト大統領の運動が激しくなった、1981年9月、反サダトと見られるイスラム指導者、共産主義者、大学教授、ナセル支持者、その他多くの知識人を逮捕、拘禁し国際的な非難を浴びた。

しかし、直ぐ後の翌月10月6日、第四次中東戦争開戦日を記念しての軍事パレード観閲中、イスラム復興主義過激派ジハード団に所属するハリド・イスランブリー中尉がパレードの列から離れ大統領を至近から狙撃し暗殺した。
後任、この観閲式に出席していた副大統領ホスニー・ムバラクが就任した。
大統領の隣に座っていたムバラク氏も重傷であったが、幸いにも命は保った。
◎イスラエル軍:正規軍は陸海空三軍で10万7千500人、徴集兵を集めると16万8千人、但し40万8千人の予備役がおり、総動員令(ラジオ放送)があると瞬時に兵力57万6千人態勢ができる。国民皆兵、男女とも兵役が課せられ「敗戦=国家消滅」の宿命を持つ、兵器はアメリカ製の輸入が多いが、砂漠戦、接近戦に向けた独自の改良を重ねた兵器が多く、兵の練度は陸軍、空軍(戦闘機)共に世界一と評価されている。
海軍は地政学的にあまり必要ではなく、小艦艇と兵員8千人を有するのみ。
国民総人口が約720万人 東京都の人口より遙かに少ない。
◎原油の量の単位バーレル:ヤード=ポンド法における体積を表す単位、語源は樽に由来する。
アメリカ・ペンシルベニア油田から採掘された原油を樽に詰めて馬車で運んだ。その樽の容積は42米液量ガロンであり、正確には158.987リットル。
現在も原油の計量と価格設定の単位として用いている。
中東情勢
1979年、イラン革命により石油生産が中断したため、イランから大量の原油を輸入していたわが国は需給が逼迫した。
1978年末、OECDが「翌1979年より原油価格を4段階に分けて計14.5%値上げする」と決定しており、原油価格は高騰した。
これが第二次石油危機(オイルショック)
その後もテヘラン在アメリカ大使館占拠事件、人質事件、アメリカとイランは国交断行、経済封鎖、今日に至も解決したわけではない。(別項で考察します)
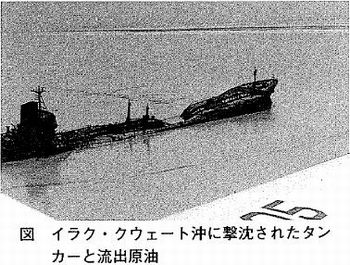
一般的には余り知られていないがタンカー戦争(Tanker War)というタンカー受難の戦争(1982年7月以降)があった。だがわが国では原油輸入に大きな影響があったにも拘わらず殆ど報じられることが無かった。
外国で日本人の生命に関わるような事件・事故があれば大々的に報じるが、海上の事故・事件になると途端に少なくなるか無視するかで、この時のペルシャ湾でのタンカー戦争や現在おきているアデン湾やソマリア半島周辺の海域でソマリ海賊の襲撃事件が連日おきているので、各国海軍は軍艦を派遣、海上自衛隊も護衛艦2隻を派遣し、協同で船舶の護衛にあたり、海自のP3C対潜哨戒機が上空から監視を続けているが、ニュースにもならないし、国民の関心も無い。

殆どの方が知らないと思うが、タンカー戦争と名付けられたペルシャ湾に於いて無差別に無防備のタンカーが攻撃され、タンカーが沈んだり、炎上したり、乗組員の犠牲者もでた。
この争いはイラン・イラク戦争中に起きたことで両国とも戦線が1進1退で泥沼状態になり、相手国を打倒するには手段を選ばずとなり、原油輸出のための港湾施設、石油採掘施設、ついにはペルシャ湾内航行中のタンカーの無差別攻撃、やがて一般船舶までも攻撃対象になり、湾内には機雷がバラ撒かれ船舶航行には最悪の海域になった。
8月9日、ギリシャ籍の貨物船(5千トン)がイラク空軍機のロケット攻撃で沈没、韓国籍貨物船イラン空軍機の攻撃で炎上、沈没。
9月4日、トルコ籍貨物船にイラク軍が発射したエグゾセが命中、乗組員が多数死傷した。これらはホンの一部にしか過ぎず、さらには触雷による被害も続発した。このため1984~1987年の4年間で総件数363隻の船舶が被害を受け、そのうち276隻はタンカーが占めている。
このペルシャ湾の危機的状態に対しアメリカ8隻、ソ連4隻、イギリス4隻、フランス3隻、イタリア3隻、オランダ2隻、ベルギー2隻の海軍艦艇を派遣、掃海と自国船舶の護衛を実施した。
当時わが国は最大のペルシャ湾利用国であったが、海上自衛隊の派遣は憲法上の制約から考慮もしなかったらしい。掃海部隊を派遣したのは後年の湾岸戦争での掃海部隊派遣からだ。
わが国関連は、日本が定期傭船していたリベリア籍タンカー「ケミカル・ベンチャー」が被弾したのみであったが、これは日本関連(日本海運会社のチャーターだが便宜置籍船)のためのタンカーは別のタンカーが運んできた原油を安全海域で積み替えいていたからで、この方法は相当高い船賃に転嫁され、更にペルシャ湾配船の船舶に対するロイドを中心とする海上保険は通常の200倍に跳ね上がった為に船舶運賃も当然ながら猛烈な高騰をみた。
このペルシャ湾の危機的状況は現在に至るも解決した訳ではない。シリアは内乱状態、首都ダマスカス中心部の治安施設で7月18日、大爆発がありラジハ国防相をはじめ軍、治安幹部が多数死傷した。武装反体制派「自由シリア軍」幹部は衛星テレビ局アルアアラビアを通じて「我々が仕掛けた爆弾が爆発した」と声明を出した。
アメリカとEUは反体制派を援助し、ロシア、中国がアサド政権を支持といういつものパターンになると内戦は長期化し、見通しは暗い。
7月19日の国連安保理事会ではアサド政権に対する制裁決議は中露の反対で否決され、国連の動きは封じられている。
シリアとゴラン高原を挟んで対峙するイスラエルはどう動くのか、レバノンは、アルカイダの動きは、シリア政府が保管する毒ガスの行へは、不安材料は山積している。もしイスラエルが直接行動を起こしシリアに介入すれば中東情勢は混沌とし第五次中東戦争が勃発しかねない危険な情勢になる。
イランの不安定も核開発問題で何時火を噴くか判らない状況にあり、そうすればホルムズ海峡の封鎖はあり得ることで,その時世界経済はどうなるのか誰にも判らない。
イランの核開発を封じるため、アメリカとEUは6月以降、原油収入削減を狙った追加制裁を相次いで発動、通貨リアルは再び下落し、輸入品を中心とした物価は上昇し、インフレ率は32%と見積もっている。
直撃するのは庶民の生活で、平均月収600万リアル(約4万円)で物価の高騰は致命的だ。
更に7月20日からラマダン(断食月)、断食はサウムと言い、ラマダンは断食月を言う。イスラム歴の第9月が断食月で、イスラム歴は太陰歴の為、太陽暦(西暦)とではラマダン時期は年に11日ほどずれるが太陰歴と太陽暦との修正はない。
今年は7月20日から日の出から日没までの間、飲食、喫煙が禁止、厳しいところでは唾を飲み込むのも禁止、この期間が1ヶ月続く。イスラム教徒にとっては聖地巡礼と並ぶ重要な義務、ただし、妊婦、病人、子供、旅行者は免除される。
私は中東に長いこと駐在員として滞在しており、イスラムの信者ではないが同僚が断食しているのに一人でむしゃむしゃ食べるわけにもいかず、断食に加わったが、砂漠地帯の乾燥した炎暑の中1滴の水も飲めない日中の辛さは凄まじいものがあったが、日没後同僚の家族や親族との団欒に招待され思い切り飲んで(但しノンアルコール)食べて大騒ぎの楽しい夕食となった。おかげでラマダン明けには体重が大分増加してしまった。
このラマダンは一般的には苛酷な宗教儀式と理解されているが、実はイスラム教徒に与えられたお祭りであり、楽しみでもある。

各家庭ではラマダンの前には大量の食糧を買い込み蓄えておくのが慣例となっているが今年は経済封鎖でインフレと食品不足、イラン国民の怒りが鬱積していることは確かで何処へ向かって爆発するのか、経済封鎖が逆効果にならないよう祈るだけだ。
ロンドン・オリンピック開催とラマダンとが重なってしまった時でも、イスラム教国の代表は断食しながら競技を続けているのだから大変だったろう。
日中全く水が呑めないのは辛いだろうし、コンディッション維持には大変苦労をしているだろうが、オリンピックだからといってこっそり飲食物の補給などはあり得ない。これは法で禁じているのではなく、神との約束事であるから心の葛藤の問題で絶対に犯すことはない。それが信者としての誇りでもあり、やすらぎでもある。

宗教が生活の中にはそれほど浸透していない日本人から見ればやや違和感があると思う。
しかし、イスラム教の本質を理解しないと中東情勢は理解できない。
正式名称はイスラーム、唯一絶対神アラビア語で「アッラーフ」を信仰し、神が最後の預言者たるムハンマド(預言者)を通じて人々に下したとされるクルアーン(コーラン)の教えを信じ、従う一神教である。(預言者であって予言者ではないことに注意)
唯一神教で、偶像崇拝を徹底的に排除し、神への奉仕を重んじ、信徒同士の相互扶助関係や一体感を重んじる。
(偶像崇拝のキリスト教を排除し、同じようにユダヤ教も否定する。またキリスト教徒の十字軍遠征に対する憎悪は未だに残っている)
始原、西暦610年、一青年の商人であったムハンマドがマッカ(メッカ)郊外で天使(ジブリール)より唯一神(アッラーフ)の啓示を受け、アラビア半島の各地でイスラームの教えを説いた、が迫害の方が多かった。
やがて努力が実り次第に信者が増え、勢力が拡大した各地にウンマ(イスラーム共同体)を建設し、周辺のアラブ人を配下に収めた。
632年ムハンマドは死去。後を継ぐイスラーム共同体の指導者として預言者の代理人(カリフ)が定められた。
ムハンマドの死後もイスラーム共同体の勢力拡大は留まることなく、第四代の正統カリフの指導のもとイスラーム帝国と呼ばれるような大帝国に成長した。
しかし、拡大成長時には内紛がつきもの、3代カリフの死後、4代カリフの座を巡って争いが生じた。
シーア派:(アリーの党派シーア・アーリの意)ムハンマドの従兄弟アリーの血筋のみがイスラーム共同体を指導するカリフであると主張する1派。
スンナ派(スンニ派):血筋にとらわれることなく、共同体を指導できる能力を有する者がカリフとなるべきだと主張、「スンナ派ムハンマド以来の習慣(スンナ)に従う者の意」
二派に分かれて今日に至っている。
現在シリア、イラク地域でゲリラ活動し、日本人湯川さん、後藤さんを殺害したISISはシーア派に属しているらしい。
イスラム教
ユダヤ教との関係:ユダヤ教はアブラハム系3宗教の根本的な宗教であり、旧約聖書の基となっており、イスラム教の立体的側面は、ユダヤ教を受け継ぎ簡素化されたものであると言われている。
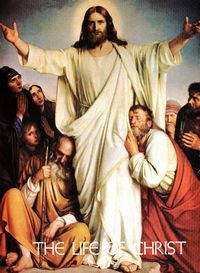
キリスト教徒の関係:ムハンマドはナザレのイエスの使徒であり預言者としており、またムハンマドに啓示を与えた天使ガブリエルは、キリスト教においてマリアの受胎告知を行った大天使と同一人物とみられている。ただし、イスラム教徒とキリスト教徒の対立は続き、西洋史はその対立の歴史だ。
イラク侵攻の時、ブッシュ大統領が多国籍軍を十字軍に喩えて演説したことがあるが、直後慌てて取り消した。もし取り消さなかったら、イスラム諸国全てがアメリカへ宣戦布告したかも知れない。
シーク教との関係:インドにおけるイスラム神秘思想とヒンドゥー教のバクティ信仰が相互浸透した結果の一神教で、ヒンドゥー教、仏教、ジャナイ教等のインド系宗教の特質と、アブラハム系宗教の特質も併せ持つ。
バハーイー教と関係:バハーイー教はイスラム教の預言者ムハンマドの外孫フサインの子孫(サイイド)であるとされているセイイェド・アリー・モハンマドによって開かれた宗教バーブ教を母体として、その弟子バハウッラーによって創始された宗教で、バハーイー教は12イマーム派から生まれた宗教であり、その思想や戒律はイスラム教の強い影響がある。
ところがイスラム教保守層から見るとバハーイー教徒は「背教者」、「異端者」であり、激しい憎悪を浴びているから、多くのイスラム教国では迫害されている。特に発祥の地イランではイスラム共和制の名のもとに弾圧されており、イラン革命後は憲法でその存在は否定されており、バハーイー教徒、無神論者は逮捕され、投獄される。最悪の場合は死刑。多数執行されたらしい。(宗教裁判は現存している)この他にも宗教、宗派があり、砂漠、遊牧民、民族、苛酷な生活環境、島国で水田耕作の土着性の我々から観て、中東の複雑な地政は理解困難だが、中東を理解する或いは世界情勢を少しでも理解しようするならば中東の諸問題を少しで理解する必要がある。

イスラエルの歴史(ユダヤ教教徒)
数度に渡る中東戦争の原因はイスラエルと周辺アラブ諸国と対立にある。
では何故対立するのか?是非ともその原因を探り理解しておく必要がある。
歴史を辿り紀元前まで遡ってみましょう。
それは何千年にも及ぶ波瀾万丈の民族史であり、苛酷な砂漠地帯の生存をかけた戦いの連続であって、島国に暮らし争いは勢力争いのみで一部の人間が闘ったにすぎないわが国の歴史からみれば民族の存亡を賭けた戦いの連続に驚きだけが先行し理解不能に陥ってしまいそうだ。
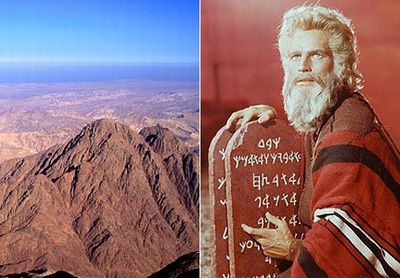
紀元前11世紀頃、古代イスラエル王国が誕生した。
旧約聖書によると、民族の始祖アブラハムが、メソポタミアのウル(現在のイラン南部)から部族を引き連れて「カナンの地」(現在のイスラエル・パレスチナ付近)(この「カナンの地」は旧約聖書に何度も記述されている)
この人達は「移住民」という意味の「ヘブライ人」と呼ばれた。この付近で遊牧民として生活していたヘブライ人は、紀元前17世紀頃カナンの地から古代エジプトに集団移住するが、やがてこの地で奴隷として古代エジプト王朝に隷属することになってしまった。
その後、ヘブライ人指導者モーゼの指揮で約60万人のヘブライ人がエジプトからシナイ半島を目指して脱出した(出エジプト記)
(この時の物語は何度も映画化され海が割れて脱出に成功するシーンには単純に感激した。映画“十戒”)
ヘブライの人達は神から与えられた「約束の地」と信じられた「カナンの地」(パレスチナ)にたどり着き、ここを永住の地と定めた。とろがそこは無人の地ではなく、先住民であるカナン人やペリシテ人が住んでいた(フェニキア系民族)から争いが起きるのは当然で、長い拮抗の末に駆逐、同化によりやっとカナンの地に定着した。
この頃からイスラエル人と称し、カナン語を取り入れたヘブライ語が成立した。(このヘブライ語を復活させ現在イスラエルの正式な言語としている)
紀元前10世紀頃、古代イスラエル人はヤハウェ信仰(ユダヤ教の原型)を国教とする古代イスラエル王国をカナンの地に建国した。
紀元前922年、国王ソロモンの死後、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂した(ユダヤとは、元来ユダ王国のあったパレスチナ南部を指す)
この民族の不幸は続き、紀元前721年北のイスラエル王国はアッシリア人によって滅ぼされ追放された(失われた十支族)。
紀元前612年、南のユダ王国も新バビロニアの侵攻によりあっけなく滅亡、多くの人々はバビロン人の奴隷になった(バビロンの捕囚)が、ユダ王国の遺民とみなされユダヤ人と称した。
紀元前538年、新バビロニア王国はアケメネス王朝のペルシャによって滅ぼされ、キュロス大王によって捕囚のユダヤ人は解放され、エレサレムへ帰還し、ペルシャ帝国の支配下で自治国として統一イスラエル国を再建した。ユダヤ教もこの頃確立したと思われる。
紀元前(334年~332年)マケドニア王国のアレキサンドロス3世による東方制遠征でパレスチナの地も征服された。大帝国が出現したが、マケドニアは分裂、トレマイオス朝、続いてセレウコス朝(シリア王国)の支配下となった。
紀元前143年、マカバイ戦争によってセレウコス朝の支配から解放され、ユダヤ人自身がこの地を支配した。
やがては遠く離れた強力なローマ帝国の支配下となりユダヤ属州となった。
紀元前20年頃、ユダヤ属州北部ナザレの民から出たイエス・キリストが活動を始めた。
紀元66年頃からローマ帝国に対して反乱を起こすが鎮圧され第一次ユダヤ戦争。紀元132年、ユダヤ人の指導者バル・コックに率いられ第二次ユダヤ戦争(バル・コックの乱)が起き、一時的には勝利を収めたが、強大なローマ帝国軍が押し返し、ユダヤ人の自治は完全に廃止され厳しい民族的な弾圧を受け、イスラエル人の呼称やユダヤ属州の国名も廃止され、かつて古代イスラエル人の敵であったベリシテ人に由来する「パレスチナ」という名が復活。ユダヤ人はこの地を追われ、ここに2000年近く国を待たず、民族を持たない人々がヨーロッパを中心とした各地に散って行った。以降「ユダヤ教徒」というただ一つの共通項として宗教的な結束で、ユダヤ人としての矜持を持ち続けて、各地で定着していった。
ヨーロッパ諸国に散ったユダヤ人はユダヤ教の信仰を堅持、その頃からヨーロッパ各地で信仰の対象になったキリスト教では、ユダヤ人がキリストを処刑したと信じられていた。(実際はローマ帝国軍が処刑したが、十字架を背負って歩むキリストを殺せと罵ったことは事実)
各地に散ったユダヤの人々は何代にも渡って苦難の道を歩んできたが(ディアスボラ)。
1798年~1878年、セルビアに住むセファルディム系の宗教的指導者ラビ・イェフダ・アルカライが聖地での贖罪を前提とした帰還を唱えた。
1909年、ルーマニアからの移民がテル・アビーブを建設
1917年、イギリス外相バルフォアがシオニズム支持を宣言(バルフォア宣言)
イギリス陸軍がオスマン軍(トルコ軍)を破り、エレサレム入城
第一次大戦後、パレスチナの地はイギリスの保護領になる
1920年、軍需相ウィンストン・チャァチルがユダヤ国家支持を表明
1931年、シオニスト会議、ダヴィド・ベングリオン二民族共存国家を提唱
1930年~1945年、ナチスドイツが政権を執るとドイツ国内からはじまり、占領地のユダヤ系市民がユダヤ人だとの理由だけで強制収容所に送り、民族絶滅、民族浄化の手段としてガス室で青酸ガスや一酸化炭素で大量殺害を実行した。
その犠牲者は定かではないが6~7百万人と言われている。
その危険を察知したユダヤ系の人々はあらゆる手段を使って逃げ出そうとしたが、他国へ行くにはパスポートとビザが必要ですが、日本関連に就いて言えば、在リトアニア日本領事館の杉原千畝副領事が外務省の省令を無視いてポーランド在住のユダヤ人に日本通過のビザを多数発行し、約6千余人の命を救った。この事実はドラマ化されたし、ミュージカル、舞台劇等で数多く発表された。
現在でもイスラエルの小学校の教科書に記載されているし、エレサレムには記念碑もある。

この功績は在リトアニア日本領事館だけが業務を続けており、それを知ったポーランドに住む多くのユダヤ人が領事館に押しかけビザ発給を求めた。ところが日独伊三国協定を結んでいた外務省はビザ発給を禁止した。
杉原副領事一人だけが省令に抗命しビザを発給し続け、その数、二千数百通で家族を含めて数千人の命を救ったことになる。
当時は全て手書きであり、ソ連によって領事館は封鎖され外交官は国外追放であったから、列車が走り出すまで発給し続けた。

イスラエルから見れば美談だが、外務省から見れば省令違反であり、杉原氏は戦後外務省を追われてしまった。
この事実を外務省は隠し続けたが鈴木宗男代議士が外務政務次官に就任したとき杉原未亡人を外務省に招待し正式に謝罪した。
その他にも数多くの日本人がユダヤ人救出の為に活躍した。
これはビザが無いが命の危険を感じ、切羽詰まってシベリア鉄道に乗って日本を目指したユダヤ人が2万人位いた。シベリア鉄道はチタの東側にあるカルムスコエという小さな駅が分岐点でハバロスクから終点ウラジオストックへ向かう線と満州へ向かう線に分かれるが、ビザのないユダヤ人達はウラジオストックへ向かえばソ連領であるから送り返されてしまう怖れがあった。 当時は未だ独ソ戦の前でソ連とドイツは共にボーランドを侵略し二分割していた。(カチンの森の悲劇はこの時)
当時は未だ独ソ戦の前でソ連とドイツは共にボーランドを侵略し二分割していた。(カチンの森の悲劇はこの時)
そこで満州に向かう列車に乗り換え、ブリヤード自治共和国の国境(蘇満国境)のオトホール駅で強制下車を命じられた(オトホール事件)

満州国外交部は入国拒否(当時満州は関東軍が事実上支配し満州国と称していた)ユダヤ難民は食糧もなく着のみきのままで厳寒のシベリアで立ち往生してしまった。
この情報に接した関東軍ハルピン特務機関長樋口季一郎少将が立ち上がり、特別列車を仕立てて自ら越境して現地で交渉を行い、無事満州国内に収容した、その数2万人と言われていたが、その後の研究・調査によると1万人強位と推定されている。
食糧や衣類を調達し、安息の宿を提供し一時的にも収容した。樋口機関長の命を受けた安江大佐、河村少佐が手足となってこの難事業を成し遂げた。ビザが調達出来た人は日本に送り出し、敦賀・神戸経由でアメリカへの客船に乗せ送り出し、ビザがどうしても調達出来ない人達は満州の地に土地を与えユダヤ自治区を創立出来ないかと関東軍上層部と交渉したが、視野が狭い幹部連は却下してしまった。

この樋口少将の行為に対し激怒したナチスドイツが厳重な抗議を申し込んできて樋口少将の罷免を要求したが、関東軍総参謀長だった東条英機中将がこれを拒否、樋口少将を庇護しているからこの頃はナチスドイツ一辺倒ではなかったらしい。また、首相になってからも「日本のヒラー」と取り巻きがお世辞を言ったところ、あんな出自の怪しげな男と一緒にするなと怒鳴った、との記録もある。

歴史に「もし、IF」は禁句だが、「もし」ユダヤ人自治区を創立していたなら小さなイスラエルを建国することであり、アメリカ国内で大きな政治力をもつユダヤ人社会が日本支持をしていたら、日米交渉であれほど強硬な態度や、ABCDラインの経済封鎖はなかったろうし、太平洋戦に突入することもなかったと考えてしまうのは飛躍のしすぎか、でも歴史にifを付して想像するのは楽しい。

このユダヤ難民の救済には続きがありビザを持ってシベリア鉄道に乗った人達はウラジオストックに到着したが、日本との定期船はなくウラジオストック港で足止めになってしまったが、その情報を知った日本交通公社(JTB)の前身である日本旅行協会に依頼があり、ユダヤ難民救済を命じられた職員の大迫辰雄さん(当時34歳)が船舶をチャーターして自らも乗り込んでソ連側との難しい交渉・手続き、病人の世話等々あらゆる仕事を一手に引き受けて、しかも次々とシベリア鉄道で到着する難民の人達を1940年から1941年の戦争開始寸前まで続き厳冬の日本海の波濤を超えての頃から開始して二十数回往復し6,000人余のユダヤ人を敦賀港まで連れてきて、そこからは陸路神戸へ、そこで旅客船に乗船させてアメリカへ送りだしたが、船待ちの何ヶ月も神戸に滞在したがすべてボランテイアの手によって世話を続けたのです。日本側官僚は日独伊三国同盟があり、敵対行為と見なされていたから我関せず、厄介者として嫌がらせをするくらいでしたから、全て民間の手でやり遂げたのです。
もう一つ「河豚計画」という壮大な計画があった。これは1934年(昭和9年)満州重工業総裁鮎川義介氏によって提唱されたものだが、満州財界も乗り気になり、後は関東軍指導部がどう判断するかであった。
満州の地はハルピンを中心として多くのロシア系の人々が住んでいた。元々はロシア皇帝の所有地とされていたが、ロシア革命でロマノフ王朝に連なる貴族や軍人、上流階級であった白系露人が祖国を追われ多数移り住んでいた。
そこへ欧州各地からユダヤ系の人々がシベリア鉄道経由で満州に難民としてやってきたから、この人達が一緒になって自治区を創ってはどうかという提唱があった。
1938年、五相会議で政府の方針として定められ、実務面では陸軍が安江仙弘大佐、海軍が犬塚惟重大佐が任命され陸海協同作戦となった。
この「河豚計画」の基本方針は、ユダヤ人の経済力、政治力を評価し、ヨーロッパ諸国で迫害を受けているのみならず、1935年にはニュールンベルク法が制定されドイツ国内ではユダヤ人は市民権を剥奪され公職追放されるなど深刻な状況にあり、そこで5万人位のユダヤ人を満州に移住を勧め、その経済力と才能を満州国建設に役立てもらおうとする計画であった(当時は未だ日独伊三国同盟締結以前であり、ナチスドイツも強制収容所は未だ無く、国外追放だけであった)
そうすればユダヤ人が持つ世界中のネットワーク、特にアメリカ社会に強力な力を持つユダヤ人に好意を持って貰えば日米の外交的対立も緩和出来るのではないかとの思惑があった。
この「河豚計画」命名の由来は、日本にとって非常に役立つかも知れないという期待と、もし失敗すると国際的な非難を浴びること必定とする二面性を持つ計画であったから、美味と猛毒の二面性のある河豚に擬えて犬塚大佐が命名した。
残念ながら内閣は次々と替わり五相会議決定事項にもかかわらず、真剣に取り組もうとする担当大臣が居らず先送りされ、さらに関東軍幹部にも消極的な将星がいて実現されないまま、シナ事変、ノモハン事変、太平洋戦争と続くうちに計画は立ち消えとなってしまった。
ただし、ユダヤ人救出の活動は続き、樋口少将、安江大佐、河村少佐、海軍の犬塚大佐の活動は終戦時まで続行された。これはナチスドイツのポーランド侵攻による英仏との開戦、独ソ不可侵条約を踏みにじっての独ソ開戦、太平洋戦争開戦と続いて、満州で収容していた約2万人が行く先を全て閉ざされ、孤立してしまった。
そこでビザが必要としなかった上海租界へ送り込み、ユダヤ人ゲットーを創り、海軍シナ方面艦隊司令部付犬塚機関として引き続き犬塚大佐を指揮官とする海軍陸戦隊の一部が管理・保護した。
食糧難の時、2万人の食糧調達や治安維持に苦労したという、それでも餓死者はなく、病没と終戦間際アメリカ空軍の爆撃に遭い十数人が爆死しただけで終戦を迎え第二次大戦後大勢のユダヤ人は無事祖国へ戻ることが出来た。
戦後しばらくして樋口季一郎、安江仙弘、犬塚惟重の三氏にユダヤ人協会からイスラエル国民が三氏から受けた恩義に対してその顕著を同族としてゴールデンブックに記録し、顕著したいと招請があった。
安江氏は既に病没しており、犬塚氏は上海のゲットーでアメリカ軍の空爆によって十数人が爆死させてしまったことを自己の責任と自分を責め続けており、申し出を丁重に断った。
後日、イスラエルから表彰状と記念品が贈られてきた。
結局、樋口氏一人だけがエレサレムで行われた式典に出席し、金襴簿(ゴールデンブック)に樋口、安江、犬塚の三氏が記載された(イスラエル国最高の顕著)
樋口氏が出席したのは理由があって、イスラエル国民に直接お礼を言いたいとのことでした。
それは、返還問題で揺れる北方四島で、8月15日終戦でしたが、9月中旬まで激しい戦闘があり、その時の日本守備隊を指揮したのは北部軍管区司令官樋口中将(少将から昇格)司令部(札幌)。ハルピン特務機関長から転任していた。
突如、ソ連は日ソ不可侵条約を踏みにじり8月8日対日宣戦布告、蘇満国境を越えて満州になだれ込み、防衛するはずであった関東軍の大半は既にフィリッピンや沖縄に転出されており、無敵関東軍とは名ばかりのもぬけの殻だけにすぎなかった。このため取り残された開拓民の数々の悲劇が満州の野に繰り広げられた。
8月15日終戦の宣言をしたのにも拘わらず、ソ連軍は攻撃の手を休めず樺太、千島列島を襲い、できる限りの占領地確保の実績を得る為に戦闘を継続した。
9月になってから北方四島に武力上陸をして守備の日本軍が、終戦宣言がなされていると告げたのを無視、攻撃してきたので防御したが、停戦になってからスターリン首相は終戦宣言されているもかかわらず樋口司令官が攻撃を命じたのはけしからんと難癖を付け、戦犯として引き渡しを要求してきた。
当時日本は連合軍が占領していたが進駐軍総司令官の同意がなければソ連単独では逮捕できない。
この情報を聴いたアメリカ在住のユダヤ人協会が立ち上がり、樋口氏の恩義に報いるのはこの時とばかり猛烈なロビー活動で、ついにはトルーマン大統領を通じて極東軍総司令官マッカサァー元帥のもとに大統領命令として樋口氏の保護を命じる通達があった。
第二次大戦での日本軍人、特に上層部の軍人の行動に関しマイナスイメージが強く印象付けられているが、立派に職責をはたし功績があった軍人も数多くいたはずで、これからも数多く掘り起こしたい。
もう一つユダヤ関連のこと、日露戦争に関し貧乏国日本が世界最大の陸軍を持つロシアと戦うのですから戦費は幾らあっても足りなので外国に金を借りることにしてアメリカやヨーロッパに特使を派遣し戦時国債を発行しようとしたが、極東の小国が巨大な熊に勝てるわけがないと戦時国債を誰も買わなかった。ところがロシア在住のユダヤ人を苦しめているロマノフ王朝を苦々しく思っていたイギリスやアメリカ在住のユダヤ人達はこの際ロマノフ王朝を崩壊させる手段として日本を支援しようとユダヤ人のシフ家が所有していたクーン・ローブ商会が中心となって戦時国債を引き受けてくれた。この時調達出来た金額は日露戦争戦費の約四割あたるというから日露戦争勝利の原動力はこの戦時外債にあったと言われているくらいだ。また「河豚計画」の目玉は、この時のシフ氏の孫にあたる銀行家ジェィコフ・シフ氏がもう一度満州に投資してくれることを願って鮎川義介氏が練った案だと言われている。
もし、この河豚計画が軌道に乗っていたら、日米戦争はなかったと断言できる。それはアメリカ政府・議会の最大のロビスト、圧力団体はユダヤ人協会で、ヨーロッパの戦乱を遁れてシベリア鉄道で東進したユダヤ同胞をなんとか救助ようとしているとき、蘇満国境から入境させ、満州で保護してくれた関東軍に感謝し、実業家鮎川義介氏の練った案と関東軍の一部高官が賛同した「河豚計画」が実現していたならば、在米ユダヤ人の有力者グループがルーズベルト大統領、ハル国務長官を動かして戦争阻止、日米会談妥協に動いてくれたと思う。事実そのような動きがあった。だが、陸軍首脳はこの案を潰してしまった。
アメリカとイスラエル(ユダヤ人)の関係
アメリカ合衆国とイスラエル国との間には深い関係があり、アメリカが最大の庇護国、支援国となってイスラエルと一心同体となっての建国を保護している。
何故これほどまでにイスラエル国を保護しなければならないのか。単に同盟関係にあるだけではなく、いわば兄弟関係にあるといえる。
ユダヤ系アメリカ人は、ユダヤ人のアイディンティを持つアメリカ市民で、その大半は中欧、東欧から移民してきたアシュケナージとその子孫である。セファルディム、ミズラヒムなどマイノリティ民族もいるが、多くのユダヤ民族のコミュニティはその独自性を今尚保持しており、絶対的なユダヤ教を信仰し、それがまた民族としての絆になっているから、他のアメリカ市民とは異なる文化を形成している。
2007年時点におけるアメリカ市民としてのユダヤ族は約512万8000人であり、アメリカ国内の人口比では約1.7%を占めるに過ぎない。それでもイスラエル本国の全人口がユダヤ人543万5800人であるから、アメリカは二番目に多いことになる。しかし重要なのはアメリカ社会で活躍するユダヤ人の多さである。
私事ですがボス(社長)と幹部がユダヤ人の会社に採用され、粉骨砕身とまではいかなかったが、ともかく相当こき使われたことは確かで鍛えられた。
彼らの才能の豊かさ、先見の明、実行力の凄さには脱帽で、世界中に張り巡らされたネットワーク、数カ国の言語(母国語と同じ位)を話せて、読めて、書けるのが常識という才能の豊かさ、思考の広さ、おそらく世界一の民族だと認めざるを得なかったし、私と同年代の同僚は十数カ国の言語を自由に喋り、新聞を読み、国際短波放送を聴いていましたから2千年以上もの流浪によって培かわてきた才能の伝承なのか、島国のそれも片田舎育ちの私にとってはただ驚異で、張り合おうなどの意欲は最初から消滅してしまった。
アメリカ社会で活躍する有名人を各界から列挙します。
先ず身近で誰でも知っているハリウッドスターから(最近はあまり映画を見ないので懐かしいスターばかりです)
ロレン・バコール、エリザベス・テーラー、バーブラ・ストラィザンド、ウディ・アレン、カーク・ダグラス、ポール・ニューマン、ほんの一部にしか過ぎません
監督 スティーブン・スビルバーグ、ロマン・ボランスキー、音楽 レナド・バーンスタイン、アイザック・スターン、政治家キッシンジャー国務長官、ルーズベルト大統領、
実業家 特に銀行、証券会社等の金融界は大半がユダヤ系の人達が握っている。学者 アルベルト・アインシュタイン、ロバート・オッペンハイマー、世界経済を牛耳る財閥、ロスチャイルド、ロックフェラー、サッスーン、クーン ロエブ、モルガン、 ベクテル、 ザハロフ、七財閥はユダヤ系大富豪
石油メジャーもエクソン、モービル、シェブロンはロックフェラーが創業した。 スタンダードオイルもユダヤ系。石油ショック後はOECDに価格決定などの権利は産油国に移ったが、未だ隠然たる影響力を有し、かつその影響力を取り戻しつつある。
ユダヤ人の定義:ユダヤ人の母から産まれた子、若しくはユダヤ教を信仰し、他 の宗教は一切信仰しない。
アメリカの東部イスタブリッシュメントの定義は、WASPの造語がある(White、AngloーSaxon、Protestant)白人、アングロサクソン、プロテスタントが基本で、その他アイビーリーグ出身とか、祖先がイングランド、スコットランド、ウエールスから移民したとかの定義があり、歴代大統領はこの定義内にあり、初めて破ったのが、ケネディー大統領でカトリック、アイルランド系だったので、一部からは猛烈に反感もたれていたことは事実です。そして現在オバマ大統領ですからアメリカ市民の認識も変わってきたのでしょう。
そのアメリカ社会の中でユダヤ人が絶対的な力を持っているのは、富豪が多いこと、金融関係は大半がユダヤ系であること、アメリカ国内の財界、経済界、それに連なる政界をも動かせる力を持っていること。
世界中を不況に陥れたリーマンショックのリーマン・ブラザースはユダヤ系で、負債総額6130億ドル(当時の円レート、約64兆5000億円)、史上最大の倒産となった。このため世界同時不況となって現在でも回復していない。
我が国はサブプライムローンには余り手をだしていなかったので大和生命保険が倒産したくらいで、打撃は少ないだろうと予想していたが、結果的には予想を覆し、残念ながら世界的な消費の落ち込み、輸出の減退、そしてなによりも大きな打撃となったのは世界の金融不安から各種通貨から逃げ出した巨額な流動資金が比較的安定している「円」買いに集中したことで超円高になってしまって日本の輸出産業を直撃し、国内産業は海外へ逃げ出し、産業空洞化、若年失業者の増大とリーマンショックの最大の被害者は日本だろうと言われており、(2011年10月22日、1ドル=75円78銭、1ユーロ=96円97銭)と回復の見込みは全くないと思われたが、2015年3月5日現在1ドル=120円12銭、1ユーロ=132円67銭に回復した)
もう努力の限界と言われているし、経済とは世界中が連動している怖ろしい魔物でその正体は掴めないし、理解もされていない。
リーマン・ブラザースの創業は1844年でバイエルン王国からの移民で、アラバマ州モンゴメリーで小さな日用品雑貨の店をリーマン兄弟は開いたのが最初。
その後綿花産業に投資、鉄道建設債権券市場に参入し、巨万の富を得た。
1887年、ニューヨーク証券取引所の会員になった。
ゴールドマン・サックスと提携するなど経営範囲を拡大していった。
1977年、日露戦争で日本の戦時外債の大半を引き受けてくれたクーン・ローブ商会が経営不振に陥入っていたのを救済・合併した。
この頃から経営は順調で大幅黒字を計上し、トレーダー社員が大幅に増え、高額の報酬を得ていた。
サブプライムローン(サブプライム住宅ローン)に余りにも大きく手を広げすぎ、損失処理を要因として経営が急速に悪化、アメリカ財務省やFRBの仲介で複数の有力金融機関と売却交渉を行ったが、負債総額が余りにも巨額なため交渉は難航し、結局は倒産、その悪影響は未だ世界中で燻っている。
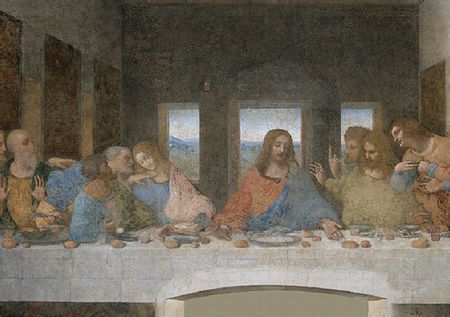 |
○ユダヤの人達がキリスト教徒から嫌われ迫害される理由
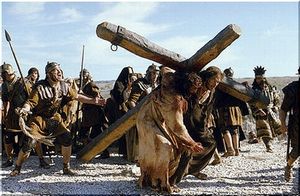
キリストはユダヤ人でユダヤ教徒ですが、新しくでた新約聖書によればイエスの処刑に関与しローマ帝国第五代ユダヤ属州総督ポンテオ・ピラトは処刑には懐疑的であったと記されている。
「ルカの福音書」では「この男には何の罪も見出せないと述べイエスは無実とする「マルコによる福音書」「ヨハネによる福音書」によるとイエスを刑死にするのには消極的であったが、群衆の要求に応じてヤムを得ずイエスを十字架の磔の刑に処したと記されている。
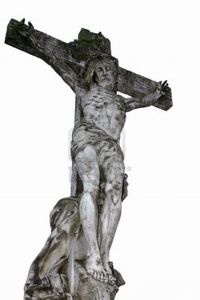
沿道にいたユダヤ人達は十字架を背負って歩むイエスを殺せ、殺せと叫び続け、罵声を浴びせかけた。
中世イスラム社会ではユダヤ人は税金を支払いさえすればユダヤ教の信仰は自由だった。
しかしヨーロッパのキリスト教社会では、ユダヤ人を嫌悪する風潮があった。
これは「キリストを殺した」「キリストの最大の敵」との観念が強く、
「ヴニスの商人」にある利子をとって金を貸すことを禁じる
中世ヨーロッパでのユダヤ人は職業が制限され、キリスト教が禁ずる利子を取って金を貸す、金融業はユダヤ人にやらせた。またユダヤ人は金融業しか生活の手段がなかった。
新約聖書の四福音書
マタイによる福音書:税吏出身の使徒マタイ
マルコによる福音書:ペトロとパウロの弟子であったマルコ
ルカによる福音書:おそらくパウロの弟子だったルカ
ヨハネによる福音書:使徒ヨハネ

これらの福音書は後世に書かれたもので、後にローマ帝国はキリスト教に帰依したのであるから、キリストの磔をユダヤ人にその責任を押しつけたく、磔を命じた総督ピラトを善人に仕立てようとしている。
ナザレのイエスがエレサレム神殿を頂点とするユダヤ教の体制を批判し、かつ神の教えを説き多くの信者が集まりだしたので、危機感を抱いたユダヤ人の指導者達は死刑に処する権限がなく、そこでローマ帝国の属州であったから、この州を支配する総督ピラトに「ローマ帝国への反逆者」の罪状で告訴した。
キリスト教の教義では、救い主であるイエスキリストが人類のその罪から救うために身代わりになって磔になったとしている。
イエスはユダヤ人であるが、その点を無視し、ユダヤ人を徹底的に迫害し続けたキリスト教徒は、ナチスの暴虐を止めるどころか加担してしまった。博愛を教義としているにもかかわらず。
磔の刑 の映画は「ベン・ハー」「最後の誘惑」「キングオブキング」「偉大なる生涯の物語」「聖衣」
2000年以上の歴史が現在でも中東で息づいており、歴史を識らなくして中東を理解することは出来ない。
 |
現在、シリア、イラクでISIL(ISIS)の武装集団がテロ活動を行い、湯川さん、後藤さんの日本人2人が処刑、虐殺された。

ISILはアルカイダから分派、絶縁した過激派組織で、イラクの旧フセイン大統領時代の旧軍人やバース党のメンバーがそのままISILになってしまったらしい。
いわば戦争のプロ集団であり、行政にも長けた有能な集団だから手強いテロ集団だ。
中東の歴史はあまりにも複雑で、闘争、政情不安の連続で、平穏だったことはないと言える位の混乱の連続だ。
原油、天然ガスがその地にあるのだからこれらの地域と今後どう付き合っていくべきか、課題は大きい。
